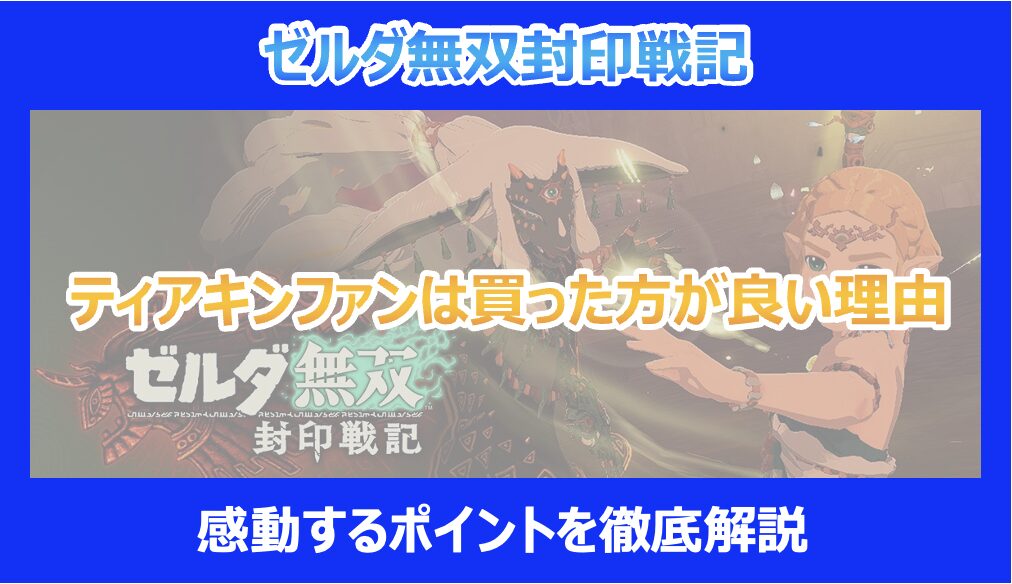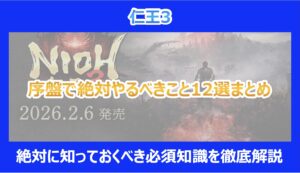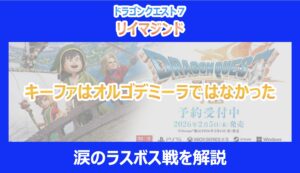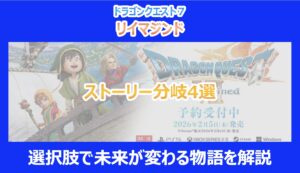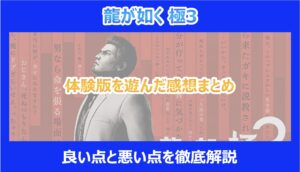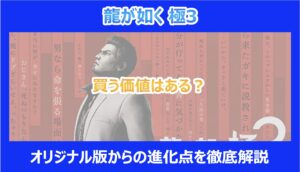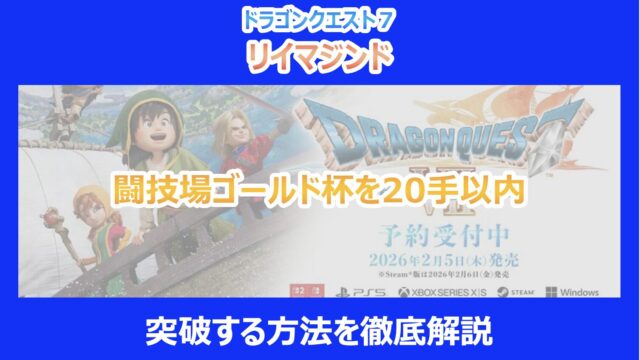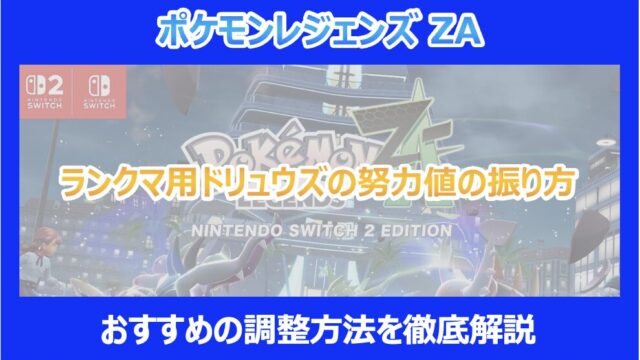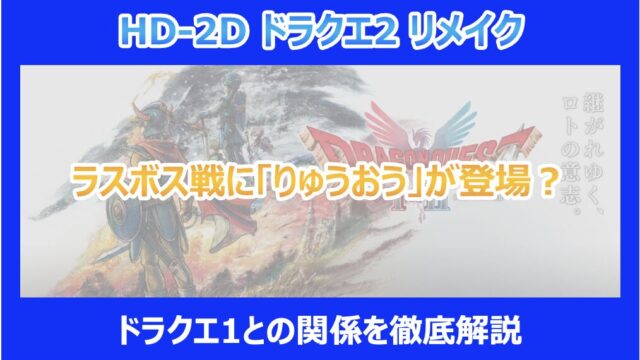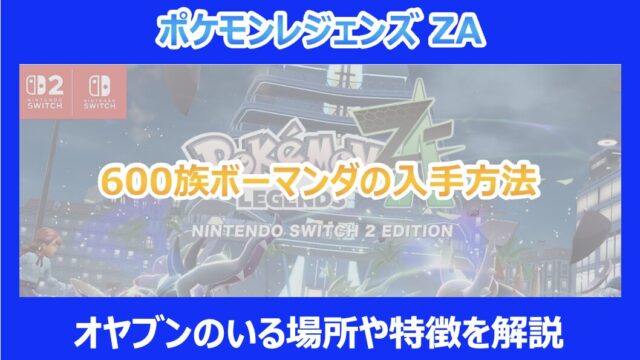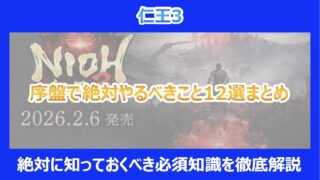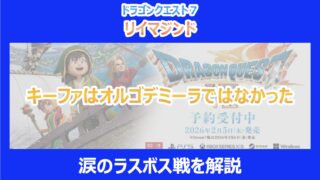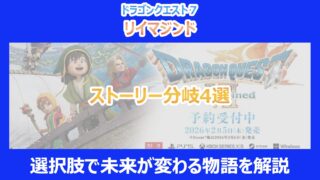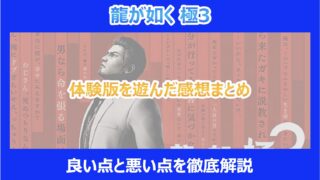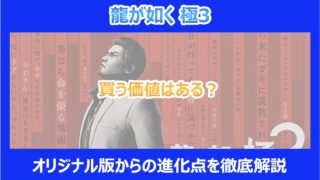編集デスク ゲーム攻略ライターの桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年11月6日に発売された「ゼルダ無双 封印戦記」が気になっている、特に「ティアキン(ティアーズ オブ ザ キングダム)ファンなら絶対に買った方が良い」という噂の真相を知りたい、と思っているのではないでしょうか。

何を隠そう、私自身も「ティアキン」にドハマりし、あの広大なハイラルを隅々まで冒険し尽くした一人です。 だからこそ、発売前に「ティアキンのゼルダサイドを描く」と聞いた時、期待と同時に「無双で本当にあの壮大な物語を補完できるのか?」という一抹の不安もありました。
しかし、エンディングを迎えた今、断言できます。 「ティアキンファンこそ、絶対にプレイすべき」だと。 本作は、私たちが愛したあの物語の「失われたピース」を完璧に埋めてくれる、まさに「もう一つの本編」と呼ぶべき傑作でした。
この記事を読み終える頃には、「ゼルダ無双 封印戦記」がなぜティアキンファンにこそ刺さるのか、その理由が明確になっているはずです。
- ティアキンの「失われた物語」を補完する完璧な前日譚
- 物語の鍵を握る衝撃の新キャラクター「謎のゴーレム」と「カラモ」
- Switch 2の性能が実現した圧巻の「真の無双体験」
- ティアキンファンなら感涙必至のファンサービスと小ネタの数々
それでは解説していきます。
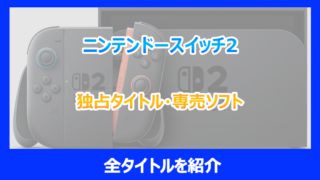
ゼルダ無双 封印戦記とは?ティアキンとの関係性を整理
まずは本作「ゼルダ無双 封印戦記」がどのようなゲームなのか、そして「ティアーズ オブ ザ キングダム(ティアキン)」とどういった関係性にあるのかを、改めて整理しておきましょう。

封印戦記の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | ゼルダ無双 封印戦記 |
| 発売日 | 2025年11月6日 |
| プラットフォーム | Nintendo Switch 2 専用 |
| ジャンル | アクション(無双) |
| 開発 | コーエーテクモゲームス(オメガフォース) |
| 概要 | 「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の時代を舞台にした無双アクション |
本作は、任天堂の次世代機「Nintendo Switch 2」のローンチタイトルの一つとして発売されました。 「ゼルダ無双」シリーズとしては、「ブレス オブ ザ ワイルド」の100年前を描いた「厄災の黙示録」に続く作品となりますが、今回は「ティアキン」の世界観、特に「太古の時代」に焦点を当てています。
ティアキンで「描かれなかった」ゼルダの物語
「ティアキン」の本編をプレイした方ならご存知の通り、物語の冒頭でリンクとゼルダ姫は離れ離れになってしまいます。

リンクは現代のハイラルで世界の異変を調査しながらゼルダ姫を探し、一方のゼルダ姫は、マスターソードの修復と未来への希望を託すため、過去(太古のハイラル)へと時間遡行します。
ティアキンの本編では、主にリンクの視点で物語が進行しました。 ゼルダ姫が過去で何をしていたのかは、「龍の泪」としてハイラル各地に残された「記憶」を通じて、断片的に語られるのみでした。 ラウルやソニアとの出会い、ガノンドロフの裏切り、そして「封印戦争」の勃発――。
もちろん、あの断片的なムービーだけでも、ゼルダ姫が背負ったものの重さや彼女の覚悟は痛いほど伝わってきました。 しかし、「記憶」であるがゆえに、どうしても「点」と「点」の間のストーリー、つまり彼女の日常や心情の細やかな変化、そして「封印戦争」の具体的な戦闘の様子は、私たちの想像で補う必要があったのです。
「ゼルダ無双 封印戦記」は、まさにその「想像で補うしかなかった部分」を、真正面から描いた作品です。
ゼルダ姫が太古の世界に降り立ってから、ラウルやソニア、ミネルたちとどう打ち解けていったのか。 「封印戦争」とは具体的にどのような戦いだったのか。 そして、彼女が「龍化」という究極の決断に至るまでの、知られざるドラマが、本作ではゼルダ姫自身の視点で、アクションゲームとして体験できるようになっています。
なぜ「無双」で描かれたのか? アクションとストーリーの融合
「封印戦争」という、その名の通り「戦争」を描くにあたって、「無双」というゲームシステムは最適だったと言えるでしょう。
「厄災の黙示録」が100年前の「大厄災」の絶望的な戦いを描いたように、本作はガノンドロフ率いる魔物の軍勢と、ラウルや賢者たちが率いるハイラル連合軍との大規模な戦闘を、「無双」ならではの「一騎当千の爽快感」と共に描いています。

単なるムービーで「壮絶な戦いでした」と語られるよりも、プレイヤー自身がゼルダ姫や太古の賢者たちを操作し、無数の敵をなぎ倒しながら戦局を打開していくほうが、その絶望感と、そこから生まれる希望の重みを、より深く体験できるはずです。
本作は、ティアキン本編では描き切れなかった「壮大な戦争の物語」を、「無双」というアクションのフォーマットで見事に補完した、まさに「公式の前日譚」と呼ぶにふさわしい作品なのです。
ティアキンファンが「絶対に買うべき」5つの理由
さて、ここからが本題です。 なぜ、私が「ティアキンファンは絶対に買うべき」と強く推奨するのか。 実際にエンディングまでプレイして「感動した」具体的なポイントを、5つの理由に分けて徹底的に解説していきます。
理由1:断片が繋がる「完璧な前日譚」としてのストーリー
本作最大の魅力は、間違いなくストーリーです。 ティアキン本編で「龍の泪」として見たあの記憶が、どのようにして紡がれていったのか。 その行間が、驚くほどの解像度で描かれています。
3時間超のムービーで描かれる「太古のハイラル」
まず驚かされるのが、ムービーシーンのボリュームです。 その総尺は、なんと3時間以上。 これは前作「厄災の黙示録」に匹敵する、あるいはそれ以上の物量です。
ゼルダ姫が太古のハイラルに戸惑いながらも、持ち前の好奇心と行動力でラウルやソニア、ミネルたちと交流を深めていく様子が、非常に丁寧に描かれています。 特に、ソニアとの関係性はティアキン本編では深く語られませんでしたが、本作では「時を司る巫女」と「光を司る巫女」として、また「未来から来たハイラル王家の末裔」と「初代王妃」として、二人が深い絆で結ばれていく過程が感動的に描かれます。
この「日常パート」が充実しているからこそ、後にガノンドロフの裏切りによって引き起こされる悲劇が、より一層重く、深く突き刺さるのです。
ラウルやソニアとの「日常」と「封印戦争」への流れ
ティアキン本編では、ラウルは「ハイラル初代国王」として威厳ある姿が印象的でしたが、本作ではゼルダ姫と接する中で見せる「優しき長」としての一面や、ソニアと過ごす穏やかな時間など、彼の人間的な魅力が深く掘り下げられています。
ミネルも同様です。 ティアキンでは「魂の賢者」としてゴーレムの姿での登場がメインでしたが、本作では生身のゾナウ族としての彼女が、研究者として、そしてラウルの妹として、いかにゼルダ姫を支えていたのかが克明に描かれます。
これらの丁寧な描写があるからこそ、「封印戦争」への流れが単なる歴史のイベントではなく、「彼らの日常が奪われた」という強烈な当事者意識を持って体験できるのです。
ティアキンの伏線を「答え合わせ」するカタルシス
そして何より、ティアキン本編に残された伏線や謎が、本作をプレイすることで「そういうことだったのか!」と見事に繋がっていくカタルシスは、ティアキンファンであればあるほど鳥肌が立つはずです。
例えば、ティアキンでは「なぜミネルだけが魂をゴーレムに移してまで未来に干渉できたのか」「ガノンドロフはなぜあれほどまでにラウルたちを憎んでいたのか」といった、断片的な情報から推測するしかなかった部分。 これらに対する「公式の答え」が、本作のストーリーの中で明確に示されます。
本作をクリアした後に、もう一度ティアキンをプレイし、「龍の泪」の記憶を見返してみてください。 以前とは比べ物にならないほどの情報量と感情が押し寄せ、ゼルダ姫やラウルたちが発する一言一句の「重み」が、まったく違って感じられるはずです。
理由2:物語の核を握る「新キャラクター」の衝撃
「どうせ結末はティアキンで見た通りなんでしょう?」 そう思っている方にこそ、本作をプレイしてほしい。
本作のストーリーは、私たちが知っている「封印戦争」の結末に向かって進んでいきます。 しかし、その過程には、ティアキン本編には一切登場しなかった「とんでもない爆弾」が仕掛けられていました。 それが、本作オリジナルの新キャラクター「謎のゴーレム」と「コログ族のカラモ」です。
リンクに酷似した「謎のゴーレム」の正体とは
発売前のトレーラーから一部で話題になっていた、リンクに酷似した「謎のゴーレム」。 緑の衣をまとい、その身のこなしや紋章までもがリンクそっくりなこのゴーレムは、一体何者なのか。
彼は物語の序盤でゼルダ姫と出会い、彼女を守るように行動を共にします。 ティアキン本編では語られなかった、ゾナウ族のゴーレム技術の更なる側面や、あるいは「リンク」という存在そのものの根幹に関わるような、非常に重要な立ち位置のキャラクターです。
なぜ彼はリンクに似ているのか。 なぜ太古の時代に存在したのか。 そして、なぜティアキンの時代に彼の存在は伝わっていなかったのか。
その全ての答えが明かされた時、私は驚きと共に、ティアキンの物語の奥深さに改めて感服させられました。 この「謎のゴーレム」の存在こそが、本作を単なる「前日譚」から、「もう一つの本編」へと昇華させている最大の要因です。
もう一人の主人公「コログ族のカラモ」
そして、もう一人の重要な新キャラクターが、コログ族の「カラモ」です。 彼は「自分が仕えるべき土地(デクの樹サマの代わり?)」を探して太古のハイラルを旅しているコログで、コログ族らしいお調子者で軽妙な口調が特徴です。
シリアスで重厚なストーリーが続く中、彼の存在は清涼剤のようであり、時にコミカルなやり取りで場を和ませてくれます。 「ああ、無双オリジナルのマスコットキャラかな」と最初は思っていました。
しかし、物語が進むにつれ、彼が担っている役割が、想像を絶するほどに重要であったことが判明します。 ティアキンで私たちが体験した「ある出来事」の裏に、この「カラモ」というコログが深く関わっていた……。 この事実が明かされるシーンは、本作屈指の感動ポイントであり、エンディングを見た後、すぐにティアキンを起動して「あの場所」へ確認しに行きたくなること間違いなしです。
なぜ限定版のメインが彼らなのか?プレイすれば分かる納得感
本作の限定版(コレクターズエディション)に付属するグッズ(マフラータオルやアクリルフィギュアなど)は、なんとゼルダ姫やラウルではなく、この「謎のゴーレム」と「カラモ」の二人がメインデザインとなっています。
発売前は「なぜ新キャラが?」と疑問に思ったものですが、クリアした後なら100%納得できます。 本作の物語は、実質的にこの二人が「もう一人の主人公」としてゼルダ姫を支え、導いていく物語でもあるからです。
ちなみに、限定版はゲームソフトがダブルのを避けたい人向けに「グッズのみ」のパッケージも販売されています。 通常版をプレイして、私のようにこの二人の大ファンになった方は、後からグッズだけ購入できるという配慮も非常に嬉しいポイントでした。
理由3:Switch 2の性能を活かした「圧巻の無双アクション」
本作は「Nintendo Switch 2」専用タイトルとして開発されたことで、そのアクションパートは前作「厄災の黙示録」から飛躍的な進化を遂げています。
60fpsと敵200体の「真の無双体験」
「厄災の黙示録」をプレイした方の中には、処理落ちやフレームレートの低下、解像度の低さに悩まされた方も少なくないでしょう。 あの壮大な戦いをSwitchで描こうとした意欲は素晴らしいものでしたが、マシンパワーの限界を感じる場面があったのも事実です。
しかし、本作は違います。 Switch 2の性能をフルに活かし、フレームレートは常時60fps(可変ではなく安定)を実現。 同時に表示される敵の数は、100体どころか、優に200体を超えてきます。
高解像度でくっきりと見える画面の中で、滑らかに動くキャラクターが、文字通り「ワラワラと」群がる敵の大群をなぎ倒していく。 これこそが私たちが求めていた「ゼルダ無双」の理想形であり、「真の無双体験」と言えるでしょう。
敵兵士の一人ひとりも棒立ちではなく、それぞれが個別に動いているのが分かるほどで、戦場の臨場感が格段に向上しています。
ミネルやゼルダ姫のアクションを徹底解剖
アクションの手触りも最高です。 ボタン連打で次々とコンボが決まる爽快感はそのままに、各キャラクターの個性がティアキンの設定を色濃く反映したものになっています。
特に感動したのが「ミネル」のアクションです。 ティアキン本編ではゴーレムに搭乗しての戦闘でしたが、本作では生身のミネル(と、彼女が製造したゴーレム)を操作できます。 彼女はゾナウギアを使ったアクションを得意としており、ボタンコンボの途中で様々なゾナウギアを瞬時に繰り出し、戦局を有利に進めます。
例えば、車輪をボクシングのグローブのように両腕に装着して高速パンチを繰り出したり、トゲ付きの車輪がついた乗り物で敵陣に突撃したり、放水栓と雷龍の頭を組み合わせて広範囲を感電させたり……。 ティアキンでは「スクラビルド」や「ブループリント」で手間をかけて作っていたような組み合わせを、無双のアクションとして瞬時に、かつド派手に繰り出せるのです。 この「ティアキンでやりたかったけど難しかったこと」を簡単に実現できるギャップが、たまらなく楽しい。
ゼルダ姫も、ティアキンで覚醒した「光の力」を存分に使ったアクションがメインとなります。 光の矢を放ったり、聖なる力で敵を拘束したりと、その動きは優雅でありながらも力強く、まさに「戦う姫」といった風格を感じさせます。
新システム「ジンクストライク」「チェンジアクション」で共闘感がMAX
本作ならではの新システムも、戦いをさらに熱くさせます。
「ジンクストライク」は、いわゆる仲間との連携必殺技です。 共闘ゲージが溜まった仲間の近くでLボタンを押すと発動し、ペアになる仲間によって異なるド派手な演出と共に、敵に甚大なダメージを与えます。
例えば「ゼルダとラウル」なら、二人の光の力が合わさり、広範囲の敵を消し飛ばす聖なる一撃を放ちます。 「ゼルダとミネル」なら、ミネルが操縦する巨大ゴーレムにゼルダが乗り込み、一定時間無敵状態で暴れ回るなど、組み合わせを試すだけでも楽しい要素です。
さらに「チェンジアクション」は、仲間が敵の攻撃を防いだり、特定の状況になったりした際に呼びかけが発生し、それに応じると即座に操作キャラクターが切り替わるシステムです。 これにより、複数のキャラクターをテンポよく切り替えながら戦う「共闘感」が、前作以上に強調されています。
中ボス戦も単なるゴリ押しでは勝てません。 敵が攻撃した後などに一瞬だけ表示される「ウィークポイントゲージ」を、通常攻撃や固有技、時にはステージの地形(ゾナウギアギミックなど)を利用して削り切ることで、大ダメージを与えるチャンスが生まれます。 この戦略性が、アクションの単調さを防ぐ良いアクセントになっています。
理由4:ティアキンファン感涙の「小ネタ」と「ファンサービス」
本作は、ティアキンのシステムや世界観を徹底的にリスペクトしており、全編にわたって「ティアキンファン」をニヤリとさせる小ネタやファンサービスが満載です。
UIからBGMまで「ティアキン」を完全踏襲
まず、メニュー画面を開いた瞬間に驚くはずです。 ミッション選択画面は、ティアキンのハイラルマップ(太古の時代のもの)を模したデザインになっています。 素材アイテムや武器の管理画面のレイアウト、アイコンのデザイン、フォントに至るまで、ティアキンのUIを忠実に踏襲しています。
流れるBGMや効果音も、その多くがティアキンで使用されたもののアレンジ、あるいはそのまま使用されています。 バトル中にティアキンのメインテーマが流れたり、ゾナウギアの起動音が聞こえたりするたびに、ティアキンでの冒険の記憶が蘇り、モチベーションが上がります。
「もう疲れちゃって…」あのコログも登場
ティアキンで(いろんな意味で)私たちを夢中にさせた「コログ族」も、もちろん登場します。 各ステージの様々な場所に隠れているコログを見つけると「コログのミ」がもらえます。
そして、ティアキンで社会現象(?)にもなった「友達のところへ連れて行ってほしいコログ」も登場。 彼らに話しかけると、あの「もう疲れちゃって…全然動けなくて…」という、聞き覚えのあるセリフを発するのです。 無双の戦場でそんなことを言われても困るのですが、このネタをしっかり拾ってくれた開発陣の「分かってる感」には、思わず笑ってしまいました。
ゾナウギアを使った無双アクション
ミネルのアクションで前述しましたが、ゾナウギアは他のキャラクターもサブウェポンとして使用できます。 放水栓で敵を濡らしてから、雷龍の頭で追撃する。 扇風機で敵を吹き飛ばし、崖から落とす。 火龍の頭で敵の拠点を丸ごと焼き払う。
ティアキンで私たちが編み出した様々なコンボを、無双アクションとして手軽に繰り出せるのは、本作ならではの楽しみと言えるでしょう。
理由5:空島が舞台の「本格シューティングパート」
本作には、通常の無双アクションステージとは別に、特殊な「シューティングパート」が存在します。 これが、往年の「スターフォックス」シリーズを彷彿とさせるような、本格的な3Dシューティングステージなのです。
「厄災の黙示録」でも神獣を操作するシューティング風のステージはありましたが、あちらはどちらかというと固定砲台的な側面が強かったのに対し、本作は違います。
ゼルダやミネルがゾナウの飛行装置(あるいはゴーレム)に乗り込み、強制スクロールで進む空島を縦横無尽に飛び回ります。 飛んでくる敵の編隊をロックオンレーザーで撃ち落とし、敵の攻撃はローリングで回避する。 道中ではゾナウギアによる特殊攻撃(炎攻撃や広範囲ロックオンなど)も使用でき、非常に戦略的かつスピーディーな空中戦が楽しめます。
何より、ティアキンであれほど夢中になって探索した「空島」が戦いの舞台になっているのが熱い。 美しい空島群の間を高速ですり抜け、最後にはティアキンで散々苦しめられた「グリオーク」のような強大な敵とドッグファイトを繰り広げる展開は、ティアキンファンにとって最高のファンサービスの一つと言えるでしょう。
実際にプレイして感じた「惜しい点」と「課題」
ここまで本作の魅力を熱弁してきましたが、もちろん手放しで全てを賞賛するわけではありません。 「無双」ゲームとして、また「ティアキンの前日譚」として、いくつか「惜しい」と感じた点や、人によっては「合わない」かもしれない課題も存在します。
課題1:キャラゲーとしては魅力が薄い? 現代の賢者たちは登場せず
本作の舞台は、はるか太古の「封印戦争」の時代です。 したがって、ティアキンでリンクと共に戦った現代の賢者たち――リト族のチューリ、ゾーラ族のシド、ゴロン族のユン坊、ゲルド族のルージュ――は、まだ生まれていません。 当然、プレアブルキャラクターとして登場することはありません。
彼らの代わりに、本作オリジナルの「仮面をかぶった4人の戦士」(リト族、ゾーラ族、ゴロン族、ゲルド族の先祖たち)や、その他のオリジナルキャラクターが操作可能になります。 しかし、彼らはメインストーリーに深く絡んでくるわけではなく、やはりティアキンで愛着のあるチューリたちに比べると、馴染みが薄いのは否めません。
「無双」ゲームの魅力の一つは、好きなキャラクターを操作して暴れ回る「キャラゲー」としての側面です。 その点で、本作はストーリーの整合性を完璧に重視した結果、ティアキンの人気キャラクターたちの多くを参戦させることができなくなってしまいました。 これは「ティアキンの前日譚」を描く上での宿命であり、苦渋の判断だったのでしょう。
個人的には、本編クリア後の「おまけ」として、時系列を無視した「ifストーリーモード」のようなもので、現代の賢者たちも参戦できたら最高だったな、と思います。
なお、本作は今後2回の無料アップデートが予定されています。 詳細は不明ですが、「無双」のお約束としてプレアブルキャラクターの追加は高確率であると予想されます。 そこに何らかのサプライズが用意されていることを期待したいですね。
課題2:戦闘のテンポを阻害する「煩雑なUI」
これは、ティアキンの「ゾナウギア」システムを無双に持ち込んだ弊害かもしれません。 本作では、各キャラクターの固有技(コンボ)の他に、サブウェポンとして「ゾナウギア」や「特殊アクション」をショートカットに登録し、戦闘中に切り替えて使用できます。
問題は、この登録できるアクションの種類が、最終的に数十種類にも及ぶことです。 戦況に合わせて「今は放水栓と雷龍の頭を使いたい」「次は扇風機で吹き飛ばしたい」と、戦闘中に何度もメニューを開いてアクションをセットし直す必要が出てきます。 この「メニューを開いてゲームを止める」という行為が、ボタン連打で敵をなぎ倒していく「無双」ゲームの直感性やテンポ感と、正直言って噛み合っていません。
さらに悪いことに、このアクションセットはキャラクターごとに個別管理です。 操作キャラクターが増えれば増えるほど、このセットアップ作業が煩雑になっていきます。
「厄災の黙示録」では、携帯アイテムとシーカーアイテムが合計8種類に固定され、瞬時に切り替えられたため、非常に直感的でした。 ティアキンの「なんでもできる自由度」を無双に取り入れようとした結果、アクションゲームとしてのテンポを少し犠牲にしてしまった印象です。
課題3:無双シリーズ特有の「反復性」と「ステージの長さ」
これは本作に限った話ではなく、「無双」シリーズが本質的に抱える課題ですが、やはりゲームプレイの反復性(マンネリ感)は否めません。 「敵を倒し、拠点を制圧する」という基本ルールは変わらないため、戦闘がパターン化しやすいのです。
また、特に後半のステージになってくると、1ステージあたりのプレイ時間が非常に長くなる傾向があります。 「ようやくボスを倒した!」と思ったら、間髪入れずに次のミッションがノンストップで始まり、増援が現れる……といった展開も多く、かなりの集中力と体力を要求されます。
ティアキンのように「ちょっとあの祠だけクリアしよう」「あのコログだけ見つけよう」といった、細切れのプレイがしにくい構造です。 メインストーリークリアまでのプレイタイムは約20時間前後、やり込み要素(全ミッションクリアや武器収集など)を含めるとその倍以上かかりますが、1ステージあたりの消費カロリーが高いため、実際のプレイ時間以上に「濃密(あるいは、疲れる)」と感じるかもしれません。
封印戦記をプレイするとティアキンの「見方」が変わる
いくつかの惜しい点を挙げましたが、それらを補って余りあるほど、本作のストーリーがティアキンファンに与える感動は絶大です。
ゼルダ姫が背負った「重み」の再認識
ティアキン本編でも、ゼルダ姫が途方もない覚悟の上で「龍化」を選んだことは描かれていました。 しかし、本作で彼女が太古のハイラルで過ごした「日常」、ラウルやソニアたちと育んだ「絆」、そして「封印戦争」での壮絶な戦いをプレイヤー自身が追体験することで、彼女が失ったものの大きさと、それでも未来(リンク)のために全てを捧げた決断の「重み」が、まったく違った次元で理解できるようになります。
本作をクリアした後では、ティアキンで白龍となってハイラル上空を飛び続けるあの姿を見るだけで、涙腺が緩んでしまうかもしれません。
ティアキン本編の「あのセリフ」が持つ本当の意味
本作をプレイすることで、ティアキン本編でのキャラクターたちのセリフ、特にラウルやミネル、そしてガノンドロフが発した言葉の「裏」にあった文脈が理解できるようになります。
なぜラウルは、リンクに対してあのような言葉を託したのか。 なぜミネルは、あそこまでしてリンクに協力しようとしたのか。 そして、新キャラクターである「謎のゴーレム」と「カラモ」の存在を知った上でティアキンの物語を振り返ると、リンクの冒険そのものが、太古から連綿と受け継がれてきた「壮大なドラマ」の集大成であったことを改めて実感させられます。
「封印戦記」クリア後にもう一度ティアキンをプレイしてほしい理由
私自身、本作をクリアした後、すぐに「ティアキン」を起動しました。 そして、真っ先に「龍の泪」を巡り、メインストーリーをもう一度追いかけました。
「ああ、あの時のゼルダ姫は、こんな想いでこの言葉を発していたのか」 「ラウルのこの行動には、封印戦記でのあの出来事が背景にあったのか」
全ての「点」が「線」として繋がった時、ティアキンの物語は、私の中で「傑作」から「神話」へと昇華されました。 本作「ゼルダ無双 封印戦記」は、ティアキンのストーリーを100%理解し、その感動を最大化するために「必須」のピースです。
まとめ
「ゼルダ無双 封印戦記」は、単なる「無双」の派生作品ではありません。 また、「厄災の黙示録」のような「ifストーリー」でもありません。 これは、ティアキンで断片的にしか語られなかった「太古の物語」を、真正面から描き切った「公式の正史」であり、「完璧な前日譚」です。
Switch 2専用タイトルとして進化した圧巻のアクション、そして何よりも、ティアキンファンであればあるほど深く突き刺さる、衝撃的で感動的なストーリー。 「キャラゲー」としての弱さや「無双」特有の反復性といった欠点はありますが、それらを霞ませるほどの圧倒的な「ティアキン補完体験」が待っています。
もしあなたが「ティアーズ オブ ザ キングダム」という作品を心の底から愛しているのなら、本作をプレイしないという選択肢はありません。 ゼルダ姫が何を失い、何を守ろうとしたのか。 その全てを、ぜひあなた自身の目で見届けてください。