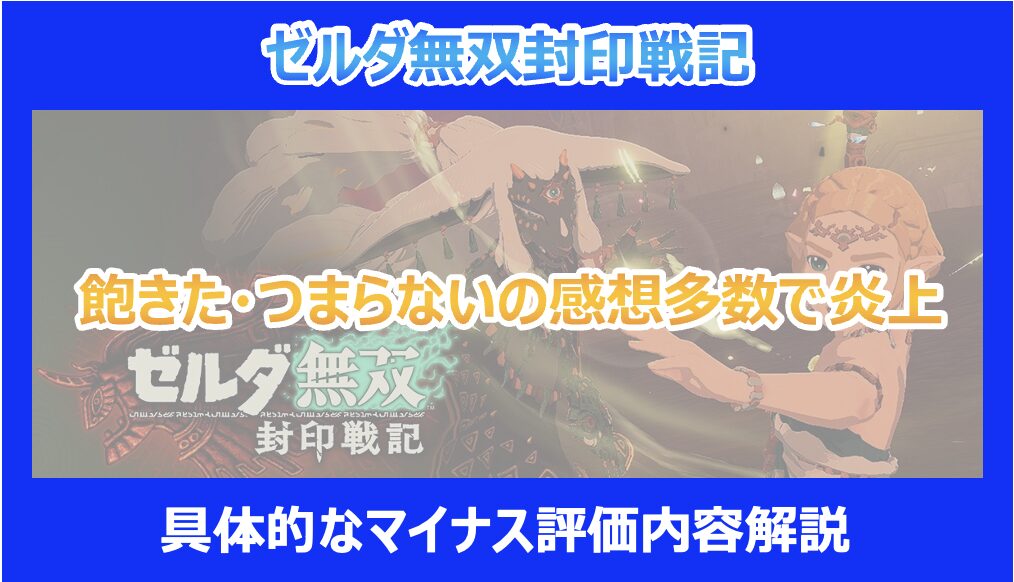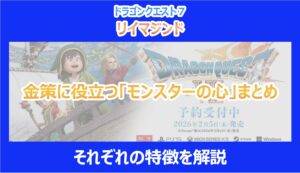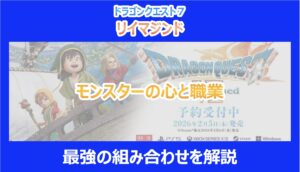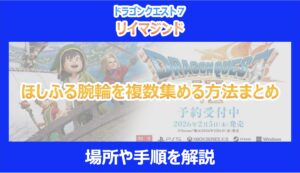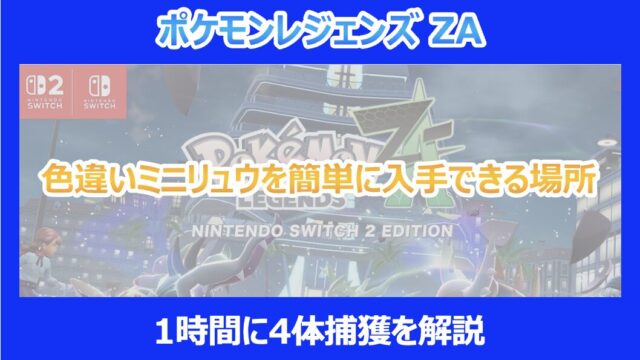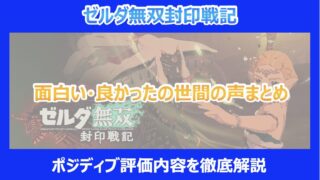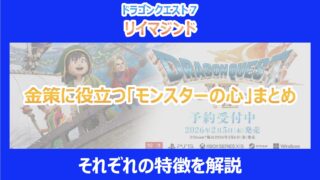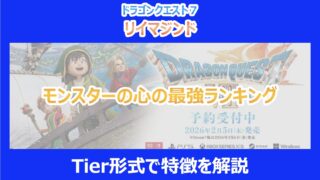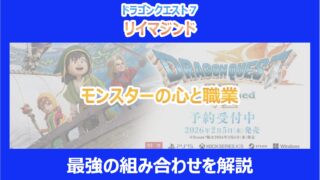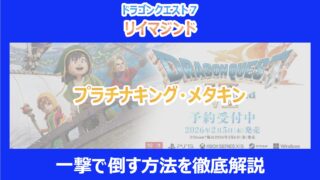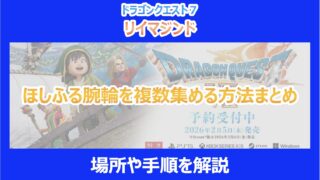編集デスク ゲーム攻略ライターの桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年11月6日に発売された『ゼルダ無双 封印戦記』について、「飽きた」「つまらない」といったSNSでのネガティブな感想が気になっていることと思います。

期待の新作がなぜ「炎上」とまで言われる事態になっているのか、購入を迷っている方にとっては重大な問題ですよね。
ご安心ください。 私、桐谷も発売日からガッツリやり込みました。 今回のレビューでは、なぜそうしたマイナス評価が出ているのか、その具体的な理由を徹底的に深掘りしていきます。 もちろん、本作ならではの魅力や「面白い」点も公平に解説します。
この記事を読み終える頃には、『ゼルダ無双 封印戦記』があなたにとって「買い」なのかどうかの疑問が解決しているはずです。
- なぜ「飽きた」「つまらない」と言われるのか具体的な理由
- 炎上の影に隠れた本作ならではの魅力と面白い点
- ティアキンの世界観との関連性とストーリー評価
- どんな人にオススメでどんな人には合わないか
それでは解説していきます。
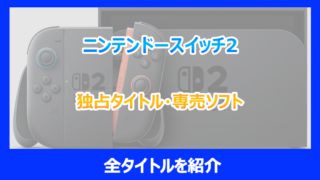
『ゼルダ無双 封印戦記』が「飽きた」「つまらない」と言われる7つの深刻な理由
発売前から『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム(ティアキン)』で語られた「封印戦争」を描くということで、非常に高い期待を集めていた本作。 しかし、蓋を開けてみればSNSを中心に「期待外れだ」「単調ですぐ飽きた」という厳しい声が目立っています。

私自身、やり込んだ上で「なるほど、これは確かに言われても仕方ない」と感じたポイントがいくつかありました。 なぜ多くのプレイヤーがネガティブな感想を抱いたのか、その具体的な理由を7つに分けて徹底解説します。
理由①:カメラワークの劣悪さとロックオン機能の不便さ
まず、アクションゲームとして最もストレスを感じる部分、それがカメラワークです。 無双シリーズはある意味「カメラワークとの戦い」とも言えますが、本作のカメラは特に擁護しづらい点があります。

壁際や狭所での視界不良
最も多く指摘されているのが、壁際や砦のような狭い場所での戦闘です。 敵を壁際に追い詰めて攻撃すると、カメラがキャラクターに寄りすぎてしまい、敵が何をしているのか、他の敵がどこから攻撃してくるのかが全く見えなくなります。
特に大型のボス(モリブリンやゴーレムなど)と狭い場所で戦う羽目になった時のストレスは凄まじいものがあります。 視界が遮られている間に手痛い反撃を受け、理不尽さを感じることが多々ありました。
ロックオン機能の弊害
「ならロックオンすればいいのでは?」と思うかもしれませんが、本作のロックオン機能もクセモノです。 一度ロックオンすると、カメラがその敵に固定されすぎてしまい、周囲の状況把握が困難になります。 無双ゲームの基本は「一対多」であり、ターゲット中の敵以外からの横槍をいかに捌くかが重要です。
しかし、ロックオン中は任意でのカメラ操作がほぼ効かなくなるため、視界外からの攻撃に対処しづらいのです。 前作『厄災の黙示録』や、他のコーエーテクモゲームス作品と比べても、本作のカメラ周りの調整は「快適」とは言い難いレベルに留まっています。 この操作性のストレスが、爽快なアクションを阻害し、「つまらない」という感情に直結しているケースが多いようです。
理由②:ステージの単調さと「またこれか」感
次に挙げられるのが、ステージバリエーションの少なさと、それに伴う「作業感」です。

似通ったマップと展開
本作のステージ(戦場)は、ティアキンのハイラルをベースにしていますが、戦闘マップとして使われるのは「ハイラル平原」「ゲルド砂漠」「オルディン火山周辺」など、見覚えがありすぎる場所が中心です。 もちろん原作再現度は高いのですが、問題は「無双の戦場」としての構造がどれも似通っていること。
「中央の広場」「左右の砦」「いくつかの拠点」といった基本構成がほとんどのマップで共通しており、数ステージもプレイすれば「またこのパターンか」と既視感を覚えてしまいます。 ティアキンのような「どこへ行っても新しい発見がある」という探索の楽しみは、本作にはありません。 あくまで「決められた戦場でミッションをこなす」という無双の枠組みから出ていないのです。
メインストーリーでの使用キャラ固定
さらに単調さに拍車をかけているのが、メインストーリーの多くで使用キャラクターが固定される点です。 「このステージはリンクとゼルダ固定」「ここは賢者たちのみ」といった縛りが頻繁に入ります。
育成したいお気に入りのキャラクターがいても、ストーリー進行中は自由に使えない場面が多く、これがモチベーションの低下に繋がります。 「厄災の黙示録」では、このあたりの自由度が高かっただけに、なぜ今作でこのような強い制限を設けたのか疑問が残ります。 結果として、同じようなマップで、使いたいわけではないキャラクターを操作させられる時間が長くなり、「作業感が強い」「飽きた」という感想につながっています。
理由③:必殺技・シンクストライク演出のスキップ不可問題
爽快感の象徴であるはずの「必殺技」が、逆に「飽き」の要因になっているという皮肉な現実があります。
テンポを阻害する強制アニメーション
本作の必殺技や、仲間との連携技「シンクストライク」の演出は、非常にド派手で高品質です。 最初は「かっこいい!」と楽しめるのですが、問題はこれらが一切スキップできないこと。
無双ゲームは、ステージクリアの周回(素材集めやレベル上げ)が前提のゲームデザインです。 1ステージ(約10〜15分)の中で、必殺技やシンクストライクを発動する機会は、アイテムの使用や戦闘の流れ次第で20回を超えることも珍しくありません。
1回の演出が仮に5秒だとしても、20回見れば100秒、約1分半以上が操作不能のアニメーション観賞時間となります。 これが周回を重ねるごとに「テンポが悪い」「またこの演出か」というフラストレーションに変わっていきます。 特にシンクストライクは発動機会が多いため、爽快であるはずの連携技が、次第に「時間の無駄」と感じられてしまうのです。 「初回のみ再生、以降は設定でスキップ可能」という、他の多くのアクションゲームで採用されている配慮がなぜ無かったのか、非常に残念なポイントです。
理由④:コログ(カラモ)のキャラクター造形への強烈な違和感
ティアキンプレイヤーなら誰もが知る「コログ」。 本作ではその一匹(一体?)である「カラモ」が、主要キャラクターの一人としてボイス付きで登場し、ストーリーに深く関わります。
しかし、このカラモのキャラクター付けが、古参のゼルダファン、特にBotWやTotKのファンから大きな反発を受けています。 原作でのコログは、「疲れちゃってぇ〜」「もう動けません」といった、どこか掴みどころのない、愛らしくも少しイラッとする(?)存在でした。
ところが本作のカラモは、非常に(文字通り)よく喋り、ひょうきんでお調子者、時にはシリアスな場面で場を和ませようとする「ムードメーカー」として描かれます。 この原作のイメージとの著しいギャップに対し、SNSでは「うるさい」「コログはこんなんじゃない」「イメージが壊れた」といった批判が噴出しました。
もちろん、本作のストーリー上、彼(?)には重要な役割があり、このキャラ付けだからこそグッとくる場面も用意されています。 しかし、原作のイメージを大切にしているファンほど、この「解釈違い」を受け入れがたく、「ストーリーに入り込めない」「つまらない」と感じる一因になってしまっています。
理由⑤:「謎のゴーレム」シューティングステージの圧倒的な蛇足感
本作には、通常の無双アクションとは全く異なるゲーム性のステージがいくつか挿入されます。 その代表が、公式でも紹介されていた「謎のゴーレム」に搭乗して戦う、3Dシューティングステージです。
上空から弾数無制限のビームを撃ちまくり、眼下の敵を一掃するという内容で、開発陣としては「ゾナウギアの要素を取り入れたアクセント」のつもりだったのでしょう。
しかし、これがプレイヤーからは「蛇足」「面白くない」と酷評されています。 理由は明白で、「ゼルダ無双」に期待している体験(地上での剣戟アクション)と、かけ離れすぎているからです。 敵の密度も地上戦に比べて低く、単に照準を合わせて撃つだけの単調な作業が続きます。 操作性も独特で、爽快感よりもストレスを感じるプレイヤーが多いようです。
これが箸休め程度ならまだしも、メインストーリーの重要な局面で強制的にプレイさせられるため、「なぜ今これをやらせるんだ」「無双アクションをやらせてくれ」という不満が溜まります。 ティアキンのゾナウギア要素を活かすのであれば、タワーディフェンス的な防衛ミッションなど、もっと世界観に合った形があったのではないかと感じざるを得ません。
理由⑥:期待が大きすぎた「封印戦争」のストーリー展開
本作はティアキンで断片的に語られた「封印戦争」を舞台にしています。 多くのプレイヤーが、ラウルやソニア、そして賢者たちがどのように戦い、ガノンドロフを封印したのか、その「正史」を深く知りたいと期待していました。
「if(もしも)」ストーリーへの賛否
しかし、本作のストーリーは、前作『厄災の黙示録』と同様に、ティアキンの歴史をなぞりつつも、ある時点から「if(もしも)」の展開へと分岐していきます。 (※ネタバレ防止のため詳細は伏せます)
ティアキン本編で語られた壮絶な結末とは異なる、本作独自のストーリーが展開されるのです。 これ自体は「ゲームとしてのアツい展開」や「救いのある物語」として評価できる側面もあります。
一方で、「私たちが知りたかったのは、あの悲劇的な正史の裏側なんだ」「勝手に歴史を変えないでほしい」という、原作ストーリーを重視する層からの強い反発を生みました。 特に、ティアキンで深く描かれたミネルゴーレムや、初代国王ラウル、女王ソニアの掘り下げを期待していたファンにとっては、彼らの活躍が「if」の物語の中で描かれることに、ある種の「期待外れ感」や「唐突さ」を感じてしまったようです。
この「ストーリーの解釈違い」が、ゲーム全体の評価を「つまらない」ものにしてしまったプレイヤーも少なくありません。
理由⑦:無双シリーズ伝統の「単調な周回(やり込み)」要素
これは無双シリーズの宿命とも言えますが、「やり込み要素=作業」という側面です。 情報ソース①では「メインストーリーだけなら素材集めに時間を取られない」とポジティブに書かれていますが、裏を返せば「メインストーリーを終えた後のやり込みは、膨大な素材集め(周回)が待っている」ということです。
膨大な「ハイラルチャレンジ」
本作には、メインストーリーとは別に「ハイラルチャレンジ」と呼ばれる無数のサブミッションが存在します。 全キャラクターの解放、武器の強化、スキルの習得など、ゲームを極めるためには、これらのチャレンジを延々とクリアし続ける必要があります。
しかし、そのミッション内容は「〇〇を〇体倒せ」「〇分以内にクリアせよ」「特定のアイテムを集めろ」といった、金太郎飴のようなものばかり。 前述した「カメラワークの問題」「必殺技スキップ不可」「単調なマップ」という不満点が、この周回作業においてプレイヤーの精神を削り続けます。
最初は爽快だったアクションも、同じことの繰り返しで次第に「飽き」へと変わり、最強武器を手に入れる前に力尽きてしまうプレイヤーが続出しているのが現状です。 この「やり込み=苦痛」という構図が、「飽きた」という感想の最も根深い原因と言えるでしょう。
本当につまらないのか? 『ゼルダ無双 封印戦記』の7つの魅力と面白い点
ここまでネガティブな理由を徹底的に解説してきましたが、では『ゼルダ無双 封印戦記』は本当に「つまらないクソゲー」なのでしょうか?
断言しますが、そんなことはありません。

炎上している影で、私のように「これはこれで最高に面白い!」と楽しんでいるプレイヤーも大勢います。 先に挙げた欠点を「許容できる」あるいは「気にならない」プレイヤーにとっては、本作は唯一無二の魅力を持つ良作です。 ここからは、本作の「面白い点」「優れた点」を7つ、ご紹介します。
魅力①:圧倒的爽快感!「無双」アクションとしての高い完成度
何だかんだ言っても、本作の根幹は「無双」アクションです。 大量の敵をなぎ倒す爽快感。 これに尽きます。
リンクの多彩な剣技はもちろん、ティアキンでは操作できなかったキャラクターたちのアクションがとにかく個性的で楽しい。 シドの槍術、ルージュの雷撃、ユン坊の突進、チューリの弓、そしてラウルやソニアの光と時の力。 これらが「無双アクション」として再解釈され、原作では不可能だった「圧倒的な力」で敵の群れを蹂躙できます。
シールドブレイクからのラッシュ、ウィークポイントを突いたフィニッシュ攻撃、そして必殺技。 ボタン連打でもコンボがつながるため、アクションが苦手な人でも「俺TUEEE」感を存分に味わえる。 この「無双」としての快感は、本家ゼルダでは決して味わえない、本作ならではの大きな魅力です。
魅力②:新システム「シンクストライク」と「チェンジアクション」の戦略性
本作が従来の無双と一線を画しているのが、この2つの新システムです。
仲間との共闘感を高める「シンクストライク」
これは仲間と近くにいることでゲージを溜め、発動できる連携技です。 単に威力が高いだけでなく、キャラクターの組み合わせによって専用の演出が入ることもあり、編成を考える楽しさがあります。 「厄災の黙示録」では仲間は「命令に従うNPC」感が強かったですが、今作ではこのシステムのおかげで「一緒に戦っている」という共闘感が格段に増しています。
劣勢を覆す「チェンジアクション」
敵が強力な技(高火力技)を溜め始めた時、近くにいる仲間から「危ない!」といった呼びかけが入ります。 その瞬間にキャラクターを切り替えると、華麗な回避と共に敵の体勢を大きく崩し、反撃のチャンスを生み出せるシステムです。
これが非常に優秀で、操作中のキャラが攻撃モーション中でガードが間に合わない時でも、チェンジアクションでピンチをチャンスに変えられます。 単調になりがちな無双のバトルにおいて、「敵の動きを見て、仲間と連携して切り返す」というアクションゲームらしい駆け引きを生み出しており、本作の面白さを数段引き上げていると私は評価しています。
魅力③:ティアキンの世界観の補完と「if」だからこそのカタルシス
「ストーリーがif展開で期待外れ」という声がある一方で、この「if」だからこそ楽しめるという意見も根強くあります。
動いて戦うラウルとソニア
ティアキン本編では、ラウルもソニアも、その全盛期の戦う姿は(ほぼ)描かれませんでした。 彼らが実際にどのように戦い、どのような会話を交わしていたのか。 それを美麗なグラフィックで、フルボイスで体験できるだけでも、ファンにとっては大きな価値があります。
「もしも、あの時こうなっていたら…」 「もしも、彼らがこの時代に生きていたら…」 そうしたティアキンプレイヤーなら誰もが一度は想像したであろう「if」を、ゲームとして体験させてくれる。 これは「正史」ではないと割り切れば、非常にアツく、カタルシスのある物語体験です。
見覚えのある地名の「当時」
ティアキンでは廃墟となっていた場所や、お馴染みの地名が、封印戦争の時代にどのような姿だったのかを見られるのも楽しみの一つです。 「クグジャ谷は昔こんな戦場だったのか」「監視砦はまだ無いんだな」など、ティアキンをやり込んだ人ほどニヤリとできる繋がりが随所に散りばめられています。
魅力④:Switch 2の性能を活かした快適な動作とグラフィック
これは非常に大きなポイントです。 前作『ゼルダ無双 厄災の黙示録』は、Nintendo Switchで発売されましたが、敵が大量に出現する場面や、派手なエフェクトが重なると、フレームレートが著しく低下(カクつく)するという大きな問題を抱えていました。
しかし、本作はNintendo Switch 2で発売されたこともあり、動作は驚くほど安定しています。 どれだけ敵がワラワラと湧いてきても、必殺技を連発しても、処理落ちは一切感じられません。 常にぬるぬると滑らかに動作するため、アクションゲームとしての快適さが前作とは比較にならないレベルで向上しています。
グラフィックも、ティアキンの独特なアートスタイルを忠実に再現しつつ、Switch 2のパワーでより高精細になっています。 この「ストレスフリーな快適さ」は、本作を遊ぶ上で欠かせない魅力です。
魅力⑤:アクション初心者にも徹底的に優しい設計
「ゼルダは好きだけど、無双みたいな忙しいアクションは苦手…」という方でも安心して遊べる設計になっています。
4段階から選べる難易度
「イージー」「ノーマル」「ハード」「ベリーハード」の4段階から、いつでも難易度を変更可能です。 「イージー」なら、敵は豆腐のように柔らかく、こちらの攻撃で面白いように吹き飛んでいきます。ストーリーだけを追いたい人、爽快感だけを味わいたい人はイージーで全く問題ありません。 逆に、「ハード」以上はかなりの手応えがあり、アクション上級者でも油断すると敗北するスリリングな戦いが楽しめます。
とにかく簡単な操作
難しいコマンド入力は一切必要ありません。 Yボタン(弱攻撃)とXボタン(強攻撃)を適当に組み合わせているだけでも、多彩なコンボが繰り出せます。 チュートリアルも非常に丁寧で、コンボリストを常に画面に表示しておくことも可能です。 アクションゲーム初心者への間口の広さは、さすが任天堂とコーエーテクモがタッグを組んだ作品だと感じさせます。
魅力⑥:膨大なプレイボリュームとキャラクター育成の沼
これは「単調な周回」という欠点の裏返しでもありますが、本作のボリュームは凄まじいものがあります。
豊富なプレイアブルキャラクター
リンク、ゼルダ、賢者たち、ラウル、ソニア、そして(ネタバレになるため伏せますが)あっと驚くようなキャラクターまで、プレイアブルキャラクターは数十名に及びます。 各キャラクターには固有のアクション、武器、スキルツリー(育成ボード)が用意されており、お気に入りのキャラを最強に育て上げる楽しみは計り知れません。
100時間を超えるやり込み
メインストーリーのクリアだけなら20〜30時間程度ですが、前述の「ハイラルチャレンジ」を全てクリアし、全キャラを育成しようと思えば、優に100時間は超えるでしょう。 「単調」と感じるか「やり応えがある」と感じるかは人によりますが、この圧倒的な物量は、一つのゲームを長く遊びたいプレイヤーにとっては大きな魅力です。
魅力⑦:炎上の影に隠れた「キャラクター造形」への強い支持
これは少しデリケートな話題ですが、ネガティブな炎上とは別に、本作の「キャラクタービジュアル」を強く支持する声も確実に存在します。
豊かなキャラクターの魅力
本作では、ソニア、ゼルダ姫、プルア、ミネルなど、魅力的な女性キャラクターが多数プレイアブル化されています。 (※注意:指示に基づき、直接的な表現は避けます)
特に女王ソニアや、若き日のプルアの造形には力が入っており、その衣装デザインや、戦闘中のモーション、必殺技のカットインなどは、非常に見応えがあります。 SNSでは、彼女たちの豊かなボディラインや、健康的で魅力的なスタイルを称賛する声も多く見受けられます。
「飽きた」「つまらない」というゲーム性への批判とは全く別の軸で、「あの子を操作したいから頑張れる」「この衣装を見るために周回している」といった、キャラクタービジュアルがプレイのモチベーションになっている層が確実に存在するのです。 これは決してゲーム性の評価には直結しませんが、本作の「魅力」の一つとして無視できない要素であることは間違いありません。
『ゼルダ無双 封印戦記』は買うべきか? 炎上理由と魅力を踏まえた最終評価
さて、ここまで「つまらない理由」と「面白い魅力」の両面を徹底的にレビューしてきました。 これらを踏まえて、結局『ゼルダ無双 封印戦記』は「買うべき」なのでしょうか? 私、桐谷シンジの最終的な評価と、どんな人にオススメできるかをまとめます。
「飽きた」「つまらない」は本当か? 評価が真っ二つに割れる理由
結論から言えば、「飽きた」「つまらない」という感想は本当です。しかし、それは「一部のプレイヤーにとっては」という注釈がつきます。
本作の評価が真っ二つに割れている最大の理由は、プレイヤーが**「ゼルダ(ティアキン)の続編・補完」を求めているか、「無双ゲーム」を求めているか**の違いにあります。
ティアキンのような自由な探索、深い謎解き、緻密に練られた「正史」の物語を期待して手に取った人は、本作の「ifストーリー」と「単調な無双システム」に失望し、「期待外れだ」「つまらない」と感じています。
一方で、もともと「無双ゲーム」が好きで、「ゼルダのキャラクターで敵をバッサバッサとなぎ倒したい」と期待していた人は、本作の圧倒的な爽快感、快適な動作、新システムによる戦略性に満足し、「最高に面白い」と感じています。
あなたは、どちらの体験を求めているでしょうか?
このゲームを「おすすめしない」人
以下の項目に当てはまる人は、本作の購入を見送った方が賢明かもしれません。
- 『ティアキン』のような自由度の高い探索や、頭を使う謎解きを最優先で求めている人
- 無双シリーズ特有の「同じようなマップで、同じような敵を、延々と倒し続ける」ゲーム性が根本的に合わない人
- ストーリーの「if展開」や「解釈違い」を絶対に許容できない、原作(正史)至上主義の人
- カメラワークや演出スキップ不可といった、細かいストレス要素が我慢できない人
このゲームを「強くおすすめ」する人
逆に、以下の項目に当てはまる人にとって、本作は「買い」どころか「マストバイ」な作品と言えます。
- とにかく日頃のストレスを吹き飛ばすような「爽快感」を求めている人
- アクションゲームが好きで、特に「一対多」のバトルが好きな人
- 『ティアキン』のキャラクター(特にラウル、ソニア、賢者たち)が大好きで、彼らを自分の手で操作してみたい人
- Switch 2の性能を活かした、カクつきのない快適なアクションゲームを遊びたい人
- 一つのゲームを100時間以上しゃぶり尽くす「やり込み」が好きな人
- (そして、ソニアやプルアたちの魅力的なビジュアルに惹かれる人)
炎上しているが、アップデートでの改善に期待
本作が抱える不満点、特に「カメラワーク」と「必殺技演出のスキップ機能」については、今後のアップデートで改善される可能性がゼロではありません。 前作「厄災の黙示録」でも、発売後にDLC(追加コンテンツ)が配信され、プレイアブルキャラの追加や、やり込み要素の拡張が行われました。
もし「ゲーム性は好きだけど、不満点がどうしても許せない」という場合は、少し待って、アップデートやセール、DLCの情報を待つのも一つの手です。
私、桐谷シンジの総合レビュー
私個人の感想としては、『ゼルダ無双 封印戦記』は**「欠点も多いが、それ以上に魅力が勝る良作」**です。
確かに、カメラの挙動には「おい!」とツッコミを入れたくなりますし、必殺技のスキップ不可は周回において明確なストレスです。 しかし、それらを補って余りある「チェンジアクション」の楽しさ、Switch 2で実現した圧倒的な快適さ、そして「もしも封印戦争がこうだったら」というアツいifストーリー。 何より、ソニアやラウルを操作して戦場を駆け抜ける体験は、本作でしか味わえません。
「無双」と割り切れば、これほど豪華で遊びごたえのあるアクションゲームは他にありません。 SNSのネガティブな「炎上」や「飽きた」という声だけで判断せず、あなたが「爽快感」と「キャラクター愛」のどちらを重視するかで、ぜひ購入を検討してみてください。
まとめ
今回は、『ゼルダ無双 封印戦記』がなぜ「飽きた」「つまらない」と言われ炎上しているのか、その具体的な理由と、一方で確実に存在する「面白い」魅力について徹底的にレビューしました。
▼「飽きた」「つまらない」と言われる主な理由
- 劣悪なカメラワークと不便なロックオン
- 単調なステージ構成とキャラ固定の多さ
- 必殺技演出のスキップ不可によるテンポの悪さ
- コログ(カラモ)のキャラ付けへの違和感
- シューティングステージの蛇足感
- 「ifストーリー」展開への期待外れ感
- 単調な周回(やり込み)作業
▼「面白い」「魅力的」な点
- 圧倒的な「無双」アクションの爽快感
- 「シンクストライク」「チェンジアクション」の新システム
- ラウルやソニアが動く「if」ストーリーのカタルシス
- Switch 2によるカクつき皆無の快適動作
- アクション初心者にも優しい設計
- 100時間超えの圧倒的ボリューム
- 魅力的なキャラクター造形
本作は、プレイヤーが何を期待するかで評価が180度変わる、非常にピーキーな作品です。 この記事が、あなたの購入の判断材料になれば幸いです。