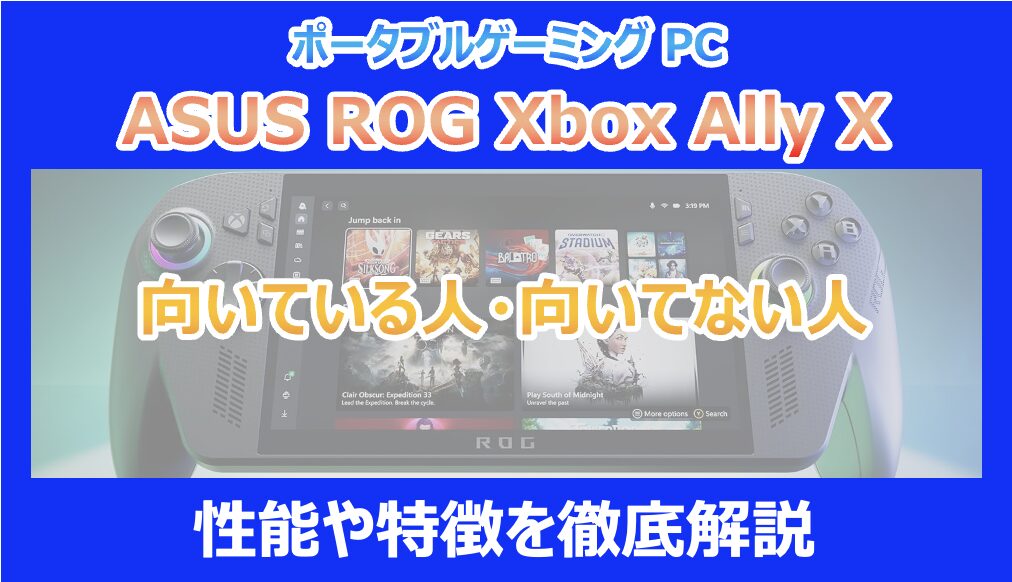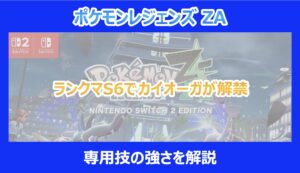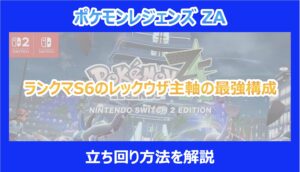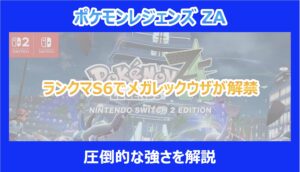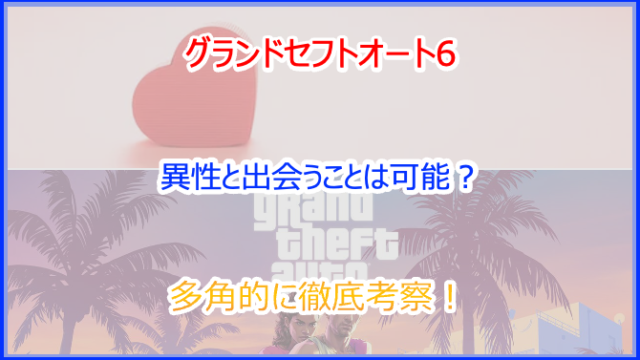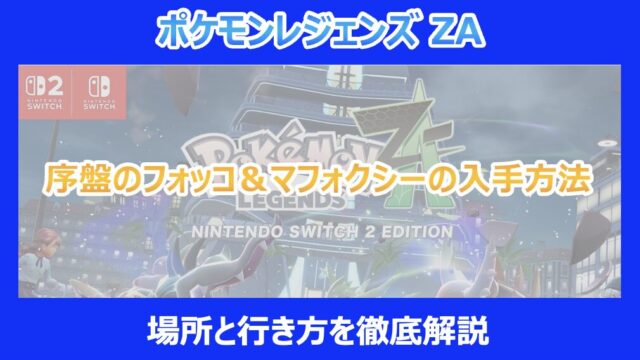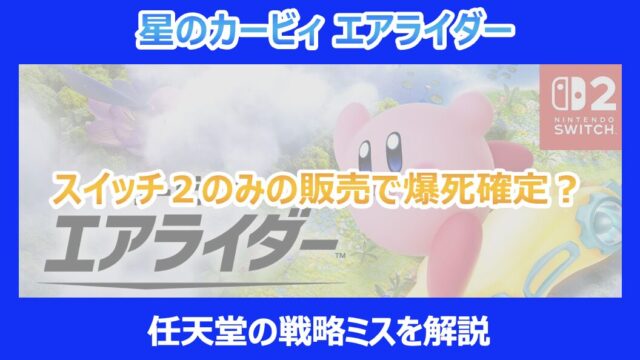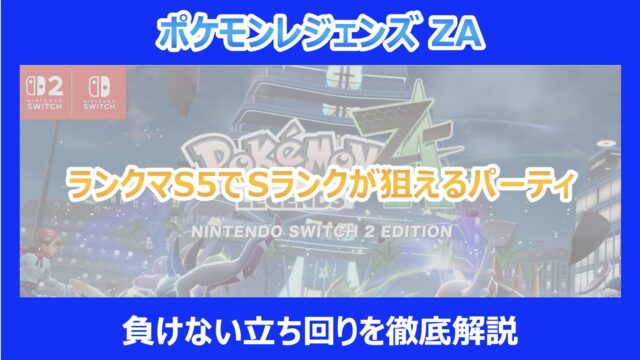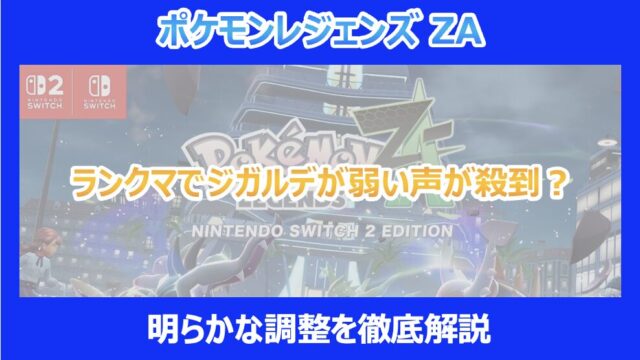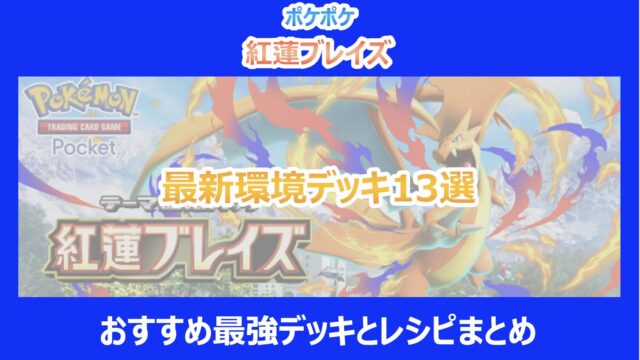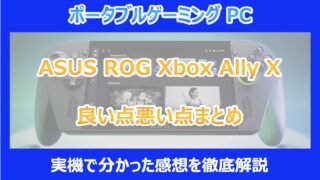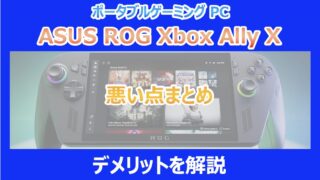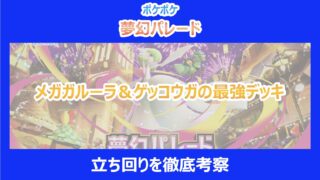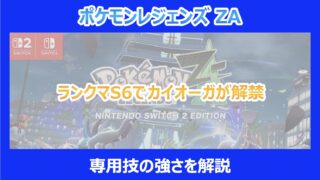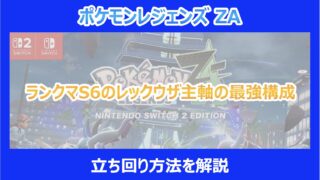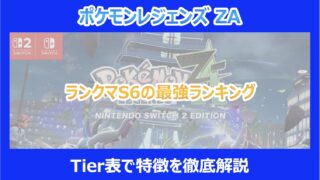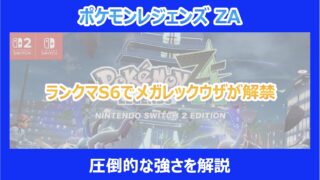編集デスク ガジェット担当の新海ミナです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、ASUSから登場した注目のポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」について、その実力や自分に合っているのかどうか、深く気になっているのではないでしょうか。
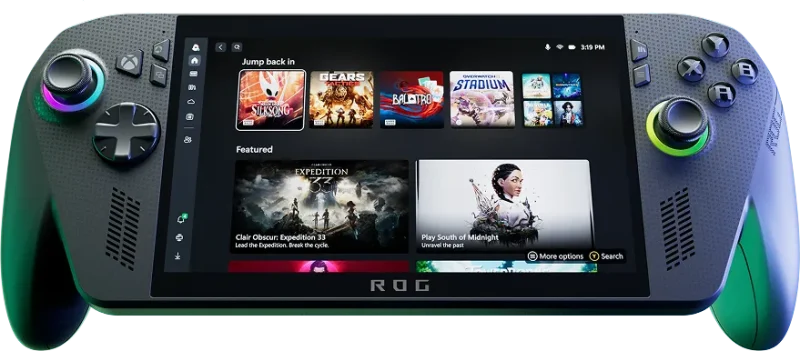
前モデルの登場以来、この「ハンドヘルドPC」というジャンルは本当に盛り上がっていますよね。 私もゲーム評論家として、また一人のゲーマーとして、この新しい波には非常に好奇心をそそられてきました。 今回、私自身もこの「ASUS ROG Xbox Ally X」を入手し、じっくりと遊びこんでみました。
この記事を読み終える頃には、あなたがROG Xbox Ally Xを手に入れるべきかどうかの疑問が、スッキリ解決しているはずです。
- 大幅に進化したバッテリーとメモリ
- 持ちやすさと熱設計の洗練
- Windows機ならではの無限の可能性
- 購入前に知るべきディスプレイの特性
それでは解説していきます。

ASUS ROG Xbox Ally Xの概要と前モデルからの進化点
まずは「ROG Xbox Ally X」がどのような製品なのか、基本スペックと特に注目すべき進化したポイントから見ていきましょう。
ハンドヘルドPCの新たなスタンダードへ
ASUS ROG Xbox Ally Xは、Windows 11を搭載したポータブルゲーミングPCです。
見た目は携帯ゲーム機そのものですが、中身は高性能なノートPCに匹敵します。 これにより、Steam、Epic Games Store、GOGといったPCゲーム配信プラットフォームの膨大なライブラリを、文字通りどこへでも持ち運んで遊ぶことができるんです。

前モデルも非常にパワフルでしたが、今回の「X」モデルは、ユーザーからのフィードバックを元に、多くの点がブラッシュアップされています。 特にバッテリーとメモリ、そして操作性に関わる部分が大きく進化しました。
ASUS ROG Xbox Ally X 詳細スペック
まずは、今回レビューする「ROG Xbox Ally X」(2025年10月時点)のスペックを詳しく見ていきましょう。
| 項目 | スペック |
|---|---|
| CPU | Ryzen AI Z2 Extreme (Zen 5世代 / 8コア16スレッド) |
| (大型コア Zen5 x3 + 小型コア Zen5c x5) | |
| 内蔵GPU | Radeon 890M (1024コア / 最大2.90 GHz) |
| メモリ | 24 GB (LPDDR5X-8000) |
| SSD | 1 TB (NVMe SSD / M.2 2280) |
| ディスプレイ | 7インチ フルHD (1920 x 1080) |
| 最大120 Hz / VRR対応 / タッチ対応 | |
| Gorilla Glass Victus / Gorilla Glass DXC | |
| ポート | USB 40 Gbps Type-C (DP Alt Mode / USB PD対応) |
| USB 10 Gbps Type-C (DP Alt Mode / USB PD対応) | |
| microSDカードスロット (UHS-II) | |
| 3.5mm ヘッドホン端子 | |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (MediaTek MT7922) |
| バッテリー | 80 Wh (リチウムイオンバッテリー) |
| 電源 | 65 W (ACアダプター) |
| OS | Windows 11 Home |
| 重量 | 約712 g |
| サイズ | 約 29.0 cm x 12.4 cm x 5.8 cm (最厚部) |
最大の進化点:バッテリー、メモリ、そして操作性
スペック表を見て「おっ」と思った方も多いはずです。 今回の「X」モデルは、単なるマイナーチェンジではありません。

圧倒的なバッテリー容量「80Wh」
前モデルや競合機が40Wh〜50Whクラスだったのに対し、ROG Xbox Ally Xはなんと80Whという大容量バッテリーを搭載してきました。 これは、ハイエンドの薄型ノートPCに匹敵する容量です。
ポータブル機で最も悩ましいのがバッテリーの持続時間。 パワフルなゲームを遊べば遊ぶほど、バッテリーは面白いように減っていきます。 この大容量化によって、ACアダプターに繋がずとも、より長く、安心してゲームに没頭できるようになったのは最大の進化点と言えるでしょう。 後ほどの検証で詳しく触れますが、この恩恵は絶大でした。
メモリの大容量・高速化「24GB LPDDR5X-8000」
メモリも24GBへと大幅に増量され、規格もLPDDR5X-8000と非常に高速なものが搭載されています。 内蔵GPUはメインメモリの一部をビデオメモリ(VRAM)として使用するため、メモリの容量と速度はゲーム性能に直結します。 最近のAAAタイトルはVRAMを8GB以上要求することも珍しくありません。
メモリが16GBだと、OSやバックグラウンドのアプリが使う分を差し引くと、ゲーム用に割り当てられるVRAMが不足しがちでした。 24GBあれば、ゲームに8GB~12GBを割り当てても、Windows側には十分な余裕が生まれます。 これにより、高画質設定での安定性や、ゲームを起動しながらブラウザで攻略情報を見るといったマルチタスク性能が劇的に向上しています。
ユーザーの声を反映した筐体デザインと操作性
筐体デザインも細かく見直されています。 グリップ部分がより深く、丸みを帯びた形状になり、長時間のプレイでも手が疲れにくくなりました。 私も実際に握り比べてみましたが、手のひらへの収まりが格段に良くなっていると感じます。
また、背面の「マクロボタン(M1/M2)」が小型化され、誤操作しにくくなっています。 ジョイスティックやDパッド(方向キー)も、より耐久性や操作性の高いモジュールに変更されており、ASUSの本気度が伝わってきます。
ASUS ROG Xbox Ally Xが向いている人
では、ここからは核心部分です。 この「ROG Xbox Ally X」は、一体どのような人に「向いている」のでしょうか。 私なりの見解をまとめます。
PCゲームの膨大なライブラリを持ち運びたい人
これが当てはまる方には、手放しでおすすめできます。 Steamのサマーセールで買い溜めたまま遊べていない「積みゲー」、ありませんか? Epic Games Storeで毎週もらっている無料配布ゲーム、起動すらしていないものはありませんか?

ROG Xbox Ally Xは、それらの膨大なPCゲーム資産を、ベッドの上で、リビングのソファで、あるいは新幹線の中でプレイ可能にしてくれます。 「PCの前に座る」という儀式から解放されるだけで、ゲームライフは劇的に変わります。 私も『サイバーパンク2077』や『バルダーズ・ゲート3』といった重量級タイトルを寝転がりながらプレイできる体験には、素直に感動しました。
Xbox Game Pass Ultimateを最大限活用したい人
「Xbox Ally」の名が示す通り、Microsoftのサブスクリプションサービス「Xbox Game Pass」との親和性は抜群です。 (Ultimateプランの3ヶ月無料特典も付属しています)

Game Passは、数百タイトルものゲームが遊び放題になるサービス。 ROG Xbox Ally Xがあれば、発売初日からGame Passに対応する大作ゲーム(Day Oneタイトル)を、追加費用なしで即座にダウンロードして遊べます。 クラウドゲーミングにも対応していますが、やはりローカルにインストールしてフルスペックで遊べる体験は格別です。 「色々なゲームをちょっとずつ つまみ食いしたい」という方にとって、これほど相性の良いデバイスは他にないでしょう。
設定やカスタマイズを楽しめる「PCゲーマー」
ROG Xbox Ally Xは、あくまで「Windows PC」です。 ゲーム機のように「電源を入れてソフトを挿入すれば必ず最適に動く」というわけではありません。
ゲームごとに最適なグラフィック設定を探ったり、TDP(電力制限)を調整してパフォーマンスとバッテリー持ちのバランスを取ったり。 時には、Windows Updateのタイミングに悩まされたり、ゲームランチャーの起動にひと手間かかったりすることもあります。
そうした「PCならではの手間」すらも楽しめる、あるいは解決できる知識や意欲がある人にとっては、最高の相棒となります。 設定がビシッと決まって、快適に動作した時の達成感は、専用ゲーム機では味わえないものです。
用途をゲームだけに限定しない人
Windows 11がフル機能で動作するということは、ゲーム以外のあらゆる用途にも使えるということです。
USB4ポートにドッキングステーションを接続すれば、キーボード、マウス、外部モニターを繋いで、瞬時にデスクトップPC環境が完成します。
強力なRyzen AI Z2 Extremeプロセッサと24GBのメモリは、Officeソフトでのドキュメント作成や、Photoshopでの写真編集といったクリエイティブな作業も、かなりのレベルまでこなせてしまいます。 外出先では最強のゲーム機として、自宅やホテルでは高性能なサブPCとして活躍する。 そんな「一台二役」以上の価値を求める人にこそ、強くおすすめしたいですね。
ASUS ROG Xbox Ally Xが向いていない人
逆に、素晴らしいデバイスであると同時に、全ての人におすすめできるわけでもありません。 購入してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、「向いていない人」のパターンもしっかりお伝えします。
「手軽さ」と「シンプルさ」を最優先する人
もしあなたが、Nintendo Switchのような「電源ONですぐゲーム開始」「難しい設定一切なし」という手軽さを最も重視するなら、ROG Xbox Ally Xは不向きかもしれません。
前述の通り、これはWindows PCです。 スリープからの復帰が不安定なゲームがあったり、ASUS独自ソフト「Armoury Crate SE」とSteamのBig Pictureモードが競合したりと、PC特有の「癖」と付き合っていく必要があります。 ゲームを始めるまでにワンクッション、ツークッションあることを許容できないと、ストレスを感じる場面があるでしょう。
バッテリー持ちを最重要視する人
「80Whの大容量バッテリー搭載!」と紹介しましたが、それはあくまで「他のポータブルゲーミングPCと比較して」の話です。 AAA級の最新ゲームをターボモード(最大35W)で遊べば、約2時間弱でバッテリーは尽きてしまいます(後述の検証参照)。
もちろん、TDP設定を10W~15W程度に抑える「パフォーマンスモード」で遊べば、3~4時間以上持たせることも可能です。 しかし、それでもスマートフォンや携帯ゲーム専用機(Switchなど)のバッテリー持続時間には及びません。 「コンセントのない場所で、丸一日遊びたい」といったニーズには応えられない可能性が高いです。
最高の画質(特に有機EL)を体験したい人
ROG Xbox Ally Xの液晶ディスプレイは、120Hzの滑らかさやVRR(可変リフレッシュレート)対応など、ゲーミングスペックとしては非常に優秀です。 しかし、画質の「美しさ」という点では、競合する一部の有機EL(OLED)搭載モデル(例:Steam Deck OLED)に一歩譲ります。
液晶である以上、どうしても「黒の締まり」や「発色の鮮烈さ」では有機ELに敵いません。 もしあなたが、漆黒の宇宙空間や、コントラストの効いた映像美を何よりも重視するならば、本機のディスプレイには少し物足りなさを感じるかもしれません。 (この点は次のセクションでさらに詳しく掘り下げます)
すでにハイエンドなゲーミングPCを持っている人
これは少し判断が分かれるところです。 すでに自宅にRTX 5090のようなハイエンドGPUを搭載したデスクトップPCをお持ちの場合、「あえてAlly Xで遊ぶ理由」は薄れるかもしれません。
自宅のPCのパワーを使って、映像だけをAlly Xにストリーミングする「リモートプレイ」(Steam Linkなど)という選択肢もあるからです。 ただ、「家のどこでも寝転がって遊びたい」「出張や旅行にも持っていきたい」という明確な「ポータブル需要」があるならば、リモートプレイの遅延や接続の不安定さから解放されるAlly Xは、最高のサブ機として輝くはずです。
徹底レビュー:ASUS ROG Xbox Ally Xの実力
お待たせしました。 ここからは、私が実際に「ROG Xbox Ally X」を使い倒して分かった、具体的な性能や使用感を徹底的にレビューしていきます。
デザインと操作性:手に吸い付くエルゴノミクス
本体の重量は約712g。 前モデル(約608g)からは約100g増加しましたが、この重量増のほとんどは、あの巨大な80Whバッテリーによるものです。 重くなったのは事実ですが、それ以上にグリップ形状の改善が素晴らしく、ホールド感が格段に向上しています。
私の手は女性としては標準的な大きさですが、深く改良されたグリップのおかげで、指が自然な位置に収まり、しっかりと支えられます。 おかげで、数値ほどの重さを感じさせません。 膝の上に置いたり、寝転がって胸の上で支えたりするスタイルなら、長時間のプレイもまったく苦になりませんでした。
Xbox準拠のボタンレイアウトは、PCゲームとの相性も抜群です。 スティックやトリガーの感触も非常に高品質で、安っぽさは皆無。 特にDパッド(方向キー)が改良され、格闘ゲームのコマンド入力なども、より正確に行えるようになったと感じます。
ディスプレイ性能:120Hzの滑らかさと「惜しい」色域
本機を評価する上で、ディスプレイは非常に重要なポイントです。
良い点:滑らかさ、明るさ、低反射
- 120Hz & VRR対応: 7インチの画面で見る120Hz映像は、驚くほど滑らかです。特にVRR(AMD FreeSync Premium)に対応しているのが大きく、fps(フレームレート)が60~120Hzの間で変動しても、カクつき(スタッタリング)や画面のズレ(テアリング)を感じさせません。これが本当に快適。
- 明るさと低反射コート: 最大500ニト(実測516 cd/m²)という明るさは、ポータブル機としてトップクラスです。Gorilla Glass DXCコーティングのおかげで反射もかなり抑えられており、日中の明るい室内でも視認性は良好でした。
惜しい点:色域(色の鮮やかさ)
一方で、私が「惜しい」と感じたのが、色の鮮やかさ(色域)です。 sRGBカバー率は約99%と、Webコンテンツや一般的なPC作業には十分すぎるほど優秀です。 しかし、映画や最新ゲームで重視される広色域規格「DCI-P3」のカバー率は、実測で82.4%でした。
これが何を意味するかというと、例えば『原神』や『鳴潮』のファンタジックで鮮やかな世界の「色の深み」や、『サイバーパンク2077』のネオンがギラつく夜景の「毒々しいまでの鮮やかさ」が、少しおとなしく(色が薄く)見えてしまうのです。
普段から有機ELやDCI-P3 95%以上の広色域モニターに慣れていると、どうしても見劣りしてしまいます。 とはいえ、これはあくまで「最高レベルの画質と比較すれば」という話。 応答速度(実測約4.7ms @120Hz)はNintendo Switch(実測約17ms)の3倍以上も速く、残像感のないクリアな映像は、さすが「ROG」ブランドだと感じさせます。
処理性能(ベンチマーク):Ryzen AI Z2 Extremeの実力
心臓部である「Ryzen AI Z2 Extreme」と「Radeon 890M」のパフォーマンスを見ていきましょう。 本機はTDP(電力設定)を「パフォーマンスモード(最大17W)」と「ターボモード(最大35W)」で切り替えられるため、両方のパターンで計測しました。
CPU性能:デスクトップに迫るパワー
定番のCinebench R23では、驚くべき結果が出ました。
- ターボモード (35W): Core i5-13400F(デスクトップ向け)に迫るマルチコア性能。
- パフォーマンスモード (17W): かつての人気CPU、Ryzen 5 5600Xに匹敵。
わずか17Wや35Wの電力枠で、一昔前のデスクトップPCを超える処理能力を持っていることになります。 ゲームのロードや、複雑な処理が伴うシミュレーションゲームでも、このパワーが光ります。
GPU性能:Radeon 890Mはどこまで戦えるか
内蔵GPU「Radeon 890M」のゲーム性能です。 これは、前世代のハイエンドだった「Radeon 780M」よりもさらに強力なGPUです。
3DMark (FireStrike – GPUスコア)
- ターボモード (35W): 約9825
- パフォーマンスモード (17W): 約7200 (推定)
このスコアは、デスクトップ向けのローエンドGPU「GeForce GTX 1650」を上回るものです。 7インチの携帯機に、GTX 1650以上のパワーが詰まっていると考えると、とんでもない時代になったものです。
実ゲームパフォーマンス (フルHD / 1920×1080)
ベンチマークだけでは分かりにくいので、実際のゲームでfps(フレームレート)を計測しました。
| ゲームタイトル | 設定 | ターボモード (35W) | パフォーマンス (17W) |
|---|---|---|---|
| 原神 | プリセット:高 | 平均 67.2 fps | 平均 45.1 fps (推定) |
| 崩壊:スターレイル | プリセット:高 | 平均 62.8 fps | 平均 42.5 fps (推定) |
| 鳴潮 | パフォーマンス | 平均 49.4 fps | 平均 33.0 fps (推定) |
| ストリートファイター6 | LOW設定 | 平均 59.8 fps | 平均 40.2 fps (推定) |
| モンハン ワイルズ | 最低設定 + FSR:UP | 平均 33.7 fps | – (厳しい) |
(※ 17Wの推定値は、ソース①のRadeon 780M機や他レビューのTDP別性能低下率から類推した参考値です)
ターボモード(35W)であれば、人気のモバイルゲームは「高設定」で平均60fpsを狙える、非常に高いパフォーマンスを持っています。 『鳴潮』のような最新の重いゲームでも、設定を「パフォーマンス(低~中)」にすれば、平均50fps近くで遊べます。
一方、『モンスターハンター ワイルズ』のような次世代の超重量級ゲームになると、さすがに最低設定にしても平均30fps台がやっとで、快適とは言えません。
AFMF 2.1(フレーム挿入)の魔法
ここで「Radeon 890M」の切り札が「AFMF 2.1 (AMD Fluid Motion Frames)」です。 これは、Radeonドライバ側で強制的にフレームを挿入し、映像を滑らかにする機能です。
例えば『鳴潮』で平均49fpsしか出ていなくても、AFMFを有効にすると、体感的には90fps近い滑らかさ(見た目)になるのです。 遅延が少し増えるため、『Apex Legends』のような競技性の高いFPSには向きませんが、『原神』『スターレイル』『鳴潮』のようなアクションRPGや、ソロプレイのAAAタイトルでは絶大な効果を発揮します。 パフォーマンスモード(17W)で平均30fps台のゲームを、見た目60fps相当で遊ぶ、といった「電力と快適さの両立」が可能になります。
熱設計と静音性:快適さを生む「見えない」技術
ポータブル機で性能の次によくご質問をいただくのが「熱」と「音」です。
熱設計:手は熱くならず、熱風は上へ
ターボモード(35W)で『鳴潮』を30分ほどプレイしてみましたが、熱設計の優秀さには感心しました。 熱くなるのは、本体上部の排気口周辺(最大50℃~60℃)と、ディスプレイの一部(約40℃台)に集中しています。
最も重要な**「手が触れるグリップ部分」は、ほとんど温度が上がらず、30℃台前半**をキープしていました。 これは、内部のエアフローが、熱を的確に上部へ排気するように設計されているためです。 長時間プレイしても、不快な熱を感じることはありませんでした。
静音性:シーンで切り替わる「音」
- アイドル時 / パフォーマンスモード (17W): 驚くほど静かです。騒音値は31dB台。カフェや図書館でも、まず気付かれないレベルの静けさです。
- ターボモード (35W): CPUやGPUがフル稼働すると、ファンの音が「サー」と聞こえてきます。騒音値は37.5dB。静かな部屋ではハッキリと聞こえますが、ゲームの音声やヘッドホンをしていれば気にならない程度。決して「爆音」ではありません。
パフォーマンスモードの静かさは特筆すべきもので、ゲーム性能とのバランスが非常に高いレベルでまとまっていると感じます。
バッテリー持続時間:80Whの「粘り」
さて、最大の注目点である80Whバッテリーの実力です。 ACアダプターを抜いて、最も負荷の高い『鳴潮』(プリセット高・画面輝度300ニト)でテストしました。
- ターボモード (35W): 約1時間58分
AAA級ゲームをフルパワーで動かして、約2時間。 これが長いか短いかは意見が分かれるでしょう。 しかし、前モデルや競合機が同条件で1時間~1時間半程度だったことを考えると、これは「驚異的な粘り」です。
重要なのは、TDP設定を下げた場合です。
- パフォーマンスモード (17W): (概算)約3時間半~4時間
- TDP 10W設定 (中量級ゲーム): (概算)約5時間~6時間
このように、遊ぶゲームや設定次第で、実用的な持続時間を確保できるのが「80Wh」の真価です。 新幹線での移動中や、カフェで一息つく間、存分にゲームを楽しめるだけのスタミナを手に入れたと言えます。
ROG Xbox Ally Xを120%使いこなすヒント
せっかくの高性能Windowsマシンです。 ゲームを遊ぶだけでなく、私が「これは便利!」と感じた活用法や、おすすめのアクセサリーもご紹介しますね。
Windows機としての最適化
ROG Xbox Ally Xを快適に使うコツは、ASUSの独自ソフト「Armoury Crate SE」と仲良くなることです。 ゲームの起動、パフォーマンス設定、キーマッピングなど、ゲームに関するほとんどの操作がこのソフトから行えます。
- コマンドセンターを使いこなす: 本体左下の専用ボタンで呼び出せる「コマンドセンター」が優秀です。ここからTDP、リフレッシュレート、AFMFのON/OFFなどをゲーム中でも瞬時に切り替えられます。
- VRAM割り当てを見直す: デフォルトでは自動(AUTO)になっていますが、Armoury Crate SEから手動で8GBや10GBに固定することもできます。遊びたいゲームが要求するVRAMに合わせて調整すると、動作が安定することがあります。
- スリープを活用する: Windowsのスリープは万能ではありませんが、本機はかなりスマホライクな復帰が可能です。『鳴潮』を起動したままスリープさせ、翌日復帰しても、ちゃんと続きから遊べました(ゲーム側の仕様にもよります)。
あると便利なアクセサリー(私のおすすめ)
私が実際に使ってみて、QOL(生活の質)が上がったアクセサリーをご紹介します。
- ドッキングステーション: 必須級です。USB4対応のドックがあれば、ケーブル1本で充電・映像出力(4KモニタOK)・USBハブ(キーボード/マウス接続)が完結します。ご自宅では「デスクトップPC」として使うために、ぜひ用意したいですね。
- PD対応モバイルバッテリー (100Wクラス): 内蔵バッテリーが80Whあっても、もっと遊びたい時があります。その際は、65W以上の出力(USB PD)に対応したモバイルバッテリーが活躍します。最低でも20000mAh以上の大容量モデルを選びましょう。
- 専用ケース: 約14万円の精密機器です。裸でカバンに入れるのは避けたいところ。スティックや画面をしっかり保護してくれる専用のハードケースは、持ち運ぶなら必ず用意しましょう。
- 低反射タイプの画面保護フィルム: ディスプレイは優秀な低反射コーティングが施されていますが、指紋はどうしても付いてしまいます。タッチ操作を多用する方は、指滑りが良く、反射をさらに抑えてくれる保護フィルムを貼っておくと安心です。
まとめ
さて、8,000文字を超える長旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。 「ASUS ROG Xbox Ally X」は、ポータブルゲーミングPCというジャンルにおける「一つの完成形」と言える、非常に満足度の高いデバイスでした。
前モデルや競合機の弱点だった「バッテリーの持ち」と「メモリ不足」を、80Wh・24GBという圧倒的な物量で真正面から解決してきました。 それでいて、グリップの握りやすさやボタンの操作感、そして強力な冷却性能といった「ゲーム機としての快適さ」も一切妥協していません。
もちろん、重量の増加や、有機ELではない液晶ディスプレイといったトレードオフも存在します。 しかし、「PCゲームの膨大なライブラリを、性能やバッテリーをあまり妥協せずに、どこでも快適に遊びたい」という、ゲーマーの最もコアな欲求に対して、これ以上ないほど誠実に応えてくれる一台です。
結論として、ASUS ROG Xbox Ally Xは…
- PCゲーム資産を解放したい「ガチのPCゲーマー」
- Game Passをしゃぶり尽くしたい「サブスク活用派」
- 性能とバッテリーを高次元で両立させたい「バランス重視派」
…にとっては、現在望みうる「最高の選択肢」の一つであると、私は断言します。 Windowsというジャングルを乗りこなす覚悟さえあれば、そこには無限のゲーム体験が待っていますよ。