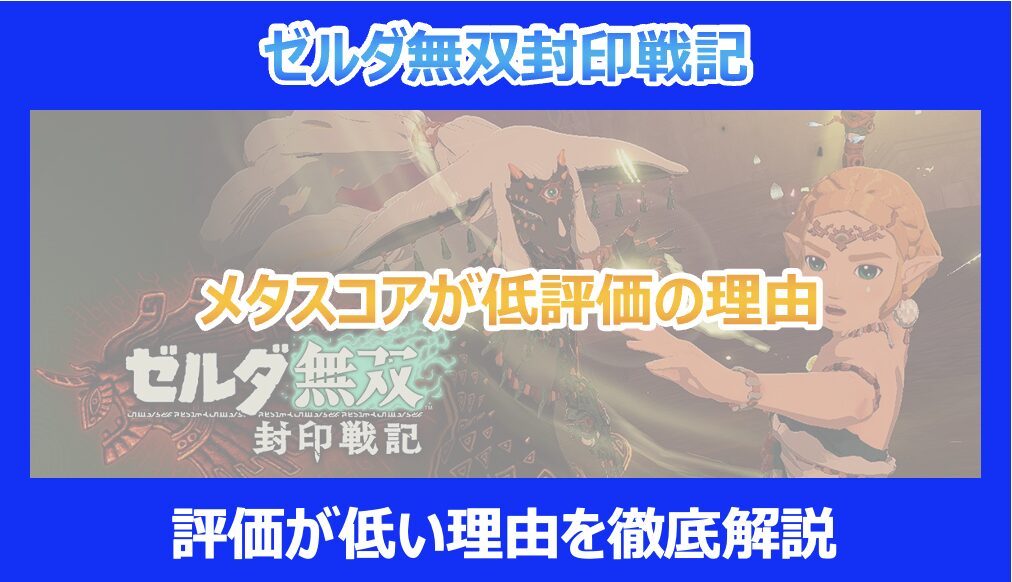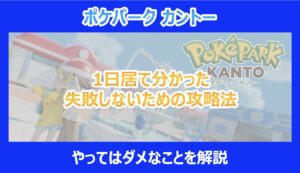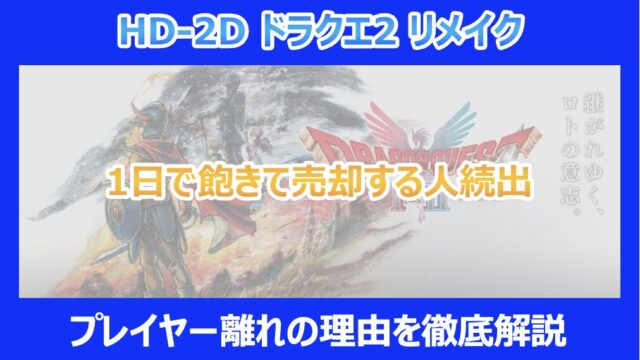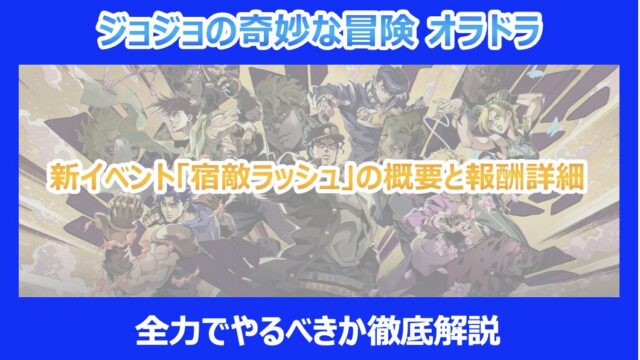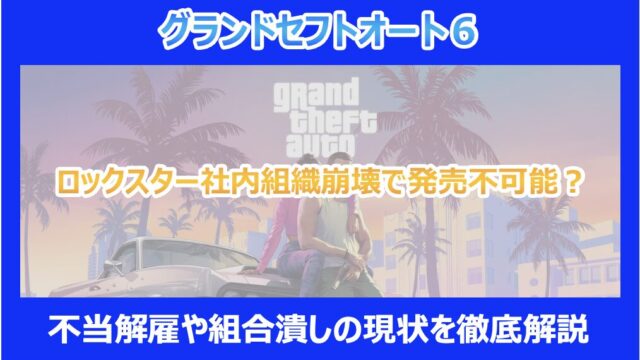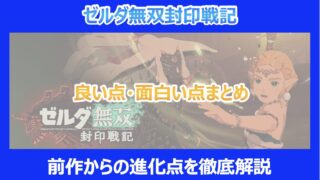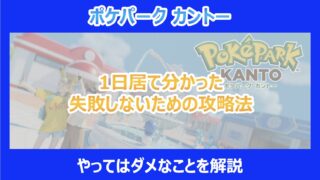編集デスク ゲーム攻略ライターの桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年11月6日に発売された待望の新作『ゼルダ無双 封印戦記』について、「メタスコアが低い」という噂を聞き、その理由が気になっていると思います。

かくいう僕も、前作『厄災の黙示録』はもちろん、本編の『ティアーズ オブ ザ キングダム(ティアキン)』や『ブレス オブ ザ ワイルド(ブレワイ)』も骨の髄までやり込んだ大ファン。 今作『封印戦記』も発売と同時に購入し、現在進行系でハイラルの大地(今回は建国時代ですが)を駆けずり回っています。
そんな僕の視点から、なぜ『封印戦記』のメタスコアが「低い」と言われるのか、その背景と、実際のプレイフィールがどうなのかを、徹底的に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、『封印戦記』のメタスコアに対する疑問が解決しているはずです。
- 封印戦記のメタスコア「79点」の実態
- レビュースコアが伸び悩んだ根本的な理由
- 本編(ティアキン)との比較によるギャップ
- 実際のプレイフィールと無双ゲームとしての評価
それでは解説していきます。
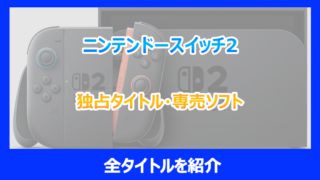
ゼルダ無双 封印戦記とは? ティアキンの「あの時代」を描く物語
まずは、『ゼルダ無双 封印戦記(以下、封印戦記)』がどのようなゲームなのか、おさらいしておきましょう。 ご存知の方も多いと思いますが、本作は任天堂の『ゼルダの伝説』シリーズの世界観をベースに、コーエーテクモゲームス(コエテク)の「無双」シリーズのシステムを融合させた、タクティカルアクションゲームです。
前作『ゼルダ無双 厄災の黙示録(以下、厄災の黙示録)』が、『ブレワイ』の100年前の「大厄災」を描いたIFストーリーだったのに対し、今作『封印戦記』が描くのは、『ティアキン』でその存在が明かされた、遥か昔の「建国時代」。 そう、ハイラル王国の初代国王ラウルと王妃ソニア、そして魔王ガノンドロフが激突した、「封印戦争」の時代です。

『ティアキン』でプレイヤーが「竜の涙」を通じて断片的に垣間見た、あの壮絶な歴史の「本編」を、無双アクションとして追体験できるというわけです。
物語はティアキンの直後から始まる
物語の導入は、『ティアキン』のオープニングを彷彿とさせます。 ハイラル城の地下深くを調査していたゼルダ姫が、謎の光に包まれ、遥か過去——ラウルたちが生きる「建国時代」へとタイムスリップしてしまうところから始まります。
プレイヤーは、戸惑いながらも建国時代のハイラルで奮闘する「ゼルダ姫」を(序盤の)主人公として操作し、ラウル、ソニア、そして若き日の賢者たち(ミネルなど)と共に、魔王ガノンドロフの台頭に立ち向かうことになります。
『ティアキン』では語り部のいなかった「封印戦争」の真実や、ラウルたちの知られざる葛藤が、当事者たちの視点で描かれていく。 これだけで、『ティアキン』ファンならずとも興奮する設定ですよね。 僕自身、この設定を聞いただけで購入を即決しました。
衝撃のメタスコア「79点」 なぜ「低い」と言われるのか
さて、そんな鳴り物入りで登場した『封印戦記』ですが、発売と同時に公開された海外レビューサイトのメタスコアは「79点」(2025年11月6日時点)という結果になりました。
「79点? 結構高いじゃないか」
そう思われる方もいるかもしれません。 確かに、一般的なゲームとしては「良作」のラインです。 しかし、これが『ゼルダの伝説』の名前を冠する作品、特にあの『ティアキン』と『ブレワイ』の関連作となると、話は変わってきます。
異常すぎた本編のスコア
参考までに、直近の本編シリーズのメタスコアを見てみましょう。
| タイトル | メタスコア |
|---|---|
| ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 96点 |
| ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 97点 |
| ゼルダ無双 厄災の黙示録 | 78点 |
(※注:上記スコアは本レビュー執筆時点のものです)
ご覧の通り、『ティアキン』『ブレワイ』は90点台後半という、ゲーム史に残るレベルの超高評価を獲得しています。 この「96点」「97点」というスコアを基準に見てしまうと、「79点」というスコアはどうしても見劣りしてしまいます。
厄災の黙示録(前作)とほぼ同等
注目すべきは、前作『厄災の黙示録』のスコアが「78点」であることです。 『封印戦記』の「79点」は、奇しくも前作とほぼ同等の評価に落ち着いたことになります。 これは、ゲームメディアのレビュアーたちが、「ゼルダ無双」というジャンルに対して、本編とは明確に異なる評価軸を持っていることを示唆しています。

先行レビュー(発売前にメディアに配布されるバージョン)の段階でこのスコアということは、今後ユーザーレビューが加わることで、さらにスコアが変動する可能性もあります。 (僕の経験上、初動のメタスコアは比較的高く出がちで、そこから少しずつ落ち着いていく傾向があります)
この「79点」という数字が、一部のファンの間で「期待外れだったのでは?」「低評価だ」という不安を引き起こしているのが現状です。
なぜメタスコアは伸び悩んだ? 低評価とされる7つの理由
では、なぜ『封印戦記』のスコアは『ティアキン』のような熱狂的な評価を得られなかったのでしょうか。 僕自身もプレイしつつ、ネット上の様々なレビューやSNSでの感想を分析した結果、以下の7つの理由が浮かび上がってきました。
理由①:最大の壁、それは「無双」というジャンル
これが最も根本的かつ最大の理由でしょう。 『封印戦記』は、あくまで「無双」ゲームです。
『ティアキン』や『ブレワイ』のような、広大なフィールドを自由に探索し、物理演算を駆使して謎を解き、強敵との1対1の緊張感ある戦闘を繰り広げる…といった「ゼルダの伝説」本編のゲーム性とは、全く異なります。

「無双」は、コエテクが誇る「1対多」のタクティカルアクション。 無数の敵をなぎ倒す爽快感、拠点を制圧していく戦略性、そしてド派手な必殺技が魅力のジャンルです。
本編ファンからすれば、「Aボタン(攻撃ボタン)を連打しているだけで敵が溶けていく」ように見えるゲーム性(もちろん、高難易度ではそんなに甘くありませんが)は、単調に映る可能性があります。 情報ソース①の配信者も言っていましたが、この「無双」というジャンル自体が、非常に「合う・合わない」がハッキリと分かれるのです。
『ティアキン』で96点を付けたレビュアーが、『封印戦記』をプレイして「これはゼルダではない」と感じ、低い点数を付けたとしても不思議はありません。
理由②:「ティアキン」という偉大すぎる比較対象
『封印戦記』がもし、『ティアキン』発売「前」にリリースされていたら、評価は変わっていたかもしれません。 しかし、我々は『ティアキン』を体験してしまいました。
あの「ウルトラハンド」による無限のクラフト、「トーレルーフ」による縦横無尽の探索、「物理演算」が生み出す奇跡のようなゲームプレイ。 『ティアキン』は、ゲームというメディアの可能性を数段階引き上げた、まさに「革命」でした。
その「革命」の熱狂が冷めやらぬ中で、同じ世界の過去を描いた作品が登場した。 当然、期待するのは「あの自由度の高さ」や「革新的なシステム」です。 しかし『封印戦記』は、その期待には応えてくれません。
ゾナウギア要素の「無双的」な解釈
『封印戦記』にも「ゾナウギア」は登場します。 僕がプレイした限りでは、「火龍の頭」「タイマー爆弾」「ロケット」「スペアバッテリー」などが確認できました。
しかし、その使われ方は『ティアキン』とは全く異なります。 「ウルトラハンド」で自由に組み合わせるのではなく、あらかじめ決められたアイテム(スキル)として、ボタン一つで消費・使用する「無双的な」システムに落とし込まれています。
これは「無双」のアクションとして見れば理にかなった仕様変更ですが、『ティアキン』の「なんでもできる」感覚を期待したプレイヤーにとっては、「機能が制限された」「劣化している」と映ってしまいます。 この「期待とのギャップ」が、評価を下げる大きな要因になったことは間違いないでしょう。
理由③:前作「厄災の黙示録」からの既視感(マンネリ)
「無双」ファンにとって、今作は「厄災の黙示録」の正統進化版として期待されていました。 しかし、基本的なゲームシステム(拠点の制圧、無数の敵、キャラごとのアクション)は、前作を色濃く踏襲しています。
もちろん、後述するようにUIの改善や新アクションの追加など、多くの点でブラッシュアップされています。 しかし、レビューの採点という観点では、「前作と代わり映えしない」と判断され、スコアが伸び悩んだ可能性があります。
「厄災の黙示録」が(IFストーリーとはいえ)『ブレワイ』の補完として一定の評価を得た一方、『封印戦記』は『ティアキン』の補完として、無双システム以上の「何か」を求められた結果、その期待に応えきれなかったと見られているのかもしれません。
理由④:『ティアキン』のストーリーを「なぞる」展開
『封印戦記』は、『ティアキン』の「竜の涙」で描かれたストーリーを、より深く、操作可能な形で追体験するゲームです。 僕がプレイした序盤の展開も、まさに「竜の涙」で見たシーンそのものでした。 (ゼルダのタイムスリップ、ラウルやソニアとの出会い、偽ゼルダの暗躍、そしてソニアの悲劇、ガノンドロフの魔王化…)
『ティアキン』をやり込んだプレイヤーにとって、この展開は「知っている」物語です。 もちろん、その裏側やキャラクターの心情が深く描かれるのはファンとして嬉しい限りですが、物語の「結末」を知っている(あるいは『ティアキン』本編で示唆されている)がゆえに、ストーリー面での「驚き」や「カタルシス」が薄い、とレビュアーに判断された可能性があります。
逆に言えば、『ティアキン』を未プレイの人が『封印戦記』を先にプレイすると、とんでもないネタバレを食らうことになります。 この「『ティアキン』既プレイ前提」という構造が、新規プレイヤーにとっての敷居の高さとなり、評価に影響したとも考えられます。
理由⑤:「リンク」の不在と新キャラクターへの戸惑い
情報ソース①では「リンクが使えないっぽい」という憶測がありましたが、これは半分正解で半分間違いです。 『ティアキン』の「リンク」は、序盤では操作できません。 その代わり、プレイヤーは序盤「ゼルダ姫」を操作し、その後「ラウル」や「ミネル」といった建国時代のキャラクターを切り替えて戦うことになります。
謎の「ゴーレムリンク」の登場
しかし、物語を進めると、あの「イニシエの勇者」を彷彿とさせる、謎の「ゴーレム(通称:ゴーレムリンク)」がプレイアブルキャラとして仲間になります。 (情報ソース②で実況者が操作していたキャラです)
こいつが、従来のリンクとは全く異なるアクション(ゾナウエネルギーを駆使した剣技や、空中戦)を見せてくれます。 これはこれで新鮮なのですが、やはり「いつものリンク」を使いたいファンにとっては、肩透かしだったかもしれません。 「ゼルダの伝説」なのに、リンク(ブレワイ/ティアキンの)が自由に操作できない。 これもまた、メタスコアが伸び悩んだ一因でしょう。
理由⑥:操作キャラクターの「クセ」の強さ
『封印戦記』では、序盤から多くの新キャラクターが操作可能になります。 ゼルダ姫(光の力)、ラウル(光とゾナウ)、ミネル(ゴーレム操作)、そして前述のゴーレムリンク(ゾナウ剣技)。 さらに、情報ソース②で判明した新キャラ「カラモ」(コログ?)や「特さ」(謎のおっさん)など、個性豊かな面々が揃います。
しかし、彼らの操作感は、前作の「英傑」たちと比べても、かなり「クセ」が強い印象を受けました。 特にミネルのゴーレム操作や、カラモのトリッキーな動きは、使いこなすまでに時間がかかります。 無双の「手軽な爽快感」を求めたプレイヤーが、このクセの強さに戸惑い、ネガティブな評価を下した可能性は否めません。
理由⑦:序盤のストーリーの「重さ」
『ティアキン』をプレイした方ならご存知の通り、「封印戦争」の物語は非常に重く、悲劇的です。 『封印戦記』は、その悲劇を(IFではなく)真正面から描きます。
序盤のハイライトである、ガノンドロフの策略によるソニアの死。 これは、無双ゲームの序盤としては、かなりショッキングで「重い」展開です。 爽快感を求めてゲームを始めたプレイヤーが、いきなり絶望的な展開を見せつけられる。 この「無双」というジャンルと、ストーリーの「重さ」のミスマッチが、レビュアーの評価を分けた可能性があります。
メタスコアは低いが…実際のプレイフィールは「最高」だ!
さて、ここまでメタスコアが低い理由を考察してきました。 これだけ見ると、「『封印戦記』は駄作なのか?」と思われるかもしれません。
断言します。そんなことはありません!
僕が数時間プレイした感想は、情報ソース②の実況者とまったく同じ。 「バリ楽しい」「面白すぎる」「一生できる」。 メタスコアの「79点」という数字が霞んで見えるほど、無双ゲームとしての「快感」と、ゼルダの世界に浸る「幸福感」に満ち溢れています。
メタスコアが「ゲームの批評」だとしたら、ここからは僕個人の「プレイレビュー」です。 『封印戦記』の、スコアには現れない「真の魅力」を語らせてください。
魅力①:圧巻のグラフィックとサウンド
まず、息を呑みました。 『ティアキン』も美しいゲームでしたが、『封印戦記』のグラフィックは、それを「無双」の物量で実現しています。 (僕の環境では、フレームレートも非常に安定しています。※個人の感想です)
情報ソース②で「スイッチ2」という発言がありましたが、それも頷けるほどの美麗さ。 建国時代の、まだ大厄災に見舞われる前のハイラル城、ラウルやソニアの気品ある佇まい、そしてド派手なエフェクト。 全てが『ティアキン』の世界観をリスペクトしつつ、無双として最適化されています。
そして音楽。 情報ソース②で「ジブリっぽい」と評されていましたが、まさにその通り。 『ティアキン』や『ブレワイ』の静謐なBGMとは異なり、壮大で勇ましいオーケストラが戦場を盛り上げます。 前作『厄災の黙示録』の戦闘BGMのアレンジも素晴らしかったですが、今作は完全新規の「建国時代」のテーマとして、完璧な仕上がりです。
魅力②:ロード時間の爆速化と快適なUI
前作『厄災の黙示録』をプレイした方ならわかると思いますが、あちらはミッション開始時のロード時間がかなりネックでした。 今作は、そこが劇的に改善されています。 情報ソース②でも実況者が驚いていましたが、ミッション開始までのロードが本当に「爆速」です。
また、武器強化やハイラルチャレンジの画面(マップ)も、『ティアキン』のUIに寄せる形で非常に見やすく、整理されています。 無双ゲームは、戦闘以外の「準備」時間が長くなりがちですが、そこが快適になったことで、ゲームのテンポが格段に良くなっています。 これは「厄災の黙示録の欠点が直された」最大のポイントかもしれません。
魅力③:爽快感マシマシ!「シンクストライク」と新アクション
無双としての爽快感も、間違いなく前作を超えています。 特に今作の目玉システム「シンクストライク」。 仲間と連携して放つ必殺技で、演出がとにかくド派手で気持ちいい。
僕が確認した序盤の「ゼルダ&ソニア」のシンクストライク(情報ソース②では「最強」と評されていました)は、ソニアの時の力でゼルダのスキル(光の弓矢など)が無限に撃てるようになるという、まさにチート級の性能。 ラウルとキーニョ(ハイリア兵)の連携技も、広範囲を殲滅するのに最適でした。
各キャラクターのアクションも、『ティアキン』の要素がうまく取り入れられています。 ゼルダは光の力だけでなく、モドレコ(のような時の力)を使ったコンボも使えますし、ゴーレムリンクはゾナウギアを駆使した多彩な攻撃が可能です。 この「『ティアキン』の要素をアクションに落とし込む」という点においては、コエテクは満点の回答を出してきたと僕は思います。
魅力④:まさかの「シューティング」パート
情報ソース②のプレイで、僕も度肝を抜かれました。 ゴーレムリンクを操作しての「空中戦」。 これはもはや「無双」ではなく、「スターフォックス」や「パンツァードラグーン」のような3Dシューティングです。
襲い来るキースの大群や、宿敵「グリオーク」を相手に、ホーミングレーザーや回避(扇風機)を駆使して戦う。 最初は戸惑いましたが、これが無双パートの合間に入ることで、最高のアクセントになっています。 「無双は単調」という批判に対する、開発陣の遊び心と挑戦を感じました。
魅力⑤:「建国時代」のキャラクターたちの圧倒的魅力
そして何より、キャラクターです。 『ティアキン』では「竜の涙」の中でしか会えなかった、ラウル、ソニア、ミネル、そして若きガノンドロフ。 彼らを自らの手で操作し、戦える。これ以上の喜びがあるでしょうか。
ラウルの王としての威厳と力強さ。 ソニアの慈愛に満ちた表情と、時を操る圧倒的な力。 ミネルの知的な佇まいと、ゴーレムを駆る戦闘スタイル。
『ティアキン』の断片的な情報だけではわからなかった彼らの「人となり」が、膨大なムービーと戦闘ボイスで(情報ソース②の実況中も、全編フルボイスでキャラクターが喋りまくっていました)、これでもかと描かれます。 ソニアの悲劇も、知っているからこそ、その直前のラウルとの夫婦のやり取り(情報ソース②の序盤)が、より胸に迫ります。
この「キャラクターの深掘り」こそが、『封印戦記』の最大の価値だと僕は断言します。
結論:『封印戦記』は「買い」か?
長々と語ってきましたが、結論です。
ティアキン・ブレワイのファン(謎解き/探索好き)の方へ
「ゲーム性は全く別物」と割り切れるなら「買い」です。
『ティアキン』のような自由度、探索、謎解きは一切期待しないでください。 これは「無双」です。 しかし、『ティアキン』で描かれた「建国時代の物語」「封印戦争の真実」を、当事者たちの視点で、最高のグラフィックと音楽で追体験できる唯一無二の作品です。 ラウルやソニアたちに会いたい、あの物語の「行間」を埋めたい、というファンにとっては、最高の贈り物となるでしょう。
無双シリーズのファンの方へ
間違いなく「買い」です。
前作『厄災の黙示録』の正統進化、あるいは現時点での「無双シリーズの最高傑作」の一つと言っても過言ではありません。 ロード時間の短縮、快適なUI、そして「シンクストライク」や「ゾナウギア」といった新システムによるアクションの進化。 『ゼルダの伝説』という強力なIP(知的財産)と、コエテクの技術が見事に融合しています。 やり込み要素も(コログや武器強化、ハイラルチャレンジなど)膨大にあるようなので、長く遊べる一本になるはずです。
ゼルダシリーズ未経験(無双も未経験)の方へ
『ティアキン』を先にプレイすることを強く推奨します。
本作は、単体のアクションゲームとしても楽しめますが、その魅力の8割は『ティアキン』の物語を知っていることを前提に構築されています。 先に『封印戦記』をプレイしてしまうと、『ティアキン』本編の最大の謎(過去の出来事)をすべて知った状態で始めることになり、感動が半減してしまいます。 まずは『ティアキン』(あるいは『ブレワイ』)でハイラルの世界を体験してから、この『封印戦記』に触れるのがベストな順番です。
まとめ
『ゼルダ無双 封印戦記』のメタスコア「79点」は、決して「駄作」の烙印ではありません。 それは、『ティアキン』という「100点」満点の革命的な本編と、「無双」という「80点」の安定した面白さを提供するジャンルを、同じ土俵で比較した結果の「ズレ」が生んだ数字です。
レビュアーは「『ティアキン』の続編」として減点したかもしれませんが、プレイヤー(僕)は「最高のゼルダ無双」として熱狂しています。
『ティアキン』で物理演算の面白さに目覚めたように、この『封印戦記』で「無双」の爽快感、キャラクターを動かす楽しさに目覚める人も多いはず。 スコアという数字に惑わされず、ぜひご自身の目で、建国時代のハイラルに飛び込んでみてください。
僕も、これから「特さ」の育成と、ゴーレムリンクの空中戦の腕を磨きに、戦場に戻ろうと思います。 それでは、また次回のレビューでお会いしましょう。 桐谷シンジでした。