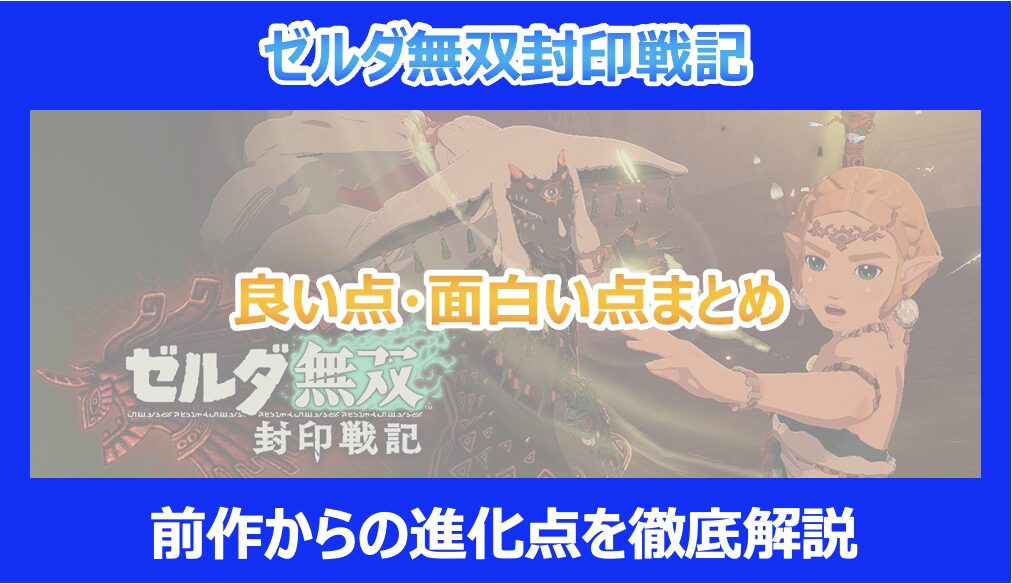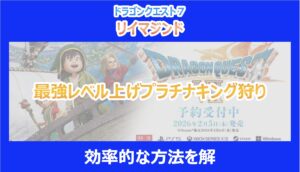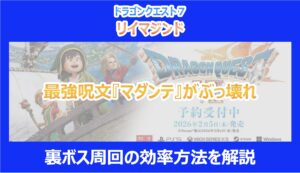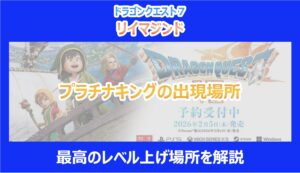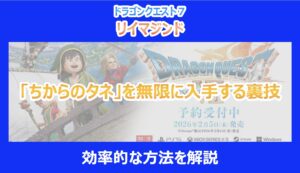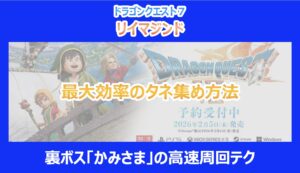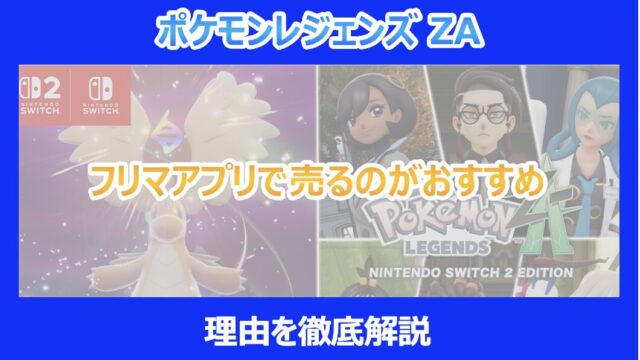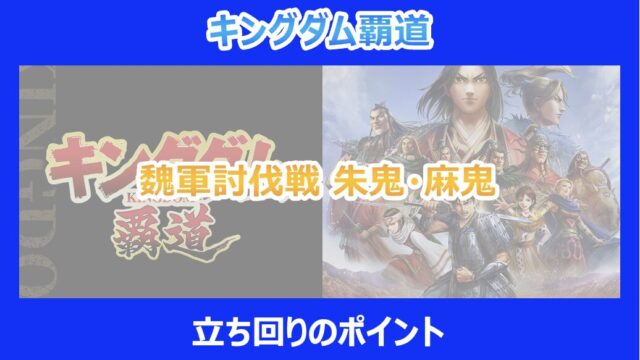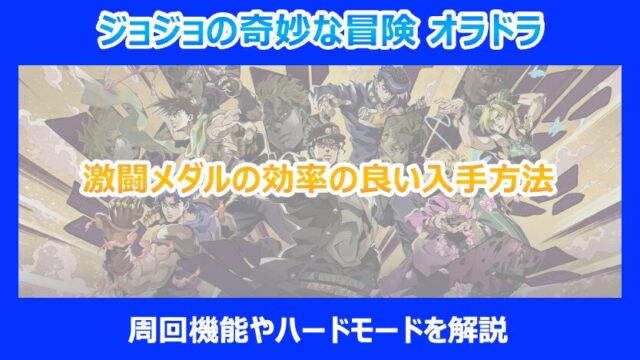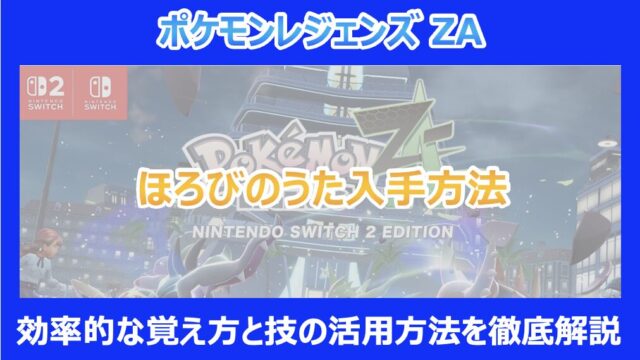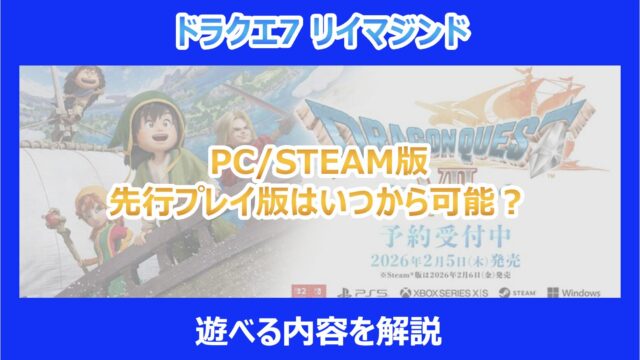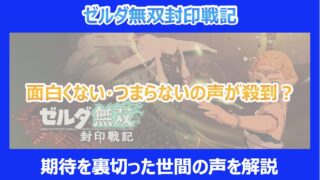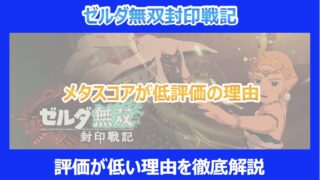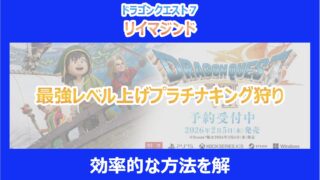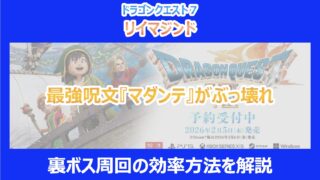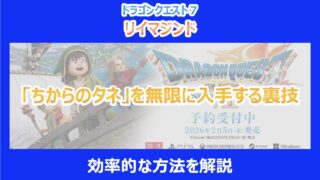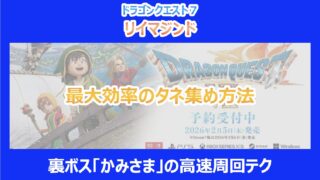編集デスク ゲーム攻略ライターの桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年11月6日に発売された待望の新作『ゼルダ無双 封印戦記』が、SNSなどで「面白すぎる」「神ゲー」と絶賛されている理由が気になっていると思います。

「前作の『厄災の黙示録』と何が違うの?」 「ティアキで語られた封印戦争って、具体的にどんな感じなの?」 「本当に買う価値ある?」
そんな疑問が渦巻いていることでしょう。 何を隠そう、私自身も発売日を指折り数えて待ちわび、発売日の深夜0時からガッツリやり込んでいる真っ最中です。
この記事を読み終える頃には、『ゼルダ無双 封印戦記』がなぜこれほどまでにプレイヤーを熱狂させているのか、その疑問が解決しているはずです。
- 『ティアキン』で語られた「封印戦争」の正史を追体験
- 『厄災』から正統進化「ゾナウギア」と「シンクストライク」
- 爆速ロードと美麗グラフィックによる圧倒的快適性
- 序盤から操作可能キャラ多数 個性的なアクションが満載
それでは解説していきます。
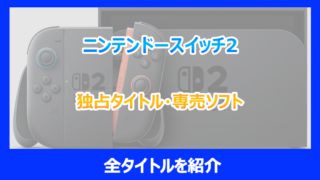
『ゼルダ無双 封印戦記』とは? 発売直後から絶賛される理由
まずは本作がどのようなゲームなのか、そしてなぜこれほどまでに話題となっているのか、その核心に迫ります。
待ち望んだ「封印戦争」の物語
本作の最大の魅力は、なんといってもその舞台設定にあります。 2023年に発売され、世界的な大ヒットとなった『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム(ティアキン)』。 あの作品の中で、プレイヤーはハイラルの大地に点在する「竜の涙」を通じて、遥か過去、ハイラル建国時代に起こった「封印戦争」の記憶を断片的に垣間見ることになりました。

ラウル王、ソニア王妃、そして魔王と化す前のガノンドロフ。 ティアキン本編ではムービーでしか描かれなかったあの壮絶な戦いを、「実際に操作して追体験したい!」と願ったプレイヤーは私だけではないはずです。
『ゼルダ無双 封印戦記』は、まさにその願いを叶える作品です。 物語は、ティアキンの冒頭、ゼルダ姫が過去のハイラルへと飛ばされてしまうシーンから始まります。 プレイヤーは過去に飛ばされたゼルダ姫として、あるいはハイラル初代国王ラウルとして、ミネルとして、そして後に登場する伝説の勇者(?)として、あの「封印戦争」に真正面から立ち向かうことになります。
前作『ゼルダ無双 厄災の黙示録』が、『ブレス オブ ザ ワイルド(ブレワイ)』の100年前を描きつつも、ガーディアンの「テラコ」による時間跳躍が介入した「if(もしも)」の物語であったのに対し、今作はティアキンで描かれた「正史」をより深く、より詳細に描く物語となっています。
序盤から、ティアキンの「竜の涙」で見たあのシーン、あの悲劇が、プレイヤー自身の操作によって展開されます。 特に、ソニア王妃に降りかかるあの運命の瞬間は……。 ティアキンをプレイした方なら、胸が締め付けられるような思いと共に、この物語に没入せずにはいられないでしょう。
『厄災の黙示録』の正統進化、あるいは完全版
「無双」と聞くと、単純に敵をなぎ倒すだけのゲームを想像するかもしれません。 しかし、『厄災の黙示録』は、「リモコンバクダン」や「ビタロック」といったブレワイの「シーカーストーン」の能力をアクションに組み込み、敵の強力な攻撃(ウィークポイント)を暴き出し、スマッシュで大ダメージを与えるという、爽快感と戦略性を両立させた独自のゲーム性で高い評価を得ました。

『封印戦記』は、その『厄災』の優れたゲームシステムをベースに、正統進化させています。 基本的な操作感は『厄災』を踏襲しているため、前作をプレイした方ならすぐに馴染めるでしょう。
しかし、本作は単なる続編ではありません。 『厄災』プレイヤーが感じていた「ある不満点」を完璧に解消し、ティアキンの新要素を大胆に取り入れたことで、まさに「完全版」とも呼べる仕上がりになっています。
特に快適性(ロード時間)の向上は目覚ましく、これだけでも前作プレイヤーにとっては「買い」の理由になります。 (この点については後ほど詳しく解説します)
序盤の登場キャラクターとそれぞれの役割
本作は序盤から操作できるキャラクターが非常に多いのも特徴です。 物語はまず、過去に飛ばされたゼルダ姫の視点から始まります。 彼女は戸惑いながらも、ラウルやソニアと出会い、自身の持つ「時」と「光」の力に目覚めていきます。
そして、ハイラル初代国王ラウル。 ティアキンでは威厳ある姿を見せていましたが、本作では自ら戦場に立ち、光の力で魔物をなぎ倒す豪快なアクションを見せてくれます。
さらに、ラウルの姉である「魂の賢者」ミネル。 彼女は自身の研究するゴーレムを駆使し、テクニカルながらも強力な攻撃を繰り出します。
この3人に加え、序盤のミッションでは、ティアキでその存在が示唆された「イニシエの勇者」を彷彿とさせる、謎のゴーレム(リンク?)や、その相棒であるコログのカラム、そしてラウルに仕える謎の屈強な戦士**特務(とくむ)**など、個性豊かなキャラクターが次々と仲間(操作可能キャラ)になります。
『厄災』では英傑たちが仲間になるまでに少し時間がかかりましたが、今作は序盤からハイラルマップを駆け巡り、多彩なキャラクターのアクションを存分に楽しめるのが大きな魅力です。
【徹底比較】前作『厄災の黙示録』からの「5大進化点」
『厄災の黙示録』も素晴らしい作品でしたが、『封印戦記』はそれを遥かに凌駕する進化を遂げています。 私が特に「これはすごい!」と感じた5つの進化点を、前作と比較しながら徹底的に解説します。
進化点①:アクションの核!「シーカーアイテム」から「ゾナウギア」へ
『厄災』のアクションの核は、「シーカーストーン」の能力でした。 リモコンバクダンで敵のガードを崩し、アイスメーカーで突進を止め、ビタロックで動きを止めてウィークポイントを叩き込む。 この流れは非常に戦略的で面白いものでした。

『封印戦記』では、このシーカーアイテムが、ティアキンの「ゾナウギア」と「能力」に置き換わっています。
これが、想像を絶するほど面白い。
例えば、ゼルダ姫は序盤から「モドレコ」や「光の弓矢」といったティアキの能力を彷彿とさせるアクションを使えます。 さらに、十字キーには「ゾナウギア」がセットされており、バッテリー(ティアキでお馴染みの緑色のゲージ)を消費して、いつでも好きな時に使用できます。
- タイマー爆弾: リモコンバクダンの代わりですが、爆発までの時間を調整できるなど、より戦略的。
- 火龍の頭: 前方に炎を放射し、敵をまとめて焼き尽くす制圧力を持ちます。
- 氷龍の頭: 敵を凍らせて動きを止め、大ダメージのチャンスを作ります。
- 雷龍の頭: 周囲に放電し、敵を感電させて足止めします。
- ロケット: 前方に急突進。移動にも攻撃にも使えます。
- 大砲: 強力な一撃を放ちます。
これらを従来の無双アクションに組み込むことで、戦闘の自由度が爆発的に向上しています。 例えば、氷龍の頭で敵をカチコチに凍らせ、そこにタイマー爆弾をセットし、強攻撃で叩き込む…といったティアキンさながらのコンボが、無双の戦場でシームレスに繰り出せるのです。
この「ゾナウギア」システムこそ、本作が『厄災』の単なる焼き直しではない、全く新しい無双アクションとして昇華された最大の要因だと感じました。
進化点②:戦術の要! 新システム「シンクストライク」
『厄災』にも仲間との共闘要素はありましたが、本作ではそれをさらに一歩進めた新システム「シンクストライク」が搭載されています。
これは、操作キャラクターと、近くにいる仲間の「シンクゲージ」が最大まで溜まると発動できる、超強力な連携必殺技です。 発動すると、ド派手な演出と共に敵に大ダメージを与えるだけでなく、組み合わせによって様々な追加効果が発生します。
私が序盤で確認できた組み合わせだけでも、その戦略性の高さが伺えます。
- ゼルダ & ソニア: 発動すると、一定時間、ゼルダのゾナウギアや特殊技のクールタイム(再使用時間)が大幅に短縮されます。 ただでさえ強力なゼルダのアクションが、ほぼ無限に連発できるようになる、まさに「チート」級の性能です。 ソニアの「時」の力が、ゼルダの「時」の力を増幅させているかのような、ストーリー的にも納得の連携です。
- ラウル & キーニョ(ハイリア隊長): ラウルの光の力と、キーニョの剣技が合わさり、超広範囲に強力なダメージ(流星群のような攻撃)を叩き込みます。 敵を一掃したい時に絶大な効果を発揮する、純粋な攻撃特化型のシンクストライクです。
- ミネル & ゼルダ: ミネルがゴーレムに乗り、ゼルダがそれを強化。 ゴーレムが暴れ回り、広範囲の敵をまとめて攻撃します。 ミネルの火力を最大限に引き出す、テクニカルな連携です。
このように、どのキャラクターと連携するかで戦い方がガラリと変わります。 『厄災』では操作キャラを切り替えて戦うのが基本でしたが、今作では「誰とシンクストライクを狙うか」を常に意識し、仲間と共闘する楽しさが格段にアップしています。 今後、ガノンドロフ(魔王化前)や、他の賢者たちとのシンクストライクがどうなるのか、想像するだけでワクワクが止まりません。
進化点③:最大のストレス要因を解消!「爆速ロード時間」
『厄災の黙示録』をプレイした方なら、誰しもが感じたであろう最大の不満点。 それは、「ロード時間の長さ」でした。 ミッションを開始する時、リトライする時、ハイラルマップに戻る時…とにかく待たされる時間が長く、ゲームのテンポを著しく削いでいました。
正直、私も『封印戦記』で最も懸念していたのはこの点です。 グラフィックがティアキベースになり、敵の数も増えるとなれば、ロードはさらに長くなるのではないか、と。
結論から言いましょう。 『封印戦記』のロードは、爆速です。
発売日の深夜0時、ダウンロード版を起動して最初のミッションが始まった瞬間、私は我が目を疑いました。 『厄災』であれば1分近く待たされてもおかしくない場面が、ほんの十数秒で終わるのです。 ミッション中のリトライもほぼ一瞬。 野営地(後述)でのファストトラベルも非常に高速です。
これは、コーエーテクモゲームス(オメガフォース)の技術力の勝利と言わざるを得ません。 現行のNintendo Switchで、あれだけの物量とグラフィックを描画しながら、このロード時間を実現したのは驚異的です。 (※筆者は現行モデルでプレイしていますが、次世代機や高性能モデルではさらに快適になる可能性もあります)
この「ロード時間の劇的な短縮」により、ミッションのクリア、素材集め、キャラクター育成といった周回プレイの快適性が『厄災』とは比較にならないほど向上しています。 これだけでも、本作の評価が「神ゲー」と呼ばれるに値すると断言できます。
進化点④:戦場に戦略を!「野営地」設営のメリット
今作からの完全新規システムとして「野営地」があります。 これは、広大なミッションマップの特定のポイントで「設営」ができる機能です。
設営すると、以下のようなメリットがあります。
- 体力(ハート)の全回復: 戦闘で減った体力を瞬時に全回復できます。 『厄災』では貴重なりんご(回復アイテム)を温存する必要がありましたが、今作では野営地をうまく使えば、回復アイテムを節約しつつ強敵に挑めます。
- ゾナウギア・スペアバッテリーの補充: 戦闘の要であるゾナウギアと、その動力源であるバッテリーが全回復します。 「ボス戦前にバッテリーが切れた!」という絶望的な状況を回避できます。
- 各種バフ(支援効果)の付与: これが非常に重要です。 野営地に「物資(ミッションで手に入る素材)」を搬入することで、様々なバフを得られます。
- 経験値アップ: キャラクターのレベルが格段に上がりやすくなります。
- 素材ドロップ率アップ: 武器強化やチャレンジに必要な素材集めが捗ります。
- 移動速度アップ: 広大なマップを快適に移動できます。
- 必殺技ゲージ増加: ミッション開始時から有利に戦えます。
- ファストトラベル地点: 一度設営した野営地には、マップ上から瞬時に移動できます。
『厄災』では、広大なマップをひたすら走り回り、敵の拠点を目指す必要がありましたが、『封印戦記』では「まずどこに野営地を設営し、どのバフを発動させ、どのルートで進軍するか」という戦略的な思考が求められます。 この新システムが、無双アクションに「陣取り合戦」のような奥深さを加えています。
進化点⑤:グラフィックとBGMの圧倒的クオリティ
グラフィックに関しても、ティアキの世界観を見事に無双の戦場に落とし込んでいます。 『厄災』もブレワイの雰囲気をよく再現していましたが、『封印戦記』では光の表現や影の処理が格段に向上しており、特に序盤のハイラル城や地底の雰囲気は息をのむ美しさです。
ラウルやソニア、そしてゼルダ姫の表情も非常に豊かで、ムービーシーンへの没入感は本家『ゼルダの伝説』シリーズに勝るとも劣りません。 (特にゼルダ姫の衣装の造形や、ソニア王妃の豊満な魅力は、SNSでも大きな話題となっていますね)
そして何より、BGM。 これが本当に素晴らしい。 序盤、ゼルダが過去のハイラルをラウル、ソニアと歩くシーンで流れるBGMは、壮大で、どこか懐かしく、一部のファンからは「ジブリ作品のようだ」と評されるほどのクオリティです。
戦闘BGMも、ティアキやブレワイのアレンジ曲、そして本作オリジナルの新曲が絶妙にミックスされています。 『厄災』の戦闘曲も非常にテンションが上がるものでしたが、今作はさらに壮大さとドラマチックさが加わっており、プレイヤーのボルテージを最高潮まで高めてくれます。 ゲーム音楽ファンは、サウンドトラック目当てで本作を購入しても損はないでしょう。
ネタバレなし! 序盤プレイで感じた「ここが面白い!」ポイント5選
ここでは、具体的なストーリーのネタバレは避けつつ、私が序盤をプレイして「これは面白い!」と唸ったポイントを5つ、ご紹介します。
① ゼルダのアクションが多彩すぎる
本作のゼルダ姫は、間違いなくシリーズ最強クラスの強さを誇ります。 序盤はラウルたちに守られながら戦いますが、力を解放してからは、まさに縦横無尽。
光の力をまとった剣技に加え、前述の「モドレコ」のようなアクション、そして「光の弓矢」での遠距離攻撃。 さらに「ゾナウギア」も使いこなし、極めつけはソニアとの「シンクストライク」による能力の超強化。
『厄災』のゼルダ(シーカーストーン)もテクニカルで強力でしたが、今作のゼルダは爽快感と制圧力が段違いです。 序盤からこれだけ強いと、物語の終盤では一体どうなってしまうのか…末恐ろしいほどのポテンシャルを秘めています。
② ラウル、ミネル…伝説の人物を操作できる感動
ティアキンで、その威厳と優しさで多くのプレイヤーを魅了したラウル王。 彼を自らの手で操作できる、これだけでも本作をプレイする価値があります。
ラウルの戦闘スタイルは、まさに王。 光の力をまとった拳や、謎の武器(槍?)で、魔物を豪快になぎ倒します。 動きはゼルダに比べると少し重めですが、一撃一撃の重みが凄まじく、敵の群れを吹き飛ばす様は爽快そのもの。
ミネルも負けていません。 彼女は自身の研究するゴーレム(ティアキンでリンクが乗ったものとは別タイプ?)を召喚・騎乗し、ビームやパンチで敵を蹂躏します。 非常にテクニカルですが、使いこなせれば敵なしの強さを発揮します。 彼女の「鉄球ストライク」は、あらゆる敵を文字通り「轢き潰す」恐ろしい技です。
<h3>③ 謎のゴーレム(リンク?)とコログ(カラム)のコンビ</h3>
序盤の大きなサプライズとして、謎のゴーレムが操作可能になります。 その姿は、ティアキンで登場した「イニシエの勇者の魂」に酷似しており、おそらく彼こそが当時の「リンク」なのでしょう。
操作感は『厄災』のリンク(片手剣)に近く、非常にスタンダードで扱いやすいです。 しかし、彼もまたゾナウギアを使いこなし、さらに固有アクションとして「リミットブレイク」のような能力(一定時間ゾナウバッテリー消費なし)も持っています。
そして、彼の相棒として登場するのが、コログのカラム。 彼は「アニキ肌」のコログで、戦闘ではティアキンでお馴染みの「水の実」「火炎の実」「氷の実」などを使い、敵に属性ダメージを与えてくれます。 カラムのアクションは、属性を使ったコンボの起点として非常に強力です。
この「ゴーレムリンク」と「カラム」という異色のコンビが、封印戦争の裏でどのような活躍をしていたのか、今後のストーリー展開が非常に楽しみです。
④ まさかのシューティングゲーム!? 空中戦が熱い
本作は、無双アクションだけではありません。 序盤、ゴーレムリンクが「ファルコン」のような飛行形態に変形し、大空で戦うミッションが発生します。
これが、まるで『スターフォックス』のような本格的な3Dシューティングゲームなのです。 機銃で敵(キースやグリオーク)を撃ち落とし、ロックオンミサイルを放ち、敵の攻撃を回避(バレルロール)する。 ゾナウギアを拾うことで機体が強化され、炎を吐いたり、3連射になったりもします。
特に、空中でグリオークと戦うミッションは圧巻の一言。 無双ゲームの中で、これほど本格的なシューティング戦が楽しめるとは思いませんでした。 今後もこういった特殊なミッションが用意されているのか、期待が高まります。
⑤ コログ探しも健在! やり込み要素の片鱗
無双プレイヤーにとって(ある意味で)悪夢であり、同時に至福でもある「やり込み要素」。 『厄災の黙示録』では、全ミッションのクリア、全コログの収集、全キャラクターの育成、全武器の強化…と、数百時間遊べる圧倒的なボリュームが待っていました。
ご安心ください(?)。 『封印戦記』でも、コログの収集は健在です。 序盤のミッションマップの片隅で、早くも「やっはー!」というボイスと共にコログを発見しました。
ハイラルマップの形式や、武器強化(今作はゾナニウムと刻印を使うシステムに変更されています)、ハイラルチャレンジ(素材納品ミッション)なども『厄災』を踏襲しています。
序盤のマップの広さやミッションの数を見ただけでも、本作が『厄災』と同等、あるいはそれ以上のやり込みボリュームを秘めていることは間違いありません。 これから年末年始にかけて、じっくりと遊び尽くせる一本となるでしょう。
購入を迷っている方へ(Q&A)
最後に、本作の購入を迷っている方からよく寄せられる質問にお答えします。
『厄災の黙示録』をプレイしてなくても楽しめる?
全く問題ありません。むしろ、今作から入ることをオススメします。
前述の通り、ロード時間などの快適性が『厄災』とは比べ物にならないほど向上しています。 基本的な無双アクションの楽しさは共通していますが、戦闘システムは「ゾナウギア」「シンクストライク」といった新要素でほぼ一新されているため、前作の知識がなくても問題なく楽しめます。 『厄災』をプレイ済みの方は、その進化に驚くことでしょう。
『ティアーズ オブ ザ キングダム』をプレイしてなくても楽しめる?
楽しめますが、ティアキンをプレイ済みだと100倍楽しめます。
本作のストーリーは、ティアキンの「封印戦争」がベースになっています。 ティアキンを未プレイでも、独立した一つの物語として楽しむことは十分に可能です。 ラウルやソニアが誰なのか、ガノンドロフがなぜ魔王になったのかを、本作で初めて知るという体験も新鮮でしょう。
しかし、ティアキンをクリアした方であれば、 「ああ、竜の涙で見たあのシーンは、こういう流れだったのか!」 「ラウル王、かっこよすぎる…」 「ソニア様…(涙)」 と、物語の節々で込み上げてくる感情が段違いのはずです。
個人的には、ぜひティアキンをクリアしてから(あるいは並行して)プレイしていただくのが、最もリッチなゲーム体験になると思います。
序盤の難易度は?
『厄災』同様、本作もミッション開始前に難易度を「イージー」「ノーマル」「ハード」「ベリーハード」から選択できます。 (※『厄災』の「アポカリプス」に相当する最高難易度は、クリア後に追加されると予想されます)
アクションゲームが苦手な方でも、「イージー」や「ノーマル」であれば、レベルを上げたり、強力な武器を手に入れたりすることで、詰まることなく爽快な無双アクションを楽しめるはずです。 逆に、腕に覚えのある方は、ぜひ「ハード」以上で、ゾナウギアやシンクストライクを駆使した歯ごたえのある戦いに挑戦してみてください。
まとめ
『ゼルダ無双 封印戦記』は、単なる「ティアキの無双ゲーム」ではありません。 『厄災の黙示録』という優れたベースを、ロード時間の爆速化によって完璧な土台へと昇華させ、そこに「ゾナウギア」「シンクストライク」という最高の新要素を注ぎ込んだ、まさに「ゼルダ無双の集大成」と呼ぶべき傑作です。
ティアキで描かれた「封印戦争」の壮絶な物語を、最高のクオリティと快適性で追体験できる。 この一点だけでも、ゼルダファン、無双ファン、いや、全てのアクションゲームファンに強くオススメできる作品です。
序盤をプレイしただけでも、その面白さ、奥深さ、そして圧倒的なボリュームの片鱗が伺えます。 SNSでの絶賛の声は、決して過大評価ではありません。
このレビューが、あなたの購入の最後のひと押しになれば幸いです。 さあ、私と一緒に、ハイラル建国の壮絶な戦場へと飛び込みましょう!