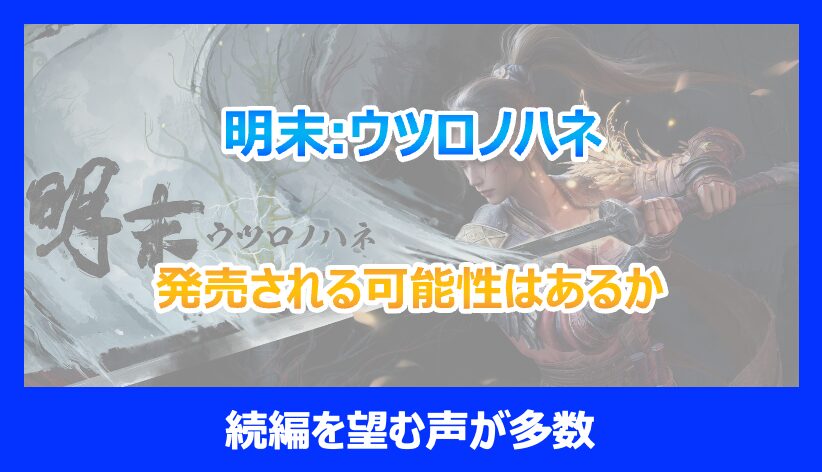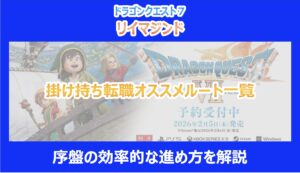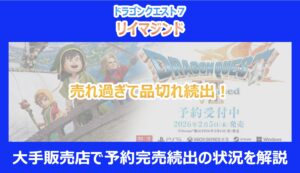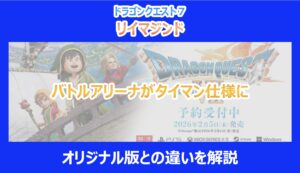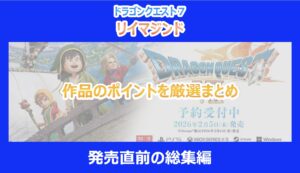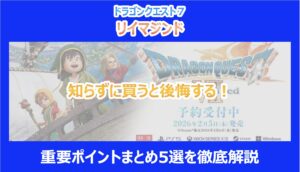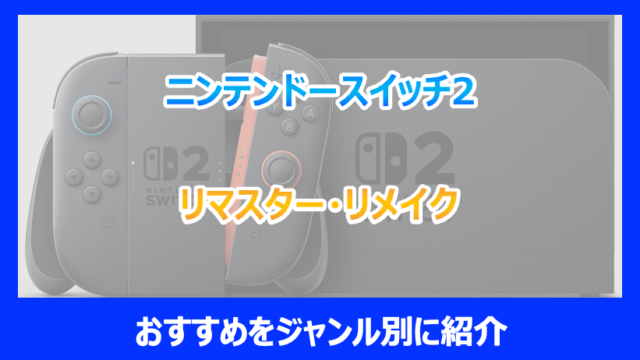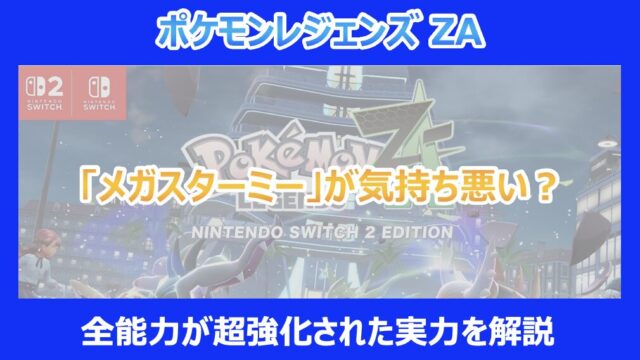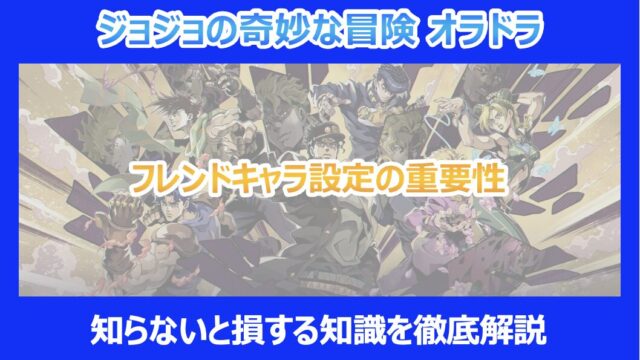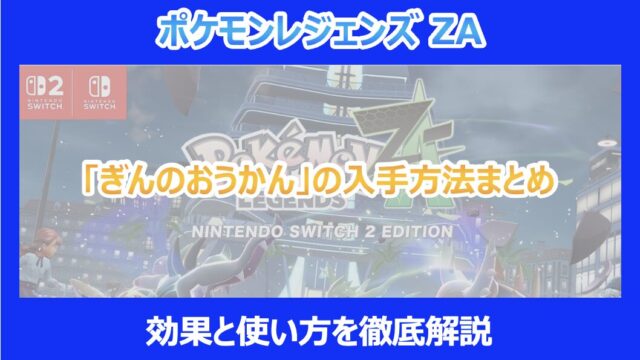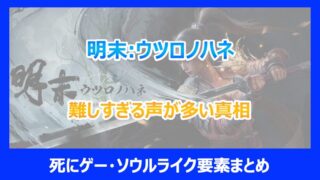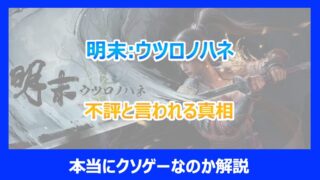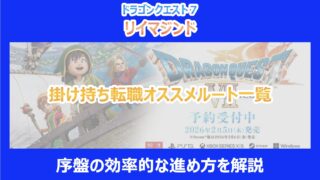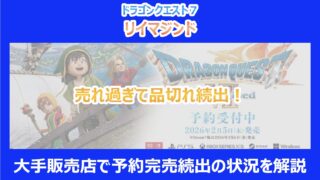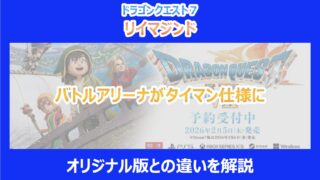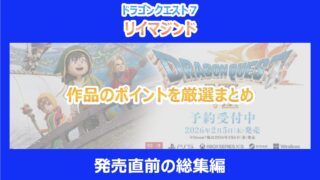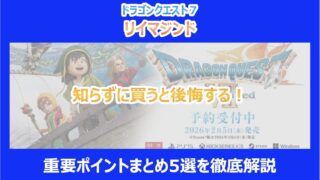ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、先日発売されて大きな話題を呼んだソウルライクアクションRPG『明末:ウツロノハネ』について、続編の可能性が気になっているのではないでしょうか。 本作をクリアし、その独特の世界観と歯ごたえのあるアクションに魅了された方々から、「ぜひ2を出してほしい」という声が数多く上がっています。

引用 : SIE HP
この記事を読み終える頃には、『明末:ウツロノハネ2』が発売される可能性についての疑問が解決しているはずです。
- 『明末:ウツロノハネ』に渦巻く賛否両論の評価
- 熱狂的なファンが続編を望む理由の徹底分析
- 続編制作にあたり開発が乗り越えるべき課題
- 売上や評価から見る続編発売の総合的な可能性
この記事を読めば、きっと問題が解決できるはず。

『明末:ウツロノハネ』とは?|多くのプレイヤーを魅了したソウルライク
まずは、『明末:ウツロノハネ』がどのようなゲームなのか、その基本情報とプレイヤーを惹きつけた独自の魅力についておさらいしておきましょう。 すでにクリア済みの方も、本作の評価を客観的に見るために、ぜひ一度振り返ってみてください。

ゲームの基本情報と世界観
『明末:ウツロノハネ』は、開発スタジオ「Lein Games」が手掛け、2024年7月24日に発売されたアクションRPGです。 対応プラットフォームはPlayStation 5、PC(Steam)で、価格は通常版が7,260円(税込)となっています。
舞台は、中国の明朝末期。 国内は混乱を極め、さらに人々の体に羽が生え、記憶を失い、やがては化け物へと変貌してしまう「羽病」と呼ばれる奇病が蔓延していました。 プレイヤーは、自身も羽病に侵され過去の記憶を失った主人公「無常(むじょう)」となり、自らの過去を解き明かし、妹を救うために過酷な旅へと身を投じます。
いわゆる「ソウルライク」と呼ばれるジャンルに分類される本作は、一筋縄ではいかない高難易度のアクションと、多くを語らないフレーバーテキストから世界観を考察していく楽しみを特徴としています。 美しいながらも退廃的な東洋の世界観は、多くのプレイヤーを引き込みました。
ソウルライクをベースにした独自のゲームシステム
本作は、フロム・ソフトウェアの『DARK SOULS』シリーズなどに代表されるソウルライクの基本を踏襲しつつも、独自のシステムを複数搭載することで、他の作品との差別化を図っています。 特に「粋」と「心魔」は、本作の戦闘を理解する上で欠かせない重要な要素です。
攻防一体の鍵を握る「粋」システム
「粋」とは、他のゲームでいうところのMPやFPに近いエネルギーです。 これを消費することで、強力な法術や武器ごとのスキルを繰り出すことができます。 本作がユニークなのは、この「粋」の回復方法にあります。 敵の攻撃をタイミングよく回避したり、ガードしたりすることで「粋」は回復していくのです。
つまり、敵の猛攻をただ耐え忍ぶのではなく、積極的に捌いていくことで、強力な反撃のチャンスが生まれるという、攻防一体のゲームデザインになっています。 敵の攻撃は苛烈を極めますが、華麗に捌ききって大技を叩き込んだ時の爽快感は、本作ならではの醍醐味と言えるでしょう。
リスクとリターンが交錯する「心魔」システム
「心魔」は、プレイヤーの死亡によって蓄積していく特殊なゲージです。 この値が高まると、敵から受けるダメージが増加し、さらに死亡時に失う経験値(ソウル)の量も増えるという、明確なデメリットが発生します。
しかし、デメリットだけではありません。 心魔の値が高ければ高いほど、「粋」の回復効率が上昇するというメリットも存在するのです。 つまり、死ねば死ぬほどハイリスク・ハイリターンな状態になっていくというわけです。
これにより、プレイヤーは自身の腕前や状況に応じて、心魔をコントロールするという戦略的な判断を求められます。 あえて高い心魔を維持して短期決戦を挑むのか、アイテムで心魔を下げて安定した戦いを求めるのか、プレイスタイルが分かれる面白いシステムです。
自由度の高いキャラクタービルド
ソウルライクの楽しみの一つに、キャラクタービルドの自由度の高さが挙げられますが、『明末:ウツロノハネ』もその点は非常に優れています。
膨大なスキルツリーと振り直しの手軽さ
本作には、片手剣、双剣、槍など5つの武器カテゴリーが存在し、それぞれに膨大なスキルツリーが用意されています。 敵を倒して得た経験値を消費して、このツリーを解放していくことで、キャラクターは強化されていきます。
特筆すべきは、スキルポイントの振り直しがいつでも、しかもコストなしで行える点です。 これにより、「あのボスが倒せないから、一時的にビルドを変えてみよう」といった試行錯誤が非常に容易になっています。 さらに、武器の強化状態もリセットできるため、気軽に色々な武器を試せるのも嬉しいポイントです。
装備重量の概念がない自由な着せ替え
多くのソウルライクゲームでは、装備の重量によって回避アクションの性能が変化しますが、本作にはその概念がありません。 防御性能や特殊効果のみを考慮すればよいため、プレイヤーは好きな見た目の装備を自由に組み合わせて冒険できます。 後述する「セクシー要素」と相まって、キャラクターの着せ替えを楽しむプレイヤーも多く見られました。
プレイヤーを惹きつけるビジュアルとキャラクター
本作が多くの注目を集めた理由の一つに、主人公「無常」をはじめとするキャラクターのビジュアルが挙げられます。 特に、昨今のアクションゲーム市場で大きな成功を収めた『Stellar Blade』と比較されることも多く、その「セクシー要素」は賛否両論を巻き起こしながらも、本作の大きな魅力となっています。

予約特典やデラックスエディションには、世界観を重視したものから、プレイヤーの目を釘付けにするような大胆なデザインのものまで、様々な衣装が用意されており、高難易度アクションの合間の癒やしとして、多くのプレイヤーに受け入れられました。
なぜ『明末:ウツロノハネ』の続編が望まれるのか?|高評価レビューから見える熱狂の理由
『明末:ウツロノハネ』は、一部で厳しい評価を受けながらも、それを上回る熱狂的なファンを生み出しました。 なぜ彼らはこれほどまでに本作に魅了され、続編を熱望しているのでしょうか。 ここでは、高評価レビューやSNSでの意見を分析し、その理由を深く掘り下げていきます。

高難易度と達成感の絶妙なバランス
「めちゃくちゃ難しい」「中盤以降のボスは全部マレニアのようだ」 あるレビュアーは、本作の難易度をこのように表現しました。 確かに、本作のボスは非常に攻撃的で、一度攻撃を受ければ立て続けに攻め込まれ、一瞬で命を落とすことも少なくありません。
しかし、本作を高く評価するプレイヤーは、それを単なる「理不尽な難しさ」とは捉えていません。 前述した「粋」システムを駆使し、敵の猛攻を捌ききって反撃に転じる。 あるいは、スキルツリーや武器の組み合わせを試行錯誤し、自分だけの「攻略ビルド」を構築して強敵に立ち向かう。
本作には、プレイヤーの工夫と努力次第で、どんな強敵にも打ち勝てる道が必ず用意されています。 だからこそ、数十回、時には百回以上挑戦してボスを撃破した時の達成感は、他のゲームでは味わえない格別なものとなるのです。 この「困難を乗り越える喜び」こそが、死にゲーの根源的な魅力であり、本作が多くのプレイヤーを虜にした最大の要因と言えるでしょう。
ビルド構築の奥深さとリプレイ性の高さ
スキルツリーの振り直しが無料である手軽さは、プレイヤーに無限の試行錯誤を促しました。 「この武器スキルと、あの法術を組み合わせたらどうなるだろうか」 「ステータスを一点特化させて、一撃の火力を追求してみよう」 といったように、自分だけの最強ビルドを見つけ出す過程は、ハックアンドスラッシュゲームのような楽しさがあります。
また、本作には周回プレイ(ニューゲームプラス)も用意されており、2周目以降は敵の強さや配置が変化し、新たな挑戦がプレイヤーを待ち受けます。 さらに、特定の条件を満たさなければ出会えないNPCや、選択肢によって結末が分岐するマルチエンディングなど、一度クリアしただけでは遊び尽くせない豊富な収集要素が、プレイヤーのリプレイ意欲を掻き立てています。
魅力的なキャラクターとダークな世界観の深掘りへの期待
記憶を失った主人公「無常」の過去、世界を蝕む「羽病」の正体、そして旅の目的である妹との関係。 本作のストーリーは、多くの謎を残したまま幕を閉じます。 この多くを語らない演出は、プレイヤーの考察意欲を刺激し、「続編で物語の真相を知りたい」という強い動機付けになっています。
美しくも退廃的な世界で、魅力的なキャラクターたちが織りなす物語の続きが見たい。 これも、ファンが続編を望む大きな理由の一つです。
「セクシー要素」がもたらした新たなファン層
『Stellar Blade』の成功が証明したように、「高難易度アクション」と「魅力的な女性主人公」の組み合わせは、非常に強力な訴求力を持ちます。 『明末:ウツロノハネ』もまた、その路線を意識したであろう魅力的なキャラクターデザインと豊富な衣装で、従来のソウルライクファンだけでなく、新たな層のプレイヤーを獲得することに成功しました。
もちろん、この要素については「あざとい」「世界観に合っていない」といった批判的な意見もあります。 しかし、結果として本作の知名度を上げ、多くのプレイヤーに手に取ってもらうきっかけになったことは紛れもない事実です。 この新たなファン層が、続編を望む声の大きな原動力となっていることは間違いないでしょう。
開発スタジオのポテンシャルへの期待
本作は開発発表当初、他作品からのモーション盗用疑惑が持ち上がるなど、決して順風満帆なスタートではありませんでした。 しかし、そこからクオリティを大幅に向上させ、独自の魅力を持つ作品として世に送り出した開発スタジオ「Lein Games」のポテンシャルを評価する声も少なくありません。
粗削りな部分はあるものの、光るものがある。 だからこそ、「DLCや続編で、さらに洗練された作品になるのではないか」という期待が寄せられているのです。
一方でなぜ厳しい評価も?|続編制作における課題点
熱狂的なファンを生んだ一方で、『明末:ウツロノハネ』が「クソゲー」「ストレスが溜まるだけ」といった手厳しい評価を受けているのも事実です。 続編の実現を考える上では、これらの批判的な意見から目を背けることはできません。 ここでは、低評価レビューで指摘されている問題点を分析し、続編制作における課題を浮き彫りにします。

アクションの根幹に関わる操作性の問題
最も多く指摘されているのが、アクションゲームの根幹である操作性に関する問題です。 高評価レビューでは「歯ごたえがある」と評された部分が、低評価レビューでは「ただただ不快」と一蹴されています。
ストレスの元凶?移動・回避・各種モーションの遅さ
- ダッシュ・移動速度の遅さ: ボスへの再挑戦(リトライ)やマップ探索において、移動に時間がかかりすぎるという意見が多数見られます。これがゲーム全体のテンポを著しく損なっていると指摘されています。
- 回避性能の低さ: 回避アクションに無敵時間が短い、連続で入力できない、ダウン中に回避で抜けられないなど、他のソウルライクゲームと比較して性能が低いと感じるプレイヤーが多いようです。敵の攻撃は高速で苛烈なのに、プレイヤー側の対処手段が追いついていないというバランスの悪さが問題視されています。
- 起き上がりや回復動作の遅さ: ダウンからの復帰や回復アイテムの使用モーションが長いため、敵からの「起き攻め」や「回復狩り」が非常に頻発します。一度の被弾が死に直結しやすく、理不尽さを感じる原因となっています。
爽快感の欠如
攻撃モーションやヒット時の効果音(SE)が軽く、「敵を斬っている」「殴っている」という感触が薄いという指摘もあります。 これにより、強敵を倒した際の爽快感や達成感が削がれてしまっていると感じるプレイヤーも少なくないようです。 死にゲーにおいて、苦労に見合ったカタルシスが得られないのは、モチベーションを維持する上で致命的と言えるかもしれません。
プレイヤーを突き放す不親切なマップデザイン
探索もソウルライクの大きな魅力の一つですが、本作のマップデザインは多くのプレイヤーを悩ませました。
考えられていないチェックポイントとショートカット
セーブポイントである「祠」からボスまでの距離が異常に遠い、あるいは意味のない場所にショートカットが設置されているなど、プレイヤーのストレスを軽減するための配慮が足りないという意見が多く見られます。 前述した移動速度の遅さと相まって、リトライのたびに長い道のりを走り直す作業は、多くのプレイヤーの心を折る原因となりました。
迷いやすいマップ構造と視認性の悪さ
マップ全体が似たような景色で構成されているため、現在地や目的地が分かりにくく、道に迷いやすいという問題も指摘されています。 マップ表示機能がないソウルライクでは、景観による誘導が非常に重要ですが、本作はその点で課題を抱えています。 また、ステージによっては極端に暗く、敵や地形の視認性が悪いことも、理不尽な死や探索のストレスに繋がっています。
「難しさ」と「理不尽」の履き違え
優れた死にゲーは、「難しいが、自分の腕が上がればクリアできる」という納得感があります。 しかし、『明末:ウツロノハネ』には、「どうしようもない」と感じさせる理不尽な要素が多いという批判が絶えません。
- 悪質な初見殺し: 画面外や死角から、回避不能な掴み攻撃が飛んでくる。
- 理不尽な敵の配置: 大量の雑魚敵がスーパーアーマー持ちで怯まない、ボスへの道中に即死効果のある地雷が大量に配置されているなど、プレイヤーを消耗させるためだけの悪意ある配置が目立ちます。
これらの要素は、プレイヤーに「自分のせいで死んだ」のではなく「ゲームのせいで死んだ」と感じさせ、挑戦する意欲を削いでしまいます。
UI/UXの未熟さ
- UIの不便さ: 戦闘中にHPバーが自動で消えてしまい、確認のためにボタン操作が必要になるなど、細かい部分での配慮不足が指摘されています。
- チュートリアル不足: 「粋」や「心魔」といった独自システムの面白さが、チュートリアル不足によって十分に伝わっていないという意見もあります。ゲームの肝となるシステムを理解できないまま、「ただ難しいだけのゲーム」という印象で投げ出してしまったプレイヤーもいるかもしれません。
これらの課題は、続編を制作する上で必ず向き合わなければならない、重い宿題と言えるでしょう。
結論:『明末:ウツロノハネ2』発売の可能性を徹底考察
さて、ここまで『明末:ウツロノハネ』が持つ魅力と、乗り越えるべき課題の両側面から分析してきました。 これらを踏まえ、本題である「続編の発売はあり得るのか?」という問いに対する、私なりの結論を述べたいと思います。

ポジティブ要素:売上とファンの熱量
まず、続編制作の可否を判断する上で最も重要なのは、1作目の商業的な成功です。 正確な販売本数は公表されていませんが、発売直後からSNSや動画サイトで大きな話題となり、多くのインフルエンサーが取り上げたことから、一定の売上は確保できていると推測されます。
特に、キャラクタービジュアルやセクシー要素に惹かれた新たなファン層からの支持は厚く、彼らが形成するコミュニティの熱量は、メーカーにとって続編制作を後押しする大きな力となります。 「荒削りだが、ポテンシャルは感じる」というコアなアクションゲームファンからの声援も無視できません。 商業的に「成功」と判断されれば、続編プロジェクトが立ち上がる可能性は十分にあります。
| 高評価と低評価のポイント比較 | |
|---|---|
| 評価ポイント | ポジティブな意見 |
| アクション | 「粋」システムによる戦略性の高さ、ビルド構築の楽しさ |
| 探索 | 豊富な収集要素、美しいビジュアル |
| 難易度 | 歯ごたえがあり、乗り越えた時の達成感が大きい |
| システム | 自由度の高いスキルツリー、装備重量なし |
| キャラクター | 主人公が魅力的、セクシーな衣装が豊富 |
ネガティブ要素:開発リソースと課題の多さ
一方で、前章で挙げた数々の課題は、続編制作における大きな障壁となります。 特に、移動や回避といったアクションの根幹部分や、マップデザインの根本的な見直しには、膨大な開発リソース(時間、人材、予算)が必要です。
単に新しいストーリーやキャラクターを追加するだけでは、1作目で不満を抱いたプレイヤーを納得させることはできません。 「2でもまた同じようにストレスが溜まるのではないか」という懸念を払拭し、ファンからの期待に応えるためには、開発チームがこれらの批判と真摯に向き合い、ゲームシステムを根本から改善する覚悟が求められます。 そのための体力と技術力が、開発スタジオにあるかどうかが鍵となるでしょう。
開発スタジオの動向と今後の展望
現時点で、開発元である「Lein Games」から続編に関する公式なアナウンスはありません。 まずは、大型アップデートやDLC(ダウンロードコンテンツ)の配信を通じて、ユーザーからのフィードバックに応え、1作目の課題点を修正していく動きがあるかどうかに注目すべきです。
もし、操作性の改善やマップ構造の調整といった根本的なアップデートが行われれば、それは開発チームがユーザーの声に耳を傾けている証拠であり、続編への期待も高まります。 逆に、そうした動きがなく、コンテンツの追加のみに終始するようであれば、続編で根本的な改善がなされる可能性は低いかもしれません。
総合的な結論と個人的な見解
以上の点を総合的に判断すると、『明末:ウツロノハネ2』が発売される可能性は**「五分五分、ただし条件付き」**というのが私の見解です。
商業的な成功とファンの熱意というポジティブな追い風は吹いています。 しかし、ゲームの根幹に関わる数多くのネガティブな課題という重い錨(いかり)も抱えています。 続編という船が航海に出られるかどうかは、開発チームがこの錨を断ち切り、ファンの期待という追い風を帆いっぱいに受ける準備を整えられるかにかかっています。
ゲーム評論家として個人的な意見を述べさせてもらえれば、私はこの作品に大きなポテンシャルを感じています。 光る部分と、あまりにも未熟な部分が混在した、非常にアンバランスな作品です。 だからこそ、課題を克服し、長所をさらに伸ばすことができたなら、『明末:ウツロノハネ』は唯一無二の魅力を持つシリーズへと飛躍できる可能性を秘めていると信じています。
まとめ
今回は、多くのプレイヤーを魅了し、同時に多くの課題も露呈したソウルライクアクションRPG『明末:ウツロノハネ』の続編の可能性について考察しました。
- 本作は「粋」や「心魔」といった独自システム、自由度の高いビルド、魅力的なキャラクターで熱狂的なファンを生んだ。
- 一方で、操作性、マップデザイン、理不尽な難易度など、ゲームの根幹に関わる多くの課題を抱えている。
- 続編が発売されるかは、1作目の商業的成功と、開発チームが課題を克服できるかにかかっている。
結論として、その可能性は決してゼロではありませんが、楽観視もできません。 まずはDLCやアップデートで、開発チームがどのような姿勢を見せるのか。 私たちプレイヤーは、今後の公式発表を注意深く見守り、続報に期待しましょう。