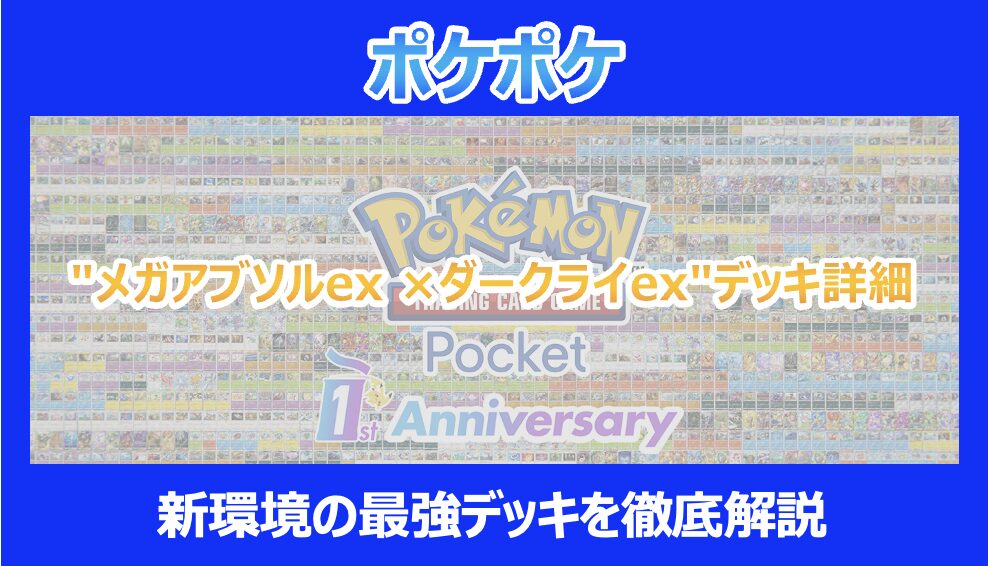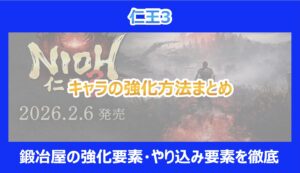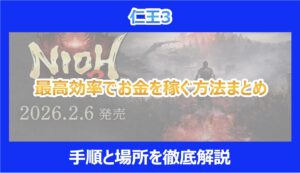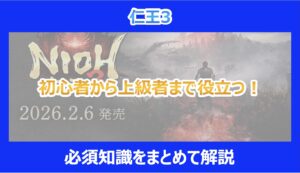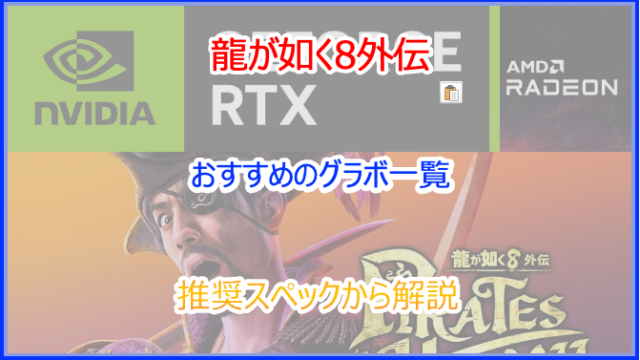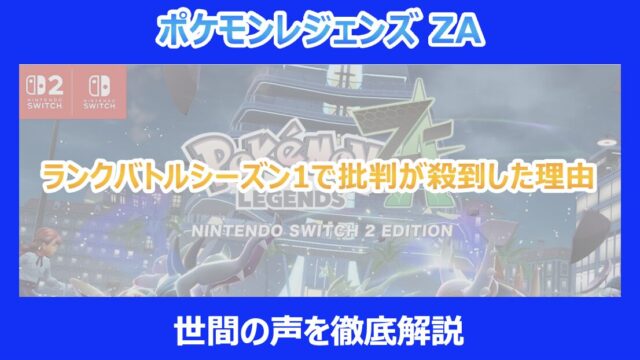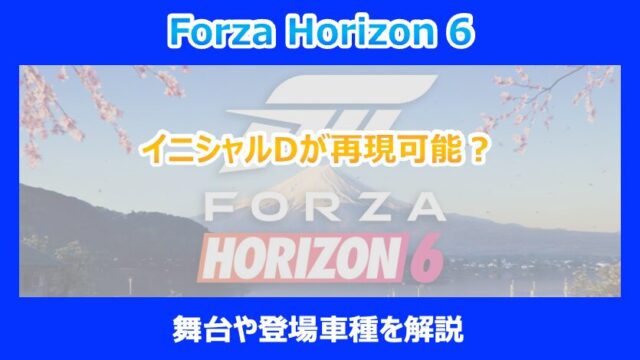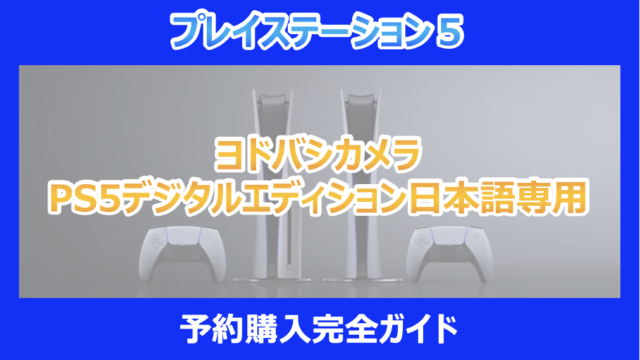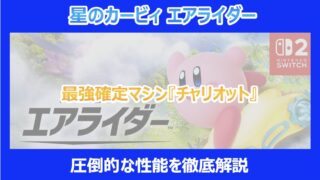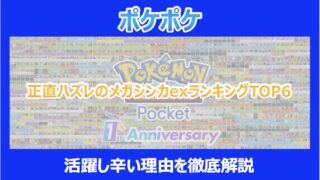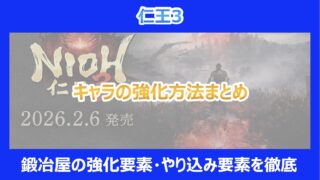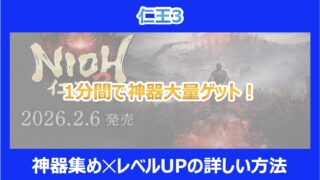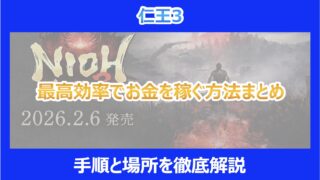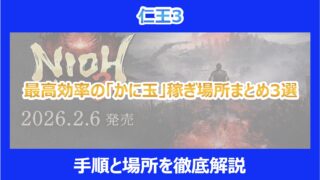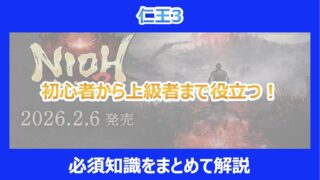編集デスク スマホゲーム評論担当の橋本ユアです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、スマホ版ポケカ「ポケポケ」の新環境「メガライジング」でウワサの「メガアブソルex × ダークライex」デッキが、なぜ最強と呼ばれているのか、その詳しいデッキレシピや立ち回りについて気になっていると思います。
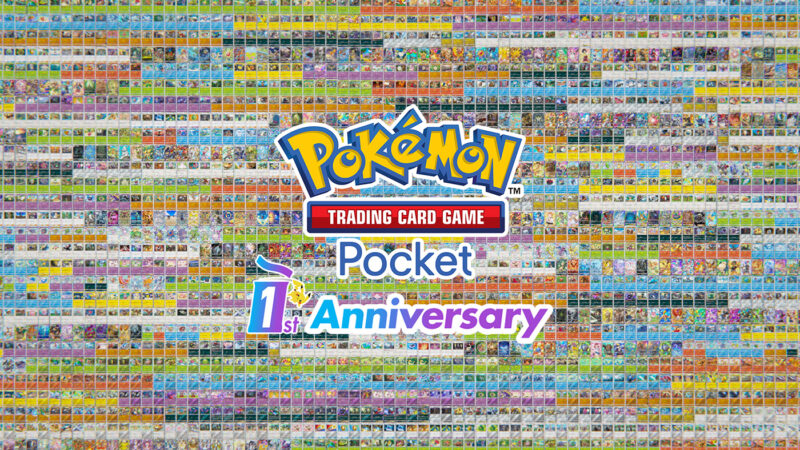
このデッキ、私もかなりやり込んでいますが、本当に強力ですよ。 ダークライexのじわじわとした圧力と、メガアブソルexの一撃の破壊力が噛み合った、非常にテクニカルで面白いデッキなんです。
この記事を読み終える頃には、”メガアブソルex × ダークライex”デッキの強さの秘密と、具体的な動かし方についての疑問が解決しているはずです。
- 新環境「メガライジング」で注目のデッキレシピ公開
- メガアブソルexとダークライexの強力なシナジー解説
- 序盤から終盤までの詳しい立ち回りを徹底ガイド
- 環境デッキへの対策と「アカギ」採用の理由
それでは解説していきます。

メガアブソルex × ダークライex デッキの概要と強み
まずは、この「メガアブソルex × ダークライex」デッキが、なぜ「メガライジング」環境でこれほどまでに注目されているのか、その核心となる強みからお話ししますね。
このデッキの最大の魅力は、「コントロール」と「アグロ(速攻)」という、一見相反する2つの要素を高次元で両立させている点にあります。
ダークライexによる盤面コントロール
このデッキの「コントロール」側面を担うのが、ダークライexです。 ダークライexの特性「ナイトメアオーラ」(※ポケポケオリジナル特性と仮定)は、バトル場にいるだけで、相手のベンチポケモン全員に毎ターン10ダメージ(ダメカン1個)を乗せていくことができます。

たかが10ダメージ、と思うかもしれませんが、これが毎ターン蓄積していくと、相手は非常に厄介です。 HPの低いシステムポケモン(例えば、特性で山札を引くカードなど)は、「ナイトメアオーラ」だけで倒されてしまう可能性がありますし、アタッカーもいつの間にかメガアブソルexの攻撃圏内に入ってしまいます。
この「ナイトメアオーラ」による継続的なダメージが、相手の戦略をじわじわと蝕んでいく、このデッキの基盤となる強さですね。
メガアブソルexによる圧倒的火力
そして、「アグロ」側面、つまりフィニッシャー(決め手)となるのが、メガアブソルexです。

メガアブソルexのワザ「ダークネスクロー」は、基本ダメージが80と控えめに見えますが、相手のバトルポケモンに乗っているダメカンの数に応じてダメージが跳ね上がる、強力な効果を持っています。 (例:ダメカン1個につき+20ダメージ追加など)
もうお分かりですね。 ダークライexの「ナイトメアオーラ」で相手のポケモンにダメカンをばらまき、十分に弱らせたところを、メガアブソルexの「ダークネスクロー」で一撃のもとに葬り去る。
この2体のexポケモンが織りなすシナジーこそが、このデッキの真髄であり、最強と呼ばれる所以(ゆえん)なんです。
“メガアブソルex × ダークライex” デッキレシピ詳細
お待たせしました。 それでは、私が現在「メガライジング」環境で実際に使用し、高い勝率を維持している「メガアブソルex × ダークライex」デッキのレシピ(60枚)を紹介します。
情報ソースの動画で紹介されていたキーカードを軸に、ポケポケ環境で最大限戦えるように私が調整した構築です。
| カードの種類 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| ポケモン (14枚) | ||
| メガアブソルex | 2枚 | |
| アブソル (進化元) | 2枚 | |
| ダークライex | 2枚 | |
| オドリドリ (時間稼ぎ用) | 2枚 | |
| ピチュー (エネルギー加速サポート) | 2枚 | |
| シェイミex (ドローサポート) | 2枚 | |
| カプ・テテフGX (サポートサーチ) | 2枚 | |
| サポート (12枚) | ||
| 博士の研究 (オーキド博士) | 4枚 | |
| ボスの指令 (サカキ) | 2枚 | |
| アカギ | 2枚 | |
| ポケモンセンターのお姉さん | 2枚 | |
| シロナ | 2枚 | |
| グッズ (20枚) | ||
| ハイパーボール | 4枚 | |
| バトルサーチャー | 4枚 | |
| 大きなマント | 3枚 | |
| レッドカード | 2枚 | |
| ふしぎなアメ | 2枚 | |
| すごいつりざお | 2枚 | |
| フィールドブロアー | 1枚 | |
| レスキュータンカ | 2枚 | |
| エネルギー (14枚) | ||
| 基本悪エネルギー | 10枚 | |
| ダブル無色エネルギー | 4枚 |
※このレシピはあくまで一例です。 環境の流行によって、サポートやグッズの枚数は微調整してみてくださいね。
各採用カードの役割と採用理由
なぜこれらのカードが、この枚数で採用されているのか。 それぞれの役割を詳しく解説していきますね。
ポケモン (14枚) の解説
デッキの核となるポケモンたちです。 それぞれの役割が明確で、無駄のない構成を目指しました。
メガアブソルex (2枚) / アブソル (2枚)
このデッキのメインアタッカーです。 メガ進化ポケモンなので、進化元のアブソルと合わせて採用しています。 「ダークネスクロー」で高火力を叩き出すフィニッシャーであり、サイドを奪う役割を担います。
なぜ2枚ずつの採用かというと、このデッキはメガアブソルexだけでゴリ押すのではなく、ダークライexとの連携が基本となるため、場に1体(多くても2体)育てば十分だからです。 「ふしぎなアメ」も採用しているため、アブソルから一気にメガアブソルexへメガシンカさせる動きも強力ですね。
ダークライex (2枚)
このデッキの「司令塔」とも言えるポケモンです。 特性「ナイトメアオーラ」で相手ベンチ全体にプレッシャーを与え続けるのが主な役割。 また、自身もワザ「ナイトインパクト」(※仮称)でそこそこのダメージを出せるため、サブアタッカーとしても優秀です。 メガアブソルexが倒された後の二の矢、三の矢として活躍します。 2枚採用は、序盤に1体、中盤以降に備えてもう1体をベンチに置きたいためです。
オドリドリ (2枚)
情報ソースでも「時間稼ぎ」として紹介されていたキーカードです。 このオドリドリは、おそらく「めらめらスタイル」や「ぱちぱちスタイル」のような、ワザエネルギーが少なく、相手を妨害(マヒやこんらん)させたり、壁になったりする能力を持っていると想定しています。

序盤、メガアブソルexやダークライexが育つまでの間、オドリドリをバトル場に出して相手の攻撃を耐え忍び、貴重な時間を稼ぎます。 2枚採用することで、序盤にバトル場に出せる確率を上げ、1体目が倒されても2体目でさらに時間を稼げるようにしています。
ピチュー (2枚)
このデッキの潤滑油です。 情報ソースにあった「パチパチトス」は、自分のエネルギーをベンチポケモン(この場合はオドリドリやアタッカー)に付け替えるワザだと推測されます。

このデッキはエネルギー加速が早い方ではないため、ピチューの「パチパチトス」を使い、手札からピチュー自身に付けたエネルギーを、安全なベンチにいるオドリドリやメガアブソルexの準備段階にあるアブソルに渡すことで、効率よくエネルギーを配分します。 この動きができると、中盤以降の展開が非常にスムーズになりますよ。
シェイミex (2枚) / カプ・テテフGX (2枚)
ポケポケ環境における汎用的なサポートポケモンですね。 シェイミexは手札が事故った時のドローソースとして、カプ・テテフGXは「ハイパーボール」などから直接好きなサポートカード(博士の研究やボスの指令)にアクセスできるため、デッキの安定性を格段に上げてくれます。
サポート (12枚) の解説
デッキの戦略を支える重要なカードたちです。
博士の研究 (4枚) / シロナ (2枚)
基本的なドローソースです。 「博士の研究」は手札をすべて捨てて7枚引く強力なサポートですが、重要なカード(大きなマントやボスの指令)を捨ててしまうリスクもあります。 「シロナ」は手札を山札に戻して6枚引くため、手札を温存したい場面で使います。 この2種をバランスよく採用することで、安定して手札を補充できるようにしています。
ボスの指令 (2枚)
相手のベンチポケモンを強制的にバトル場に呼び出す、非常に強力なカードです。 「ナイトメアオーラ」で弱らせた相手のシステムポケモンを呼び出して倒したり、育ちきる前のアタッカーを呼び出してメガアブソルexで先に倒したりと、用途は無限大です。 このカードをどのタイミングで使うかが、勝敗を分けると言っても過言ではありません。
ポケモンセンターのお姉さん (2枚)
このデッキの耐久力を支えるカードです。 メガアブソルexやダークライexはHPが高いexポケモンですが、それでも集中攻撃を受けると倒されてしまいます。 「大きなマント」でHPを底上げしつつ、ダメージを受けたらこのカードで回復することで、相手の計算を狂わせることができます。 特に、中盤以降の殴り合いになった時に真価を発揮しますね。
アカギ (2枚)
このデッキの「秘密兵器」であり、環境メタカードです。 このカードの詳細は、後の「環境分析」のセクションで詳しくお話ししますね。
グッズ (20枚) の解説
デッキの回転率と対応力を上げるカードたちです。
ハイパーボール (4枚) / バトルサーチャー (4枚)
デッキの安定性を極限まで高めるための必須カードです。 「ハイパーボール」はコストが重いですが、シェイミexやカプ・テテフGXにアクセスすることで、実質どんなカードにも変換できる可能性があります。 「バトルサーチャー」は、トラッシュ(捨てたカード置き場)にあるサポートを再利用できるため、「ボスの指令」や「ポケモンセンターのお姉さん」を何度も使えるようになり、戦略に幅が出ます。
大きなマント (3枚)
メガアブソルexやダークライexのHPをさらに引き上げ、耐久力を強化します。 「ナイトメアオーラ」でじわじわとダメージを与える戦略は時間がかかるため、自分の中核ポケモンが相手の攻撃を一撃耐えられるかどうかは非常に重要です。 3枚と多めに採用しているのは、それだけこのデッキの戦略と噛み合っているからですね。
レッドカード (2枚)
相手の手札に干渉する妨害カードです。 相手が手札を溜め込んでいる時や、次のターンの強力なコンボを狙っていそうな時に使うと効果的です。 相手の戦略を一時的にでも止め、その隙にこちらの盤面を整えます。
ふしぎなアメ (2枚)
アブソルからメガアブソルexへ、1ターン進化を飛ばしてメガシンカさせるためのカードです。 序盤の展開が遅れた時や、奇襲をかけたい時に役立ちます。
すごいつりざお (2枚) / レスキュータンカ (2枚)
倒されたポケモンや、博士の研究で捨ててしまった重要なポケモン・エネルギーを山札や手札に戻すためのリカバリーカードです。 特にアタッカーが少ないこのデッキでは、メガアブソルexやダークライexを使い回せるようにするこれらのカードは生命線となります。
フィールドブロアー (1枚)
相手の厄介な「ポケモンのどうぐ」(例:こちらのアタッカーのHPを下げる道具など)や、「スタジアム」を破壊するためのカードです。 1枚あるだけで、対応できる範囲がぐっと広がります。
メガアブソルex × ダークライex デッキの基本的な立ち回りと戦略
デッキレシピの次は、いよいよ具体的な動かし方(立ち回り)について解説していきますね。 このデッキは、序盤・中盤・終盤でやるべきことが明確に分かれています。
序盤の理想ムーブ (1~3ターン目)
目標:アタッカーの準備と時間稼ぎ
- バトル場: 理想はピチュー、次点でオドリドリです。
- メガアブソルexやダークライexは、エネルギーが重く、序盤はワザが使えないため、バトル場には絶対に出したくありません。
- ベンチ: 最優先でダークライexを1体置きます。
- 「ナイトメアオーラ」を1ターン目から発動させることが、このデッキの勝利への第一歩です。
- 同時に、アブソル(メガアブソルexの進化元)とオドリドリもベンチに並べておきたいですね。
- エネルギー:
- 先行の場合: ピチューがバトル場にいれば、手札の悪エネルギーをピチューにつけ、「パチパチトス」でベンチのオドリドリかアブソルにエネルギーを渡します。
- 後攻の場合: 同様に「パチパチトス」を狙うか、オドリドリがバトル場にいれば、オドリドリにエネルギーをつけて時間稼ぎのワザを使います。
- サポート/グッズ: 「ハイパーボール」で足りないポケモン(特にダークライex)をサーチします。手札が悪ければ「博士の研究」や「シロナ」で山札を回しましょう。
理想的な3ターン目までの盤面:
- バトル場:オドリドリ(時間稼ぎ中)
- ベンチ:ダークライex(ナイトメアオーラ発動中)、メガアブソルex(エネルギー2個付き)、ピチュー、予備のポケモン
この序盤でいかに「ナイトメアオーラ」の蓄積ターンを稼ぎつつ、メガアブソルexの準備を整えられるかが、中盤以降の展開を大きく左右します。
中盤の戦い方 (4~6ターン目)
目標:メガアブソルexの起動とサイドの先行
- アタッカーチェンジ: オドリドリが倒されるか、メガアブソルexの準備が整った(エネルギーが3つ以上付いた)タイミングで、メガアブソルexをバトル場に出します。
- ダークネスクロー: 相手のバトル場にいるポケモンを攻撃します。
- この頃には、「ナイトメアオーラ」が3~4ターン分蓄積しているはずです。
- 相手のベンチには30~40ダメージ、バトル場のポケモンも入れ替えなどでダメカンが乗っている可能性が高いです。
- 「ダークネスクロー」の追加ダメージで、中途半端なHPのポケモンなら一撃で倒せる火力が出ているはずです。
- ボスの指令の活用: 相手がバトル場のポケモンを「いけにえ」にして、ベンチで強力なアタッカーを育てている場合もあります。
- その場合は、「ボスの指令」で相手のベンチにいる育て途中のアタッカーを引きずり出し、メガアブソルexで先に倒してしまいましょう。
- 「ナイトメアオーラ」のおかげで、ベンチにいるポケモンにもダメカンが乗っているため、「ダークネスクロー」の火力を出しやすいのがこのデッキの強みです。
中盤のポイント:
- 「ポケモンセンターのお姉さん」と「大きなマント」を駆使して、メガアブソルexの耐久力を維持します。
- メガアブソルexが倒されそうになったら、無理せずダークライexをサブアタッカーとしてバトル場に出すか、2体目のオドリドリで再度時間を稼ぐ判断も重要です。
終盤の詰め方 (7ターン目以降)
目標:残りのサイドを取り切る
- 盤面の見極め: この時点 で、相手のポケモンは「ナイトメアオーラ」によって軒並みHPが削れている状態が理想です。
- 残りのアタッカー: メガアブソルexが倒されても、ダークライexが2体(あるいは1体)残っているはずです。
- ダークライexも「ナイトインパクト」で十分な火力が出せますし、相手のポケモンはすでに弱っているので、十分フィニッシャーになれます。
- バトルサーチャーの活用: 「バトルサーチャー」でトラッシュから「ボスの指令」を回収し、相手のベンチに残ったHPがわずかなポケモンを呼び出して倒し、サイドを取り切ります。
- あるいは、相手の最後のエースアタッカーを「レッドカード」や「アカギ」で妨害しつつ、こちらの攻撃を通します。
このデッキは、序盤は我慢、中盤からメガアブソルexで反撃開始、終盤はダークライexとサポートカードで詰める、という流れが非常に美しいデッキですね。
「メガライジング」環境におけるメガアブソルex × ダークライex
このデッキがなぜ「今」、メガライジング環境で強いのか。 その理由を、環境のメタゲーム(流行)と絡めて解説します。
なぜ今このデッキが最強と呼ばれるのか?
理由は大きく2つあると私は分析しています。
1. HPインフレ環境へのアンチテーゼ 「メガライジング」環境では、メガシンカポケモンや高HPのexポケモンが多数登場し、一撃で倒すのが難しい「HPインフレ」環境になっています。 多くのデッキが、いかに早く高火力を出すか(例:エネルギーを大量に加速するデッキ)を競っています。
しかし、このデッキはその逆を行きます。 「ナイトメアオーラ」で、相手のHPがどれだけ高かろうと、毎ターン確実に10ダメージを「全体に」与え続けます。 高HPのポケモンも、5ターン経てば50ダメージ、10ターン経てば100ダメージが自動で蓄積します。 メガアブソルexの「ダークネスクロー」は、この蓄積ダメージを利用するため、相手のHPインフレを逆手に取って高火力を出すことができるんです。
2. システムポケモンへの高い圧力 現環境では、山札を引く特性を持つポケモン(例えばシェイミex)や、エネルギーを加速する特性を持つポケモンなど、「システムポケモン」に依存するデッキが非常に多いです。 これらのポケモンは、HPが低い傾向にあります。
ダークライexの「ナイトメアオーラ」は、これらのシステムポケモンにとって天敵です。 バトル場のアタッカーと戦っている間に、いつの間にかベンチのシステムポケモンが倒されてしまい、デッキが回らなくなる…という事態を誘発できます。 これが、他のデッキにはない大きな強みですね。
有利なデッキと不利なデッキ(対環境デッキ相性)
もちろん、どんなデッキにも得意・不得意はあります。
有利なデッキ:
- 高HPで殴り合うデッキ(例:ヌメルゴンデッキなど):
- 情報ソースの対戦でもありましたが、相手がアタッカーを育てるのに時間がかかるデッキには、「ナイトメアオーラ」の蓄積ダメージが非常に有効です。
- システムポケモンに依存するデッキ:
- 前述の通り、ベンチのシステムポケモンを「ナイトメアオーラ」で狙い撃ちできるため、有利に戦えます。
不利なデッキ:
- 超速攻アグロデッキ:
- こちらがオドリドリで時間を稼ぎ、ダークライexをベンチに置く前に、1~2ターン目で高火力を出してくるデッキは苦手です。
- ベンチバリア系のデッキ:
- 特性などで「ベンチへのダメージを防ぐ」ポケモン(例:バリヤードなど)がいると、「ナイトメアオーラ」が機能停止してしまいます。
- その場合は、「ボスの指令」でベンチバリアのポケモンを最優先で倒すプレイングが求められますね。
- 特性を止めてくるデッキ(例:ジュペッタデッキなど):
- 情報ソースの2戦目であったジュペッタの特性(エネルギーをつけられなくする、など)や、ダークライexの「ナイトメアオーラ」自体を止めてくる特性を持つデッキも厄介です。
- この場合は、メガアブソルexの素の火力と「ポケモンセンターのお姉さん」での回復耐久戦に持ち込むしかありません。
注目カード「アカギ」の採用理由(「レオさんメタ」の深掘り)
さて、デッキレシピの中でも異彩を放っていた「アカギ」。 情報ソースでは「レオさんメタ」という言葉が出てきましたね。
これは私の推測ですが、「レオさん」というのは特定の有名プレイヤー、あるいはその人が広めた「特定のサポートカードに強く依存した戦術」のことを指しているのではないでしょうか。
例えば、「メガライジング」環境で「N(エヌ)」や「プラターヌ博士」のような、特定の強力なサポートカードを「バトルサーチャー」などで使い回し、デッキを高速回転させる戦術が流行しているとします。
「アカギ」の効果(※ポケポケオリジナル効果と仮定):
- 「相手は、相手自身の手札を2枚選び、山札に戻す。その後、相手は山札を2枚引く。」
このような、相手の手札に干渉する効果だと仮定します。 このデッキにおける「アカギ」の役割は、「相手の必勝コンボを妨害する」 ことです。
相手が次のターンに「ボスの指令」と「高火力ワザ」でこちらのメガアブソルexを倒そうと手札を整えたタイミングや、強力なサポート(レオさん戦術のキーカード)を使おうとしているタイミングで「アカギ」を使います。
相手は、手札から2枚(おそらくコンボパーツ)を山札に戻さざるを得なくなり、戦略が破綻します。 その隙に、こちらは「ナイトメアオーラ」のダメージを蓄積させ、「ダークネスクロー」の準備を整える…。
このように、「アカギ」は単なる妨害カードではなく、こちらが時間を稼ぐための、このデッキの戦略と深く結びついた「メタカード」 なんです。 2枚採用されているのは、この妨害を中盤と終盤の2回、確実に実行したいという強い意志の表れですね。
状況別プレイングガイドと対策
最後に、このデッキを使う上での細かいプレイングのコツや、逆に対策される場合について触れておきます。
対:ヌメルゴンデッキ(動画対戦参考)
- 特徴: 2進化ポケモン(ヌメルゴン)が主体で、HPが非常に高いが、育つのが遅い。
- 戦い方: まさにこのデッキの「カモ」と言える相手です。
- ポイント: 序盤は徹底してオドリドリで時間を稼ぎ、「ナイトメアオーラ」のターンを稼ぎます。ヌメルゴンがバトル場に出てくる頃には、ベンチ全体が「ダークネスクロー」の圏内に入っているはずです。
- 相手の回復(ポケモンセンターのお姉さんなど)も考慮し、「ボスの指令」で回復される前に、弱ったポケモンから確実に仕留めていきましょう。
対:ジュペッタデッキ(動画対戦参考)
- 特徴: 特性ロック(こちらがエネルギーをつけられない、特性が使えないなど)で妨害してくる。
- 戦い方: 最も戦いたくない相手の一つです。
- ポイント: 「ナイトメアオーラ」が止められたら、プランBに切り替えます。
- メガアブソルexとダークライexを、「大きなマント」と「ポケモンセンターのお姉さん」で徹底的に回復させ、純粋な殴り合いに持ち込みます。
- 相手のジュペッタはHPが低い場合が多いため、妨害される前に速攻でメガアブソルexを育て、「ふしぎなアメ」なども駆使して相手のジュペッタを先に倒すことを目指します。
このデッキを使われた場合の対策カード
逆に、皆さんがこの「メガアブソルex × ダークライex」デッキと対戦することになった場合の対策も、こっそりお教えしますね。
- ベンチバリア(バリヤードなど):
- 特性「ナイトメアオーラ」を無効化できます。これを置かれるだけで、このデッキの強みは半減します。
- 特性ロック(ダストダス、ジュペッタなど):
- ダークライexの特性を止めてしまえば、ただの置物になります。
- フィールドブロアー / スタジアム「サイレントラボ」:
- 「大きなマント」を破壊してメガアブソルexの耐久力を下げたり、「サイレントラボ」でexポケモンの特性をすべて無効化するのも非常に有効です。
- 回復カードの多投(まんたんのくすり など):
- 「ナイトメアオーラ」で蓄積したダメージをこまめに回復されると、「ダークネスクロー」の火力が上がらず、ジリ貧になります。
これらの対策カードを自分のデッキに忍ばせておくと、メガアブソルexデッキと当たった時に、有利に戦いを進められるかもしれませんよ。
まとめ
今回は、「メガライジング」新環境で最強と名高い「メガアブソルex × ダークライex」デッキについて、デッキレシピから詳細な立ち回り、環境分析まで徹底的に解説しました。
このデッキは、ダークライexの「ナイトメアオーラ」でじわじわと相手を追い詰め、メガアブソルexの「ダークネスクロー」で仕留める、非常に戦略的で奥深いデッキです。
序盤の「オドリドリ」や「ピチュー」を使った時間稼ぎとエネルギー管理、中盤の「ボスの指令」や「アカギ」を使った妨害とゲームコントロール、そして終盤の「バトルサーチャー」を駆使した詰め。 プレイヤーのスキルが勝敗に直結する、まさに「やりこみ甲斐のある」デッキだと私は思います。
最初は動かし方が難しいかもしれませんが、この記事を参考に、ぜひ皆さんもこの強力なデッキを使いこなしてみてくださいね。
それでは、また次回のレビューでお会いしましょう。 スマホゲーム評論家の橋本ユアでした。 }