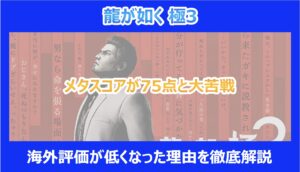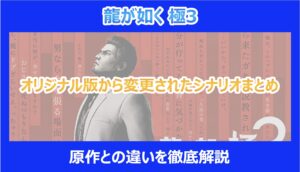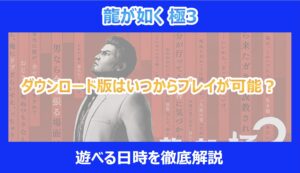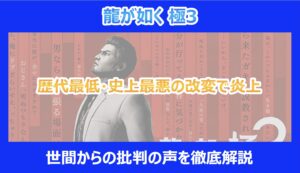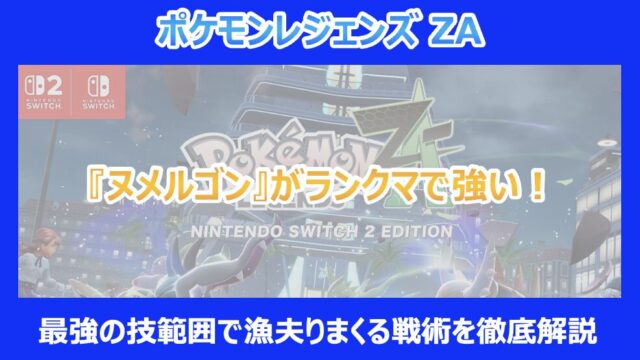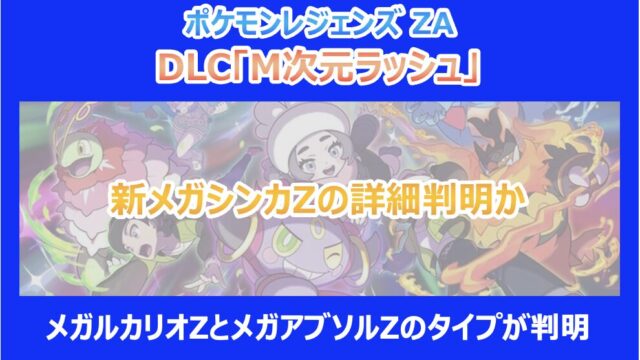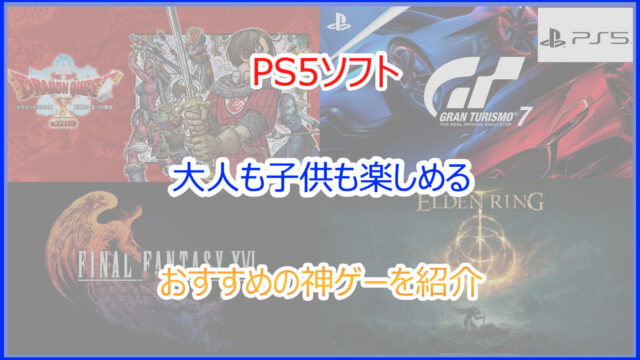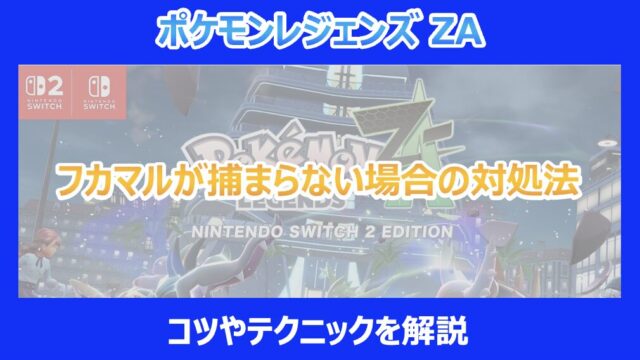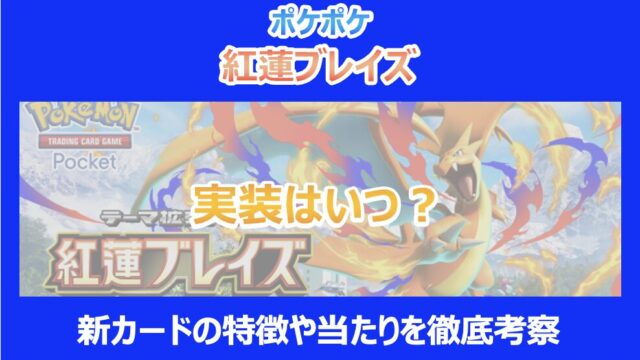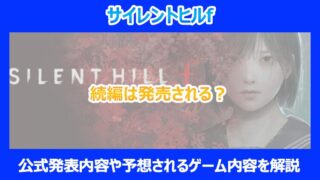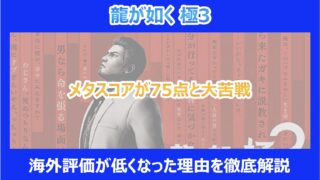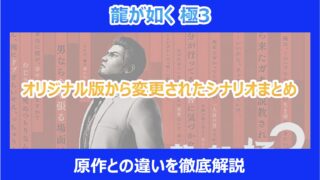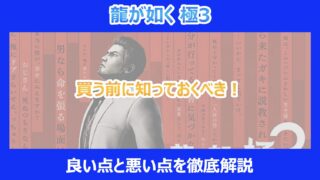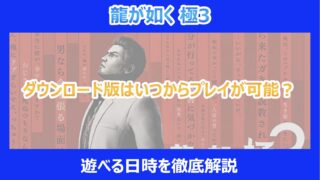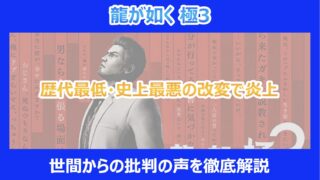ゲームジャーナリストの桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、期待の新作『Ghost of Yōtei』にまつわる炎上騒動の真相が気になっていると思います。 「前作は最高だったのに、続編で何が起こったんだ?」 「開発者の不適切な発言が原因らしいけど、具体的にどんな内容だったの?」 「予約キャンセルや不買運動まで起きているって本当?」 そんな疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。

この記事を読み終える頃には、『Ghost of Yōtei』の炎上から不買運動に至るまでの経緯、その根本的な原因、そして一人のゲーマーとしてこの問題にどう向き合うべきか、全ての疑問が解決しているはずです。
- 開発者の不適切発言の具体的な内容とその背景
- 一つの発言が大規模な不買運動へ発展したメカニズム
- 過去の類似事例との比較で見る今回の問題の本質
- ゲーマーとして購入を判断するための客観的な視点
それでは解説していきます。

Ghost of Yōtei開発者の炎上事件、その全貌
待望の続編として、世界中のゲーマーから大きな期待を寄せられていた『Ghost of Yōtei』。 しかし、発売を目前にして、開発スタジオ「サッカーパンチ・プロダクションズ」のシニアスタッフによるSNS上での発言が、大きな波紋を呼びました。 ここでは、一体何が起こったのか、事の経緯を時系列で詳しく見ていきましょう。

炎上の発端となった開発者の不適切発言とは
今回の騒動の中心人物は、サッカーパンチ・プロダクションズに所属するシニアキャラクターアーティスト、ドリ・ハリソン氏です。 問題となったのは、彼が自身のSNSアカウントで行った一つの投稿でした。
その内容は、アメリカで起こったある著名な政治活動家の銃撃殺害事件を揶揄し、嘲笑するかのようなものでした。 人の死を軽んじる不謹慎な内容に、多くのユーザーが強い不快感を示し、批判が殺到。 これが、後に大きなうねりとなる炎上の最初の火種となったのです。
企業に所属する人間として、また多くのファンを持つ大作ゲームの開発者として、その立場をわきまえない無神経な発言は、瞬く間に拡散されていきました。
発言の背景にある「チャーリー・カーク氏銃撃事件」
ハリソン氏の発言を理解するためには、その背景にある事件を知る必要があります。 2025年9月10日、アメリカの保守派著名政治活動家であるチャーリー・カーク氏が、公演中に銃撃され亡くなるという衝撃的な事件が発生しました。
カーク氏は、中絶や同性愛、銃規制に反対するなどの過激な主張で知られ、多くの支持者を持つ一方で、同数かそれ以上の反対派から強い反感を買っていた人物です。 彼の死に対し、追悼の声が上がる一方で、一部からは彼の死を喜ぶかのような心無い声も上がっていました。 ハリソン氏の投稿は、後者の立場から、この悲劇的な事件をジョークのネタとして消費したものだったのです。
発言内容の解説:「マリオとルイージ」の皮肉なジョーク
ハリソン氏の具体的な投稿内容は、「犯人の名前がマリオだといいな。そうすればルイージは兄が味方だと分かるからね」というものでした。 一見すると意味が分かりにくいこの文章には、アメリカで物議を醸した別の殺害事件が下敷きにされています。
別の事件との関連性
2024年12月、アメリカの大手保険会社ユナイテッドヘルスケアのCEO、ブライアン・トンプソン氏が殺害される事件がありました。 トンプソン氏は、顧客への保険金の支払いを意図的に拒否する戦略を取っていたとされ、適切な治療を受けられずに亡くなった人々やその遺族から、強い恨みを買っていました。 そして、この事件の犯人の名前が「ルイージ・マジョーネ」だったのです。
つまり、ハリソン氏の投稿は、 「保険金不払いで人々を苦しめたCEOを殺害した犯人『ルイージ』のように、今回のカーク氏殺害の犯人が『マリオ』だったら、彼ら(マリオとルイージ)は社会悪を排除する仲間(兄弟)ということになる。それは面白いじゃないか」 という、極めて悪質で皮肉に満ちたジョークだったのです。
人の死を、しかも二つの別の殺害事件を絡めてエンターテイメントのように語ったこの投稿は、倫理的に決して許されるものではなく、多くの人々の怒りを買うのは当然の結果でした。
開発者のその後の対応とさらなる燃料投下
通常、このような炎上が発生した場合、問題の人物は速やかに謝罪し、事態の鎮静化を図るのが一般的です。 しかし、ハリソン氏の対応は全く逆でした。
彼は自身の投稿への批判に対し、反省や謝罪の言葉を述べるどころか、批判するユーザーを煽るような投稿を繰り返したのです。
「誰かの雇用主にメールするより、議員にメールして銃規制を要求すべきでは?」
これは、銃規制に反対していたカーク氏が銃によって殺害されたことをさらに皮肉る内容であり、火に油を注ぐ結果となりました。 反省の色を全く見せない彼の態度は、ユーザーの怒りをさらに増幅させ、事態をより深刻なものへと発展させていったのです。
アカウント名の変更
最終的に、ハリソン氏は自身のアカウント名を「ドリだけど死ぬまで(差別主義者を)殴り続けるドリ」といった趣旨の名前に変更。 これは、彼が自身の行いを正当化し、批判する人々を敵と見なしていることの現れであり、もはや対話による解決は不可能であることを示していました。 この一連の行動は、彼個人の資質の問題だけでなく、彼が所属する企業の管理体制にも疑問符を突きつけるものとなりました。
所属スタジオ「サッカーパンチ」の肩書削除の経緯
炎上が拡大する中、ユーザーたちはハリソン氏の雇用主であるサッカーパンチ・プロダクションズ、そしてその親会社であるソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)に対して、説明と対応を求める通報を相次いで行いました。
事態を重く見たのか、しばらくしてハリソン氏のSNSプロフィールや、ビジネス特化型SNS「LinkedIn」のプロフィールから、「サッカーパンチ・プロダクションズ所属」という肩書きが削除されました。 これは、事実上の解雇、あるいは懲戒処分が下されたことを示唆しています。
しかし、ハリソン氏本人は「反ファシズムのために10年間勤めた夢の仕事を失うことになっても、私は100倍強くなってやり直す」といった投稿をしており、解雇を不当として争う姿勢も見せています。 この一連の騒動により、彼はゲーム開発者としてのキャリアに、自ら終止符を打った形となりました。
不買運動(ボイコト)へと発展した理由と現状
一人の開発者による不適切な発言。 それはなぜ、ゲームそのものの「不買運動」という、最も深刻な事態にまで発展してしまったのでしょうか。 その背景には、SNS時代の消費者行動の変化と、企業側の対応の遅れが複雑に絡み合っています。

なぜ一つの発言が不買運動にまで発展したのか
現代において、消費者は単に製品の品質だけでなく、それを提供する企業の倫理観や姿勢(スタンス)をも厳しく評価します。 特に、SNSの普及は、個人の意見や抗議の声を瞬時に集約し、大きな力を持つムーブメントへと昇華させることを可能にしました。
今回のケースでは、
- 発言内容の悪質さ: 人の死を嘲笑うという、倫理的に許容しがたい内容だったこと。
- 当事者の不誠実な対応: 謝罪せず、逆にユーザーを煽るという態度が、怒りを増幅させたこと。
- 企業の対応の遅れ: サッカーパンチやソニーからの公式な声明がなかなか出されず、ユーザーの不信感を募らせたこと。
これらの要因が重なり、「このような人物が開発に関わり、利益を得るような製品は購入したくない」「問題に対して真摯に向き合わない企業の製品は支持できない」という考えが広がり、個人の抗議が組織的な不買運動へと繋がっていったのです。
SNSで広がる予約キャンセル報告とボイコットの呼びかけ
X(旧Twitter)などのSNS上では、「#BoycottGhostOfYotei」といったハッシュタグと共に、予約をキャンセルしたことを証明するスクリーンショットの投稿が相次ぎました。 一件一件は個人の小さな行動ですが、これらが可視化され、拡散されることで、「自分もキャンセルしよう」「このゲームを買うのはやめよう」という同調圧力が生まれ、運動はさらに大きな広がりを見せています。
「ゲームは楽しみだったけど、こんな気分の悪い騒動があった後では素直に楽しめない」 「開発チームの他のメンバーには同情するが、企業の姿勢が許せない」
といった声が多数見られ、多くのファンが複雑な心境でこの事態を受け止めていることが分かります。
開発会社とソニーの沈黙が招いたさらなる憶測
本稿執筆時点においても、サッカーパンチ・プロダクションズおよびソニーからは、この件に関する公式な声明や謝罪は発表されていません。 肩書きの削除という事実上の処分は行われましたが、なぜこのような事態が起きたのか、再発防止策はどうするのか、といった点について企業としての見解が示されていないのです。
この「沈黙」は、ユーザーにとって「問題を軽視している」「ほとぼりが冷めるのを待っている」という不誠実な態度と受け取られかねません。 「会社ぐるみでハリソン氏の思想を容認しているのではないか」といった憶測まで生んでおり、企業ブランドへのダメージは計り知れないものとなっています。 迅速かつ誠実な対応がなされない限り、ユーザーの信頼を取り戻すことは困難でしょう。
過去の類似事例:DCコミック作者の炎上とシリーズ打ち切り
同様の事例は、過去に他のエンターテイメント業界でも発生しています。 例えば、大手アメリカンコミック出版社であるDCコミックでは、所属の作家が今回のハリソン氏と類似した不謹慎な発言をSNSで行った結果、その作家が担当していたコミックシリーズが打ち切りになるという事態にまで発展しました。
この事例は、クリエイター個人の問題行動が、作品そのものの存続にまで影響を及ぼすという厳しい現実を示しています。 今回の『Ghost of Yōtei』が発売中止にまで至る可能性は低いと考えられますが、売上への深刻なダメージは避けられないでしょう。
『アサシン クリード シャドウズ』の炎上事件との比較分析
近年のゲーム業界で大きな炎上事件といえば、ユービーアイソフトの『アサシン クリード シャドウズ』が記憶に新しいでしょう。 しかし、今回の『Ghost of Yōtei』の炎上は、それとは性質が異なります。
| 項目 | Ghost of Yōtei | アサシン クリード シャドウズ |
|---|---|---|
| 炎上の中心 | 開発者個人の倫理観に欠ける言動 | ゲームの内容(歴史考証、主人公設定) |
| 問題の種類 | ゲーム外での不適切発言 | 作品そのものの設定や表現に対する批判 |
| ユーザーの批判対象 | 開発者個人と、企業の管理体制 | 開発スタジオの歴史認識と制作方針 |
| 日本人ゲーマーの関わり | 間接的(倫理的な問題として) | 直接的(日本文化の扱い方として) |
『アサシン クリード シャドウズ』の炎上は、ゲームの内容、特に日本の歴史や文化の扱い方に対する批判が中心でした。 一方で、『Ghost of Yōtei』の問題は、ゲームの内容とは直接関係のない、開発者個人の倫理観が問われるものです。
しかし、どちらのケースにも共通しているのは、**「開発・販売企業のユーザーに対する姿勢」**が厳しく問われている点です。 ユーザーからの批判や懸念に対し、真摯に向き合い、対話する姿勢を示すのか、それとも無視や反論を貫くのか。 その対応一つで、作品の運命、ひいては企業の未来が大きく左右される時代になっているのです。
ゲーマーとして今どう向き合うべきか?購入判断のポイント
この複雑な状況の中、一人のゲーマーとして、私たちはどう判断し、行動すれば良いのでしょうか。 前作のファンであればあるほど、購入すべきか否か、その決断は難しいものになるはずです。 ここでは、冷静に判断するためのいくつかの視点を提供します。

ゲームの内容そのものに問題はあるのか?
まず最も重要なのは、今回の騒動はゲームの内容や品質そのものとは直接関係がないという点です。 ハリソン氏の発言はあくまでゲーム外での出来事であり、それによって『Ghost of Yōtei』の物語やアクション、グラフィックの価値が損なわれるわけではありません。
もしあなたが純粋にゲーム体験を求めているのであれば、「作品に罪はない」という考え方で、騒動と作品を切り離して評価することも一つの選択肢です。 これまでに公開されているトレーラーやゲームプレイ映像から感じたワクワク感を信じ、予定通り購入するという判断も十分に尊重されるべきでしょう。
開発チーム全体の問題と個人の問題を切り分ける視点
『Ghost of Yōtei』の開発には、200人近いスタッフが関わっていると言われています。 今回の問題は、その中のたった一人が引き起こしたものです。
残りの多くの開発者たちは、長年にわたって情熱を注ぎ、素晴らしいゲームをファンに届けようと努力を続けてきました。 その彼らの努力の結晶である作品を、一人の問題行動だけを理由に否定してしまうのは、あまりにも乱暴ではないか、という考え方もあります。
もちろん、問題を起こした人物がチームのシニアスタッフであったことは事実であり、その責任は軽視できません。 しかし、チーム全体の功績と個人の過ちを同一視せず、冷静に切り分けて考えることも、フェアな視点と言えるかもしれません。
今すぐ予約キャンセルすべき?公式発表を待つべきか
現時点で最も賢明な行動は、感情的に動かず、まずはサッカーパンチおよびソニーからの公式発表を待つことだと私は考えます。 企業としてこの事態をどう受け止め、どう対応するのか。 その姿勢を見極めてから、最終的な購入判断を下しても決して遅くはありません。
もし、企業が真摯な謝罪と再発防止策を示し、ユーザーの信頼回復に努める姿勢を見せるのであれば、改めて作品を応援するという選択肢も出てくるでしょう。 逆に、このまま沈黙を続けたり、ユーザーを軽視するような声明を出したりした場合には、購入を見送るという判断がより強固なものになるはずです。 予約のキャンセルはいつでもできます。 焦らず、冷静に情報を見極めることが重要です。
私(桐谷シンジ)の見解:ジャーナリストとしての中立的な立場から
ゲームジャーナリストとしての私の立場から言えることは、『Ghost of Yōtei』はゲームとして非常に大きな可能性を秘めた作品であるということです。 前作が打ち立てた金字塔を、さらに超えようという開発チームの気概は、これまでに公開された情報からもひしひしと伝わってきます。
しかし同時に、今回の騒動は現代のゲーム業界が抱える根深い問題を浮き彫りにしました。 クリエイターの倫理観、企業のコンプライアンス意識、そしてファンとのコミュニケーションのあり方。 これら全てが、一本のゲームの評価を左右する重要な要素となっているのです。
私自身、予約は済ませていますが、そのキャンセルボタンを押すかどうかは、今後の企業の対応次第だと考えています。 ゲームの内容が素晴らしいものであっても、それを作る人、売る人の姿勢に納得ができなければ、心からその作品を楽しむことはできないからです。 これは、多くのゲーマーが共有する感覚ではないでしょうか。
Ghost of Yōtei ゲーム自体の魅力と期待
一連の騒動に焦点を当ててきましたが、ここで一度、ゲームそのものの魅力に目を向けてみましょう。 炎上の影に隠れがちですが、『Ghost of Yōtei』は前作を凌駕するポテンシャルを秘めた、期待の大作であることに変わりはありません。

前作『Ghost of Tsushima』からの進化点
前作『Ghost of Tsushima』は、美しい対馬の自然をオープンワールドで再現し、黒澤明監督の時代劇映画への深いリスペクトに満ちた剣戟アクションで、世界中のプレイヤーを魅了しました。 メタスコアでも高い評価を獲得し、多くのゲームアワードを受賞した名作です。
『Ghost of Yōtei』では、その核となる魅力を受け継ぎながら、あらゆる面で正当進化を遂げていると期待されています。 特に、PlayStation 5の性能を最大限に活かしたグラフィックの向上は、より没入感のある世界体験を提供してくれるでしょう。
新たな舞台と主人公、物語への期待
今作の舞台や時代設定、そして主人公が誰になるのか、まだ多くは明かされていません。 しかし、「Yōtei(羊蹄)」というタイトルから、北海道の羊蹄山周辺が舞台になるのではないかという考察が広まっています。 もしそれが事実であれば、対馬とは全く異なる、雪深く厳しい北の大地で、どのような物語が紡がれるのか、期待は膨らむばかりです。
前作の主人公・境井仁の物語は一つの区切りを迎えましたが、彼のその後の物語なのか、あるいは全く新しい主人公による新たな「冥人(くろうど)」の伝説が描かれるのか。 ファンの間では様々な憶測が飛び交っており、公式からの続報が待たれます。
ゲームシステムやグラフィックの進化
前作で好評だった、緊張感あふれる「一騎討ち」や、ステルスアクションと正面からの斬り合いを両立させた戦闘システムは、さらに深みを増していることでしょう。 新たな武器や技、探索要素の追加も期待されます。
何よりも、サッカーパンチが得意とする、風や光、天候といった自然の表現が、PS5のパワーによってどこまで進化するのか。 息をのむほどに美しい日本の原風景を再び旅できることは、多くのプレイヤーにとって最大の楽しみの一つであるはずです。
まとめ
今回は、期待の新作『Ghost of Yōtei』を巡る炎上騒動について、その発端から不買運動に至るまでの経緯、そしてゲーマーとしての向き合い方までを詳しく解説してきました。
- 炎上の原因は、開発者個人のSNSにおける極めて不謹慎な発言。
- 当事者の反省なき態度と、企業の対応の遅れが、不買運動という最悪の事態を招いた。
- この問題はゲーム内容とは無関係だが、企業の姿勢が問われている。
- 購入を判断する際は、感情的にならず、今後の公式発表を待つのが賢明。
ゲームは、プログラムやグラフィックだけで出来ているわけではありません。 そこには開発者の思想や情熱、そしてそれをファンに届けようとする企業の姿勢が必ず反映されます。 今回の騒動は、私たちゲーマーに、一本のゲームとどう向き合うべきか、改めて問いかける出来事となりました。
『Ghost of Yōtei』という作品が、この逆風を乗り越え、再び私たちに感動を与えてくれることを願いつつ、今後の動向を注意深く見守っていきたいと思います。