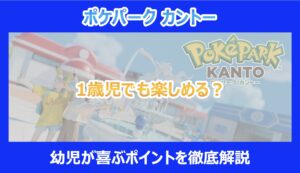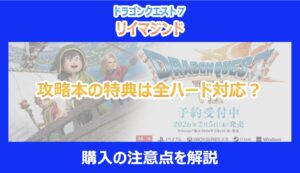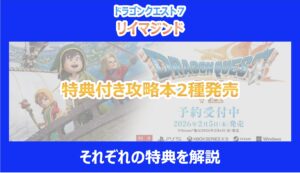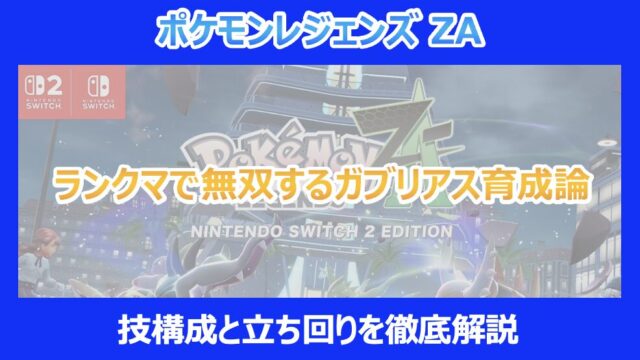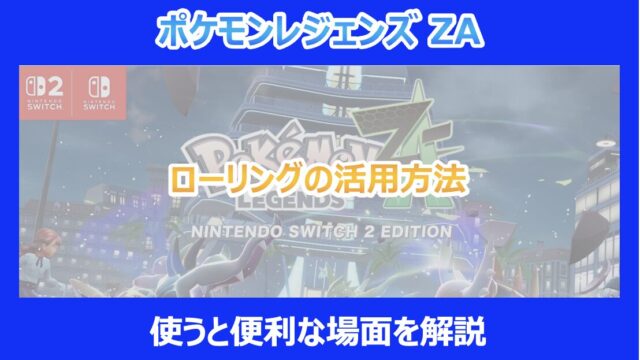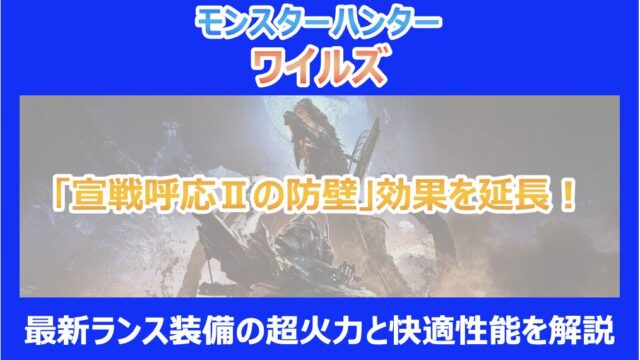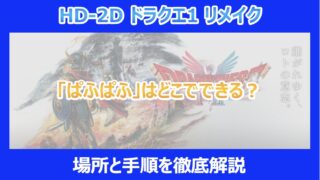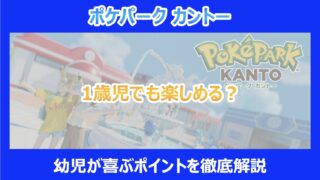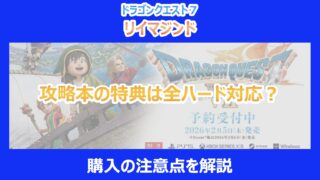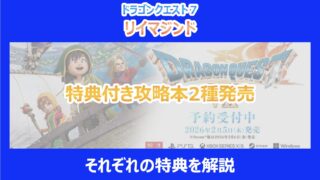ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年に発売が予定されているHD-2D版『ドラゴンクエストI&II』、特に『ドラクエ2』の「ぱふぱふ」について、場所や効果がどうなるのか気になっていると思います。 シリーズ伝統のこの「お遊び要素」が、美しいHD-2Dグラフィックでどう表現されるのか、今から楽しみですよね。

この記事を読み終える頃には、『ドラクエ2』のぱふぱふに関する場所・手順・効果、そしてリメイク版でどうなるかの予想まで、その全ての疑問が解決しているはずです。
- ドラクエ2のぱふぱふの場所
- ぱふぱふの具体的な手順
- ぱふぱふの効果とセリフ分岐
- リメイク版での変更点の予想
それでは解説していきます。
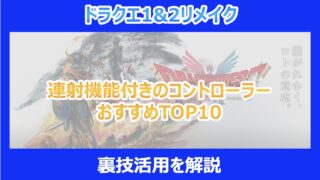
HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』と『ドラクエ2』への期待
2024年の「ドラクエの日」に発表され、ゲームファンの心を鷲掴みにしたHD-2D版『ドラゴンクエストI&II』。 特に『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』のHD-2D版が控えている中で、その原点となるロト伝説の始まりと続きが、どのような形で現代に蘇るのか、期待は高まるばかりです。
私自身、ファミコン版から始まる全ての『ドラクエ』シリーズをプレイしてきましたが、今回のHD-2D化は、ドット絵の温かみと現代の映像技術が融合した、まさに理想的なリメイクの一つだと感じています。
HD-2D版で蘇るロト伝説
HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』は、2025年に発売が予定されています。 『ドラクエ1』は言わずと知れた日本RPGの金字塔。 そして『ドラクエ2』は、シリーズで初めて「パーティ」の概念を導入し、冒険のスケールを飛躍的に拡大させた意欲作です。

この2作品が、美しい背景と精緻なドット絵キャラクターで再構築されるのです。 特に『ドラクエ2』の広大な世界、海を船で渡り、いくつもの大陸を巡る冒険が、HD-2Dでどれほど感動的に描かれるのか。 想像するだけでワクワクしますね。
なぜ今『ドラクエ2』が注目されるのか
『ドラクエ2』と言えば、当時のプレイヤーにとっては「高難易度」の代名詞でもありました。 特に有名なのが、ラストダンジョン「ロンダルキアへの洞窟」の理不尽とも思える難しさです。 落とし穴、無限ループ、そして強力すぎるモンスターの群れ。 当時の子供たち(もちろん私も含みます)は、何度も心を折られながら「ふっかつのじゅもん」を書き写したものです。
今回のリメイクでは、そうした難易度やゲームバランスが現代向けに調整されるのか、それともオリジナルの歯ごたえを残すのか、非常に注目されています。 HD-2D版『ドラクエ3』がオリジナルのFC版準拠ではなく、SFC版ベースのシステムを採用しているように、『ドラクエ2』もSFC版やスマホ版で加えられた調整(例えば、サマルトリアの王子がデイン系呪文を覚えるなど)が踏襲される可能性が高いと私は見ています。
ドラクエ伝統の「ぱふぱふ」とは? シリーズにおける位置づけ
そして、そんな『ドラクエ2』の冒険の中で、プレイヤーたちに一時の「癒やし」(あるいは「戸惑い」)を提供してきたのが、シリーズ伝統の「ぱふぱふ」です。
そもそも「ぱふぱふ」とは、ドラクエシリーズに登場する、いわゆる「お色気要素」の一つです。 『ドラクエ1』のラダトームの町で、「ぱふぱふしませんか?」と誘われ、ゴールドを支払うと謎のサービス(?)が受けられる、というのが始まりでした。 もちろん、画面上では何も起こらず、テキストと想像力だけで完結する、堀井雄二氏らしいウィットに富んだ遊び心です。
この「ぱふぱふ」は以降のシリーズにも受け継がれ、作品ごとに様々なバリエーションが登場します。 『ドラクエ3』のアッサラームでの多種多様なぱふぱふ(中にはオチがつくものも)、『ドラクエ8』のゼシカの特技としてのぱふぱふ、『ドラクエ11』ではクエストになるなど、シリーズを象徴する小ネタとして定着しています。
『ドラクエ2』のぱふぱふは、この伝統が確立する初期段階のものであり、その内容は非常にシンプルです。 しかし、そのシンプルさの中にも、後のシリーズにつながる「分岐」の要素が隠されています。
『ドラクエ2』の「ぱふぱふ」基本情報:場所と手順
では、本題である『ドラクエ2』のぱふぱふについて、その場所と具体的な手順を徹底的に解説していきましょう。 HD-2D版でも、この場所が変更される可能性は極めて低いと予想されますので、今のうちにしっかりと予習しておくことをお勧めします。
ぱふぱふができる場所は「ルプガナの町」
『ドラクエ2』でぱふぱふを体験できる場所。 それは、海辺の港町「ルプガナ」です。

ルプガナは、冒険の序盤から中盤にかけて訪れることになる町です。 この町はストーリー上、非常に重要な役割を担っています。 そう、「船」を手に入れる場所なのです。
この町を支配している商人の「あらくれ」たち(リメイク版では少しマイルドになっているかもしれませんが)との騒動を経て、プレイヤーはついに待望の「船」を入手します。 これにより、行動範囲は一気に世界規模へと広がり、『ドラクエ2』の冒険が本格的にスタートすると言っても過言ではありません。
ぱふぱふは、そんな新たな門出の町、ルプガナで体験できるのです。
ルプガナへの行き方と推奨レベル
HD-2D版で初めて『ドラクエ2』をプレイする方のために、ルプガナへの道のりも簡単におさらいしておきましょう。
サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女との合流
まず、ローレシアの王子(主人公)は、打倒ハーゴンを目指し、仲間を探す旅に出ます。 リリザの町でサマルトリアの王子の情報を得て合流し、次にムーンブルクの王女を探します。 ムーンペタの町で犬にされている王女を発見し、「ラーのかがみ」で呪いを解くことで、ようやく3人のパーティが揃います。
船の入手と冒険の海の広がり
3人パーティとなった一行は、風の塔で「かぜのマント」を手に入れ、ドラゴンの角の塔から飛び降りて対岸へ渡ります。 そこがルプガナの町です。
ルプガナでは、町を牛耳るグレムリンたち(あるいは商人)から船を譲り受ける(あるいは取り返す)イベントが発生します。 このイベントをクリアすることで、プレイヤーは自由に海を航海できるようになります。
ルプガナ到着の目安
ルプガナに到着する推奨レベルは、大体レベル10~13前後でしょうか。 ローレシアの王子がレベル10、サマルトリアの王子がレベル8、ムーンブルクの王女がレベル7程度あれば、道中の敵とも十分に渡り合えるはずです。 もちろん、HD-2D版でのバランス調整次第ではありますが、一つの目安として覚えておくと良いでしょう。
ぱふぱふをしてくれる女性の具体的な居場所(教会上)
さて、船を手に入れ、意気揚々と出航する……その前に。 ルプガナの町には、かの「ぱふぱふ」のお誘いがあります。
場所は、ルプガナの町の北東(右上)にある「教会」です。 しかし、教会の中ではありません。 教会の建物の上、屋上のようなスペースに、一人の女性がポツンと立っています。
SFC版やスマホ版では、教会の左側にある階段(SFC版では見えにくいですが)から屋根に登ることができました。 HD-2D版でも、この構造はおそらく踏襲されるでしょう。 教会の屋根の上という、なんとも言えないシチュエーションが、すでにドラクエらしい遊び心を感じさせます。
ぱふぱふを体験する詳細な手順(会話と選択肢)
教会の屋根の上にいる女性に話しかけると、彼女は主人公(ローレシアの王子)に向かって、こう問いかけてきます。
「ねえ ぼうや。 ぱふぱふ しに きたの?」
この直球の誘いに対し、プレイヤーには「はい」と「いいえ」の選択肢が提示されます。 ここで「はい」を選ぶと、ぱふぱふを体験することができます。
『ドラクエ1』では20ゴールドが必要でしたが、『ドラクエ2』のぱふぱふは、なんと「無料」です。 港町で船を手に入れた勇者たちへの、ささやかな「はなむけ」なのかもしれませんね。
『ドラクエ2』の「ぱふぱふ」の効果とセリフの分岐
では、このルプガナのぱふぱふには、一体どのような「効果」があるのでしょうか。 無料で体験できるからには、何か特別な力があるのでは? と期待するプレイヤーも多いかもしれません。 その詳細と、隠されたセリフの分岐について、深く掘り下げていきます。

結論:ぱふぱふに特別な効果は無い
いきなり結論から申し上げてしまい恐縮ですが、『ドラクエ2』のぱふぱふには、残念ながら(あるいは、幸いにも)特別な効果は一切ありません。
ステータスが上がったり、HPやMPが回復したり、毒や呪いなどの状態異常が治ったりすることは、一切ないのです。 純粋に、特定の会話と演出が発生するのみ。 これぞまさしく、ドラクエにおける「ぱふぱふ」の原点であり、本質と言えるでしょう。
ステータス変化や回復効果の有無
後のシリーズ、例えば『ドラクエ8』では、ゼシカの「ぱふぱふ」が敵一体を「みりょう」状態にすることがあるなど、戦闘で役立つ効果を持つ場合もありました。 しかし、『ドラクエ2』の時代は、まだそうした実利的な意味合いは持たされていませんでした。
あくまでフレーバーテキスト、世界観を彩るジョークの一つとして存在しているのです。 宿屋に泊まる代わりにはなりませんので、HPが減っている場合は、ちゃんとお金を払って宿屋を利用しましょう。
『ドラクエ1』との比較(有料から無料へ)
前作『ドラクエ1』では、ラダトームの町でぱふぱふを体験するのに20ゴールドが必要でした。 当時の20ゴールドと言えば、序盤においては「どうのつるぎ」を買うための貴重な資金源の一部です。 それを支払ってまで体験するかどうか、プレイヤーは悩んだことでしょう。
それに対し、『ドラクエ2』では無料です。 これは、ゲームのスケールが大きくなり、ゴールドのインフレが起きたから、という側面もあるかもしれませんが、私はむしろ「ぱふぱふ」という概念が、開発者側(堀井雄二氏)の中で「お金を取るサービス」から「単なるお遊びの小ネタ」へとシフトした瞬間だったのではないかと分析しています。
選択肢「はい」を選んだ場合の演出
では、実際に「はい」を選ぶとどうなるのか。 女性は「あら うれしい。 じゃあ こっちへ おいで……。」 と誘ってきます。
そして、画面が暗転。 (HD-2D版では、ここで美しいライティングの演出が入るかもしれませんね)
暗転が明けると、主人公は満足げな(?)表情を浮かべ、女性がこう言います。 「うふふ……。 どう きもちよかった? また きてね。」
これだけです。 何が行われたのかは、プレイヤーの想像に委ねられます。 この「想像の余地」こそが、ドラクエの「ぱふぱふ」の醍醐味なのです。 リメイク版で変に生々しい描写が追加されることはまず無いでしょうし、この伝統的な「暗転」は守られるはずです。
選択肢「いいえ」を選んだ場合のセリフ分岐
このぱふぱふイベントの真骨頂は、実は「はい」を選んだ時ではなく、「いいえ」を選んだ時にあります。 しかも、パーティの状況によって、セリフが微妙に変化するという、非常に凝った作りになっているのです。
これは、当時のファミコンの容量(ROMカートリッジ)がカツカツだった時代において、わざわざフラグを立ててセリフを分岐させるだけの「こだわり」が、この小ネタに注がれていた証拠です。
ムーンブルクの王女が生存している場合
パーティにムーンブルクの王女がいて、かつ彼女が戦闘不能(死亡・棺桶)状態ではない場合。 つまり、元気にパーティの後ろをついてきている状況で「いいえ」を選ぶと、女性はこう言います。
「あら つれないわね。 もしかして うしろの おんなの こが こわいの?」
なんと、パーティメンバーである王女の存在を認識し、彼女に遠慮しているのではないか、と指摘してくるのです。 これには驚かされます。 『ドラクエ2』のNPCが、パーティ構成(特に王女の存在)に言及するセリフは、実は非常に珍しいのです。
ローレシアの王子が「いえ、そういうわけでは……」と慌てている姿が目に浮かぶようです。
ムーンブルクの王女が死亡(棺桶)状態の場合
では、もしムーンブルクの王女が戦闘などで力尽き、棺桶を引きずっている状態で「いいえ」を選ぶとどうなるのでしょうか。 (あるいは、王女を預かり所に預けている場合など、パーティに王女がいない状況も含む)
この場合、女性のセリフはこう変わります。
「あら つれないわね。 ……また きてね。」
王女への言及が、きれいさっぱり無くなるのです。 非常にシンプルなセリフに戻ります。
この分岐は、当時のプレイヤーたちの間で「細かい!」と話題になりました。 ただの小ネタかと思いきや、しっかりとパーティの状態(フラグ管理)をチェックしている。 この細部へのこだわりが、ドラクエを名作たらしめている所以の一つだと、私は常々感じています。
なぜセリフが分岐するのか? 開発の遊び心と当時の仕様考察
なぜ、このような分岐を用意したのでしょうか。 一つは、純粋な開発陣の「遊び心」でしょう。 気づく人は気づくだろう、というイタズラ心です。
もう一つは、当時のゲーム開発における「フラグ管理」のデモンストレーション的な意味合いもあったのかもしれません。 『ドラクエ2』は、3人パーティという複雑なシステム(当時のRPGとしては)を採用しました。 仲間がいるか、死んでいるか、呪われているか。 そうした状態を管理するプログラムが、ゲームの根幹にありました。
そのフラグ管理の仕組みを、ストーリーの本筋とは全く関係のない「ぱふぱふ」という小ネタに応用してみせる。 それは、開発チームの技術的な自信の表れだった可能性も考えられます。
王女だけでもぱふぱふは可能か?
ちなみに、情報ソース①にもありましたが、このぱふぱふイベントは、ローレシアの王子やサマルトリアの王子が死亡状態(棺桶)で、ムーンブルクの王女だけが生き残っている状態でも発生します。 (SFC版以降、先頭が王女になるため)
その場合、女性は王女に向かって「ぱふぱふしませんか?」と問いかけることになります。 女性が女性にぱふぱふを勧めるという、ある意味で非常にシュールな光景が展開されます。 もちろん、「はい」を選んでも結果は同じ(暗転して終了)です。
HD-2D版でも、このあたりの仕様は忠実に再現されることを期待したいですね。
歴代リメイク版での「ぱふぱふ」の扱いの変遷
『ドラクエ2』は、ファミコン版の登場以来、何度もリメイクされてきました。 そのたびに、グラフィックやシステムが洗練されてきましたが、「ぱふぱふ」の扱いはどう変わってきたのでしょうか。 HD-2D版を予想する上で、この変遷を知っておくことは非常に重要です。
| リメイク版 | 発売年 | プラットフォーム | ぱふぱふの主な仕様 |
|---|---|---|---|
| オリジナル | 1987年 | ファミコン (FC) | ルプガナ教会上。セリフ分岐あり。 |
| リメイク① | 1993年 | スーパーファミコン (SFC) | FC版の仕様をほぼ踏襲。グラフィック向上。 |
| リメイク② | 1999年 | ゲームボーイカラー (GBC) | 基本的にSFC版に準拠。 |
| リメイク③ | 2011年~ | スマートフォン (スマホ) | SFC版ベース。操作性やバランスが現代向けに。 |
| HD-2D版 | 2025年予定 | (各種現行機) | 詳細は未発表。スマホ版ベースの可能性大。 |
ファミコン(FC)版:原点
全ての原点です。 上記で解説した「ルプガナの教会上」「無料」「セリフ分岐」という基本仕様は、この時点で既に完成していました。 限られたドット絵とカタカナのみのテキストで、プレイヤーの想像力をかき立てる演出は、まさに圧巻でした。
スーパーファミコン(SFC)版:演出とセリフの確立
1993年に『ドラゴンクエストI・II』としてリメイクされたSFC版。 グラフィックが大幅に向上し、キャラクターが表情豊かになりました。 ぱふぱふの演出も、FC版の仕様(セリフ分岐含む)を忠実に、しかし美しいグラフィックで再現しました。
教会の屋根に登る階段が見やすくなるなど、ユーザビリティも向上しています。 多くのプレイヤーにとって、『ドラクエ2』のぱふぱふと言えば、このSFC版のイメージが強いかもしれません。
ゲームボーイカラー(GBC)版
1999年に発売されたGBC版も、基本的にはSFC版の移植であり、ぱふぱふの仕様に変更はありませんでした。 携帯機でいつでもどこでも「ぱふぱふ」が楽しめるようになった、とも言えますね。
スマートフォン(スマホ)版:現行の基準
現在、最も手軽にプレイできるのがスマホ版(iOS/Android)です。 これもSFC版をベースにしており、ぱふぱふのイベントも健在です。 セリフの分岐ももちろん再現されています。
操作性がタッチパネルに最適化されていますが、イベント内容そのものは変わっていません。
HD-2Dリメイク版での「ぱふぱふ」はどうなる?(予想)
そして、2025年発売予定のHD-2D版です。 これまでのリメイクの歴史を鑑みると、以下の点が予想されます。
グラフィックの進化による演出の期待
HD-2Dの真骨頂は、光と影、水の表現、そして空気感です。 ルプガナの港町がどれほど美しく描かれるのか。 夜の教会の上で、月明かりに照らされながら行われる「ぱふぱふ」は、ある種の幻想的な雰囲気すら纏うかもしれません。
「暗転」の演出も、ただ真っ暗になるのではなく、フェードアウトや特殊なエフェクトが加わる可能性もあります。 とはいえ、中身はあくまで「想像にお任せします」という、ドラクエらしいスタイルは崩さないでしょう。
内容(セリフや効果)の変更の可能性
セリフの分岐は、あまりにも有名かつ秀逸な小ネタであるため、ほぼ100%の確率で「踏襲される」と私は断言します。 これを削除する理由はどこにもありません。
また、HD-2D版で急に「ぱふぱふにHP回復効果が追加される」といった実利的な変更が加えられる可能性も低いでしょう。 それは『ドラクエ2』のぱふぱふの「味」を損なうことになりかねません。 あくまで、原作のフレーバーを尊重した、美しいリメイクになるはずです。
『ドラクエ2』の「ぱふぱふ」に関する深い考察
単なる小ネタとして片付けるのは簡単ですが、ゲーム評論家としては、もう少し深くこの「ぱふぱふ」について考察してみたいと思います。
なぜルプガナなのか? 港町の「癒やし」としての役割
ぱふぱふが配置された場所が「ルプガナ」であることには、明確な意図があったと私は考えています。 ルプガナは、前述の通り「船」を手に入れる場所です。 ここから、プレイヤーは「どこへでも行ける」という高揚感と同時に、「どこへ行けばいいんだ?」という途方もない不安(特にFC版ではノーヒントに近い)に直面します。
また、船を手に入れた直後に乗り出す海は、陸上とは比べ物にならないほど強力なモンスター(マンドリルやガーゴイルなど)が跋扈する危険な場所です。 そんな、緊張と緩和が入り混じる「船出の町」に、この「ぱふぱふ」という、緊張感を一気に緩ませるジョークが配置されている。
これは、プレイヤーの心情を巧みにコントロールする、計算されたレベルデザインの一環だったのではないでしょうか。 「これから大変な冒険が待ってるけど、まあ、たまにはこんな息抜きもいいじゃないか」という、開発者からのメッセージだったのかもしれません。
なぜ無料なのか? 『ドラクエ1』からの変化が示すもの
『ドラクエ1』のぱふぱふは、有料(20G)でした。 ラダトームの女性は、それを「商売」として提供していました。 しかし、『ドラクエ2』の女性は、教会の屋根の上というおよそ商売には向かない場所で、勇者たちを待っています。 そして、無料です。
これは、彼女が「商売」でやっているのではなく、ある種の「奉仕」あるいは「趣味」でやっている可能性を示唆しています。 (だからこそ、王女の目を気にする、という人間臭い反応が返ってくるのかもしれません)
『ドラクエ1』では、まだ世界観も手探りで、「大人のためのお遊び」としてゴールドを要求するリアルさがありました。 しかし『ドラクエ2』では、すでに「ドラクエ」という世界観が確立し、「ぱふぱふ」はファンサービス的な「お約束のネタ」へと昇華した。 その表れが「無料化」だったのではないかと、私は推察します。
プレイヤーの反応:当時と現代の「ぱふぱふ」への見方
発売当時(1987年)、この「ぱふぱふ」に、多くのプレイヤー(主に少年たち)は、ドキドキしたり、意味もわからず「はい」を押したりしていました。 セリフ分岐に気づいたプレイヤーは、友人たちに自慢げに話したことでしょう。
それから約40年。 現代のプレイヤーにとって、「ぱふぱふ」はもはや説明不要の「伝統芸能」です。 新作が出れば「今回のぱふぱふはどこだ?」と探すのがお決まりになりました。
HD-2D版で初めて『ドラクエ2』に触れる若い世代が、このルプガナのぱふぱふにどう反応するのか。 そして、王女のセリフ分岐に気づいた時、どんな感想を抱くのか。 それを見るのも、リメイク版の楽しみの一つですね。
『ドラクエ2』リメイクで気になる他の要素
『ドラクエ2』のリメイクとなれば、当然「ぱふぱふ」以外にも気になる点は山積みです。 特にペルソナ(読者)の皆さんが興味を持ちそうな、HD-2D版への期待と不安について、いくつかピックアップしておきましょう。
高難易度バランスの調整は?(ロンダルキアへの洞窟など)
やはり最大の焦点は、ゲームバランスです。 特に以下の点は、多くのプレイヤーが注目しています。
- ロンダルキアへの洞窟: あの理不尽な落とし穴と無限ループは緩和されるのか。
- 敵の強さ: ギガンテスやブリザード、アークデーモンといった凶悪なモンスターたちの強さ。
- ザラキの恐怖: 『ドラクエ2』は、とにかく敵が「ザラキ」を多用します。この即死呪文の嵐がどう調整されるのか。
- サマルトリアの王子の性能: SFC版以降で強化されたとはいえ、他の二人に比べると見劣りしがちなサマルトリアの王子の性能が、さらにテコ入れされるのか。
私としては、オリジナルの歯ごたえは残しつつも、理不尽な部分は現代的に遊びやすく調整されることを期待しています。
「ふっかつのじゅもん」の扱いはどうなる?
『ドラクエ2』と言えば、あの長い「ふっかつのじゅもん」も象徴的です。 SFC版やスマホ版では、もちろん現代的なセーブシステム(冒険の書)が採用されました。
HD-2D版も当然、オートセーブや教会でのセーブが基本となるでしょう。 しかし、HD-2D版『ドラクエ3』では、ファミコン版の「冒険の書」作成演出が再現されていました。 『ドラクエ2』でも、オマージュとして「ふっかつのじゅもん」を入力できる(あるいは、当時のじゅもんがコンバートできる)ような「遊び」が搭載されるかもしれません。
ルプガナ周辺の攻略(船入手後の自由度と危険度)
ぱふぱふの町・ルプガナで船を手に入れた後、プレイヤーは広大な海に漕ぎ出します。 ここからの自由度が『ドラクエ2』の魅力ですが、同時に危険度も跳ね上がります。
SFC版やスマホ版では、次に行くべき場所へのヒントが比較的丁寧に示されていました。 HD-2D版でも、その導線はしっかりと確保されるでしょう。 船を手に入れたら、まずは南の大陸(デルコンダル)や、世界の中心にある「紋章」の情報を集める旅が始まるはずです。 くれぐれも、いきなりロンダルキア(マップ北東の雪国)方面へ向かわないように注意が必要です。
他の小ネタ(ラゴス、福引、はかいのはやぶさ)
『ドラクエ2』には、ぱふぱふ以外にも印象的な小ネタがあります。
- ラゴス: 「すいもんのカギ」をなかなか渡してくれない、テパの町のラゴス。彼とのやり取りも楽しみです。
- 福引: アイテムを買うと貰える「ふくびきけん」。SFC版以降で追加されたこのシステムも健在でしょう。
- はかいのはやぶさ: 「はやぶさのけん」と「はかいのつるぎ」を組み合わせる裏技(バグ)は、リメイク版では修正されていますが、何らかの形で「最強の剣」は用意されるはずです。
『ドラクエ1』リメイクの「ぱふぱふ」はどうなる?
今回のHD-2D版は『I&II』セットでの発売です。 『ドラクエ2』のぱふぱふを語るなら、『ドラクエ1』の「元祖ぱふぱふ」にも触れないわけにはいきません。
元祖・ラダトームのぱふぱふ
『ドラクエ1』のぱふぱふは、スタート地点であるラダトームの町の宿屋の裏(SFC版などでは場所が少し変わりますが)にあります。 こちらは前述の通り、有料(20G)です。
「はい」を選ぶと、やはり暗転し、 「ああ なんて きもちの いい あさなんだ! ……じゃなくて ぱふぱふ しませんか?」 と、テキストだけで状況を表現する、秀逸な演出が待っています。 (このセリフはリメイク版で変更されている場合もありますが、「きもちのいいあさ」のくだりは有名ですね)
HD-2D版での再現度予想
『ドラクエ1』は、主人公一人旅のゲームです。 そのため、『ドラクエ2』のようなパーティメンバーによるセリフ分岐はありません。 非常にシンプルな構成です。
HD-2D版でも、この元祖ぱふぱふは忠実に再現されるでしょう。 有料である点、そして「きもちのいい あさ」のオマージュがどう表現されるのか。 『ドラクエ2』のぱふぱふと見比べてみるのも、リメイク版ならではの楽しみ方と言えますね。
まとめ
今回は、HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』、特に『ドラクエ2』の「ぱふぱふ」について、その場所、手順、効果、そしてセリフの分岐まで、徹底的に解説しました。
結論として、『ドラクエ2』のぱふぱふは以下の点が重要です。
- 場所: ルプガナの町の教会の屋根の上。
- 手順: 女性に話しかけ、「はい」を選ぶ。
- 費用: 無料。
- 効果: 特になし。会話と演出のみ。
- 特筆点: 「いいえ」を選んだ際、ムーンブルクの王女の生死(パーティにいるか)によってセリフが分岐する。
2025年の発売が待れるHD-2D版リメイク。 美しいグラフィックで蘇るロトの世界で、あの懐かしい「ぱふぱふ」がどう再現されるのか。 そして、王女のセリフ分岐は健在なのか。 高難易度バトルの合間に、ルプガナの教会の上で一息つくのが、今から楽しみでなりません。
ゲーム評論家・桐谷シンジがお届けしました。 また次回のレビューでお会いしましょう。