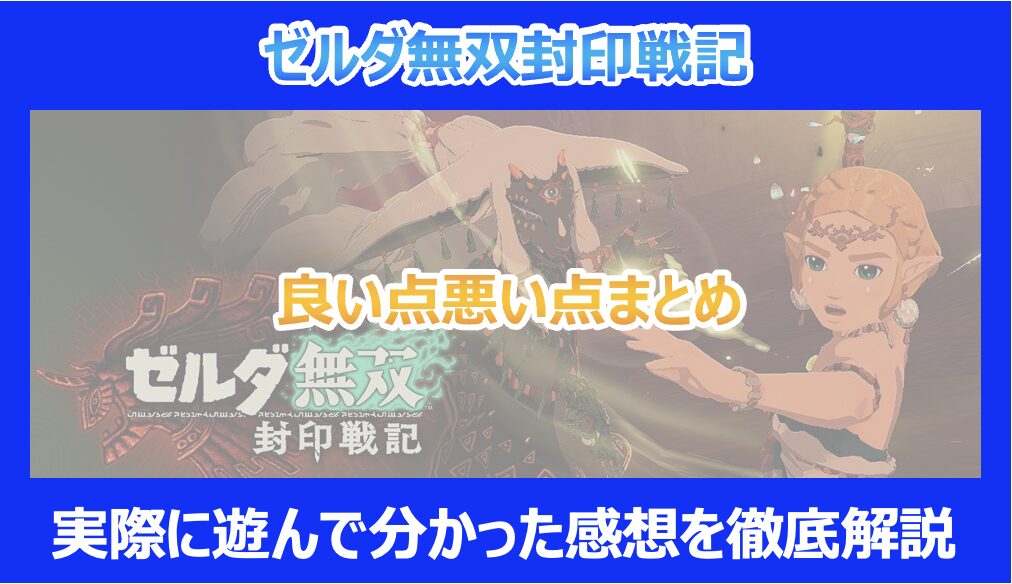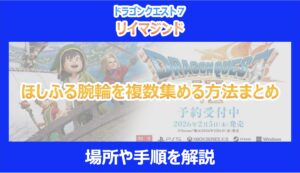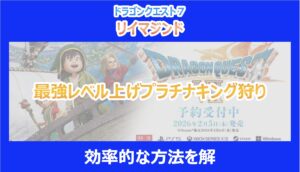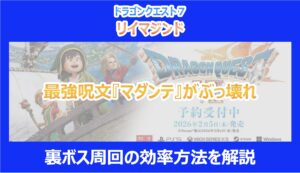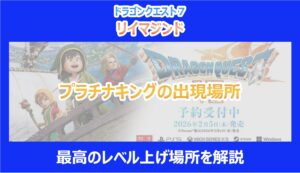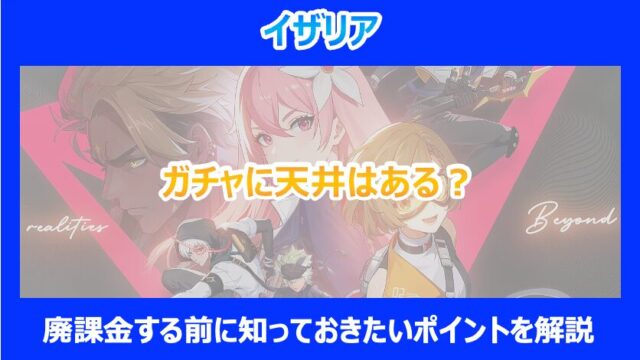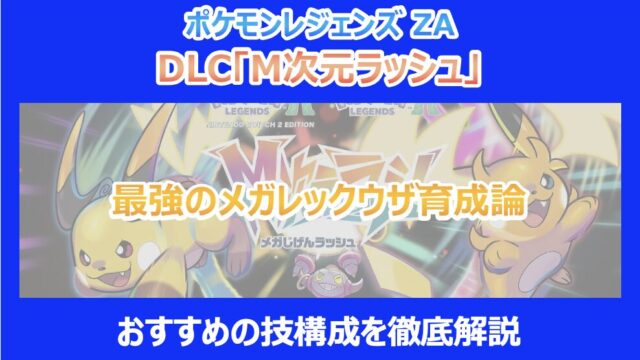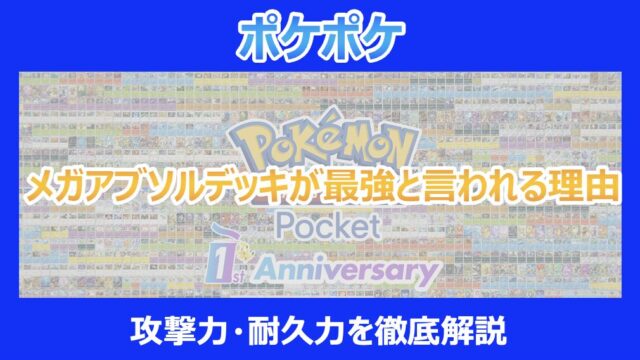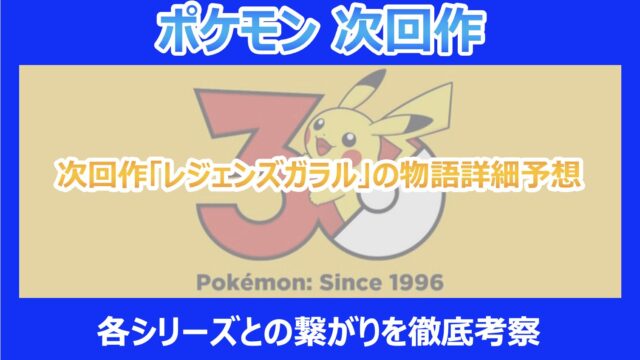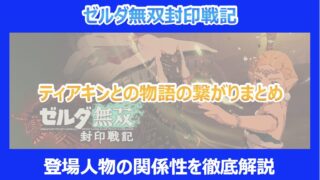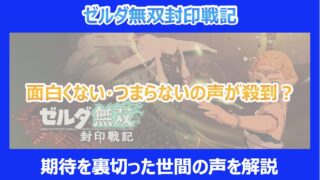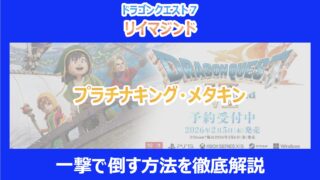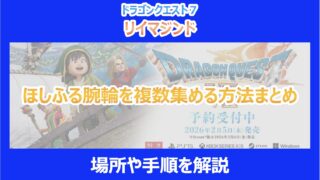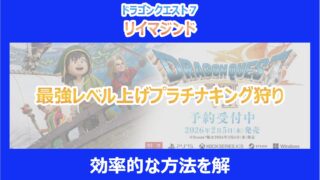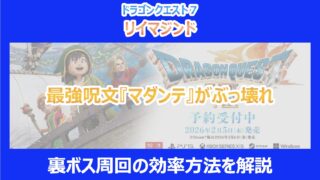編集デスク ゲーム攻略ライターの桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年11月6日についに発売された待望の新作『ゼルダ無双 封印戦記』について、実際のところどうなのか、その評価や感想が気になっていると思います。

前作『ゼルダ無双 厄災の黙示録』(以下、『厄災の黙示録』)からどう進化したのか、そして何より『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』(以下、『ティアキン』)で描かれたあの「封印戦争」がどのように描かれているのか、買う価値があるのかどうか、徹底的に知りたいですよね。
私自身、発売日から睡眠時間を削ってやり込んでいます。
この記事を読み終える頃には、『ゼルダ無双 封印戦記』を買うべきか、その疑問が解決しているはずです。
- 『厄災の黙示録』の欠点を徹底改善した正統進化
- 『ティアキン』で語られた「封印戦争」の重厚な物語
- ゾナウギアとシンクストライクによる爽快な新バトル
- シリーズファンなら「買い」の一択と言える完成度
それでは解説していきます。
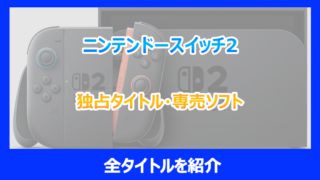
『ゼルダ無双 封印戦記』とは? ティアキンの「過去」を描く物語
まずは本作『ゼルダ無双 封印戦記』がどのようなゲームなのか、基本情報をおさらいしておきましょう。
本作は、任天堂の『ゼルダの伝説』シリーズの世界観をベースに、コーエーテクモゲームスの「無双」シリーズならではの「一騎当千」の爽快なアクションを楽しめる『ゼルダ無双』シリーズの最新作です。

『厄災の黙示録』が『ブレス オブ ザ ワイルド』の100年前を描いた作品であったのに対し、本作は『ティアキン』でその存在が語られた、ハイラル建国時代の「封印戦争」を真正面から描いた作品となっています。
封印戦争を徹底的に掘り下げるストーリー
『ティアキン』をプレイした方なら、ハイラル各地に残された「竜の涙」を通じて、建国時代のゼルダ姫の記憶を追体験したことでしょう。
ラウルとソニアの出会い、ガノンドロフの台頭、そしてソニアの悲劇と魔王の誕生…。
『封印戦記』は、まさにあの時代、あの戦争を舞台にしています。
物語は、『ティアキン』の冒頭、ゼルダ姫が過去へと飛ばされたあのシーンから始まります。 プレイヤーはまず建国時代のゼルダ姫を操作し、初代ハイラル王ラウル、そしてソニア王妃と出会うことになります。
『ティアキン』では断片的にしか描かれなかった「封印戦争」の全貌が、本作では濃密なストーリーとして展開されます。 なぜガノンドロフは魔王となったのか、ラウルたちはどう戦ったのか、そしてミネルや他の種族はどう関わったのか。 そのすべてが、圧倒的な物量と美麗なムービーシーンで描かれます。
序盤からソニアがガノンドロフによって殺害され、秘石を奪われるという衝撃的な展開が待ち受けており、『ティアキン』の歴史をなぞる重厚な物語であることがわかります。
『厄災の黙示録』との違いは「IF」ではない歴史の追体験
前作『厄災の黙示録』は、「もしも未来を知るガーディアン(テラコ)が過去に介入したら」という「IFストーリー」でした。 それ故に、原作(ブレス オブ ザ ワイルド)では救えなかった英傑たちが生存するという、希望のある展開が描かれたのが特徴です。

しかし、『封印戦記』は違います。 今のところ、本作は『ティアキン』で確定した歴史を「追体験」する物語として進んでいます。 つまり、待ち受けるのは「IF」の希望ではなく、すでに結末がわかっている「悲劇」です。
この「歴史の追体験」という側面が、本作のストーリーに『厄災の黙示録』とは比較にならないほどの重厚さと切なさをもたらしています。 覚悟してプレイする必要がありますが、だからこそ『ティアキン』の物語をより深く理解できる、ファンにとってはたまらない内容となっています。
魅力的な新キャラクターたちと操作可能な英傑
本作では、ラウルやソニア、ミネルといった『ティアキン』の過去の時代の重要人物たちが、当然のようにプレイアブルキャラクターとして登場します。
光の力を操るラウル、時の力を操るソニア、そしてゴーレムを駆使するミネル。 彼らを自由に操作し、無数の魔物を薙ぎ倒せるのは本作ならではの大きな魅力です。
さらに、配信の序盤で確認できただけでも、
- カラモ: コログのような見た目だが、属性の実などを使うトリッキーな戦闘スタイル。
- 特務(とくむ): 「謎のおっさん」として登場。ラウル軍の兵士? 溜め攻撃主体のパワーファイター。
- ゴーレムリンク: ティアキンの「いにしえの勇者の魂」に似た謎のゴーレム。ゾナウギアを駆使し、飛行形態でのシューティングまでこなす。
- アルディ: ゲルド族の戦士。ガノンドロフの部下として登場。
といった新キャラクターたちが続々と登場し、操作可能になります。 『ティアキン』で謎に包まれていた人物たちが、どのようなアクションで戦うのか。 それを自分で確かめられるだけでも、本作をプレイする価値は十分にあります。
【結論】『封印戦記』は買うべきか? 実際にやり込んだ感想
さて、結論から申し上げましょう。 『ゼルダ無双 封印戦記』は「買い」です。 特に、以下のどちらかに当てはまる人には、強く購入をおすすめします。
『厄災の黙示録』が好きだった人は「絶対買い」
前作『厄災の黙示録』を楽しんだプレイヤーは、本作を「絶対買うべき」です。 なぜなら、『封印戦記』は『厄災の黙示録』の正統進化であり、前作でプレイヤーが感じていたであろう「不満点」をことごとく潰してきたからです。

詳しい理由は後述しますが、特に「ロード時間の長さ」と「フレームレートの不安定さ」という、前作の二大欠点が見事に改善されています。 あの爽快なアクションはそのままに、快適さだけが向上しているのです。 これだけでも『厄災』ファンが買わない理由はありません。
『ティアキン』のストーリーに惹かれた人も「買い」
『ティアキン』をプレイし、あの壮大な物語、特に過去の「封印戦争」のドラマに心を揺さぶられた人も「買うべき」です。

『ティアキン』では竜の涙(ムービー)でしか見られなかったラウル、ソニア、ガノンドロフたちの激動の時代を、今度は自分自身が「無双アクション」という形で体験できます。
「もし自分がラウルだったら、ソニアだったら、どう戦ったか」
そんな想像を膨らませたファンにとって、本作はその答えをくれる最高のファンアイテムと言えるでしょう。 悲劇的な結末を知っているからこそ、一戦一戦に重みを感じられるはずです。
アクションが苦手な人でも楽しめるか?
「無双」シリーズと聞くと、複雑なコマンドや激しいアクションを想像して尻込みしてしまうかもしれません。 ご安心ください。
本作にも、前作同様に「イージー」や「ノーマル」といった難易度設定が用意されています。 イージーモードであれば、ボタンを連打しているだけでも十分に敵を倒せる爽快感を味わえます。
また、ストーリーやムービーのクオリティが非常に高いため、アクションはそこそこに、主に『ティアキン』の過去の物語を深く知るためにプレイするという楽しみ方も十分に「あり」です。
実際に遊んで分かった『封印戦記』の良い点(メリット)
ここからは、私が実際に数時間ぶっ通しでプレイして感じた『封印戦記』の具体的な「良い点(メリット)」を、前作『厄災の黙示録』との比較を交えながら徹底的に解説します。
良い点①:ロード時間がほぼゼロ! 驚異の快適性
前作『厄災の黙示録』をプレイした誰もが感じた最大の不満点。 それは「ロード時間の長さ」でした。
ミッション選択から戦闘開始まで、時には1分近く待たされることもあり、これがテンポを著しく阻害していました。 特に素材集めや武器厳選のために同じミッションを「周回」するのが基本となる無双ゲームにおいて、この長いロードは致命的とも言えました。
しかし、『封印戦記』では、この欠点が完全に解消されています。 ミッションを選択してから戦闘が始まるまで、わずか数秒。 ムービーシーンへの移行も、マップの読み込みも、ほぼシームレスです。
本作の容量が44GBと、前作(約15GB)の約3倍になっていることからも、おそらくは新型のSwitch(通称Switch 2)の性能を前提に最適化されているのでしょう。 (※編集部注:本レビューは新型Switchを使用してプレイしています)
ストレスフリーで戦闘を繰り返せる。 これこそが、本作における最大の「進化」であり、最高の「良い点」だと断言します。
良い点②:進化したグラフィックと安定したフレームレート
ロード時間と並んで『厄災の黙示録』で指摘されていたのが、フレームレート(画面の滑らかさ)の不安定さでした。 特に敵が大量に出現したり、必殺技を使ったりすると、処理落ちで画面がカクカクになることが頻繁にありました。
『封印戦記』では、この点も劇的に改善されています。 無数の敵が画面を埋め尽くし、派手なエフェクトが飛び交う中でも、フレームレートは非常に安定しており、滑らかなアクションを常に楽しむことができます。
グラフィックも『ティアキン』のトゥーンシェーディング(アニメ調)のスタイルを踏襲しつつ、さらに高解像度かつ美しくなっています。 特に光の表現や影の描写は目を見張るものがあり、建国時代のハイラルの美しい風景(始まりの台地など)や、地底の不気味な雰囲気が見事に再現されています。
快適なロードと安定した動作。 ゲームプレイの「土台」が強固になったことで、アクションへの没入感が格段に増しています。
良い点③:「ゾナウギア」と「シンクストライク」によるバトルシステムの革新
『厄災の黙示録』の戦闘システムは、ウィークポイントを削ってスマッシュ、という流れが基本で、シーカーストーン(ビタロックやリモコンバクダン)がアクセントとなっていました。
『封印戦記』もその基本は踏襲していますが、戦闘の戦略性を大きく変える2つの新システムが導入されています。
1. ゾナウギア(アイテム)
『ティアキン』でお馴染みの「ゾナウギア」が、戦闘中に使用できるアイテムとして登場します。 序盤で確認できただけでも、
- 火龍の頭: 前方に炎を放射し、敵を燃やす。
- タイマー爆弾: 設置型の爆弾。
- ロケット: 高速移動。
- 氷龍の頭: 敵を凍結させる。
- 雷龍の頭: 敵を感電させる。
などがあり、これらを十字キーで切り替えて瞬時に使用できます。
『厄災』のシーカーストーン技がクールタイム制だったのに対し、こちらは「スペアバッテリー」を消費する仕組みのようです。 「敵を凍らせてタイマー爆弾で大ダメージ」といった、『ティアキン』のようなコンボも可能で、アクションの幅が大きく広がりました。
2. シンクストライク(合体技)
本作の目玉システムが「シンクストライク」です。 味方キャラクターの近くで戦うと「シンクゲージ」が溜まり、最大になると強力な合体技を放つことができます。
このシンクストライクは、組み合わせるキャラクターによって効果が全く異なります。
例えば、配信で確認できた
- ゼルダ&ソニア: ゼルダが強化され、一定時間、強力な固有技(時の力?)を連発できるようになる。
- ラウル&キーニョ(ハイリア隊長): 画面全体に雷の流星群を降らせる、超広範囲の殲滅技。
- ミネル&ゼルダ: ミネルのゴーレムにゼルダが乗り込み、ボコボコに殴りつける。
など、ド派手な演出と共に戦局を一変させる力を持っています。 どのキャラクターをパートナーとして連れていくか、どの組み合わせのシンクストライクを狙うか、という戦略性が生まれました。 序盤で解放される「ゼルダ&ソニア」の組み合わせは、固有技の回転率が異常で、ボスすら瞬時に溶かすほどのチート性能を誇ります。 まずはこれを試してみてください。
良い点④:奥深くなった武器強化と育成システム
『厄災の黙示録』では、武器に武器を合成してレベルを上げ、刻印を付け替えるシステムでした。 これはこれで奥深かったのですが、大量の武器を管理する必要があり、やや煩雑な面もありました。
『封印戦記』では武器強化システムが一新されています。 まず、キャラクターごとに使用できる武器カテゴリは固定(あるいは非常に少ない)ようです。 例えばゼルダは「光の剣」、ラウルは「槍」といった具合です。
強化は、「ゾナニウム鉱」などの専用素材とルピーを消費して行います。 そして、『ティアキン』の「武器合成(スクラビルド)」のように、素材(ゾナニウム鉱など)に付与されている「刻印(通常攻撃ダメージアップなど)」を武器に引き継ぐことができるのです。
これにより、不要な武器を大量にストックする必要がなくなり、お気に入りの一本をじっくりと育て上げていく楽しみに集中できるようになりました。 UIも整理され、非常に分かりやすくなっています。
良い点⑤:シューティングも? 多彩なゲームプレイ
『厄災の黙示録』では、神獣(ヴァ・ナボリスなど)を操作する巨大バトルがありましたが、操作感が独特で賛否が分かれる部分でもありました。
『封印戦記』では、序盤で「ゴーレムリンク」に乗り込み、空島を舞台に戦う「3Dシューティングステージ」が登場しました。 これが『スターフォックス』のような本格的な作りで、非常に驚かされました。
大量のキースを撃ち落とし、障害物を破壊し、最後はグリオークと空中戦を繰り広げる。 通常の無双アクションとは全く異なるゲームプレイが、ストーリーの良いアクセントになっています。 今後もこうした特殊なバトルステージが用意されていることに期待が持てます。
良い点⑥:BGMやSE(効果音)の圧倒的なクオリティ
これは『厄災の黙示録』でも素晴らしかった点ですが、本作も健在、いや、むしろパワーアップしています。
『ティアキン』や『ブレス オブ ザ ワイルド』の名曲たち(地底のBGMやメインテーマなど)が、無双らしい激しいロック調や壮大なオーケストラ調にアレンジされており、戦闘を大いに盛り上げます。 特にモルドラジーク戦のBGMは必聴です。
また、特筆すべきはSE(効果音)の気持ちよさ。 敵を殴る「パスパス」「バシッ」という音が非常に小気味よく調整されており、ボタンを連打しているだけで脳汁が出るような爽快感を演出しています。 この「殴っている感触の良さ」は、無双ゲームにおいて最も重要な要素の一つであり、『封印戦記』はそこを見事にクリアしています。
覚悟すべき『封印戦記』の悪い点・気になる点(デメリット)
ここまで良い点を中心にレビューしてきましたが、もちろん気になる点、人によっては「悪い点」と感じるであろう部分もあります。 購入してから後悔しないよう、以下の点も把握しておいてください。
悪い点①:ストーリーが重厚(人によっては辛い展開)
これは良い点の裏返しでもあります。 前述の通り、本作は『厄災の黙示録』のような「IF」のハッピーエンドではなく、『ティアキン』の歴史をなぞる「悲劇」です。
序盤から、ソニアがガノンドロフに殺害され、目の前で魔王が誕生します。 『ティアキン』の竜の涙で見たあの絶望的なシーンを、より鮮明に、より詳細な描写で追体験することになります。
ラウルの悲痛な叫び、ゼルダの後悔。 こうした重く、辛い展開が苦手な人にとっては、プレイするのがしんどくなる可能性があります。 希望のある明るいストーリーを求めている場合は、『厄災の黙示録』の方が向いているかもしれません。 (ただし、ゴーレムリンクやカラモといった新キャラクターたちが、この重い物語にどう絡んでくるのか、そこに新たな「if」が生まれる可能性もゼロではありませんが…)
悪い点②:ラッシュの難易度が上昇?
『厄災の黙示録』では、敵の攻撃に合わせて回避(ジャスト回避)をすると「ラッシュ」が発動し、一方的に攻撃できる爽快なシステムがありました。
本作にもラッシュは健在ですが、プレイした感触として、『厄災』よりもタイミングがシビアになっているように感じます。 (単に私が下手になっただけかもしれませんが…)
『厄災』ではラッシュ主体でゴリ押しできていた場面でも、『封印戦記』では敵の攻撃パターンをしっかり見極めないと、手痛い反撃をもらうことが増えました。 アクションゲームとしての歯ごたえは増していますが、ライトユーザーにとっては少し難しく感じられるかもしれません。
悪い点③:育成や素材集めの「無双らしさ」は健在
これも「無双」シリーズの宿命とも言えます。 ロード時間が短縮されたとはいえ、キャラクターの育成、武器の強化、ハイラルチャレンジ(素材納品ミッション)のクリアのためには、何度も同じミッションを周回して素材を集める必要があります。
「コログの実」も前作同様に健在で、マップの隅々まで探索(あるいは周回)して集めることになります。
こうしたコツコツとした「作業」要素が苦手な人にとっては、中盤以降、面倒に感じてしまう可能性があります。 「ストーリーだけ楽しみたい」という人には少し冗長に映るかもしれません。
序盤の攻略と知っておきたい豆知識
最後に、これから『封印戦記』を始める方に向けて、序盤を効率よく進めるための豆知識をいくつかご紹介します。
まずは「野営地」の経験値アップを解放
ストーリーを進めると、「野営地」というシステムが解放されます。 これは、ミッション開始前に素材を投入することで、「経験値アップ」「移動速度アップ」「必殺技ゲージ増加」などのバフ(支援効果)を得られるというものです。
特に「経験値アップ」は非常に重要です。 複数のキャラクターを並行して育てる必要がある本作において、獲得経験値が30%アップする効果は絶大です。 まずはこの野営地を解放し、戦闘に出る前は必ず経験値アップのバフをかけるクセをつけましょう。
強力な「シンクストライク」の組み合わせ
前述の通り、「シンクストライク」は本作の鍵を握るシステムです。 序盤で特におすすめなのは、以下の組み合わせです。
| キャラクターA | キャラクターB | シンクストライクの効果 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ゼルダ | ソニア | ゼルダが強化状態になり、固有技(時の力)を短時間で連発可能になる。 | SSランク(壊れ)。ボスのウィークポイントを一瞬で削り切る火力が出せる。 |
| ラウル | キーニョ | 広範囲に雷の流星群を降らせる。 | Aランク。殲滅力が高く、拠点制圧に非常に便利。 |
| ゴーレムリンク | カラモ | カラモがゴーレムに乗り、全属性の実をばら撒きながら突進する。 | Bランク。派手で楽しいが、威力はそこそこ。 |
まずはゼルダとソニアを組ませて、その圧倒的な火力を体験してみてください。
コログの実は今作も健在
お馴染みのコログの実(「やっはー!」)は、本作でもマップの各地に隠されています。 『厄災の黙示録』と同様に、集めることで武器の所持枠が増える…と思いきや、本作は武器システムが違うため、別の恩恵(おそらくハイラルチャレンジの納品アイテム)があるものと予想されます。
怪しい風車や、不自然な岩など、見かけたらとりあえず攻撃してみることをおすすめします。 序盤のステージだけでも、かなりの数が隠されていました。
まとめ
『ゼルダ無双 封印戦記』は、『厄災の黙示録』の正統進化であり、『ティアキン』の物語を補完する最高のファンアイテムです。
前作の最大の欠点であったロード時間とフレームレートを完璧に克服し、ゾナウギアやシンクストライクといった新システムによって、戦闘の爽快感と戦略性はさらに高まっています。
『ティアキン』で描かれた「封印戦争」という重厚で悲劇的な物語を、「無双」というアクションゲームで追体験する。 この唯一無二の体験は、ゼルダファン、無双ファン双方にとって、間違いなく「買い」と言えるものです。
確かにストーリーは重く、無双ならではの周回要素もあります。 しかし、それを補って余りあるほどの快適さ、爽快感、そして物語への没入感が本作にはあります。
2025年を代表する一本になるであろうこの傑作を、ぜひその手で体験してみてください。