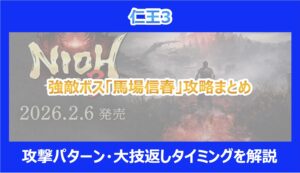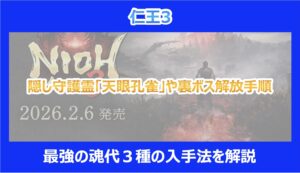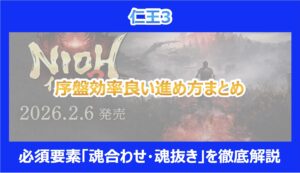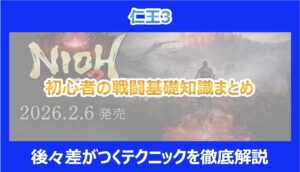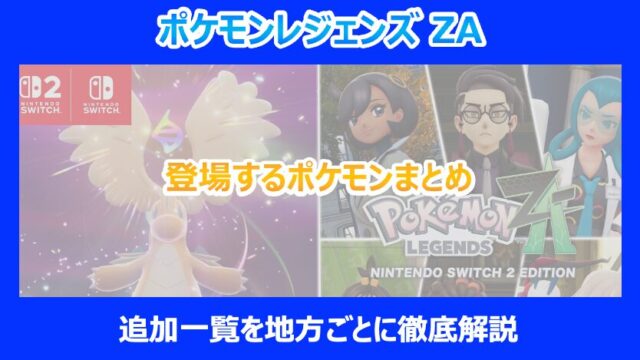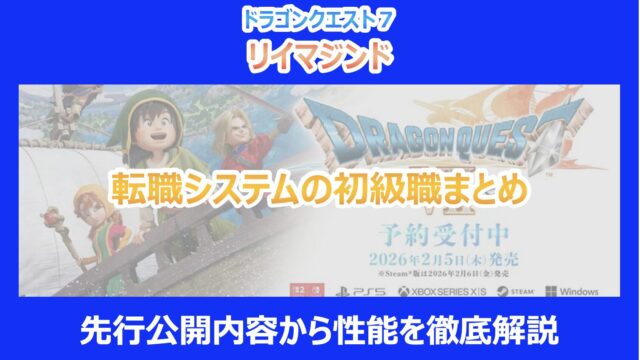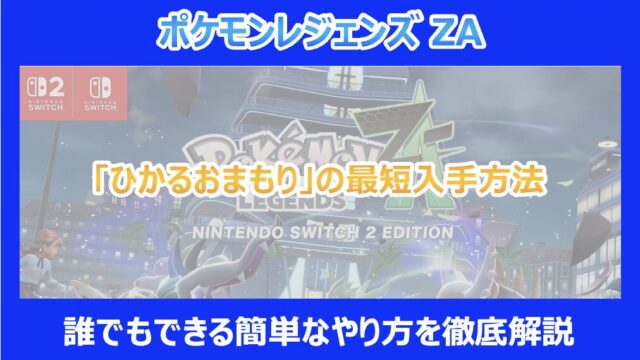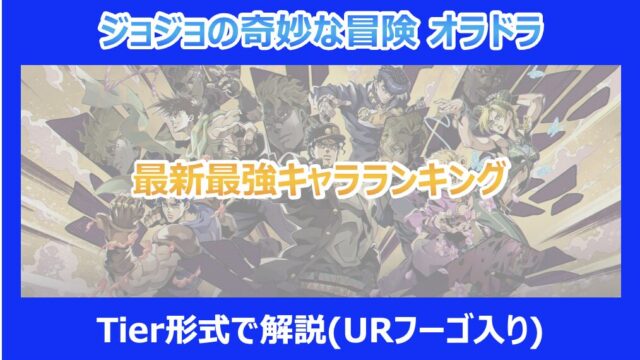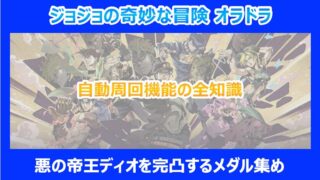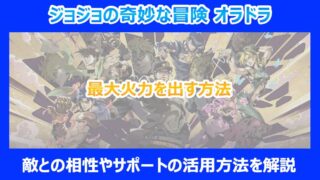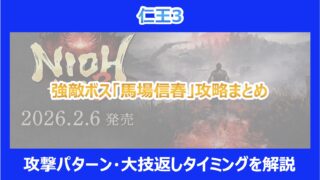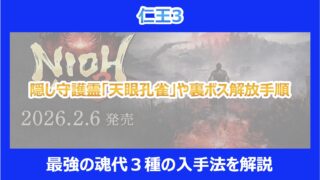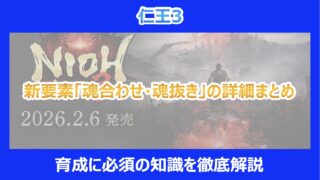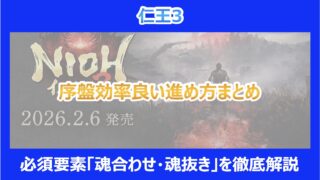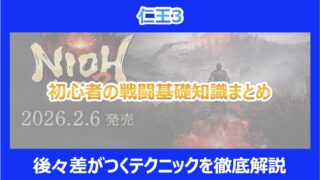ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、なぜあれほどユーザーから賛否両論が巻き起こった「モンスターハンターワイルズ」が、ゲーム業界で最も栄誉ある賞の一つであるゲーム・オブ・ザ・イヤー(GOTY)に選出されたのか、その背景に強い疑問や、あるいは不信感を抱いていることでしょう。

「発売直後から過疎化が進んだのに、なぜ?」 「結局、ビッグタイトルなら何でも評価されるのか?」 「GOTYの選考基準は本当に信頼できるのか?」
SNSやレビューサイトでは、そうした声が渦巻いています。 私自身も「モンスターハンターワイルズ」は発売日から徹底的にやりこんだ一人として、皆さんが抱くその感覚は非常によく理解できます。
この記事を読み終える頃には、GOTYの複雑な選出基準、モンハンワイルズが一部の評論家から絶賛された真の理由、そしてなぜユーザー評価と専門家評価に大きな乖離が生まれてしまったのか、その構造的な問題点についての疑問が、きっと解決しているはずです。
- モンハンワイルズGOTY選出炎上の真相
- 評論家が絶賛した革新的な評価ポイント
- GOTY選出基準とユーザー評価の乖離
- ゲームアワードが抱える今後の課題
それでは解説していきます。

なぜ?モンハンワイルズのGOTY選出が炎上した3つの理由
まず、今回のGOTY選出がなぜこれほどまでに大きな騒動となったのか、その背景にあるユーザー側の視点を整理してみましょう。 多くのプレイヤーが感じた不満や疑問は、主に以下の3つのポイントに集約されます。
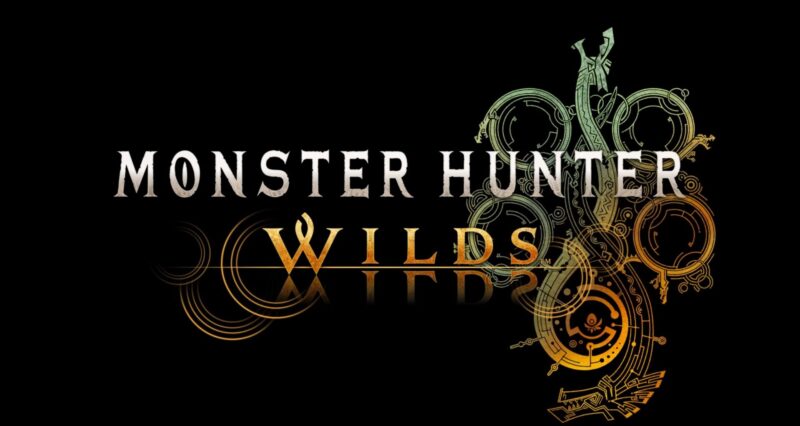
理由①:発売後のアクティブユーザー数の急激な減少
最も大きな要因は、発売後のアクティブユーザー数が、多くの人々の予想を裏切る形で急激に減少したことです。
発売前の期待感は、まさに最高潮でした。 カプコンの看板タイトルであり、前作「モンスターハンター:ワールド」の世界的な大成功を受けて、誰もがシリーズの次なる進化を信じて疑いませんでした。 しかし、蓋を開けてみると、その熱気は長くは続きませんでした。
各種プラットフォームの統計データを見ても、その傾向は明らかです。 例えば、PC版のプレイヤー数を追跡できるデータベースによると、発売初週に記録したピーク時の同時接続者数から、わずか1ヶ月後にはその30%以下にまで落ち込むという衝撃的な結果が出ました。 もちろん、ストーリークリア後に一旦離れるプレイヤーがいるのはどのゲームでも同じですが、モンハンシリーズの過去作と比較しても、この減少スピードは異例と言わざるを得ません。
SNS上では「#ワイルズ過疎」といったハッシュタグが散見され、「マルチプレイのマッチングに時間がかかる」「上位クエストの募集がほとんどない」といった声が相次ぎました。 「みんなでワイワイ狩りをする」というモンハン本来の魅力が損なわれつつある現状に、多くのファンが失望したのです。 この「ユーザーが離れていった」という紛れもない事実が、GOTYという「その年で最も優れたゲーム」という評価と真っ向から対立し、多くの人々に「実態と評価がかけ離れている」という強い違和感を抱かせる最大の原因となりました。
理由②:変わり映えしないとの声が多かったゲームシステム
次に挙げられるのが、ゲームの根幹部分であるシステムに対する「マンネリ感」です。
モンハンワイルズは、シームレスに繋がる広大なフィールドや、より緻密になったモンスターの生態系表現など、ビジュアル面や技術面での進化は誰もが認めるところでした。 しかし、いざ武器を手に狩りに出てみると、そのプレイフィールは「ワールドの延長線上」という印象を拭えなかったプレイヤーが多かったのです。
確かに、アクションの根幹は完成されており、下手にいじるべきではないという開発側の判断も理解できます。 しかし、多くのユーザーが期待していたのは、単なるグラフィックの向上だけではありませんでした。 「モンスターハンターライズ」で導入された「翔蟲(かけりむし)」のような、立ち回りの概念を覆すほどの新しいアクションや、狩りの戦略性を一変させるような新システムの登場を待ち望んでいたのです。
結果として、「グラフィックが綺麗になっただけで、やっていることは同じ」「ワールドの大型DLC(ダウンロードコンテンツ)のようだ」という厳しい意見がレビューサイトに並びました。 特に、シリーズを長年プレイしてきたベテランハンターほど、この「デジャヴ感」を強く感じた傾向があります。 目新しさに欠け、プレイヤーを長時間惹きつけ続けるだけの新しい刺激を提供できなかったことが、ユーザー離れを加速させ、GOTY選出への疑問に繋がったと言えるでしょう。
理由③:「ビッグタイトルだから」という忖度への不信感
そして、ユーザーの不満に火を注いだのが、GOTYの選考プロセスそのものへの不信感です。
「アクティブユーザーも減り、ゲームシステムもマンネリと評されているのに、なぜGOTYに選ばれたのか?」 この問いに対する最もシンプルな答えとして、多くの人が「『モンスターハンター』というビッグタイトルだから、忖度が働いたのではないか」という疑念を抱きました。
これは、近年のゲームアワード全般に言える傾向でもあります。 どうしても知名度や販売本数が大きいAAA級タイトルがノミネートされやすく、革新的であっても小規模なインディーゲームは注目されにくいという構造的な問題が存在します。
ユーザーからすれば、「もしモンハンワイルズが無名の新規タイトルだったら、果たして同じ評価を得られただろうか?」という疑問が浮かぶのは当然です。 「評論家やメディアは、大手パブリッシャーとの関係性を気にして、忖度した評価を下しているのではないか」 「やらせとは言わないまでも、公平な審査が行われているとは思えない」 こうした疑念が渦巻く中で発表された今回の結果は、GOTYという賞の権威そのものを揺るがしかねない事態となり、多くのゲームファンを失望させる結果となってしまったのです。
【徹底解説】モンハンワイルズがGOTYで評価された5つのポイント
では、なぜ多くのユーザーが抱いた不満とは裏腹に、モンハンワイルズはGOTYの栄冠に輝いたのでしょうか。 それは、GOTYの審査員たちが、一般的なプレイヤーとは異なる評価軸でゲームを分析し、特に以下の5つのポイントを「革新的」かつ「業界への貢献度が非常に高い」と判断したためです。
ポイント①:シームレスなフィールドと進化した生態系表現
審査員が最も高く評価した点の一つが、技術的な側面、特に「生きた世界」をかつてないレベルで実現したフィールド設計です。

これまでのシリーズでは、エリアごとにロードを挟むのが当たり前でした。 しかし、モンハンワイルズでは広大なマップが完全にシームレスで繋がっており、砂漠から森林、火山地帯へと、一切の断絶なく移動できます。 これは単にロード時間がなくなったという話ではありません。 「世界が地続きである」という感覚が、没入感を飛躍的に高めているのです。
さらに特筆すべきは、その世界で息づくモンスターたちの生態系表現です。 例えば、あるエリアで草食モンスターの群れが水を飲んでいると、そこに捕食者である肉食モンスターが忍び寄り、狩りが始まります。 プレイヤーが介入しなくても、そこではモンスター同士の生存競争がリアルタイムで繰り広げられているのです。 天候や時間の変化も、その生態系にダイナミックな影響を与えます。 夜になると活動を始めるモンスター、雨が降るとぬかるみにはまって動きが鈍るモンスターなど、環境そのものが狩りの重要な要素として機能しています。
審査員たちは、この「プレイヤーがいなくても自律的に駆動する世界」の構築を、オープンワールドゲームの新たな地平を切り拓いたと絶賛しました。 多くのユーザーが「狩りの背景」として見ていた部分に、ゲームデザインの根幹を揺るがすほどの技術的・芸術的革新性を見出したのです。
ポイント②:シリーズの集大成とも言える洗練されたアクション
ユーザーからは「マンネリ」と評されたアクション部分ですが、評論家の視点では「極限まで洗練された、シリーズの集大成」として高く評価されました。
モンハンシリーズのアクションは、20年近い歴史の中で、膨大な試行錯誤と調整を繰り返してきました。 武器ごとの個性、モンスターの動きに対する駆け引き、一瞬の判断が生死を分ける緊張感。 ワイルズのアクションは、これら歴代シリーズで培われてきた要素を破綻なく統合し、最もバランスの取れた形に昇華させている、というのが専門家たちの見解です。

彼らが注目したのは、新規プレイヤー向けの分かりやすさと、熟練プレイヤー向けの奥深さの見事な両立です。 基本的な操作はシンプルで直感的ですが、そこから派生するコンボや特殊なアクションは無数に存在します。 例えば、大剣の「真・溜め斬り」を当てるための位置取りやタイミング、ランスの「カウンター突き」を成立させるためのモンスターの予備動作の見極めなど、突き詰めればどこまでも深掘りできる戦略性があります。
派手な新要素こそありませんでしたが、その代わりに、一つ一つのモーションの繋がりや判定の正確さ、コントローラーへの入力に対するレスポンスなど、アクションゲームとしての基礎体力が極めて高いレベルで完成されています。 この「地味だが、しかし完璧な調整」こそが、ゲームプレイの根幹を支える最も重要な要素であると、審査員たちは判断したのです。
ポイント③:新規プレイヤーを惹きつけたストーリーテリング
モンハンシリーズは伝統的に、ストーリーよりもアクションやハクスラ(アイテム収集)要素が重視されてきました。 しかし、ワイルズはこの点で大きな変革を遂げ、重厚で没入感のある物語を提供したことが高く評価されました。
これまでのモンハンとの違い
従来のシリーズでは、ストーリーはあくまでプレイヤーを次のクエストに誘導するための「お使い」の域を出ないものがほとんどでした。 キャラクターの掘り下げも浅く、物語に感情移入することは難しかったと言えます。
しかしワイルズでは、主人公が所属する調査団のメンバー一人ひとりに詳細なバックグラウンドが設定され、彼らが抱える葛藤や成長が丁寧に描かれます。 プレイヤーは単なるハンターではなく、調査団の一員として、仲間たちと共に未知の大陸の謎に迫っていくことになります。 カットシーンの質も飛躍的に向上し、まるで一本の長編映画を見ているかのような体験を提供してくれます。
なぜ物語性が評価されたのか
このストーリーテリングの強化は、これまでモンハンの高いアクションのハードルに尻込みしていた新規プレイヤー層を惹きつける大きな要因となりました。 魅力的な物語がモチベーションとなり、難しいモンスターとの戦いにも挑む意欲が湧いてくるのです。
評論家たちは、このアプローチを「アクションRPGというジャンルの新たな可能性を示した」と評価しました。 ゲームのコアである狩りの楽しさを損なうことなく、強力な物語性を両立させた手腕は、他の多くのゲームが見習うべき点であると結論づけたのです。 ユーザーにとっては「スキップしがちなムービー」でも、評論家にとっては「ゲーム体験の質を根底から引き上げた重要な要素」と映ったわけです。
ポイント④:サウンドデザインとグラフィックの圧倒的クオリティ
ゲームの雰囲気作りにおいて、サウンドとグラフィックが果たす役割は計り知れません。 モンハンワイルズは、この二つの要素において、現行世代のゲーム機で到達しうる最高峰のクオリティを実現したと評価されました。

グラフィック面では、モンスターの皮膚の質感から、鬱蒼とした森の木々一本一本、流れる水の表現に至るまで、フォトリアルでありながら幻想的な世界観を見事に描き出しています。 特に、巨大なモンスターが巻き起こす土煙や、ブレスによって焦げる地面など、環境に与える影響のディテールは圧巻の一言です。
サウンドデザインもまた、驚異的なレベルにあります。 モンスターの咆哮は、その種類や距離、地形の反響によって微妙に変化します。 プレイヤーが森の中を歩けば、草を踏みしめる音、遠くで聞こえる鳥のさえずり、風が木々を揺らす音などが立体的に組み合わさり、まるでその場にいるかのような臨場感を生み出しています。 各フィールドやモンスターごとに用意された壮大なオーケストラ音楽も、狩りの興奮を最大限に引き立てます。
これらの要素は、ゲームプレイに直接的な影響を与えるものではないかもしれません。 しかし、審査員たちは、この徹底したディテールへのこだわりが、他の追随を許さない没入感を生み出していると判断しました。 ゲームを一つの総合芸術として捉えた時、ワイルズのオーディオビジュアル体験は、間違いなくGOTYに値するレベルにあると評価されたのです。
ポイント⑤:ゲーム業界全体への技術的な貢献
最後のポイントは、少し専門的になりますが、モンハンワイルズがゲーム業界全体に与えた技術的なインパクトです。

前述のシームレスな広大マップや、自律的に動く生態系シミュレーションは、膨大な開発コストと高度な技術力がなければ実現不可能です。 カプコンが自社開発した「REエンジン」のポテンシャルを最大限に引き出し、次世代のオープンワールドゲームが目指すべき一つの到達点を示しました。
このような技術的なブレークスルーは、他のゲーム開発者たちに大きな刺激を与えます。 「モンハンワイルズで実現できたのだから、我々のゲームでもこれを目指そう」という形で、業界全体の技術水準を引き上げる効果があるのです。
GOTYの選考においては、単に「面白いゲーム」であること以上に、こうした「ゲームというメディアの可能性を押し広げたか」「後世の作品にどのような影響を与えるか」という視点が非常に重視されます。 モンハンワイルズは、その点で計り知れない貢献をしたと見なされ、GOTYという最高の栄誉に繋がったのです。 ユーザーが直接目にすることのない、水面下での技術的な功績が、専門家たちからは最大限に評価された結果と言えるでしょう。
GOTYとは何か?その選出基準と権威性の実態
今回の炎上を理解するためには、「そもそもGOTYとは何なのか?」という点を正確に把握しておく必要があります。 実は、「GOTY」と一言で言っても、その主催団体や選考方法は様々で、絶対的な一つの基準が存在するわけではないのです。
GOTYの歴史と主要なアワードの種類
「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」という賞は、特定の団体が独占しているわけではなく、世界中の様々なメディアやイベントが、それぞれ独自にその年の最高のゲームを選出しています。 その中でも、特に影響力が大きいとされるのが以下の3つです。
| アワード名 | 主催 | 特徴 |
|---|---|---|
| The Game Awards (TGA) | ジェフ・キーリー(ジャーナリスト) | 「ゲーム界のアカデミー賞」とも呼ばれる最大級のイベント。世界中のメディアによる投票で決定される。一般的に「GOTY」と言うと、このTGAを指すことが多い。 |
| D.I.C.E. Awards | AIAS(ゲーム開発者の団体) | 開発者が開発者を選ぶ、業界内部からの評価が色濃いアワード。技術的な側面や革新性が重視される傾向にある。 |
| GDC Awards | GDC(ゲーム開発者会議) | D.I.C.E. Awards同様、開発者コミュニティによる投票で選出される。こちらも業界内での評価を示す重要な指標。 |
今回のモンハンワイルズが受賞したのは、最も知名度と影響力の高い「The Game Awards (TGA)」です。 TGAは、単なる授賞式ではなく、新作タイトルの発表やライブパフォーマンスなども行われる一大エンターテインメントショーであり、世界中のゲーマーが注目するイベントとなっています。
審査員は誰?選考プロセスの透明性
TGAの審査は、世界各国の100以上の影響力のあるゲームメディアやインフルエンサーによって構成される審査員団の投票によって行われます。 日本からも、週刊ファミ通やIGN Japanといった主要なメディアが参加しています。
選考プロセスは以下の流れで進みます。
- ノミネート作品の選出: 各審査メディアが、その年に発売されたゲームの中から、各部門にふさわしいと思うタイトルを推薦します。
- 投票: 集計された推薦リストの中から、最終的なノミネート作品が決定されます。その後、審査員団が各部門の受賞作品を決定するために投票を行います。
- 結果発表: TGAのイベント当日に、生放送で結果が発表されます。
審査員を務めるメディアの一覧は公式サイトで公開されており、一定の透明性は確保されていると言えます。 しかし、どのメディアがどの作品に投票したかまでは公開されないため、「完全に透明」とは言えない側面も残っています。
ユーザー票と審査員票の比率と影響力
TGAには、一般ユーザーが投票に参加できる「プレイヤーズボイス部門」も存在しますが、主要な部門(GOTYを含む)の選考においては、ユーザー投票も加味される仕組みになっています。
ただし、その比重は**「審査員票が90%、ユーザー票が10%」**と定められています。
これは、選考が単なる人気投票に陥るのを防ぐための措置です。 しかし、この仕組みが、まさに今回のモンハンワイルズのような「ユーザー評価と専門家評価の乖離」を生み出す一因ともなっています。 たとえ多くのユーザーが「ノー」を突きつけても、9割を占める審査員たちが「イエス」と判断すれば、それが結果としてまかり通ってしまうのです。 この10%という比率は、多くのユーザーにとって「自分たちの声はほとんど反映されない」と感じさせるには十分な数字であり、アワードへの不信感を助長する要因にもなっています。
商業的成功が選考に与える影響は?
「売れたゲームが評価されやすいのではないか」という疑問は、多くの人が抱くところです。 公式には、売上本数や商業的な成功は、GOTYの直接的な選考基準には含まれていません。 あくまで評価されるのは、ゲームの内容、つまり芸術性、革新性、技術的な完成度などです。
しかし、現実問題として、商業的に成功したAAA級タイトルは、多くのメディアでレビューされ、話題になる機会も多いため、審査員の目に留まりやすくなるという側面は否定できません。 開発に莫大な予算をかけられるため、結果的にグラフィックやサウンドのクオリティが高くなり、評価に繋がりやすいという側面もあります。
意図的な「忖度」や「やらせ」が存在するかどうかを断定することはできません。 しかし、結果的に「ビッグタイトルが有利になりやすい構造」が存在することは事実であり、これがユーザーの不信感を生む土壌となっていることは間違いないでしょう。
ユーザー評価と評論家評価はなぜ乖離するのか?
今回の騒動の核心は、この「なぜプロの評価と俺たちの評価はこんなに違うんだ?」という点にあります。 この現象はゲームに限らず、映画や音楽など、あらゆるエンターテインメントで起こりうることです。 その背景には、評価を下す際の「視点」や「価値基準」の根本的な違いが存在します。
評価軸の違い:「革新性・芸術性」を重視する評論家
ゲーム評論家やジャーナリストが作品を評価する際、最も重視するポイントの一つが**「革新性」**です。 つまり、「このゲームは、これまでの常識を打ち破るような新しい体験を提供してくれたか?」「ゲームというメディアの可能性を押し広げたか?」という視点です。 モンハンワイルズが評価された技術的な功績や、業界への貢献といったポイントは、まさにこの革新性の文脈で語られます。
また、**「芸術性」**も重要な評価軸です。 物語のテーマ性、キャラクターデザインの独創性、世界観の構築、音楽との調和など、ゲームを一つの総合芸術として捉え、その完成度を評価します。 彼らは、日々数多くのゲームに触れているため、ありきたりな表現やシステムには既視感を覚えやすく、何か新しい刺激や知的な発見を求めがちです。 そのため、一般のプレイヤーが気にも留めないような細部の作り込みや、野心的な試みに高い価値を見出す傾向があります。
評価軸の違い:「継続的な面白さ・満足度」を重視するユーザー
一方、我々一般のプレイヤーがゲームに求めるものは、よりシンプルで本質的です。 それは**「継続的な面白さ」**、言い換えれば「このゲームに費やした時間とお金に見合うだけの満足感が得られるか?」という点に尽きます。
私たちは、ゲーム業界の歴史や技術的な背景を深く知っているわけではありません。 重要なのは、今この瞬間にプレイしていて「楽しい」と感じられるかどうかです。 モンハンワイルズのユーザーが感じた「マンネリ感」は、まさにこの「継続的な面白さ」が損なわれた結果と言えます。 いくらグラフィックが進化し、世界観がリアルになっても、プレイフィールが前作と大差なければ、新鮮な驚きや楽しさは得られません。
また、ユーザーにとって**「コストパフォーマンス」や「プレイ時間」**も重要な要素です。 何百時間も遊べるやり込み要素があるか、運営のアップデートは頻繁か、といったライブサービス的な視点も、現代のゲーム評価には欠かせません。 評論家が一通りクリアしてレビューを書くのに対し、ユーザーは何ヶ月、あるいは何年もそのゲームと付き合っていく可能性があるのです。
プレイ時間の長さが評価に与える影響
この「プレイ時間」の違いは、評価の乖離を生む非常に大きな要因です。
評論家は、レビューの締め切りがあるため、比較的短時間(数十時間程度)でゲームの全体像を把握し、評価を下さなければなりません。 そのため、ゲームの第一印象や、ストーリークリアまでの体験が評価の多くを占めます。 モンハンワイルズの重厚なストーリーや、序盤の圧倒的な世界の作り込みは、この短期間のレビューにおいては非常に高く評価されやすいポイントでした。
しかし、ユーザーはそこからさらに何百時間とプレイを続けます。 すると、最初は感動した要素も次第に当たり前になり、ゲームシステムの根幹にある問題点や、コンテンツ不足といった部分が目につくようになります。 「ストーリーは良かったけど、エンドコンテンツが薄い」「最初は楽しかったけど、同じことの繰り返しですぐに飽きた」という感想は、まさに長期的なプレイから生まれるものです。
評論家が「素晴らしい短距離走者」を評価しているのに対し、ユーザーは「頼れる長距離走のパートナー」を求めている。 この目的意識の違いが、評価の乖離を生んでいるのです。
過去作からの期待値とマンネリ感の問題
特にモンハンのような長寿シリーズにおいては、プレイヤーが抱く「過去作からの期待値」が評価に大きな影響を与えます。
ベテランハンターであればあるほど、「ワールドの次はこう進化するはずだ」「ライズのあの便利機能は当然引き継がれるべきだ」といった、自分の中での理想像を持っています。 ワイルズがその期待に応えられなかった時、その失望は「マンネリ」という言葉になって現れます。
一方で、評論家は、その作品を一つの独立したゲームとして客観的に評価しようと努めます。 シリーズの文脈を理解しつつも、「この作品単体で見た時の完成度はどうか?」という視点を忘れません。 そのため、ユーザーが感じる「マンネリ感」よりも、ゲームとしての基礎的な完成度の高さを評価する傾向にあるのです。 この視点の違いが、「集大成」と「マンネリ」という、全く正反対の評価を生み出す原因となっています。
モンハンワイルズ炎上から見るゲームアワードの今後の課題
今回のモンハンワイルズを巡る一件は、単なる一つのゲームの評価に留まらず、現代のゲームアワードが抱える構造的な問題を浮き彫りにしました。 今後、GOTYのような賞がその権威と信頼を維持していくためには、いくつかの重要な課題に取り組む必要があります。
課題①:多様化するプレイヤーニーズへの対応
かつてゲームは、一部のコアなファンが楽しむ趣味でした。 しかし今や、スマートフォンゲームの普及などにより、プレイヤー層は性別や年齢を問わず、爆発的に拡大しています。 カジュアルに楽しみたい人、eスポーツとして競技性を求める人、仲間とのコミュニケーションツールとして利用する人など、そのニーズは極めて多様化しています。
現在のGOTYは、依然として「コンソールやPCでプレイする、ストーリー主導型の高品質なゲーム」を高く評価する傾向にあります。 この評価軸だけでは、多様化する現代のプレイヤー全体の価値観を代表しているとは言えません。 今後は、より細分化された部門を設けるなど、様々なプレイスタイルや価値観に対応できるような、柔軟な評価の仕組みが求められるでしょう。
課題②:「ライブサービス型ゲーム」をどう評価するか
モンハンワイルズもそうですが、現代の多くのゲームは「発売したら終わり」ではありません。 定期的なアップデートによってコンテンツが追加され、バランス調整が行われ、数年単位で運営されていく「ライブサービス型」が主流となっています。
これは、ゲームアワードにとって非常に悩ましい問題です。 発売直後の初期バージョンを評価すべきなのか、それとも1年後の完成された状態を評価すべきなのか。 例えば、発売当初は評価が低かったものの、後のアップデートで「神ゲー」と化した作品は、どのように扱えば良いのでしょうか。
現在の年単位の選考システムでは、こうしたライブサービス型ゲームの長期的な価値を正しく評価することが困難です。 ゲームの評価が常に変動し続ける時代に合わせて、アワードのあり方そのものを見直す時期に来ているのかもしれません。
課題③:透明性と信頼性の確保に向けて
今回の炎上で最も問われたのは、やはり選考プロセスへの信頼性です。 「審査員90%、ユーザー10%」という比率が妥当なのかどうか、再検討の余地はあるでしょう。 ユーザーの声をより反映させる仕組みを導入しなければ、アワードが一部の専門家たちだけの閉じたコミュニティであるという印象は拭えません。
また、審査員がどのような基準で、なぜその作品を選んだのか、その理由をより具体的に公開することも、透明性を高める上で重要です。 単に結果を発表するだけでなく、各作品のどこが評価されたのかを詳細に解説することで、ユーザーとの認識のズレを埋める努力が必要不可欠です。
ゲームという文化が成熟し、社会的な影響力を持つようになった今、その文化の指標となるべきアワードには、これまで以上に高い公平性と透明性、そしてプレイヤーからの信頼が求められています。
まとめ
今回は、「モンスターハンターワイルズ」のGOTY選出がなぜ炎上したのか、その背景を多角的に掘り下げてきました。
ユーザー側から見れば、アクティブユーザーの減少やマンネリ感といった明確な不満点がありながらの受賞は、到底納得できるものではなかったでしょう。 その背景には、GOTYというアワードへの忖度や不透明性に対する根強い不信感がありました。
一方で、評論家・審査員の視点に立てば、ワイルズが成し遂げた技術的革新や、シリーズの集大成としての圧倒的な完成度、そして業界全体に与えた貢献は、GOTYに値するものでした。
この両者の評価の乖離は、「面白い」の定義が一つではないことを示しています。 評論家が求める「革新性・芸術性」と、ユーザーが求める「継続的な面白さ・満足度」。 どちらが正しくて、どちらが間違っているという話ではありません。 ただ、現在のゲームアワードが、前者の価値観に偏りがちであることは事実です。
今回の騒動をきっかけに、ゲームを評価することの難しさと奥深さについて、そしてこれからのゲームアワードのあり方について、多くの人が考えるきっかけになったのではないでしょうか。 一人のゲームファンとして、そして評論家として、私もこの議論の行方を注意深く見守っていきたいと思います。