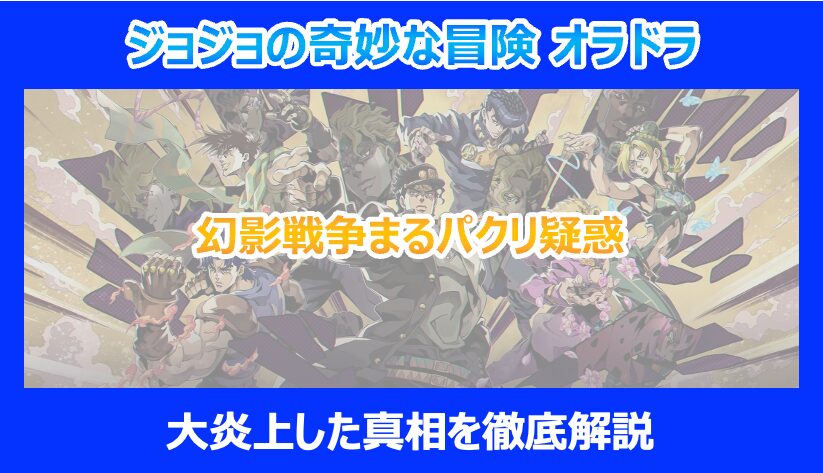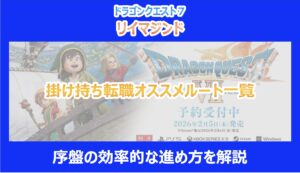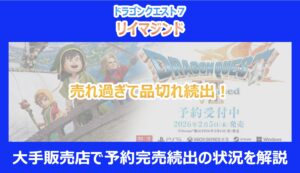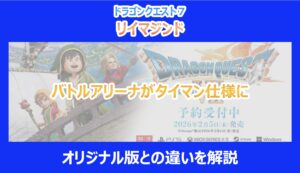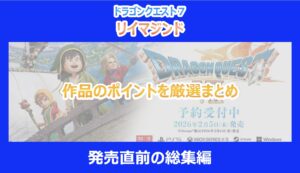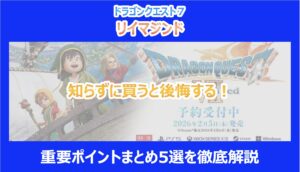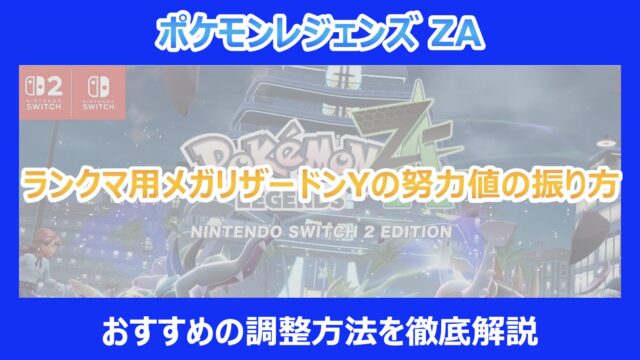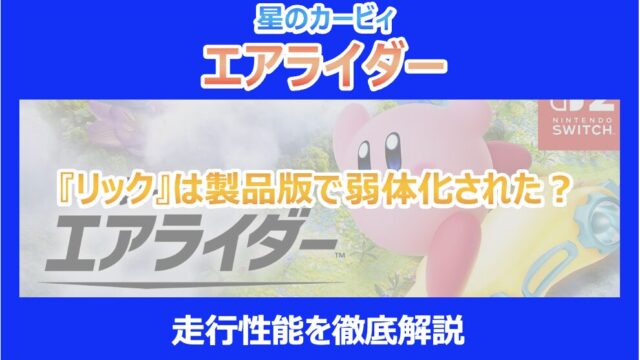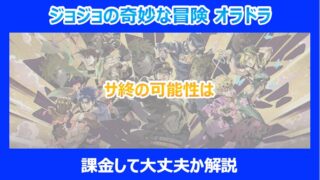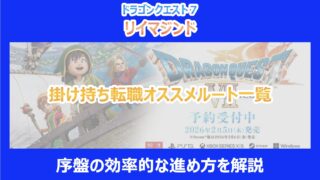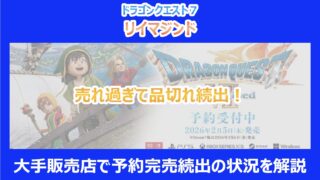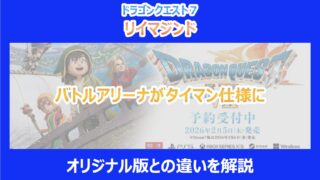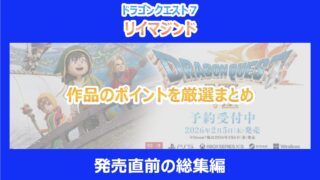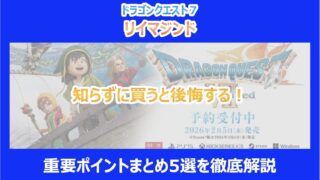ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年9月25日にリリース予定の新作スマホゲーム「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」(以下、オラドラ)が、既存の人気ゲーム「FFBE 幻影戦争 WAR OF THE VISIONS」(以下、幻影戦争)のパクリではないかと炎上している件について、その真相が気になっていると思います。
リリース前からこれほどの騒ぎになるのは異例ですが、それだけ両作品、そして原作への注目度が高い証拠でしょう。

この記事を読み終える頃には、オラドラと幻影戦争の具体的な類似点、開発会社の戦略、そしてこの「パクリ疑惑」を踏まえた上で、オラドラが本当に期待できる作品なのかという疑問が、きっと解決しているはずです。
- オラドラと幻影戦争の驚くべきシステム上の類似点
- 開発会社gumiの戦略「皮の被せ替え」とは何か
- 幻影戦争から予測するオラドラの具体的なゲーム性
- パクリ疑惑を超えたオラドラへの期待と懸念の最終結論
それでは解説していきます。

ジョジョ新作「オラオラオーバードライブ」とは? 基本情報を総まとめ
まずは、大きな話題を呼んでいる「オラドラ」がどのようなゲームなのか、現在公開されている情報から基本スペックを整理していきましょう。 この概要だけでも、勘の良いSRPGファンならピンとくる部分があるかもしれません。

オラドラのゲームジャンルと世界観
「オラドラ」の公式ジャンルは「オラオラシミュレーションRPG」と銘打たれています。 これは、マス目状のフィールドでキャラクターを動かして戦う、いわゆる「タクティクス系」や「シミュレーションRPG(SRPG)」に分類されるゲームです。 家庭用ゲームで言えば、「ファイナルファンタジータクティクス」や「ファイアーエムブレム」シリーズをイメージすると分かりやすいでしょう。
プレイヤーは「ジョジョの奇妙な冒険」に登場する歴代のキャラクターたちでドリームチームを編成し、原作の物語を追体験しながら強敵たちと戦っていくことになります。 原作の持つ独特のセリフ回しや手に汗握る頭脳戦が、SRPGというジャンルでどのように表現されるのかが大きな見どころです。
登場キャラクターとストーリー
リリース時点では、アニメシリーズの「ファントムブラッド」から「ストーンオーシャン」までのキャラクターが登場することが確定しています。 各部の主人公や仲間たちはもちろん、ディオ・ブランドーをはじめとする魅力的な敵キャラクターも育成し、味方としてパーティに組み込むことが可能です。 ジョナサンとディオ、承太郎とDIOが共闘するといった、原作ではありえなかった夢の組み合わせを実現できるのは、オールスターゲームならではの醍醐味と言えるでしょう。

ストーリーは、原作を追体験する形で展開され、キャラクターの立ち絵と豪華声優陣によるフルボイスで物語が進行します。 ジョースター家の長きにわたる因縁の物語を、ゲームを通じて改めてじっくりと味わうことができます。
リリース日と対応プラットフォーム
気になるリリース日ですが、2025年9月25日を予定しています。 対応プラットフォームは、iOS(App Store)とAndroid(Google Play)で、スマートフォンさえあれば誰でもプレイ可能です。 料金形態は、基本プレイ無料のアイテム課金制。 いわゆる「ソシャゲ」と呼ばれるビジネスモデルですね。
過去のジョジョスマホゲームの歴史
「オラドラ」は、ジョジョの奇妙な冒険を題材としたスマートフォン向けゲームとしては4作目となります。 過去の作品を振り返ることで、今回の「オラドラ」にかけられる期待の大きさがより理解できるでしょう。
| タイトル | 開発/提供 | ジャンル | サービス期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| スターダストシューターズ | ドリコム / バンダイナムコ | おはじきバトル | 2014年3月~2021年4月 | 「モンスターストライク」風のシステム。約7年間続く長寿タイトルとなった。 |
| ダイヤモンドレコーズ | バンダイナムコ | アクション → ターン制バトル | 2017年2月~2019年11月 | 途中でゲーム性を大幅に変更。賛否両論の末、比較的短命に終わった。 |
| ピタパタポップ | バンダイナムコ | パズルゲーム | 2018年10月~2021年9月 | デフォルメされたキャラが特徴。売上は伸び悩んだものの、ファンからの評価は悪くなかった。 |
このように、過去のジョジョソシャゲは、長寿タイトルもあれば、迷走の末に短命で終わったものもあります。 そんな中で、満を持して登場する4作目の「オラドラ」が、シリーズ初の本格SRPGというジャンルでどこまで成功できるのか、多くのファンが固唾を飲んで見守っています。
【比較検証】オラドラは幻影戦争の丸パクリなのか? 炎上した8つの類似点
さて、本題です。 なぜ「オラドラ」は「幻影戦争のパクリ」とまで言われ、これほどまでに炎上してしまったのでしょうか。 百聞は一見に如かず。 現在公開されている「オラドラ」のゲーム画面と、「幻影戦争」の画面を比較しながら、その驚くべき類似点を具体的に8つ挙げて徹底解説していきます。 これからご覧いただく内容は、もはや「インスパイア」や「オマージュ」といった言葉では説明がつかないレベルかもしれません。

①:酷似するバトル画面のUI(ユーザーインターフェース)
まず最も指摘されているのが、戦闘中の画面構成です。

- 画面構成: マス目状のフィールド、キャラクターのHPやSP(EP)を示すゲージ、行動順を示すタイムライン、画面右下のコマンドボタン(通常攻撃、アビリティ、待機など)、オートバトルや倍速ボタンの配置。
- デザイン: 各種ゲージやボタンの色味、フォントの雰囲気まで、両者は驚くほど似通っています。
- システム: マップに高低差の概念があり、キャラクターの向きや高さが戦略に影響する点も共通しています。
片方のゲームをプレイしたことがある人なら、もう片方をチュートリアル無しで遊べてしまうほど、UIと基本的なバトルシステムは酷似していると言わざるを得ません。
②:完全に一致する編成画面のシステム
次に、バトル前のキャラクター編成画面を見てみましょう。 ここでも、偶然では済まされないレベルの一致が見られます。
- パーティ構成: メインキャラクター5名+フレンド枠1名の計6名でクエストに出撃する形式。
- 装備枠: 各キャラクターに「アシストカード(幻影戦争ではビジョンカード)」と「サポーター(幻影戦争では召喚獣)」をセットする枠が存在する。
- コスト概念: パーティ全体に「コスト」の上限が設定されており、強力なキャラクターやカードほどコストが高く、無制限に編成できない。
キャラクターのアイコン配置、装備枠のレイアウト、コスト表示の位置まで、寸分違わぬと言っても過言ではないほど構成が同じです。
③:「アシストカード」と「ビジョンカード」
「オラドラ」には、アニメの名場面をカード化した「アシストカード」という装備アイテムが存在します。 これをキャラクターに装備させることで、ステータスが上昇したり、特殊なアビリティが使えるようになったりします。
一方、「幻影戦争」にも全く同じ役割を持つ「ビジョンカード」というものが存在します。 こちらもキャラクターのイラストが描かれたカードで、装備することでパーティ全体や個人を強化できます。 カードをガチャで入手し、欠片を集めて凸(限界突破)していく育成システムまで含めて、名称が違うだけで実質的に同じものと考えて間違いないでしょう。
④:キャラクターのレアリティと属性・ロール
ソシャゲではおなじみのレアリティですが、これも共通しています。 「オラドラ」では「R」「SR」「UR」といったレアリティが確認されており、これは「幻影戦争」で使われているものと同じです。
さらに、キャラクターの分類方法も酷似しています。
- 属性: 「オラドラ」では正(青)、悪(紫)など色分けされた属性が存在し、属性間の相性がバトルに影響します。これは「幻影戦争」の火、水、風、土、雷、光、闇、氷といった属性相性と概念的に同じです。
- ロール: 「物理攻撃」「特殊攻撃」「妨害」「治療」といった役割(ロール)が設定されている点も、「幻影戦争」の「斬撃」「刺突」「打撃」「射撃」「魔法」といった攻撃タイプや役割分担と非常に似た考え方です。
これにより、キャラクターの分類は「属性×ロール」で細分化され、育成の複雑さと戦略の幅を生み出していますが、その根幹のシステム設計が共通しているのです。
⑤:高低差のある3Dタクティクスバトル
「オラドラ」のバトルフィールドは、単なる平面ではありません。 建物や地形による「高低差」が存在し、高い位置から攻撃すると命中率が上がるといった戦略的な要素が盛り込まれています。 これは、タクティクスRPGの金字塔である「ファイナルファンタジータクティクス」から受け継がれ、「幻影戦争」でも重要なゲームシステムとして採用されているものです。 この高低差の概念と、それを活かしたマップデザインの思想が、両作品で共通している可能性は非常に高いでしょう。
⑥:迫力満点の3D必殺技演出
「オラドラ」の魅力の一つとして、キャラクターが繰り出す必殺技のド派手な3Dグラフィック演出が挙げられています。 キャラクターの3Dモデリングがダイナミックに動き回り、原作さながらの迫力あるアクションが展開されます。
これもまた、「幻影戦争」における「リミットバースト」の演出と全く同じコンセプトです。 通常はマス目上のキャラクターが、必殺技使用時のみ専用のカットシーンに移行し、美麗な3Dグラフィックで技を繰り出す。 この見せ方までそっくりなのです。
⑦:ユニット閲覧画面のデザイン
キャラクターの詳細を確認できる「ユニット図鑑」や閲覧画面。 ここでも両者のUIデザインは酷似しています。 キャラクターの3Dモデルを回転させて様々な角度から眺められる機能や、ステータス、アビリティ、プロフィールを表示する画面のレイアウトが非常に似ています。 ボイスを再生できる機能や、ポーズを取らせる機能がある点も共通しています。
⑧:結論:ゲームシステムはほぼ幻影戦争そのもの
以上の8つの点を総合的に判断すると、「オラドラ」のゲームシステムは、「幻影戦争」のそれをほぼそのまま流用している、と結論付けざるを得ません。 これは、開発会社が同じgumiであることから、「偶然の一致」や「単なる模倣」ではなく、意図的に行われた「システムの使い回し」であると考えるのが自然です。
ユーザーが「パクリ」と指摘し炎上するのも無理はなく、もはや「ジョジョの皮を被った幻影戦争」と揶揄されても仕方がない状況と言えるでしょう。
開発会社gumiの戦略から紐解く「皮の被せ替え」商法とは
では、なぜ開発会社である株式会社gumiは、このようなあからさまなシステムの流用を行ったのでしょうか。 そこには、近年のソシャゲ業界、特にgumiという会社が置かれている状況と、彼らなりの戦略が見え隠れします。

gumiはどんな会社? 事業内容を解説
株式会社gumiは、2007年に設立された日本のゲーム会社で、東証プライムに上場しています。 主力事業は大きく分けて2つです。
- モバイルオンラインゲーム事業: 「ファントム オブ キル」や「誰ガ為のアルケミスト」、そして今回の「幻影戦争」など、スマートフォン向けのゲームを開発・運営しています。
- ブロックチェーン等事業: NFTやメタバースといった、いわゆるWeb3.0領域に近年非常に力を入れています。ゲームで遊びながら稼ぐ(Play to Earn)という概念を取り入れた新しいコンテンツ開発を進めており、SBIやスクウェア・エニックスからも出資を受けるなど、将来の柱として期待されています。
現状としては、モバイルオンラインゲーム事業が安定的な収益源となりつつも、会社の未来はブロックチェーン事業に賭けている、という側面が強い企業です。
gumiの「皮の被せ替え」開発スタイル
実は、gumiが既存のゲームシステムを流用して新作を開発するのは、今回が初めてではありません。 同社が開発した「誰ガ為のアルケミスト(タガタメ)」というSRPGがあり、その後にリリースされた「アスタータタリクス」は、多くのシステムを「タガタメ」から引き継いでいました。
そして今回の「オラドラ」は、「幻影戦争」のシステムをベースにしています。 このように、一度成功した(あるいは完成度の高い)ゲームシステムを「骨格」として、その上に異なるIP(知的財産、この場合はジョジョ)のキャラクターやストーリーという「皮」を被せて新しいゲームとしてリリースする。 これが、gumiの常套手段となりつつある「皮の被せ替え」戦略なのです。
なぜ同じようなゲームシステムを使い回すのか
この戦略には、開発会社側にとって明確なメリットが存在します。
- 開発コストの削減と期間の短縮: ゲームの根幹システムをゼロから開発するのは、膨大な時間とコストがかかります。既存のシステムを流用すれば、この部分を大幅にショートカットできます。
- 品質の安定: すでに長期間運営され、ユーザーからのフィードバックを受けて改善され続けてきたシステムを使うため、バグが少なく、ゲームバランスもある程度完成された状態でリリースできます。
- ヒットの確率向上: 元となったゲーム(幻影戦争)が商業的に成功しているため、その面白さの根幹は保証されています。そこにジョジョという強力なIPを組み合わせることで、失敗のリスクを低減できます。
一方で、ユーザー側から見ればデメリットもあります。
- 新鮮味の欠如: 元のゲームをプレイしているユーザーにとっては、やっていることがほぼ同じなため、新鮮な驚きがありません。
- IPの安易な消費: 「結局はいつものgumiのゲームか」と思われ、IPそのものの価値を損なうリスクがあります。
- 運営リソースの分散: 似たようなゲームを複数運営することで、開発チームのリソースが分散し、一つ一つのゲームのアップデートや改善が疎かになるのではないかという懸念。
gumiはこれらのメリット・デメリットを天秤にかけ、コストを抑えつつ安定した品質のゲームをスピーディに市場へ投入する戦略を選んでいるのです。
神ゲー?それとも… 幻影戦争から予測するオラドラのゲーム性
「オラドラは幻影戦争の皮違い」という事実を受け入れた上で、次に気になるのは「では、幻影戦争は面白いゲームなのか?」という点です。 骨格となる幻影戦争のゲーム性を知ることで、オラドラがどのようなプレイ体験になるのか、具体的に予測することができます。 幻影戦争は5年半以上もサービスが続いている人気タイトルであり、その中身は非常に奥深く、そして一筋縄ではいかない特徴を持っています。

ガチャの確率と凸仕様はどうなる?
まず、多くのプレイヤーが気になるであろうガチャと育成システムです。 幻影戦争は、はっきり言って「課金圧が非常に強い」ゲームとして知られています。
- ガチャ確率: 最高レアリティであるURキャラクターの排出率は、サービス開始当初0.8%でした。しかし、後に「コスト100」と呼ばれる特に強力なキャラクターが登場し、その排出率はさらに低い**0.4%**に設定されました。これは、ソシャゲ全体で見てもかなり厳しい確率です。
- 凸(限界突破)仕様: 幻影戦争では、ガチャでキャラクターを1体引いただけでは、その性能をほとんど発揮できません。「限界突破」と呼ばれる育成が必要不可欠ですが、そのためには「キャラクターの欠片」というアイテムが数百個単位で必要になります。この欠片は、ガチャで同じキャラを重ねて引くか、ショップで交換するなど、時間かお金をかけて集めるしかありません。
この厳しいガチャ確率と、時間のかかる凸仕様が、幻影戦争の高い課金圧の根源となっています。 オラドラがこのシステムをそのまま継承する場合、好きなキャラクターを最強の状態にするには、かなりの覚悟(とお金)が必要になるでしょう。 ただし、版権元がスクウェア・エニックスから集英社に変わることで、この辺りの仕様が少しマイルドに調整される可能性に期待したいところです。
対人要素はメインコンテンツになる可能性大
幻影戦争の面白さの中核を担っているのが、「対人戦」です。
- アリーナ: 他のプレイヤーが設定した防衛パーティと戦い、ランキングを競う非同期型の対人戦。
- ギルドバトル: ギルドメンバーと協力して、相手ギルドと戦う大規模な対人戦。
- マッチバトル: リアルタイムで他のプレイヤーとマッチングして戦う、最も競技性が高い対人戦。
これらの対人コンテンツで勝利するために、キャラクターを育成し、最適な編成を考えるのが幻影戦争の主な楽しみ方です。 ガチ勢と呼ばれるプレイヤーのほとんどは、この対人要素に魅了されています。 オラドラもこのシステムを踏襲するならば、ストーリーを楽しむだけでなく、他のプレイヤーとの頭脳戦がゲームのメインコンテンツになることは間違いありません。
幻影戦争で培われた「賢いオートAI」の継承
幻影戦争の対人戦が面白い最大の理由は、その**「非常に賢いオートAI」**にあります。 サービス開始当初はAIの挙動もお粗末なものでしたが、5年半以上の運営を経て、驚くほど洗練されてきました。
- ヒーラーは無闇に前に出ず、回復に専念する。
- アタッカーは最も効果的な敵を狙って攻撃する。
- アビリティの使用/不使用を事前に設定できる。
など、プレイヤーの戦略意図を汲んでキャラクターが自動で動いてくれます。 このため、「自分の考えた最強の編成とAI設定が、オートバトルでいかに上手く機能するか」という、まるでプログラミングのような楽しさがあります。 この洗練されたAIは、gumiのSRPGにおける最大の資産であり、オラドラにも間違いなく継承されるでしょう。 ジョジョのキャラクターたちが、原作さながらのクレバーな立ち回りを見せてくれると期待できます。
ストーリーやソロコンテンツの充実度
対人戦がメインとはいえ、一人でじっくり遊べるソロコンテンツも重要です。 幻影戦争には、フルボイスで展開されるオリジナルストーリーのほかにも、様々なソロコンテンツが用意されています。
- セレクションクエスト: 特定のレアリティや属性のキャラしか使えない、詰め将棋のような高難易度クエスト。
- 白磁の塔: 一度倒れたキャラは使えなくなる特殊なルールで、手持ちの全戦力を駆使して塔を登っていくコンテンツ。
これらのコンテンツは、無課金や微課金ではクリアが難しいものも多いですが、SRPGとしての歯ごたえは十分にあります。 オラドラも、原作ストーリーの追体験だけでなく、ジョジョの世界観を活かした高難易度コンテンツが多数実装されることが予想されます。
【結論】オラドラはプレイすべき? 評論家が斬る期待と懸念点
さて、ここまで「オラドラ」が「幻影戦争」のシステムを流用したゲームであること、そしてその骨格となる幻影戦争がどのようなゲームであるかを詳しく解説してきました。 これらの情報を踏まえ、ゲーム評論家として「オラドラはプレイすべきなのか?」という問いに最終的な結論を出したいと思います。
期待できる点①:完成されたSRPGシステムの面白さ
最大の期待点は、やはり「ゲームとしての面白さが保証されている」ことです。 皮の被せ替えは、聞こえは悪いですが、裏を返せば「5年半かけて磨き上げられた、面白さが実績で証明済みのゲームシステム」を、リリース初日から楽しめるということです。 バグだらけでゲームバランスが崩壊した新作をプレイさせられるリスクは極めて低いでしょう。
特に、賢いオートAIによる戦略性の高いバトルは、他の凡百のソシャゲSRPGとは一線を画す面白さがあります。 この完成されたシステムの上で、ジョジョのキャラクターたちがどう躍動するのか。 これは素直に楽しみです。
期待できる点②:ジョジョの世界観との高い親和性
SRPGというジャンルと、ジョジョの奇妙な冒険という作品の相性は、実は非常に良いと考えられます。 スタンド能力の多様性や、敵との駆け引き、頭脳戦といった原作の魅力は、キャラクターのスキルやアビリティ、属性相性といったSRPGのシステムに落とし込みやすいはずです。 「スタープラチナ」の時間停止能力や、「ゴールド・エクスペリエンス」の生命を生み出す能力が、ゲーム内でどのようなスキルとして再現されるのか、想像するだけでワクワクします。
懸念点①:幻影戦争譲りの「高い課金圧」
一方で、最大の懸念点は、幻影戦争から引き継がれるであろう「高い課金圧」です。 もし、ガチャ確率や凸仕様が幻影戦争と同等の厳しさであれば、無課金・微課金のプレイヤーが対人戦で上位を目指すのは極めて困難になります。 「好きなキャラクターを手に入れても、お金をかけないとまともに活躍させられない」という状況は、多くのプレイヤーにとって大きなストレスとなるでしょう。 この点が、オラドラが幅広いファンに受け入れられるか、それとも一部の重課金者だけが残るゲームになるかの分水嶺になるかもしれません。
懸念点②:運営リソースの分散は大丈夫か
gumiは、幻影戦争の運営を続けながら、新たにオラドラの運営も開始することになります。 システムの骨格が同じとはいえ、キャラクターの追加やイベントの開催には多大なリソースが必要です。 両タイトルの間で開発チームの人員が食い合いになり、結果としてどちらのサービスの質も低下してしまうのではないか、という懸念は拭えません。 特に、gumiがブロックチェーン事業に注力している現状を考えると、モバイルゲーム事業に割けるリソースが限られている可能性もあります。
まとめ
長くなりましたが、今回のレビューをまとめます。
「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」が、「FFBE 幻影戦争」のシステムをほぼそのまま流用している、いわゆる**「皮の被せ替え」ゲームであることは、ほぼ間違いない事実**です。 この点において、ユーザーから「パクリ」と批判され炎上するのは当然の流れと言えます。
しかし、その事実は必ずしも「オラドラがつまらないゲームである」ことを意味しません。 むしろ、骨格となる幻影戦争は、5年半の運営実績が証明する通り、非常に戦略的で奥深い、優れたSRPGです。 完成されたゲームシステムと、ジョジョという魅力的なIPの組み合わせは、大きなポテンシャルを秘めています。
最終的な評価は、**「ゲームの面白さはほぼ確定しているが、幻影戦争譲りの高い課金圧が最大の懸念点」**となります。
もしあなたが、
- 歯ごたえのある本格的なSRPGが好き
- ジョジョのキャラクターで夢のチームを組みたい
- 対人戦で他のプレイヤーと戦略を競い合いたい
というのであれば、「オラドラ」は間違いなく”買い”のゲームです。 一方で、
- 無課金・微課金でまったり遊びたい
- 複雑な育成や対人戦は苦手
という方にとっては、少しハードルが高いゲームになるかもしれません。
いずれにせよ、これだけの話題を呼んでいる「オラドラ」が、今年のスマートフォンゲーム市場の目玉の一つであることは確かです。 リリースされた暁には、私自身も一人のプレイヤーとして、その「覚悟」が試される世界に飛び込んでみたいと思います。