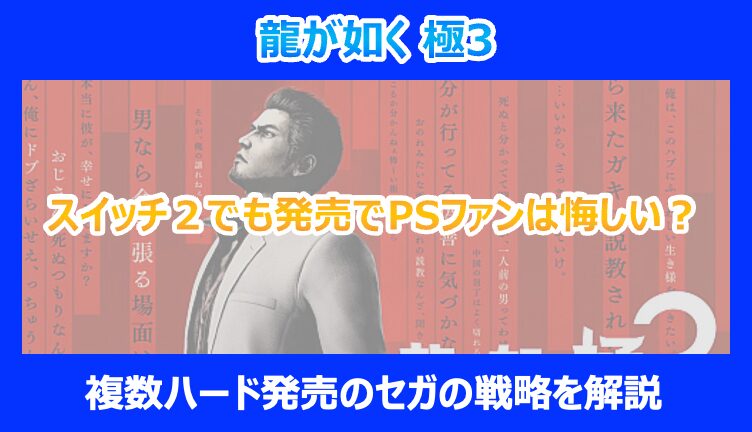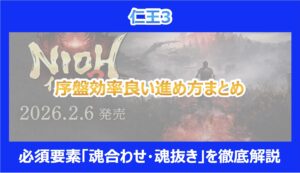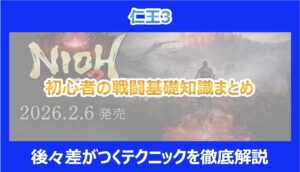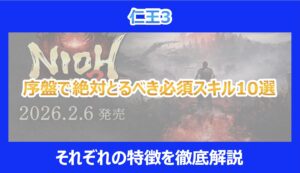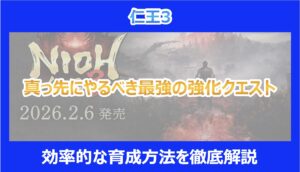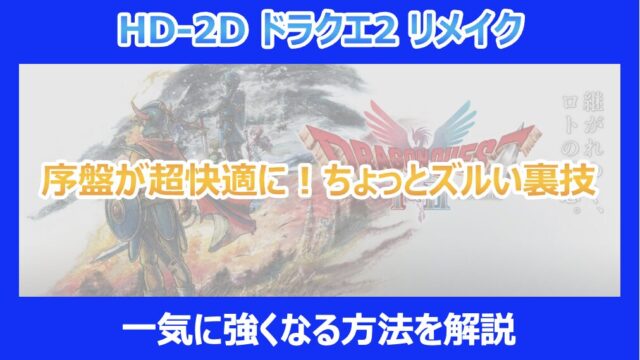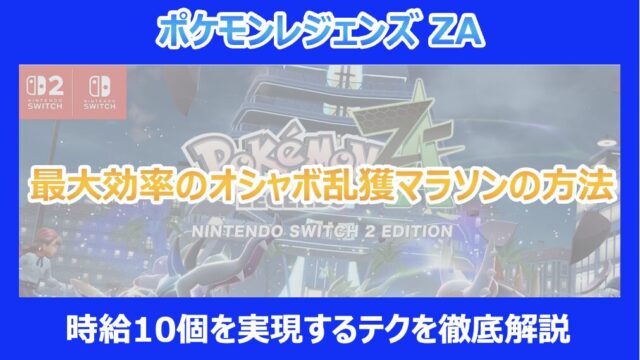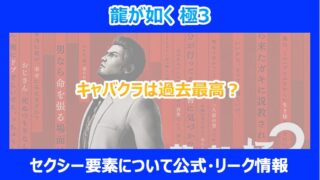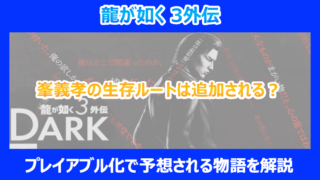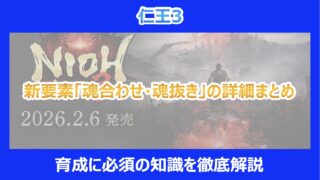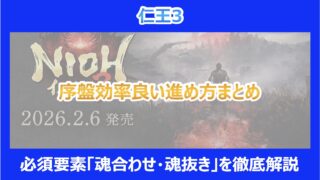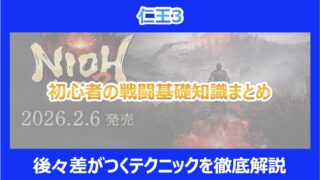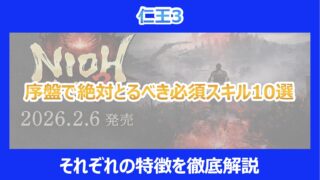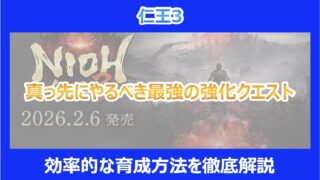ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、待望の「龍が如く 極3」がPlayStationシリーズだけでなく、Nintendo Switch 2でも発売されるというニュースについて、その背景や理由が気になっていると思います。

長年のファン、特にPlayStationと共にシリーズを追いかけてきた方にとっては、喜びと共に一抹の寂しさや、なぜ?という疑問が湧くのも無理はありません。
この記事を読み終える頃には、「龍が如く 極3」のマルチプラットフォーム化の裏にあるセガの深い戦略や、今後のゲーム業界の大きな変化についての疑問が解決しているはずです。
- 待望のフルリメイク「龍が如く 極3」の発売情報
- 長年のPSファンが抱く独占終了への複雑な心境
- セガが採用するマルチプラットフォーム戦略の論理的な理由
- 今後のゲーム業界と「龍が如く」シリーズの未来予測
それでは解説していきます。

「龍が如く 極3」発売決定!その衝撃とファンの反応
伝説が、再び現代に蘇ります。 多くのファンが待ち望んでいた「龍が如く3」のフルリメイク作品、「龍が如く 極3」の発売が決定しました。 しかし、その発表は純粋な喜びだけでなく、長年のファンコミュニティに大きな波紋を広げることとなったのです。 まずは、この待望の新作の概要と、なぜこれほどまでに注目されているのかを紐解いていきましょう。
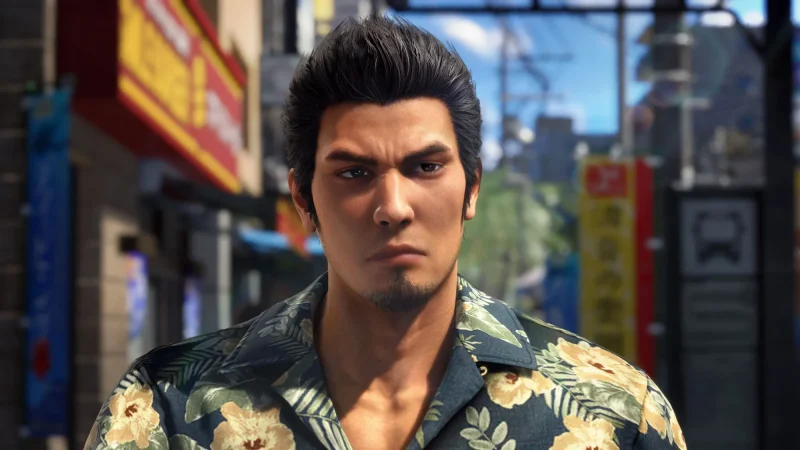
待望のフルリメイク「龍が如く 極3」の基本情報
長きにわたる沈黙を破り、ついに「龍が如く 極3」の詳細が明らかになりました。 発売日は2026年2月を予定しており、桐生一馬の物語の中でも特に異色で、かつ重要なターニングポイントとなった沖縄での日々が、最新技術によって描かれます。
対応プラットフォームは、PlayStation 5 (PS5)に加え、任天堂の次世代機であるNintendo Switch 2での同時発売が予定されています。 これは「龍が如く」シリーズのナンバリング最新作(リメイク含む)としては、歴史的な出来事と言えるでしょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| タイトル | 龍が如く 極3 |
| 発売予定日 | 2026年2月 |
| ジャンル | アクションアドベンチャー |
| 対応ハード | PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, Steam |
| CERO | 審査予定 |
| 開発 | 龍が如くスタジオ |
| 販売 | セガ |
本作は、「龍が如く0」から続く「極」シリーズの流れを汲み、ただのグラフィック向上に留まらない、大幅な追加要素やシナリオの深掘りが期待されています。 オリジナル版の良さを尊重しつつ、現代のゲームファンが楽しめるよう、バトルシステムや操作性も大幅に改良される見込みです。
オリジナル版「龍が如く3」とは?不朽の名作の魅力
ここで、オリジナル版である「龍が如く3」がどのような作品だったかを振り返っておきましょう。 2009年にPlayStation 3で発売された本作は、それまでの舞台であった神室町に加え、日本の南国・沖縄の琉球街という新たなロケーションを導入した意欲作でした。
東城会の跡目を継いだ大吾を支え、裏社会から身を引いた桐生一馬が、沖縄で養護施設「アサガオ」を営み、子供たちと穏やかな日々を送るところから物語は始まります。 しかし、その平穏は土地買収を巡る地元ヤクザと、日本の中枢を揺るがす大きな陰謀によって打ち砕かれます。
愛する子供たちや沖縄の日常を守るため、桐生は再び伝説の龍として立ち上がるのです。 シリーズの中でも特に「家族」や「守るべきもの」というテーマが色濃く描かれ、人間ドラマの深さから多くのファンの心を掴みました。 一方で、当時のPS3というハードの性能を活かした美しい沖縄の風景描写も高く評価されました。
ただし、バトルシステムにおいては、敵が過剰にガードを多用する傾向があり、一部のプレイヤーからは「ガードマン」と揶揄されるなど、ゲームプレイの面で課題が指摘されていたのも事実です。 今回の「極3」では、そうした点がどのように改善されるのかも、大きな注目ポイントとなっています。
なぜ「極」シリーズはファンを魅了するのか?
「龍が如く 極」「龍が如く 極2」の成功がなければ、「極3」への期待もこれほど大きくはならなかったでしょう。 「極」シリーズの最大の魅力は、単なるリマスター(高画質化)ではなく、フルリメイクである点にあります。
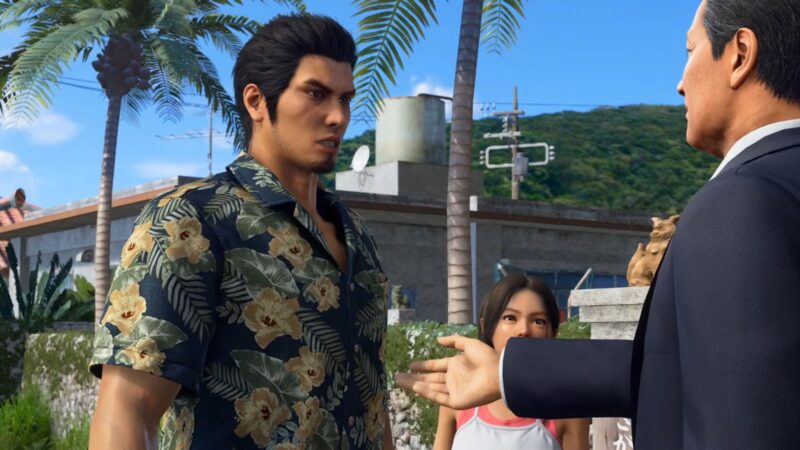
グラフィックの全面的な刷新
「ドラゴンエンジン」などの最新ゲームエンジンを用いて、キャラクターモデルから街並みまで、すべてが一から作り直されます。 これにより、オリジナル版をプレイしたファンも、まるで新作をプレイしているかのような新鮮な驚きを体験できます。
ストーリーの補完と追加エピソード
オリジナル版では語りきれなかったキャラクターの心情や背景を深掘りする追加エピソードが挿入されます。 特に「極」では錦山彰が豹変するまでの苦悩が、「極2」では真島吾朗の追加シナリオが大きな話題を呼びました。 「極3」でも、峯義孝や神田といった魅力的な敵役たちの新たな一面が見られるかもしれません。
現代的なゲームプレイへの改良
バトルシステムやミニゲーム、操作性が現代のスタンダードに合わせて大幅に改善されます。 前述した「龍が如く3」の課題であったバトルも、「極」シリーズのノウハウを活かして、より爽快で戦略的なものに進化することが期待されます。
このように、「極」シリーズは過去作への最大限のリスペクトと、現代の技術・感性を融合させることで、新規ファンと既存ファンの両方を満足させることに成功してきました。 「極3」もまた、その成功体験を踏襲し、シリーズの歴史に新たな1ページを刻む作品となるはずです。
Switch 2での発売が意味するもの
そして、今回の最大のトピックがNintendo Switch 2での発売です。 これまで「龍が如く」シリーズは、Wii Uで「1&2 HD」が発売された例はあるものの、基本的にPlayStationプラットフォームを中心に展開されてきました。 最新作が任天堂の最新ハードで同時発売されるのは、まさに「事件」と言っても過言ではありません。
これは、開発元である龍が如くスタジオ、そして販売元であるセガが、新たな市場、新たな顧客層へ本気でアプローチしようとしている意志の表れです。 携帯モードでも遊べるSwitch 2の特性を活かし、寝転がりながら沖縄の街を散策したり、外出先でサブストーリーを楽しんだりといった、新しいプレイスタイルが生まれる可能性も秘めています。 この決定が、長年のPSファンに複雑な感情を抱かせている一方で、シリーズの未来にとって非常に重要な一歩であることは間違いありません。
なぜPSファンは悔しい?独占からマルチプラットフォームへの変化
「龍が如く 極3」がSwitch 2でも発売されるというニュースは、シリーズのファン層拡大という観点からは喜ばしいことです。 しかし、その一方で、長年PlayStationと共にこのシリーズを愛し続けてきたファン、いわゆる「PSファン」の中から、戸惑いや寂しさ、そして「悔しい」という声が上がっているのも事実です。 この複雑な感情の背景には、「龍が如く」とPlayStationが築き上げてきた、切っても切れない深い関係の歴史が存在します。
「龍が如く」とPlayStationの蜜月の歴史
「龍が如く」シリーズの歴史は、PlayStationの歴史と共にありました。 初代「龍が如く」が誕生したのは2005年、プラットフォームはPlayStation 2でした。 当時、「大人が楽しめるエンタテインメント」を掲げ、実在の繁華街をモデルにしたリアルな世界観、重厚な人間ドラマ、そして爽快なケンカバトルは、ゲーム業界に衝撃を与えました。

それ以来、シリーズはナンバリング作品からスピンオフまで、その主戦場を常にPlayStationに置いてきました。
- PlayStation 2: 龍が如く, 龍が如く2
- PlayStation 3: 龍が如く 見参!, 龍が如く3, 龍が如く4, 龍が如く OF THE END
- PlayStation 4: 龍が如く 維新!, 龍が如く0, 龍が如く 極, 龍が如く6, 龍が如く 極2, 龍が如く7
- PlayStation 5: 龍が如く7外伝, 龍が如く8
このように、ハードの世代交代に合わせて常に最新作が供給され、「PlayStationを買えば、最新の龍が如くが遊べる」という信頼関係が、メーカーとユーザーの間に築かれてきたのです。 ハードの性能進化をいち早くゲームに取り入れ、美麗なグラフィックやシームレスな体験を実現してきたのも、PlayStationという特定のプラットフォームに開発リソースを集中できたから、という側面もあったでしょう。
「プレステのゲーム」という強いブランドイメージ
長年にわたる蜜月関係は、ファンの中に「龍が如くはプレステのゲームである」という強烈なブランドイメージを植え付けました。 これは単なる思い込みではなく、一種のアイデンティティに近いものです。
自分が選んだ「PlayStation」というハードに、自分たちが愛する「龍が如く」というキラーコンテンツが存在する。 その事実に誇りを持ち、他のハードのユーザーに対して優越感を抱くこともあったかもしれません。 それは、特定のチームを応援するスポーツファンの心理にも似ています。 自分たちのホームグラウンドで、自分たちのスター選手が活躍する。 その一体感が、ファンとしての熱量を高めてきたのです。
この「独占」という状況が、ファンに特別な帰属意識と満足感を与えていたことは間違いありません。
独占タイトルが持つ意味とファンが抱く特別な感情
ゲーム業界において、独占タイトル(エクスクルーシブタイトル)は、特定のゲーム機を所有する理由そのものになります。 「あのゲームが遊びたいから、このハードを買う」という購買意欲の最大の源泉です。
ファンにとって独占タイトルは、ただのゲームソフト以上の価値を持ちます。 それは、そのハードの魅力を象-徴する「顔」であり、同じハードを持つ仲間との共通言語であり、そして自分たちの選択が正しかったことの証明でもあります。
「龍が如く」シリーズがPlayStationの独占であり続けたことは、PSファンにとって、ハードの価値を支える大きな柱の一つでした。 その柱が、今回ついにマルチプラットフォームという形で、他の陣営にも開かれることになったのです。 これが「裏切られた」とまではいかなくとも、一種の喪失感や、自分たちの特別だったものが失われてしまうかのような寂しさを感じさせる原因となっています。
マルチプラットフォーム化への戸惑いの声
SNSなどでは、ファンの率直な声が見受けられます。
「嬉しいニュースだけど、正直ちょっと寂しい。龍が如くはプレステでやるのが当たり前だったから」 「Switchで龍が如くができるのは新規ファンが増えそうで良いこと。でも、PS独占じゃなくなるのか…」 「昔からのファンとしては複雑な心境。自分だけの宝物だったのに、みんなのものになってしまう感じ」
これらの声は、決して排他的な考えから来るものではありません。 長年、特定のプラットフォームで作品を愛し、支え続けてきた自負と愛情の裏返しなのです。
それでもPS版を選ぶ理由とは?
しかし、こうした複雑な感情を抱きつつも、多くのPSファンは最終的に「龍が如く 極3」をPS5でプレイすることを選ぶでしょう。 その理由はいくつか考えられます。
トロフィー機能の存在
PlayStationには、ゲームの達成度を示す「トロフィー」機能があります。 「全てのサブストーリーをクリアする」「特定の条件でボスを倒す」といった目標を達成するとトロフィーが獲得でき、最難関の「プラチナトロフィー」を目指すことは、多くのやり込み派プレイヤーのモチベーションとなっています。 過去シリーズのトロフィーをPSで集めてきたファンにとって、そのコレクションを途切れさせることは考えにくく、「極3」も当然PSでトロフィーコンプリートを目指す、という強い動機になります。
最高のゲーム体験への期待
一般的に、マルチプラットフォームで発売されるゲームは、最も高性能なハードであるPS5やPCで、最高のグラフィックやフレームレートを体験できる可能性が高いです。 「最高の環境で龍が如くの世界に没入したい」と考えるファンにとって、PS5版は最も魅力的な選択肢であり続けます。
「故郷」のような安心感
何よりも大きいのは、これまで培ってきた「慣れ」と「愛着」です。 コントローラーの感触、ボタンの配置、メニュー画面の操作性、そして何より「龍が如くはプレステで遊ぶ」という、長年体に染み付いた感覚。 それはまるで「実家のような安心感」であり、他のハードでは得難い特別なプレイ体験なのです。
マルチプラットフォーム化は時代の流れとして受け入れつつも、自らのプレイスタイルは変えない。 それもまた、ファンの一つのあり方と言えるでしょう。
セガの深謀遠慮!「龍が如く 極3」を複数ハードで発売する戦略的背景
長年のPSファンが抱く複雑な心境とは裏腹に、メーカーであるセガ、そして開発の龍が如くスタジオが「龍が如く 極3」をマルチプラットフォームで展開するのは、極めて合理的かつ戦略的な経営判断です。 これは単に目先の利益を追うだけでなく、シリーズの未来、そして変化し続けるゲーム市場全体を見据えた深謀遠慮に基づいています。 その戦略的背景を、5つの理由から徹底的に解説します。
理由①:ユーザー層の拡大と新規ファンの獲得
これが最も大きな理由です。 どれだけ素晴らしいゲームを作っても、それを遊んでくれるプレイヤーがいなければ意味がありません。 特定のハードにソフト供給を限定する「独占戦略」は、そのハードのファンには強くアピールできますが、同時にそのハードを持っていない全てのゲームファンを機会損失していることになります。
特に「龍が如く」シリーズは、初代の発売から20年近くが経過し、ブランドとして成熟期に入っています。 今後のシリーズの発展のためには、これまでのファンを大切にしつつも、新しい世代のファン、これまでシリーズに触れてこなかった層をいかに取り込むかが至上命題です。
ここで、Nintendo Switch 2というプラットフォームが持つ意味は非常に大きい。 前世代機であるNintendo Switchは、全世界で1億台以上を売り上げ、幅広い年齢層、特にファミリー層やライトユーザーに普及しました。 その後継機であるSwitch 2も、その巨大なユーザーベースを引き継ぐことが予想されます。 ここに「龍が如く」を投入することで、PlayStationやXboxを持っていない膨大な数の潜在顧客に、シリーズの魅力を直接届けることができるのです。 「名前は知っているけど、遊ぶ機会がなかった」という層が、Switch 2をきっかけに初めて「龍が如く」の世界に足を踏み入れる。 これは、シリーズの寿命をさらに10年、20年と延ばしていくために不可欠な戦略なのです。
理由②:「PS5が障壁」?ハード普及台数が与える影響
近年、ゲーム業界では「PS5の普及台数が伸び悩んでいる」という声が聞かれます。 実際に、カプコンの辻本春弘社長が「PS5が(ソフト販売の)障壁になっている」と発言したことは、業界に大きな衝撃を与えました。 これは、PS5の性能が低いという意味ではなく、ソフトメーカーが期待するほどの台数が市場に行き渡っていないため、PS5向けだけにソフトを開発・販売しても、十分な売り上げが見込めない、というビジネス上の課題を指摘したものです。
以下の表は、各ハードの世界累計販売台数のおおよその比較です(2025年時点での推定値)。
| ハードウェア | 世界累計販売台数(推定) | 特徴 |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 約1億4,000万台 | 圧倒的な普及台数。携帯機としても据置機としても利用可能。 |
| PlayStation 5 | 約6,000万台 | 高性能だが、Switchに比べると普及ペースは緩やか。 |
| Xbox Series X/S | 約3,000万台 | 北米市場で強み。ゲームパス戦略が特徴。 |
(※販売台数は常に変動しており、あくまで参考値です)
この数字を見れば、ビジネスの観点から判断は明らかです。 約6,000万台の市場(PS5)だけにソフトを出すよりも、そこにSwitch 2の潜在市場(数千万台〜1億台以上)や、Xbox、PC(Steam)の市場を加えることで、販売機会は単純計算で数倍に膨れ上がります。 メーカーとしては、より多くのユーザーがいる場所で商品を売るのは当然の選択と言えるでしょう。 セガも数年前からXboxやSteamへの展開を本格化させており、「龍が如く7外伝」が発売初日からXbox Game Passに対応したことは、その象徴的な出来事でした。
理由③:開発コストの回収と収益最大化
現代のAAA級(大作)ゲームの開発費は、高騰の一途をたどっています。 「龍が如く 極3」のようなフルリメイク作品でも、最新のグラフィック、洗練されたゲームシステム、豪華な声優陣などを実現するためには、数十億円規模の開発費がかかっていると推測されます。
この莫大な投資を回収し、さらに利益を上げて次の作品開発へと繋げるためには、販売本数を最大化する必要があります。 マルチプラットフォーム展開は、この課題に対する最も直接的で効果的な解決策です。 複数のハードでソフトを販売することで、それぞれのハードのユーザーから売上を得ることができ、開発費回収のリスクを分散させながら、収益の最大化を目指せます。 かつてのように、ハードメーカー(ソニーなど)から独占契約金を受け取るビジネスモデルよりも、自社で広く販売して利益を確保する方が、長期的に見て安定的だと判断しているのです。
理由④:グローバル市場への本格展開
「龍が如く」シリーズは、かつては日本やアジア市場が中心でしたが、「YAKUZA」というタイトルで海外展開を続けた結果、欧米でも非常に高い評価を受ける人気シリーズへと成長しました。 特に「龍が如く7」以降は、グローバル市場での成功が、シリーズ全体の売上を大きく牽引しています。
グローバル市場、特に北米市場に目を向けると、PlayStationだけでなくXboxも非常に強いプラットフォームです。 また、PCゲームプラットフォームであるSteamは、全世界で巨大なユーザーコミュニティを形成しています。 これらの市場で本気で成功を収めるためには、PlayStation独占という選択肢はあり得ません。 Xboxユーザー、PCゲーマーにも平等に遊ぶ機会を提供することが、グローバルIPとして成長するための絶対条件となります。 今回のマルチプラットフォーム化は、セガが「龍が如く」を、日本のドメスティックな人気タイトルから、世界で戦える真のグローバルブランドへと押し上げようとする、強い決意の表れなのです。
理由⑤:任天堂との新たな関係構築
セガと任天堂は、かつては家庭用ゲーム機市場で覇権を争ったライバルでした。 しかし、セガがハード事業から撤退して以降、両社は良好なパートナー関係を築いています。 「マリオ&ソニック AT オリンピック」シリーズはその代表例です。
今回、「龍が如く 極3」をSwitch 2で同時発売することは、この関係をさらに一歩進めるものです。 任天堂としても、自社ハードにこれまで不足していた「大人向けの重厚なストーリーを持つAAA級タイトル」が加わることは、ハードの魅力を高める上で大きなプラスになります。 一方、セガにとっては、任天堂が持つ巨大な販売網とユーザーベースを活用できるという大きなメリットがあります。 この協力関係は、両社にとってWin-Winであり、今後のゲーム業界の勢力図にも影響を与える可能性を秘めています。
ゲーム業界の地殻変動!今後の「龍が如く」とハード戦争の未来
「龍が如く 極3」のマルチプラットフォーム化は、単なる一本のソフトの販売戦略に留まらず、ゲーム業界全体で今まさに起きている大きな地殻変動を象徴する出来事です。 かつてのような「ハードの垣根」は溶け始め、メーカーもプレイヤーも、より自由な選択肢を持つ時代へと突入しています。 この変化が、今後の「龍が如く」シリーズ、そしてゲームの未来に何をもたらすのかを考察します。
「極4」「極5」もマルチプラットフォーム化は続くのか?
結論から言えば、この流れは今後も加速していくでしょう。 「龍が如く 極3」がマルチプラットフォームで成功を収めれば、「龍が如く4」「龍が如く5」のリメイク、さらには「見参!」「OF THE END」といったスピンオフ作品の「極」シリーズが制作される際も、同様にマルチプラットフォームで展開される可能性は極めて高いです。
一度、複数のプラットフォームに向けて開発する体制とノウハウを確立すれば、それを継続する方がビジネス的にも効率が良いからです。 龍が如くスタジオは、今後開発する全ての新作を、最初からマルチプラットフォーム展開を前提として設計していくことになるでしょう。 将来的には、「龍が如く」のナンバリング作品が、全ての主要なゲーム機で発売初日から遊べるのが当たり前の時代になるはずです。
Switch 2の登場で変わるサードパーティの戦略
今回のセガの決断は、他の国内サードパーティ(ソフトメーカー)にも大きな影響を与えています。 もはや、特定のハードメーカーに忖度して独占供給する時代ではない、という空気が業界全体に広がっています。
カプコンの事例
「モンスターハンター」シリーズや「バイオハザード」シリーズを擁するカプコンは、以前からマルチプラットフォーム戦略に積極的です。 最新作「バイオハザード9」や、過去作の「7」「8」もSwitch 2向けに供給することを発表しており、自社の有力IPを可能な限り多くのユーザーに届けるという明確な方針を打ち出しています。
スクウェア・エニックスの事例
かつてはPlayStationとの関係が深かったスクウェア・エニックスも、その戦略を大きく転換しています。 これまでPS独占だった「ファイナルファンタジーVII リメイク」シリーズをSwitch 2を含むマルチプラットフォームで展開することを発表。 これは、ゲーム業界にとって「龍が如く」の件と同様、あるいはそれ以上のインパクトを持つニュースでした。
このように、国内の主要メーカーが続々とSwitch 2市場へ参入し、自社の看板タイトルを投入しています。 これは、Switch 2が今後の国内ゲーム市場の覇権を握る可能性が高いと、多くの企業が判断している証拠に他なりません。
ハードの垣根を越えるクロスプラットフォーム時代の到来
マルチプラットフォーム化がさらに進んだ先には、「クロスプラットフォーム」という未来が待っています。 これは、PlayStationのプレイヤーと、Switchのプレイヤー、Xboxのプレイヤーが、オンライン上で一緒にゲームを遊べる仕組みです。
「龍が如く」シリーズは現状、オンラインマルチプレイがメインのゲームではありませんが、今後オンライン要素が強化されたスピンオフなどが登場すれば、クロスプラットフォーム対応も視野に入ってくるでしょう。 ハードの違いを意識することなく、誰もが同じゲーム世界で繋がれる。 そんな時代が、もうすぐそこまで来ています。
プレイヤーにとってのメリット・デメリット
この業界の変化は、我々プレイヤーに何をもたらすのでしょうか。
メリット
- ハード選択の自由: 「あのゲームをやるために、このハードを買わなければならない」という制約から解放されます。自分のライフスタイルや好みに合ったハードを自由に選べるようになります。
- 友人と同じゲームを遊びやすい: 友人が持っているハードが自分と違っても、同じゲームを購入して話題を共有しやすくなります(クロスプラットフォーム対応なら一緒にも遊べます)。
- 市場競争による品質向上: 各ハードメーカーは、ソフトの独占ではなく、サービスの質(オンライン環境、サブスクリプションなど)で競争せざるを得なくなります。その結果、より良いサービスをプレイヤーは受けられる可能性があります。
デメリット
- ハード独自の魅力の希薄化: 独占タイトルが減ることで、「このハードならではの体験」が少なくなり、各ハードの個性が薄れてしまう可能性があります。
- 最適化の問題: 複数のハードで同時に開発・販売するため、特定のハードの性能を限界まで引き出した、いわゆる「神がかった最適化」が施されたゲームは生まれにくくなるかもしれません。
総合的に見れば、プレイヤーにとってはメリットの方が大きい時代へと移行していると言えるでしょう。
ゲーム評論家が予測する「龍が如く」シリーズの未来
「龍が如く」は、マルチプラットフォーム戦略によって、より巨大で、よりグローバルなIPへと進化を遂げるでしょう。 桐生一馬や春日一番といったキャラクターが、ハードの垣根を越えて、世界中のゲームファンに愛される存在になる。 それは、シリーズを長年見守ってきた一人のファンとしても、非常に喜ばしい未来です。
PSファンが感じた一抹の寂しさは、愛するシリーズが新たなステージへと旅立つことへの、親心のようなものかもしれません。 しかし、その旅立ちが、「龍が如く」という物語をさらに多くの人々に届け、未来永劫語り継がれる伝説にしていくための、必要不可欠な一歩なのです。 これからも、ハードという枠に囚われることなく、純粋に「龍が如く」という作品そのものの進化を、共に見届けていこうではありませんか。
まとめ
今回は、「龍が如く 極3」がNintendo Switch 2を含むマルチプラットフォームで発売される背景について、長年のPSファンが抱く心情と、メーカーであるセガの戦略的な視点から深く掘り下げてきました。
- 「龍が如く 極3」は2026年2月、PS5とSwitch 2などで発売予定の待望のフルリメイク作品である。
- 長年PlayStation独占だった歴史から、一部のPSファンは寂しさや戸惑いを感じている。
- セガのマルチプラットフォーム戦略は、新規ファン獲得、開発費回収、グローバル展開など、シリーズの未来を見据えた合理的な判断である。
- この動きはゲーム業界全体のトレンドであり、今後ハードの垣根はますます低くなっていく。
結論として、「龍が如く」がPlayStationの独占タイトルでなくなることは、 mộtつの時代の終わりを意味します。 しかし、それは同時に、より多くのプレイヤーがこの素晴らしいシリーズに出会う、新しい時代の幕開けでもあるのです。
私自身、長年の慣れ親しんだPlayStation 5版でトロフィーコンプリートを目指しつつ、携帯モードで気軽に遊べるNintendo Switch 2版にも手を伸ばしてみようかと、今からワクワクしています。 それぞれのハードに、それぞれの良さがある。 プレイヤーが自分に合ったスタイルで作品を楽しめることこそ、マルチプラットフォーム化の最大の恩恵と言えるでしょう。
伝説の龍の新たな伝説が、全てのゲームファンに届く日を楽しみに待ちたいと思います。