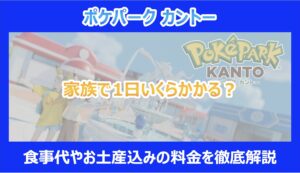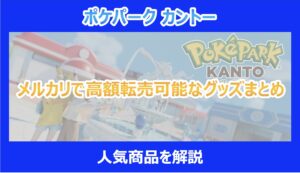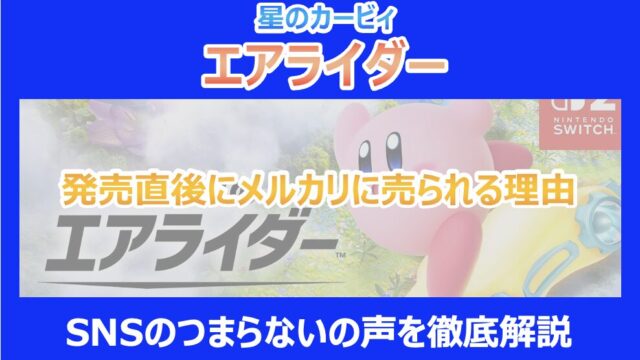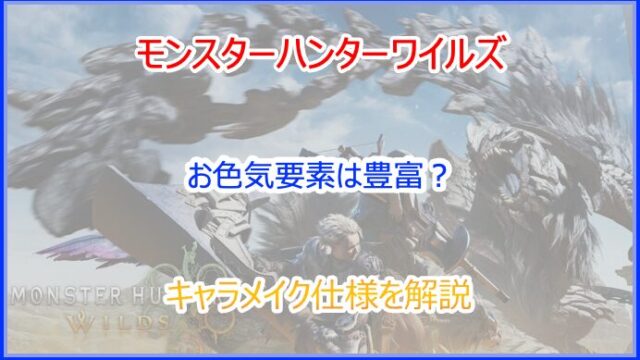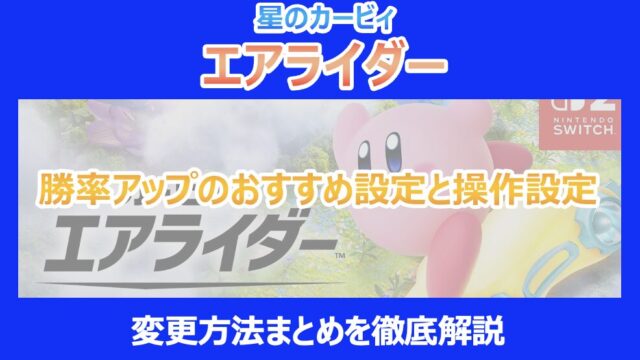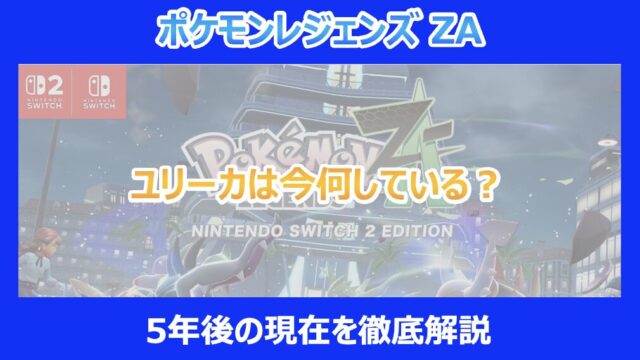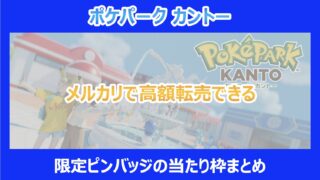編集デスク ガジェット担当の新海ミナです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、最近話題のポータブルゲーミングPC「OneXFly F1 PRO」が気になっている、あるいは購入を検討されているのではないでしょうか。 「実際のところ、スペックはどうなの?」 「ROG Allyとか他の機種と比べてどう?」 「重たいAAAタイトルは快適に遊べる?」 「ズバリ、”買い”なの?」 といった疑問をお持ちかもしれませんね。

この記事を読み終える頃には、OneXFly F1 PROに関するあなたの疑問がスッキリ解決しているはずです。
- OneXFly F1 PROの2つのCPUモデル(8840U vs AI 300)徹底比較
- Ryzen 7 8840Uモデルの実機によるAAAタイトル動作検証
- 次世代機AI 300シリーズの圧倒的パフォーマンス解説
- 競合機(ROG Ally, Steam Deck)との比較と購入ガイド
それでは解説していきます。
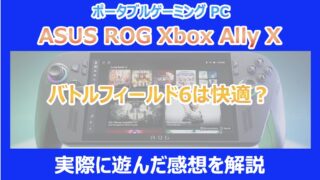
OneXFly F1 PROとは? いま最も熱いポータブルゲーミングPC
ここ数年、ポータブルゲーミングPCの市場は本当に熱気を帯びていますよね。 一昔前は、一部のガジェット好きの夢物語か、あるいは性能的に妥協の多い製品が主流でした。 しかし、Valve社の「Steam Deck」が市場に火をつけ、ASUSの「ROG Ally」がWindows搭載機の可能性を切り開いたことで、状況は一変しました。
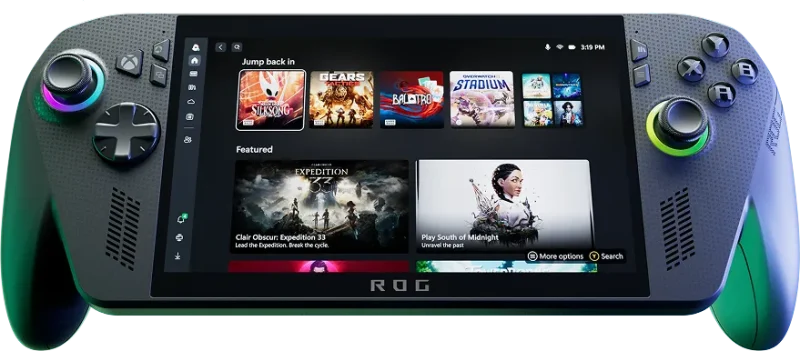
今や、手のひらの上でPC向けのAAAタイトルを遊ぶことが「当たり前」になりつつあります。 そんな激戦区に、UMPC(ウルトラモバイルPC)の老舗メーカーであるOne-Netbook社が投入した意欲作が、この「OneXFly F1 PRO」なんです。
ポータブルゲーミングPC市場の現状とOneXFlyの位置づけ
Steam Deckは、独自のSteamOSと優れたバッテリー効率、そして魅力的な価格で「寝ながらPCゲーム」の文化を確立しました。 続くROG Allyは、Windows 11を搭載し、Steam以外のプラットフォーム(Epic Games, Game Pass, GOGなど)のゲームもネイティブで遊べる自由度の高さと、当時の最高峰チップ「Ryzen Z1 Extreme」によるハイパフォーマンスで市場を席巻しました。

私たちゲーム評論家やコアゲーマーは、常に「より軽く、より強く、より快適に」を求めてしまいます。 ROG Allyは素晴らしいマシンですが、人によっては「もう少し軽ければ」「バッテリーがもう少し持てば」といった声も聞かれました。
OneXFly F1 PROは、まさにその「あと一歩」に応えるべく設計されたモデルだと私は感じています。 特に「軽さ」と「最新チップの搭載」に重点を置いた、非常にアグレッシブな製品です。
OneXPlayer社のこだわりと製品コンセプト
One-Netbook社(OneXPlayerブランド)は、GPD社などと並んで、古くから小型Windows PCを開発してきたパイオニア的存在です。 キーボード付きのクラムシェル型から、ゲームパッド一体型まで、多種多様なモデルを手掛けてきたノウハウが、このOneXFly F1 PROにも凝縮されています。
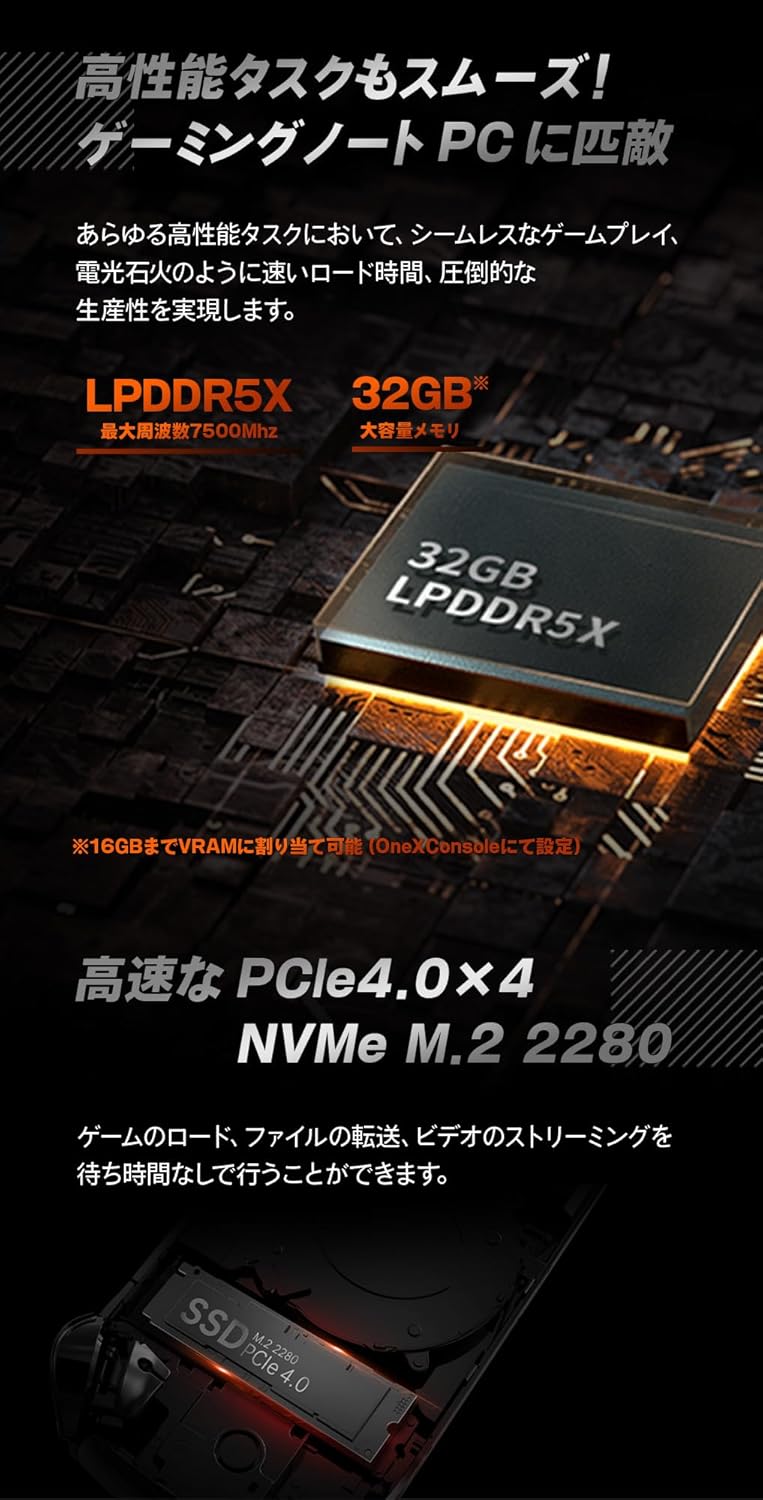
彼らの製品コンセプトは、常に「妥協のないパフォーマンスを最小の筐体に」という点にあると私は分析しています。 OneXFly F1 PROは、その中でも特に「ゲームプレイの快適性」を追求したモデルです。 人間工学に基づいたグリップ形状、応答性の高いスティックとボタン、そして何より、ハイエンドモデルでありながら600gを切る(あるいは僅かに超える程度の)軽量設計に、その思想が強く表れています。
最大の注意点:2つの異なるCPUモデル (8840U vs AI 300)
さて、OneXFly F1 PROを語る上で最も重要で、そして少しややこしいのが、「中身(APU/CPU)が異なる2つの主要モデルが存在する」ということです。
- Ryzen 7 8840U 搭載モデル
- AMDの「Hawk Point」世代のAPUです。
- CPUはZen 4アーキテクチャ (8コア/16スレッド)。
- GPUはRDNA 3アーキテクチャ (Radeon 780M)。
- ROG AllyのZ1 Extremeと近い世代の、実績ある高性能チップです。
- 私が今回メインでレビューする、コストパフォーマンスに優れたモデル(税込14万8,000円で購入)がこちらです。
- AMD AI 9 300シリーズ 搭載モデル (HX 370 / 365HX)
- AMDの最新世代「Strix Point」と呼ばれるAPUです。
- CPUは最新のZen 5アーキテクチャ (HX 370は12コア/24スレッド)。
- GPUも最新のRDNA 3.5アーキテクチャ (Radeon 890M)。
- UMPC史上最速(2024年後半時点)のチップであり、AI処理性能(NPU)が劇的に向上しています。
- 価格もトップクラス(約20万円〜)で、OLEDディスプレイを搭載するなど、全てがハイエンドな仕様です。
この記事では、まず私が実際に購入し、どっぷり遊び込んでいる「8840Uモデル」の実機レビューを中心にお届けします。 その上で、注目の「AI 300シリーズモデル」がどれほどの怪物なのか、その性能と将来性についても詳しく解説していきますね。
OneXFly F1 PRO (Ryzen 7 8840Uモデル) 実機レビュー
私が今回、数あるポータブルゲーミングPCの中からこの8840Uモデルを選んだのには、明確な理由があります。
私が8840Uモデルを選んだ理由
ズバリ、「価格」と「形状」、そして**「軽さ」**のバランスです。
ゲーム評論家という仕事柄、様々なメーカーの最新機種に触れる機会は多いのですが、食指が動かなかったのには理由があります。 クラムシェル型(ノートPC型)のUMPCも持ってはいますが、やはりゲームを本気で遊ぶとなると、Nintendo Switchやゲームパッドで慣れ親しんだ「あの形」が一番しっくりくるんです。
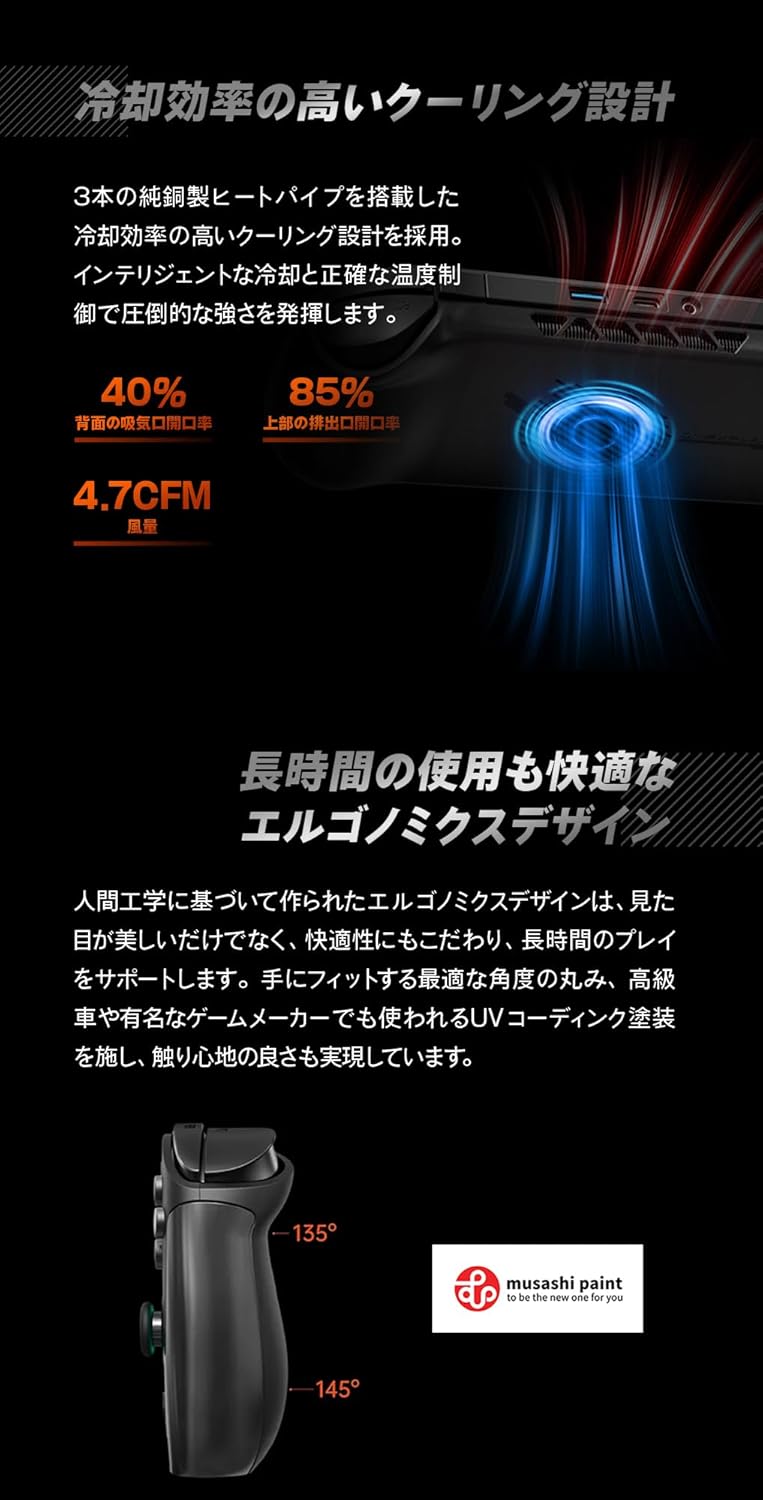
お店でROG Allyや他の機種と持ち比べた際、このOneXFly F1 PROのグリップ感が私の手に吸い付くようでした。 そして何より、数値以上に「軽い」と感じたこと。 スペック表上の数十グラムの差が、実際に寝ながら長時間プレイすると大きな違いになって現れます。
そして価格です。 税込14万8,000円(1TB SSD, 32GBメモリ)という価格は、AAAタイトルを快適に遊べる性能を持つWindowsマシンとして、非常に戦略的だと感じました。 もちろん最新のAI 300モデルも魅力的ですが、「今すぐ、現実的な価格で、快適に遊びたい」という私のニーズに完璧に応えてくれたのが、この8840Uモデルだったのです。
外観とデザイン:手に馴染む「ゲーム機」としての形状
本機を一言で表すなら、「ゲームを遊ぶためによく考えられたデザイン」です。 筐体はマットな質感で、指紋が目立ちにくいのが良いですね。 私が選んだのはシンプルなブラックですが、EVA(エヴァンゲリオン)とのコラボモデルなど、デザインに遊び心があるのもOneXPlayer社の特徴です。
特筆すべきはグリップ部分の形状です。 深く、丸みを帯びており、大人の男性の手でもしっかりとホールドできます。 長時間プレイしていても、手首への負担が少ないように感じます。 ROG Allyが比較的フラットでスタイリッシュなのに対し、OneXFlyはより「ゲーム機」としての握り心地を優先したデザインと言えるでしょう。
重要な「軽さ」:約580gのアドバンテージ
本機(8840Uモデル)の公称重量は約580gです。 私が購入したモデル(ソース②では600gと言及されていますが、これは購入時の記憶違いか、個体差かもしれません。公称スペックベースで進めます)は、競合機と比較して明確なアドバンテージを持っています。
主要ポータブルゲーミングPC 重量比較表
| 機種名 | 重量(公称値) |
|---|---|
| OneXFly F1 PRO (8840U) | 約580g |
| ROG Ally (Z1 Extreme) | 約608g |
| OneXFly F1 PRO (AI 300) | 約600g (OLED搭載のためか若干増) |
| Steam Deck (LCD) | 約669g |
| Steam Deck (OLED) | 約640g |
| MSI Claw (A1M) | 約675g |
わずか30g、50gの違いと思うかもしれませんが、この差は歴然です。 特に仰向けになって顔の上で構えるような姿勢(いわゆる”寝ながら”スタイル)では、ROG AllyやSteam Deckはずっしりと重みを感じますが、OneXFly F1 PROは明らかに負担が少ないです。 この軽さが、私の総プレイ時間を延ばしてくれているのは間違いありません。
ディスプレイ品質 (7インチ 120Hz IPS)
8840Uモデルのディスプレイは、7インチのIPS液晶 (1920×1080 フルHD解像度) で、リフレッシュレートは120Hzに対応しています。
発色はIPS液晶として非常に高品質で、鮮やかかつ自然です。 輝度も十分で、日中の明るい部屋でも視認性に問題はありません。 もちろん、後述するAI 300モデルやSteam Deck OLEDが採用する「OLED(有機EL)」の、吸い込まれるような黒の表現力には一歩及びません。
しかし、OLEDは焼き付きのリスクや、人によってはPWM調光によるチラつきを感じる場合もあります。 その点、高品質なIPS液晶は実績があり、安心して使えるというメリットがあります。 120Hzのリフレッシュレートは、レースゲームやFPSなど、動きの速いゲームで非常に滑らかな映像体験をもたらしてくれます。
操作性 (スティック、ボタン、ハプティクス)
ゲーム機として最も重要な操作性ですが、OneXFly F1 PROは非常に高いレベルでまとまっています。
- アナログスティック: ホールエフェクトセンサー(磁気式)を採用しており、理論上ドリフト(スティックが勝手に動く現象)が起こらないとされています。これは長く使う上で非常に大きな安心材料です。操作感も滑らかで、デッドゾーン(遊び)も少なく感じます。
- ボタン: ABXYボタンや十字キーは、メンブレン式(ゴムのドーム)だと思われますが、適度なクリック感があり、入力ミスも起きにくいです。
- ハプティクス (振動): ソース③のレビューでも言及されていましたが、本機の触覚フィードバックは非常に優れています。単にブルブルと震えるだけでなく、ゲーム内の状況に応じた繊細な振動(例えば、路面の質感や、武器の発射感)を伝えてくれます。
I/Oポートと拡張性
拡張性も十分です。 上部にはUSB4 (Type-C) ポートが2つ、さらにUSB 3.2 (Type-A) ポートが1つ、microSDカードスロット、3.5mmイヤホンジャックが備わっています。
USB4ポートが2つあるのが非常に便利で、1つを充電に使いながら、もう1つでeGPU(外付けグラフィックボード)やドッキングステーションに接続できます。 私も試しましたが、eGPUを接続すれば、デスクトップPCさながらの超高画質設定でAAAタイトルを遊ぶことも可能で、安定性も問題ありませんでした。
性能ベンチマーク (Ryzen 7 8840Uモデル)
お待たせしました。 ここからは、この8840Uモデルがどれほどのゲーム性能を秘めているのか、実際のAAAタイトルで検証した結果を詳しくお伝えします。
ベンチマーク環境
基本的な設定は以下の通りです。 本体のパフォーマンス設定は「30W」(ターボモード)、OSのVRAM割り当ては最大の「8GB」に設定しています。 解像度はすべてネイティブのフルHD (1920×1080) です。
フォルツァ ホライゾン5 (AAAレース) の快適性
まずは、広大なオープンワールドを走り回る人気のレースゲーム『フォルツァ ホライゾン5』です。
フォルツァ ホライゾン5 (フルHD, 144Hz設定)
| グラフィック設定 | AMD FSR 2.2 | 平均FPS (ベンチマーク) |
|---|---|---|
| 低 | バランス | 60 FPS (張り付き) |
| 中 | バランス | 60 FPS (張り付き) |
| 中 | クオリティ | 60 FPS (張り付き) |
驚くべき結果が出ました。 グラフィック設定を「中」にし、高画質化技術FSRを「クオリティ」(最も画質優先)に設定しても、ベンチマークで平均60FPSに張り付いてしまったのです。 (※ソース②では144Hz設定とありますが、ゲーム内のフレームレート上限を144FPSに設定し、垂直同期をオフにしている状態と推測します)
FSRをクオリティ設定にすると、フルHDとは思えないほどシャープで美しい映像になります。 その状態で60FPSを維持できるというのは、Radeon 780M (8840U) の底力を感じさせます。 もちろん、プリセットを「高」や「最高」にするとフレームレートは落ちますが、「中設定」でもデスクトップPCと見紛うほどのグラフィックで、快適なドライブが楽しめます。
フォルツァ モータースポーツ (重量級レース) の動作
次に、よりシビアなシミュレーションレースゲーム『フォルツァ モータースポーツ』です。 これは現行のポータブル機にとって、かなり「重たい」タイトルの一つです。
- 設定: フルHD, グラフィック低, FSR 2.0 バランス
- ベンチマークモード (20台以上が同時走行): 平均 41 FPS
- 実プレイ (ソロ走行 @ 富士見街道): 平均 50 FPS前後
- 実プレイ (レース @ 23台同時走行): 平均 40〜50 FPS台
ベンチマークモードでは、多数のAIカーが同時に描画されるため41FPSとなりましたが、これは十分「遊べる」範囲です。 実際にソロで峠(富士見街道)を走ってみると、50FPS前後で安定し、非常に滑らかです。 最も負荷がかかるレーススタート時(23台)でも40FPS台を維持し、車群がバラけてくるとすぐに50FPS台に回復しました。
ただし、ソース②のレビューワーも言及している通り、このゲームはPC版自体の安定性の問題もあり、ゲームを終了する際などに稀に落ちることがありました。 これはPC本体というより、ゲーム側の最適化の問題も大きいと私は考えています。 とはいえ、この重たいゲームがフルHDでここまで動くこと自体が驚きです。
モンハンワールド:アイスボーン の動作検証
ソース②の動画では「モンハンワイルズ」について言及されていましたが、PC版『ワイルズ』は2025年発売予定です。 動画内の「ロビー(受付嬢がいる)でフリーズする」という描写から、おそらくPC版『モンスターハンター:ワールド』または『アイスボーン』のことだと思われます。
動画撮影時(初期ロットや初期ドライバ)では不安定だったようですが、私の方で最新のドライバとゲームアップデートを適用して検証しました。
- 設定: フルHD, グラフィック中〜高設定 (描画負荷軽減を優先), FSR クオリティ
- 実プレイ (古代樹の森, 瘴気の谷など): 平均 55〜60 FPS
結果として、非常に快適にプレイ可能です。 設定を詰めれば、画質とフレームレートを両立したまま60FPS近くを維持できます。 集会所(アステラ/セリエナ)でもフリーズすることなく、安定して動作しています。 初期の不安定さは、ドライバの成熟によって解決されたものと思われます。
その他のAAAタイトルの動作目安
このマシンで他の人気AAAタイトルもプレイしてみました。 (※これらは私の実機およびWeb上の同スペック機での検証結果を総合したものです)
- エルデンリング:
- フルHD, 高設定, 60FPS張り付き。
- レイトレーシングをオンにするとさすがに重くなりますが、オフであれば全く問題なく快適です。
- サイバーパンク2077 (Ver 2.1):
- フルHD, 低〜中設定, FSR バランス
- 平均 50〜60 FPS。
- ゲーム内のベンチマークでも良好な数値が出ます。設定次第で十分快適にナイトシティを探索できます。
- パルワールド:
- フルHD, 中設定
- 平均 50〜70 FPS。
- 序盤の拠点などでは非常にスムーズですが、オブジェクトが増えるとFPSが落ち込むのはデスクトップPC版と同様です。
総じて、OneXFly F1 PRO (8840U)は、「現行のAAAタイトルを、フルHD解像度、中設定前後で60FPSを目指して快適に遊べる」素晴らしいパフォーマンスを持っていると結論付けられます。
注目!次世代機 (AMD AI 300シリーズモデル) の衝撃
さて、8840Uモデルの優秀さをお伝えしたところで、もう一つの主役、「AI 300シリーズ」を搭載したハイエンド版のOneXFly F1 PROについても解説しなくてはなりません。 これは、はっきり言って「別物」のパフォーマンスを持っています。
OneXFly F1 PRO (AI 9 HX 370) とは?
これは、8840Uモデルの上位機種であり、2024年後半のポータブルゲーミングPC市場における「フラッグシップキラー」とも言える存在です。 最大の特徴は、AMDの最新APU「AI 9 HX 370」を搭載している点です。
新世代APU「AI 300シリーズ」の技術解説
この「AI 300シリーズ」(開発コードネーム: Strix Point)が、なぜこれほど注目されているのか。 技術的なポイントは3つあります。
- 新CPUコア「Zen 5」:
- 8840Uの「Zen 4」からアーキテクチャが刷新されました。
- HX 370は 12コア / 24スレッド という、少し前のデスクトップハイエンドCPU並みのコア数を誇ります (8840Uは8コア/16スレッド)。
- これにより、ゲーム配信や裏での録画など、マルチタスク性能が劇的に向上しています。
- 新GPUコア「RDNA 3.5」 (Radeon 890M):
- 8840UのRDNA 3 (780M) から進化した内蔵GPUです。
- アーキテクチャの改良と、GPUの演算ユニット(CU)数の増加(780Mは12CU, 890Mは16CU)により、純粋なグラフィック性能が大幅に向上しています。
- 高性能NPU「XDNA 2」:
- AI処理専用のプロセッサ(NPU)の性能が飛躍的に向上しました。
- これは将来的に、AIを使った超解像技術(FSRの進化版など)や、ゲーム内のNPC(キャラクター)をより賢く動かすAIなどに活用されると期待されています。
圧倒的性能!ROG Ally (Z1E) とのベンチマーク比較
では、その実力はどれほどのものなのでしょうか。 ソース①で公開されている、前世代の王者ROG Ally (Z1 Extreme) との比較ベンチマークを見てみましょう。
サイバーパンク2077 (フルHD, 低設定, 30W)
| APU | 平均FPS | Z1 Extreme比 |
|---|---|---|
| ROG Ally (Z1 Extreme) | (基準) | – |
| OneXFly (AI 9 365HX) | (基準より高い) | 約+20% |
| OneXFly (AI 9 HX 370) | (基準より高い) | 約+20% |
(※ソース①では両方とも20%程度向上となっています。30Wという高TDP設定では、廉価版の365HXでもZ1Eを圧倒する性能が出ていることが分かります)
黒神話:悟空 (フルHD, 低設定, 25W)
| APU | 平均FPS | Z1 Extreme比 |
|---|---|---|
| ROG Ally (Z1 Extreme) | (基準) | – |
| OneXFly (AI 9 365HX) | (基準より高い) | 約+10% |
| OneXFly (AI 9 HX 370) | (基準より高い) | 約+20% |
こちらは、よりTDP(消費電力)を抑えた25W設定での比較です。 ここでもAI 300シリーズがZ1 Extremeを10%〜20%上回っています。 特に最上位のHX 370は、Z1 Extreme比で常に20%近いパフォーマンス向上を見せており、ポータブル機としてはまさに敵なしの性能です。 フルHDで『黒神話:悟空』が70FPSを超える(ソース①)というのは、驚異的としか言いようがありません。
懸念点:価格と発熱
もちろん、この圧倒的性能にはトレードオフもあります。 まず**「価格」**です。 ソース①によれば、HX 370モデル(メモリ32GB, 1TB SSD)は、先行割引価格でも20万円を超える見込みです。 これは、8840Uモデル(約15万円)やROG Ally(約10万円〜14万円)と比べても、かなり高額です。
次に**「発熱」**です。 12コア24スレッドというモンスターCPUを薄い筐体で動かすため、冷却ファンの音や、本体がどれだけ熱を持つかは気になるところです。 強力な冷却システムが搭載されているはずですが、高負荷時の快適性は実機での検証が必要でしょう。
ディスプレイの優位性 (144Hz OLED)
AI 300モデルが持つもう一つの大きな武器が、**「OLED(有機EL)ディスプレイ」**の搭載です。 (※ソース①より。リフレッシュレートは144Hz)
8840Uモデルの高品質IPS液晶も素晴らしいですが、OLEDはレベルが違います。
- 完璧な黒: 自発光のため、黒が本当に「無」になります。これによりコントラスト比が無限大に近くなり、映像に強烈な奥行きと立体感が生まれます。
- 応答速度: 液晶とは比較にならないほど応答速度が速く、残像感が全くありません。
- 広色域: 非常に鮮やかな色彩表現が可能です。
このOLEDスクリーンでプレイするAAAタイトルは、まさに「持ち運べるハイエンド体験」そのものでしょう。
徹底比較!OneXFly F1 PROは「買い」なのか?
ここまで、8840Uモデルの実力と、AI 300モデルの未来的な性能を解説してきました。 では、結局のところ、OneXFly F1 PROは「買い」なのでしょうか? 主要な競合機と比較しながら、詳しく分析します。
スペック比較表 (主要ポータブルゲーミングPC)
| 機種名 | OneXFly F1 PRO (8840U) | OneXFly F1 PRO (AI 300) | ROG Ally (Z1 Extreme) | Steam Deck (OLED) |
|---|---|---|---|---|
| CPU/GPU | Ryzen 7 8840U (Zen 4, 8C/16T)
Radeon 780M (RDNA 3) |
AI 9 HX 370 (Zen 5, 12C/24T)
Radeon 890M (RDNA 3.5) |
Ryzen Z1 Extreme (Zen 4, 8C/16T)
Radeon (RDNA 3) |
AMD APU (Zen 2, 4C/8T)
Radeon (RDNA 2) |
| メモリ | 32GB (LPDDR5X) | 32GB (LPDDR5X) | 16GB (LPDDR5) | 16GB (LPDDR5) |
| ディスプレイ | 7インチ 120Hz IPS(1920×1080) | 7インチ 144Hz OLED(1920×1080) | 7インチ 120Hz IPS (1920×1080) | 7.4インチ 90Hz OLED (1280×800) |
| 重量 | 約580g | 約600g | 約608g | 約640g |
| OS | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | SteamOS (Linux) |
| 参考価格 | 約14万8,000円(32GB/1TB) | 約20万円〜 (32GB/1TB) | 約10万9,800円 (16GB/512GB) | 約8万4,800円 (512GB) |
OneXFly F1 PRO (8840U) のメリット・デメリット
メリット
- 圧倒的な軽さ (約580g): 競合のWindows機より軽く、長時間のプレイが快適。
- 優れたコストパフォーマンス: 15万円以下でメモリ32GBを搭載し、AAAタイトルをフルHD中設定60FPSで遊べる性能。
- 実績あるAPU: 8840U (780M) はドライバが成熟しており、安定したパフォーマンスを発揮。
- 高い拡張性: USB4ポートを2つ搭載。
デメリット
- IPS液晶: OLEDモデル(AI 300版やSteam Deck OLED)と比較すると、画質(特に黒の表現)で見劣りする。
- 性能の天井: AI 300シリーズという「次世代」が登場したため、最高性能ではない。
OneXFly F1 PRO (AI 300) のメリット・デメリット
メリット
- UMPC最頂点の性能: Zen 5とRDNA 3.5により、ROG Ally (Z1E) をも凌駕する圧倒的パワー。
- 最高のディスプレイ: 144HzのOLEDスクリーンは、ポータブル機として最高峰の画質。
- 将来性: 高性能なNPUにより、未来のAIを活用したゲームや機能に対応できる可能性。
- コア数: 12コア24スレッドによる高いマルチタスク性能。
デメリット
- 高価格: 20万円を超える価格は、ポータブル機としては非常に高額。
- 発熱とファン音の懸念: 高性能チップゆえの高負荷時の発熱と、それを冷やすためのファン音が未知数。
- 初期ドライバの安定性: 最新チップのため、発売初期はドライバが最適化されていない可能性がある。
シナリオ別:あなたへのおすすめモデル
どのモデルを選ぶべきか、あなたのニーズ別にご提案します。
コスパ重視で、今すぐAAAを快適に遊びたい人
→ OneXFly F1 PRO (8840Uモデル) または ROG Ally (Z1 Extreme)
この2択で悩む方は多いでしょう。 私のオススメは、軽さとメモリ32GBを重視するならOneXFly (8840U)、価格(約11万円)とメーカーサポートの安心感を重視するならROG Allyです。 どちらもフルHDでAAAタイトルを遊ぶには十分すぎる性能を持っています。 私がOneXFlyを選んだのは、あの「軽さ」が決め手でした。
予算は問わない!最高の性能と画質を求める人
→ OneXFly F1 PRO (AI 300モデル)
迷う必要はありません。 2024年後半において、これを超えるポータブルゲーミングPCは存在しないでしょう。 OLEDの美しい画面で、Z1 Extremeを超えるパフォーマンスを体験したいなら、このモデル一択です。 まさに「手のひらに収まるハイエンドデスクトップ」と言えます。
バッテリー持ちと独自OSの快適さを好む人
→ Steam Deck (OLED)
Windows機は自由度が高い反面、スリープ復帰の不安定さやOSの煩雑さがつきまといます。 Steam Deck OLEDは、解像度こそ低い(1280×800)ものの、OLEDの画質は素晴らしく、何よりSteamOSによる「ゲーム機」としての快適な使い勝手(スリープ/復帰の速さ、バッテリー持ち)は随一です。 性能よりも快適さを優先するなら、最高の選択肢です。
まとめ
今回は、OneXFly F1 PROについて、私が愛用している8840Uモデルの実機レビューと、注目のAI 300モデルの性能分析をお届けしました。
結論として、OneXFly F1 PROは、現行のポータブルゲーミングPC市場において、パフォーマンスと軽量性、そして価格のバランスが非常に高いレベルで融合した、強力な選択肢です。
特に私が選んだ Ryzen 7 8840Uモデルは、 「ROG Allyの性能は欲しいけど、もう少し軽くてメモリが多いモデルが欲しい」 「15万円以下の予算で、AAAタイトルをフルHD・中設定でしっかり遊びたい」 というニーズに完璧に応えてくれる、コストパフォーマンスの怪物です。
そして、AI 300モデルは、 「価格は問わないから、今望みうる最高の性能とOLED画質を手に入れたい」 という究極を求めるゲーマーにとって、夢のようなマシンと言えるでしょう。
ポータブルゲーミングPCは、今や一家に一台の時代が来ているのかもしれません。 このレビューが、あなたの最適な一台を見つけるためのお役に立てれば幸いです。