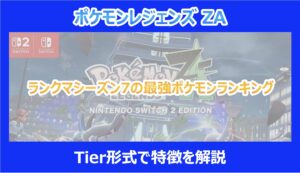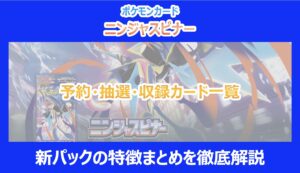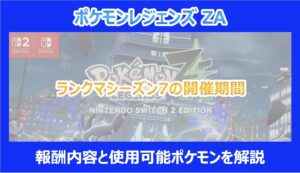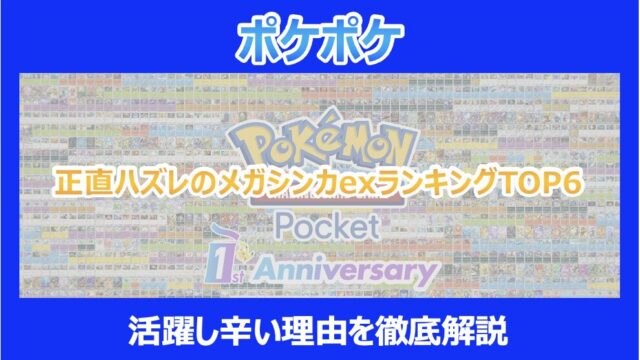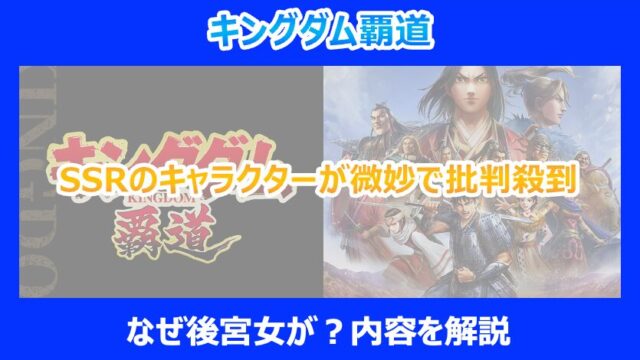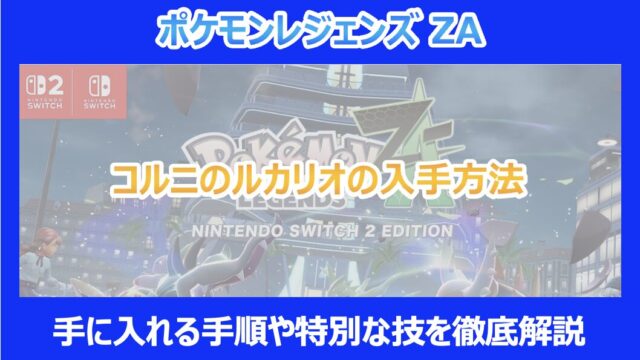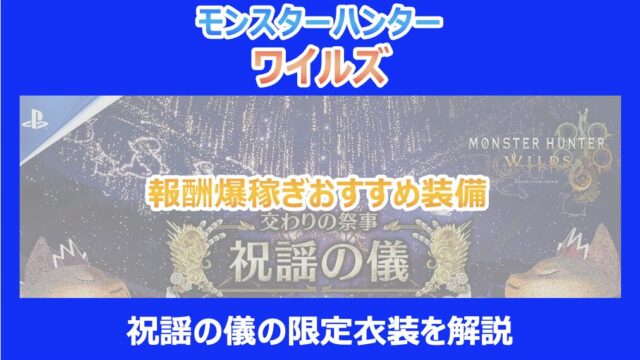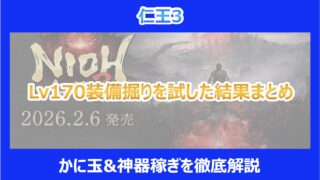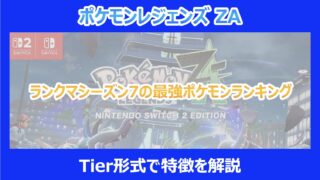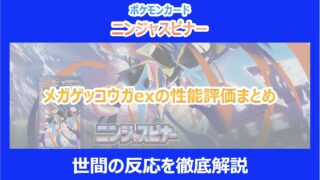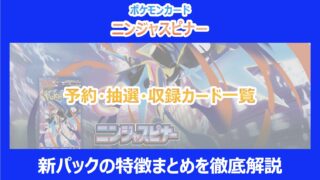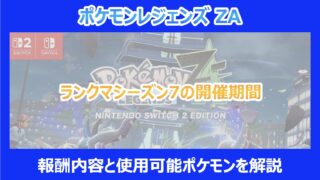ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、先日ニンダイで発表され、2026年3月5日の発売が決定したポケモンの新作スローライフゲーム、『ぽこあポケモン』の最新映像に対する世間の反応が気になっていると思います。 映像公開後、SNSや各種コミュニティはまさに「お祭り騒ぎ」となりましたが、その反応は単純な歓迎だけではないようです。

この記事を読み終える頃には、『ぽこあポケモン』の映像に対して寄せられた期待(良い点)と懸念(悪い点・不穏な点)、そして白熱する考察の数々についての疑問が解決しているはずです。
- 待望の発売日2026年3月5日決定
- 映像から見える「スローライフ」と「クラフト要素」への期待
- 「不穏」と評されるストーリー考察の白熱
- 謎に満ちた新ポケモン(?)たちへの注目
それでは解説していきます。
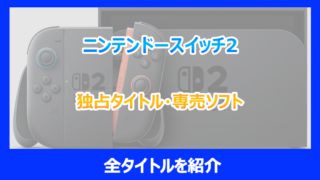
『ぽこあポケモン』最新映像の概要と基本情報
まずは、今回公開された映像から判明した『ぽこあポケモン』の基本的な情報と、ゲームの骨格について整理しておきましょう。 多くのファンがこの発表に驚き、そして期待を寄せています。
2026年3月5日発売決定!ニンダイでの発表内容
ファンの間で長らく噂されていたポケモンの新作スローライフゲーム、通称『ぽこあポケモン』が、先日のニンテンドーダイレクトでついに正式発表されました。

最も大きなニュースは、発売日が2026年3月5日に決定したことです。 映像は約10分という、ニンダイのトリを飾るにふさわしいボリュームで、ゲームの基本的な世界観やシステムの一端が公開されました。
これまでの『ポケットモンスター』本編とは一線を画す、新たな挑戦に多くの注目が集まっています。 私自身、この発表には心が躍りました。 ポケモンという強力なIP(知的財産)が、「スローライフ」というジャンルとどのように融合するのか、非常に興味深い試みです。
映像で確認できたゲームシステム:「スローライフ」と「クラフト」
映像から強く伝わってきたのは、本作が「スローライフ」と「本格的なクラフト」を二本柱としている点です。 主人公(プレイヤー)は、どうやら「変身がうまくないメタモン」のようです。 このメタモンが、荒廃した町を少しずつ開拓し、家具や建物をクラフトしていく様子が描かれました。
映像では、ブロックを積み上げて家を建てる様子や、様々な家具を配置して屋内を装飾するシーンが確認できます。 これは、単なる「どうぶつの森」ライクなスローライフに留まらず、「マインクラフト」や「ドラゴンクエストビルダーズ」のような、自由度の高いサンドボックス型ゲームの要素を強く感じさせます。
また、「生息地を整えるとポケモンが生えてくる(戻ってくる?)」といった表現もあり、環境整備がゲームの重要なサイクルになっていることが伺えます。 ポケモンたちとの交流を楽しみながら、自分だけの町を作り上げていく。 このコンセプトは、多くのゲームファンの心を掴んだようです。
物語の舞台は?「誰もいなくなった」世界の謎
しかし、映像はただ明るいスローライフを描くだけではありませんでした。 物語の舞台は、明らかに「誰もいなくなった」後の廃墟と化した町です。 建物は崩壊し、草木は枯れています。
ナレーションや登場するキャラクター(後述する「もジャンボ博士」)のセリフからは、かつては人間とポケモンが楽しく暮らしていた町が、何らかの理由で荒廃してしまったことが示唆されます。 この「ポストアポカリプス(文明崩壊後)」とも取れる世界観が、本作の大きな特徴であり、同時にファンの間で様々な憶測を呼ぶ「不穏さ」の源となっています。
なぜ誰もいなくなったのか。 人間たちはどこへ行ったのか。 プレイヤーであるメタモンは、この世界で何を目指すのでしょうか。 この謎が、本作の縦軸となるストーリーを牽引していくことになりそうです。
映像に対する世間のポジティブな反応(良い点)
今回の映像公開を受け、SNSやゲームフォーラムは歓喜の声で溢れました。 特に評価が高かった点、ファンが「良い点」として挙げているポイントを、私なりの分析も交えて深掘りしていきます。

『ビルダーズ』や『あつ森』を彷彿とさせる本格クラフト要素への期待
最も多くの好意的な反応が寄せられたのは、やはりクラフト要素です。
自由度の高そうな建築システム
「思ったよりビルダーズできそうで嬉しい」 「屋外はビルダーズっぽくて、屋内はあつ森っぽい」
こうした声が象徴するように、映像で見られた建築システムは、既存の人気クラフトゲームの良いところ取りをしているように見えます。
地面にブロックを敷き詰め、壁を作り、屋根をかける。 さらには立体的な加工も可能なようで、「ここの右当たりとか立体的に作れる感じありがたい」といった、クラフトゲーム熟練者からの鋭い指摘も見られました。
『あつまれ どうぶつの森』が家具の配置(屋外含む)の自由度で人気を博したのに対し、『ドラゴンクエストビルダーズ』シリーズはブロック単位での地形編集や建築の自由度で高い評価を得ました。 『ぽこあポケモン』は、この両方の魅力を併せ持つ可能性があります。
「サンドボックスってマイクラが強いからなかなか新作でないもんね」という意見もあり、高品質なサンドボックスゲームを待ち望んでいた層にとって、本作はまさに渇望していたタイトルと言えるでしょう。 ポケモンという強力なコンテンツが、このジャンルに本格参入することへの期待は計り知れません。
『ビルダーズ』経験者からの熱い視線
特に『ドラゴンクエストビルダーズ』(特に2)のファンからは、「植えてるビルダーズ難民の多さを感じる」「ビルダーズさんはもうこれでいいですになってしまった」といった、半ば冗談、半ば本気の「移住宣言」とも取れる反応が多く見られました。
『ビルダーズ』シリーズは、ストーリー主導型のクラフトRPGとして独自の地位を築きましたが、残念ながら現状では新作の望みは薄いとされています。 そこへ現れた『ぽこあポケモン』が、ストーリー性を持ちつつ(後述する不穏な世界観)、自由なクラフトも楽しめるという、『ビルダーズ』ファンが求めていた要素を色濃く持っていたのです。
「ビルダーアイとかコテとかカッターみたいな便利建築機能はあるのだろうか」と、具体的なシステム面での期待を口にする人も多く、本作が単なるポケモンゲームとしてではなく、純粋なクラフトゲームとしてもしっかりと評価・期待されていることがわかります。
主人公(メタモン)の可愛らしさと便利屋としての役割
本作の主人公(プレイヤーの分身)がメタモンである、という点も非常に好評です。
変身がうまくないメタモンの愛嬌
映像では、メタモンが他のポケモンに変身しようとするものの、顔だけはメタモンのまま、という愛嬌のある姿が描かれています。

「メタモンの変身可愛い」 「変身があまりうまくない個体なのかな」 といった反応が多く、この「ちょっとドジなメタモン」というキャラクター造形が、プレイヤーの心を掴んでいます。
完璧に変身できるメタモンではなく、あえて「うまくない」という設定にしたことで、プレイヤーの感情移入を誘い、スローライフの主役としての愛着を生み出すことに成功していると言えるでしょう。 「ぬいぐるみ欲しい」「ポケセンで売ってくんないかな」という声も早くも上がっており、キャラクタービジネスとしての展開も万全のようです。
ポケモンと会話できる通訳機能
メタモンが主人公であることのもう一つの利点は、「ポケモンとの会話」です。 「メタモンだから普通にポケモンと会話できるのうまいよな」 「ポケモン結構喋るんだな」 という反応の通り、本作ではメタモンが他のポケモンの言葉を(おそらくプレイヤーに)通訳してくれるようです。
これにより、従来作では「ピカピカ」「フシフシ」といった鳴き声でしか表現されなかったポケモンたちの意思や感情が、よりダイレクトにプレイヤーに伝わります。 これはスローライフゲームにおいて、住民(ポケモン)との交流を深める上で非常に重要な機能です。 ポケモンたちが何を考え、何を求めているのかがわかることで、クラフトのモチベーションにも繋がるでしょう。
個性豊かな登場ポケモンたち
映像では、主人公のメタモン以外にも、魅力的なポケモンたちが登場しました。
メインキャラ抜擢の「もジャンボ博士」
特に注目を集めたのが「もジャンボ博士」です。
「もジャンボがメインキャラに抜擢されると思ってなかったから嬉しい」 「絶対にお前が満足する開発をしてやるからな」 「人生で1回はこういうもジャンボみたい欲がすごい勢いで満たされてしまった」 など、発表からわずかな時間で熱狂的なファンを生み出しています。
映像での彼は、丸メガネをかけ、穏やかで知識が豊富そうな、まさに「博士」といった風情を醸し出しています。 「老博士っぽい見た目」「リアクション大きめなのも可愛い」と、そのキャラクターデザインも好評です。 彼が「誰もいなくなった」世界で何を研究し、プレイヤー(メタモン)をどう導くのか、ストーリーの鍵を握る重要人物であることは間違いありません。 「博士、100年は生きてもらうぞ」というファンの悲痛な(?)叫びは、彼が背負っているかもしれない「不穏さ」(後述)への裏返しでもあるのでしょう。
可愛いメタモンのコスプレ(ジムリーダー衣装など)
主人公のメタモンには「お着替え要素」もあるようです。 映像では「ジムりのコスプレ」や「お天場な人魚なメタモン」など、様々な姿が確認できました。 「メタモンカスミいたけどこれ楽のジムりメタモン期待していいのか?」 「原作主人公衣装もあると嬉しい」 「ライバルたちの衣装もくれ」 と、過去作のオマージュを含めた衣装(変身)のバリエーションにも期待が寄せられています。 これはコレクション要素としても、マルチプレイでの自己表現としても、非常に魅力的な機能です。
マルチプレイ(おすそわけ通信)への期待
本作は「最大4人マルチか」「お裾分け通信ありがたいな」という反応の通り、マルチプレイにも対応しています。 公式情報(という設定)では「真っさな町でのみ行うことができ最大2名で遊ぶことができます」という補足もありましたが、映像では4人で遊んでいるように見えるシーンもありました(※このあたりは情報が錯綜している可能性も考慮しつつ、ファンは期待しています)。
『あつ森』や『ビルダーズ』がマルチプレイによって遊びの幅が大きく広がったように、友達と一緒に広大な世界をクラフトし、ポケモンと触れ合える機能は、本作の寿命を大きく延ばす要素となるでしょう。 「家族分慌ててに買わなくて良さそうだ」という現実的な安堵の声もあり、おすそわけプレイの手軽さにも期待が集まります。
ポケパークや短編映画のような懐かしさを感じる雰囲気
「ポケン味とポケパーク味を感じてすごく楽しみ」 「女性の声でポケモンしかいない世界のナレーションしてるのがちょっぴり同時上映短編映画っぽかった」 といった意見も見られました。
『ポケパーク』シリーズは、ポケモンたちが主役のアクションアドベンチャーゲームであり、ポケモン同士の交流がメインでした。 また、かつてのポケモン映画と同時上映されていた短編作品は、ポケモンたちの言葉(字幕)で進行する、ほのぼのとした(時には少し切ない)物語が特徴でした。
本作の「メタモン(ポケモン)が主人公」「ポケモンと会話できる」「人間が(ほぼ)いない世界」という設定が、これらの作品を彷彿とさせ、古くからのポケモンファンにとっては「懐かしさ」や「安心感」を与えているようです。 戦闘と育成がメインの本編とは異なる、『ポケモン』のもう一つの魅力を引き出す作品になるのではないか、という期待感が高まっています。
映像に対する世間のネガティブ・懸念点(悪い点・不穏な点)
ポジティブな反応が大多数を占める一方で、映像の随所に散りばめられた「謎」や「不穏な要素」が、ファンの間で大きな議論と懸念を呼んでいます。 これらは「悪い点」というよりは、「ストーリーへの興味を強く惹きつけるフック」として機能していますが、同時にシリアスな展開を予感させるものでもあります。

「誰もいなくなった」世界の真相は?ポストアポカリプス的な世界観
最も多くの考察を集めているのが、この世界観そのものです。
廃墟と化した町並み
「明らかになんかあったとしか思えない町」 「建物が崩壊していて草は枯れている」 「ダイレクトにぶっ壊れたポケ出てきて笑った」 映像に映る世界は、スローライフという言葉から連想される穏やかな自然とはかけ離れた、「後輩」した風景です。 ファンは、この町がなぜこうなったのか、その原因を探ろうと必死です。
「割と本格的なポスト赤ポリプスっぽい」という感想の通り、ただ人が去っただけではなく、何らかの災害や事件があったことを強く匂わせています。 「ガサごそ中はゴミばっかり」という描写も、文明が失われた後の世界のリアルさを感じさせます。
人間は本当に戻ってくるのか?
もジャンボ博士は「人もポケモンも楽しく暮らす街に」という願いを口にしますが、映像には人間らしき姿はほとんど映りません。 「人間たちも戻ってくるかもしれん」「人間もいるかもしれないのね」という期待の声もありますが、一方で、 「人間たちは(戻ってこないのでは?)」 「メタモンの持ち主死んでるんじゃないの?」 「多分人間は戻ってこないから博士もジャンボの願いが叶わないのがもう分かって辛いんだが」 といった、悲観的な予測も多く見られます。
スローライフを謳いながら、その根底には「喪失感」や「孤独」といったテーマが流れている可能性があり、これが本作の独自の深みを生むのではないかと、私は分析しています。
謎の「変わった姿のポケモン」たち
映像の最後、そして公式ページで紹介された「変わった姿のポケモン」たちは、この「不穏さ」を象徴する存在です。 「リージョンフォーム」とも違う、独特の雰囲気を持つ彼らに、ファンの考察は集中しています。
「薄色ピカチュウ」の正体(幽霊説、改造ポケモン説)
「白いピカチュウは幽霊といい」 「薄色。記憶がないとかやっぱ幽霊か何かなのでは?」 公式(という設定)の説明で「記憶がない」「儚さを感じる」とされたピカチュウは、その名の通り色彩が薄く、どこか弱々しい印象を与えます。
「尻尾が焼けに小さい」「弱ってるんかな?」という観察もあり、通常のピカチュウとは明らかに異なる存在です。 「メスのピカチュウだし」「窓際のお嬢様じゃな」「1人称私発酵。ピカチュウ可愛い」と、そのキャラクター性(儚げなお嬢様)に惹かれる声も多い一方で、その出自については不穏な説が飛び交っています。
「ミミッキュの色違いと同じ色ですか?」という指摘や、「改造ポケモン的なのだったりしないよな」という懸念も。 後述する「グレンタウン説」と関連し、「火山灰をかぶって白くなった説」も有力視されています。
「コケむしたカビゴン」の意味(ラピュタのロボット兵?)
ピカチュウと共に映し出されたカビゴンは、全身がコケに覆われています。
「カビゴンはかびてるし。やばそう感が強い」 「カビゴンはずっと寝ててコケ生えただけに見えるけど」 という比較的のんきな意見もありますが、 「なんか最後のカビゴンがラピュタにいるロボット兵みたいだった」 「最終兵器みたいな起こすとやべえカビゴかもしれん」 と、単なる眠りすぎたカビゴンではなく、何か特殊な役割を持つ存在ではないかという考察もあります。
『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』のガーディアンや、『天空の城ラピュタ』のロボット兵のように、古代のテクノロジーや自然の守り神といった、ストーリーの根幹に関わる存在かもしれません。 「笛で起きるかしら」という、原作ネタを交えた心配の声も印象的です。
「カラフルなドーブル」の役割
「カラフルなドーブル」も登場しました。 「ドーブルでペイント機能解放だな、これ」 「ペインター ドーブル矢印汚れちゃったのか」 と、こちらはゲームシステム(ペイント機能)に関わるキャラクターではないか、という推測が主流です。 「顔にかかったインクを髭に見立てるセンスよ」「ドーブル先生は誰もチーフなのかな?」と、そのデザインも好評のようです。
ただ、「薄色」や「コケむし」と同様に、彼もまた「変わった姿」の一体であり、何らかの事情を抱えている可能性は否定できません。
ストーリーはシリアス?『ビルダーズ』のトラウマ再来か
これらの「不穏な要素」から、多くのファンが『ドラゴンクエストビルダーズ』シリーズ、特に初代『ビルダーズ』のストーリーを連想しています。
「ほらやっぱり不穏だったよ」 「ビルダーズはどっちも後編に行くほど不穏でシリアス」 『ビルダーズ』は、明るいビジュアルとクラフト要素の裏で、「世界が魔王に支配された後のバッドエンドから始まる」という非常にシリアスな物語が展開されました。 特に初代の特定の章(患者のエピソードなど)は、多くのプレイヤーにトラウマを植え付けたと言われています。
『ぽこあポケモン』が『ビルダーズ』ライクなゲーム性であることから、「ポケモンでまさかあのトラウマを繰り返すのでは?」という懸念が生まれています。 「子供が遊んでするような内容にはならんとは思う」「ポケモンではしないはず」と信じたいファンの気持ちと、「不穏だけどほのぼ押しされてるし大丈夫じゃないかな」という希望的観測が入り混じっています。 私個人としては、ポケモンという全年齢対象のIPである以上、過度に陰惨な展開にはならないと信じていますが、『ビルダーズ』がそうであったように、ギャップこそが物語の魅力になる可能性も秘めています。
仄めかされる「グレンタウン説」
世界が荒廃した理由について、現在最も有力視されている考察が「グレンタウン説」です。
火山噴火と後輩した世界
「赤緑の頃はグレンタウン問題なく行けるんだけど、近銀の時代になると噴火で壊滅してるんすよ」 「グレン島なら溶岩や地震でボロボロでも納得」 原作の『ポケットモンスター 金・銀』では、『赤・緑』から3年後、カントー地方のグレンタウン(グレン島)は火山の噴火によって壊滅的な被害を受け、ポケモンセンター以外の施設が失われています。
『ぽこあポケモン』の荒廃した風景が、このグレンタウンの未来、あるいは「もっとでかい噴火があった」後の世界ではないか、という考察です。 「薄色ピカチュウ」の白い体色も、「火山灰をまとってるのかな」「振り積もった火山灰を洗い流してるのか」と、この説を補強する材料と見なされています。 また、「あの辺というかマサラとグレンタウンの間にもんじラが野生で出たはず」という指摘もあり、キーキャラクターである「もジャンボ博士」との関連性も疑われています。
ポケモン屋敷とミュウツーの関連は?
グレンタウンといえば、火山だけでなく「ポケモン屋敷」の存在も重要です。
ポケモン屋敷は、最強のポケモン「ミュウツー」が人工的に生み出された場所であり、多くの実験記録が残されていました。 「グレン島は火山以外にもミュウツーが作られたポケモン屋敷合あった曰く付きの場所だからな」 「薄色ちゃん」「元グレンタウン説と合わせてポケモン屋敷関連の改造ポケモン的なのだったりしないよな」 と、「薄色ピカチュウ」のような特殊な個体が、ポケモン屋敷の研究と関連しているのではないか、という深読みも始まっています。
さらには、「主人公が負けるかなんかしてレインボーロケット段差が爆端しちゃった世界の関東とか」「ミュウツーが破壊の限りを尽くして滅びた関東とか」といった、本編とは異なる「if」の世界線を想定する声もあり、考察は尽きません。
「マッサラタウン」との関連性は?
もう一つの舞台に関する考察として、「マサラタウン説」も浮上しています。 これは、マルチプレイの説明(という設定)にあった「真っさな町で飲み行うことができ」という一文が発端です。 「ねえ。これマサラタウンじゃ」 「マサラタウン?いやいやいや」 「壊れた図鑑やポケの外観はほぼFRLG(ファイアレッド・リーフグリーン)だから関東よな」
「マッサラ」と「マサラ」。 これが単なる誤字なのか、意図的な当て字なのかは不明ですが、カントー地方の始まりの町であるマサラタウンを連想させるには十分でした。 グレンタウンとマサラタウンは地理的にも近いため、「グレンタウンの噴火の影響がマサラタウンにまで及び、後輩した」というシナリオも考えられます。 「マッサラタウンにさよなら。バイバイ」と、有名なセリフをもじった反応もありました。
『ぽこあポケモン』今後の注目ポイントと考察
期待と不安(不穏)が入り混じる『ぽこあポケモン』。 発売までまだ時間がありますが、ゲーム評論家の視点から、今後の注目ポイントと、さらに踏み込んだ考察を加えておきます。
ゲームのタイトル「ポコアポコ」の意味とは?
映像を見たファンからは「ポコってどういう意味なんだろ?」という素朴な疑問も上がっていました。 これに対し、「ポコアポコじゃなくて音楽用語があって少しずつって意味なんだ」という回答が寄せられています。
音楽用語の “poco a poco”(ポコ・ア・ポコ)は、イタリア語で「少しずつ、徐々に」という意味を持ちます。 これは、荒廃した世界を「少しずつ」開拓し、ポケモンたちとの絆を「少しずつ」育んでいく、本作のゲーム性を完璧に表したタイトルと言えるでしょう。 このタイトル自体が、ゲームの核となる体験をプレイヤーに約束しているのです。 非常に秀逸なネーミングセンスだと感じます。
クラフト要素の具体的なシステム(ビルダーアイ的な機能は?)
ポジティブな反応の項でも触れましたが、クラフトゲームとしての快適性がどれほどのものかは、本作の評価を左右する重要なポイントです。 『ビルダーズ2』で絶賛された、三人称視点と一人称視点(ビルダーアイ)をシームレスに切り替え、細かい調整を可能にするシステム。 あるいは、ブロックや家具を一括で設置・破壊・移動できるような便利機能(コテ、カッターなど)。
これらの「クラフトゲームの快適なお作法」がどれだけ搭載されているか。 ポケモンという強力なIPに甘えることなく、サンドボックスゲームとしての完成度をどこまで高めてくるか。 開発が「光栄テ的もなんや」という反応もありましたが(※おそらくコーエーテクモゲームスとの共同開発を指す憶測)、もしそうであれば『ゼルダ無双』や『FE無双』などで見せた高いアクションゲーム開発力とはまた異なる、丁寧なシステム構築が求められます。 続報でのシステム詳細の公開が待たれます。
登場ポケモンは全種類実装されるのか?DLCの可能性
「ジェネリックポケパークにしたいから今出てる全てのポケモン出してほしい」 これは、多くのポケモンファンの偽らざる願いでしょう。 現在、ポケモンの総数は1000種類を超えています。 これら全てをスローライフゲームに実装し、それぞれに固有のアクションや交流パターンを用意するのは、想像を絶する物量です。
現実的には、ゲームの舞台となる地方(カントー地方?)に縁のあるポケモンや、スローライフやクラフトというテーマに合ったポケモンが厳選されて登場する可能性が高いと私は見ています。 しかし、ファンからは「DLC累計5万までなら出す」「DLCは登場ポケモン追加経過なあるなら」と、有料DLC(ダウンロードコンテンツ)によるポケモン追加を歓迎する声がすでに上がっています。
まずはゲームの土台となるシステムをしっかりと構築し、発売後にDLCで対応ポケモンや新しいマップを追加していく、というビジネスモデルは、本作のゲーム性と非常に相性が良いはずです。 全ポケモンの実装は難しくとも、ファンが「自分のお気に入りのポケモン」と暮らせる可能性が残されているかどうかに、注目していきたいです。
ストーリーの落としどころは?ハッピーエンドを信じて
そして最大の注目点は、やはりストーリーです。 「不穏」な要素が散りばめられ、「ビルダーズ」のトラウマが蘇るファンもいますが、誰もが願っているのはハッピーエンドです。
「何が何でもハッピーエンドにしてやるからな。待ってろよ。不穏。」 「最後はハッピーエンドだと信じて予約するわ」
これらの反応は、シリアスな展開を予想しつつも、最後には救いのある結末を望むプレイヤーの総意でしょう。 「誰もいなくなった」世界の謎を解き明かし、もジャンボ博士の願い通り「人もポケモンも楽しく暮らす街」を(たとえ人間が戻ってこない形だとしても)実現できるのか。
私個人の見解としては、ポケモンというブランドが持つ「優しさ」を裏切るような、救いのない結末にはならないと確信しています。 むしろ、その「不穏」や「喪失」を乗り越えて「再生」へと向かうプロセスこそが、本作最大のカタルシス(感動)を生むのではないでしょうか。 「少しずつ (poco a poco)」復興していく町と、そこに集うポケモンたちの姿は、プレイヤーに大きな達成感と感動を与えてくれるはずです。
まとめ
2026年3月5日の発売が決定した『ぽこあポケモン』。 ニンダイで公開された最新映像は、ファンの期待を遥かに超えるものでした。
『あつ森』のようなスローライフ、『ビルダーズ』のような本格クラフト要素。 そして、『ポケパーク』や短編映画を彷彿とさせる、ポケモンたちとの心温まる(?)交流。 主人公の愛嬌あるメタモンや、人気爆発中のもジャンボ博士など、魅力的なキャラクターたちも揃っています。
その一方で、「誰もいなくなった」ポストアポカリプス的な世界観、「薄色ピカチュウ」や「コケむしたカビゴン」といった謎のポケモンたち、そして「グレンタウン説」に代表されるシリアスなストーリー考察など、「不穏」な要素がファンの心を強く掴んで離しません。
この「明るいスローライフ」と「影のある世界観」というギャップこそが、『ぽこあポケモン』の最大の魅力であり、他のどのゲームにもない独自の立ち位置を確立しようとしています。
クラフトゲームとしてどこまでの快適さと自由度を提供してくれるのか。 そして、この「不穏」な物語は、私たちをどのような結末に導いてくれるのか。 ゲーム評論家として、そして一人のゲームファンとして、これほど発売が待ち遠しいタイトルも久しぶりです。
2026年3月5日、私(メタモン)がこの荒廃した世界を「少しずつ」復興させ、もジャンボ博士を満足させる開発を成し遂げる日を楽しみに待ちたいと思います。