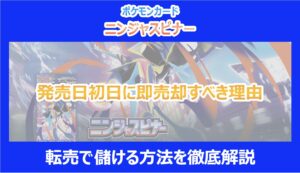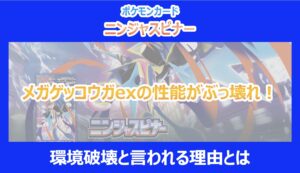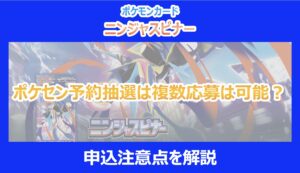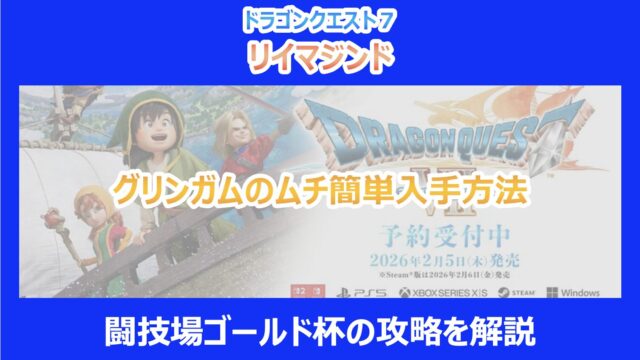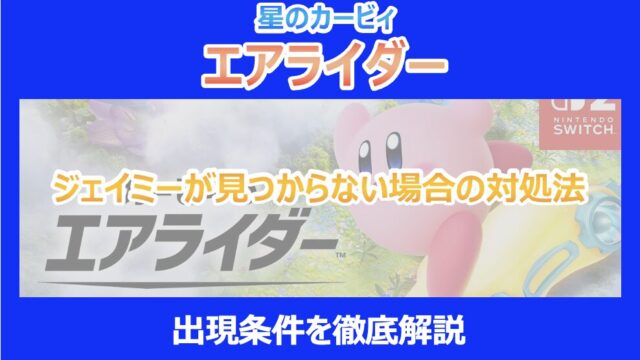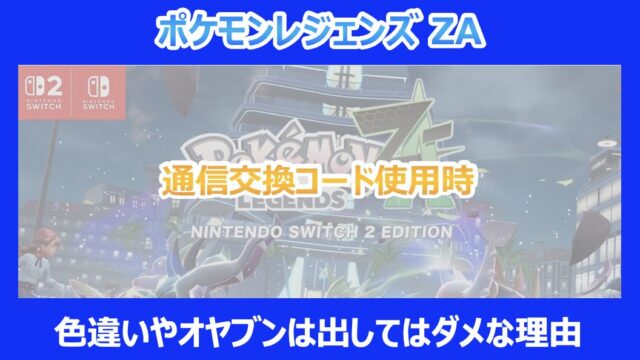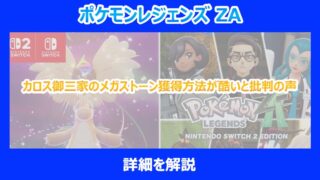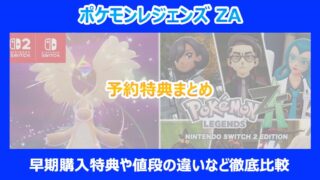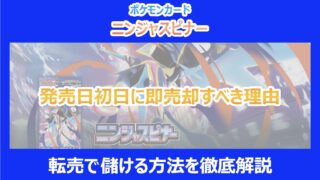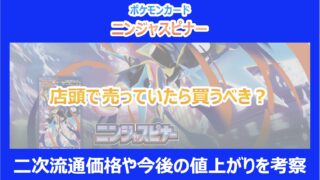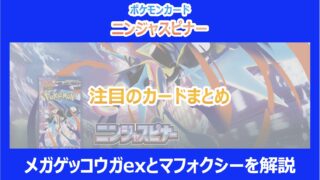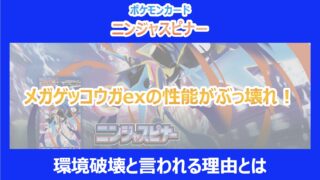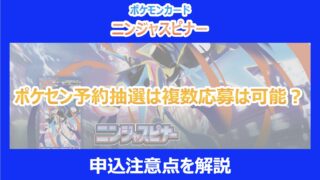ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年発売予定の「Pokémon LEGENDS Z-A」のグラフィックがなぜこれほどまでに批判されているのか、その具体的な理由が気になっているのではないでしょうか。 期待の新作発表にもかかわらず、SNSでは「ショボい」「がっかりした」といった手厳しい意見が飛び交っています。

この記事を読み終える頃には、レジェンズZAのグラフィックを巡る問題の全体像と、その背景にある根深い課題についての疑問が解決しているはずです。
- レジェンズZAのグラフィックに対する具体的な批判内容
- 他社人気タイトルとの比較で浮き彫りになる課題
- ポケモンシリーズが抱える開発体制の構造的問題
- 今後の改善の可能性とファンが本当に望むもの
それでは解説していきます。

Pokémon LEGENDS Z-A グラフィック炎上の経緯と批判の具体的内容
待望の新作として発表された「Pokémon LEGENDS Z-A」ですが、その映像が公開されると、期待の声と共にグラフィックのクオリティに対する厳しい批判の声が瞬く間に広がりました。 一体、どのような点が問題視されているのでしょうか。 まずは、炎上の経緯と批判の具体的な内容を詳しく見ていきましょう。

発表当初の大きな期待と現状のギャップ
2025年に発売が予定されている「Pokémon LEGENDS Z-A」は、「Pokémon LEGENDS アルセウス」に続くレジェンズシリーズの最新作として、多くのファンから大きな期待を寄せられていました。 発表当初、ミアレシティを舞台にした新たな冒険や、これまでにない都市開発といった要素が示唆され、SNS上では「ついにポケモンも本格的なオープンワールドに進化するのか」「新しいゲーム体験が楽しみだ」といったポジティブな反応で溢れかえっていたのです。

最初の発表映像は短いものでしたが、その中に散りばめられた新しい可能性の数々は、ファンの想像力を大いに掻き立てました。 しかし、その熱狂的な期待感は、後日公開されたプロモーションビデオやスクリーンショットによって一変します。
SNSやゲーム関連の掲示板には、「期待していたものと違う」「これは2025年のゲームとは思えない」といった失望の声が殺到。 特にグラフィックのクオリティに対する批判が集中し、大規模な「炎上騒動」へと発展してしまったのです。 この騒動は国内に留まらず、海外のゲームメディアでも取り上げられるほど大きなものとなりました。 世界的な人気を誇るIPだからこそ、ファンの期待値は非常に高く、その期待を裏切られたと感じた時の反動もまた、大きくなってしまうのです。
「ショボい」「生成AI以下」とまで言われるグラフィックの技術的課題
では、具体的にグラフィックのどの部分が批判の対象となったのでしょうか。 最も多く指摘されたのは、一言で言えば「時代遅れ感」です。
圧倒的に足りないオブジェクトの密度
公開された映像では、街並みやフィールドの作り込みの甘さが目立ちました。 特に建物のテクスチャが平面的でのっぺりとしており、遠景の建物はまるで「ハリボテ」のように見えるという指摘が相次ぎました。 また、地面や草木の表現も単調で、オブジェクトの密度が低いため、全体的にスカスカな印象を与えてしまっています。 近年のオープンワールドゲームでは、高精細なテクスチャと膨大な数のオブジェクトによって、没入感のある世界を構築するのが当たり前になっています。 それらと比較すると、レジェンズZAのグラフィックが見劣りしてしまうのは否めません。
不自然なライティングと影の表現
現代のゲームグラフィックにおいて、光と影の表現(ライティング)は、世界のリアルさや雰囲気を決定づける非常に重要な要素です。 しかし、レジェンズZAの映像では、このライティングが不自然であるという批判が多く見られました。 キャラクターや建物に落ちる影がぼんやりとしていたり、光源がどこにあるのか分かりにくい場面があったりと、リアリティを損なう要因となっています。 リアルタイムで複雑な光の反射や影を計算する技術は、マシンスペックを要求しますが、それを差し引いても「もう少し何とかならなかったのか」と感じるユーザーが多かったようです。
なぜ「生成AI以下」と揶揄されるのか
一部では「生成AIが作る画像の方がマシ」といった辛辣な意見まで飛び出しました。 これは、ここ数年で画像生成AIのクオリティが飛躍的に向上したことが背景にあります。 簡単な指示(プロンプト)で、プロのアーティストが描いたような、あるいは写真と見紛うような高精細な画像を生成できるようになったため、それと比較してレジェンズZAのグラフィックが物足りなく見えてしまう、というわけです。 もちろん、一枚の静止画を生成するAIと、プレイヤーが360度自由に動き回れる3D空間をリアルタイムで描画するゲームグラフィックを同列に語ることはできません。 しかし、それほどまでにユーザーの「見る目」が肥えてきていることの表れと言えるでしょう。
背景・環境グラフィックへの集中砲火
今回の批判で特徴的なのは、ポケモンのキャラクターモデルそのものよりも、背景やフィールドといった「環境グラフィック」に不満が集中している点です。
ファンからも「ポケモンのモデルはいつも通り可愛いのに、背景が足を引っ張っている」という声が多く聞かれます。 キャラクターのモデリングやアニメーションは、ポケモンという作品の根幹をなす部分であり、開発チームも長年のノウハウを蓄積しています。 そのため、キャラクター単体で見れば、多くの人が満足するクオリティを維持していると言えるでしょう。
しかし、そのキャラクターが動き回る世界の作り込みが甘いと、せっかくのキャラクターの魅力も半減してしまいます。 例えば、美しいデザインのポケモンが、まるで書き割りのような質感の建物や、単調な色の地面の上にいると、どうしても違和感が生まれてしまうのです。 このアンバランスさが、ユーザーの失望感をより一層大きなものにしていると考えられます。
Nintendo Switch後継機への期待が招いた失望
この炎上騒動には、ハードウェアの世代交代というタイミングも大きく影響しています。 レジェンズZAの発表時期は、任天堂の次世代機(通称:Nintendo Switch 2)の噂が最高潮に達していた頃と重なります。
多くのファンは、「次のポケモンは、より高性能な次世代機で、美麗なグラフィックで遊べるに違いない」という期待を抱いていました。 しかし、発表された対応ハードは現行のNintendo Switchファミリーのみ。 そして、公開された映像は、お世辞にも次世代機の性能を活かしているとは言えないクオリティでした。
これにより、「次世代機を買う意味がない」「Switch 2世代のユーザーが置き去りにされるのではないか」といった不安や不満が噴出しました。 これは単なるグラフィックの問題に留まらず、ポケモンシリーズ全体の将来性に対する懸念にも繋がっています。 他のメーカーが次世代機のスペックをフルに活用したゲームを開発する中で、ポケモンだけが旧世代のクオリティに留まってしまうのではないか、という危機感がファンの間で共有されているのです。
なぜここまで批判が?レジェンズZAグラフィック問題の根深い背景
レジェンズZAのグラフィック問題は、単に「開発チームの技術力が低い」という単純な話ではありません。 その背景には、ポケモンという巨大IPが長年抱え続けてきた、構造的かつ複合的な課題が存在します。 ここでは、なぜこのような事態に陥ってしまったのか、その根深い原因を多角的に掘り下げていきます。

驚異的な開発スピードの代償とは?開発サイクルの問題点
最も大きな原因として指摘されているのが、ポケモンシリーズの「開発サイクルの異常な短さ」です。 近年のポケモン本編シリーズは、ほぼ1〜2年に1本という驚異的なペースでリリースされ続けています。 これは、ゲームだけでなく、アニメ、映画、カードゲーム、グッズ展開など、多岐にわたるメディアミックス戦略と密接に連携しているためです。 商業的には大成功を収めているこの戦略ですが、その裏で、ゲーム開発の現場には計り知れないプレッシャーがかかっています。
| タイトル | 開発期間の目安 |
|---|---|
| Pokémon LEGENDS Z-A | 約2〜3年? |
| 一般的なAAA級オープンワールドゲーム | 4〜6年以上 |
| ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク | 約5年 |
| ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 約6年 |
| サイバーパンク2077 | 約8年以上 |
上記の表を見てもわかる通り、高品質なグラフィックで知られるAAA級タイトルは、開発に少なくとも4〜5年、長いものではそれ以上の歳月を費やしています。 コンセプトアートの作成から始まり、3Dモデリング、テクスチャ制作、ライティング設定、膨大なデバッグ作業など、グラフィック制作には無数の工程が存在し、それぞれに専門的なスキルと時間が必要です。
しかし、ポケモンシリーズの短い開発サイクルでは、これらの工程を丁寧に行う時間を確保することが極めて困難です。 結果として、どこかの工程で妥協せざるを得なくなり、それがグラフィックのクオリティに直結していると考えられます。 実際に、「ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール」では外部スタジオに開発が委託され、「スカーレット・バイオレット」でも複数の外部スタジオとの分業体制が取られていました。 開発負荷の分散は期間短縮に有効ですが、一方でクオリティの管理や全体の統一感を保つのが難しくなるというデメリットも生じさせます。
比較対象が悪すぎた?「パルワールド」ショックの衝撃
レジェンズZAへの批判が激化したもう一つの要因は、比較対象となる強力なライバルの登場です。 その筆頭が、2024年初頭にリリースされ、世界的なブームを巻き起こした「パルワールド」です。
「パルワールド」は、小規模なインディー開発チームによって作られたにもかかわらず、美しいグラフィックと滑らかなアニメーション、広大なオープンワールドを実現し、多くのゲーマーを驚かせました。 特に、世界最大級のゲーム会社である任天堂とゲームフリークが手掛けるポケモンと、インディーチームの作品とで、技術面に大きな差が見られなかった(むしろ部分的にはパルワールドが上回っていた)ことは、多くのポケモンファンに衝撃を与えました。
「なぜ巨大企業であるポケモンが、インディーチームにグラフィックで劣っているのか」という純粋な疑問が、批判の大きな原動力となったのです。 もちろん、ゲームのコンセプトや目指す方向性が異なるため、単純比較はできません。 しかし、同じ「モンスターを収集・育成して冒険する」というジャンルである以上、ユーザーが両者を比較してしまうのは自然な流れと言えるでしょう。
「ゼルダ」や「モンハン」とは何が違うのか?任天堂内での立ち位置
同じNintendo Switchで発売されている他の大ヒットタイトルとの比較も、批判を加速させています。 特に頻繁に比較対象として挙げられるのが、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」や「モンスターハンターライズ:サンブレイク」です。
これらのタイトルは、Switchの性能を限界まで引き出したと評される美しいグラフィックと、緻密に作り込まれた世界観で、非常に高い評価を得ています。 同じプラットフォームでこれほどのクオリティが実現できているのに、なぜポケモンはできないのか、という不満の声は根強いです。
ここには、開発体制の違いが関係していると考えられます。 「ゼルダの伝説」シリーズは、任天堂のトップチームが長い年月をかけて開発する、まさに社運を賭けたタイトルです。 一方、ポケモンシリーズは株式会社ゲームフリークが開発の主体であり、任天堂は販売やプロデュースを担う、という関係性です。 IPとしては任天堂の看板の一つですが、開発リソースの投入のされ方には違いがあるのかもしれません。 この「同じ任天堂のゲームなのに」という感覚が、ファンの期待値と現実のギャップを広げている一因と言えそうです。
ポケモンブランドが抱える「ファミリー層向け」というジレンマ
ポケモンは、子供から大人まで、非常に幅広い年齢層に愛されているIPです。 特に、ファミリー層や低年齢層は重要なターゲットであり、その層に向けた「わかりやすさ」「親しみやすさ」はブランドの根幹を成しています。
この「全年齢向け」という方針が、グラフィック進化の足枷になっている可能性も指摘されています。 過度にリアルでフォトリアリスティックなグラフィックは、ポケモンが持つ温かみのある世界観とは相容れないかもしれません。 また、低年齢層のプレイヤーが安心して遊べるように、あえてデフォルメされた、親しみやすい表現を重視しているという側面もあるでしょう。
これは一種の制約として機能しており、技術的には可能であっても、あえて最新のグラフィック技術をフル活用しない、という経営判断が働いている可能性があります。 しかし、古くからのファンや、他の最先端ゲームに慣れ親しんだ層からすると、その表現が「古臭い」「手抜き」と映ってしまう。 このターゲット層の広さが故のジレンマが、評価の分かれる大きな要因となっています。
繰り返される歴史 – 過去作でも見られたグラフィック問題
実は、ポケモンシリーズのグラフィックに関する炎上は、今回が初めてではありません。 記憶に新しいところでは、「ポケットモンスター ソード・シールド」の通称「リストラ問題」と並行してグラフィックのクオリティが議論されましたし、「ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール」の二頭身デザイン、「スカーレット・バイオレット」の数々のバグや処理落ち問題など、近年は新作が出るたびに同様の批判が繰り返されています。
これらの事例を見ると、今回のレジェンズZAの問題は単発的なものではなく、ポケモンシリーズが長年抱える構造的な課題が、再び表面化したものと捉えることができます。 ファンからは「いつまで同じことを繰り返すのか」という、諦めに似た厳しい声も上がっており、開発体制の根本的な見直しを求める声は日増しに強まっています。
海外と日本での反応の温度差はなぜ生まれるのか
興味深いことに、この炎上騒動に対する反応は、日本と海外で若干の温度差が見られます。 日本のSNSでは感情的な批判や失望の声が目立つ一方で、海外の掲示板「Reddit」などでは、比較的冷静な分析や建設的な意見交換が行われています。
海外ファンからは、 「批判は理解できるが、キャラクターモデルではなく環境描写に問題が絞られている」 「まだ開発途中の映像だ。最終版で改善される可能性に期待しよう」 「Switchのスペックを考えれば、大規模なオープンワールドでこのグラフィックは妥当なラインでは?」 といった、技術的な制約を理解しようとする姿勢が見られます。
この違いは、ゲームに対する価値観の違いも反映していると考えられます。 海外では、完璧なクオリティでなくとも、ゲームとして楽しめれば良い、と考えるユーザーが多い傾向があります。 また、早期アクセスやベータ版など、未完成な状態のゲームをプレイする文化が根付いているため、開発途中の映像に対してより寛容な見方をするファンが多いのです。 とはいえ、海外ファンからもライティングの改善やテクスチャの解像度向上など、具体的な改善案は多数寄せられており、より良いゲームを望む気持ちは万国共通と言えるでしょう。
一方で存在する擁護論と今後の展望
これまでの批判的な意見とは対照的に、レジェンズZAの現状を擁護する声や、今後に期待する声も決して少なくありません。 物事を多角的に見るためにも、これらの冷静かつ建設的な意見にも耳を傾けてみましょう。

グラフィックだけがゲームの全てではない – ゲームシステムへの期待
擁護派の意見として最も多いのが、「グラフィック以外の要素に期待している」というものです。 レジェンズシリーズは、従来のポケモンとは一線を画すアクション性の高いバトルシステムや、広大なフィールドをシームレスに冒険する探索要素が高く評価されました。
レジェンズZAでも、
- さらに広大になったであろうフィールド
- UI(ユーザーインターフェース)やシステムの刷新
- 「都市開発」という全く新しいゲームプレイ
など、ゲーム体験そのものを向上させるであろう新要素に大きな期待が寄せられています。 「グラフィックが多少悪くても、ゲームとして面白ければ問題ない」という意見は、ゲームの本質を突いたものであり、多くの支持を集めています。 結局のところ、プレイヤーがゲームに求めるのは「楽しい時間」であり、グラフィックはその楽しさを構成する一要素に過ぎない、という考え方です。
Nintendo Switchの性能限界という現実的な視点
「現行のNintendo Switchの性能を考えれば、公開されているグラフィックは妥当だ」という現実的な見方も多く存在します。 Switchは2017年に発売されたハードであり、最新の据え置き機であるPlayStation 5やXbox Series X/S、あるいはハイエンドPCと比較すれば、その性能には大きな隔たりがあります。
特に、広大なオープンワールドをシームレスに描画することは、マシンに極めて高い負荷をかけます。 その限られた性能の中で、安定したフレームレートを維持しつつ、ポケモンの世界を表現しようとすれば、グラフィックのディテールをある程度犠牲にするのは、技術的に避けられない選択とも言えるのです。 前述の「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」が奇跡的な作品であっただけで、すべてのゲームが同じレベルに到達できるわけではない、という冷静な指摘もなされています。
まだ開発途中?今後のブラッシュアップに期待する声
現在公開されている映像やスクリーンショットは、あくまで「開発中のもの」であるという点も忘れてはなりません。 多くのゲームタイトルでは、最初の発表から発売までの間に、グラフィックの大幅なブラッシュアップが行われるのが通例です。 ファンのフィードバックを受けてライティングを改善したり、テクスチャをより高解像度のものに差し替えたり、オブジェクトを追加して世界の密度を高めたりと、最適化作業は発売直前まで続きます。
そのため、「現段階で最終的なクオリティを判断するのは時期尚早だ」という意見には、一定の説得力があります。 今回の炎上騒動が開発チームに届けば、それを真摯に受け止め、発売までに可能な限りの改善を施してくれる可能性は十分に考えられます。 今後の追加情報や新しいプロモーションビデオで、我々を驚かせるような進化を遂げた映像が公開されることに期待したいところです。
開発陣はファンの声にどう応えるのか
最終的に重要なのは、開発チームがこの一連の騒動、つまりファンの声にどう向き合い、応えていくかです。 批判も擁護も、その根底にあるのは「ポケモンが大好きだからこそ、もっと良い作品になってほしい」という熱い想いです。
技術的な制約や開発スケジュールの問題など、乗り越えるべきハードルは数多くあるでしょう。 しかし、その中で何を選択し、何を優先するのか。 グラフィックの進化と、ポケモンらしい温かみの両立。 商業的な成功と、ファンが満足するクオリティの担保。 これらの難しいバランスをどう取っていくのかが、今後のポケモンシリーズの未来を占う上で極めて重要な鍵となります。
我々ファンにできることは、一方的に批判するだけでなく、なぜそう感じるのかを建設的に伝え、そして開発チームの挑戦を信じて見守ることなのかもしれません。
まとめ
今回は、「Pokémon LEGENDS Z-A」のグラフィック炎上問題について、その経緯から背景にある構造的な課題、そして今後の展望までを深く掘り下げてきました。
この問題は、単なる「グラフィックがショボい」という表面的な話ではなく、
- 異常なまでに短い開発サイクル
- 「パルワールド」など強力な比較対象の登場
- ハードの世代交代期におけるファンの過度な期待
- 全年齢向けIPであるが故の表現のジレンマ
といった、複数の要因が複雑に絡み合った、現代のポケモンシリーズが直面する根深い課題を浮き彫りにしています。
批判の声が大きいのは事実ですが、それは裏を返せば、ポケモンという作品がそれだけ多くの人々に愛され、期待されている証拠でもあります。 ゲームシステムへの期待や、今後の改善を信じる声も数多く存在します。
開発チームがこれらの多様な声にどう応え、技術的進歩と商業的成功、そしてポケモンらしさのバランスをどのように取っていくのか。 今後の公式発表や続報が、ファンの期待に応えるものになることを心から願いつつ、注目していきたいと思います。