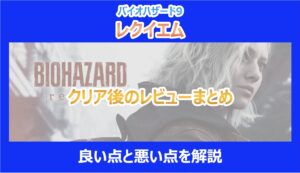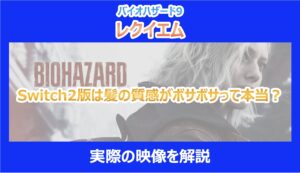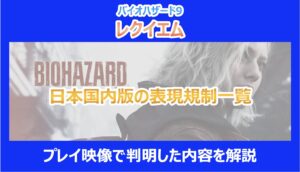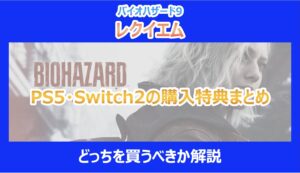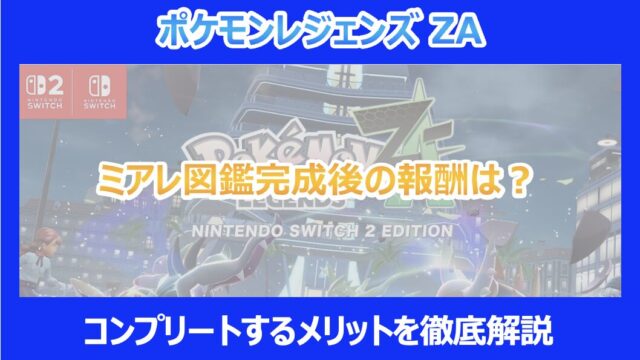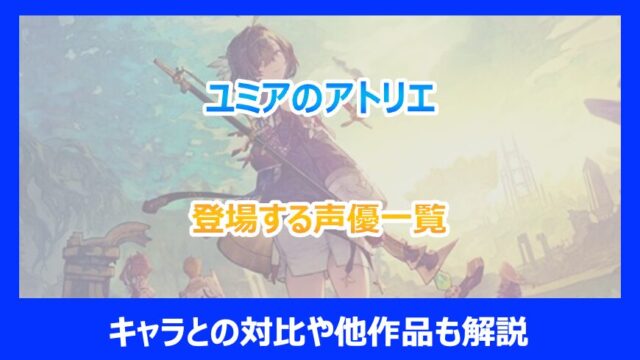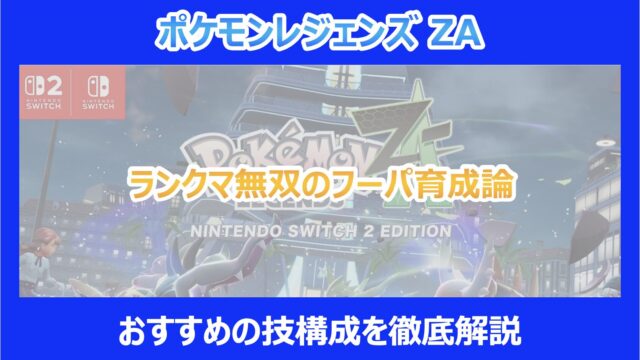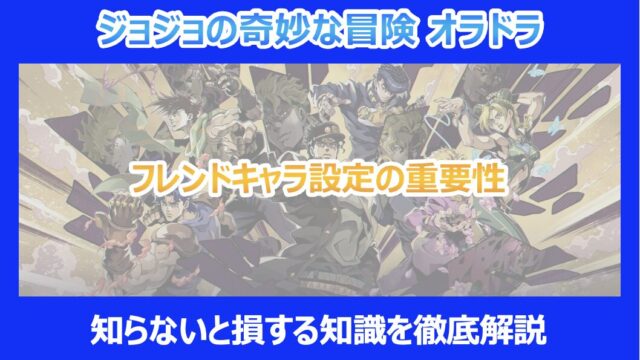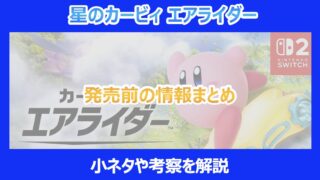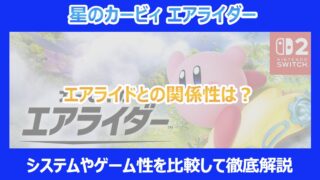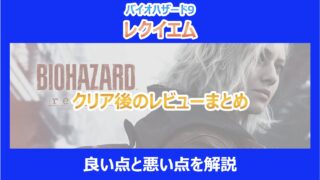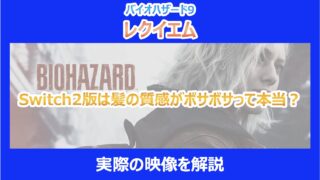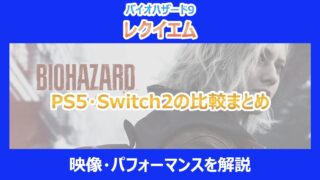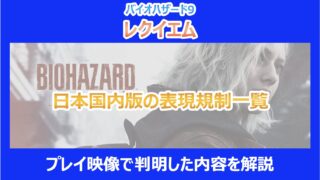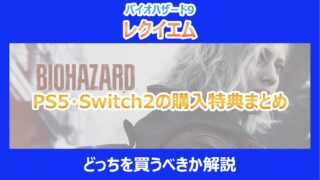ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年11月20日に発売が迫る待望の新作『星のカービィ エアライダー』、特にカービィの代名詞ともいえる「コピー能力」が本作でどのように進化しているのか、その詳細が気になっているのではないでしょうか。 前作から約20年の時を経て、グラフィックやシステムがどのように洗練されたのか、そして新要素がレースにどんな影響を与えるのか、期待と疑問が入り混じっていることでしょう。

この記事では、現在公開されている情報を基に、『星のカービィ エアライダー』の根幹をなすコピー能力のシステムを徹底的に解説します。 さらに、進化したゲームシステムや操作性、そして魅力的な参戦キャラクターたちについても、前作との比較を交えながら深掘りしていきます。
この記事を読み終える頃には、『星のカービィ エアライダー』のコピー能力とゲームシステムの全貌に関するあなたの疑問が、きっと解決しているはずです。
- 全キャラクターが使用可能なコピー能力システム
- 懐かしさと新しさが融合した多彩なコピー能力
- ライダーとマシンの組み合わせによる無限の戦略
- 現代の技術で蘇る爽快感抜群のレース体験
それでは解説していきます。

『星のカービィ エアライダー』の基本システムと進化したポイント
まずは、本作の根幹をなすゲームシステムが前作からどのように進化したのかを見ていきましょう。 UIの洗練から新アクションの追加まで、レースゲームとしての完成度が飛躍的に向上していることが分かります。

UIとゲーム画面の劇的な進化
まずゲーム画面を一目見て感じるのは、圧倒的な「スピード感」の向上です。 これは単にグラフィックが綺麗になったというだけでなく、現代のレースゲームにふさわしい演出の強化によるものが大きいでしょう。

スタートのカウントダウンから、その違いは明らかです。 カウントダウン演出の疾走感、スタートダッシュを決めた際の派手な光のエフェクト、画面を覆いつくす集中線など、レース開始直後からプレイヤーのテンションを最大限に引き上げてくれます。 前作のどこか牧歌的なスタート演出と比較すると、その差は歴然です。
UI(ユーザーインターフェース)の配置も大きく変更され、より洗練されました。
- 左上: マップ
- 右上: ラップ数
- 左下: 順位
- 右下: チャージゲージ、速度表示
前作とは一部の配置が逆転しており、UIパーツ自体もコンパクトになったことで、画面の圧迫感が軽減されています。 これにより、美麗なコースの風景や、キャラクターたちの生き生きとしたアクションをより広く楽しめるようになりました。
特にマップ表示は大きく進化しています。 前作ではコース全体を静的に表示していましたが、今作ではプレイヤーを中心に表示し、走行方向と連動してマップがダイナミックに動く形式に変更されました。 これにより、直感的にコースの状況を把握しやすくなっています。
基本操作と新アクション「スペシャル」
基本的な操作性は、ゲームキューブで発売された前作の『カービィのエアライド』をしっかりと踏襲しています。 Aボタン(ゲームキューブコントローラー)で行っていた「プッシュ」が、最新のコントローラーに合わせてBボタンに変更されている点が主な違いでしょう。
コーナリングの気持ちよさも格段に向上しています。 カメラアングルやエフェクトの強化により、カーブを曲がる際のスピード感が前作よりもダイレクトに伝わってきます。 ワープスターに乗るカービィの表情も、前作の無表情から、今作では力を込めてコーナリングを決める、いきいきとした表情に変わっています。 ジャンプ台からの滑空操作は、スティック下で上昇、上で下降という、いわゆる「リバース操作」が採用されていますが、これも前作と同様です。 現代のゲームに慣れたプレイヤーのために、設定でノーマル操作への変更が可能になることを期待したいところです。
そして、本作最大の新アクションが「スペシャル」です。 画面下部に追加された「スペシャルゲージ」を溜めることで、Yボタンで発動できる各キャラクター固有の必殺技です。 これは『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズの「最後の切りふだ」に近いシステムと言えるでしょう。
実践プレイの映像を見る限り、ゲージは比較的溜まりやすいようです。 レースの展開を大きく左右する切り札として、どのタイミングで使うかという戦略性が生まれ、レースの駆け引きをより熱いものにしてくれるはずです。
新要素「星くず」と強化された「スタースリップ」
レースの戦略に新たな深みを与える新要素として「星くず」が追加されました。 敵を倒したり、ライバルを攻撃したりすることで星くずが出現し、これを集めることでマシンがわずかに加速します。 これは『マリオカート』シリーズにおける「コイン」のような役割と考えると分かりやすいでしょう。
さらに、前作にも存在した「スタースリップ」システムが大幅に強化されています。 前を走るマシンの軌跡が光の道として表示され、その後ろを走ることで急加速できるこのシステムは、後続のプレイヤーにとって大きなチャンスとなります。 スタースリップ発動中はプレイヤーの周りに光のエフェクトが表示されるため、視覚的にも分かりやすくなりました。
この「星くず」と「スタースリップ」の強化により、1位のプレイヤーが独走しにくいゲームバランスになっています。 常に逆転の可能性がある、ハラハラドキドキのレース展開が期待できるでしょう。
ライバルへの攻撃は妨害が目的ではない?
ライバルを攻撃して「星くず」を奪うことはできますが、公式の説明によると、これは相手を妨害することが主目的ではないようです。 あくまでも、奪った星くずで「自分がスピードアップする」ことが目的とされています。 ダメージを受けた際のリアクションは小さめに調整されており、攻撃された側のストレスが軽減されている点もポイントです。 これにより、攻撃的なプレイが爽快な加速感に繋がり、バトルレースとしての楽しさを純粋に追求できるデザインになっています。
多彩なルール設定とマシンから降りるアクション
詳細なルール設定画面も公開されており、遊び方の幅が大きく広がっていることが伺えます。
- 対戦形式: 通常戦とチーム戦
- 参加人数: 最大6人
- ルール: 周回数や時間の設定
- リタイア: マシンの耐久性の有無
特に注目すべきは「マシンの耐久性」です。 この設定をONにすると、攻撃を受けて体力がゼロになったマシンは破壊されてしまいます。 これにより、爽快なレースだけでなく、より激しく殺伐としたバトルを楽しむことも可能です。 さらに、体力が減って破壊されそうになっているマシンは、リスクと引き換えにスピードが上がるという面白い新要素も追加されており、逆境からの大逆転劇も生まれるかもしれません。
また、前作同様、キャラクターはマシンから降りることが可能です。 降りた状態での新アクションとして「アピール」のようなモーションが追加されている可能性も示唆されています。 各キャラクターに専用のモーションが用意されていれば、ファンにとってはたまらない要素となるでしょう。
最大6人対戦がもたらす新たな駆け引き
前作の最大4人対戦から、今作では最大6人対戦へと進化しました。 「たった2人増えただけ?」と思うかもしれませんが、開発者である桜井政博氏によると、ゲームバランスを考慮した上でこれが最適な人数だと判断したとのことです。 人数が多すぎるとコース上が混雑しすぎ、レースとしての戦略性が失われてしまうため、ゲーム性を重視した結果の判断と言えるでしょう。
オンライン対戦では、自分がゴールした後、他のプレイヤーのゴールを待たずに次の対戦へ進める機能もあるようです。 待ち時間を最小限に抑え、テンポよく何度も対戦できるこの仕様は、まさに「サクライズム」を感じさせる快適な設計です。
『星のカービィ エアライダー』の根幹をなすコピー能力とキャラクター
ここからは、本レビューの核心である「コピー能力」と、個性豊かな「ライダー」たちについて徹底的に解説していきます。 常識を覆す新システムと、ファン待望のキャラクター参戦は、本作を唯一無二のレースゲームへと昇華させています。

全員コピー可能!ゲームの常識を覆す革命的システム
カービィシリーズにおいて、敵の能力を吸い込んで自分のものにする「コピー能力」は、長年カービィだけの専売特許でした。 しかし、『星のカービィ エアライダー』では、その常識が覆されます。 なんと、カービィ以外の参戦キャラクター全員がコピー能力を使えるようになったのです。
これは、特定のキャラクターだけが突出して有利になることを防ぎ、純粋なレースゲームとしての公平性を保つための英断と言えるでしょう。 世界観の設定よりも、対戦ゲームとしての面白さを優先する桜井氏の哲学が色濃く反映された革命的な変更点です。 これにより、どのキャラクターを選んでも平等に多彩な攻撃を繰り出すことができ、「カービィ一強」という状況にはなりません。 デデデ大王がファイアを吐き、メタナイトがマイクで熱唱する姿は、シリーズのファンであればあるほど新鮮で、面白おかしく映るはずです。
公開されたコピー能力一覧と詳細解説①
ダイレクトで発表された9種類のコピー能力に加え、その後の映像で判明した能力について、一つずつ詳しく見ていきましょう。 デザインの変更点や性能の進化に注目です。
ファイア
前方に火炎弾を放つ、おなじみの能力です。 前作ではやや当てにくかった印象ですが、今作では弾速や誘導性が向上しているように見え、より実用的な性能になっているようです。 炎のエフェクトも大きくなり、「ファイアボール」としての迫力が増しています。 コピー元となる敵は、炎の虫のような新キャラクター「バーニャン」です。
ソード
近くの敵を自動で斬りつける近接攻撃能力です。 特筆すべきは、そのデザインが『星のカービィ スーパーデラックス』やアニメ版などで見られた、緑の帽子に「黄色い剣」という懐かしいスタイルに戻っている点です。 近年の作品では銀色の剣が主流でしたが、桜井氏の原点回帰へのこだわりが感じられます。 剣の振り方や斬撃のエフェクトもよりシャープで格好良くなっています。
ボム
投げると大爆発を起こす、強力な範囲攻撃能力です。 こちらもデザインが、かつてポピーブラザーズJr.が被っていたクラッカー型の帽子に戻っています。 本作では、爆弾を投げる際に着弾点を示す照準(標準)が表示されるようになりました。 これにより、運任せではなく、しっかりと狙って爆弾を当てることが可能になり、戦略性が向上しています。
公開されたコピー能力一覧と詳細解説②
続いて、テクニカルな能力からユニークな能力まで、さらに見ていきましょう。
ホイール
タイヤに変身して高速で爆走する、レースゲームと相性抜群の能力です。 どのマシンに乗っていても安定した加速が得られるため、レースでは非常に強力な能力となるでしょう。 変身中のタイヤのデザインがよりリアルになっている一方で、加速時のエフェクトは『スーパーデラックス』に近いものになっており、新旧のデザインが融合しています。
マイク
画面全体の敵にダメージを与える絶叫攻撃です。 前作と比較してエフェクトが大幅に豪華になっており、爽快感が格段にアップしています。 叫ぶ際の表情やモーションはキャラクターごとに個別のものが用意されているようで、各キャラクターの個性的なシャウト(あるいは桜井氏本人によるシャウト)が聞けるのか、期待が高まります。
カッター
ブーメランのように軌道するカッターを投げる中距離攻撃能力です。 エアライドシリーズでは初登場となります。 投げたカッターは手元に戻ってくるまで攻撃判定が持続するため、『マリオカート』のブーメランフラワーのように、往復でヒットを狙うことが可能です。 コピー元の敵は、どこか影のある雰囲気をまとったサーキブルです。
公開されたコピー能力一覧と詳細解説③
最後に、特に注目度の高い能力や、謎に包まれた新能力を紹介します。
プラズマ
エネルギーを溜めて強力な電撃を放つ能力です。 グラフィックの進化により、頭上でスパークするプラズマの表現がより美麗になりました。 前作ではスティックを激しく入力する(レバガチャ)ことでエネルギーを溜めていましたが、今作では自動でパワーが溜まっていく仕様に変更されたようです。 これにより操作は簡単になりましたが、溜め時間が固定化されたことで、前作とは異なる戦い方が求められるでしょう。
スチールボール
巨大な鉄球に変身し、無敵状態でゴロゴロと転がる謎の新コピー能力です。 映像では、ホイールよりもスムーズにコーナリングしているように見えます。 その巨体を生かして、ライバルたちをボウリングのピンのようになぎ倒すのが爽快そうです。 『星のカービィ 参上!ドロッチェ団』に登場した「メタル」の球体化に近い能力かもしれませんが、詳細はまだ不明です。
ジェット
そして、多くのファンが歓喜したであろう能力が「ジェット」の復活です。 『星のカービィ ロボボプラネット』以来、実に9年ぶりの登場となります。 本作のジェットは単なる復活に留まらず、完全なフルモデルチェンジが施されています。
- デザイン: 従来の背中のブースターから、両手に巨大なブースターを装備した「ダブルブースター」仕様に。バイザーも過去作より巨大化しています。
- 性能: 事前にパワーを溜める必要がなく、常に噴射し続けて加速できる、アニメ版に近い操作感になっているようです。チャージ攻撃も可能で、その際はエフェクトの色が青から赤に変化します。
レースゲームである本作にこれ以上なくマッチした能力であり、その性能と進化したデザインから、本作の花形コピー能力の一つとなることは間違いないでしょう。
未公開のコピー能力も多数存在?
公式サイトやダイレクトではまだ大々的に発表されていませんが、試遊台のプレイ映像などを注意深く見ると、「スリープ」「ファイター」「ニードル」といった能力の存在も確認できます。 これらは前作にも登場したおなじみの能力ですが、エフェクトなどが刷新されているようです。 まだ隠されたコピー能力が多数存在する可能性は高く、今後の続報から目が離せません。
| 確認済みのコピー能力 | 特徴 |
|---|---|
| ファイア | 前方に火炎弾を発射。今作では当てやすさが向上。 |
| ソード | 近接する敵を自動で斬りつける。旧デザインに回帰。 |
| ボム | 大爆発を起こす。照準が追加され狙いやすく。 |
| ホイール | タイヤに変身し高速移動。レースの切り札。 |
| マイク | 画面全体の敵に大ダメージ。エフェクトが豪華に。 |
| カッター | ブーメラン軌道のカッターを投げる中距離攻撃。 |
| プラズマ | 自動チャージ式の電撃攻撃。操作が簡単に。 |
| スチールボール | 巨大な鉄球に変身する無敵の突進攻撃。謎の新能力。 |
| ジェット | 9年ぶりに復活。フルモデルチェンジされた高速移動能力。 |
| ファイター | 映像で確認。格闘攻撃を繰り出す。 |
| ニードル | 映像で確認。全身からトゲを出す。 |
| スリープ | 映像で確認。眠ってしまうが、何かが起こる? |
参戦が確定したライダーたちを一挙紹介
本作では「ライダー」という概念が導入され、カービィシリーズのオールスターキャラクターたちがマシンに乗り込みます。 現時点で判明している12名のライダーたちを、その特徴とともに紹介します。
ライダー紹介
- カービィ: 主人公らしいオールラウンダー。スペシャル技は「ウルトラソード」。
- デデデ大王: パワーと耐久力に優れた重量級。スペシャル技はスマブラでもおなじみの「ジェットハンマー」。
- メタナイト: スピードとテクニックに長ける。スペシャル技は翼が4枚に増える「ナイトウィング」。
- バンダナワドルディ: 加速力と小回りに優れた軽量級。スペシャル技は槍を回転させる「スピアサイクロン」。
- コックカワサキ: 食べ物アイテムでの回復量がアップ。スペシャル技は「激からクッキング」。
- マホロア: スタースリップ性能が高い。スペシャル技は極太レーザー「マホロア砲」。
- グーイ: 長い舌を使ったトリッキーなアクションが特徴。スペシャル技は「ダークマター」化。
- スージー: 飛行能力に優れる。スペシャル技はジェット噴射「アフターバーナー」。
- キャピー: キノコ帽子がシールドになる防御型。スペシャル技は「ブースターキャップ」。
- ワドルドゥ: 自動でビームを放つオート攻撃持ち。スペシャル技は「ワドルドゥビーム」。
- ナックルジョー: 近接戦闘が得意。スペシャル技は「ナックルラッシュ」。
- ウィングスターマン: 飛行能力とジャンプ力が高い。スペシャル技は「スーパースターマン」。
キャラクター選択画面にはまだ多くの空きスペースがあり、少なくとも倍以上のキャラクターが参戦することは確実と見てよいでしょう。 カービィ版スマブラとも言える豪華なラインナップに期待が高まります。
ライダーとマシンの組み合わせが生む無限の戦略性
本作の奥深さを決定づけているのが、「ライダー」と「マシン」の組み合わせです。 各ライダーには固有の性能やスペシャル技がありますが、それとは別に、搭乗するマシンごとにも操作性や性能が異なります。 この2つの要素が掛け合わさることで、無数の性能差が生まれるのです。
例えば、基本的なマシンである「ワゴンスター」に乗る場合でも、
- カービィが乗る: 加速や機敏性に優れたバランス型
- デデデ大王が乗る: 最高速、攻撃力、耐久力に優れたパワー型
というように、ライダーによってマシンの特性が大きく変化します。 場合によっては、デデデ大王が乗るとマシンのサイズ自体が大きくなるといった変化も見られます。
現時点で判明しているだけでも「12キャラ × 15種以上のマシン」で、実に180通り以上の組み合わせが存在します。 今後キャラクターやマシンが増えれば、そのバリエーションは天文学的な数に膨れ上がるでしょう。 これは、キャラクターゲームとしての魅力と、戦略的なレースゲームとしての奥深さを両立させる、非常に優れたシステムです。 自分だけの最強の組み合わせを見つけ出す楽しみは、本作の大きな魅力となるはずです。
まとめ
今回のレビューでは、2025年11月20日に発売される『星のカービィ エアライダー』について、特に「コピー能力」と進化したゲームシステムを中心に解説してきました。
- 洗練されたレースシステム: UIの刷新、スピード感を増す演出、新要素「星くず」や「スペシャル」技の追加により、現代のレースゲームとして最高の体験を提供してくれる。
- 革命的なコピー能力: 全キャラクターがコピー能力を使えるという大胆な変更により、キャラクター間の格差がなくなり、対戦ゲームとしての公平性と面白さが飛躍的に向上した。
- 無限の戦略性: 個性豊かなライダーと多種多様なマシンの組み合わせは、プレイヤーに無限の戦略と遊びの幅を与えてくれる。
前作『カービィのエアライド』が持つ唯一無二の面白さを核としながら、約20年分の技術の進化と、桜井政博氏のゲームデザインの粋が詰め込まれた本作は、シリーズファンだけでなく、すべてのレースゲームファンにとって必見の作品となるでしょう。
コピー能力を駆使してライバルを蹴散らし、自分だけの最高の走りでゴールを目指す。 その爽快感を味わえる日まで、あともう少しです。