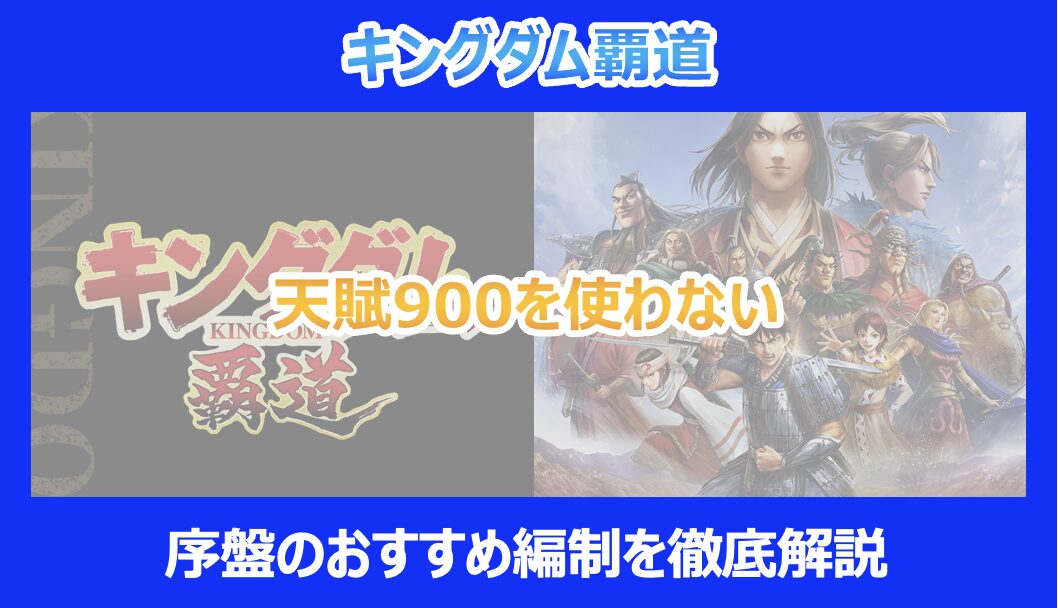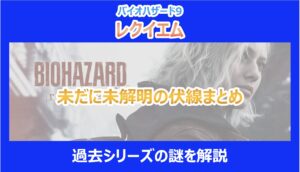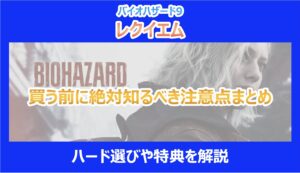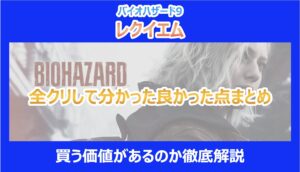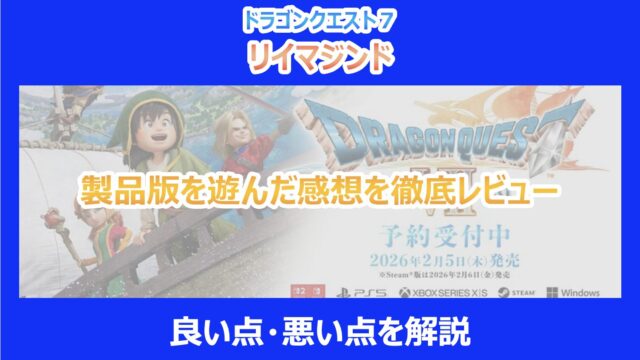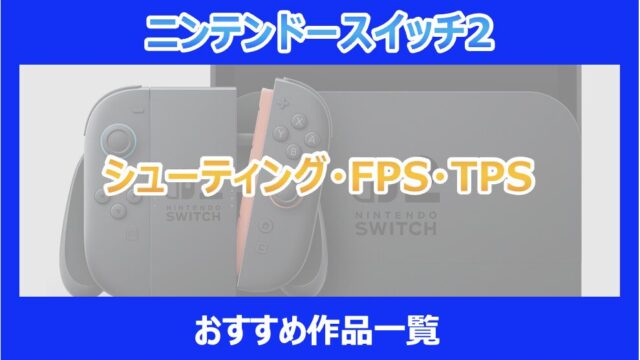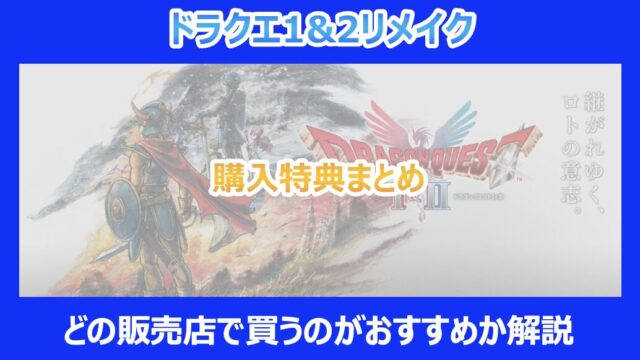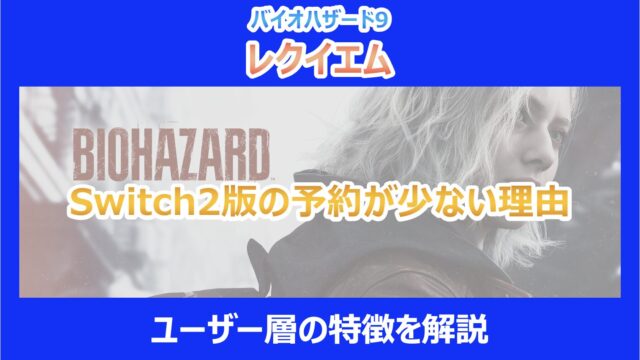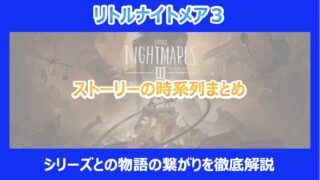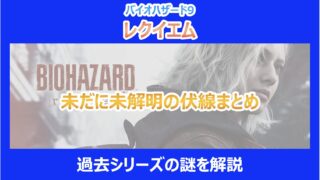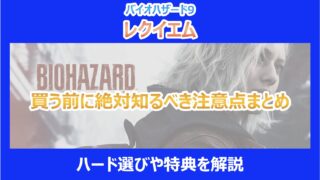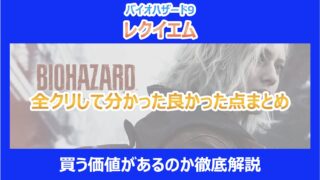ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、「キングダム覇道でリセマラを頑張ったけど、結局天賦900の武将が出なかった…」「無課金・微課金で天賦900なしでも、序盤を有利に進められる編成が知りたい」といったことが気になっていると思います。 強力な天賦900武将がいないと、どうしても戦力的に不安になりますよね。

ご安心ください。 キングダム覇道は、戦略次第で天賦900がいなくても十分に戦える奥深いゲームです。 この記事を読み終える頃には、天賦900武将を使わない序盤のおすすめ編制に関する疑問が解決しているはずです。
- 天賦900武将なしでも戦える編成の根幹
- 最重要システム「陣形効果」の完全解説
- 具体的な序盤おすすめ編成のパターン紹介
- 後悔しないためのSR武将育成の注意点
それでは解説していきます。
https://www.youtube.com/watch?v=yv-r7xU1fG0

キングダム覇道の編成における基本戦略
まずはじめに、部隊を編制する上で絶対に押さえておくべき基本的な考え方から解説していきます。 キングダム覇道は、ただレアリティの高い武将を並べるだけでは勝てません。 システムの仕様を深く理解し、武将同士のシナジーを最大限に引き出すことが勝利への鍵となります。
なぜ天賦900武将がいなくても戦えるのか?
多くのゲームでは、最高レアリティのキャラクターがいるかいないかで、序盤の難易度が大きく変わります。 しかし、キングダム覇道においては、天賦900武将の有無が絶対的な戦力差に直結するわけではありません。

その最大の理由は、後述する「陣形効果」や武将スキルの組み合わせ、つまり「シナジー」が非常に重要だからです。 たとえ一体一体の武将の能力が最高レベルでなくとも、部隊全体として強力なバフをかけたり、特定の戦法をコンボのように繋げたりすることで、格上の相手を打ち破ることも可能です。
特にゲーム序盤は、すべてのプレイヤーが育成途上です。 この段階では、強力な単体武将を持つことよりも、いかに効率よく部隊全体の戦力を底上げできるかが重要になります。 天賦850やSR武将の中にも、特定の役割に特化した非常に優秀な武将が数多く存在します。 彼らを適切に組み合わせることで、天賦900武将を擁する部隊とも互角以上に渡り合えるのです。 絶望する必要は全くありません、むしろここからが戦略の腕の見せ所です。
【最重要】戦闘力を飛躍させる「陣形効果」を理解しよう
序盤の編制において、何よりも優先すべきなのが「陣形効果」です。 これを意識するかしないかで、部隊のステータスに雲泥の差が生まれます。
陣形効果とは、特定の兵科タイプ(強襲、支援、防御、妨害、遊撃)の主将を3部隊以上編制することで発動する、強力な全体バフのことです。
基本的な陣形効果一覧
| 陣形タイプ | 3部隊以上編制時の効果 | 主な役割・特徴 |
|---|---|---|
| 強襲 | 部隊の攻撃+20% | 物理攻撃によるダメージディーラー。敵部隊の殲滅を得意とする。 |
| 支援 | 部隊の戦法威力+25% | 戦法(スキル)によるダメージやバフ・デバフが強力。部隊の核となる。 |
| 防御 | 部隊の防御+20% | 高い耐久力で前線を支える。味方を守ったり、敵の攻撃を引きつけたりする。 |
| 妨害 | 部隊の策略+20% | 策略攻撃やデバフで敵をかく乱する。知力系の武将が多い。 |
| 遊撃 | 部隊の破壊+20% | 攻城戦において、城や施設へのダメージが高くなる。 |
見ての通り、特定のステータスが20%~25%も上昇するのは破格の効果です。 例えば、強襲タイプの武将3人で部隊を組めば、それだけで全部隊の攻撃力が20%もアップします。 これは武将のレベルをいくつか上げるよりも遥かに大きな影響を及ぼします。
したがって、序盤の編制では、まず「どの陣形効果を発動させるか」を決めることから始めましょう。 手持ちの武将の中で、比較的数が揃っているタイプの主将を3人選び、それを軸に他の部隊を組んでいくのが定石です。 序盤で特におすすめなのは、戦法の威力を大きく高める「支援」タイプか、物理攻撃の要となる「強襲」タイプを3部隊揃えることです。
編成の前に知るべき「状態変化」のルール
次に重要なのが「状態変化」、いわゆるバフやデバフの仕様です。 これを知らないと、せっかくのスキルが無駄になってしまう可能性があります。 キングダム覇道の状態変化は、大きく「能力変化」と「特殊変化(有利変化・不利変化)」に分けられます。
能力変化と有利変化の決定的な違い
| 項目 | 能力変化 | 特殊変化(有利変化) |
|---|---|---|
| 概要 | 攻撃上昇、防御上昇など、基本的なステータスを直接増減させる効果。 | 会心発生上昇、強化延長、防御貫通など、特殊な効果を付与するもの。 |
| 重ねがけ | 効果量・効果時間ともに重複(加算)する。 | 効果量が高い方が優先。効果時間は延長される。 |
| 具体例 | 攻撃+50%の効果中に、攻撃+30%のバフがかかると、合計で攻撃+80%になる。 | 会心発生+20%の効果中に、会心発生+15%のバフがかかっても、+20%のまま。ただし、効果時間はリセット・延長される。 |
この違いは非常に重要です。 特に注目すべきは、特殊変化(有利変化)の仕様です。 例えば、「会心発生率を上げるスキルを複数重ねがけして、発生率100%ループを狙う」といった戦術は、残念ながら不可能です。 効果量の高いスキルで上書き(効果時間は延長)されるだけなので、同じ種類の有利変化を持つ武将を同時に採用する場合は、その発動タイミングや効果量を考慮する必要があります。
一方で、能力変化は単純に加算されていくため、攻撃上昇バフを持つ武将を複数編制し、一気に火力を高めるという戦術は非常に有効です。 この仕様を理解した上で、どの武将のどのスキルを、どの順番で発動させるかを考えるのが編制の醍醐味と言えるでしょう。
主将・副将・補佐の役割と選び方の基本
部隊は主将1人、副将2人、補佐2人の最大5人で構成されます。 それぞれの役割を理解し、適切に配置することが重要です。
- 主将: 部隊の顔となる最も重要なポジションです。部隊の兵科タイプを決定し、主将の戦法がその部隊の基本的な戦い方になります。ステータスも最も反映されやすいため、一番育成が進んでいる武将を配置しましょう。
- 副将: 主将の能力を補強し、戦法連鎖を狙う役割です。主将と技能(スキル)の相性が良い武将を選ぶのがセオリーです。副将の戦法は、主将の戦法発動時に一定確率で連鎖して発動します。
- 補佐: 副将よりもステータスへの影響は小さいですが、技能を100%発動させられるのが大きなメリットです。部隊の特定の能力を底上げしたり、特定の状況で役立つ技能を持つ武将を配置するのが効果的です。例えば、「〇〇の兵力をアップ」や「特定の敵に対するダメージアップ」などの技能が有効です。
序盤は、まず主将と副将の組み合わせを重視しましょう。 特に、主将の戦法を強化できるような技能を持つ武将を副将に置くと、部隊の火力が大きく向上します。
天賦900不要!序盤のおすすめ編制具体例
それでは、ここまでの基本戦略を踏まえた上で、天賦900武将を使わずに組める具体的な序盤のおすすめ編制を3パターン紹介します。 ご自身の手持ち武将と照らし合わせながら、参考にしてみてください。

パターン1:会心攻撃特化型・強襲編制
SR武将「信」を主軸に、通常攻撃の火力を極限まで高める編制です。 シンプルながら非常に強力で、敵部隊を素早く殲滅できます。
編成コンセプトと強み
この編成のコンセプトは、「陣形効果で底上げした攻撃力を、会心発生率アップのバフでさらに強化し、信の通常攻撃で大ダメージを叩き出す」ことです。 強襲タイプの陣形効果(攻撃+20%)を発動させることを前提とします。
- 強み:
- SR信が主人公であり、比較的入手・育成しやすい。
- 戦法だけでなく、通常攻撃でも継続的に火力を出せる。
- 武将同士のシナジーが分かりやすく、初心者でも扱いやすい。
編成例と各武将の役割
| ポジション | 部隊1(主軸) | 部隊2 | 部隊3 | 部隊4 | 部隊5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SR 信(強襲) | SR 壁(支援) | SR 沛浪(強襲) | (自由枠・強襲) | (自由枠) |
| 副将1 | (攻撃系武将) | (サポート系武将) | (攻撃系武将) | ||
| 副将2 | (攻撃系武将) | (サポート系武将) | (攻撃系武将) |
※部隊4には強襲タイプの主将を配置し、陣形効果を発動させます。
- SR 信(主将): この編成のメインアタッカー。自身の戦法で攻撃力を上げつつ、高い攻撃力で敵を圧倒します。
- SR 壁(主将): 非常に重要なサポーター。戦法で味方中列に「会心発生率+20%」のバフを付与します。このバフを信に届かせるのが最大の目的です。
- SR 沛浪(主将): 壁のサポート役。戦法でこちらも「会心発生率+15%」のバフを付与します。前述の通り、効果量は壁の20%が優先されますが、効果時間を延長する役割を担います。これにより、信が長時間にわたって高会心率を維持できます。
戦闘の流れと部隊配置
この編成の鍵は「部隊配置」と「戦法の発動順」です。
- 部隊配置: 信、壁、沛浪の3部隊を中列に配置します。壁のバフは中列の味方にしかかからないため、この配置は必須です。
- 戦闘開始後: まず信が自身の戦法で攻撃力を高めます。
- 次に壁の戦法が発動: 信に会心発生+20%のバフがかかります。
- 続いて沛浪の戦法が発動: 信にかかっている会心発生バフの効果時間を延長します。
- 結果: 約20秒間、信は会心発生率が20%アップした状態で通常攻撃を繰り出し続け、大ダメージを稼ぎます。
この一連の流れが非常に強力です。 自由枠には、同じく強襲タイプの主将を入れて陣形効果を確定させつつ、残りの1枠は手持ちで最も強力な武将を入れましょう。
パターン2:戦法ダメージ重視・支援編制
次に、強力な戦法(スキル)を連打して敵を殲滅する、支援タイプを軸とした編制です。 知力系の武将が揃っている場合におすすめです。
編成コンセプトと強み
コンセプトは「支援タイプの陣形効果(戦法威力+25%)を最大限に活かし、高威力の戦法を叩き込む」ことです。 物理攻撃ではなく、スキルダメージが主なダメージソースとなります。
- 強み:
- 一撃の火力が非常に高く、短期決戦を狙える。
- 範囲攻撃を持つ武将を組み合わせれば、複数の敵部隊を同時に削れる。
- UR武将「王翦」など、強力な知力系武将を引けた場合に真価を発揮する。
編成例と各武将の役割
| ポジション | 部隊1(主軸) | 部隊2 | 部隊3 | 部隊4 | 部隊5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | UR 王翦(支援) | SR 舜水樹(支援) | SR 河了貂(支援) | (自由枠) | (自由枠) |
| 副将1 | (知力系武将) | (サポート系武将) | (サポート系武将) | ||
| 副将2 | (知力系武将) | (サポート系武将) | (サポート系武将) |
※主軸はUR王翦としていますが、他の高威力戦法を持つ支援タイプの武将でも代用可能です。
- UR 王翦(主将): 強力な範囲攻撃戦法を持つメインアタッカー。陣形効果で威力がさらに増し、敵部隊を一網打尽にします。
- SR 舜水樹(主将): 敵にデバフを付与しつつ、ダメージを与えることができる優秀なサポーター兼サブアタッカー。
- SR 河了貂(主将): 味方部隊の戦法ゲージを上昇させる非常に貴重な戦法を持ちます。これにより、味方全体の戦法回転率が上がり、結果的に総ダメージ量を増やすことができます。
戦闘の流れ
この編成では、いかに早く主軸となるアタッカーの戦法を発動させるかが重要になります。
- 戦闘開始後: まず河了貂の戦法を発動させ、王翦などアタッカーの戦法ゲージを溜めます。
- ゲージが溜まり次第: 王翦や舜水樹の戦法を敵部隊に叩き込みます。
- 繰り返し: 河了貂のサポートを受けながら、高威力の戦法を連発して敵を圧倒します。
この編成は、戦法ダメージを強化する技能を持つ武将を副将や補佐に置くことで、さらに火力を高めることができます。
パターン3:鉄壁の守り・防御編制
最後に、高い耐久力で敵の猛攻を受け止め、じっくりと勝利を目指す防御タイプの編制です。 格上の敵に挑む際や、長期戦になりがちな場面で輝きます。
編成コンセプトと強み
コンセプトは「防御タイプの陣形効果(防御+20%)で部隊全体の耐久力を高め、敵の攻撃を耐え凌ぎながら反撃の機会を窺う」ことです。
- 強み:
- 部隊が壊滅しにくく、安定した戦いができる。
- 敵の強力な攻撃を引きつけ、味方のアタッカーを守ることができる。
- SR武将にも優秀な防御タイプの武将が多い。
編成例と各武将の役割
| ポジション | 部隊1(タンク) | 部隊2 | 部隊3 | 部隊4(アタッカー) | 部隊5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SR 蒙驁(防御) | SR 馮忌(防御) | SR 黒桜(防御) | (強襲or支援) | (自由枠) |
| 副将1 | (防御系武将) | (防御系武将) | (サポート系武将) | (攻撃系武将) | |
| 副将2 | (防御系武将) | (防御系武将) | (サポート系武将) | (攻撃系武将) |
- SR 蒙驁(主将): 自身に防御バフをかけ、さらに敵の攻撃を引きつける「挑発」効果を持つ優秀なタンク役です。
- SR 馮忌(主将): 味方への防御バフを持ち、部隊全体の耐久力を底上げします。
- SR 黒桜(主将): 敵の攻撃力を下げるデバフを持ち、相対的に味方の生存率を高めます。
- 部隊4(アタッカー): 防御部隊が稼いだ時間で、信や王翦などのアタッカーが敵を殲滅します。
戦闘の流れ
この編成は、前線で敵の攻撃を受け止めるタンク役と、後方からダメージを出すアタッカー役の連携が重要です。
- 戦闘開始後: 蒙驁などのタンク部隊を敵のアタッカー部隊にぶつけ、攻撃を引きつけます。
- 同時に: 馮忌や黒桜がバフ・デバフで戦線を維持します。
- 後方から: 安全を確保されたアタッカー部隊が、敵を一体ずつ確実に撃破していきます。
派手さはありませんが、確実に勝利を掴むための堅実な編成と言えるでしょう。
序盤を効率よく進めるための育成ガイド
強力な編成を組んでも、武将の育成が伴わなければ宝の持ち腐れです。 ここでは、特に序盤に意識すべき育成のポイントを解説します。
どの武将から育てるべき?育成優先度の考え方
リソースが限られる序盤では、育成する武将を絞ることが非常に重要です。 優先すべきは、以下の特徴を持つ武将です。
- 編成の核となる主将: 上で紹介した編成例で言えば、信や王翦、蒙驁など、部隊のコンセプトを決定づける武将を最優先で育成しましょう。
- 汎用性の高いサポーター: 壁や河了貂のように、様々な編成で活躍できるバフ・デバフ役も育成優先度は高いです。
- 技能が優秀な武将: たとえステータスが低くても、補佐枠で輝く優秀な技能を持つ武将もいます。レベル上げは後回しでも、技能のレベルだけは上げておくと良いでしょう。
まずは主軸となる5部隊の主将レベルを均等に上げ、その後、メインアタッカーのレベルを重点的に上げていくのが効率的です。
【要注意】SR武将の将星ランクアップは慎重に
武将の育成要素の中でも、特に注意が必要なのが「将星ランクアップ」です。 将星を上げるには、同じ武将の友好度を集めるか、「将星石」という貴重なアイテムを使用します。
この将星石ですが、序盤は比較的入手できるものの、すぐに枯渇します。 そのため、手当たり次第にSR武将の将星を上げてしまうと、本当に上げたい武将が出てきたときに石が足りないという事態に陥ります。
- 対策:
- 将星石を使うのは、本当に主力として長く使うと決めたSR武将だけに絞る。
- まずはガチャなどで武将が重複し、自然に将星が上がるのを待つ。
- 特に、R武将に将星石を使うのは避けましょう。
どの武将に将星石を使うべきか迷ったら、一度立ち止まって考える時間を持つことが重要です。 この判断が、後々大きな戦力差となって表れてきます。
武将だけじゃない!装備と兵士レベルの重要性
部隊の戦力は、武将のレベルや将星ランクだけで決まるわけではありません。 「装備」と「兵士レベル」も非常に重要な要素です。
- 装備: 武将に装備させることで、ステータスを直接強化できます。特に、主将に装備させる武器や防具は、強化を怠らないようにしましょう。不要な装備は分解して、主力の装備の強化素材にすることができます。
- 兵士: 各兵舎のレベルを上げることで、出陣する兵士のレベルと質が向上します。兵士は部隊のHPであり、手数でもあります。君主レベルが上がったら、まずは各兵舎のレベルを上げることを習慣づけましょう。
武将の育成に行き詰まりを感じたら、装備や兵士レベルの見直しをしてみてください。 それだけで部隊の戦力が大きく向上することがあります。
まとめ
今回は、天賦900武将を使わない序盤のおすすめ編制について、基本的な考え方から具体的な編成例、育成のポイントまでを徹底的に解説しました。
- 最重要は「陣形効果」。まずは特定のタイプを3部隊揃えることを目指す。
- バフの仕様を理解し、武将同士のシナジーを考える。
- 「会心攻撃型」「戦法ダメージ型」「防御型」など、自分の手持ちに合った編成を組む。
- 将星石などの貴重なリソースは、慎重に使う。
キングダム覇道は、高い戦略性が魅力のゲームです。 天賦900武将がいなくても、知識と工夫次第で十分に最前線で戦うことができます。 今回紹介した内容を参考に、あなただけの最強部隊を編制し、中華統一への道を突き進んでください。