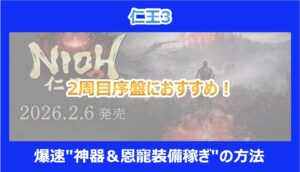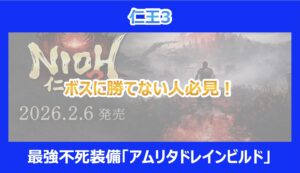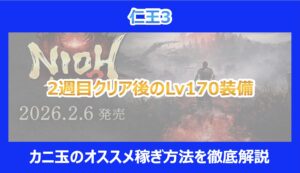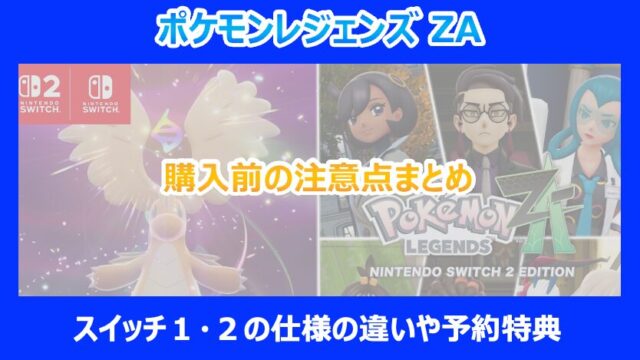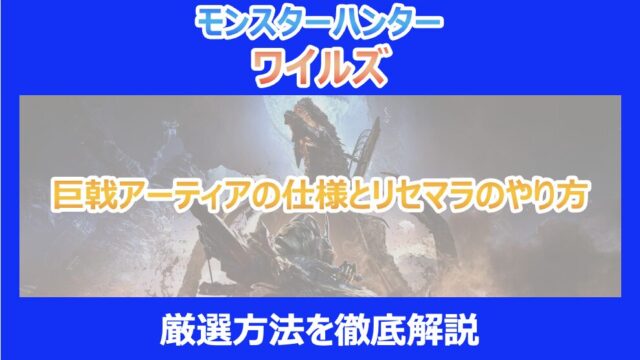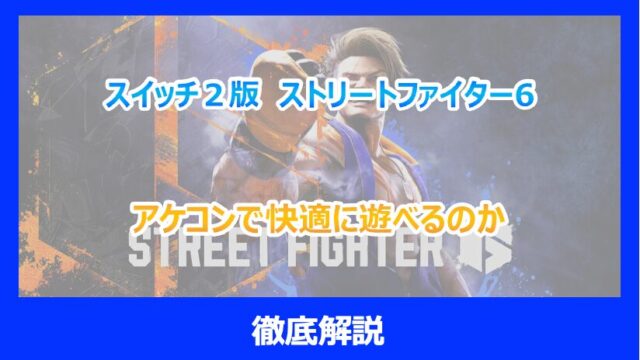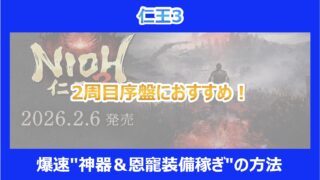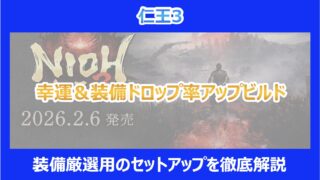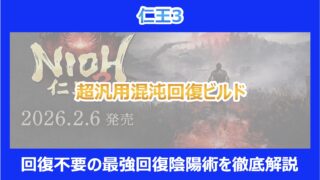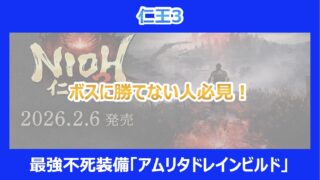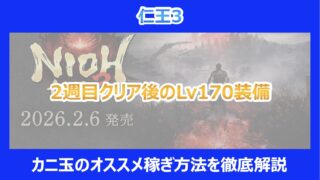ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年10月2日に発売された待望の新作オープンワールド時代劇アクション『Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)』のリアルな評価や、購入すべきかどうかを知りたいと思っているのではないでしょうか。

この記事を読み終える頃には、あなたが『Ghost of Yōtei』を買うべきかどうかの疑問が解決しているはずです。
- 美麗なグラフィックで描かれる新たな舞台
- 前作から正統進化した奥深い戦闘システム
- 広大な大地を冒険する探索の楽しさ
- 本作を購入すべきかどうかの最終判断
それでは解説していきます。

Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)とは?ゲーム概要と全体評価
待望の新作『Ghost of Yōtei』、通称「GOY」がついに発売されました。 前作『Ghost of Tsushima』の魂を受け継ぎつつ、新たな舞台、新たな物語、そして進化したシステムで我々プレイヤーを再び魅了してくれます。 私自身、発売日から時間を忘れてプレイに没頭していますが、結論から言うと「期待を遥かに超える傑作」です。 このセクションでは、まず本作がどのようなゲームなのか、その概要と全体的な評価について解説していきます。

Ghost of Yōteiの製品情報
本作は、Sucker Punch Productionsが開発を手掛けたオープンワールド時代劇アクションゲームです。 まずは基本的な製品情報を見てみましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | Ghost of Yōtei (ゴースト・オブ・ヨウテイ) |
| 発売日 | 2025年10月2日 |
| 対応機種 | PlayStation 5, PC (Steam, Epic Games Store) |
| ジャンル | オープンワールド・時代劇アクションアドベンチャー |
| CERO | Z (18才以上のみ対象) |
| 開発元 | Sucker Punch Productions |
| 価格 | 通常版: 9,880円 (税込) / デラックス版: 11,880円 (税込) |
前作同様、今作もCERO Z指定となっており、容赦のない斬り合いや血の表現が含まれています。 しかし、それが本作のリアリティと緊張感を高めている重要な要素であることは間違いありません。
やり込みゲーマーによる最速プレイレビュー
ゲーム評論家として、そして一人のゲーマーとして、忖度なしのレビューをお届けします。 まず、本作を起動して最初に感じたのは、その圧倒的なまでのグラフィックの進化です。 PS5の性能を限界まで引き出した映像美は、息をのむほど。 特に光や風、そして雪の表現は、もはや実写と見紛うレベルに達しています。

ゲームプレイの核となる戦闘は、前作の完成されたシステムをベースに、新たな要素が加わることで、さらに戦略的で奥深いものへと進化しました。 単に敵を斬り伏せるだけでなく、敵の種類や状況に応じて武器や戦術を切り替える必要があり、常に緊張感のある駆け引きが楽しめます。
探索面では、舞台が対馬から北海道(蝦夷地)へと移ったことで、全く新しい冒険が待っています。 広大で厳しい自然、アイヌの文化など、前作とは異なる魅力に満ちた世界が広がっており、ただ歩いているだけでも新たな発見や出会いがプレイヤーを待ち受けています。
ストーリーは前作のテーマ性を引き継ぎつつも、新たな主人公による復讐の物語が描かれます。 単純明快でありながら、プレイヤーの心を揺さぶる重厚なドラマが展開され、一度始めるとやめ時を見失うほど引き込まれます。
総じて、前作ファンはもちろん、これまでこのシリーズに触れてこなかったアクションゲームファン、時代劇ファンにも自信を持っておすすめできる、まさに「神ゲー」と呼ぶにふさわしい一作です。
前作『Ghost of Tsushima』との違いは?
多くの人が気になるのが、前作『Ghost of Tsushima』との違いでしょう。 本作は続編ではありますが、単なる舞台やストーリーの変更に留まらない、数多くの進化を遂げています。

舞台の変更とそれに伴う環境の変化
最大の変更点は、舞台が対馬から、幕末の動乱期にある「蝦夷地」、現在の北海道に移ったことです。 羊蹄山を望む雄大な大地、厳しい冬の雪景色、そして独自の文化を育んできたアイヌの集落など、対馬とは全く異なるロケーションが広がっています。 この環境の変化は、単なるビジュアルの違いだけでなく、ゲームプレイにも影響を与えます。 例えば、吹雪の中では視界が悪くなり、敵に気づかれやすくなったり、雪深い場所では移動速度が落ちたりと、よりサバイバル要素が強まっています。
戦闘システムの深化
戦闘システムも大きく進化しました。 前作の「型」のシステムは、「武器の切り替え」という形で昇華されています。 刀、二刀流、槍、大太刀など、複数の武器を瞬時に切り替えながら戦うことが可能になり、敵の兵種に対する特効を考える戦略性が増しました。 詳細は後述しますが、この新システムが戦闘をよりダイナミックで面白いものにしています。
強化要素の初期解放
前作ではストーリーを進めることでアンロックされていた強化系の要素(連続キルで発動する無双状態など)が、本作では序盤から解放されています。 これにより、ゲーム開始直後から爽快感のあるアクションを存分に楽しむことができ、プレイヤーがストレスを感じにくい設計になっている点も評価できます。
美麗すぎるグラフィックと世界観
本作のグラフィックは、現行機最高峰と言っても過言ではありません。 PS5版のパフォーマンスモード(60FPS)でプレイしていても、その美しさに何度も足を止めてしまうほどです。

光と自然の圧倒的な表現力
開発スタジオの光の使い方は、もはや芸術の域に達しています。 木々の間から差し込む太陽光、月明かりに照らされる雪原、燃え盛る炎の揺らめきなど、全てのシーンが絵画のように美しいです。 特に、本作の舞台となる北海道の雄大な自然描写は圧巻の一言。 どこを切り取ってもスクリーンショット映えする美しい世界が、プレイヤーの冒険心を掻き立てます。
細部まで作り込まれた世界
建物やキャラクターの衣装、小道具に至るまで、時代考証に基づいた作り込みが徹底されています。 和人の町並みと、アイヌのコタン(集落)では、文化や生活様式の違いが明確に表現されており、その世界に生きる人々の息遣いまで感じられるようです。 こうした細部へのこだわりが、ゲームへの没入感を極限まで高めています。
Ghost of Yōteiの核心的魅力!戦闘システムを徹底解剖
『Ghost of Yōtei』の面白さの中核をなすのが、緊張感と爽快感が両立した戦闘システムです。 前作で高く評価された剣戟アクションをベースに、さらなる改良と新要素が加えられ、プレイヤーを飽きさせない工夫が凝らされています。 ここでは、本作の戦闘システムの魅力を徹底的に解剖していきます。

基本となる戦闘スタイルと操作感
本作の戦闘は、大きく分けて二つのスタイルがあります。 一つは、侍の作法に則り、正面から正々堂々と敵に挑む「武士(もののふ)」の道。 もう一つは、闇に紛れ、音もなく敵を葬り去る「冥人(くろうど)」の道です。 プレイヤーは状況に応じてこれらのスタイルを使い分けることになります。
「武士」としての戦闘では、敵の攻撃をギリギリで受け流す「パリィ」や、タイミングよく回避する「見切り」が重要となります。 敵の動きを読み、一瞬の隙を突いて斬り込む剣戟は、まさに真剣勝負そのもの。 敵の攻撃を完璧に捌き、反撃の一太刀を浴びせた時の快感は、本作ならではのものです。
操作感は非常にレスポンシブで、プレイヤーの入力がダイレクトにキャラクターの動きに反映されます。 ストレスなく、思い通りの剣戟アクションが楽しめるでしょう。
新要素「武器の切り替え」と敵との相性
本作で最も注目すべき新要素が「武器の切り替え」システムです。 主人公は「刀」「二刀流」「槍」「薙刀」といった複数の武器を装備しており、戦闘中に十字キーで瞬時に切り替えることができます。
このシステムが面白いのは、それぞれの武器に得意な相手がいる、という点です。
- 刀: バランスが取れた標準的な武器。剣を持つ敵に対して有効。
- 二刀流: 手数が多く、素早い連続攻撃が魅力。槍兵など、防御が手薄な敵に効果的。
- 槍: リーチが長く、間合いを取って戦える。盾を持つ敵の防御を崩しやすい。
- 薙刀: 広範囲を薙ぎ払う攻撃が可能。複数の敵に囲まれた際に真価を発揮する。
例えば、槍を構えた敵に対して刀で挑んでも、リーチの差で苦戦を強いられます。 しかし、素早い二刀流に切り替えて懐に潜り込めば、一気に勝機が見えてきます。 このように、敵の編成や兵種を見極め、最適な武器を選択する戦略性が、本作の戦闘を単調なものにしていません。 戦闘中に流れるように武器を切り替え、コンボを叩き込む様は、さながらアクション映画のワンシーンのようです。
爽快感抜群の「無双状態」とカウンター
戦闘を盛り上げる要素として、「気力ゲージ」が存在します。 敵を倒したり、パリィを成功させたりすることでゲージが溜まっていき、最大になると強力な必殺技や、一定時間無敵に近い状態になる「無双状態」を発動できます。 この無双状態では、敵を次々と一撃で倒すことができ、圧倒的な爽快感を味わえます。 窮地に陥った時の一発逆転技としても、格下の敵を一掃する手段としても非常に有効です。
また、本作から追加された新たなカウンターギミックも戦闘に深みを与えています。 敵が黄色く光る特殊な攻撃を繰り出すことがあり、このタイミングに合わせて特定のボタンを長押しして離すと、強力なカウンターが発動します。 この攻撃に当たってしまうと、主人公は武器を一時的に落としてしまい、無防備な状態になってしまいます。 タイミングはシビアですが、成功した時のリターンは絶大。 リスクとリターンが絶妙に調整されており、プレイヤーの挑戦意欲を掻き立てます。
闇討ち(ステルス)は健在?
もちろん、冥人としての闇討ちも健在です。 物陰に隠れ、敵の背後から忍び寄り、一撃で仕留めるステルスキルは、多くの敵が待ち受ける拠点を攻略する上で非常に有効な手段となります。 煙玉やクナイといったお馴染みの暗器に加え、アイヌの狩猟道具を応用した新たな暗器も登場し、ステルスプレイの幅がさらに広がりました。
ただし、本作では敵のAIも強化されており、物音や仲間の異変に敏感に反応するようになっています。 闇討ちを成功させるには、より慎重な立ち回りと、地形や道具を駆使した戦略が求められます。 真正面からの斬り合いに自信がないプレイヤーでも、冥人の道を極めることでゲームを有利に進めることが可能です。
引き込まれる物語と広大なオープンワールド
『Ghost of Yōtei』の魅力は、戦闘システムだけではありません。 プレイヤーを惹きつけてやまない重厚な物語と、どこまでも冒険したくなる広大なオープンワールドも、本作を傑作たらしめる重要な要素です。
単純明快な復讐のストーリー
物語の舞台は、幕末の蝦夷地。 主人公は、かつて蝦夷地を統治していた松前藩の若き侍。 しかし、突如として現れた謎の勢力の襲撃により、一族も仲間も全てを失い、自らも死の淵を彷徨います。 かろうじて一命を取り留めた彼は、復讐の念を胸に、己の名を捨てて冥府から蘇った「冥人」として、たった一人の戦いを始める…というのが本作のあらすじです。
「復讐劇」という王道のストーリーラインは、非常に分かりやすく、プレイヤーが感情移入しやすい作りになっています。 前作のような「武士の誉れ」と「冥人の道」との間で揺れ動く内面の葛藤は、今のところ薄い印象ですが、その分、復讐という一つの目的に向かって突き進む純粋な物語は、プレイヤーを飽きさせることなく、エンディングまで一気に駆け抜けさせてくれます。 もちろん、物語を進める中で、復讐の先に何があるのか、主人公の心境にどのような変化が訪れるのか、という点にも注目です。
北海道を舞台にした広大なマップの探索
本作のオープンワールドは、ただ広いだけではありません。 その広大なマップの中に、探索したくなる魅力的な要素がびっしりと詰め込まれています。
情報を集めてマップを切り開く楽しみ
本作のユニークな点として、ゲーム開始直後のマップには、ほとんど情報が記載されていないことが挙げられます。 道端で助けた村人や、町で出会った情報屋など、人々との交流を通じて、新たな場所やクエストの情報がマップに書き込まれていくのです。 このシステムにより、「あそこに行けば何かあるかもしれない」という、手探りの冒険を楽しむことができます。 自分の足で世界を切り開いていく感覚は、他のオープンワールドゲームではなかなか味わえない、本作ならではの醍醐味と言えるでしょう。
多様なロケーションと自然環境
雪深いの山々、広大な湿原、神秘的な雰囲気の森、活気あふれる港町、そして静かなアイヌのコタン。 蝦夷地には、驚くほど多様なロケーションが存在します。 季節や天候の概念もあり、同じ場所でも訪れるタイミングによって全く違う表情を見せてくれます。 美しい景色を求めて、愛馬と共にただ当てもなく旅をするだけでも、十分に価値のある時間となるはずです。
偶然の出会いが新たなクエストを生む
広大なマップを移動していると、様々なイベントに遭遇します。 熊に襲われている旅人、野盗に捕らえられた村人、そして主人公の首を狙う賞金稼ぎ。 こうした偶然の出会いが、新たなサブクエスト(浮世草)の始まりとなることも少なくありません。
特に本作で数多く登場するのが、「賞金首」の討伐クエストです。 各地に潜むお尋ね者たちの情報を集め、彼らを追い詰めていく一連のクエストは、メインストーリーとはまた違った楽しさがあります。 マップ上では何もないように見える場所でも、一歩足を踏み入れると、思わぬドラマが待っている。 この寄り道の楽しさが、プレイヤーを『Ghost of Yōtei』の世界に深く没入させてくれます。
Ghost of Yōteiは買うべき?こんな人におすすめ!
ここまで本作の魅力を語ってきましたが、最終的に「このゲームは買う価値があるのか?」という点が最も重要でしょう。 ここでは、本作のメリット・デメリットを整理し、どのような人に『Ghost of Yōtei』がおすすめできるのかを解説します。
本作のメリット・良い点まとめ
まずは、本作をプレイして感じた素晴らしい点をまとめます。
- 圧倒的なグラフィック: 現行機最高峰の映像美で描かれる世界は、それだけで価値がある。
- 進化した戦闘システム: 武器の切り替えによる戦略性の高いアクションが楽しめる。
- 爽快感のあるアクション: 序盤から強力な技が使え、ストレスなく敵をなぎ倒せる。
- 探索の楽しさ: 自分の足でマップを埋めていく、手探りの冒険が味わえる。
- 引き込まれるストーリー: 王道ながらも重厚な復讐の物語に没入できる。
- 豊富なコンテンツ: メインストーリー以外にも、やり込み要素が満載で長く遊べる。
本作のデメリット・注意点まとめ
一方で、完璧なゲームというわけではありません。 人によっては合わないと感じる可能性のある点も挙げておきます。
- 新鮮味の薄さ: 基本的なゲームシステムは前作を踏襲しているため、全く新しい体験を求める人には物足りないかもしれない。
- CERO Z指定: 残酷な表現が苦手な人にはおすすめできない。
- 高めの難易度: アクションゲームが苦手な人にとっては、一部の戦闘が難しく感じられる可能性がある。(ただし、難易度設定は変更可能)
- 単調さを感じる可能性: 広大なマップの移動や、似たようなサブクエストに作業感を感じる人もいるかもしれない。
時代劇やアクション好きなら間違いなく「買い」
上記のメリット・デメリットを踏まえた上で、私が断言できるのは「時代劇やアクションゲームが好きなら、間違いなく『買い』」だということです。 特に、以下のような嗜好を持つ方には、本作が最高のゲーム体験を提供してくれることを保証します。
- 美しい和の世界を自由に冒険したい人
- 緊張感のある剣戟アクションを楽しみたい人
- 映画のような重厚なストーリーに浸りたい人
- 一つのゲームをじっくりと長く遊びたい人
- 前作『Ghost of Tsushima』が好きだった人
これらのいずれかに当てはまるのであれば、購入して後悔することはないでしょう。
特殊モード(黒澤モードなど)の楽しみ方
本作には、通常のプレイとは一味違った体験ができる特殊な描画モードが搭載されています。 有名なのが、往年の時代劇映画のような白黒映像になる「黒澤モード」です。 このモードでは、映像だけでなく、音声にも特殊な加工が施され、まるで古い映画を観ているかのような感覚でゲームをプレイできます。
ただし、ゲームプレイ上のデメリットもあります。 敵の攻撃予兆を示す色の違いが分からなくなるため、戦闘の難易度が格段に上がります。 ゲームに慣れてきた2周目以降や、腕に自信のあるプレイヤーが雰囲気を楽しむためのモードと考えるのが良いでしょう。
他にも、カメラアングルが近くなり、より臨場感が増す「三池モード」や、BGMが変化する「渡辺モード」など、ユニークなモードが用意されています。 これらを組み合わせることで、自分だけの映画的体験を創り出すのも、本作の楽しみ方の一つです。
まとめ
今回は、2025年10月2日に発売された『Ghost of Yōtei』について、徹底的にレビューしました。
本作は、前作『Ghost of Tsushima』の成功を見事に受け継ぎ、あらゆる面で正統進化を遂げた傑作です。 PS5の性能をフルに活かした圧倒的なグラフィック、より深く、より戦略的になった戦闘システム、そして新たな舞台で繰り広げられる壮大な復讐の物語。 そのどれもが、最高品質でプレイヤーに提供されます。
もちろん、前作を踏襲している部分も多いため、斬新な驚きという点では少し物足りなさを感じるかもしれません。 しかし、その完成度の高さ、作り込みの深さは、他の追随を許さないレベルに達しています。
もしあなたが、息をのむほど美しい世界で、魂を揺さぶるような冒険をしたいと願うなら、『Ghost of Yōtei』は、その期待に120%で応えてくれるはずです。 この秋、最高のゲーム体験を求めるすべてのゲーマーに、私は本作を強く推薦します。 ぜひ、あなたの手で、蝦夷地の冥人として新たな伝説を刻んでください。