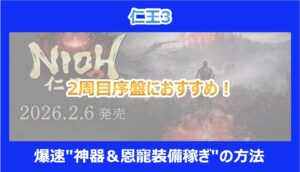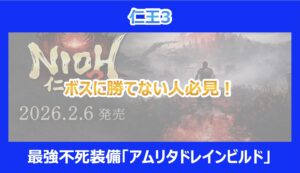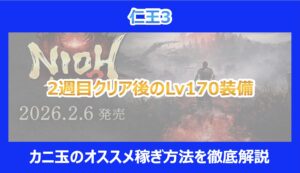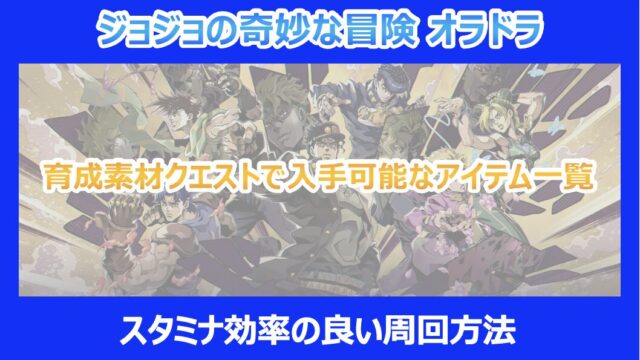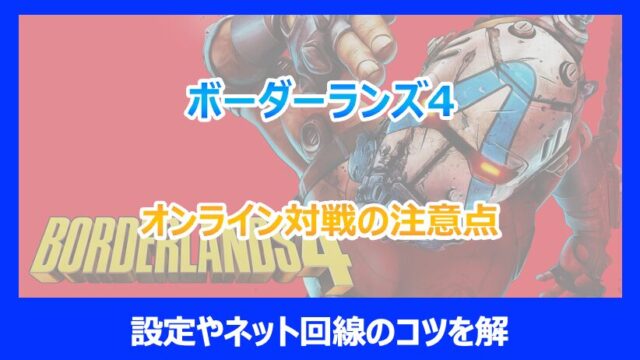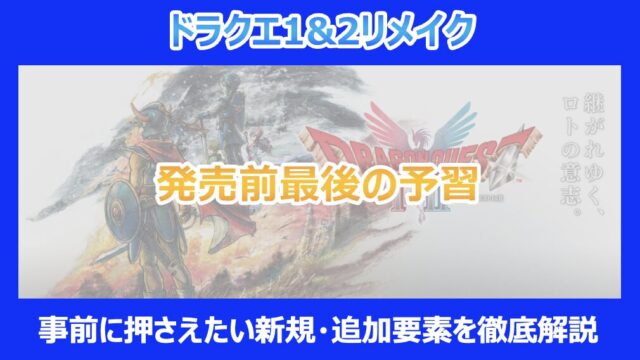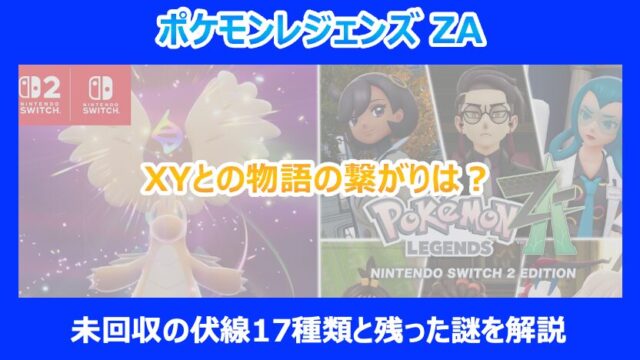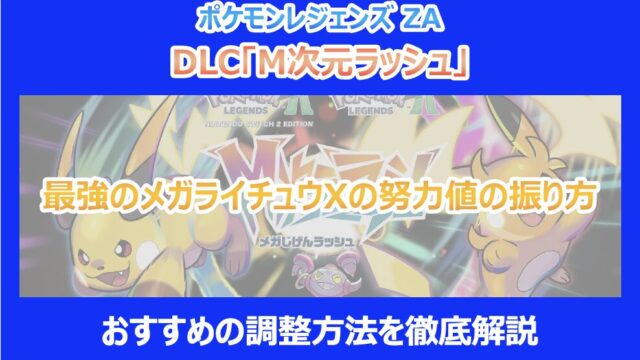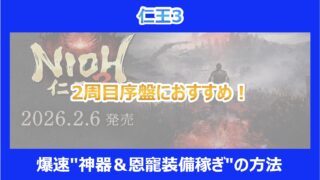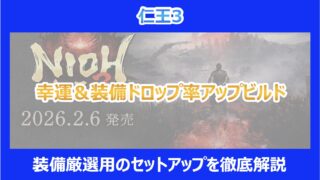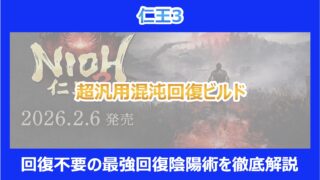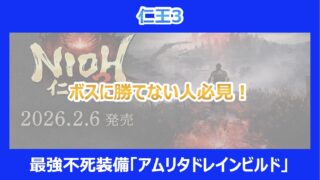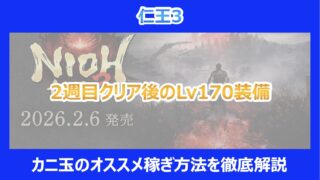ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年10月2日に発売された待望の新作『Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)』の難易度について、「前作は難しかったって聞くけど、今作はどうなの?」「アクションが苦手な自分でもクリアできるかな?」といった点が気になっているのではないでしょうか。

ご安心ください。 私自身、発売日からじっくりとクリアまでやり込みました。 その経験から断言します。 今作は、驚くほど幅広いプレイヤー層が楽しめるように設計されています。
この記事を読み終える頃には、あなたが『Ghost of Yōtei』を購入すべきかどうか、その難易度に対する疑問がスッキリ解決しているはずです。
- 今作の親切な難易度設定の詳細
- アクションが苦手な人向けの豊富な救済措置
- 前作と今作の難易度の徹底比較
- 初心者でも上達できる具体的な攻略のコツ
それでは解説していきます。

Ghost of Yōteiの難易度はどう?【結論:初心者でも全く問題なし】
さっそく結論からお伝えします。 『Ghost of Yōtei』の難易度は、アクションゲーム初心者の方でも全く問題なくクリアできるレベルです。
前作『ゴースト・オブ・ツシマ』が、その歯ごたえのある戦闘から一部で「高難易度」という評価を受けていたため、心配する声が多いのも無理はありません。 しかし、開発スタジオのサッカーパンチ・プロダクションは、その点を十分に理解しているようです。

今作では、プレイヤーが自身のスキルレベルに合わせて細かく難易度を調整できる機能が大幅に強化されました。 ストーリーを純粋に楽しみたい人から、ギリギリの死闘を求める熟練プレイヤーまで、誰もが満足できる懐の深い作品に仕上がっています。
もしあなたが「美しい世界観やストーリーは気になるけど、アクションで詰みたくない」という理由で購入を迷っているなら、それは非常にもったいないことです。 ぜひ、このレビューを読んでその不安を払拭してください。
Ghost of Yōteiの難易度設定を徹底解説
今作の難易度は、ゲーム開始時、またゲームの途中でもいつでも、以下の4つの主要な設定から選択できます。 それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
| 難易度 | 対象プレイヤー | 敵の強さ | パリィ(受け流し)の易しさ | プレイヤーの体力 |
|---|---|---|---|---|
| 物語 | アクションが苦手な方・物語に集中したい方 | 非常に弱い | 非常に易しい | 非常に多い |
| 易しい | アクション初心者の方 | 弱い | 易しい | 多い |
| 普通 | 標準的な難易度で楽しみたい方 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 難しい | 歯ごたえのある戦闘を求める方 | 強い | シビア | 少ない |
| 冥人 | クリア後に解放される最高難易度 | 非常に強い | 非常にシビア | 一撃で瀕死 |
難易度「物語」:ストーリーテリングを最大限に楽しむモード
「アクションは本当に苦手。 でも、江戸時代の北海道を舞台にした復讐劇は見たい!」。 そんなあなたのためのモードが、この「物語」です。
この難易度では、敵の攻撃力や体力が大幅に低下し、プレイヤーがやられることはほとんどありません。 戦闘はあくまで物語のスパイスとして機能し、難しい操作を要求される場面は皆無と言っていいでしょう。
また、敵の攻撃に合わせてタイミングよくボタンを押す「パリィ(受け流し)」の受付時間も非常に長く設定されています。 適当に防御ボタンを連打しているだけでも、まるで達人のような華麗なカウンターが決まることも。 これにより、アクションが苦手な方でも爽快感のある剣戟を簡単に体験できます。
主人公「あつ」の心の成長を描く重厚な人間ドラマに、どっぷりと浸かりたい方には最適な選択です。
難易度「易しい」:アクションの基本を学ぶのに最適
「アクションゲームはあまりやったことがないけど、少しは自分で戦っている感覚も味わいたい」。 そんなアクション入門者の方におすすめなのが「易しい」モードです。
「物語」モードほど極端ではありませんが、敵は手強くなく、プレイヤーの体力にも余裕があります。 基本的な操作やコンボ、多彩な兵具(飛び道具や暗器)の使い方を、実践を通じてゆっくりと学んでいくことができます。
もし戦闘で何度か負けてしまっても、ペナルティはほとんどありません。 直前のチェックポイントからすぐにリトライできるため、ストレスなく挑戦を続けられます。 このモードでゲームに慣れ、「もっとやれそうだ」と感じたら、途中で「普通」に切り替えてみるのも良いでしょう。
難易度「普通」:開発者が想定する標準バランス
ほとんどのプレイヤーが最初に選ぶであろう、最も標準的な難易度です。 開発者が意図した通りのゲームバランスで、『Ghost of Yōtei』の世界を隅々まで堪能できます。
油断すれば雑魚敵の集団にも苦戦しますし、ボス敵との戦いでは緊張感のある駆け引きが求められます。 しかし、理不尽な難しさはありません。 敵の動きをよく観察し、適切な武器を選び、スキルや兵具を駆使すれば、必ず勝機は見えてきます。
試行錯誤の末に強敵を打ち破った時の達成感は格別です。 前作をプレイした方や、他のアクションゲームに慣れている方であれば、この「普通」モードで始めるのが最も楽しめるはずです。
難易度「難しい」以上:己の技量を試す修羅の道
ゲームに自信のあるベテランプレイヤー向けの高難易度モードです。 敵の攻撃は苛烈を極め、体力も大幅に上昇します。 わずかなミスが命取りとなるため、完璧な立ち回りが要求されます。
特に、ゲームを一度クリアすると解放される最高難易度「冥人」は圧巻です。 敵味方ともに攻撃力が極限まで高められ、一太刀が勝敗を分けるリアルな斬り合いを体験できます。 まさに、時代劇の達人になりきってプレイするモードと言えるでしょう。
全てのスキルを解放し、装備を整え、万全の準備で挑んでください。 このモードを制覇した時、あなたは真の「羊蹄の冥人」となるでしょう。
アクション初心者を支える豊富なアシスト機能
難易度設定だけでなく、今作にはアクションが苦手なプレイヤーを助けるための機能が数多く搭載されています。 これらを活用することで、ゲームの難しさをさらに緩和することが可能です。

狙いやすさ(エイムアシスト)機能
弓や銃といった遠距離武器を使う際に、自動で敵に照準を合わせてくれる機能です。 アシストの強度は複数段階から調整可能。 最大にすれば、だいたい敵のいる方向にカメラを向けるだけで、面白いようにヘッドショットが決まります。 遠くの敵を素早く処理できると、近接戦闘が非常に楽になります。
パリィタイミングの視覚化
敵が攻撃を繰り出す直前に、その武器が一瞬だけ光るエフェクトが追加されました。 この光に合わせて防御ボタンを押せば、パリィが成功しやすくなります。 「どのタイミングでボタンを押せばいいか分からない」という初心者の方が、視覚的にタイミングを掴むための優れたガイドとなっています。
ロックオン機能の強化
前作ではやや癖のあったロックオン機能が改善され、より直感的に狙いたい敵を捉え続けられるようになりました。 特に複数の敵に囲まれた際に、特定の敵に集中して攻撃を加えたい場面で非常に役立ちます。 乱戦が苦手な方には嬉しい改良点です。
稽古場(チュートリアルモード)の充実
今作では、いつでも立ち寄れる「稽古場」が各地に存在します。 ここでは、新しく覚えた技やコンボを、心ゆくまで練習することができます。 木の人形を相手に、ダメージを受けることなく立ち回りの確認ができるため、強敵に挑む前の準備運動として最適です。
これらのアシスト機能は、オプション画面からいつでもオン・オフを切り替えられます。 自分の成長に合わせて少しずつ機能をオフにしていくことで、上達を実感できるでしょう。
前作『ゴースト・オブ・ツシマ』との難易度比較
「結局、前作と比べて簡単になったの?難しくなったの?」という疑問にお答えします。

結論としては、**「最低難易度はより優しく、最高難易度はより手強く」**なったと言えます。 つまり、難易度の選択肢の幅が大きく広がったということです。
戦闘システムの変更点と難易度への影響
前作の戦闘の核であった「構え」システムが、今作では廃止されました。 代わりに、刀、二刀、槍、鎖鎌、大太刀という5種類の武器を切り替えて戦うシステムへと進化しています。
これは一見複雑に思えるかもしれませんが、実際にはより直感的で分かりやすくなりました。 例えば、「盾を持つ敵には大太刀の重い一撃が有効」「素早い敵には二刀の連続攻撃が効果的」といったように、敵の種類と有効な武器の関係が非常に明確だからです。
前作では、状況に応じて4つの構えを瞬時に切り替える判断力が求められ、これが初心者にとって高いハードルとなっていました。 今作では、敵の見た目からどの武器を使えば良いかが判断しやすいため、戦闘の基本戦略を立てやすくなっています。 この変更は、特にアクションゲームに慣れていないプレイヤーにとって、難易度を大きく引き下げる要因となっているでしょう。
探索とサバイバル要素の追加
一方で、探索面では新たな要素が加わり、少しだけ歯ごたえが増しています。 今作の舞台である江戸(北海道)は、ツシマよりも過酷な自然環境です。
- 寒冷地: 雪深い山岳地帯などでは、時間経過で体力が徐々に減少していきます。焚き火や特定の装備で対策しなければ、探索もままなりません。
- 野生動物: 特にヒグマは非常に強力な敵として登場し、油断していると一瞬でやられてしまいます。
しかし、これらの要素も理不尽なものではありません。 「野営システム」を使えば好きな場所にキャンプを設営して体力を回復できますし、ヒグマも倒せば貴重な素材を手に入れられます。 これらはゲームの難易度を上げるというよりは、世界への没入感を高めるためのスパイスとして、見事に機能していると感じました。
アクション初心者が『Ghost of Yōtei』を攻略するコツ
難易度「易しい」やアシスト機能を使えばクリアは難しくありませんが、どうせならカッコよく敵を倒したいですよね。 ここでは、アクションが苦手な方でも上達できる、いくつかの基本的なコツをご紹介します。

1. まずは防御と回避に専念する
アクションゲームで最も重要なのは、「敵の攻撃を受けないこと」です。 焦って攻撃を仕掛ける前に、まずはガード(L1ボタン)を固め、敵の動きをじっくり観察することから始めましょう。
- 敵の攻撃パターンを覚える: 敵は必ず特定の予備動作の後に攻撃してきます。「剣を振りかぶったら横斬り」「槍を突き出す前に体をひねる」など、敵の動きの癖を見抜きましょう。
- 回避をマスターする: ガードできない赤い光の攻撃は、回避(〇ボタン)で避けるしかありません。敵から離れるようにステップするだけでなく、敵の懐に飛び込むようにステップすると、攻撃後の隙を狙いやすくなります。
慣れないうちは、敵が攻撃を終えて隙を見せるまで、ひたすら防御と回避に徹してみてください。 「攻撃しない」と決めるだけで、心に余裕が生まれ、敵の動きがよく見えるようになります。
2. 「冥人の型」を積極的に活用する
「冥人の型」は、敵を連続で倒すことで溜まるゲージを消費して発動できる、いわば必殺技モードです。 発動中は周囲の敵がスローモーションになり、一撃で敵を仕留めることができます。
特に、多数の敵に囲まれてしまった時に絶大な効果を発揮します。 「もうダメだ!」と思う前に、この冥人の型を使えば、一気に形成を逆転することが可能です。 ゲージは比較的溜まりやすいので、出し惜しみせずに積極的に使っていきましょう。
3. 兵具(飛び道具・暗器)を惜しみなく使う
侍の戦いというと、どうしても刀での斬り合いをイメージしがちです。 しかし、主人公の「あつ」は、目的のためなら手段を選ばない「冥人」でもあります。
- くない: 敵をひるませるのに最適。コンボの起点や、敵に囲まれた際の緊急離脱に使えます。
- てつはう(爆弾): 盾を持つ敵や、密集した敵集団に投げ込むと効果的です。
- 煙玉: 敵の視界を奪い、安全に体勢を立て直したり、背後からステルスキルを狙ったりできます。
これらの兵具は、戦闘を圧倒的に有利に進めるための重要な鍵です。 特に強敵との戦いでは、刀だけで戦うのは得策ではありません。 使えるものはすべて使い、泥臭く勝利を掴み取りましょう。
4. ステルス(隠密)を基本にする
敵の拠点に正面から乗り込むのは、最も危険な選択肢です。 可能な限り、敵に見つからないように行動する「ステルス」を心がけましょう。
草むらや建物の屋根裏に隠れ、敵を一人ずつ静かに暗殺していくのが基本です。 弓を使って遠くの敵を始末したり、誘い鈴で敵をおびき寄せたりと、ステルスの手段も豊富に用意されています。
敵の数を減らしてから戦闘に突入するだけで、難易度は劇的に下がります。 面倒に思えるかもしれませんが、結果的に最も安全で効率的な攻略法なのです。
難易度以外の評価・レビューまとめ
『Ghost of Yōtei』の魅力は、もちろん遊びやすい難易度だけではありません。 クリアまでプレイした私が感じた、特筆すべき点をいくつかご紹介します。
前作を継承し、さらに進化した映像美
これはもう、圧巻の一言です。 前作でも息をのむほど美しかったビジュアルは、PlayStation 5の性能を得て、さらなる高みへと到達しています。
雪に覆われた羊蹄山の荘厳さ、風に揺れるススキ野原、凍てつく流氷が浮かぶ海。 日本の、特に北海道の雄大な自然が、まるで実写かと見紛うほどのクオリティで描かれています。 ただフィールドを馬で駆けているだけでも、時間が経つのを忘れてしまうほどです。
また、今作では新たに「三船モード」「渡辺モード」といった、日本の偉大な映画監督や俳優にインスパイアされた映像フィルターが追加されました。 これらを使うことで、ゲームプレイ全体が一本の芸術映画のような趣になります。 フォトモードも健在で、一度始めると止め時が見つからなくなること請け合いです。
より人間的で感情移入しやすいストーリー
前作の主人公「仁」の物語が、国を守るという大義のための「英雄譚」だったのに対し、今作の主人公「あつ」の物語は、家族を殺された「個人的な復讐」から始まります。
このスケールダウンを残念に思う方もいるかもしれませんが、私はむしろ、この個人的な動機こそが物語に深みを与えていると感じました。 復讐の旅のなかで、様々な人々と出会い、仲間との絆を育むうちに、「あつ」の心は少しずつ変化していきます。
復讐の果てに何が待っているのか。 憎しみを超えた先に、人は何を見出すのか。
前作が「動」の物語なら、今作は「静」の、より内面的な心の動きを丁寧に描いた物語です。 アクションゲームでありながら、上質な人間ドラマとしても楽しめる、非常に完成度の高いシナリオでした。
探索の楽しさと自由度の向上
今作の探索面で最も大きな進化は「野営システム」です。 好きな場所にキャンプを設営でき、そこがファストトラベルの拠点にもなるため、広大なマップをより自由に、自分のペースで探索できるようになりました。
前作で好評だった、狐や鳥が導いてくれるシステムも健在。 彼らの後をついていくと、温泉(体力上限アップ)や神社(装備品ゲット)など、様々な発見があります。 攻略の順番もプレイヤーに委ねられており、「今日は北の雪山を探索してみよう」「明日は東の湿地帯へ行ってみよう」といったように、寄り道をしながら冒険する楽しさは前作以上です。
『Ghost of Yōtei』に関するよくある質問
最後に、読者の皆さんからよく寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。
Q1. 前作をプレイしていなくても楽しめますか?
A1. はい、全く問題ありません。 本作の物語は前作から約300年後が舞台であり、ストーリー的な繋がりはほぼありません。 独立した一つの作品として、心から楽しむことができます。 もちろん、前作をプレイしているとニヤリとできるファンサービス的な要素も散りばめられていますが、知らなくても全く損はありません。
Q2. グロテスクな表現はありますか?
A2. はい、あります。 レーティングがCERO Z(18歳以上のみ対象)となっている通り、戦闘では部位欠損などの過激な表現が含まれます。 ただし、これらの表現は設定でオフにしたり、血の色を黒に変更したりすることが可能です。 グロテスクな表現が苦手な方でも、安心してプレイできる配慮がされています。
Q3. プレイ時間はどのくらいですか?
A3. 私の場合、メインストーリーだけを追ってクリアまで約30時間でした。 温泉や神社巡り、サブクエストなどの寄り道要素をすべてコンプリートしようとすると、おそらく60時間以上はかかると思います。 非常にボリュームのある作品です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
『Ghost of Yōtei』は、前作が持つ圧倒的な世界観や爽快なアクションといった魅力を正当進化させつつ、難易度選択の幅を大きく広げることで、より多くのプレイヤーが楽しめる傑作へと昇華されています。
「アクションゲームは苦手だけど、美しい和の世界を冒険したい」 「歯ごたえは欲しいけど、理不尽な難易度は嫌だ」
そんなあなたの願いを、本作は完璧に満たしてくれるはずです。 難易度への懸念から購入をためらっているのなら、ぜひその一歩を踏み出してみてください。 きっと、忘れられないゲーム体験があなたを待っています。
このレビューが、あなたの決断の助けとなれば幸いです。