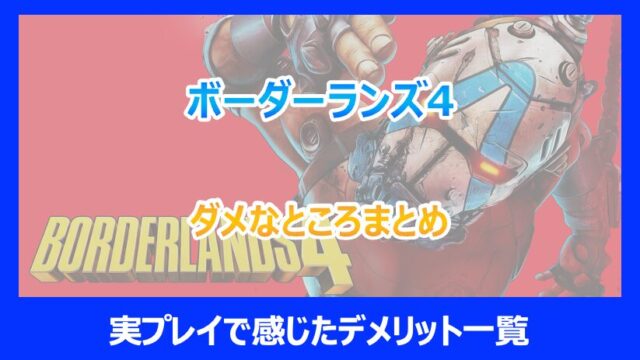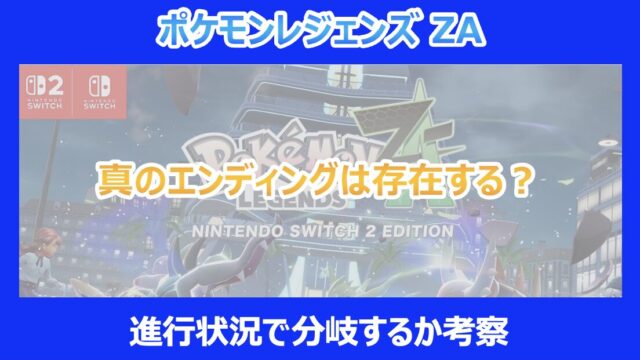ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年10月2日に発売された超大作「Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)」の評価が、発売後に徐々に低下している理由が気になっていると思います。 発売前の圧倒的な期待感と、発売直後の高評価はいったい何だったのか。 なぜ今、厳しい意見が目立つようになってきたのか。

この記事を読み終える頃には、Ghost of Yōteiのメタスコアが悪化している理由と、その背景にある具体的な評価についての疑問が解決しているはずです。
- 発売後に急増した忖度なしのレビュー
- 前作と比較して新鮮味に欠けるゲームシステム
- プレイヤーの期待値を下回ったストーリー展開
- 見過ごせない技術的な問題とボリューム不足
それでは解説していきます。

Ghost of Yōteiのメタスコア低下、その背景を徹底解剖
2025年秋の最注目タイトルとしてリリースされた「Ghost of Yōtei」。 前作「Ghost of Tsushima」の歴史的成功を受け、多くのゲーマーがその進化に期待を寄せていました。 しかし、発売から数週間が経過した今、その評価は当初の熱狂から少し落ち着き、むしろ厳しい目が向けられ始めています。 一体何が起きているのでしょうか。 まずは客観的なデータから、その背景を紐解いていきましょう。

発売直後の高評価から一転、現在のメタスコア状況
「Ghost of Yōtei」は発売日である2025年10月2日を迎える数日前から、一部メディアによる先行レビューが解禁されていました。 その時点でのメタスコアは、なんと92点という非常に高い数値を記録。 「GOTY(ゲーム・オブ・ザ・イヤー)最有力候補」「前作を超える傑作」といった絶賛の声が並び、多くのプレイヤーの期待を最高潮にまで高めました。
しかし、発売後は状況が一変します。 一般プレイヤーがプレイを開始し、そして何より、先行レビュー以外のメディアレビューが出揃い始めると、スコアは徐々に下降。 この記事を執筆している10月下旬現在、メタスコアは86点まで落ち込んでいます。
| 評価指標 | 発売直後(先行レビュー) | 現在(2025年10月下旬) |
|---|---|---|
| メタスコア | 92 | 86 |
| レビュー数 | 約30件 | 113件 |
もちろん、86点というスコアは決して低いものではありません。 「概ね好評(Generally Favorable Reviews)」に分類される立派な良作の指標です。 しかし、問題は「92点からの下落」という事実にあります。 なぜこれほどのスコア変動が起きたのでしょうか。 その最大の要因として挙げられるのが、次にお話しするレビューの性質の違いです。
なぜスコアは下がったのか?忖度なしレビューの増加
発売前に公開される先行レビューの多くは、開発会社や販売会社(本作の場合はソニー・インタラクティブエンタテインメント)から事前にゲームソフトの提供を受けて執筆されます。 これは、発売日と同時にレビュー記事を公開するための業界の慣習であり、それ自体が悪いことではありません。

しかし、どうしてもそこには「ソフトを提供してもらった」という関係性が生じます。 レビュアーは意図せずとも、提供元に対してポジティブな評価を下しやすくなる傾向がある、と指摘されることも少なくありません。 いわゆる「忖度」や「癒着」とまでは言かなくても、無意識のバイアスがかかりやすい構造であることは否定できないでしょう。 その結果、先行レビューでは高評価が連発され、メタスコアは大きく跳ね上がります。
一方で、発売日以降に公開されるレビューには、メディアが自費でソフトを購入してプレイした上で執筆されるものが多く含まれます。 当然、そこにはメーカーとの利害関係は存在せず、より公平で、時にはより厳しい視点からの評価が下されることになります。 「Ghost of Yōtei」のスコア低下は、まさにこの「忖度なし」のレビューが100件を超える規模で追加された結果と分析できます。 初動の熱狂的な高評価は、ある種、プロモーションの影響を色濃く受けたものだったと言えるのかもしれません。
Metacriticユーザースコアとの乖離は?
メディアの評価であるメタスコアと合わせて注目したいのが、一般プレイヤーの投票によって形成される「ユーザースコア」です。 現在、「Ghost of Yōtei」のユーザースコアは7.2点(10点満点)となっています。
メタスコアの86点(100点満点)と比較すると、やや低い印象を受けます。 これは、メディアが評価するポイント(グラフィックの美しさ、革新的なシステムなど)と、一般プレイヤーが重視するポイント(純粋な面白さ、ストレスなく遊べるか、コストパフォーマンスなど)にズレがあることを示唆しています。 特に、後述する技術的な問題や、前作ファンならではの厳しい視点がユーザースコアに反映されていると考えられます。 決して「炎上」するほどの低評価ではありませんが、手放しで絶賛されているわけではない、というプレイヤーのリアルな温度感が伝わってきます。
前作「Ghost of Tsushima」とのスコア比較
今回の評価を語る上で、前作「Ghost of Tsushima」の存在は無視できません。 前作がいかに偉大なゲームであったか、そのスコアが物語っています。
| タイトル | メタスコア | ユーザースコア |
|---|---|---|
| Ghost of Tsushima | 83 | 9.1 |
| Ghost of Yōtei | 86 | 7.2 |
この表を見ると、非常に興味深い事実が浮かび上がります。 メディア評価であるメタスコアは、意外にも今作「Yōtei」の方が3点上回っています。 これは、グラフィックの進化や新要素の追加などが、メディアからは正当に評価されていることを示しています。
しかし、ユーザースコアは前作が「9.1」という驚異的な高評価だったのに対し、今作は「7.2」と大きく差をつけられています。 この逆転現象こそが、今の「Ghost of Yōtei」が置かれている状況を最も的確に表していると言えるでしょう。 プレイヤーは、メディアが評価するような表面的な進化以上に、「魂」の部分、つまり心を揺さぶる体験が前作に及ばなかったと感じているのかもしれません。
他の2025年発売タイトルとの比較
情報ソースにもあった通り、2025年は豊作の年で、メタスコア90点を超えるような傑作が複数リリースされています。 例えば、春に発売されたフロム・ソフトウェアの完全新作「Blood Omen」はメタスコア94点を記録。 夏に発売されたスクウェア・エニックスの「ファイナルファンタジーXVII」も91点を獲得しています。
こうした超大作と比較した時、「86点」というスコアは、残念ながら少し見劣りしてしまうのが現実です。 「良作ではあるが、GOTYを争うほどの傑作ではない」という立ち位置に落ち着いてしまった感が否めません。 期待値が異常なまでに高かっただけに、そのギャップが相対的な評価の低下に繋がっている側面もあるでしょう。
売上不振の噂は本当か?Amazonランキングと初動予測
評価と合わせて気になるのが、実際の売上本数です。 現時点で、ソニーからの公式な販売本数の発表はありません。 しかし、いくつかの指標から、その売れ行きが必ずしも好調とは言えない可能性が浮上しています。
その一つが、大手通販サイトAmazonのゲーム売れ筋ランキングです。 「Ghost of Yōtei」はPlayStation 5の独占タイトルでありながら、発売初週のランキングで1位を獲得できませんでした。 これは異例の事態です。 同時期に発売された「ファイナルファンタジータクティクス リマスター」や、根強い人気の「マリオカート」シリーズ最新作などに後塵を拝する結果となりました。
もちろん、これはパッケージ版の売上であり、ダウンロード版の比率が高まっている現代において、全てを測る指標ではありません。 しかし、他のタイトルも同じ条件下で販売されていることを考えると、初動の勢いが想定を下回っている可能性は高いと推測されます。 個人的な予測では、全世界での初週販売本数は200万本前後ではないでしょうか。 もし300万本を超えていれば、早々に公式発表があるはずです。 前作の累計販売本数が1000万本に迫る勢いだったことを考えると、このスタートはやや物足りないと言わざるを得ません。
開発スタジオ「Sucker Punch Productions」への影響
今回の評価と売上は、開発元であるSucker Punch Productionsにどのような影響を与えるのでしょうか。 「Ghost of Tsushima」で一躍世界のトップスタジオの仲間入りを果たした彼らにとって、今回は真価が問われる重要な一作でした。
メタスコア86点という結果は、決して失敗ではありません。 しかし、前作で築き上げた高いハードルとファンの期待には、完全には応えきれなかった、という見方もできます。 今回のレビューで指摘された問題点を真摯に受け止め、今後のDLCや次回作でどのようにプレイヤーの信頼を回復していくのか。 スタジオの今後の動向が注目されます。
プレイヤーが指摘する「Ghost of Yōtei」の具体的な問題点
メタスコア低下の背景をデータから見てきましたが、ここからはより具体的に、プレイヤーがどのような点に不満を感じているのか、その「悪い評価」の中身に迫っていきます。 SNSや海外のレビューサイトで指摘されている声を、私自身のプレイフィールと合わせて解説します。

ゲームプレイ:新鮮味に欠ける戦闘と探索
最も多く聞かれる意見が、「ゲームプレイが前作の焼き増しに過ぎない」というものです。 確かに、「Ghost of Yōtei」の基本的なシステムは前作を色濃く踏襲しています。 「型」を切り替えて戦う剣戟アクション、美しい風景を頼りに進む探索、敵の拠点を解放していくオープンワールドの構造など、根幹部分はほとんど変わっていません。
焼き増しと揶揄される戦闘システム
もちろん、新たな武器種として「長巻(ながまき)」が追加されたり、鉤縄(かぎなわ)を使った立体的なアクションが増えたりと、細かな進化は見られます。 しかし、プレイフィール全体を劇的に変えるほどの革新性はなく、数時間もプレイすれば「ああ、これは対馬だ」と感じてしまうのです。 前作をやり込んだプレイヤーほど、このマンネリ感を強く感じてしまう傾向にあります。 「正当進化」という好意的な見方もできますが、「代わり映えしない」という厳しい意見が多いのも事実です。
作業感の強いオープンワールド
探索に関しても同様です。 舞台を蝦夷(現在の北海道)に移し、雪景色や独自の文化が描かれる点は非常に魅力的です。 グラフィックはPS5の性能を活かして、息を呑むほど美しく進化しました。 しかし、ワールド内でやることは前作と大差ありません。 狐の巣を追いかけ、温泉を見つけ、俳句を詠む。 これらのアクティビティは、前作では新鮮な驚きがありましたが、今作では「またこれか」という作業感に繋がってしまっています。 収集要素の数も増えており、コンプリートを目指すプレイヤーにとっては苦痛に感じる場面もあるかもしれません。
ストーリー:期待を超えられなかった物語とキャラクター
前作「Ghost of Tsushima」が絶賛された最大の要因は、武士の誉れと冥府の道との間で葛藤する主人公「境井仁」の重厚な物語でした。 多くのプレイヤーが彼の生き様に心を揺さぶられ、涙しました。 その感動を知っているからこそ、今作のストーリーに対する期待は非常に高かったのです。
しかし、蓋を開けてみれば、その物語は多くのプレイヤーの期待を超えるものではありませんでした。 今作の主人公は、アイヌの血を引く若き女性「カイ」。 彼女が故郷を脅かす新たな敵に立ち向かう、という王道のストーリーです。 しかし、その展開は驚きに乏しく、やや単調に感じられます。
主人公のカイをはじめ、登場するキャラクターたちの掘り下げが浅く、感情移入しにくいという声も少なくありません。 特に、前作の仁や伯父・志村のような、プレイヤーの記憶に強く刻まれるほどの魅力的なキャラクターが不在だった点は、物語の評価を大きく下げる一因となっています。 決して出来が悪いわけではないのですが、前作が描いた人間ドラマの深みには一歩及ばなかった、というのが正直な感想です。
ポリコレ要素は評価に影響したのか?
発売前から、一部のコミュニティでは本作の「ポリコレ(ポリティカル・コレクトネス)要素」について懸念の声が上がっていました。 主人公が女性であること、そしてアイヌという特定の民族をテーマにしていることなどが、その理由です。
私が実際にクリアまでプレイした感想としては、情報ソース①の発言者同様、過度にポリコレを意識したような描写は感じられませんでした。 物語は史実やアイヌ文化に対して敬意を払って丁寧に作られており、不快感を覚えるようなシーンは皆無です。
しかし、主人公「カイ」のキャラクターデザインが、いわゆる「美形」ではない点については、賛否が分かれています。 「なぜもっと魅力的な見た目にしなかったのか」という不満の声が、特に海外のプレイヤーから多く上がっているのは事実です。 これが直接的にスコアを大きく下げる原因になったとは考えにくいですが、一部のプレイヤーが購入を躊躇したり、ネガティブな第一印象を抱いたりする要因になった可能性は否定できません。
技術的な問題点:バグや最適化不足の指摘
美しいオープンワールドを誇る「Ghost of Yōtei」ですが、その裏でいくつかの技術的な問題を抱えています。 発売直後から、SNSやフォーラムでは様々なバグの報告が相次ぎました。
- 特定のクエストが進行不能になるバグ
- キャラクターが地形に埋まって動けなくなる
- フレームレートが不安定になり、戦闘中にカクつく
- アプリケーションが強制終了するクラッシュ
これらの問題の多くは、その後のパッチで修正されつつあります。 しかし、発売初期にこうしたストレスを経験したプレイヤーが、低いユーザースコアを付ける一因となったことは間違いありません。 特に、高難易度での戦闘中にフレームレートが低下するのは致命的であり、ゲーム体験を大きく損ないます。 超大作として、万全の状態でリリースしてほしかった、というのがプレイヤーの本音でしょう。
UI/UXの不満点:プレイヤーを悩ませる操作性
ゲーム全体の評価をじわじわと下げる要因として、UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)の細かな不満点も挙げられます。
例えば、アイテム管理画面の煩雑さです。 今作では装備や護符の種類が大幅に増えましたが、ソート機能やフィルタリング機能が不十分で、目的のアイテムを見つけにくいという声が多く聞かれます。 また、マップ画面のアイコン表示が分かりにくく、探索中にストレスを感じる場面もありました。
一つ一つは些細な問題かもしれません。 しかし、数十時間にわたってプレイするゲームにおいて、こうした小さなストレスの積み重ねは決して無視できません。 没入感を削ぎ、プレイヤーに「不親切なゲームだ」という印象を与えてしまうのです。
やりこみ要素とエンドコンテンツのボリューム不足
ストーリーのボリュームは前作と同程度で、寄り道をしなければ20〜30時間ほどでクリアできます。 問題は、クリア後のやりこみ要素やエンドコンテンツです。
前作では、発売後に追加されたオンライン協力マルチプレイモード「Legends/冥人奇譚」が非常に高い評価を受け、ゲームの寿命を大きく延ばしました。 しかし、今作には発売時点でそれに代わるような大型の追加モードは実装されていません。 ストーリーをクリアし、マップをすべて埋めてしまうと、やることがなくなってしまうのです。
もちろん、今後のアップデートで「冥人奇譚」のようなモードが追加される可能性は十分にあります。 しかし、現状では「クリアしたら終わり」という印象が強く、価格に見合ったボリュームがないと感じるプレイヤーも少なくないようです。 周回プレイを促すような魅力的な引き継ぎ要素が少ない点も、物足りなさを助長しています。
競合タイトルの存在:「FFタクティクス リマスター」との比較
最後に、間接的な要因として、発売時期の悪さも挙げられます。 本作の発売とほぼ同時期に、スクウェア・エニックスの不朽の名作シミュレーションRPG「ファイナルファンタジータクティクス」のリマスター版がリリースされました。
ジャンルは全く異なりますが、オリジナルの熱狂的なファンを多く抱える強力なタイトルです。 ゲーマーの財布と時間は有限であり、どちらか一方しか買えない、という選択を迫られた人も多かったでしょう。 その結果、ユーザーが分散し、「Ghost of Yōtei」の初動の勢いが削がれてしまった側面は否めません。 もし単独で発売されていれば、売上も評価も、もう少し違った結果になっていた可能性があります。
まとめ
今回は、「Ghost of Yōtei」のメタスコアが発売後に低下した理由について、多角的に分析してきました。
結論として、その原因は単一のものではなく、以下のような複合的な要因が絡み合った結果であると言えます。
- レビューの質の変化: 発売前の「メーカー提供による先行レビュー」から、発売後の「自費購入による忖度なしのレビュー」へと移行したことで、より客観的で厳しい評価が増え、スコアが現実的な数値に落ち着いた。
- ゲーム内容への不満: 前作「Ghost of Tsushima」の偉大な功績が、かえって高いハードルとなった。ゲームプレイのマンネリ感、期待を超えられなかったストーリー、魅力に欠けるキャラクターなどが、特に前作ファンからの厳しい評価に繋がった。
- 技術・仕様的な問題: 見過ごせないバグや最適化不足、ボリューム不足といった問題点が、プレイヤーの満足度を下げ、ユーザースコアの低下を招いた。
「Ghost of Yōtei」は、決して駄作ではありません。 息を呑むほど美しい世界を旅し、爽快な剣戟アクションを楽しめる、紛れもない「良作」です。 しかし、「歴史に残る傑作」かと問われれば、残念ながら首を縦に振ることは難しい、というのが私の偽らざる評価です。
今後のアップデートによる改善や、大型DLCの追加によって、この評価が覆る可能性はまだ残されています。 開発スタジオであるSucker Punch Productionsが、プレイヤーの声に真摯に耳を傾け、再び私たちを驚かせてくれることを期待せずにはいられません。
もしあなたが購入を迷っているなら、こうアドバイスします。 「前作のシステムが好きで、大きな変化を求めず、美しい世界を旅したいのであれば、十分に楽しめるだろう。しかし、前作を超える感動や、革新的なゲーム体験を期待しているのなら、少し待った方が賢明かもしれない」と。