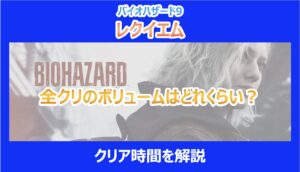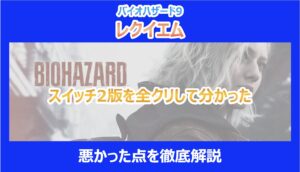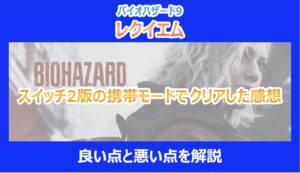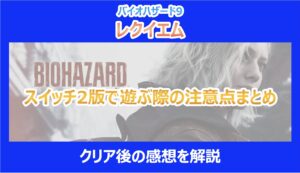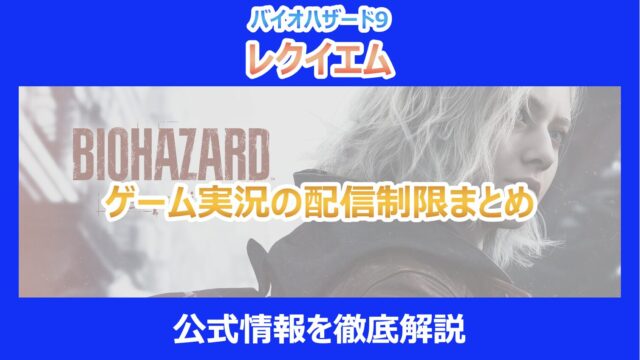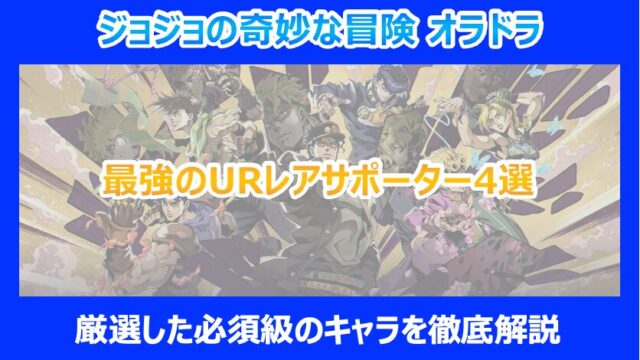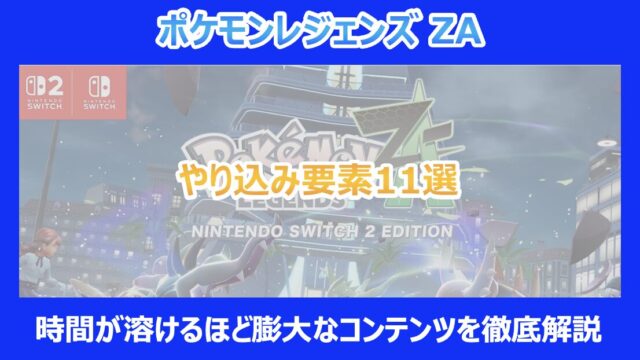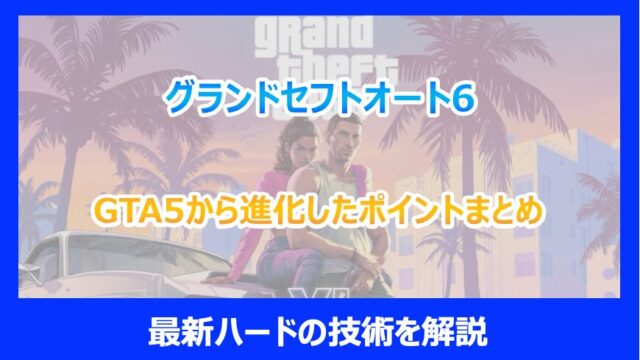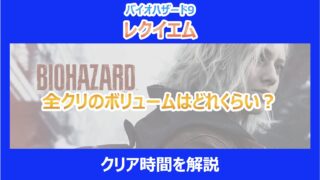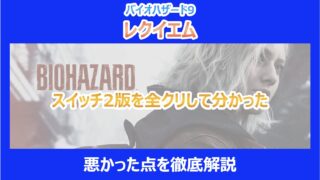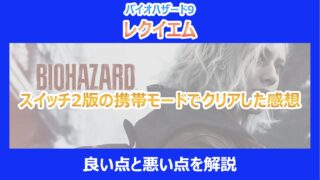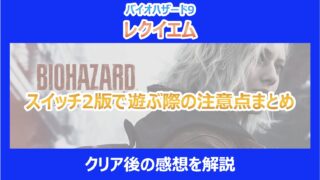ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられている質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年10月2日に発売された「Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)」の評価、特に「革新性がない」「新鮮味がない」といった意見について、その真意が気になっているのではないでしょうか。

発売から少し時間が経ち、多くのレビューが出揃った今、そうした声を聞いて購入を迷っていたり、プレイしながらも他の人の評価が気になったりしているかもしれません。
この記事を読み終える頃には、本作がなぜ「革新性がない」と評されるのか、そしてそれが本当に欠点なのか、その裏にある「成熟した魅力」とは何なのか、全ての疑問が解決しているはずです。
- 前作から正当進化した圧倒的なビジュアルと剣戟アクション
- 発見が連鎖する高密度なオープンワールド体験
- 一部に残る保守的なデザインとUIの課題
- 「革新」ではなく「成熟」を選んだAAAタイトルとしての立ち位置
それでは解説していきます。

Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)とは?前作からの進化点を振り返る
まずは、本作がどのようなゲームなのか、基本情報と前作「ゴースト・オブ・ツシマ」からの進化点を整理していきましょう。 すでにプレイしている方も、改めて本作の立ち位置を確認することで、この後のレビューへの理解が深まるはずです。
基本情報:蝦夷地を舞台にした復讐の物語
「Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)」は、2020年に発売され、その美しい和の世界観と本格的な時代劇アクションで全世界累計1,300万本以上という驚異的なヒットを記録した「ゴースト・オブ・ツシマ」の正統な続編です。

開発は前作に引き続き、Sucker Punch Productions(サッカーパンチ・プロダクションズ)が担当。 約5年の歳月をかけて生み出された完全新作となります。
物語の舞台は、前作の対馬から一新され、1603年の「蝦夷地(えぞち)」。 プレイヤーは、悲惨な過去を背負い、復讐の炎に身を焦がす女武芸者「圧(あつ)」となり、北の広大な大地を巡る過酷な旅路を体験することになります。
彼女の抱える怒りと孤独を、プレイヤー自身が追体験していく重厚な物語が、本作の大きな魅力の一つです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| タイトル | Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ) |
| 発売日 | 2025年10月2日 |
| 対応機種 | PlayStation 5 |
| 開発会社 | Sucker Punch Productions |
| ジャンル | オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー |
| 舞台 | 1603年 蝦夷地 |
| 主人公 | 圧(あつ) |
グラフィックの進化:PS5の性能を最大限に活かした圧倒的ビジュアル
本作を起動して誰もが最初に息をのむのが、その圧倒的なビジュアル表現でしょう。

前作「ゴースト・オブ・ツシマ」も、PlayStation 4時代の最後を飾るにふさわしい、驚異的なグラフィックで多くのプレイヤーを魅了しました。 しかし、本作はPlayStation 5専用タイトルとして開発されたことで、その映像美は新たな次元へと到達しています。
息づく自然の描写
広大な草原、陽光が差し込む深い森、荒々しい波が打ち寄せる海岸線。 どのロケーションも、まるで実写かと見紛うほど精緻に作り込まれています。
特に、本作の象徴でもある「羊蹄山(ようていざん)」を望む風景は、圧巻の一言。 風に揺れる草木の音、静寂に包まれた吹雪、雪を強く踏みしめる足音といった環境音の表現も極めて細やかで、映像と音響の両面から、プレイヤーを蝦夷地へと誘います。
この圧倒的な没入感は、まさに次世代機だからこそ実現できた体験と言えるでしょう。
ストーリーテリングの深化:復讐に燃える孤独な怨霊「篤」
本作の物語は、前作とは大きく異なる色合いを帯びています。
前作の主人公「酒井仁(さかい じん)」は、元寇という未曾有の国難に際し、武士としての「誉れ」と、民を守るための非情な手段「冥人(くろうど)」との間で葛藤する姿が描かれました。 これは、国を守るという大義と、叔父である志村との個人的な対立という二重構造が絡み合い、物語に深みを与えていました。
一方で、本作の主人公「篤」の物語は、より個人的で、血と記憶に根差した「復讐」という一点に収束していきます。
物語は、幼い圧の回想シーンから始まります。 蝦夷地で家族と穏やかに暮らしていた彼女の日常は、「羊蹄六人衆」と呼ばれる賊の襲撃によって無残にも打ち砕かれます。 両親を殺され、双子の弟と生き別れた圧は、たった一人で本土へ逃れ、16年の歳月を経て、復讐の念だけを胸に再び故郷の地を踏むのです。
彼女にとって戦いとは、誰かを守るための行為ではなく、過去の痛みを何度もなぞり、己の怨念を晴らすための儀式に他なりません。
このテーマを象徴するのが、ゲーム冒頭で描かれる羊蹄六人衆の一人「蛇」との対峙シーンです。 酔って無防備な蛇に対し、圧は一切のためらいなく刃を振るい、その亡骸に火を放ちます。 そこには正義や理念といった感情は介在せず、ただ純粋な憎悪と痛みに突き動かされる圧の心理が鮮烈に描き出されています。
前作が「誉れを失う葛藤」の物語だったとすれば、本作はその葛藤すら失った者が、復讐の果てに何を見出すのかを描く物語。 このダークでパーソナルな作風が、前作とは異なる重厚なプレイフィールを生み出しています。
オープンワールド設計の再構築:発見が発見を呼ぶ連鎖的探索体験
広大な蝦夷地もまた、本作のもう一人の主人公と言えます。 本作のオープンワールドは、前作で確立されたデザイン設計を継承しつつ、その構造をより高密度に、より偶発的に再構築することに成功しています。

正直なところ、前作のオープンワールドは、その美しさとは裏腹に、どこか「整いすぎている」という印象がありました。 「風の導き」や「狐の巣」といった自然による誘導はユニークでしたが、やや予定調和感が強く、プレイヤーの予測を超えるような偶発的な出会いや緊張感には欠けていたと言えます。 良くも悪くも、用意された舞台装置の上をなぞっている感覚があったのです。
その課題を踏まえ、本作では探索のリズムそのものが再設計されています。 自然がプレイヤーを導くという基本コンセプトは引き継ぎつつ、より偶発的で連鎖的な探索体験が生まれるよう、世界の至る所に無数の仕掛けが施されています。
例えば、こんな体験がありました。 町で購入した「地蔵の地図」を頼りに馬を走らせていると、途中で獰猛な狼の群れに遭遇。 これを撃退し、ふと見ると近くに狼の巣穴が。 興味本位で巣穴を抜けた先で、再び地蔵を探し始めると、思わぬ場所で賞金首とその一味に遭遇し、命からがら討伐することに。 すると、まさにその場所こそが、最初に目指していた地蔵の隠し場所だったのです。
このように、一つの目的が次の発見を呼び、その発見がまた別の出来事へと繋がっていく。 この有機的な「探索の連鎖」が、蝦夷地を単なる背景ではなく、「生きている空間」としてプレイヤーに感じさせてくれます。
開発者の意図が透けて見えてしまうと、それは途端に「作業」になってしまいますが、本作はタスクの種類や報酬、発見までの道のりを多様に変化させることで、その危うさを見事に回避しています。 この緻密な設計こそが、プレイヤーを北の大地へと駆り立てる、強力なモチベーションを生み出しているのです。
Ghost of Yōteiの評価点:成熟したゲームデザインの魅力
「革新性はないが、完成度は極めて高い」 これが本作を一言で表す言葉かもしれません。 ここからは、その「成熟」した魅力、つまり高く評価されるべきポイントを具体的に掘り下げていきます。
バトルシステムの深化:泥臭くも爽快な剣戟アクション
本作の戦闘は、前作のシステムを正当進化させ、より泥臭く、肉体的な迫力を増した仕上がりになっています。

侍の様式美を追求した前作に対し、本作では圧のキャラクター性を反映し、「生きるため、殺すため」の無骨な戦いが表現されています。
基本的な操作感や、一瞬の判断が生死を分ける「受け流し(パリィ)」システムの緊張感は健在。 それに加え、新たに「二刀」「大太刀」「槍」「鎖鎌」「火縄銃」といった多彩な武器種が導入されました。
- 刀: バランスの取れた標準的な武器
- 二刀: 手数の多さと素早い連撃による速攻が得意
- 大太刀: 相手の防御を叩き割る重厚な一撃が持ち味
- 槍: リーチを活かした突きで間合いを制圧
- 鎖鎌: トリッキーな動きで敵を翻弄
- 火縄銃: 遠距離から敵の体勢を崩すのに有効
これらの武器は戦闘中に瞬時に切り替え可能で、敵の種類や状況に応じて戦略を組み立てる楽しさは格別です。
難易度「普通」でプレイしても、敵の攻撃は苛烈を極めます。 複数の敵に囲まれれば一瞬で体勢を崩され、わずか2〜3発の攻撃で倒されてしまうことも珍しくありません。 だからこそ、敵の攻撃の予備動作を読み切り、連続攻撃を全て受け流して反撃に転じた時の爽快感は、他のゲームでは味わえないものがあります。
また、新要素として、敵が戦闘中に武器を落とすようになった点も、戦闘の泥臭さを象徴しています。 落ちた武器を拾い、即座に敵に投げつけることができ、これが非常に強力。 重装備の屈強な兵士を一撃で葬り去ることも可能で、圧のなりふり構わない戦闘スタイルをプレイヤー自身が体感できます。 この「使えるものは何でも使う」という感覚が、復讐者としてのリアリティを高めています。
育成要素:戦闘スタイルを色濃く反映するスキルと装備
本作の成長要素は、戦闘の緻密さと比較すると、ややシンプルに感じられるかもしれません。 スキルツリーや装備強化の幅は限定的で、育成の自由度が低いと感じるプレイヤーもいるでしょう。
しかし、これは意図的なデザインだと私は考えています。 複雑すぎる育成要素は、時にプレイヤーの負担となり、本作の核であるアクション部分への集中を妨げる可能性があります。
本作のスキルツリーは、各武器種の新たな技や、隠密行動を強化する能力など、習得することでプレイスタイルが明確に変化するものに絞られています。 どのスキルから習得していくかによって、真正面からの斬り合いを好む「武士」スタイルにも、闇討ちを主軸とする「冥人」スタイルにも特化させることができ、プレイヤーの好みを反映させる余地は十分にあります。
装備の強化も同様で、素材を集めて性能を向上させるだけでなく、見た目もより豪華になっていくため、育成のモチベーションに繋がります。 あえて育成要素を複雑化せず、剣戟アクションそのものの奥深さをプレイヤーに味わわせようとする。 その潔い設計思想は、本作の「成熟」を象徴していると言えるでしょう。
重厚なサイドストーリー:蝦夷地の文化と人々に触れる物語
本作の魅力は、復讐を軸としたメインストーリーだけではありません。 広大な蝦夷地の各地には、この土地に生きる人々の息遣いを感じさせる、数多くのサイドストーリーが散りばめられています。
特に印象的なのが、蝦夷地の先住民であるアイヌの文化を題材とした物語です。 彼らの独自の信仰や生活様式に触れるクエストは、単なるお使いに留まらず、圧自身の価値観にも影響を与えていきます。 開発チームの丁寧な取材と、文化への深い敬意が感じられるこれらの物語は、本作の世界観に圧倒的な深みとリアリティを与えています。
その他にも、各地で噂される賞金首を追い詰めたり、隠された温泉や句を詠む場所を探したりと、寄り道をしたくなる魅力的な要素が満載です。 これらのサイドクエストは、メインストーリーの緊張感を和らげる緩衝材として機能するだけでなく、圧というキャラクターの多面性を描き出す上でも重要な役割を担っています。
復讐鬼として非情に振る舞う彼女が、困っている人々を助ける中で見せる、ほんの僅かな人間性。 そうした機微に触れることで、プレイヤーは圧という人物をより深く理解し、その旅路に感情移入していくのです。
Ghost of Yōteiの賛否両論点:「革新性がない」と言われる理由
ここまで本作の優れた点を解説してきましたが、一方で「革新性がない」「新鮮味がない」といった批判的な意見が存在するのも事実です。 ここからは、なぜそのような評価が生まれるのか、その理由を客観的に分析していきます。
保守的なゲームデザイン:一部に見られる古臭さ
オープンワールドや戦闘面で確かな進化を遂げた一方、一部のシークエンスにおいては、前作から変化のない、あるいは現代の基準ではやや古臭いと感じられる保守的なデザインが散見されます。

決まったルートをなぞるだけのパルクール
特に気になるのが、「パルクール」と「パズル」の設計です。 パルクールは、崖を登り、ロープを伝って目的地を目指す移動アクションですが、本作のそれは、基本的に「印のついた岩壁を登り、決められた木を伝い、ロープを掴む」という、あらかじめ決められた動作を順番に行うだけの構造になっています。
プレイヤーの創意工夫が介在する余地はほとんどなく、見た瞬間に正解ルートがわかるため、爽快なアクションというよりは機械的な作業になりがちです。 これがメインミッションに頻繁に組み込まれているため、物語のテンポを著しく損なっていると感じました。
物語と乖離したパズル要素
パズル要素も同様です。 登場頻度は少ないものの、特定のオブジェクトを特定の位置に動かすといった単純なものが多く、物理演算や環境を利用した近年の革新的なパズルデザインと比較すると、見劣りするのは否めません。
根本的な問題は、これらのアクションやパズルが、物語を強化する演出として十分に機能していない点にあります。 なぜ圧は崖を登らなければならないのか、なぜ像を動かす必要があるのか。 そこに彼女自身の心情とリンクする動機付けが乏しいため、プレイヤーにとっては「ゲームだからやらされている」という義務感だけが残ってしまうのです。
UI/UXの課題:テキストスキップ非対応のストレス
もう一点、細かいようでいて無視できないのが、会話中のテキストスキップに対応していないという仕様です。 ムービーシーン自体を丸ごとスキップすることは可能ですが、会話のテキストを個別に早送りすることはできません。
本作は、サイドクエストや野営イベントなど、プレイヤーの意図しないタイミングで会話が発生することが多く、それ自体は世界の臨場感を高める優れた演出です。 しかし、全ての音声を律儀に待たなければならないため、特にプレイ時間が長くなるにつれて、じわじわとストレスが溜まっていきます。
全体の完成度が非常に高いだけに、こうした細かな配慮の欠如は、どうしても悪目立ちしてしまいます。 UI/UXの最適化が進んだ現代のAAAタイトルとしては、時代遅れな仕様と言わざるを得ません。
一貫性に欠けるキャラクター描写:「圧」の人物像の揺らぎ
主人公「圧」のキャラクター描写にも、やや一貫性に欠ける部分があり、プレイヤーによっては感情移入が難しいと感じるかもしれません。
序盤こそ、家族を奪われた悲劇の復讐者として、その行動原理は明確に描かれます。 しかし、物語が進むにつれて、彼女の人物像の掘り下げが十分に行われているかには疑問が残ります。
彼女のセリフは多くが短く、感情の起伏も乏しい。 誰かに心情を問われても、返ってくるのは「六人衆を斬る」といった直線的な言葉ばかりで、彼女の内面で渦巻いているはずの葛藤や逡巡がほとんど描かれません。 もちろん、寡黙な主人公という設定自体が悪いわけではありません。 しかし、本作の場合、プレイヤーがその沈黙の裏にある意味を読み解くためのヒントが、十分に与えられていないのです。
物語終盤になると、彼女の心理的な変化に焦点が当てられますが、それまでの描写が不足しているため、やや唐突な印象を受けます。 結果として、行動の動機は理解できても、そこに至る心の機微が見えづらく、どっちつかずのキャラクターになってしまっている感は否めません。
AAAタイトルのジレンマ:なぜ「革新」ではなく「成熟」を選んだのか
ここまで見てきた課題点、特に保守的なクエスト設計やキャラクター描写の揺らぎは、本作が抱える、そして近年の多くのAAA(トリプルエー)タイトルが抱える構造的なジレンマに起因していると私は考えています。
「AAAタイトル」とは、巨額の開発費と長い開発期間をかけて作られる超大作ゲームのことです。 本作のようなタイトルは、開発に5年以上を要することも珍しくありません。 しかし、ゲームデザインの根幹部分は、開発の初期段階で決定されるため、変更することは極めて困難です。
つまり、開発チームは「数年後に主流となるであろうゲームデザイン」を予測しながら、開発を進めなければなりません。 そのため、企画時点では最先端のデザインであっても、発売される頃には、ゲーム業界のトレンドが変化し、「時代遅れ」になってしまうリスクを常に抱えているのです。
本作は、まさにそのジレンマの典型例と言えるでしょう。 前作「ゴースト・オブ・ツシマ」は、2015年の「ウィッチャー3 ワイルドハント」から始まった、物語主導型オープンワールドの潮流を受け継いだ、一つの集大成的な作品でした。
しかし、その後のオープンワールドというジャンルは、さらなる進化と分岐を遂げます。 「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」は、プレイヤーの自由な発想が攻略に繋がる新たな体験を提示し、「エルデンリング」は、高難易度のアクションと圧倒的な探索の自由度を融合させました。
こうした文脈で見ると、「Ghost of Yōtei」の構造は、良くも悪くも2020年当時の文法を色濃く踏襲しています。 マップで示された目的地へ向かい、イベントをこなし、敵を一掃するという定型的なクエスト設計は、近年の自由度の高いオープンワールドゲームに慣れたプレイヤーにとっては、物足りなく映るかもしれません。
しかし、これは決して開発力の不足ではなく、続編としての責任と、ブランドとしての一貫性を守るための、意図的な「選択」だったのではないでしょうか。 過剰な革新を狙えば、前作のファンが愛したゲーム体験を損なう恐れもある。 そう考えれば、本作が「革新」ではなく「完成」と「成熟」を選び取ったのは、極めて理に適った判断だと言えます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。 「Ghost of Yōtei」は、サッカーパンチ・プロダクションズがこれまで築き上げてきた、物語主導型オープンワールドの一つの集大成と呼ぶにふさわしい作品です。
連鎖的な発見に満ちた探索、泥臭くも鋭い手応えを感じさせる剣戟。 その完成度は、数あるオープンワールドゲームの中でもトップクラスであることは間違いありません。
一方で、メインクエストの構成や一部のゲームデザインには、前作の設計思想をそのまま踏襲した部分もあり、ジャンル全体の進化と比較すると、やや保守的に映る点も確かです。
しかし、それこそが続編としての責任を果たし、安定した品質とシリーズらしさを両立させるための「成熟」の証なのです。 「革新性がない」という評価は、この作品の一側面を捉えたものに過ぎません。
前作「ゴースト・オブ・ツシマ」に心を奪われたプレイヤーはもちろん、重厚な時代劇の世界に浸りたい、そして最高峰の剣戟アクションを体験したいと願う全てのゲームファンに、自信を持っておすすめできる一本です。
完成を極めたその先で、サッカーパンチが次にどのような物語と世界を描き出すのか。 その新たな挑戦に、今から大いに期待したいと思います。