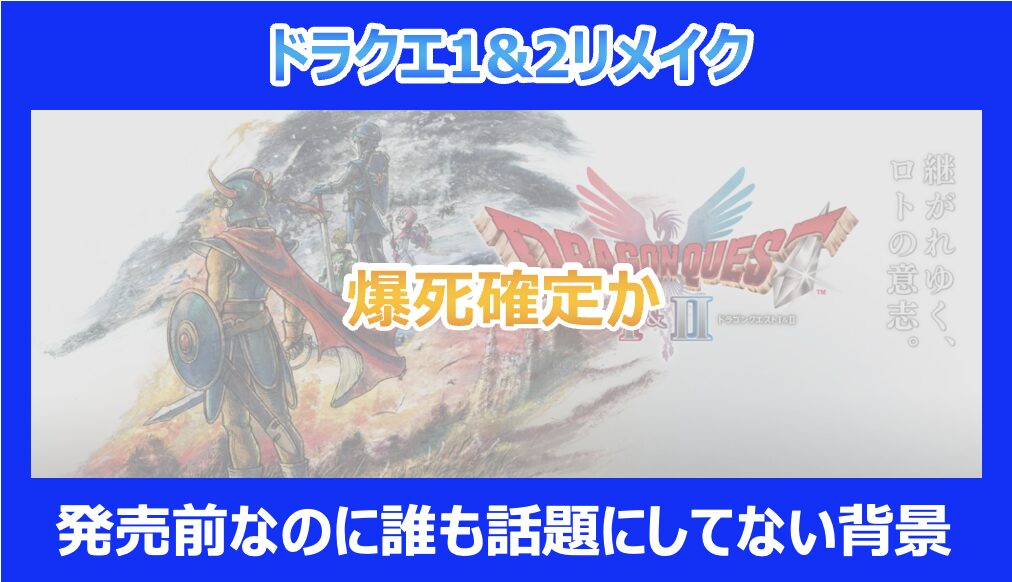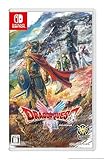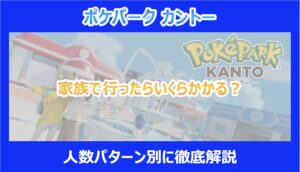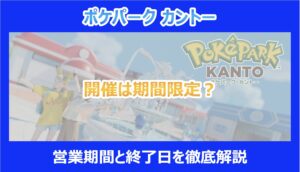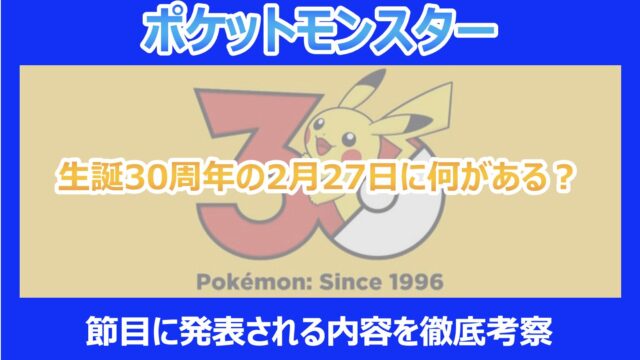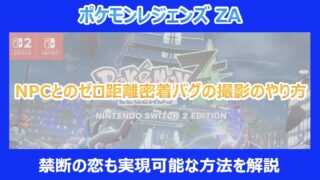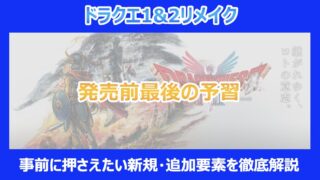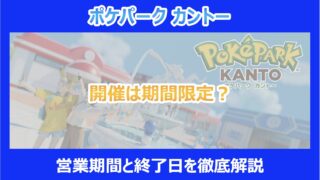ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2024年11月14日に発売が迫ったHD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』リメイクについて、「本当に盛り上がっているのか?」「ポケモン新作などに比べて、世間の話題が少なすぎるのではないか」と気になっていると思います。 国民的RPGの原点とも言える作品のリメイクにも関わらず、SNSなどでの熱狂が感じられない。 それどころか「爆死するのでは?」といった不安の声さえ聞こえてきます。

この記事を読み終える頃には、なぜHD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』が発売前にして静かなのか、その背景にある複雑な要因についての疑問が解決しているはずです。
- ドラクエⅠ&Ⅱリメイクが話題になりにくい構造的理由
- ポケモンなど他作品と比べた時の「熱量」の差
- ドラクエブランドが抱える「高齢化」という深刻な課題
- HD-2Dリメイクという手法への期待と限界
それでは解説していきます。

HD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』リメイクの現状とファンの認識
まずは、今回レビューするHD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』がどのような作品で、現在どのような状況に置かれているのかを整理しましょう。
そもそもHD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』とは?
HD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』は、1986年に発売された『ドラゴンクエスト』と、1987年に発売された『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』の2作品を、「HD-2D」というグラフィック技術を用いて現代に蘇らせるリメイク作品です。 発売日は2024年11月14日、対応プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S、そしてPC(Steam/Windows)と、現行のほぼ全ての主要ハードで展開されます。

この「HD-2D」とは、スクウェア・エニックス(以下スクエニ)が得意とする技術で、ファミコンやスーパーファミコン時代のドット絵の「味」を残しつつ、背景に3DCGを融合させ、光の表現や画面の奥行き感を加えたものです。 『オクトパストラベラー』や『ライブアライブ』のリメイクで高い評価を受けた手法であり、懐かしさと新しさを両立させる技術として注目されています。
『Ⅰ』は勇者ロトの血を引き、竜王に立ち向かう物語。 『Ⅱ』はその子孫たちが、大神官ハーゴンを倒すために集結する物語。 まさに日本RPGの金字塔「ロト三部作」の原点です。 今回のリメイクでは、グラフィックの一新はもちろん、UI(ユーザーインターフェース)の改善、オーケストラ音源の採用、そして『Ⅱ』で悪名高かった難易度の調整なども期待されています。
予約状況は好調?世間の「体感温度」とのズレ
では、本当に本作は「話題になっていない」のでしょうか。 Amazonなどの予約ランキングを見ると、常に上位に食い込んでおり、決して「売れていない」わけではないことがわかります。 発売元のスクエニも、一定の販売本数を見込んでいるはずです。
しかし、読者の皆さんが感じている「盛り上がりのなさ」は、私も同感です。 ここで言う「盛り上がり」とは、予約本数という「実利」ではなく、SNSでのトレンド入り、ファンによる考察合戦、インフルエンサーによる先行プレイ動画の熱狂といった「熱量」のことでしょう。
例えば、2025年発売予定の『ポケモン レジェンズ Z-A』が発表された時、X(旧Twitter)のトレンドは関連ワードで埋め尽くされ、何日も考察が続きました。 あるいは、任天堂が『ゼルダの伝説』の新作を発表した時の、あの空気感を想像してください。
それに比べ、『ドラクエⅠ&Ⅱ』リメイクの発表や続報が出た際の反応は、どこか「静か」です。 「お、出るんだ」「HD-2D綺麗だね」といった感想はあっても、それが社会的なムーブメントに発展する気配がありません。
この「予約はされているが、熱狂的な話題にはなっていない」というギャップこそが、現在のドラクエブランドが抱える問題を象徴しているのです。
全ての元凶?HD-2D版『ドラクエ3』という「本命」の存在
この「盛り上がりのなさ」を語る上で、絶対に避けられないのがHD-2D版『ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…』の存在です。
そもそも、スクエニがHD-2Dリメイクプロジェクトとして最初に発表したのは『3』でした。 2021年5月、多くのドラクエファンがあの日、熱狂したのは間違いなく『3』のリメイク発表に対してです。 『3』は、ロト三部作の完結編であり、自由なパーティ編成、転職システム、広大な世界地図、そして衝撃的なエンディングと、シリーズのシステムを確立させた最高傑作として名高い作品です。

ファンが3年間待ち望んでいたのは、この『3』でした。 しかし、2024年6月に満を持して公開されたのは、『3』の発売日(2025年予定)と、その「前座」とも言える『Ⅰ&Ⅱ』の先行発売(2024年11月)だったのです。
この発表順序は、マーケティング戦略としては理解できます。 『3』から入ったファンに、その前日譚である『Ⅰ&Ⅱ』も遊んでもらおうという意図でしょう。
しかし、ファンの心理としては「本命は『3』であり、『Ⅰ&Ⅱ』はそのために仕方なく(あるいは予習として)買うもの」という認識が生まれてしまいました。 『Ⅰ』と『Ⅱ』は、『Ⅲ』と比べると良くも悪くもシステムがシンプルです。 特に『Ⅰ』は主人公と竜王の一騎打ち、『Ⅱ』は仲間こそ増えますが、職業の概念はありません。
「一番面白い『3』を先に発表しておきながら、システム的に劣る『1&2』を先に売る」という戦略が、ファンの中で「盛り上がるべき本番は2025年」という空気感を生み出し、『Ⅰ&Ⅱ』単体への熱量を著しく下げている。 これが、話題にならない最大の理由の一つであることは間違いありません。
ドラクエⅠ&Ⅱリメイクが「話題になっていない」7つの背景
『3』の存在以外にも、このリメイクが世間の話題を独占できない理由は、さらに根深く、複雑に絡み合っています。 ゲーム評論家として、その背景を7つの視点から徹底的に解剖します。
理由①:『ポケモン』という巨大すぎる比較対象の存在
読者の方が懸念されている通り、『ポケモン』との熱量の差は決定的です。 『ポケモン レジェンズ Z-A』は2025年発売予定であり、直接的な競合(同月発売)ではありません。 しかし、ゲーム業界において「期待値」というのは、常に比較されるものです。
なぜ『ポケモン』はあれほどまでに世代を超えて熱狂を生むのでしょうか。

世代を超えたIP戦略の成功
ポケモンは、ゲームだけでなく、アニメ、カードゲーム、グッズ、映画と、子供の頃に触れるあらゆるメディアで展開され続けています。 今の10代、20代にとって、『ドラクエ』は「親がやっていたゲーム」かもしれませんが、『ポケモン』は「自分が子供の頃から今も触れているゲーム」です。 新作が出るたびに、子供から大人まで、親子で、あるいは友人と、共通の話題として成立します。
「革新」への挑戦
『ポケモン』は、『ソード・シールド』での賛否両論、『アルセウス』でのオープンワールドへの挑戦、そして『スカーレット・バイオレット』での完全なオープンワールド化(技術的な問題は多発しましたが)と、常に「新しい遊び」を提供しようと挑戦を続けています。
一方、『ドラクエ』は良くも悪くも「伝統」を重んじます。 『ドラクエ11』は「伝統の集大成」として絶賛されましたが、それはあくまで既存ファンの期待に応えた結果です。
そして、今回の『ドラクエⅠ&Ⅱ』は「リメイク」です。 片や『ポケモン』が未来の新しい遊び(レジェンズ Z-A)を提示してファンを熱狂させているのに対し、『ドラクエ』は過去の作品の「焼き直し」(HD-2D)を提示している。 この「未来への期待値」と「過去への懐古」という構図が、世間の話題性の差として明確に現れているのです。
理由②:メインターゲット層の深刻な「高齢化」
情報ソース①で「老人ホーム向け」と辛辣な言葉が使われていましたが、これは残念ながら的を射ている部分があります。 ファミコンで『ドラクエⅠ』をリアルタイムでプレイした層は、現在50代から60代。 スーパーファミコンで『Ⅲ』や『Ⅴ』に熱中した層も、40代に突入しています。
この「ドラクエおじさん」と呼ばれるコアファン層が、現在のドラクエブランドを支えている最大の顧客であることは間違いありません。
SNSでの発信力と「熱量」の乖離
40代、50代がSNSを使わないわけではありません。 しかし、10代、20代のように、新作ゲームの発表に対して瞬時に反応し、考察を投稿し、トレンドを形成するほどの「熱量」を持つ層は、相対的に少数です。
彼らの多くは、静かに情報を収集し、発売日にパッケージ版を買い、黙々とプレイします。 予約ランキングが好調なのは、この「サイレントマジョリティ」であるコアファン層が、確実に購入しているからです。
しかし、SNS上で観測される「話題性」は、彼らの声が可視化されにくいため、実態よりも低く見えてしまいます。 話題の中心が「懐かしいね」「買うけどね」で止まってしまい、そこから先のムーブメントに繋がらないのです。
ライフスタイルの変化と「ゲーム疲れ」
さらに深刻なのは、このターゲット層が、仕事や家庭で最も多忙な時期を迎えていることです。 「ゲームをやる気力がない」 「20時間のゲームクリアも億劫」 という声は、決して大げさではありません。
昔のように、寝る間も惜しんでレベル上げに没頭できた時代は終わりました。 可処分時間が減り、体力も落ち、老眼も始まる。 そんな中で、HD-2Dの細かいドット絵や、古き良きRPGの「お使い」や「レベル上げ」が、本当に快適にプレイできるのか。
「懐かしいけど、今さらまた『ふっかつのじゅもん』はいいかな…」 という、ある種の「ゲーム疲れ」が、新規の話題として盛り上がることを妨げています。
理由③:『Ⅰ』『Ⅱ』という原点ゆえの「地味さ」
前述の通り、『Ⅲ』に比べて『Ⅰ』と『Ⅱ』は、ゲームシステムが非常にシンプルです。
- 『Ⅰ』:勇者とタイマン。仲間なし。町の人もほぼ動かない。
- 『Ⅱ』:初の仲間(3人パーティ)。しかし職業概念なし。
このシンプルさが、リアルタイム世代にとっては「原点の良さ」として映る一方、現代のRPGに慣れたプレイヤー(あるいは『Ⅲ』以降のドラクエしか知らない層)にとっては、単なる「ボリューム不足」や「地味さ」として認識されがちです。
何度もリメイクされてきた「新鮮味のなさ」
『ドラクエⅠ&Ⅱ』は、これまでも様々なハードでリメイクされてきました。
| リメイク遍歴(主なもの) | 特徴 |
|---|---|
| SFC版 (1993) | グラフィック一新、システム改善(『Ⅱ』の難易度緩和) |
| GB版 (1999) | 携帯機への移植 |
| スマホ版 (2013) | 縦画面操作、グラフィック(SFC版ベース) |
SFC版で既にグラフィックやシステムは一度完成されています。 スマホ版も手軽にプレイ可能です。 「今、フルプライス(約7,000円)を払ってまで、HD-2D版を遊ぶ必要があるのか?」 という疑問は、当然生まれます。
HD-2Dというガワ(外見)は新しくても、中身の体験がSFC版やスマホ版と大差ないのではないか、という懸念。 これが、積極的な話題への参加をためらわせる一因となっています。 特に『Ⅱ』の悪名高い「ロンダルキアへの洞窟」や、凶悪な難易度バランスが、HD-2D版でどこまで「遊びやすく」かつ「理不尽さを残して」調整されているのか。 その具体的な情報が少ないことも、盛り上がりに欠ける要因です。
理由④:HD-2Dグラフィックへの「既視感」と「不安」
HD-2Dという技術自体が、もはや「最新」とは言えなくなってきている点も見逃せません。
「またこのグラフィックか」という飽き
『オクトパストラベラー』(2018年)で衝撃的なデビューを飾ったHD-2Dですが、その後『トライアングルストラテジー』『ライブアライブ』と、スクエニ内部(特に浅野チーム)で多用されてきました。
美麗であることは間違いありません。 しかし、同時に「どのゲームも同じに見える」という既視感(デジャヴ)も生まれ始めています。 特に、光のブルーム(ぼかし)表現が過剰で、「目が疲れる」「ドット絵の良さが消えている」といった批判も根強くあります。
『ドラクエ』という国民的IPに、この「浅野チームの作風」がそのまま持ち込まれることへのアレルギー反応を示すオールドファンも少なくありません。
『ドラクエ3』のPVで露呈した「不安」
2021年に公開された『ドラクエ3』リメイクのPVでは、戦闘シーンのモンスターが小さく見える、アニメーションが硬い、といった点への批判がありました。 情報ソース①でも「モンスター小さい気がすんだよね」と指摘がありましたが、これは多くのファンが感じた違和感です。
『ドラクエ』の戦闘の魅力は、鳥山明氏デザインのモンスターが、画面いっぱいに迫力を持って動く点にありました。 HD-2Dのワイド画面と3D的な奥行き表現が、逆にモンスターの存在感を希薄にしてしまうのではないか。
『Ⅰ&Ⅱ』のPVではその点は改善されているように見えますが、一度抱かれた「HD-2D化は、本当にドラクエにとって正解なのか?」という不安は、熱狂的な支持を妨げるブレーキとなっています。
理由⑤:スクエニという企業への「信頼低下」
これは『ドラクエ』単体の問題ではなく、現在のスクエニという企業全体が抱える問題です。 ここ数年、スクエニがリリースした作品群は、ファンの期待を裏切るものが少なくありませんでした。
『バランワンダーワールド』『フォースポークン』『ハーヴェステラ』など、鳴り物入りで発表された新規IPの失敗。 『ファイナルファンタジー16』の「RPGかアクションか」という賛否両論。 『ファイナルファンタジー7 リバース』の高い評価とは裏腹の、販売本数の伸び悩み。
そして何より、「フルプライスに見合わないボリューム」「最適化不足のバグ多発」「未完成商法」といった批判が絶えません。 リメイクやリマスター作品においても、価格設定が強気すぎると感じているユーザーは多いです。
「どうせまた、中身はSFC版のままで、グラフィックを変えただけでフルプライス取るんだろう」 「発売日に買ったらバグだらけかもしれない」
こうしたスクエニへの根本的な不信感が、「とりあえず様子見」という層を生み出し、発売前の「お祭り騒ぎ」を阻害しているのです。
理由⑥:堀井雄二氏の「監修」への疑問符
『ドラクエ』は、ゲームデザイン・シナリオを手掛ける堀井雄二氏の作品です。 彼の作る温かみのある世界観、巧みなシナリオこそが『ドラクエ』の魂でした。
しかし、情報ソース①で指摘されている通り、近年の堀井氏の「監修」が、どこまで深く作品に関与しているのかを疑問視する声が出始めています。 特に『ドラクエ11』以降の派生作品(トレジャーズなど)や、今回のリメイクプロジェクトにおいて、堀井氏がどれだけ細部までチェックしているのか。
『ドラクエ3』リメイクの開発が難航した(ように見えた)こと、そして今回の『Ⅰ&Ⅱ』が『3』の開発ラインを使って急遽作られた(ように見える)ことから、 「堀井雄二氏が看板として表に出ているだけで、実際の開発はHD-2Dチームに丸投げなのではないか」 「堀井氏の全ての力を詰め込んだ神ゲー、という熱意が感じられない」 という疑念です。
もちろん、これは憶測にすぎません。 しかし、かつてのような「堀井さんが作るなら間違いない」という絶対的な信頼が揺らぎ始めていることも、ファンが熱狂しきれない一因と言えるでしょう。
理由⑦:圧倒的な情報発信(プロモーション)の不足
発売まで1ヶ月を切ろうかという時期(※執筆時点の想定)にも関わらず、本作に関する具体的な新情報が驚くほど少ない、という点も指摘せざるを得ません。
『Ⅰ』と『Ⅱ』がどのようにシームレスに繋がるのか。 『Ⅱ』の難易度調整の具体的な内容。 SFC版やスマホ版からの追加要素はあるのか。 戦闘のテンポ、UIの使い勝手は?
こうした、ファンが本当に知りたい「リメイクとしての価値」を示す情報がほとんど公開されていません。 公開されるのは、既に知っているストーリーの紹介や、HD-2Dの美麗なフィールド映像ばかり。
これでは「懐かしいけど、買う決め手に欠ける」という状態から抜け出せません。 ポケモンが次々と新情報や戦略的なリーク(?)でファンの期待を煽り続けるのとは対照的に、『ドラクエ』のプロモーションはあまりにも「静か」で「受け身」すぎます。
では、HD-2D版『ドラクエⅠ&Ⅱ』は「爆死」するのか?
これら7つの理由から、「話題になっていない」ことは事実だと結論付けられます。 では、このまま「爆死」してしまうのでしょうか。 これについても、冷静に分析する必要があります。
「爆死」の定義:商業的失敗は考えにくい
まず、「爆死」の定義をはっきりさせましょう。 「評論家やファンからの評価が低い」ことと、「商業的に失敗する(売れない)」ことはイコールではありません。
結論から言えば、本作が商業的に「爆死」する可能性は極めて低いと私は見ています。
理由は単純で、前述した「サイレントマジョリティ」である40代〜50代のコアファン層が、確実に購入するからです。 彼らにとって『ドラクエ』は「お布施」であり、生活の一部です。 話題性があろうがなかろうが、「ドラクエが出るなら買う」のです。
また、プラットフォームがSwitch、PS5、Xbox、PCと全方位展開(マルチプラットフォーム)である点も強みです。 Switch層(ファミリー、ライト層)と、PS5/PC層(グラフィック重視のコアゲーマー)の両方に取りこぼしがありません。
国内でミリオン(100万本)は難しいかもしれませんが、世界累計であれば、HD-2D版『3』への「予習」需要も見込めるため、手堅く50万本から100万本ラインは超えてくると予測します。 これは、近年のリメイク作品としては「成功」の部類に入ります。
「爆死」するのは「話題性」と「新規層の獲得」
本作が「爆死」するとすれば、それは「売上本数」ではありません。 「ドラクエというIPの未来」です。
結局、この『Ⅰ&Ⅱ』リメイクが、既存の「ドラクエおじさん」だけで完結してしまい、今の10代、20代という新規層に全く届かなかった場合。 「やっぱりドラクエは老人ホーム向けのゲームだったね」 と再確認されるだけに終わってしまった場合。 それこそが、本当の意味での「爆死」です。
ポケモンが『アルセウス』で過去作(ダイパリメイク)とは全く違うアプローチを見せたように、ドラクエも「懐古」だけに頼らない「革新」を見せなければ、未来はありません。 今回のリメイクが、その「革新」の第一歩たり得るのか、それとも単なる「同窓会」で終わるのか。 そこが最大の焦点です。
評論家が注目する「真の評価ポイント」
私が本作をレビューする上で注目しているのは、グラフィックの綺麗さではありません。 いかに現代のプレイヤーがストレスなく「ロトの伝説の原点」を体験できるか、その「再構築」の手腕です。
『Ⅱ』の難易度という「呪い」の解放
特に『Ⅱ』です。 理不尽なエンカウント率、広すぎるフィールド、強すぎる敵、そして「ロンダルキアへの洞窟」という名のトラウマ。 これらを、ただ簡単にする(ヌルくする)だけでは、当時のファンは納得しません。
かといって、当時のままでは新規層は間違いなく脱落します。 この「理不尽さ」と「達成感」の黄金比を、HD-2D版で見つけ出すことができるのか。 ヒントの配置、レベルアップのテンポ、セーブポイントの追加など、地味ながらも重要な調整が、本作の評価を決定づけます。
『Ⅰ』の「孤独」をどう演出するか
『Ⅰ』は、たった一人で広大な世界を冒険する「孤独」の物語です。 仲間がいる『Ⅱ』や『Ⅲ』とは全く異なるゲーム体験です。 この「孤独感」と「世界の広さ」を、HD-2Dの美麗なグラフィックとオーケストラサウンドで、いかに演出し直せるか。
単にグラフィックが綺麗になっただけでは、すぐに飽きてしまいます。 フィールドを歩いているだけで「冒険している」と感じられるような、環境音、光の表現、人々の息遣い。 そうした細部へのこだわりが試されています。
今後のドラクエブランドとHD-2Dリメイクの未来
今回の『Ⅰ&Ⅱ』は、単なる1本のソフトに留まらず、今後のドラクエブランドの方向性を占う試金石となります。
なぜ今、ロト三部作のリメイクなのか?
本命である『ドラクエ12』の開発が難航している、あるいは大幅に遅れている、という噂は絶えません。 その「穴埋め」として、開発リソースが比較的少なく済む(と思われる)HD-2Dリメイクが選ばれた、という見方は自然です。
しかし、それだけではないはずです。 スクエニは、ドラクエブランドの「再定義」を迫られています。 『ドラクエ11』で一つの頂点を極めた今、次(『12』)で全く新しいものを見せなければならないプレッシャーの中、もう一度「原点」に立ち返る必要があったのでしょう。
HD-2Dで『Ⅰ』から『Ⅲ』までを再体験してもらい、新規層には「ドラクエとはこういうものだ」と提示し、古参ファンには「あの頃のワクワクを思い出してくれ」と呼びかける。 『12』という本編への「橋渡し」として、ロト三部作リメイクは重要な役割を担っているのです。
HD-2D技術とドラクエの相性、そして「天空シリーズ」への期待
もし、今回の『Ⅰ&Ⅱ』、そして来年の『Ⅲ』が商業的・批評的に成功すれば、当然ファンが次に期待するのは「天空シリーズ」のHD-2Dリメイクでしょう。
- 『ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち』
- 『ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁』
- 『ドラゴンクエストⅥ 幻の大地』
特に『Ⅴ』は、親子三代にわたる物語、結婚イベント、モンスターを仲間にするシステムと、ドラクエ史上最も人気のある作品の一つです。 DSでリメイクされましたが、HD-2Dで蘇るビアンカとフローラ、パパスとの再会を望む声は非常に大きい。
今回の『Ⅰ&Ⅱ』は、この「未来への期待」を繋ぐためにも、失敗できないプロジェクトなのです。 HD-2Dとドラクエの相性が「最高」であったと証明しなければ、天空シリーズへの道は閉ざされてしまいます。
「老人ホーム」からの脱却は可能か
結局のところ、ドラクエが生き残る道は、新規層の獲得以外にありません。 ポケモンが常に子供たちを巻き込み、新しい世代のファンを生み出し続けるのと同じことを、ドラクエも成し遂げなければなりません。
『Ⅰ&Ⅱ』リメイクは、そのための「入口」として機能するでしょうか。 私は、難しいかもしれないが、可能性はある、と考えています。
HD-2Dのグラフィックは、レトロゲームを知らない今の若年層にとって、逆に「エモい」「新しい」ドット表現として映る可能性があります。 『オクトパストラベラー』が若年層にも受け入れられたのがその証拠です。
問題は、ゲームの中身です。 「お使い」ばかりの単調な展開や、理不尽な難易度が残っていては、彼らはすぐに見限るでしょう。 見た目は新しく、中身は遊びやすく、しかしドラクエの「魂」は失わない。 この難題をクリアできた時、初めて「老人ホーム」からの脱却が見えてくるはずです。
まとめ
HD-2D版『ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ』リメイクが発売前に「話題になっていない」背景には、以下のような複雑な要因が絡み合っています。
- 本命である『3』の前座という認識
- 『ポケモン』など他IPの圧倒的な話題性
- ターゲット層の高齢化とSNS発信力の低下
- 『Ⅰ&Ⅱ』自体のシステム的な地味さと、リメイクの新鮮味のなさ
- HD-2Dグラフィックへの既視感と不安
- スクエニという企業への信頼低下
- プロモーション(情報発信)の絶対的な不足
これらの要因により、世間的な「熱狂」は生まれていません。 しかし、コアファン層の堅実な購入により、商業的な「爆死」は考えにくいと予測します。
本当の「爆死」とは、売上ではなく、このリメイクが新規層に全く響かず、ドラクエブランドが「過去の遺産」であることを再確認させてしまうことです。
ゲーム評論家・桐谷シンジとしては、話題性や売上本数以上に、このリメイクが『ドラクエ』の原点である「冒険のワクワク感」を、現代の技術でいかに再構築できたかに注目しています。 特に『Ⅱ』の難易度調整が、古参ファンと新規層の両方を納得させられる「神調整」となっているか。 それを確かめるために、私は発売日に本作をプレイするつもりです。