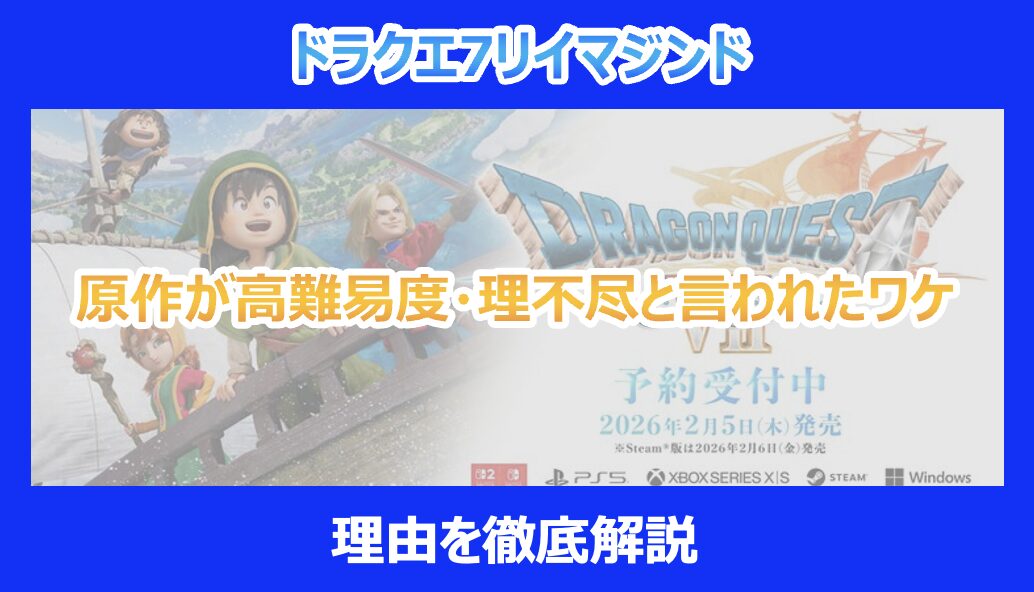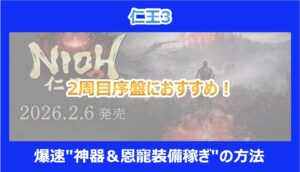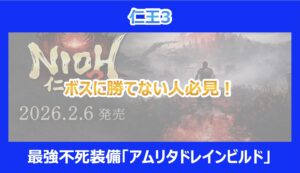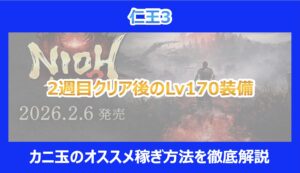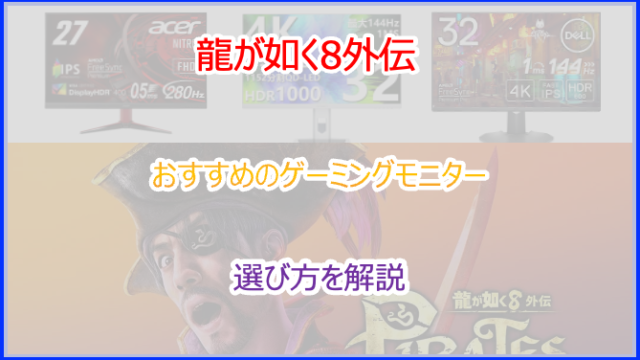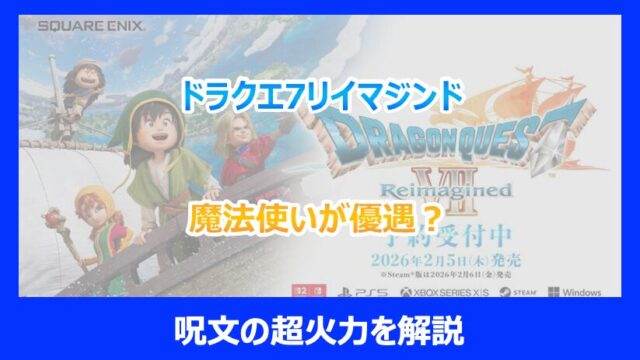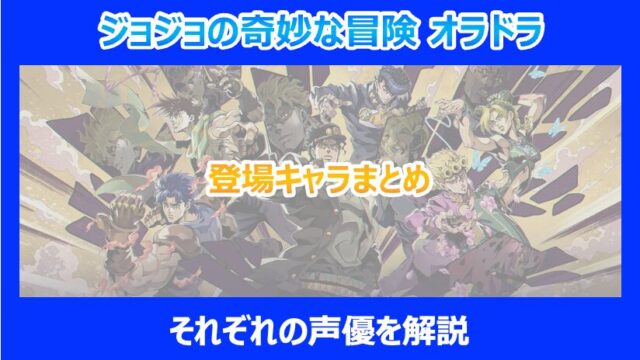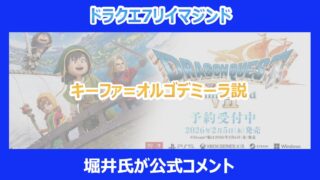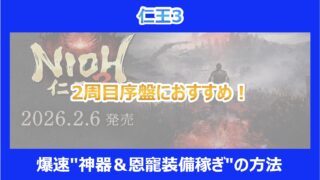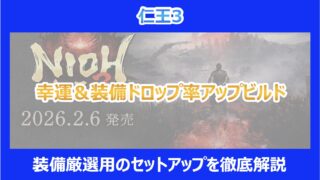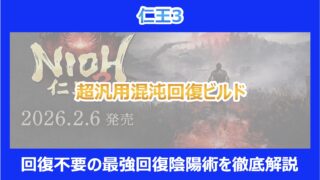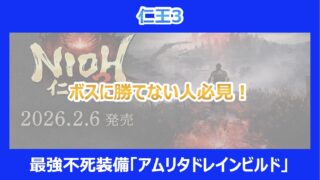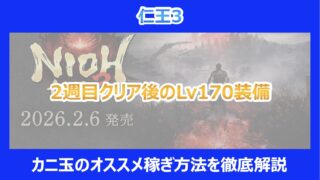ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2026年2月5日に発売が迫る『ドラゴンクエストVII リイマジンド』に期待を寄せつつも、原作がいかにして「高難易度」「理不尽」と評されたのか、その具体的な理由が気になっているのではないでしょうか。
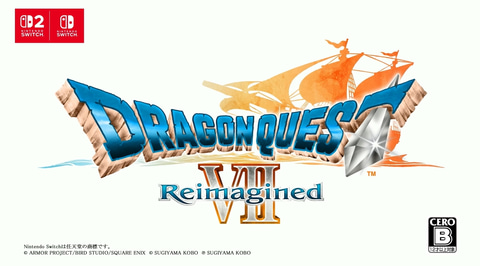
この記事を読み終える頃には、原作ドラクエ7がプレイヤーに与えた衝撃の数々と、リメイク版でそれらがどう昇華されるのか、その全貌がクリアになっているはずです。
- 原作ドラクエ7が高難易度と言われた7つの理由
- 開発側とユーザー双方を苦しめた鬼畜な環境
- リメイク作「リイマジンド」での改善点と期待
- 賛否両論ありながらも愛されるドラクエ7の魅力
それでは解説していきます。

ドラクエ7が高難易度・理不尽と言われた7つの鬼畜要素
2000年に発売されたPlayStation版『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』は、当時の販売本数記録を塗り替えるほどの大ヒットを記録しました。 その一方で、シリーズの中でも特に「尖った作品」として、多くのプレイヤーの心に良くも悪くも深い爪痕を残したことでも知られています。 ここでは、なぜドラクエ7が「高難易度」「理不尽」とまで言われたのか、その象徴的な7つの要素を徹底的に解説していきます。
1. 戦闘開始までが長すぎる問題
多くのRPGでは、ゲーム開始後すぐ、あるいは数分後には最初の戦闘が始まり、プレイヤーはレベル上げや戦闘システムの基本を学んでいきます。 しかし、ドラクエ7はこの常識を根底から覆しました。

物語は、広大な海にぽつんと浮かぶ平和な島「エスタード島」から始まります。 この島にはモンスターが一匹も生息しておらず、プレイヤーは主人公とその友人キーファ、マリベルと共に、謎の遺跡を探索することになります。 目的は、遺跡で見つかる「ふしぎな石板」のかけらを集め、台座にはめ込んでいくこと。 この一連の謎解きと探索が、ドラクエ7のプロローグとなっています。
問題は、その長さにあります。 初めてプレイする多くのプレイヤーが、最初の敵であるスライムに遭遇するまでにかかる時間は、平均して約2時間から3時間。 それまでの間、一切の戦闘が発生しないのです。 ひたすら島の中を歩き回り、人々と会話をし、遺跡の仕掛けを解き明かす。 このゲームデザインは、発売を心待ちにしていたファン、特に「ドラクエといえば戦闘とレベル上げ」というイメージを持っていた層にとっては、かなりのストレスとなりました。
この意図について、生みの親である堀井雄二氏は、当時のRPGが「序盤はまずレベル上げ」というワンパターンな流れになっていることに疑問を感じていたと語っています。 プレイヤーがその流れに飽きているのではないかと考え、自身が好きだった謎解きアドベンチャーゲーム『MYST』を参考に、あえて戦闘のない導入部を作り上げたそうです。 当初は「5時間くらい戦闘がなくてもいい」とすら考えていたというのですから驚きです。
しかし、この挑戦的な試みは、結果として多くのプレイヤーを戸惑わせました。 後に堀井氏自身も「今考えるとあれは必要だったのか」と振り返っており、プレイヤーの期待と作り手の意図が必ずしも一致しなかった象徴的な要素と言えるでしょう。 リメイク作である『リイマジンド』では、この導入部がどのようにテンポ良く調整されているのか、まず注目したいポイントの一つです。
2. シナリオが長すぎる問題
最初の戦闘にたどり着くまでの長さもさることながら、ドラクエ7は本編そのものがシリーズ屈指の長さを誇ります。 「ゲームが長く遊べる」と言えば聞こえは良いですが、そのボリュームは当時の基準を遥かに超えるものでした。
| 作品名 | 平均クリア時間(目安) |
|---|---|
| ドラクエ6 | 約40時間 |
| ドラクエ7 | 約80~100時間 |
| ドラクエ8 | 約60~70時間 |
前作であるドラクエ6の倍以上という、圧倒的なボリュームです。 やり込み要素である裏ボスの討伐まで含めると、120時間を超えることも珍しくありませんでした。

この長さの理由は、ゲームの根幹をなすオムニバス形式のストーリーテリングにあります。 プレイヤーは石板を完成させることで過去の様々な土地へ旅立ち、そこで起きている問題を解決していきます。 その土地の数は全部で16箇所。 一つ一つのエピソードが短編小説のように作り込まれており、それぞれに濃密な物語が待っています。 一つのストーリーをクリアするのに数時間かかることもザラで、これが積み重なって膨大なプレイ時間となるのです。
開発側の熱量も凄まじく、シナリオの原稿はA4用紙にして1万6000ページにも及んだと言われています。 当時はその膨大な量のシナリオを毎回紙に印刷し、堀井氏とスタッフが朝から終電までアナログな環境で読み合わせをしていたというエピソードも残っており、その制作環境の過酷さが伺えます。
しかし、このオムニバス形式は、プレイヤーにとっては諸刃の剣でした。 従来のドラクエのように一本の壮大な物語が徐々に盛り上がっていくのではなく、独立した物語が連続するため、中盤で「今、何のために戦っているんだっけ?」と目的を見失いがちになり、中だるみを感じて挫折するプレイヤーが後を絶ちませんでした。 『リイマジンド』では、このシナリオを取捨選択し、テンポ感を意識して再構築したとアナウンスされています。 どのエピソードが残り、どのように一本の物語としてまとめ上げられるのか、原作ファンにとっても非常に気になるところです。
3. シナリオが暗すぎる・鬱展開が多い問題
ドラクエ7のキャラクターデザインや世界の雰囲気は、どこか絵本のような温かみを感じさせます。 しかし、その見た目とは裏腹に、展開される物語の多くは非常に暗く、後味の悪い、いわゆる「鬱展開」を多く含んでいました。

物語の大きな流れは、魔王によって封印された過去の世界を石板で訪れ、人々を絶望させている「災いの元」を断ち切り、現代にその土地を復活させるというものです。 しかし、この問題解決が必ずしもハッピーエンドに繋がらないのが、ドラクエ7の鬼畜たる所以でした。
忘れられない後味の悪さ
例えば、物語の序盤で出会う女戦士マチルダ。 彼女は主人公たちを助けてくれる親切な人物ですが、実は彼女こそが村に災いをもたらしていた元凶でした。 その理由は、かつて村人に裏切られて命を落とした兄への復讐心から。 最終的に彼女は自らの過ちを認め、自らの命を絶つことで村を救うという、非常にやるせない結末を迎えます。 最初のボスが、単純な悪ではなく、悲しい過去を背負った人間だったという展開は、多くのプレイヤーの心をえぐりました。
この他にも、
- 町の平穏を守るために自ら魔物の姿になった結果、町人から迫害され続ける神父の話(レブレサック)
- 津波によって壊滅した町で、救世主と崇められる男の裏切りと、それに翻弄される人々の悲劇(ハーメリア)
- 昼ドラのようなドロドロとした人間関係が悲劇を生む物語
など、これまでの「勇者が正義の力で悪を討つ」というドラクエの王道とは一線を画す、人間の業や哀しみを深く描いたストーリーが数多く存在します。 大人になった今プレイすれば、その物語の奥深さを味わうことができますが、シンプルな冒険活劇を期待していた当時の子供たちにとっては、免疫のないままに心を抉られる、あまりにもヘビーな体験だったかもしれません。 ある意味、時代を先取りした作風だったとも言えるでしょう。
4. 主要メンバーの離脱問題
RPGにおいて、共に冒険する仲間はプレイヤーの分身であり、感情移入の対象です。 その仲間が、物語の途中で永久にパーティから離脱するという展開は、プレイヤーに大きな衝撃と喪失感を与えます。 ドラクエ7におけるキーファの離脱は、まさにその象徴でした。

キーファはエスタード島の王子でありながら冒険に憧れ、主人公を引っ張っていく好奇心旺盛なキャラクターです。 物語の序盤、彼が主人公を誘うところから冒険は始まります。 まさに「お前が始めた物語じゃないか」と誰もがツッコミたくなるような中心人物でした。 しかし彼は、過去の世界で出会った踊り子の女性と恋に落ち、その時代に生きることを選び、パーティから永久に離脱してしまいます。
この離脱がもたらす理不尽さは、単なるストーリー上の寂しさだけではありませんでした。 キーファはパーティの物理攻撃の要であり、多くのプレイヤーは彼に「ちからのたね」などの貴重なアイテムを集中して使っていました。 育成計画を根底から覆されるこの展開は、まさに「初見殺し」であり、多くのプレイヤーの心を折りました。
追い打ちをかけるマリベルの離脱
さらに、キーファ離脱後の難所として名高い「ダーマ神殿編」を、攻撃の要を失った状態で攻略しなければならないという鬼畜仕様。 特技や呪文を奪われた状態で強力なボスとの連戦が続くこのパートは、ドラクエ7屈指の難関として語り継がれています。
そして、キーファの件で心に傷を負ったプレイヤーに追い打ちをかけるのが、マリベルの一時離脱です。 物語中盤、父親が病に倒れたという理由で、彼女もパーティを離れてしまいます。 後に復帰はするものの、「マリベル、お前もか…」と絶望したプレイヤーは少なくなかったでしょう。 魔法使い系の職業で育てていたマリベルが離脱し、あまり育っていない新メンバーのアイラが加入することで、戦力バランスが大きく崩れ、ストレスを感じたという声も多く聞かれました。 キャラクターの育成計画が、プレイヤーの意図しない形で強制的に変更させられる。 これもまた、ドラクE7の理不尽さを象徴する要素だったのです。
5. 石板システムが面倒すぎる問題
ドラクエ7の冒険の鍵を握る「ふしぎな石板」。 これを集め、台座にはめることで新たな世界への道が開かれるというシステムは、本作の最大の特徴です。 しかし、このシステムがプレイヤーを最も苦しめた要因の一つでもありました。
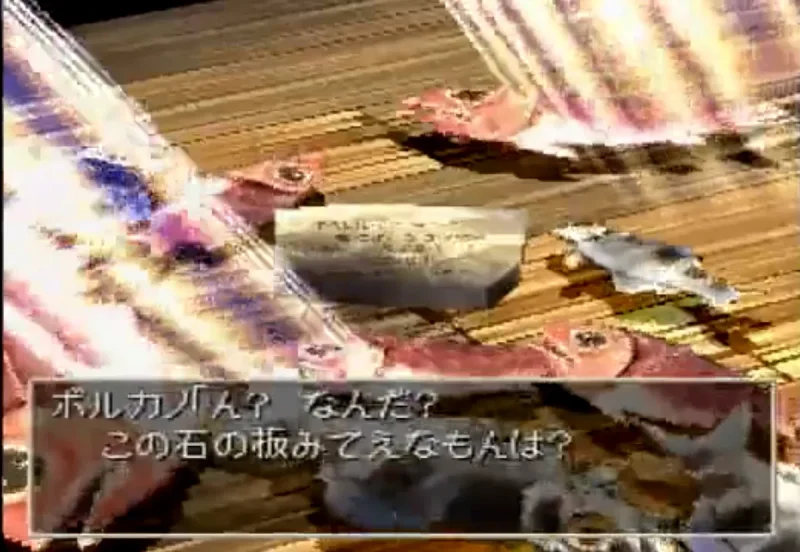
基本的な流れは以下の通りです。
- 石板のかけらを集める
- 台座にはめて完成させる
- 過去の世界へ行く
- イベントをこなしながら、新たな石板のかけらを集める
- 現代に新たな土地が復活する
- 復活した土地でイベントをこなし、さらに石板のかけらを集める
- 1に戻る
問題は、この石板のかけらが非常に入手しづらい場所に隠されていることが多い点です。 ボスを倒したり、重要人物からもらえたりする分かりやすいものもありますが、ダンジョンの隅の宝箱や、町の民家のタンスの中、一見何もなさそうなツボの中など、ありとあらゆる場所に隠されています。
3Dマップとの最悪の相性
この探索の難易度を跳ね上げたのが、本作から導入された3D回転マップです。 プレイヤーはL・Rボタンで視点を360度回転させることができましたが、これが逆に死角を生み出し、「視点を変えないと見えない通路」や「建物の裏側にある入り口」などを大量に生み出しました。 くまなく探索したつもりでも、視点変更を怠ったことで石板を見逃し、物語が進行不能になる…いわゆる「詰み」の状態に陥るプレイヤーが続出したのです。
当時は攻略サイトも今ほど充実しておらず、情報交換の手段も限られていました。 「石板がどこにあるか分からない」というクレームの電話が、開発会社のエニックスに殺到したという逸話もあるほどです。
さらに理不尽なのは、手に入れた石板が必ずしも次の目的地のものではない、という点。 ようやく石板のかけらを集めて台座に向かっても、どの台座も完成しない。 そうなると、これまで訪れた全ての過去と現代の世界を、もう一度しらみつぶしに探索し直すという、途方もない作業が待っているのです。 この「石板どこだよ問題」は、多くのプレイヤーの心を折り、挫折へと導きました。 『リイマジンド』では、この石板探しが大幅に緩和されると明言されており、現代のプレイヤーがストレスなく物語に集中できるような配慮がなされることに期待が高まります。
6. 職業システムが複雑すぎる問題
ドラクエ3や6で好評だった転職システムは、ドラクエ7で大幅に拡張され、究極のやり込み要素として進化しました。 しかし、その進化はあまりにも尖りすぎていました。

| 作品名 | 職業数(人間職) |
|---|---|
| ドラクエ3 | 9種類 |
| ドラクエ6 | 18種類 |
| ドラクエ7 | 50種類以上(モンスター職含む) |
前作の約3倍という圧倒的な職業数。 各職業には「熟練度」というレベルがあり、戦闘回数を重ねることでランクが上がっていきます。 特定の職業をマスター(最高ランクのレベル8に到達)することで、さらに上位の職業に就けるようになるという、育成の楽しさに満ちたシステムです。
問題は、一つの職業をマスターするために必要な戦闘回数の多さです。 少ないものでも約120回、多いものだと250回以上の戦闘をこなす必要があります。 しかも、自分のレベルに対して弱すぎる敵との戦闘はカウントされないため、常に適正なレベルの敵と戦い続けなければなりません。
コンプリートへの果てしない道
さらに、本作にはモンスターの心を手に入れることで転職できる「モンスター職」が存在します。 この「モンスターの心」は、特定のモンスターを倒した際に低確率でドロップするアイテムであり、入手は困難を極めます。 全ての職業をマスターしようとすれば、膨大な時間を戦闘に費やすことになり、これがクリアまでのプレイ時間を押し上げる大きな要因となっていました。
この複雑で時間のかかるシステムは、育成好きのプレイヤーにとってはたまらない魅力である一方、ストーリーをサクサク進めたいプレイヤーにとっては、高すぎるハードルとして立ちはだかったのです。 『リイマジンド』では、このモンスター職を廃止し、代わりに複数の人間職の能力を同時に使える「職業かけもち」という新システムが導入されます。 これにより、育成の幅を広げつつも、よりテンポの良いキャラクター育成が可能になることが期待されます。
7. フリーズバグが多すぎる問題
そして、プレイヤーにとって最も理不尽で、全ての努力を無に帰す可能性があったのが、頻繁に発生するフリーズバグです。 唐突にゲーム画面が固まり、音が止まり、一切の操作を受け付けなくなる。 対処法は、PlayStation本体の電源を落とすことだけ。 最後にセーブした時点からのやり直しを余儀なくされるこの現象は、当時のプレイヤーにとって悪夢でした。
開発段階で2万個ものバグがあったという逸話が残るドラクエ7ですが、製品版にも修正しきれなかったバグが残っていました。 フリーズの原因は、データロード時間を短縮するために実装された「先読みローディング」という技術にあったと言われています。 常にディスクから次のデータを読み込み続けるこの処理が、ハードに大きな負荷をかけ、フリーズを引き起こしやすくしていたようです。
何時間もかけてレベル上げをし、強敵を倒したその瞬間に画面がフリーズする。 貴重なアイテムを手に入れた直後にフリーズする。 そうした悲劇が、当時は日常茶飯事でした。 オートセーブが当たり前の現代では考えられないかもしれませんが、このフリーズの恐怖が、プレイヤーに「こまめなセーブ」の重要性を骨の髄まで叩き込んだのです。 ドラクエシリーズは、初代の「ふっかつのじゅもん」の書き間違いから始まり、「冒険の書が消える」問題など、セーブデータに関するトラブルの歴史がありますが、ドラクエ7のフリーズ問題は、その歴史に新たな1ページを刻んだと言えるでしょう。
なぜドラクエ7は今なお愛されるのか?賛否両論の先にある魅力
ここまで紹介してきたように、初代ドラクエ7は数多くの「鬼畜」な要素を抱えた、非常に尖った作品でした。 しかし、それにも関わらず、本作には今なお熱烈なファンが多く存在し、今回のリメイク発表も大きな歓声をもって迎えられました。 なぜ、これほどまでに賛否両論ありながらも、ドラクエ7は人々の心に残り続けているのでしょうか。

唯一無二の重厚なストーリー
本作の魅力の根幹にあるのは、やはりその重厚で奥深いストーリーです。 前述したように、物語には暗く、救いのない展開が多く含まれています。 しかし、そのビターな味わいこそが、他のシリーズにはないリアリティと深みを物語に与えています。 単純な勧善懲悪では描かれない、人間の弱さ、愚かさ、そして、それでも失われない希望。 一つ一つのエピソードがプレイヤーに問いかけるテーマは非常に深く、大人になった今だからこそ、その真価を理解できるというファンは少なくありません。 絵本のような見た目と、シリアスな物語のギャップが、強烈なインパクトとなってプレイヤーの記憶に刻み込まれているのです。
圧倒的なボリュームとやり込み要素
「長すぎる」と評されたボリュームも、見方を変えれば大きな魅力です。 当時は、今のように気軽に何本もゲームソフトを買える子供ばかりではありませんでした。 「一本のソフトをしゃぶり尽くすまで遊びたい」というユーザーにとって、ドラクエ7の圧倒的なボリュームは、まさに最高の贈り物でした。 ストーリーをクリアするだけでも100時間近くかかり、そこからさらに膨大な数の職業をマスターしたり、隠しダンジョンを攻略したりと、文字通り無限に遊べるほどのやり込み要素が用意されていました。 この底なしのゲーム体験が、多くのプレイヤーにとって忘れられない思い出となっているのです。
「不便さ」が生んだコミュニケーション
現代のようにインターネットが普及していなかった時代、ドラクエ7の「不便さ」は、かえってプレイヤー同士のコミュニケーションを生み出すきっかけとなりました。 「あの石板、どこで見つけた?」 「ダーマ神殿のボス、どうやって倒した?」 学校の休み時間や放課後、友人たちと攻略情報を交換し、ああでもないこうでもないと知恵を出し合った経験は、多くの30代、40代のゲームファンにとって、かけがえのない青春の一ページです。 一人で黙々と攻略するのではなく、家族や友人と一緒に悩み、一緒に喜びを分かち合った。 その共有体験こそが、ドラクエ7を単なるゲーム以上の「特別な思い出」に昇華させた最大の要因なのかもしれません。
まとめ
『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』は、シリーズの中でも類を見ないほど挑戦的で、尖った作品でした。 長すぎる導入部、重すぎるシナリオ、理不尽なメンバー離脱、そして悪夢の石板探し。 その高難易度と理不尽さは、多くのプレイヤーをふるいにかけ、挫折させました。
しかし、その一方で、他に類を見ない重厚な物語、圧倒的なやり込み要素、そして不便さの中から生まれたプレイヤー同士の絆は、何物にも代えがたい魅力として、今なお多くのファンの心に深く刻まれています。
2026年2月5日に発売される『ドラゴンクエストVII リイマジンド』は、原作の持つその強烈な個性を尊重しつつ、現代のプレイヤーがストレスなく楽しめるよう、あらゆる面で快適化が図られています。 原作で心を折られた方も、これから初めてドラクエ7の世界に触れる方も、誰もがこの壮大な物語を最後まで楽しめる作品になることは間違いないでしょう。
かつて石板探しに苦しんだあの冒険が、最新の技術でどのように生まれ変わるのか。 発売の日を、心から楽しみに待ちたいと思います。