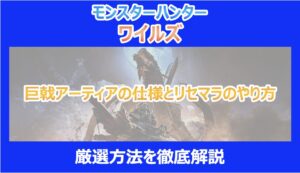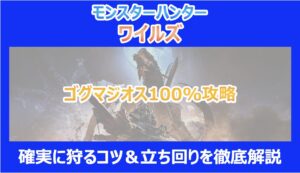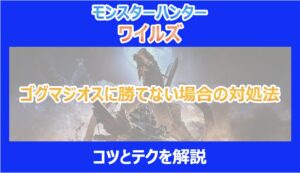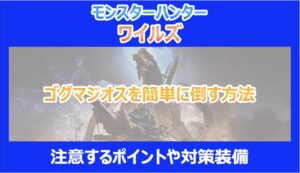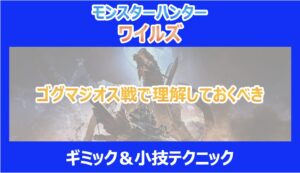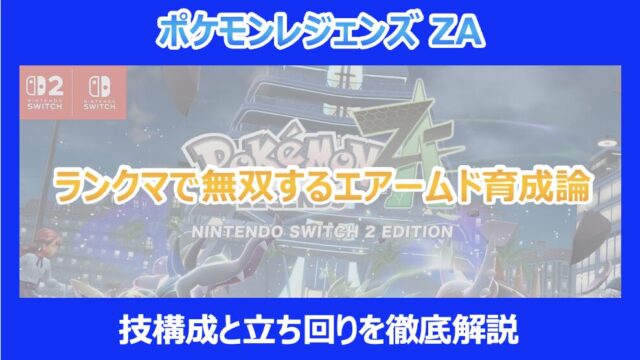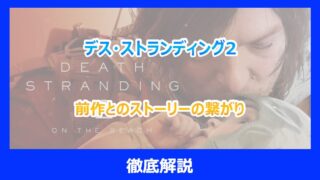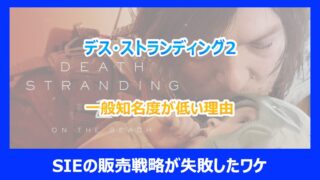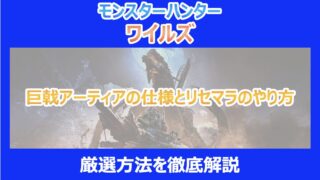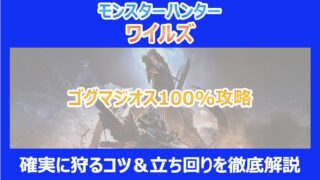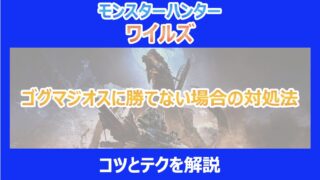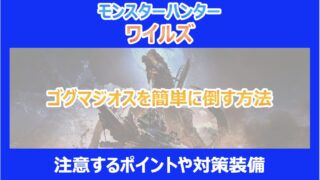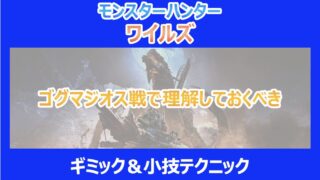ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年2月28日に発売された「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」について、「神ゲーと絶賛されているのに、なぜ販売本数が振るわないの?」という疑問をお持ちだと思います。
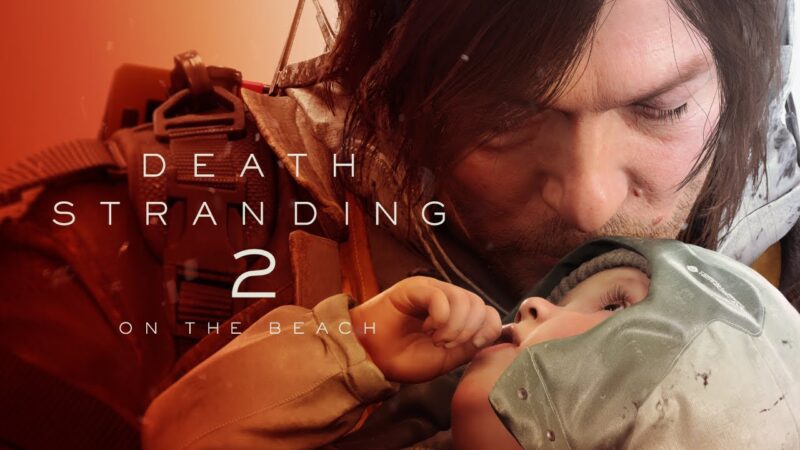
前作ファン待望の続編でありながら、発売後のセールスに関する少しネガティブな情報や、思ったほどの盛り上がりに欠ける現状に、購入をためらっている方も少なくないでしょう。
この記事を読み終える頃には、デス・ストランディング2が置かれている現状と、その評価の真実、そしてあなたがこのゲームをプレイすべきかどうかについての疑問が解決しているはずです。
- 前作を凌駕する「神ゲー」と呼べるクオリティ
- 販売本数が伸び悩む複数の明確な理由
- 万人に勧められる作品ではないという事実
- 購入を判断するための具体的なポイント
それでは解説していきます。

デス・ストランディング2の評価|神ゲーと呼ばれる理由とは
まず結論から述べると、デス・ストランディング2は間違いなく「神ゲー」と呼ぶにふさわしいクオリティの作品です。 私自身、先行プレイを含めて既に100時間以上この世界に没頭していますが、その作り込みと独自性には驚かされるばかりです。 では、具体的にどのような点がプレイヤーを魅了し、「神ゲー」と言わしめるのでしょうか。 前作からの進化点を中心に、その核心に迫っていきます。

驚きと感動に満ちた唯一無二のストーリー
本作の魅力として、何よりも先に挙げたいのがそのストーリーです。 前作のエンディングから約1年後、主人公サム・ポーター・ブリッジズが新たな仲間と共に、分断された世界を再び繋ぐため、北米大陸を越えてメキシコ、そしてその先の新大陸へと旅立ちます。

謎が謎を呼ぶ衝撃的な展開
物語は序盤からプレイヤーをグイグイと引き込みます。 前作で共に旅をしたBB「ルー」のその後、サム自身の過去、そして新たな脅威として現れる謎の勢力。 次から次へと提示される謎と、それらが巧みに絡み合い、予測不能な展開が続きます。 「一体どういうことなんだ?」と翻弄されながらも、物語を進める手が止まらなくなるのです。 そして、散りばめられた伏線が一つに繋がっていく終盤のカタルシスは、まさに圧巻の一言。 ネタバレになるため詳細は語れませんが、私はエンディングで思わず涙してしまいました。 それほどまでに、心に深く突き刺さる重厚な物語が待っています。
小島秀夫監督ならではの演出と世界観
いわゆる「小島節」も健在です。 他のゲームでは決して見られないような、奇抜でセンス溢れるシチュエーションや演出が随所に盛り込まれています。 リアリティとフィクションが絶妙に融合した世界観、ノーマン・リーダスやエル・ファニングといった豪華俳優陣による素晴らしい演技、そしてゲームプレイとシンクロする美しいBGM。 これらが一体となり、プレイヤーに圧倒的な没入感をもたらします。 前作は専門用語が多く難解な部分もありましたが、今作では物語の展開が比較的ストレートで理解しやすくなっています。 さらに、作中でいつでも用語やあらすじを確認できる「コーパス」機能が追加されたことで、新規プレイヤーでも世界観に入り込みやすくなった点は、大きな改善点と言えるでしょう。
快適性と中毒性が増した配達要素
デス・ストランディングの核となるゲームプレイは「配達」です。 この配達要素が、前作から大幅に進化し、より快適で中毒性の高いものへと昇華されています。

圧倒的なグラフィックで描かれる新大陸
まず驚かされるのが、そのグラフィックです。 PS5の性能を最大限に活かした映像美は、息をのむほどリアル。 荒野、密林、砂漠、雪山といった多彩なロケーションが、前作以上に美しく、そして過酷な姿でプレイヤーの前に広がります。 今作から導入された時間帯の概念により、昼と夜でフィールドの表情は一変し、天候の変化も視覚的に大きな影響を与えます。 この進化したグラフィックが、配達という行為そのものの楽しさと没入感を格段に引き上げています。
工夫が試される自由度の高いゲームプレイ
主人公のサムはスーパーマンではありません。 重すぎる荷物を背負えばバランスを崩して転び、急な川に足を取られれば流されてしまいます。 地形を読み、天候を予測し、どのようなルートで、どのような装備を使って荷物を運ぶか。 この「工夫」こそが、本作の面白さの根幹です。 崖にはしごをかけ、川に橋を渡し、時には大きく迂回して安全なルートを選ぶ。 ゲームが進行すると、国道や今作で新たに登場した「モノレール」といった大規模なインフラを整備することも可能になります。 膨大な資材を集め、コツコツと道を繋げていく作業は、まるでシミュレーションゲームのような達成感があり、一度ハマると抜け出せない中毒性を持っています。
プレイヤーの負担を軽減する数々の改善
前作で指摘された「不便さ」もかなり改善されています。 配達をサポートする建設物や乗り物の種類が増え、比較的早い段階から使用可能になります。 特に、大量の物資を長距離輸送できるモノレールの存在は大きく、よりダイナミックで戦略的な配達計画が立てられるようになりました。 面倒な移動をいかに効率化し、快適にしていくか。 そのプロセス自体が、本作の大きなやり込み要素の一つとなっているのです。
前作から大幅に進化した本格的な戦闘
前作では、戦闘はどちらかというと「おまけ」や「回避すべきもの」という側面が強かったかもしれません。 しかし、本作の戦闘はメインコンテンツの一つとして、本格的かつ非常に楽しめるものへと進化を遂げています。
TPSとして純粋に面白いシューティングアクション
基本的な戦闘システムは、三人称視点のシューティングアクション(TPS)です。 サムの行く手を阻む武装集団「ミュール」や、謎の勢力「ゴーストメック」と銃火を交えることになります。 特筆すべきはその自由度の高さ。 アサルトライフルやショットガンで真正面から撃ち合うもよし、ステルスで敵を無力化するもよし。 新たに加わったスナイパーライフルでの遠距離狙撃など、戦術の幅は大きく広がりました。 敵のAIも賢くなっており、単調な作業になりがちな戦闘も、常に緊張感を持って楽しめます。
アグレッシブになった近接戦闘
銃撃戦だけでなく、近接戦闘も大きく進化しています。 前作よりもスピーディーかつアグレッシブなアクションが可能になり、飛び蹴りやコンボ技を駆使して敵を圧倒できます。 特に、早い段階で入手できる「スタンロッド・カスタム」は非常に強力で、これを振り回しているだけでも爽快感があります。 ステルスが苦手なプレイヤーでも、近接戦闘でゴリ押しするという選択肢が生まれたのは嬉しいポイントです。 巨大なボスとの戦闘も健在で、その迫力とスケール感は前作以上。 戦闘シチュエーションも多彩で、プレイヤーを飽きさせない工夫が凝らされています。
数百時間は遊べる豊富なやり込み要素
デス・ストランディング2は、ストーリーをクリアするだけでも数十時間はかかるボリュームですが、本当の魅力はその先にあります。 膨大なやり込み要素が、プレイヤーをこの世界に長く留まらせてくれるのです。
無数のサブミッションと育成要素
メインストーリーとは別に、各拠点では様々な配達依頼(サブミッション)が受注できます。 これらの依頼をこなすことで、拠点の信頼ランクが上昇し、新たな武器や装備、便利な機能が解放されていきます。 攻略の幅が広がるだけでなく、世界の謎に迫るサイドストーリーが語られることもあるため、積極的にこなしたくなる魅力があります。
また、今作では育成要素も強化されました。 配達、戦闘、ステルスといったプレイヤーの行動に応じて、サムの能力が細かく成長していきます。 スキルツリー形式の「BBポッド・エンハンスメント」も加わり、自分のプレイスタイルに合わせてサムをカスタマイズしていく楽しみも増えています。
インフラ整備という名の壮大な箱庭遊び
前述した国道やモノレールの整備は、それ自体がエンドコンテンツになり得るほど奥深いやり込み要素です。 広大なマップに自分の手で道を通し、他のプレイヤーがそれを利用して「いいね!」をくれる。 この緩やかな繋がりと貢献の実感が、他のゲームにはない独特の達成感を生み出します。 大陸全土にインフラ網を張り巡らせるという壮大な目標は、まさにプレイヤー自身が世界を繋いでいく体験そのものと言えるでしょう。 この他にも、隠し要素や収集要素、美しい景色を撮影するフォトモードなど、語り尽くせないほどの要素が詰まっており、数百時間、あるいはそれ以上遊べるポテンシャルを秘めています。
デス・ストランディング2の販売本数が少ない理由
これほどまでに作り込まれた「神ゲー」でありながら、なぜ「販売本数が少ない」「盛り上がっていない」と言われてしまうのでしょうか。 その背景には、作品の性質と販売戦略に起因する、いくつかの明確な理由が存在します。

そもそも人を選ぶ「配達」というゲーム性
最大の理由は、やはりその独特すぎるゲーム性にあります。 本作のプレイ時間の大半は「移動」です。 荷物を運び、目的地へ向かう。 この行為を「楽しい」と感じられるか、「退屈な作業」と感じるかで、評価は180度変わります。
「お使いゲー」の究極形
悪い言い方をすれば、本作は究極の「お使いゲー」です。 一般的なオープンワールドゲームのように、派手なイベントが次々と起こるわけではありません。 むしろ、地道でストイックなプレイが求められます。 コツコツと何かを達成していくプロセスを楽しめない人にとっては、ただただ面倒な作業の繰り返しに感じられてしまうでしょう。 演出面もやや冗長な部分があり、一つ一つの動作が丁寧な反面、テンポが悪いと感じる人もいるかもしれません。 この唯一無二のゲーム体験は、熱狂的なファンを生む一方で、同じくらい多くのプレイヤーをふるいにかけてしまうのです。
ユーザー数を限定する「PS5独占」という戦略
本作は発売時点でPlayStation 5(PS5)の独占タイトルです。 この販売戦略が、販売本数に大きな影響を与えていることは間違いありません。
| ハード | 推定普及台数(2025年初頭時点) | 特徴 |
|---|---|---|
| PS5 | 全世界 約6,000万台 | 本作の発売プラットフォーム。性能は高いが、普及台数はまだ限定的。 |
| PS4 | 全世界 約1億1,700万台 | 前作のメインプラットフォーム。今作は非対応。 |
| PC(Steam) | アクティブユーザー数 億単位 | 巨大な市場だが、本作のPC版発売は未定(将来的には発売される可能性が高い)。 |
| Nintendo Switch | 全世界 約1億4,000万台 | 巨大なユーザー層を持つが、スペック的に本作の移植は困難。 |
巨大なPS4市場の切り捨て
前作「デス・ストランディング」はPS4で発売され、全世界で多くのプレイヤーを獲得しました。 しかし、本作はPS5専用となったことで、まだPS4でプレイしている前作ファンの多くが、今作をプレイできずにいます。 PS5の普及は進んでいるとはいえ、PS4の巨大なユーザーベースを切り捨てた影響は計り知れません。
PC版の不在による機会損失
近年、AAAタイトルの多くは発売当初からマルチプラットフォームで展開するのが主流です。 特にPC(Steam)市場の重要性は増すばかり。 本作もいずれPC版が発売されると思われますが、発売時点での独占戦略は、初動の売上を最大化する機会を逃していると言えます。
新規層には高いハードルとなる「続編」であること
本作は明確な続編であり、ストーリーは前作から地続きです。 この点も、新規プレイヤーが手を出しにくい要因となっています。
作中には前作の振り返り機能があるため、本作からプレイを始めても物語を理解することは可能です。 しかし、前作で描かれたサムとルーの旅路や、因縁のあるキャラクターとの関係性を知っているかどうかで、物語への感情移入の深さは大きく変わってきます。 「続編を最大限に楽しむためには、前作をプレイしておくべき」という情報が、かえって新規層の参入障壁を高くしてしまっている側面は否めません。
SNSでバズりにくいゲーム内容と配信映えの問題
現代のゲームヒットの法則において、SNSでの口コミや動画配信は非常に重要な役割を担っています。 しかし、デス・ストランディング2は、その性質上、爆発的なバズを起こしにくいゲームと言えます。
地道なプレイは「切り抜き」に不向き
本作の面白さは、長時間かけてじっくりと世界に向き合うことで、徐々に理解できるものです。 派手な戦闘シーンもありますが、プレイの大半は地道な配達です。 こうしたゲームプレイは、短い動画でインパクトを伝える「切り抜き」や、視聴者を飽きさせない展開が求められるライブ配信とは、あまり相性が良くありません。 結果として、大手配信者がこぞってプレイするようなムーブメントが起きにくく、一般層への認知拡大に繋がりにくいのです。
パッケージ版売上からでは見えない実情
発売後、「前作に比べてパッケージ版の売上が66%減少した」というニュースが流れ、セールスの不振を印象付けました。 しかし、この数字だけで全てを判断するのは早計です。

現代のゲーム市場は、パッケージ版よりもダウンロード版が主流になりつつあります。 特に海外ではその傾向が顕著です。 パッケージ版の売上はあくまで一部のデータであり、ダウンロード版を含めた総販売本数は、メーカーからの公式発表を待たなければ正確には分かりません。 とはいえ、無視できない数字であることも事実であり、セールスが好調とは言えない状況を示唆しています。
コアなファンとライト層での評価の乖離
これまでの理由を総括すると、デス・ストランディング2は「コアなゲームファンや小島監督の作風を愛する人々からは絶賛されるが、ライト層には魅力が伝わりにくい」作品であると言えます。 Amazonのレビューを見ても、絶賛の星5と、ゲーム性に合わなかったであろう星1の評価に二極化している傾向が見られます。 「神ゲー」という評価は真実ですが、それはあくまで特定の層に向けられた評価であり、万人が同じように感じられるわけではないのです。 この評価の乖離が、「神ゲーなのに売れていない」という不思議な状況を生み出す最大の要因でしょう。
まとめ
さて、ここまでデス・ストランディング2が「神ゲー」である理由と、それでも販売本数が伸び悩む背景について、多角的に解説してきました。
結論として、本作は小島秀夫監督の作家性が色濃く反映された、唯一無二の体験ができる傑作です。 進化した配達要素、本格的な戦闘、そして心を揺さぶる重厚なストーリーは、前作ファンであれば間違いなく満足できる内容ですし、この独特な世界観にハマることができれば、他の何にも代えがたい最高のゲーム体験が待っています。
しかし、その一方で、「配達」というストイックなゲーム性、PS5独占という販売形態、そして続編であるがゆえのハードルの高さから、万人に受け入れられる作品ではないこともまた事実です。 「売上が少ない」という現状は、作品のクオリティが低いからではなく、そのあまりにも鋭く尖った個性が原因なのです。
もしあなたが購入を迷っているのなら、以下の点を自問自答してみてください。
- 派手さよりも、地道なプロセスや達成感を重視するプレイスタイルか?
- 難解でも、考察のしがいがある深いストーリーや世界観が好きか?
- 他のゲームにはない、全く新しい体験を求めているか?
これらの質問に「イエス」と答えられるのであれば、あなたは本作を心の底から楽しめる素質があります。 逆に、手軽な爽快感や分かりやすい楽しさを求めるのであれば、本作は合わない可能性が高いでしょう。
最終的には、YouTubeなどで実際のプレイ動画を少し見てみて、その独特の空気感を受け入れられるかどうかを判断するのが最も確実です。 このレビューが、あなたの決断の一助となれば幸いです。 世界を繋ぐ、孤独で、しかし美しい旅へ。 その一歩を踏み出すかどうかは、あなた次第です。