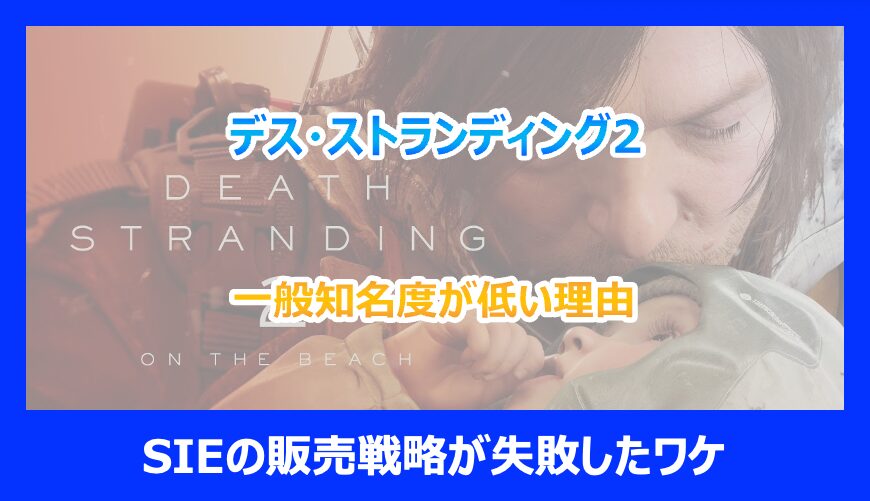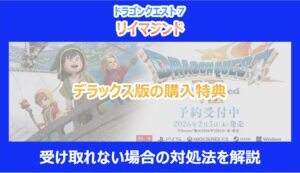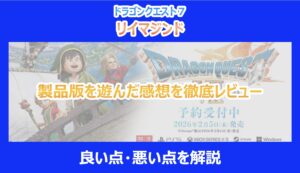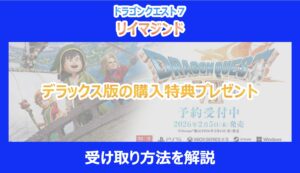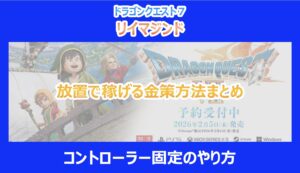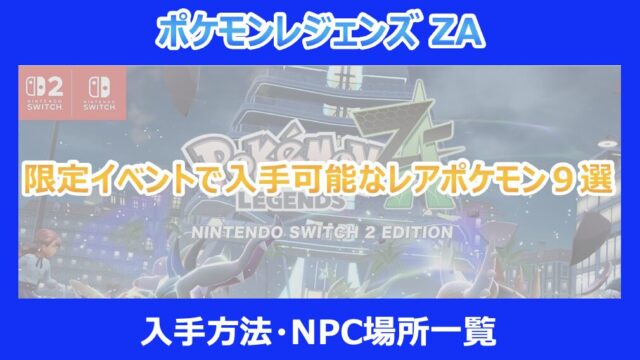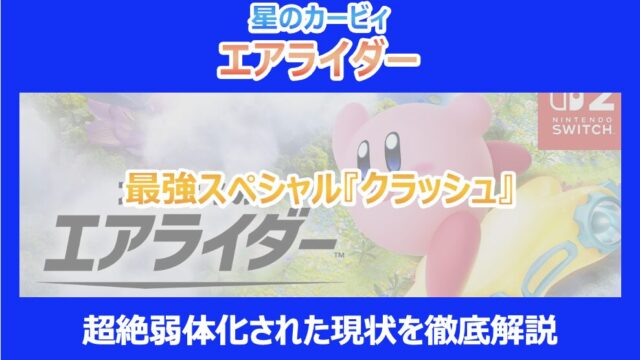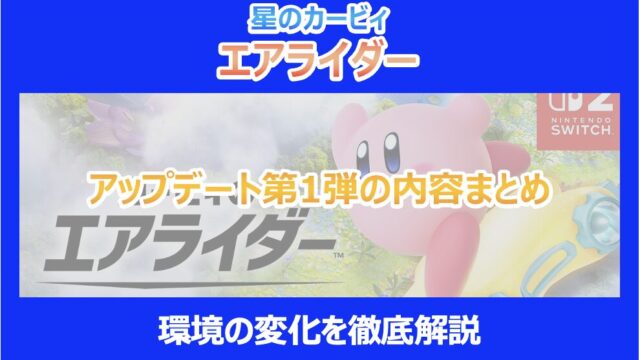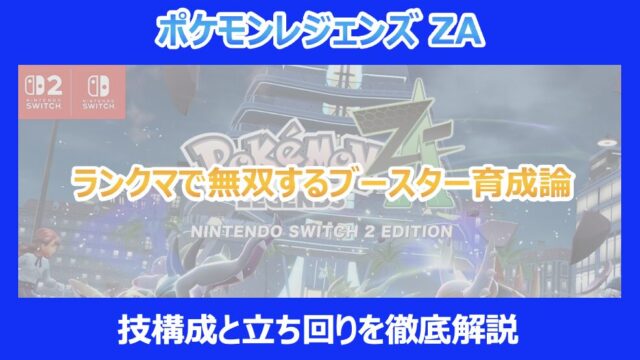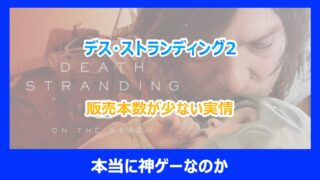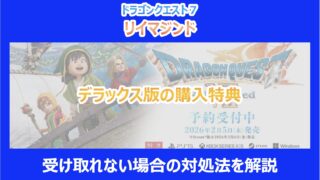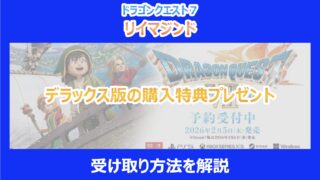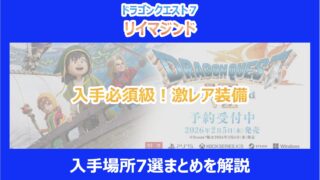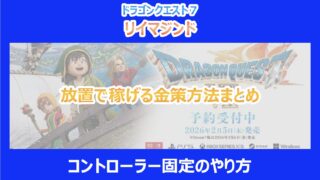ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年に発売され、多くのコアゲーマーから「神ゲー」と絶賛されているにもかかわらず、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』(以下、デス・ストランディング2)が、なぜこれほどまでに一般知名度が低いのか、気になっていると思います。
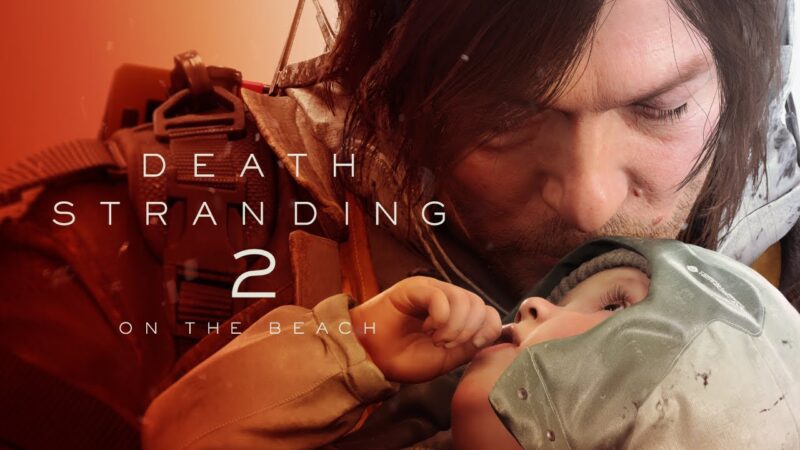
続編の発表に歓喜し、発売を心待ちにしていたファンがいる一方で、世間的な盛り上がりは限定的に感じられます。 ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)も、他の大型タイトルほど積極的な宣伝を行っていないように見えるのはなぜでしょうか。
この記事を読み終える頃には、デス・ストランディング2の魅力と、その知名度が伸び悩んでいる背景、そしてSIEの販売戦略に関する疑問が解決しているはずです。
- 唯一無二だが人を選ぶ中毒性の高いゲーム性
- 新規層を阻む「続編」という構造的なハードル
- PS5独占販売というSIEの販売戦略が招いた機会損失
- 小島秀夫監督の強烈な作家性と一般層の距離感
それでは解説していきます。

デス・ストランディング2は本当に「神ゲー」なのか?その魅力と正統進化
まず大前提として、デス・ストランディング2がゲームとして高い評価を受けているのは事実です。 では、具体的にどのような点がプレイヤーを魅了し、「神ゲー」と言わしめるのでしょうか。 前作をプレイしたファンはもちろん、未プレイの方にも分かるように、その核心的な魅力を掘り下げていきます。
独創的すぎる世界観と衝撃に満ちたストーリー
本作の最大の魅力は、やはり小島秀夫監督によって生み出された、他に類を見ない独創的な世界観と、プレイヤーの心を揺さぶる重厚な物語にあります。

「デス・ストランディング」という謎の現象によって生と死の境界が曖昧になり、人々が分断されてしまった世界。 前作で北米大陸を繋いだ伝説の配達人サム・ポーター・ブリッジズが、今度は新たな仲間たちと共に、北米を越えてメキシコ、さらにはオーストラリア大陸まで、再び世界を繋ぐために旅に出ます。
物語は序盤から謎が謎を呼ぶ展開の連続です。 前作でサムと旅を共にしたBB「ルー」の隠された真実、サム自身の過去、そして新たな脅威として立ちはだかる謎の勢力。 多くの伏線が巧みに張り巡らされ、それらが終盤に見事に回収されていくカタルシスは、まさに圧巻の一言です。
特に、本作の物語は前作以上に分かりやすさを意識して作られている点も評価できます。 前作は専門用語が多く、難解な部分もありましたが、本作では「コーパス」という用語解説機能が実装され、物語の理解を助けてくれます。 もちろん、小島監督作品特有の哲学的・思索的なテーマは健在ですが、物語の主軸は追いやすく、より多くのプレイヤーが没入できるような配慮がなされています。
ノーマン・リーダスをはじめとする豪華俳優陣の演技も、モーションキャプチャー技術によってキャラクターに生命を吹き込み、物語への没入感を極限まで高めています。 壮大な音楽と相まって、まるで一本の長大な映画を体験しているかのような感動が、そこにはあります。
より快適に、より奥深くなった「配達」という唯一無二のゲーム性
デス・ストランディングの核となるゲームプレイ、それは「配達」です。 荷物を目的地まで運ぶ。 言葉にすれば単純ですが、その道中は決して平坦ではありません。
険しい山々、荒れ狂う川、荷物の重さによるバランスの変化、そしてBT(座礁物)や敵対組織といった脅威。 プレイヤーは地形を読み、最適なルートを選択し、時には梯子やロープ、橋といったインフラを整備しながら、困難な道のりを乗り越えていきます。 この「移動」そのものをゲームデザインの根幹に据えた点が、本作の最大の特徴です。
本作では、この配達要素が前作から大幅に進化し、さらに快適で中毒性の高いものになっています。
新たな建設物と乗り物の登場
ゲームの早い段階から多様な建設物や乗り物が利用可能になり、攻略の自由度が格段に向上しました。 特に、新たに登場した「モノレール」は、大量の物資を長距離にわたって輸送できるため、インフラ整備の概念を大きく変えました。 プレイヤーは自らの手で分断された世界に道を通し、線路を敷き、大陸を繋いでいく達成感を味わうことができます。
ソーシャル・ストランド・システムの深化
他のプレイヤーと緩やかに繋がる「ソーシャル・ストランド・システム」も健在です。 自分が設置した梯子や橋を他のプレイヤーが利用し、「いいね!」を送り合う。 誰かが整備した国道をバイクで駆け抜ける。 直接的な協力プレイとは異なりますが、見知らぬ誰かの善意に助けられ、また自分も誰かの助けになるという、独特の連帯感がこのゲームの温かい世界観を形作っています。
このシステムがあるからこそ、困難な配達も「誰かのために」というモチベーションに繋がり、作業的になりがちな移動に意味を与えてくれるのです。 本作では、この繋がりがさらに多様な形で表現され、プレイヤーは孤独でありながらも、決して一人ではないという感覚を強く抱くことになるでしょう。
本格的な三人称視点シューター(TPS)へと進化した戦闘
前作の戦闘は、どちらかといえばステルスで敵をやり過ごしたり、逃げたりすることが主体で、やや単調な側面がありました。 しかし、デス・ストランディング2では、この戦闘要素が劇的に進化を遂げています。

アサルトライフルやショットガンを使った本格的な銃撃戦が可能になり、敵のAIも賢くなったことで、歯ごたえのあるアクションが楽しめます。 もちろん、前作同様のステルスプレイや、非殺傷兵器を使った攻略も可能で、プレイヤーのスタイルに合わせた多様な戦闘が展開されます。 新武器や新装備も多数追加され、特に近接戦闘では空手のようなアグレッシブなアクションも可能になりました。
巨大なボスとの戦闘も迫力満点で、単なる配達ゲーのおまけではない、一つの独立したアクションゲームとして成立するほどのクオリティに達しています。 この戦闘の進化により、配達の道中における脅威がよりスリリングなものとなり、ゲーム全体の緩急を生み出すことに成功しています。
数百時間は遊べる膨大なやり込み要素
デス・ストランディング2は、メインストーリーをクリアするだけでも数十時間のボリュームがありますが、その真価はクリア後の広大な世界にあります。
無数の配達依頼と拠点ランク
メインストーリーとは別に、各拠点からは無数の配達依頼(サブミッション)が受注できます。 これらの依頼をこなすことで、拠点のランクが上昇し、新たな武器や装備の設計データ、便利な機能などが解放されていきます。 攻略の幅が広がるだけでなく、各拠点の住人たちのサイドストーリーに触れることもでき、世界への理解がより深まります。
インフラ整備という壮大な目標
国道やモノレールといったインフラを整備すること自体が、本作における大きなやり込み要素です。 整備には大量の資材が必要となり、プレイヤーは資材を集めるためにミッションをこなしたり、敵の拠点を制圧したり、時には他のプレイヤーと協力して資材を融通し合ったりします。 コツコツと資材を納品し、荒野にアスファルトの道が伸びていくのを見た時の達成感は、他のゲームでは味わえない格別なものがあります。 これは、まるで『マインクラフト』のように、世界を自らの手で創造していく喜びに通じるものがあるかもしれません。
深化した育成システム
本作では、プレイヤーの行動によってサムの能力が細かく成長していくシステムが導入されました。 配達をこなせば運搬能力が、戦闘を繰り返せば戦闘能力が向上するなど、プレイスタイルがサムの成長に直接反映されます。 さらに、「Aパスエンハンスメント」と呼ばれるスキルツリー形式の成長要素も加わり、より能動的にサムをカスタマイズしていく楽しみも増えました。
このように、デス・ストランディング2は前作をあらゆる面で正統進化させた、紛れもない「神ゲー」と呼ぶにふさわしい内容となっています。 ではなぜ、これほどのクオリティを持ちながら、一般層への広がりを欠いているのでしょうか。
なぜ知名度が低いのか?デス・ストランディング2が抱える課題とSIEの販売戦略
「神ゲー」であるはずのデス・ストランディング2が、なぜ世間的な盛り上がりに欠けるのか。 その理由は、ゲームの内部的な要因と、SIEの販売戦略という外部的な要因が複雑に絡み合った結果だと考えられます。
致命的ともいえる「人を選ぶ」ゲーム性
本作の最大の魅力であり、同時に最大のハードルとなっているのが、その特異なゲーム性です。 「配達」、つまり「移動」をゲームの中心に据えたデザインは、ハマる人にはとてつもない中毒性を生み出しますが、合わない人には徹底的に合わない、という両極端な評価を生み出します。

「お使いゲー」と揶揄される作業感
ゲームプレイの大部分が目的地への移動であるため、これを単調な「お使い」や「作業」だと感じてしまうプレイヤーが一定数存在するのは事実です。 特に序盤は、使える装備も少なく、ひたすら徒歩で険しい地形を進むことになるため、ここで挫折してしまう人も少なくありません。 「この面倒な移動をどう工夫して快適にするか」という部分に面白さを見出せるかどうかが、このゲームを楽しめるか否かの分水嶺となります。
派手なアクションやスピーディーな展開を求めるプレイヤーにとっては、このストイックなゲーム性は退屈に映る可能性が高いでしょう。 この点が、幅広い層に受け入れられる上での大きな障壁となっています。
新規プレイヤーを遠ざける「続編」という高い壁
デス・ストランディング2は、前作のエンディングから直接繋がる物語です。 もちろん、作中には前作のあらすじを振り返る機能があり、新規プレイヤーへの配慮は見られます。 しかし、このゲームの物語の感動は、前作でサムやルー、そして魅力的な登場人物たちと共に過酷な旅を乗り越えたという経験があってこそ、最大限に引き出されるものです。
前作のキャラクターとの因縁や、彼らの変化を知っているかどうかで、物語への感情移入の度合いは大きく変わってきます。 「本作からでも楽しめるが、前作をプレイしていた方が100倍楽しめる」という構造は、必然的に新規プレイヤーの参入障壁を高くしてしまいます。 これが、前作ファン以外の層に訴求する上での弱点となっていることは否めません。
SIEの販売戦略の失敗?PS5独占が招いた機会損失
ここが、本作の知名度が伸び悩む最大の外部要因だと考えられます。 SIEはデス・ストランディング2を、PlayStation 5(PS5)の独占タイトルとして発売しました。 この戦略が、結果的に多くの潜在的なプレイヤーを遠ざけてしまった可能性があります。
パッケージ売上の衝撃的な減少
| タイトル | 発売週のイギリス市場パッケージ版売上 |
|---|---|
| デス・ストランディング (PS4) | 基準値 (100%) |
| デス・ストランディング2 (PS5) | 前作比 -66% |
海外の調査によると、イギリスのパッケージ版の初週売上は、前作と比較して66%も減少したと報告されています。 もちろん、現代のゲーム市場はダウンロード販売が主流であり、パッケージ版の売上だけで全てを判断することはできません。 しかし、それを考慮しても、この数字は看過できないほどの落ち込みであり、市場へのインパクトが前作よりも弱かったことを示唆しています。
PC版不在がもたらした「盛り上がり」の欠如
現代のゲーム市場において、PC(Steam)プラットフォームの存在は無視できません。 PCには膨大な数のゲーマーが存在し、TwitchやYouTubeといった配信プラットフォームでの盛り上がりは、多くの場合PCゲームが中心となっています。
前作は発売から約8ヶ月後にPC版がリリースされ、新たなファン層を獲得すると同時に、MOD文化なども含めて長期的に話題を提供し続けました。 しかし、本作はPS5独占であるため、この巨大なPC市場にリーチできていません。 結果として、ゲーム実況配信のシーンでも一部の人気配信者を除いて大きなムーブメントとはならず、「界隈で盛り上がっていない」という印象に繋がってしまいました。
『エルデンリング』や『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』が発売初日にSNSのトレンドを席巻したような熱狂が生まれにくかったのは、このPC版の不在が大きく影響しているでしょう。
PS5の普及台数という物理的な限界
前作が発売されたのは、全世界で1億台以上が普及していたPS4の成熟期でした。 一方で、本作はまだ普及途上にあるPS5での発売です。 PS5の販売台数は好調に推移しているとはいえ、PS4時代のアクティブユーザー数にはまだ及びません。 単純に、ゲームをプレイできる環境を持つ人の母数が少ないことも、売上や知名度の伸び悩みの一因となっています。
SIEとしては、PS5を牽引するキラータイトルとして本作を位置づけたかったのでしょう。 しかし、結果的には、プラットフォームを限定したことが、作品のポテンシャルを最大限に引き出す上での足かせとなってしまった側面は否定できません。
小島秀夫というクリエイターの作家性が生む「誤解」
小島秀夫監督は、世界中に熱狂的なファンを持つカリスマ的なクリエイターです。 しかし、その一方で、彼の作品には常に「難解」「哲学的」「マニア向け」といったイメージがつきまといます。 この強烈な作家性が、かえって一般層やライトユーザーを遠ざけてしまう「食わず嫌い」を生んでいる可能性があります。
「小島監督のゲームだから、きっと複雑で難しいに違いない」 「ムービーが長くて、ゲームを遊んでいる時間より見ている時間の方が長いのでは?」
こうした先入観が、新規プレイヤーの「ちょっと試してみよう」という気持ちにブレーキをかけているのかもしれません。 実際にプレイすれば、その深い世界に引き込まれるプレイヤーも多いはずですが、その入り口に立つまでのハードルが、クリエイター自身のブランドによって高くされているという皮肉な状況が生まれています。
発売直後のネガティブな評価の影響
Amazonのレビューなどを見ると、発売直後には「単調でつまらない」「作業的だ」といった星1つの低評価レビューが散見されました。 これらは、本作の特殊なゲーム性が合わなかったプレイヤーによる正直な感想でしょう。 しかし、こうしたネガティブな意見が先行してしまうと、購入を検討している層が「やっぱりこのゲームは自分には合わないかもしれない」と躊躇してしまう原因になります。
特に、先行アクセスでプレイした一部のプレイヤーの意見が、発売日を迎えた一般プレイヤーの購入意欲に影響を与えた可能性も考えられます。 熱狂的なファンと、全く合わないと感じる層との間で評価が真っ二つに割れる本作の性質が、発売直後の口コミ形成において不利に働いたと言えるでしょう。
まとめ
デス・ストランディング2が「神ゲー」であることに疑いの余地はありません。 前作をあらゆる面で進化させ、唯一無二のゲーム体験を提供してくれる、現代のビデオゲームが到達した一つの極地とも言える作品です。
しかし、その成功は、皮肉にも知名度の低さと表裏一体となっています。
- 特異すぎるゲーム性: 「配達」という行為は、万人が楽しめるものではなく、プレイヤーを厳しく選別する。
- 続編という構造: 前作のプレイが半ば前提となっており、新規プレイヤーが参入しにくい。
- PS5独占という販売戦略: PCという巨大市場を切り捨て、配信文化の潮流から外れてしまった。普及台数の限界も足かせとなった。
- 強烈な作家性: 小島秀夫監督への「難解」という先入観が、ライトユーザーを遠ざけている。
これらの要因が複合的に絡み合った結果、デス・ストランディング2は「知る人ぞ知る、極上の神ゲー」という、ややニッチな立ち位置に落ち着いてしまったのです。 SIEの販売戦略は、PS5プラットフォームの価値を高めるという点では意味があったかもしれませんが、作品のポテンシャルを最大限に広げるという点では、必ずしも成功したとは言えないでしょう。
しかし、だからこそ、このレビューを読んで興味を持ったあなたには、ぜひこの世界に飛び込んでみてほしいのです。 もしあなたが、他の誰とも違う体験を求め、じっくりと一つの世界に没入することに喜びを感じるタイプのゲーマーであるならば、デス・ストランディング2は、あなたのゲーム人生における忘れられない一本になることを、私が保証します。