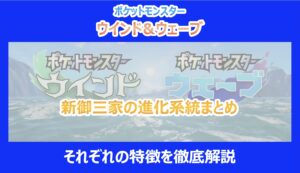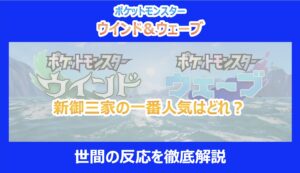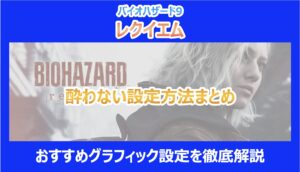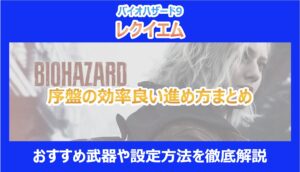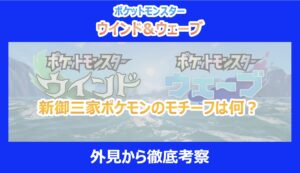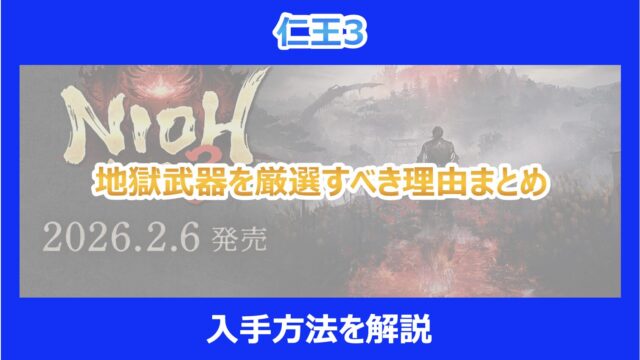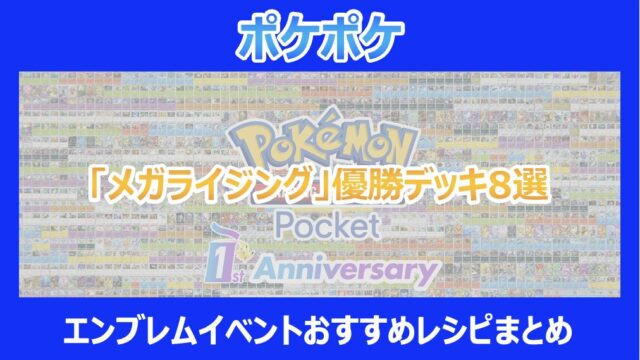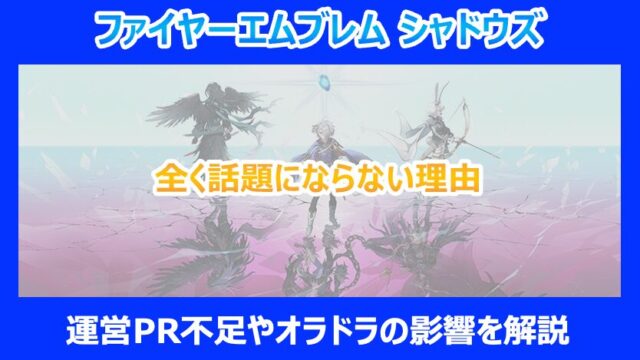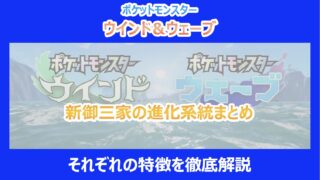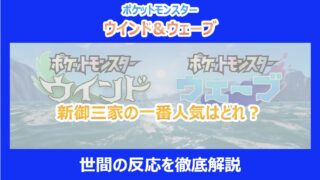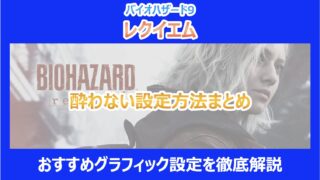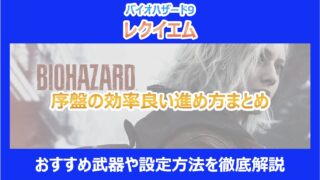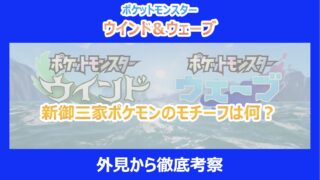ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられている質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年10月10日に発売されたばかりの人気FPSゲーム「バトルフィールド6(BF6)」をお子さんがプレイすることについて、どのような影響があるのか気になっていると思います。 「学校で流行っているから買ってほしいと言われたけど、FPSは性格が攻撃的になるって本当?」「毎日イライラするようになったらどうしよう…」そんな保護者の方々の不安の声をよく耳にします。 私自身も一人のゲーマーとして、そして多くのゲームを見てきた評論家として、そのお気持ちはよくわかります。

この記事では、ゲームがお子さんに与える影響について、ネット上の漠然とした情報だけでなく、なぜそう言われるのかというメカニズムから、具体的なメリット・デメリット、そして最も重要な「家庭内での向き合い方」まで、深く掘り下げて解説していきます。
この記事を読み終える頃には、バトルフィールド6がお子さんに与える影響への疑問が解決しているはずです。
- バトルフィールド6の具体的なゲーム内容と対象年齢
- FPSが子供に与える精神的なデメリットとその科学的背景
- FPSを通じて得られる学力や社会性へのポジティブな影響
- 親子で実践できる具体的なゲームとの付き合い方とルール作り
それでは解説していきます。

バトルフィールド6(BF6)はどのようなゲームなのか?
まず最初に、話題の中心である「バトルフィールド6」が、一体どのようなゲームなのかを正確に理解しておく必要があります。 漠然と「銃で撃ち合う怖いゲーム」というイメージだけでは、適切な判断はできません。 ここではゲーム評論家の視点から、BF6の核心的な面白さと特徴を解説します。
大規模な戦場を体験できるリアル系FPS
バトルフィールドシリーズの最大の特徴は、なんといってもその「規模感」にあります。 一般的なFPSが5対5や6対6といった少人数での戦闘を主軸に置くのに対し、BF6では最大64人対64人、合計128人(※プラットフォームによる)が同じマップで戦闘を繰り広げます。

歩兵同士の撃ち合いはもちろん、戦車、戦闘機、ヘリコプター、装甲車といった様々な兵器に実際に乗り込み、操作することが可能です。 プレイヤーは一人の兵士として、広大な戦場で仲間と協力し、拠点を奪い合います。 ただ敵を倒すだけでなく、「どの拠点を攻めるか」「どこを守るべきか」「兵器をどう活用するか」といった戦略的な判断が常に求められるのです。 この「戦場の一員になる」という没入感こそが、BF6が世界中のファンを魅了する最大の理由です。
CEROレーティングは「D」:17才以上が対象
BF6の対象年齢区分(CEROレーティング)は「D」に設定されています。 これは「17才以上対象」を意味し、暴力、犯罪、言葉などの表現が17才以上の方に適した内容であることを示しています。 具体的には、以下のような表現が含まれる可能性があります。
- 暴力表現: 銃撃による出血描写や、兵士が倒れる際のリアルな表現。
- 犯罪表現: ゲームのシナリオ上で、戦争やそれに準ずる行為が描かれる。
- 不適切な言葉: ゲーム内のキャラクターが、俗語や汚い言葉を使用する場面がある。
CEROレーティングは、あくまでゲームの内容を評価し、購入時の目安を示すものです。 法的な拘束力はありませんが、メーカーが「このゲームは17才以上のプレイヤーを想定して作られています」と明示している重要な指標です。 お子さんがこの年齢に達していない場合、なぜこのレーティングが設定されているのかを親子で話し合い、内容を理解した上で購入を検討することが不可欠です。
勝利の鍵は「チームワーク」と「戦略性」
BF6で勝利するためには、個人の銃の腕前(エイム力)だけでは不十分です。 むしろ、それ以上に重要となるのが「チームワーク」です。
BF6には主に4つの兵科(役割)が存在します。
- 突撃兵: 最前線で戦い、敵の戦車などを破壊する役割。
- 工兵: 味方の兵器を修理したり、敵の兵器を破壊するための地雷を設置したりする役割。
- 援護兵: 味方に弾薬を補給し、機関銃で敵の進行を食い止める役割。
- 偵察兵: 遠距離から敵を狙撃し、敵の位置を味方に知らせる索敵の役割。
これらの役割が有機的に連携することで、初めて戦況を有利に進めることができます。 例えば、戦車が前進する際には工兵が後ろから修理し、敵の突撃兵から守るために援護兵が弾幕を張る、といった具体的な協力が求められます。 ボイスチャットやテキストチャットを使って仲間とコミュニケーションを取り、刻一刻と変化する戦況に対応していく能力は、BF6の醍醐味であり、プレイヤーに求められる重要なスキルなのです。
FPSが子供の精神に与える悪影響とは?ストレスの正体を解説
保護者の方が最も懸念されているのが、FPSが子供の精神面に与える「悪影響」でしょう。 「イライラしやすくなる」「攻撃的になる」「依存してしまう」といった声は、決して無視できるものではありません。 ここでは、なぜそのような状態に陥るのか、そのメカニズムと具体的なリスクについて深く掘り下げていきます。

なぜイライラしやすくなるのか?脳科学的な視点
FPSをプレイしていて、思わず声を荒らげたり、物に当たってしまったりする経験は、多くのプレイヤーが持っています。 これには、脳の働きが大きく関係しています。
1. 競争環境と敗北によるストレス
BF6のような対戦型ゲームは、常に「勝ち負け」が存在します。 勝利すれば達成感や高揚感が得られますが、敗北、特に理不-尽な負け方(一方的に倒される、味方のミスで負けるなど)を経験すると、強いストレスを感じます。 このストレス反応として、脳内では「コルチゾール」というストレスホルモンが分泌されます。 コルチゾールが過剰に分泌されると、イライラや不安感が増大し、感情のコントロールが難しくなるのです。
2. ドーパミンの過剰分泌と報酬系への刺激
敵を倒したり、チームが勝利したりすると、脳の「報酬系」と呼ばれる部分が刺激され、快感物質である「ドーパミン」が放出されます。 このドーパミンによる快感が、「もっとプレイしたい」という意欲に繋がります。 しかし、この刺激に脳が慣れてしまうと、より強い刺激を求めるようになり、ゲームをしていない時に物足りなさやイライラを感じるようになります。 これがゲーム依存の入り口となる可能性も指摘されています。
3. 高速な情報処理による脳の疲労
FPSは、画面上で非常に多くの情報が高速で行き交うゲームです。 敵の位置、味方の状況、弾薬の残数、マップの構造など、膨大な情報を瞬時に処理し、判断を下さなければなりません。 この状態は、脳、特に前頭前野(思考や理性を司る部分)に大きな負荷をかけます。 長時間のプレイは脳を極度に疲労させ、思考力や集中力の低下を招き、結果として些細なことでイライラしやすくなるのです。
「ゲーム脳」は本当?攻撃性や暴力的行動との関連性
「暴力的なゲームをすると、現実でも暴力的になる」という説は、長年議論されてきました。 これに関しては、様々な研究が行われていますが、専門家の間でも意見が分かれているのが現状です。
- 攻撃性を高めるという研究: 一部の研究では、暴力的なゲームをプレイした直後に、被験者の攻撃的な思考や感情が高まることが示されています。 これは、ゲーム内の仮想的な攻撃行動が、一時的に現実の思考パターンに影響を与える「プライミング効果」によるものと考えられています。
- 因果関係は証明されていないという研究: 一方で、アメリカ心理学会(APA)など多くの権威ある機関は、「暴力的なゲームと、深刻な暴力的行動との間に直接的な因果関係を示す科学的根拠は不十分である」との見解を示しています。 乱暴な性格の子供が暴力的なゲームを好む傾向がある(相関関係)かもしれませんが、ゲームがその子を乱暴にした(因果関係)とは断定できない、ということです。
重要なのは、ゲームという一つの要因だけで子供の攻撃性が決まるわけではない、という点です。 家庭環境、学校での人間関係、本人の性格など、様々な要因が複雑に絡み合って形成されます。 ゲームを過度に悪者扱いするのではなく、数ある影響の一つとして捉え、子供の現実世界での様子を注意深く見守ることが大切です。
オンラインプレイに潜むリスク|暴言やネットいじめ
BF6の主戦場はオンラインです。 世界中のプレイヤーと繋がり、協力したり、時には敵として戦ったりします。 この繋がりは大きな魅力である一方、深刻なリスクもはらんでいます。
ボイスチャット・テキストチャットでの暴言
試合が白熱すると、感情的になったプレイヤーから暴言(いわゆる「暴言VC」や「煽りチャット」)を受けることがあります。 「死ね」「雑魚」「使えない」といった直接的な罵倒は、特に感受性の強い子供の心を深く傷つけます。 顔が見えない匿名の環境だからこそ、言葉の暴力はエスカレートしやすい傾向にあります。
ネットいじめへの発展
ゲーム内のトラブルが、SNSなどゲーム外のコミュニティに持ち込まれ、ネットいじめに発展するケースも少なくありません。 特定のプレイヤーを集団で無視したり、悪質な噂を流したりといった行為は、子供に深刻な精神的ダメージを与えます。
これらのリスクから子供を守るためには、ゲーム機本体やゲーム内に搭載されているペアレンタルコントロール(保護者による利用制限)機能を活用することが非常に有効です。 ボイスチャットの利用を制限したり、特定のプレイヤーからの通信をブロックしたりするなど、事前に設定を確認し、お子さんに合った環境を整えてあげましょう。
FPSは悪影響だけじゃない!子供の成長を促すメリット
これまでデメリットやリスクに焦点を当ててきましたが、FPSには子供の能力を伸ばすポジティブな側面も数多く存在します。 これらのメリットを理解することは、ゲームとの健全な付き合い方を考える上で非常に重要です。 教育やリハビリの分野でもゲームが活用されている事実を知れば、少し見方が変わるかもしれません。
脳を鍛える?認知能力や問題解決能力の向上
近年の研究では、FPSのようなアクションゲームが、プレイヤーの様々な認知能力を向上させることが明らかになっています。

1. 注意力と情報処理能力の向上
FPSプレイヤーは、画面の広範囲に注意を払い、複数の対象を同時に追跡し、必要な情報だけを選択して素早く反応する能力に長けていることが分かっています。 これは、ゲームプレイを通じて「選択的注意」や「持続的注意」といった能力が鍛えられるためです。 この能力は、学習において集中力を維持したり、スポーツにおいて瞬時の判断を下したりする際にも役立ちます。
2. 空間認識能力の向上
3Dで描かれた複雑なマップを駆け巡り、敵や味方の位置関係を立体的に把握する行為は、空間認識能力を養います。 どこに隠れれば安全か、どのルートを通れば敵の裏をかけるか、といった思考は、地図を読んだり、図形問題を解いたりする能力にも繋がると言われています。
3. 問題解決能力と意思決定の迅速化
BF6の戦場では、常に予期せぬ事態が発生します。 敵に囲まれた、味方が倒された、目標が奪われそうだ、など、次々と発生する問題に対し、手持ちのリソース(武器、ガジェット、仲間)でどう対処すべきかを瞬時に判断し、実行に移さなければなりません。 この「現状分析→仮説立案→実行→結果検証」というサイクルを高速で繰り返す経験は、現実世界での問題解決能力や、迅速な意思決定能力を育む上で非常に有効なトレーニングとなり得ます。
| 向上する可能性のある認知能力 | 具体的なゲーム内での行動例 |
|---|---|
| 選択的注意 | 大勢の敵の中から、脅威度の高い敵を優先して狙う |
| 持続的注意 | 試合中、長時間にわたりミニマップや戦況に集中し続ける |
| 空間認識能力 | 2Dのマップを見て、3Dの戦場での最適な移動ルートを判断する |
| ワーキングメモリ | 敵の位置や味方の状況を短期的に記憶し、次の行動に活かす |
| 意思決定速度 | 突如現れた敵に対し、撃つか、隠れるか、逃げるかを0.5秒以内に判断する |
チームプレイで学ぶ協調性とコミュニケーション能力
BF6は、個人技だけでは決して勝てない「チームスポーツ」のような側面を持っています。 この経験を通じて、子供は社会で必要とされる重要なスキルを学ぶことができます。
役割分担と責任感
前述の通り、BF6には明確な「兵科」という役割が存在します。 自分が選んだ兵科の役割を理解し、チームのためにその責任を全うすることが勝利に直結します。 「自分は味方を蘇生する衛生兵だから、むやみに突っ込まず、味方の後ろで待機しよう」といった思考は、集団の中での自分の役割を認識し、責任感を持って行動する訓練になります。
コミュニケーションの重要性
有利な状況を作るためには、「右から敵が来ている!」「戦車を修理してほしい!」「一緒にあの拠点を攻めよう!」といった仲間との情報共有が不可欠です。 自分の考えを的確に伝え、仲間の意図を正確に汲み取るコミュニケーション能力は、ゲームをプレイする中で自然と磨かれていきます。 特に、普段は引っ込み思案な子供でも、ゲームという共通の目的がある場では、積極的にコミュニケーションを取れるようになるケースも少なくありません。
成功体験がもたらす自己肯定感と挑戦する心
学校の勉強やスポーツが苦手でも、ゲームの世界ではヒーローになれることがあります。
小さな成功体験の積み重ね
「初めて敵を倒せた」「難しい目標をクリアできた」「チームの勝利に貢献できた」といった成功体験は、子供に大きな自信と達成感を与えます。 これらの小さな成功体験を積み重ねることで、「やればできる」という自己肯定感が高まり、ゲーム以外の様々なことにも前向きに挑戦する意欲が湧いてくる可能性があります。
失敗から学ぶ力
ゲームでは、数え切れないほどの失敗を経験します。 何度も倒され、何度も敗北します。 しかし、その度に「なぜ負けたんだろう?」「次はどうすれば勝てるだろう?」と考え、試行錯誤を繰り返すことで、プレイヤーは少しずつ上達していきます。 このプロセスは、失敗を恐れずに挑戦し、失敗から学んで次に活かすという、非常に重要な「レジリエンス(精神的な回復力)」を育むことに繋がります。
BF6を子供にプレイさせる前に|家庭で決めるべき7つのルール
ここまでBF6が子供に与える影響について、メリットとデメリットの両面から解説してきました。 結論として、FPSが「絶対的に良い」とも「絶対的に悪い」とも言えません。 最も重要なのは、ゲームという「道具」を、家庭でどのように管理し、付き合っていくかです。 ここでは、お子さんにBF6をプレイさせる前に、親子で話し合って決めておくべき具体的なルールを7つ提案します。
1. プレイ時間を明確に決める(タイマーの活用)
最も基本的で、最も重要なルールです。 「1日1時間まで」「夜9時以降はプレイしない」「宿題やお手伝いが終わってから」など、具体的な時間を決めましょう。 ただ口約束で終わらせるのではなく、キッチンタイマーやスマートフォンのアラーム機能を使い、時間が来たら必ず中断する習慣をつけることが大切です。 ゲーム機本体のペアレンタルコントロール機能で、プレイ時間を強制的に制限することも有効です。
2. CEROレーティングについて親子で話し合う
なぜBF6が「17才以上対象」なのか、その理由を子供自身の言葉で説明させてみましょう。 ゲームに含まれる暴力表現などについて、それが現実世界とは違う「フィクション」であることを親子で確認し、理解を深める良い機会になります。 内容を理解した上で、「我が家ではOK」とするのか、それとも「もう少し大きくなってから」とするのか、家庭の方針を明確にしましょう。
3. ボイスチャットやフレンド申請のルールを設ける
オンラインでのトラブルを防ぐために、コミュニケーションに関するルールは必須です。
- 知らない人とは話さない: フレンド(ゲーム内の友達)以外とはボイスチャットをしない。
- 個人情報は教えない: 本名、学校名、住所、SNSアカウントなどは絶対に教えない。
- 嫌な思いをしたらすぐに相談: 暴言を言われたり、不快なメッセージを受け取ったりしたら、すぐに保護者に相談する約束をする。
- フレンド申請は許可制に: 新しい友達を追加する際は、必ず保護者の許可を得る。
これらのルールを守れるか不安な場合は、前述のペアレンタルコントロール機能で、ボイスチャットやメッセージの送受信自体を制限することを推奨します。
4. ゲームはリビングなど目の届く場所でプレイさせる
子供部屋など、保護者の目の届かない場所でプレイさせるのは避けましょう。 リビングなどの共有スペースでプレイさせることで、子供がどのような表情で、どのような言葉を発しながらプレイしているのかを把握できます。 過度にイライラしていたり、暴言を吐いたりしている様子が見られたら、すぐに声をかけ、クールダウンさせるきっかけを作ることができます。
5. 課金に関するルールを厳格に決める
BF6には、キャラクターの見た目を変えるスキンなど、ゲームプレイを有利にする以外のアイテムを購入できる「ゲーム内課金」の要素が含まれる可能性があります。 子供が無断で高額な課金をしてしまうトラブルは後を絶ちません。
- 課金は許可制: お小遣いの範囲内であっても、課金する際は必ず保護者に相談し、許可を得る。
- 支払い情報は登録しない: ゲーム機のアカウントにクレジットカード情報を登録しない。課金する場合は、必要な分だけプリペイドカードを購入するなど、管理しやすい方法を選ぶ。
6. 親子で一緒にプレイしてみる
もし可能であれば、保護者の方も一度、お子さんと一緒にBF6をプレイしてみることを強くお勧めします。 実際に体験することで、なぜ子供がこのゲームに夢中になるのか、どのような点に難しさや面白さを感じているのかを理解できます。 共通の話題を持つことは、親子のコミュニケーションを深める絶好の機会となり、「ゲームを禁止する親」ではなく、「ゲームを理解してくれる味方」として、子供との信頼関係を築く上で非常に効果的です。
7. ルールを破った時のペナルティを決めておく
ルールを設定するだけでなく、それを破った場合にどうするかを事前に決めておくことも重要です。 「時間を超えたら、次の日はゲーム禁止」「暴言を吐いたら、1週間ボイスチャット禁止」など、具体的で実行可能なペナルティを親子で合意しておきましょう。 感情的に叱るのではなく、決められたルールに基づいて淡々と実行することが、子供にルールを守る重要性を学ばせる上で効果的です。
まとめ
今回は、人気FPS「バトルフィールド6」がお子さんに与える影響について、多角的に掘り下げてきました。
ネット上で囁かれる「FPSは子供に悪影響」という言葉の裏には、脳科学的な根拠やオンライン特有のリスクが確かに存在します。 競争によるストレスやドーパミンによる刺激は、子供の感情を不安定にさせる可能性がありますし、オンラインでの暴言やいじめは深刻な問題です。
しかしその一方で、FPSが注意力や問題解決能力といった認知スキルを向上させ、チームプレイを通じて協調性やコミュニケーション能力を育むという、ポジティブな側面も科学的に示されています。
最終的に、BF6がお子さんにとって「良い薬」になるか「悪い毒」になるかは、ゲームそのものではなく、家庭での関わり方によって決まります。
今回提案した7つのルールを参考に、お子さんと真剣に向き合い、話し合ってみてください。 プレイ時間や課金のルールを決め、オンラインでの危険性から守るための設定を行い、そして何より、お子さんがゲームの世界で何を感じ、何を学んでいるのかに関心を持ってあげることが大切です。
一方的に禁止するのではなく、ゲームを親子のコミュニケーションツールの一つとして捉え、共に楽しみ、共に学ぶ姿勢を持つこと。 それが、これからのデジタル時代における、ゲームとの最も健全な付き合い方なのではないでしょうか。 この記事が、皆様の家庭でのゲームとの向き合い方を考える一助となれば幸いです。