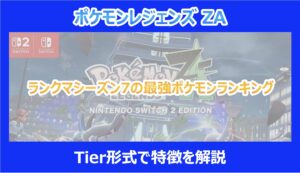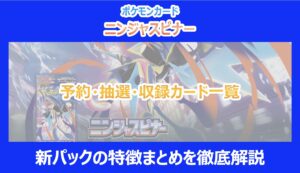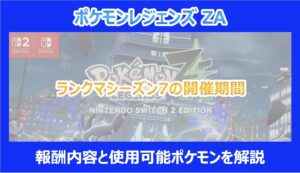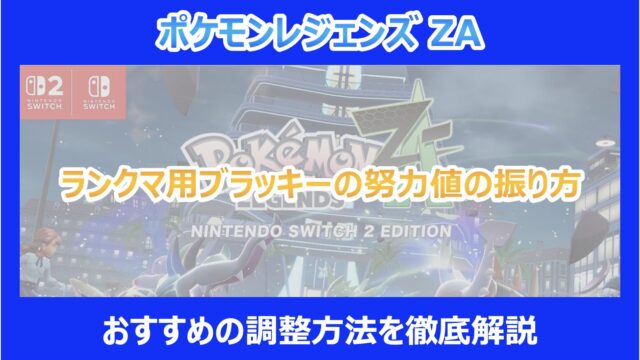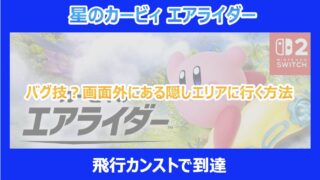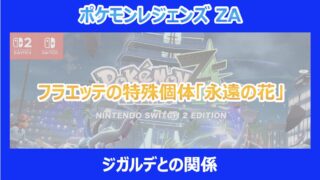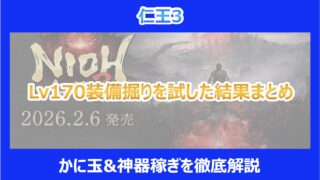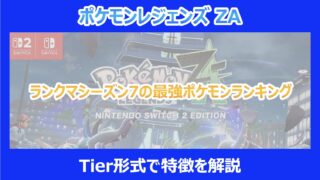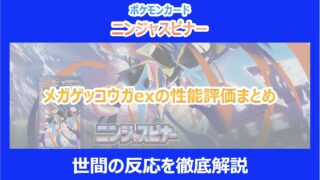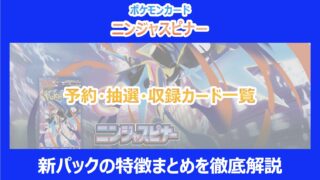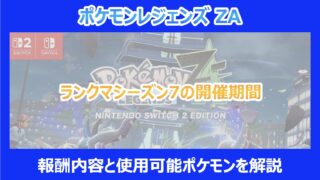ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2026年3月5日に発売が決定したポケモンのスローライフ新作『ぽこあポケモン(Pokoa Pokémon)』の舞台が、まさかの「滅びたカントー地方」ではないか、という噂が気になっていると思います。

特に、公開されたフィールド映像が『ポケットモンスター 赤・緑』に登場した「セキチクシティ」のマップと酷似している、という説は衝撃的です。
この記事を読み終える頃には、『ぽこあポケモン』の舞台に関する謎と、その考察の具体的な根拠についての疑問が解決しているはずです。
- 『ぽこあポケモン』の舞台が「滅びたカントー地方」とされる複数の根拠
- 衝撃のマップ比較で見る「セキチクシティ」との驚異的な一致点
- 薄色ピカチュウや苔むしたカビゴンが示唆する世界の謎
- カントー地方が荒廃した理由と「復興」というゲームテーマの考察
それでは解説していきます。
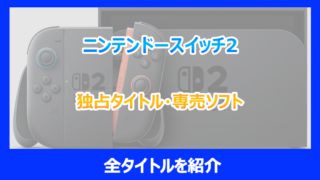
ぽこあポケモンの世界観|「滅びたカントー地方」説が濃厚な理由
2026年3月5日、我々の前に姿を現す『ぽこあポケモン』。 「ポケモンたちと島で暮らすスローライフ」というキャッチコピーとは裏腹に、公開されたトレーラー映像は、どこか切なく、物悲しい雰囲気を漂わせています。

緑は豊かですが、人工物は朽ち果て、文明の痕跡が辛うじて残るのみ。 この「文明が滅びた後の世界」こそが、今回の考察の出発点です。 そして、その滅びた文明が、我々が最もよく知る「カントー地方」である可能性が、各方面から指摘されています。 ゲーム評論家である私の視点から見ても、これらは単なる偶然やこじつけとは思えない、非常に説得力のある根拠に満ちています。 一つずつ、その詳細を解き明かしていきましょう。
根拠1:薄色ピカチュウ(薄チュウ)の謎|ゲームボーイ時代へのオマージュか
まず、最新トレーラーで最も注目を集めたポケモン、通称「薄色ピカチュウ(薄チュウ)」の存在です。
このピカチュウは、通常の個体とは異なり、まるで幽霊のように全体的に色素が薄く、白黒に近い色合いをしています。 尻尾が小さく、耳の形状もどことなく異なり、お嬢様のような特徴的な口調で話すことも確認されています。
この「白黒」という特徴。 これこそが、1996年に発売された初代『ポケットモンスター 赤・緑』が動作したハード、「ゲームボーイ」のモノクロ液晶を表現しているのではないか、という考察です。
さらに興味深いのは、この『赤・緑』を後発の「ゲームボーイカラー」でプレイした時の仕様です。 ゲームボーイカラーで起動すると、白黒だった世界に「ほんのり」と色が付きます。 この時、ピカチュウに割り当てられた配色が、まさに『ぽこあポケモン』の「薄チュウ」の色味と驚くほど似ているのです。
つまり、この薄チュウは、ゲームボーイ時代の白黒の世界、あるいは色づき始めたばかりのあの頃のピカチュウそのもの。 30年近い時を経て、何らかの理由(それこそ幽霊のように)で、我々の前に再び現れた姿なのかもしれません。 「滅びた世界」という舞台設定と、「過去の時代の象徴」としての薄チュウ。 この組み合わせは、本作の根幹に関わる重要なメッセージである可能性が極めて高いと私は分析しています。
根拠2:苔むしたカビゴンの存在|起こされなかった世界のカビゴン
次に、フィールドの奥深く、朽ち果てた遺跡のような場所で眠り続ける「苔むしたカビゴン」です。
カントー地方を冒険したトレーナーなら誰もが知っている通り、『赤・緑』では、カビゴンは特定の道路を塞ぐ形で眠っており、「ポケモンのふえ」を使わなければ起こすことができませんでした。 セキチクシティへ向かう道中や、シオンタウンの近くなど、物語の進行上、必ず遭遇するイベントでした。
しかし、『ぽこあポケモン』で登場するカビゴンは、誰にも起こされることなく、長い、長い時間をそこで過ごしてきたかのように、全身が苔や植物に覆われています。 これは何を意味するのか。
これは、トレーナー(プレイヤー)が存在しなくなった世界。 「ポケモンのふえ」を吹く者がいなくなり、永遠に目覚めることのなかったカビゴンの「if」の姿、つまり「起こされなかった世界線」の象徴なのではないでしょうか。 『赤・緑』の物語が進行しなかった世界。 トレーナーが冒険を「やめてしまった」後の世界。 この苔むしたカビゴンの姿は、「滅びたカントー地方」説を補強する、非常に強力な視覚的証拠と言えます。
根拠3:もんじゃら博士と色褪せたポケモンたち|白黒からの進化
本作の案内役として登場する「もんじゃら博士」。 彼のベースとなっているポケモンは、もちろん「モンジャラ」です。
ここで注目したいのは、彼の「顔回り」だけが白く、まるで『赤・緑』のゲームボーイ時代のドット絵(白黒)のようになっている点です。 一方、博士としての人格が芽生え、進化した(?)部分である触手やその他の部分は、鮮やかな青色(モンジャラの通常色)をしています。

これは、薄チュウの考察とも繋がります。 「白黒=ゲームボーイ時代の過去の姿」であり、「色づいた部分=現代での新たな進化・変化」を象徴しているという仮説です。 『ぽこあポケモン』の世界では、過去(白黒)の存在が、何らかのきっかけで現在(カラー)の姿へと変貌を遂げている、あるいは、過去の記憶を引き継いだまま新しい姿を得ているのかもしれません。
博士のベースが、なぜ数あるポケモンの中から「モンジャラ」なのか。 これについては、後述する「セキチクシティ」との関係で、さらに驚くべき繋がりが見えてきます。
根拠4:博士の服の色|「赤・緑・青・黄」の4色
非常に細かい点ですが、ゲーム評論家としては見逃せないポイントです。 もんじゃら博士が身につけているローブ(あるいは白衣)の色に注目してください。
メインカラーは「赤」と「緑」。 そして、差し色として「青」と「黄色」が使われています。
「赤」「緑」「青」「黄(ピカチュウ)」。 これは、言うまでもなく、カントー地方を舞台にした初代ポケモンの全バージョンを象徴するカラーリングです。 開発者が、この配色に何の意味も込めていないとは到底考えられません。 これは、本作が紛れもなく『赤・緑』、すなわちカントー地方と深い繋がりを持つ作品であるという、開発陣からの明確なサインだと受け取るべきでしょう。
マップ徹底比較|ぽこあポケモンの舞台はセキチクシティで確定か
前述の根拠だけでも、「滅びたカントー地方」説は十分に説得力を持ちます。 しかし、我々初代直撃世代の度肝を抜いたのは、トレーラーで公開されたフィールドマップの「地形」そのものでした。

主人公であるメタモンが、もんじゃら博士と最初に出会うシーン。 そこには、特徴的な「壊れたポケモンセンター」が映し出されます。 一見すると、単なる「荒廃した世界の象徴」としか思えないこの風景。 しかし、このマップを上空から見た配置が、カントー地方の「セキチクシティ」とほぼ完全一致するとしたら…?
この比較は、SNS上で発見されたものですが、私も手持ちの『レッツゴーピカチュウ』(『赤・緑』のリメイク)を起動し、改めてセキチクシティを訪れて比較検証を行いました。 結論から言えば、鳥肌が立つレベルで「一致」しています。
衝撃の比較画像|ポケモンセンターと民家の配置が完全一致
まずは、建物の配置を見てみましょう。
『ぽこあポケモン』のマップ: 中央に「壊れたポケモンセンター(らしき建物)」。 そのすぐ左隣に、「民家(らしき建物)」が2軒、縦に並んでいます。

『赤・緑』および『レッツゴーピカチュウ』のセキチクシティ: マップの中央やや右寄りに「ポケモンセンター」。 そのすぐ左隣に、「民家」が2軒、縦に並んでいます。
この「ポケモンセンター+民家2軒」という特徴的な配置は、カントー地方の他の街には見られない、セキチクシティ固有のものです。 これが偶然である可能性は、限りなくゼロに近いと言わざるを得ません。
地形と道路のディテール|縁石、段差、分岐路まで酷似
驚きは建物の配置だけではありません。 地面のディテールに注目すると、その確信はさらに強まります。
- 道の模様と縁石 『ぽこあポケモン』の地面は、石畳のような模様が描かれています。 『レッツゴーピカチュウ』のセキチクシティの道も、非常によく似た石畳の模様です。 さらに驚くべきは、その「縁取り」の部分。 道の端にある縁石のデザイン、その配置までが酷似しているのです。
- 段差(飛び跳ねる箇所) 『赤・緑』経験者ならお馴染みの、一方通行の「段差」。 『ぽこあポケモン』のトレーラーでは、主人公のメタモンがこのマップの右側(セキチクシティで言えば東側)で、ぴょんと段差を飛び降りるようなモーションを見せます。 セキチクシティのマップを確認すると、まさにその位置(ポケモンセンターの右側)には、南へ向かうための「段差」が存在します。
- 道の分岐 『ぽこあポケモン』のマップの左側(セキチクシティで言えば西側)には、道が二股に分かれる分岐路がはっきりと確認できます。 セキチクシティのマップでも、ポケモンセンターの左側には、北(サファリゾーン方面)と西(19番水道方面)へと向かうための、T字路が存在します。
これらの地形情報の一致は、もはや「オマージュ」や「ファンサービス」といったレベルを超えています。 これは、『ぽこあポケモン』のこのフィールドが、「セキチクシティであった場所」であることを示す、決定的な証拠と私は判断します。
ラプラスの噴水|セキチクシティの水場の痕跡
さらに、マップを詳細に見ると、『ぽこあポケモン』のマップ左側、分岐路の奥に「噴水」のような水場があり、そこにラプラス(らしきポケモン)がいるのが確認できます。
一方、セキチクシティのマップでは、ポケモンセンターの左奥には大きな池(水場)が存在します。 『レッツゴーピカチュウ』では、この水場の近くにラプラスを連れたトレーナーが立っています。
『ぽこあポケモン』の噴水は、このセキチクシティの水場が、長い年月を経て形を変えた「痕跡」なのではないでしょうか。 あるいは、かつてそこにいたラプラスの記憶が、何らかの形で具現化したものかもしれません。
なぜセキチクシティなのか|サファリゾーンともんじゃらの関係
ここで、先ほどの「もんじゃら博士」の謎が繋がってきます。 なぜ、セキチクシティが荒廃した姿で登場するのか。 そして、なぜ案内役が「モンジャラ」なのか。
それは、セキチクシティにかつて存在した施設を思い出せば明らかです。 そう、「サファリゾーン」です。
『赤・緑』において、野生の「モンジャラ」が出現するのは、カントー地方広しといえども、この「サファリゾーン」(と、ハナダの洞窟)のみ。 ※『ピカチュウ』版では21番水道にも出現しますが、サファリゾーンのイメージが強いポケモンであることは間違いありません。
つまり、セキチクシティとモンジャラは、切っても切れない深い関係にあるのです。 もんじゃら博士が、この荒廃したセキチクシティ(らしき場所)で主人公を待っていたのは、彼が元々「サファリゾーンに生息していたモンジャラ」であり、この地の主のような存在だからではないでしょうか。
トレーナーが訪れなくなり、管理されなくなったサファリゾーン。 そこから溢れ出したポケモンたちが、長い年月を経て、朽ち果てたセキチクシティの跡地で独自の生態系を築いている。 『ぽこあポケモン』の物語は、そんな場所から始まるのかもしれません。
ぽこあポケモンとカントー地方|さらなる深掘り考察
「滅びたカントー地方のセキチクシティ」という仮説が、いかに有力であるかをお分かりいただけたかと思います。 しかし、この仮説を前提とすると、さらに多くの疑問と、それに対する興味深い考察が浮かんできます。 ここからは、評論家としての視点を交え、さらに深く『ぽこあポケモン』の謎に迫っていきます。
カントー地方が荒廃した理由|グレンタウンの火山噴火説
まず、最大の謎。 「なぜ、カントー地方は荒廃してしまったのか」
これについては、いくつかの説が考えられますが、地理的な観点から最も有力視されているのが「グレンタウンの火山噴火説」です。
ご存知の通り、セキチクシティの南西、海を隔てた先には、カツラがジムリーダーを務める「グレンタウン(グレンじま)」が存在します。 グレンタウンは活火山のある島であり、『赤・緑』の続編である『金・銀』の時代には、その火山が大噴火を起こし、島全体が壊滅的な被害を受けたことが描かれています。
『ぽこあポケモン』の世界が、『金・銀』の時代よりもさらに未来であると仮定した場合。 あの噴火が一度きりとは限りません。 あるいは、『金・銀』で描かれた以上の、カントー地方全土を巻き込むような超大規模な噴火が、過去に起こったのではないでしょうか。
セキチクシティは、グレンタウンから比較的距離が近い沿岸部の街です。 火山の噴火による火砕流、火山灰、あるいはそれに伴う大津波などによって、文明が崩壊した。 そして、長い年月を経て、火山灰が降り積もった大地に、再び植物が芽吹き、現在の緑豊かな(しかし荒廃した)『ぽこあポケモン』の世界が形成された。
この「火山噴火説」は、荒廃の理由として非常に現実味があり、ポケモンの世界観とも矛盾しない、有力な仮説の一つだと私は考えています。
主人公はなぜメタモンなのか|「長い眠りから目覚めた」の意味
本作の主人公は、人間ではなく「メタモン」です。 これも非常に異例な設定ですが、公式ホームページには「長い眠りから目覚めたメタモン」という記述があります。
このメタモンは、モンスターボールから登場するシーンがトレーラーで描かれています。 これは、元々は「誰かの(=トレーナーの)ポケモンだった」ことを示唆しています。 そして、このメタモンが見つめる先には、壊れた「初代ポケモン図鑑」が…。
壊れた初代ポケモン図鑑とトレーナーの影|30年の時の流れ
トレーラーには、主人公のメタモンが、地面に落ちている「初代ポケモン図鑑」を見つめる印象的なシーンがあります。
図鑑はひび割れ、画面にはかつての持ち主であった「トレーナー」の影(あるいは姿)が一瞬映り込みますが、そのままノイズと共に消えてしまいます。
このトレーナーこそ、今から約30年前(1996年)に、カントー地方を冒険した我々プレイヤー自身なのではないでしょうか。
30年という時の流れ。 我々プレイヤーが成長し、ゲームボーイを置き、カントー地方から「いなくなった」。 誰も遊ばなくなったカントー地方。 人も、ポケモンもいなくなり、文明は(何らかの理由で)崩壊し、荒廃した。
そんな世界で、「ポケモンのふえ」で起こされることのなかったカビゴンは苔むし、サファリゾーンのモンジャラは博士となり、そして、トレーナーのモンスターボールの中で「長い眠り」についていたメタモンが、今、再び目覚めた。
『ぽこあポケモン』の物語は、我々が「置き忘れてきた世界」の、その後の物語なのかもしれません。
コスチュームの秘密|タケシやカスミの姿が示すもの
『ぽこあポケモン』では、主人公のメタモンが様々なコスチューム(変身)を見せてくれます。 その中には、明らかに『赤・緑』の主人公(レッド)や、ハナダシティのジムリーダー「カスミ」、ニビシティのジムリーダー「タケシ」の姿を模したものも確認されています。
なぜ、メタモンは彼らの姿に変身できるのか。 それは、この舞台が「カントー地方」であり、かつてこの地で活躍したトレーナーやジムリーダーたちのことを、メタモンが(あるいは世界そのものが)「記憶」しているからではないでしょうか。
メタモンは、トレーナーとの思い出、カントー地方の記憶を頼りに、彼らの姿に変身する。 それは、失われた人々への追憶であり、世界を「復興」させるための手がかりなのかもしれません。 この変身能力が、ゲームシステムの中核を担う可能性も高いでしょう。
シオンタウンの街灯|冒険はセキチクシティの外へも?
セキチクシティ説を裏付ける証拠は、まだあります。 トレーラーに映る「街灯」のデザイン。 これが、『レッツゴーピカチュウ』で登場する「シオンタウン」の街灯と酷似している、という指摘もあります。
また、薄チュウが眠っていた場所には、紫色の花が咲き乱れています。 「紫」は、言わずと知れたシオンタウンのテーマカラーです。
これは、冒険の舞台が、セキチクシティ(らしき場所)だけに留まらない可能性を示唆しています。 セキチクシティを拠点に、東のシオンタウン方面、あるいは北のカビゴンが眠っていた(であろう)12番道路方面など、荒廃したカントー地方の「別のエリア」へも冒険の足が延びる。 もしそうなれば、本作のスケールは我々の想像を遥かに超えるものになります。
アレンジされたBGM|カントー地方の楽曲が示唆するもの
映像だけでなく、「音」にも注目すべきです。 トレーラーで流れているBGM。 どこか懐かしく、切ないメロディですが、よく聴くと、これは『赤・緑』のカントー地方で流れていた楽曲の「アレンジバージョン」が使われています。
街のBGM、戦闘BGMなど、複数の楽曲のフレーズが、スローライフの雰囲気に合わせて巧みに組み込まれています。 これはもはや「匂わせ」ではなく、答えそのものです。 『ぽこあポケモン』は、音楽の面からも、「カントE地方の物語」であることを強く主張しているのです。
ぽこあポケモンのゲーム性|「復興」というテーマの魅力
これまでの考察で、『ぽこあポケモン』の舞台が「滅びたカントー地方」である可能性が極めて高いことが明らかになりました。 では、そんな物悲しい世界で、我々は何をするのでしょうか。
開発はコーエーテクモゲームス|『ビルダーズ2』との共通点
ここで重要になるのが、本作の開発を担当するのが「コーエーテクモゲームス」(オメガフォース)であるという事実です。
彼らの過去作で、世界的に高い評価を受けた作品に『ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島』があります。 このゲームのテーマが、まさに「破壊」された世界を「復興」させること、そして「モノづくり」でした。
『ぽこあポケモン』のトレーラーでも、主人公のメタモンが、荒廃した土地を整備し、家具を作り、建物を建てていく「クラフト要素」が大々的にフィーチャーされています。 これは、『ビルダーズ2』で培われたノウハウが、ポケモンの世界で遺憾なく発揮されることを期待させます。
スローライフと復興|失われたものを取り戻す物語
『ぽこあポケモン』は、「スローライフ」と銘打たれています。 しかし、それは単にのんびりと暮らすだけではないでしょう。 開発会社の実績と、これまでの考察(荒廃した世界)を鑑みるに、本作の核心にあるのは「復興」というテーマだと私は推測します。
トレーナー(プレイヤー)が去り、荒廃してしまったカントー地方。 長い眠りから目覚めたメタモン(=プレイヤーの新たな分身)が、残されたポケモンたちと共に、失われた文明を、活気を、そして思い出を「復興」させていく。 それこそが、本作『ぽこあポケモン』の真の目的なのではないでしょうか。
<h3>なぜ今、滅びたカントーなのか|初代世代へのメッセージ</h3>
1996年に『赤・緑』でカントー地方を冒険した我々は、今や大人になりました。 『ぽこあポケモン』が発売される2026年は、奇しくも初代発売から「30周年」という節目の年にあたります。
なぜ、このタイミングで「滅びたカントー」なのか。 それは、30年前にあの世界を冒険し、そしていつしか「置き忘れてきた」我々初代世代に対する、任天堂と株式会社ポケモンからの強烈なメッセージではないでしょうか。
「あなたが忘れたあの世界は、今、こうなっています」 「もう一度、戻ってきて、あの場所を復興させてみませんか?」
そう問いかけられているような気がしてなりません。 『ぽこあポケモン』は、単なるスローライフゲームではなく、我々が失った(忘れていた)「時間」そのものを取り戻すための、壮大な物語になる。 ゲーム評論家として、これほどまでに胸が熱くなる設定はありません。
まとめ
今回は、『ぽこあポケモン』の舞台が「滅びたカントー地方」であるという説、特に「セキチクシティ」とのマップ比較について、ゲーム評論家の視点から徹底的に考察しました。
- 薄チュウや苔カビゴン、もんじゃら博士など、登場するポケモンが「カントー地方の過去」を強く示唆していること。
- 壊れたポケモンセンター周辺のマップが、建物の配置、道路の形状、段差、水場に至るまで、『赤・緑』のセキチクシティと驚くほど一致すること。
- セキチクシティと縁の深い「モンジャラ」が案内役であることや、「サファリゾーン」の存在が、この説の信憑性を高めていること。
- 荒廃の理由は「グレンタウンの火山噴火」が有力であり、主人公のメタモンは「30年前にトレーナーが残したポケモン」である可能性が高いこと。
- ゲームのテーマは、開発会社(コーエーテクモ)の実績から見ても、「スローライフ」と「復興」である可能性が極めて高いこと。
『ぽこあポケモン』は、我々が愛した『赤・緑』の世界の「その後」を描く、切なくも壮大な「復興」の物語になる。 私の考察は、そう結論づけています。
もちろん、これらはすべて発売前の「考察」に過ぎません。 しかし、これほどまでに多くの「証拠」が、一つの結論を指し示しているのです。 2026年3月5日。 我々は、かつて冒険したあの懐かしい場所、しかし今は変わり果てた「カントー地方」で、メタモンとして新たな一歩を踏み出すことになるのかもしれません。 発売の日が、今から待ち遠しくてたまりません。