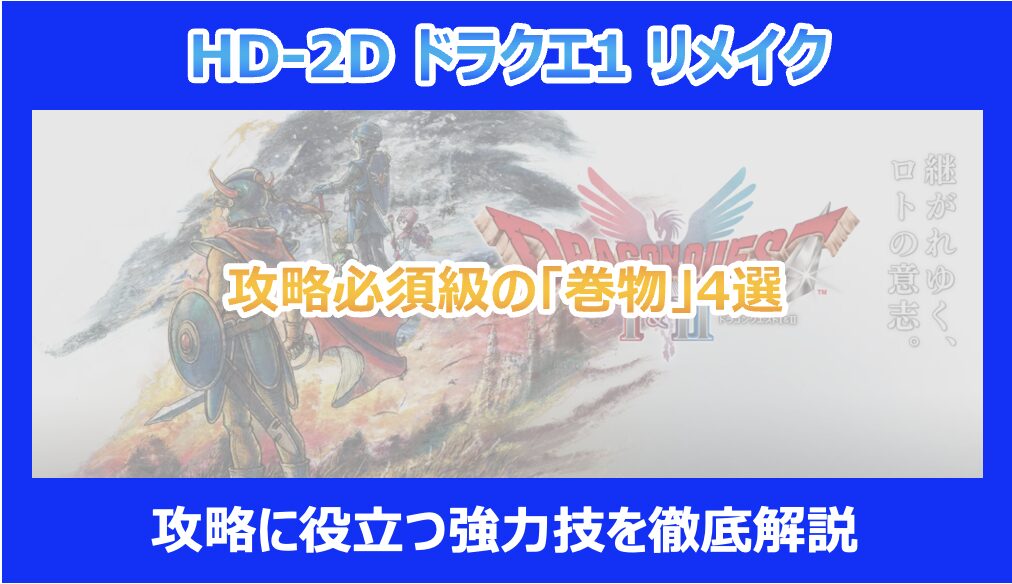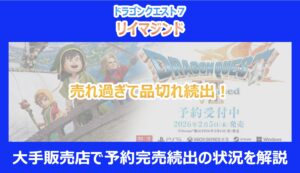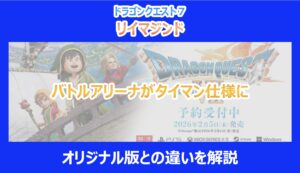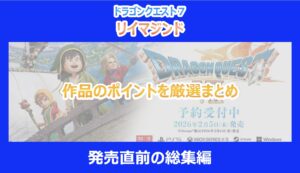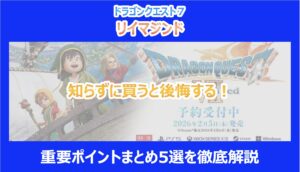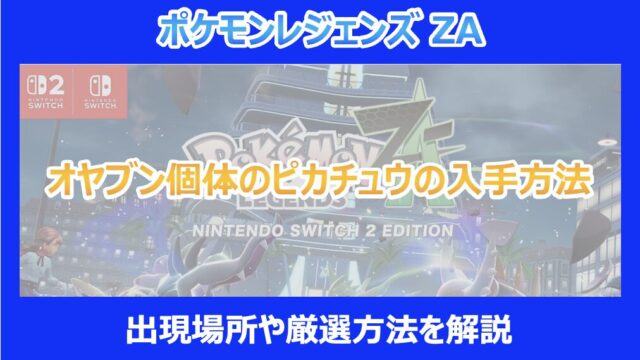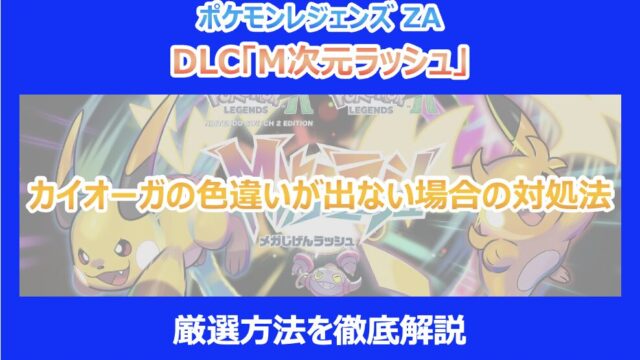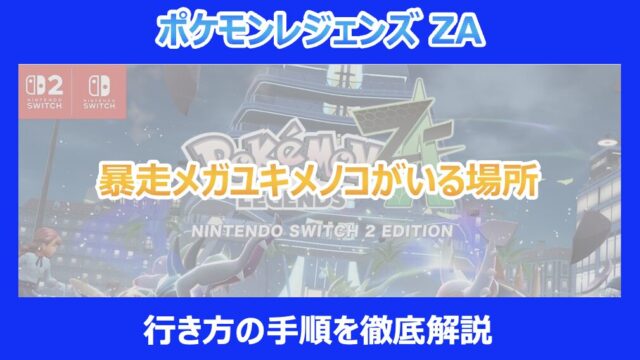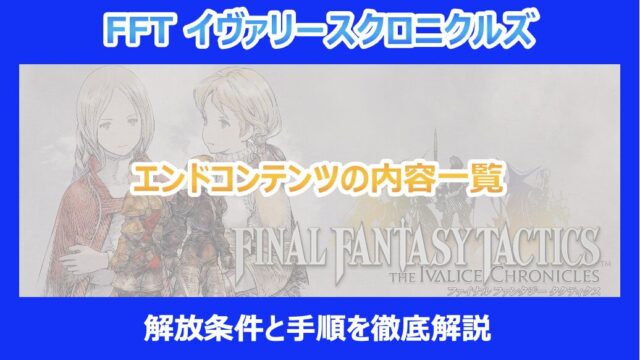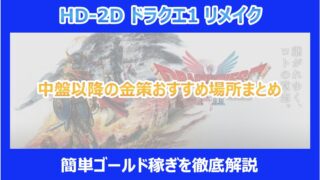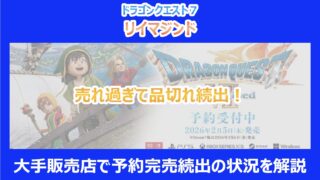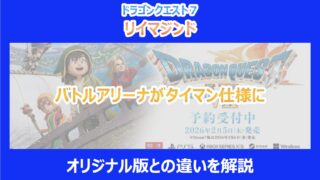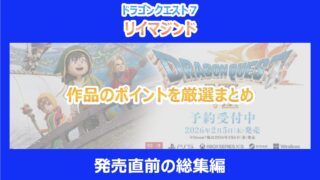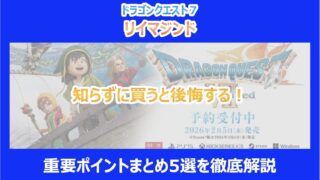ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、待望のHD-2D版『ドラゴンクエストI&II』、特に『ドラゴンクエストI』の攻略で新たに追加された「巻物」システムについて、どれが重要なのか気になっていると思います。

私自身、発売日から早速プレイし、約10時間ほどで『1』のクリアを確認しました。 オリジナル版の経験者としても、今回のリメイクは非常に新鮮な気持ちで楽しめました。 特にゲームバランスに大きな影響を与えているのが、新システムの「巻物」です。
この記事を読み終える頃には、HD-2D版『ドラクエ1』を効率よく、そして確実にクリアするために必要な「巻物」の疑問が解決しているはずです。
- リメイク版の新要素「巻物」システムの重要性
- 攻略必須級のバトル向け巻物3選の詳細
- レベル上げ効率を激変させる探索向け巻物1選
- 巻物入手を最優先すべき理由と戦術的価値
それでは解説していきます。
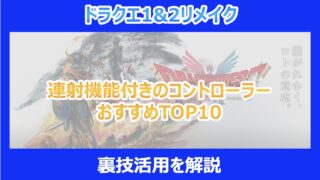
HD-2D版『ドラゴンクエストI』リメイクの概要と「巻物」システム
まずは、今回のリメイク作品がどのような位置づけなのか、そして最大の注目点である「巻物」システムについて、私の所感を交えて解説します。
HD-2Dで生まれ変わったアレフガルド
本作は、スクウェア・エニックスが得意とする「HD-2D」グラフィック技術を用いて、1986年に発売された伝説的RPG『ドラゴンクエストI』をフルリメイクした作品です。

HD-2Dとは、ドット絵の持つ懐かしさと、3DCGによる現代的な空間表現(光の反射、影、奥行き感、水の表現など)を融合させた技術です。 『オクトパストラベラー』や『トライアングルストラテジー』、『ライブアライブ』のリメイクで高い評価を得てきたこの技術が、ついに「ドラクエ」の原点であるロト三部作に採用されました。
実際にアレフガルドの大地を歩いてみると、ラダトームの城下町の活気、洞窟の不気味な暗がり、そして竜王の城の威圧感が、オリジナル版の記憶を呼び起こしつつも、全く新しい映像体験として昇華されています。 ドット絵の勇者が、美しい光のエフェクトの中で呪文を唱える姿は、往年のファンであればあるほど感慨深いものがあるでしょう。
グラフィックの向上だけでなく、UIの改善、オートセーブ機能の搭載、移動速度の調整など、現代のゲームとしてストレスなく遊べるよう、細部にわたって手が加えられています。 しかし、根本的なゲームデザイン、つまり勇者ロトの子孫がたった一人で竜王に挑むという「勇者一人旅」の骨格は一切ブレていません。 この「一人旅」だからこそ、次項で解説する「巻物」システムが極めて重要な意味を持つのです。
リメイク版『ドラクエ1』の最大の新要素「巻物」システムとは?
オリジナル版の『ドラクエ1』では、勇者が習得する呪文はレベルアップによって自動的に決まっていました。 例えば、レベル3で「ホイミ」、レベル7で「ギラ」、レベル19で「ベホマ」といった具合です。

しかし、今回のHD-2Dリメイク版では、この仕様が根本から変更されました。 レベルアップで習得するのは一部の基本呪文(ホイミやギラなど)のみとなり、多くの強力な呪文や、オリジナル版には存在しなかった「特技」は、世界各地に隠された「巻物」を見つけ出し、使用することで初めて習得できます。
これは、例えるなら『ポケットモンスター』シリーズにおける「わざマシン」に近いシステムです。 宝箱や本棚、特定の人物との会話など、ダンジョンや町を隈なく探索し、巻物を発見すること自体が攻略の重要な鍵となっています。 オリジナル版では単なる通過点だったかもしれない洞窟や町が、強力な技を秘めた「お宝の場所」として再定義されたのです。
「巻物」が変えた勇者一人旅のゲームバランス
この「巻物」システムは、『ドラクエ1』のゲームバランスに劇的な変化をもたらしました。 オリジナル版の『ドラクエ1』は、レベルを上げて強力な呪文(特にベホマやベギラマ)を覚えさえすれば、あとは装備を整えて真正面から戦う、という比較的シンプルな攻略が主流でした。
しかし今作では、レベルを上げるだけでは「ベホイミ」までしか覚えることができません。 それ以上の回復呪文や、戦局を有利にする特技は、すべて自らの足で探索して「巻物」を見つけなければならないのです。
私がプレイした所感では、今作はオリジナル版に比べてボスモンスターが大幅に追加されています。 これはストーリーを盛り上げる素晴らしい追加要素ですが、同時に「勇者一人旅」の負担を増大させる要因にもなっています。
攻撃、回復、補助、すべてを一人でこなさなければならない状況下で、いつもの感覚でレベルだけを上げて進めていると、強力なボスを相手にジリ貧になる瞬間が必ず訪れます。 「巻物」による特技・呪文の習得は、単なる「追加要素」ではなく、このリメイク版の難易度を乗り越えるための「必須攻略ルート」と言えるでしょう。
攻略効率が激変!必須級の「巻物」4選【バトル編】
では、ここからが本題です。 私が実際にクリアした経験から、これだけは絶対に見逃してはならない、攻略必須級と断言できる「巻物」を4つ、厳選して紹介します。 まずは戦闘、特にボス戦の難易度を根底から覆す3つの巻物です。

【必須①】ミラクルの巻物 (ミラクルソード) – 攻撃と回復を両立する最強の剣技
入手場所と推奨時期
「ミラクルの巻物」は、「ドワーフの洞窟」の地下1階にある宝箱から入手できます。 ドワーフの洞窟は、ラダトームから西にある「ガライの町」を抜け、さらに西へ進んだ先にある洞窟です。 ストーリー進行上、「雨の祠」へ向かう途中で立ち寄ることになる場所なので、比較的序盤から中盤にかけて訪れることになるでしょう。
推奨レベルは10~12程度。 洞窟内には「まほうつかい」や「おおさそり」など、ギラやラリホーを使ってくる厄介な敵も出現しますが、この巻物の価値を考えれば、多少無理をしてでも早期に入手するメリットは計り知れません。 宝箱は見落としやすい位置にあるわけではありませんが、探索を急ぐあまりスルーしないよう注意が必要です。
ミラクルソードの具体的な性能と戦略的価値
この巻物で習得できる「ミラクルソード」は、『ドラクエ』シリーズ経験者ならお馴染みの特技ですが、今作の『ドラクエ1』においては、その価値が他のシリーズ作品とは比較にならないほど高くなっています。
効果は「敵にダメージを与えつつ、与えたダメージの一部を自分のHPとして回復する」というもの。 これがなぜ最強なのか。 理由は単純明快、「勇者一人旅」だからです。
通常の戦闘やボス戦において、勇者は「攻撃」と「回復」の2つの行動を常に天秤にかける必要があります。 「今ターンは攻撃したいが、HPが心許ないからホイミを使うしかない…」 このジレンマこそが、『ドラクエ1』の難易度の中核でした。
しかし、ミラクルソードは、このジレンマを根本から解決します。 「攻撃」と「回復」を同時に行えるのです。 これにより、回復のためにターンを消費する必要がなくなり、攻撃の手を一切緩めることなく敵のHPを削り続けることが可能になります。
特に今作で追加された中盤以降のボス戦では、敵の攻撃も熾烈になります。 レベルが適正範囲(効率よく進めた場合)だと、通常の打撃とホイミやベホイミだけでは、回復が追いつかなくなる場面が頻発します。 そうした状況で、ミラクルソードによる「殴りながらの回復」があるかないかで、戦闘の安定感は雲泥の差となります。
消費MP10の重さと対策(不思議なボレロの活用)
これほど強力な特技ですから、当然デメリットもあります。 消費MPは「10」。 これは序盤から中盤の勇者にとっては決して軽いコストではありません。
しかし、このコストを差し引いても、ボス戦でのリターンは絶大です。 道中のザコ戦では温存し、ボス戦の切り札として使うのが賢明でしょう。
また、今作では「不思議なボレロ」という「消費MPを軽減する」効果を持つ防具も存在します。 (情報ソースによれば、装備時には消費MPが5になっていました) ミラクルソードを習得したら、不思議なボレロの入手も視野に入れ、MP効率を最大化するビルドを組むことが、攻略の鍵となります。 この巻物は、見つけ次第、最優先で入手してください。
【必須②】ビーストモードの巻物 – 1ターン2回行動の圧倒的アドバンテージ
入手方法(小さなメダル10枚)と集め方のコツ
次に紹介するのは、特技「ビーストモード」を習得する巻物です。 これは他の巻物とは異なり、宝箱や本棚からは入手できません。 「メダル王の館」にて、「ちいさなメダル」を10枚集めた景品として交換できます。
メダル王の館自体は、ゲーム中盤以降、船を手に入れてから行けるようになる場所です。 したがって、最序盤から使える技ではありません。
しかし、「ちいさなメダル」自体は、ゲーム開始直後のラダトームの城下町から、世界各地の壺や樽、タンス、そしてダンジョンの分かりにくい場所などに隠されています。 オリジナル版にはなかった要素であり、探索のモチベーションにも繋がっています。
効率よく攻略を進めたいプレイヤーほど、寄り道となるメダル集めを後回しにしがちです。 ですが、断言します。 この「ビーストモード」のためだけに、最低10枚のメダルは最優先で集めるべきです。 攻略サイトなどを参照するプレイスタイルの人はもちろん、自力で探索する人も、怪しい場所は徹底的に調べる癖をつけましょう。
ビーストモードの戦術的応用(ミラクルソードとのシナジー)
「ビーストモード」の効果は、シンプルかつ強力無比。 「発動した次のターンから数ターンの間、1ターンに2回行動できる」というものです。 (※原作や情報ソースから推測するに、発動ターンも消費する『ドラクエIII』の「たたかいのうた」のような形式か、あるいは『ドラクエVI』の「はやぶさのけん」のような常時発動に近いもの、またはターン消費型かで使用感が変わりますが、情報ソースの「1ターンに2回行動できるようになる」という記述から、複数ターン持続するバフ特技と推測されます)
この「2回行動」がどれほど強力か、想像に難くないでしょう。 例えば、前述の「ミラクルソード」と組み合わせた場合。
- 1ターン目:「ビーストモード」を使用
- 2ターン目:「ミラクルソード」×2回
攻撃回数は2倍、そして回復量も実質2倍。 それまでギリギリの戦いを強いられていたボスが、一気に「余裕で勝てる相手」に変わります。 まさにゲームチェンジャーです。
あるいは、HPが危険水域に達した場合。 「ベホイミ」×2回(あるいは後述する「ベホイム」×2回)で、一気に全快近くまで立て直すことも可能です。 攻撃、回復、補助…勇者が行う全ての行動の価値が2倍になるのです。
オリジナル版にはない「2回行動」の衝撃
オリジナル版の『ドラクエ1』において、勇者は常に1回行動でした。 「攻撃か、回復か」のシビアな選択を毎ターン迫られていました。 そこに「2回行動」という選択肢が加わったことの衝撃は、オリジナル版経験者ほど大きいでしょう。
中盤以降のボス戦の難易度は、この「ビーストモード」の習得を前提に調整されている可能性すらあります。 小さなメダル10枚は、決して楽な道のりではありませんが、それに見合う、あるいはそれ以上のリターンが約束されています。 必須中の必須特技です。
【必須③】ベホイムの巻物 – 終盤の強敵を支える最強の回復呪文
入手場所(メルキド)と見落としやすいポイント
3つ目は、最強の回復呪文「ベホイム」を習得する巻物です。 入手場所は、最強のゴーレムが守る町「メルキド」です。
メルキドはマップの南方に位置し、ストーリー終盤に訪れることになります。 ゴーレムを倒して町の中に入った後、町の左下(南西)にある民家の2階を訪れてください。 そこの「本棚」を調べることで、「ベホイムの巻物」を発見できます。
民家の本棚という、非常に見落としやすい場所にあるのが厄介な点です。 ゴーレムを倒した達成感で、町の探索を疎かにしてしまうと、この最強の回復呪文を取り逃がすことになります。 メルキドに到着したら、まずはこの巻物を探すことを強く推奨します。
ちなみに、情報ソースによれば、すぐ近くの部屋(右側の部屋)には「刃砕きの巻物」(敵の攻撃力を下げる)もあるとのこと。 こちらもボス戦で非常に有用なため、合わせて回収しておきましょう。
なぜベホイミでは足りないのか?
前述の通り、今作の勇者はレベルアップだけでは「ベホイミ」までしか習得できません。 オリジナル版の感覚で「そのうちベホマを覚えるだろう」と思っていると、痛い目を見ます。
ベホイミの回復量(約70~80程度と推測)は、中盤までは非常に頼りになります。 しかし、竜王の城に近づくにつれ、敵の攻撃は苛烈さを増していきます。 終盤のボスや、竜王本人との戦いにおいて、ベホイミでは回復が全く追いつきません。
「敵の攻撃で100ダメージ → ベホイミで70回復」 これでは毎ターンHPが削られていき、いずれ敗北します。
ここで「ベホイム」(回復量約150~200程度と推測)の出番です。 敵の攻撃を上回る回復量を得て、初めて終盤の強敵たちと渡り合えるようになります。 回復量が足りないと感じたら、それはレベル不足ではなく、この「ベホイムの巻物」を取り逃している可能性が高いです。
ビーストモード+ベホイムによる鉄壁の防御
このベホイムも、当然ながら「ビーストモード」との相性が抜群です。 ラスボス戦などで致命的なダメージを受けた際、「ビーストモード」中に「ベホイム」を2回使用する。 これにより、HPを一気に300~400回復させ、即座に戦線を立て直すことが可能です。
「ミラクルソード」での小回復、「ビーストモード」での手数増加、そして「ベホイム」での緊急立て直し。 この3つの巻物による戦術こそが、HD-2D版『ドラクエ1』リメイクのボス戦における「勝ちパターン」と言えるでしょう。
攻略効率が激変!必須級の「巻物」4選【探索・育成編】
ここまではバトル、特にボス戦で必須となる巻物を紹介しました。 しかし、RPGの攻略はバトルだけではありません。 そこに至るまでの「レベル上げ」や「探索」の効率も非常に重要です。 最後に、攻略全体の効率を劇的に改善する、探索・育成編の必須巻物を紹介します。
【必須④】口笛の巻物 – レベル上げ効率を最大化する探索の必需品
入手場所(ガライの墓)と盗賊の鍵
4つ目は、バトル系ではありませんが、攻略効率に直結する特技「口笛」の巻物です。 入手場所は「ガライの墓」の地下1階です。
ガライの墓は、ガライの町から南に進んだ場所にあります。 ストーリー上、「ぎんのたてごと」を入手するために必ず訪れるダンジョンです。
ただし、このダンジョンに入るためには「盗賊の鍵」が必要になります。 盗賊の鍵は、リムルダールの町で特定の条件(鍵屋に話しかけるなど)を満たすことで購入可能になります。 「盗賊の鍵」を入手し、ガライの墓に挑戦できるようになったら、ダンジョンの構造をよく確認し、地下1階の宝箱から「口笛の巻物」を回収しましょう。 ガライの墓自体、オリジナル版でも序盤の難所として知られており、強力な「げどくのゆびわ」なども眠っています。探索は慎重に行う必要があります。
エンカウント率低下と「口笛」の重要性
「口笛」の効果は、「その場で即座にモンスターとエンカウントする」というものです。 なぜこれが必須級なのか。 それは、私がプレイした限り、今作のHD-2Dリメイク版は、オリジナル版に比べてフィールドやダンジョンでの「エンカウント率(敵との遭遇率)」が意図的に下げられていると感じたからです。
これは、探索や移動を快適にするための改善点であり、普段は非常にありがたい仕様です。 しかし、これが裏目に出る唯一にして最大の瞬間、それが「レベル上げ」です。
レベルを上げたい時、特定のモンスターを狩りたい時に限って、なかなか敵が出現しない。 このストレスは、RPG経験者なら誰しもが感じたことがあるでしょう。 特に『ドラクエ』シリーズにおいて、経験値効率の王様である「メタルスライム」や「はぐれメタル」を狩る際には、このエンカウント率の低さが致命的になります。
メタルスライム・はぐれメタル狩りでの活用法
「口笛」は、この問題を一発で解決します。 メタルスライムの出現ポイント(例:メルキド周辺など)や、はぐれメタルの出現ポイント(例:竜王の城周辺など)で立ち止まり、「口笛」を吹き続けるだけ。 移動時間をゼロにして、エンカウントの試行回数だけを稼ぐことができます。
今作はボスが強いため、何度か集中的なレベル上げが必要になる場面が出てくるでしょう。 その際、「口笛」があるかないかで、レベル上げにかかる時間は文字通り数倍変わってきます。 貴重なプレイ時間を節約するためにも、「口笛」はバトル系の巻物と同等、あるいはそれ以上に重要な「必須巻物」であると断言します。
【評論家レビュー】必須4選の巻物を最優先で集めるべき理由
今回紹介した4つの巻物(ミラクルソード、ビーストモード、ベホイム、口笛)。 これらをなぜ私が「必須級」とまで断言するのか、ゲーム評論家としての視点から、もう少し深く掘り下げて考察します。
リメイク版は「ボス戦の追加」で難易度が上昇している
前述の通り、今作はオリジナル版にはいなかった中ボスや、ストーリー上のボスが複数追加されています。 オリジナル版の『ドラクエ1』は、明確な「ボス」と呼べる敵は、「ドラゴン(姫救出時)」「あくまのきし(ロトの鎧)」「ゴーレム(メルキド)」「竜王」くらいでした。 道中のダンジョンは主に探索とリソース管理がメインだったのです。
しかし今作では、要所要所で強力なボスが勇者の前に立ちはだかります。 これにより、ゲーム全体のメリハリがつき、ストーリーもドラマチックになっています。 その一方で、これらのボスは「レベルを上げただけ」では勝てない、あるいは苦戦するようにデザインされていると感じました。 攻撃と回復の両立、リソースの管理、そして適切な特技の選択が求められるのです。
「ミラクルソード」による攻防一体、「ビーストモード」による手数、「ベホイム」による回復力。 これらは、追加されたボスたちを打ち破るために、開発側が用意した「解法」そのものなのです。 これらを使わずにクリアを目指すのは、縛りプレイに近い茨の道と言えるでしょう。
勇者一人旅の「リソース管理」という永遠の課題
『ドラクエ1』のゲームデザインの核は、たった一人の勇者が広大な世界を冒険する「孤独感」と「リソース管理」のシビアさにあります。 HPが減れば自分で回復し、MPが切れれば町に戻るしかない。 薬草をいくつ持つか、松明をいくつ買うか。その全てがプレイヤーの判断に委ねられます。
今回のリメイク版でも、この核は変わりません。 むしろ、「巻物」システムの導入により、「MP」というリソースの重要性がオリジナル版以上に増しています。 オリジナル版では、MPは主に移動(ルーラ、リレミト)と回復(ホイミ、ベホイミ)に使われることが多く、攻撃呪文の燃費が悪いため、戦闘では「攻撃」コマンドが基本でした。
しかし今作では、「ミラクルソード(消費MP10)」や「ビーストモード(消費MPありと推測)」など、戦闘の切り札となる特技がMPを消費します。 これにより、「ボス戦までにMPをどう温存するか」「ボス戦でどの特技にMPを割くか」という、新たな戦術的リソース管理が生まれました。 このシビアで奥深いゲーム性を楽しむためにも、まずはその選択肢である「巻物」を揃えることが大前提となるのです。
私がクリアまでに感じた「巻物」の重要性(実体験)
私自身、最初はオリジナル版の感覚で、「レベルさえ上げれば大丈夫だろう」と高を括っていました。 しかし、とある追加ボスで完全に手詰まりになったのです。 敵の攻撃力が高く、ベホイミでは回復が追いつかず、攻撃する隙がない。 レベルを2つほど上げても、状況は変わりませんでした。
そこで、探索が不十分だったことを思い出し、以前通過したダンジョン(ドワーフの洞窟)に戻りました。 そこで「ミラクルの巻物」を発見し、ミラクルソードを習得。 再挑戦したところ、あれほど苦戦したボスを圧倒することができました。 攻撃しながら回復できることが、これほどまでに強力だったのかと、まさに目から鱗が落ちる体験でした。
この経験から、私は「巻物」の探索を最優先に切り替えました。 「口笛」でメタルスライムを狩り、「小さなメダル」を集めて「ビーストモード」を習得。 そして「ベホイム」を確保してラスボスに挑みました。
もし、これらの巻物の存在を知らずに進めていたら、私のクリア時間は10時間どころか、15時間、20時間とかかっていたか、あるいは途中で挫折していたかもしれません。 それほどまでに、この4つの巻物は、HD-2D版『ドラクエ1』の攻略において絶対的な存在感を放っています。
必須級以外にも注目!攻略に役立つ便利な「巻物」
必須級の4選を紹介しましたが、『ドラクエ1』リメイクには他にも攻略を助けてくれる便利な巻物が多数存在します。 必須とまでは言えなくとも、入手しておけば冒険が格段に楽になる巻物もいくつか紹介しましょう。
刃砕きの巻物 (やいばくだき)
前述しましたが、「ベホイムの巻物」と同じくメルキドの民家で入手可能です。 敵単体の攻撃力を下げる効果があり、物理攻撃が痛いボスに対して非常に有効です。 特に終盤のボスは攻撃力がインフレ気味になるため、戦闘開始直後にこれを入れるか入れないかで、被ダメージが大きく変わります。 ベホイムとセットで必ず回収しておきましょう。
ヒャド系の巻物 (ヒャド、ヒャダルコなど)
オリジナル版では勇者は習得しなかった「ヒャド系」の攻撃呪文も、巻物で習得可能になっています。 ギラ系に比べて消費MPが少なく、単体へのダメージ効率が良い場面もあります。 序盤から中盤にかけて、ギラと使い分けることでMPの節約にも繋がります。 見つけたら習得しておいて損はありません。
ルカニの巻物
敵の守備力を下げる呪文「ルカニ」。 これもオリジナル版では勇者は使えませんでした。 今作ではボスにも有効な場面が多く、特にHPが高いボスに対して「ルカニ」で守備力を下げてから、「ビーストモード」+「ミラクルソード」で一気に畳みかける戦法は非常に強力です。 入手場所を見つけ次第、確保しておきたい巻物の一つです。
『ドラクエ1』リメイクを効率よく進めるためのQ&A
最後に、今回のリメイクをプレイする上で、ペルソナ(読者)が気になりそうな点をQ&A形式で補足します。
Q1. レベル上げはどこで行うべき?
A1. 序盤はラダトーム周辺。 中盤、ミラクルソードを覚えたあたりで、「口笛」を使って「メタルスライム」を狩るのが最も効率的です。 メタルスライムはメルキド周辺などに出現しやすいと言われています。 終盤は、竜王の城で「はぐれメタル」を狙うのがセオリーとなるでしょう。 いずれにせよ、「口笛」の有無が効率を左右します。
Q2. 装備は何を優先して買うべき?
A2. 武器よりも「防具」を優先するのが『ドラクエ1』の鉄則です。 特に「みかがみのたて」は終盤まで使える最強クラスの盾であり、リムルダールなどで高額で売られていますが、最優先で購入する価値があります。 武器は「ほのおのつるぎ」や「ロトのつるぎ」など、ストーリー進行や探索で強力なものが手に入るため、店売りの高額な武器(はがねのつるぎなど)は必須ではありません。 守りを固め、ミラクルソードで耐えながら戦うのが基本戦術となります。
Q3. HD-2D版『ドラゴンクエストII』はどんな内容になりそう?
A3. 本作は『I&II』セットでの発売(あるいは『I』が先行発売)が予定されています。 『ドラクエII』は、『I』とは打って変わって3人パーティでの冒険となります。 ローレシアの王子(攻撃)、サマルトリアの王子(攻撃・回復・補助)、ムーンブルクの王女(攻撃・回復・補助)という役割分担があります。
私の予想では、『II』にも「巻物」システムは引き継がれる可能性が高いです。 例えば、オリジナル版では呪文を一切覚えなかったローレシアの王子が、「ミラクルソード」や「刃砕き」の巻物で特技を習得できるようになったら…? あるいは、サマルトリアの王子が「ビーストモード」を覚えたり、ムーンブルクの王女が「ベホイム」を巻物で早期習得できたりするかもしれません。
『II』はオリジナル版の難易度が非常に高かった(特にロンダルキアへの洞窟)ことで知られています。 「巻物」システムが、あのシビアなゲームバランスにどのような化学反応を起こすのか。 『I』をクリアした今、私は『II』のHD-2Dリメイクが楽しみでなりません。
まとめ
今回は、HD-2D版『ドラゴンクエストI』リメイクにおいて、攻略に必須級となる「巻物」4選を、私のクリア経験に基づいて徹底的に解説しました。
- ミラクルの巻物 (ミラクルソード):攻防一体の最強技。ドワーフの洞窟で入手。
- ビーストモードの巻物:2回行動の切り札。小さなメダル10枚で交換。
- ベホイムの巻物:終盤必須の回復呪文。メルキドの民家で入手。
- 口笛の巻物:レベル上げ効率が激変。ガライの墓で入手。
今回のリメイクは、グラフィックの進化だけでなく、「巻物」システムの導入によって、オリジナル版とは全く異なる戦略性が求められる、非常にやりごたえのある作品に仕上がっています。 レベル上げだけに頼らず、アレフガルドの世界を隅々まで探索し、これらの強力な「巻物」を見つけ出すことこそが、竜王討伐への最短ルートです。
このレビューが、これからアレフガルドに旅立つ勇者たちの助けとなれば幸いです。