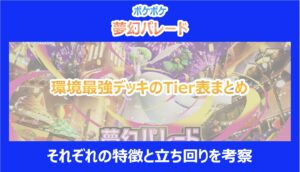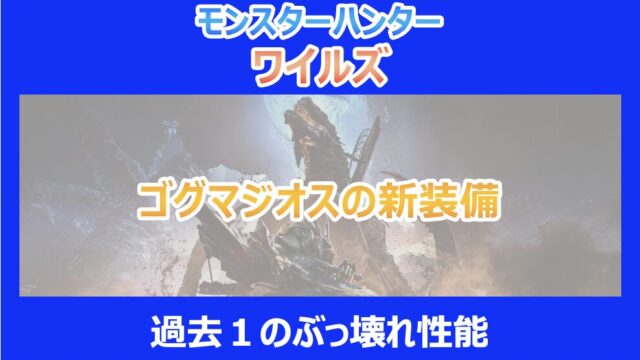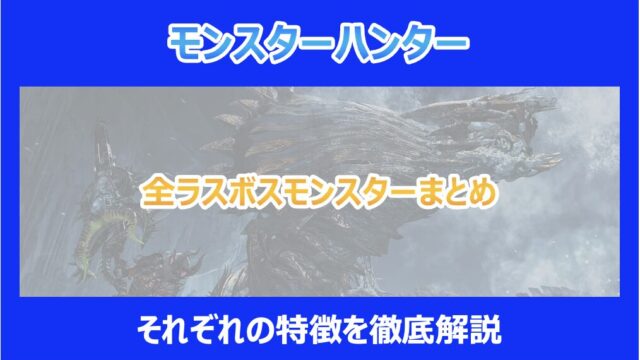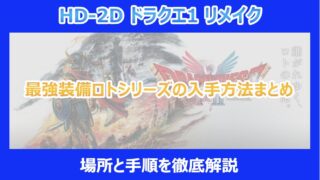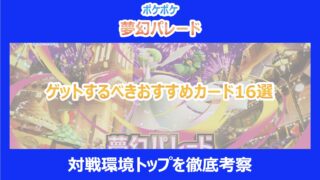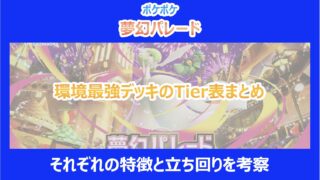ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年に発売が予定されているHD-2D版『ドラゴンクエストI&II』、特にシリーズの原点である『ドラゴンクエストI』を初めてプレイするにあたり、何に気を付ければいいか気になっていると思います。

『ドラゴンクエストI』は、日本のRPGの礎を築いた偉大な作品ですが、そのシステムは現代のRPGとは大きく異なる部分も多く、独特の「お作法」を知らないと苦戦は必至です。
この記事を読み終える頃には、HD-2D版『ドラゴンクエストI』リメイクで初心者が押さえるべきポイントと、冒険をスムーズに進めるための知識がすべて解決しているはずです。
- HD-2D版DQ1で初心者が知るべきこと
- 原作DQ1の独自システムと注意点
- 序盤を効率的に進めるためのコツ
- HD-2D版DQ1&2への期待と考察
それでは解説していきます。
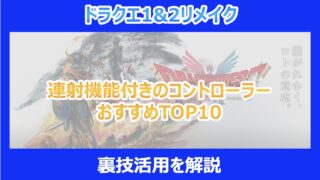
HD-2D版『ドラゴンクエストI』初心者が気を付けるべきポイント8選
HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』の発売が2025年に決定し、多くのゲームファンがロト伝説の始まりに期待を寄せています。 特に『ドラゴンクエストI』は、全ての冒険の原点であり、そのシンプルながらも奥深いゲーム性は、HD-2Dという最新のグラフィック表現でどのように蘇るのか、私自身も非常に楽しみにしています。

しかし、『DQ1』は1986年にファミリーコンピュータで発売された作品がベースです。 それゆえに、現代のRPGに慣れたプレイヤー、あるいは本作で初めて『DQ1』に触れるプレイヤーにとっては、「常識」が通用しない場面が多々あります。
ここでは、ゲーム評論家である私が、過去のシリーズ作品(FC版、SFC版など)の経験を踏まえ、HD-2D版リメイクをプレイする上で初心者が特に気を付けるべきポイントを8つに厳選して徹底解説します。
1. 主人公の名前は慎重に
まず最初のポイントは、冒険の始まりである主人公の名前入力です。 結論から言うと、主人公の名前は一度決めたら二度と変更できません。

「そんなの当たり前だ」と思うかもしれませんが、原作のFC版『DQ1』では、ゲームの再開は「ふっかつのじゅもん」というパスワード方式でした。 この「じゅもん」は、レベルや所持アイテムなどの状態を文字列に変換したもので、書き間違えればデータが消えるという緊張感がありました。 (当時の子供たちは、濁点や半濁点を見間違えて泣いたものです)
しかし、HD-2D版では、先に発売される『DQ3』と同様に、間違いなく**「冒険の書」(セーブデータ方式)**が採用されます。 これにより、「ふっかつのじゅもん」の煩わしさからは解放されます。
その代わり、一度作成した「冒険の書」の名前は、ゲーム内で変更する手段はおそらく提供されません。 『DQ1』は、プレイヤー=主人公の没入感が非常に高いゲームです。 その勇者の名前は、あなたの分身としてアレフガルドの世界で語り継がれます。 後で後悔しないよう、最初の名前入力は慎重に行いましょう。
HD-2D版でのセーブ仕様予想
HD-2D版『DQ3』では「オートセーブ」や「中断セーブ」機能が搭載されることが発表されています。 『DQ1&2』もこれに準拠する可能性が極めて高いです。 原作ではセーブ(王様に進捗を報告)できる場所がラダトーム城の王様の前だけだったので、ダンジョンの奥深くで力尽きると、前回セーブした城からやり直しでした。 オートセーブが導入されれば、ダンジョン内やフィールドでも直前の状態から復帰できる可能性があり、難易度は大幅に遊びやすくなると予想されます。 とはいえ、油断は禁物。手動セーブの癖もつけておくと万全です。
2. 戦闘は「1対1」が基本(集団戦の常識を捨てよ)
現代のRPG、いや、『ドラゴンクエストII』以降のシリーズ作品に慣れている人ほど戸惑うのが、このポイントです。 原作の『ドラゴンクエストI』の戦闘は、敵も味方も1体ずつ、完全な「1対1」のタイマンバトルです。
スライムが3匹現れたり、おおがらすの群れに襲われたりすることはありません。 必ず、敵1体が出現し、それを主人公が1人で倒す。 これを繰り返して進んでいきます。
この仕様がHD-2D版で変更されるか(例えば『DQ3』のようにパーティバトルになったり、敵が複数出現するようになるか)は、現時点では不明です。 しかし、もし原作のゲームバランスを尊重するのであれば、この「1対1」の形式は維持される可能性が高いと私は考えています。
この「1対1」の仕様は、戦闘の戦略に大きな影響を与えます。 複数の敵を一度に攻撃する呪文(イオナズンなど)や特技は存在しません。 (※SFC版リメイクでは敵が複数出現するようになりました。HD-2D版がSFC版準拠であれば、この限りではありません。しかし、もしFC版の緊張感を再現するなら1対1の可能性も残されています)
HD-2D版がSFC版(複数敵)準拠だった場合の注意点
もし、SFC版リメイクのように敵が複数出現する仕様だった場合、話は変わってきます。 主人公が覚える呪文「ギラ」は、原作(FC版)では敵1体への攻撃でしたが、SFC版では敵グループへの攻撃に変更されました。 複数の敵が出現する場合、「ギラ」や後述する「ベギラマ」の価値が飛躍的に高まります。 戦闘システムが「1対1」なのか「1対複数」なのかは、ゲーム開始後、真っ先に見極めるべき最重要ポイントの一つです。
3. 装備の更新はレベルアップより重要
RPGの基本はレベルアップですが、『DQ1』においては**「装備の更新」がレベルアップ以上に生存率に直結します。**
主人公は「ゆうしゃ」であり、戦士と魔法使いの能力を併せ持ちますが、序盤はとにかく非力です。 ラダトーム城を出た直後の主人公は「ぬののふく」と「こんぼう」(あるいは「たけざお」)しか持っていません。 この状態で城の周辺にいるスライムやスライムベスと戦うのは問題ありませんが、少し離れた場所に出る「ゴースト」や「まほうつかい」に遭遇すると、あっという間に倒されてしまいます。
最初の目標は、ラダトームの城下町で「どうのつるぎ」と「かわのたて」「かわのふく」を買い揃えることです。 これらを装備するだけで、受けるダメージは劇的に減り、与えるダメージは倍増します。 『DQ1』の攻略は、「レベルを上げて次の町へ」ではなく、「装備を整えて次の町(村)へ進む」という意識が非常に重要です。
レベルアップでHPやMPを上げつつ、稼いだゴールドで常に最強の装備を買い揃える。 このサイクルを徹底することが、冒険をスムーズに進める最大のコツです。
4. 消耗品「たいまつ」と「かぎ」の管理を徹底せよ
現代のRPGでは、ダンジョンは最初から明るく、扉はイベント以外なら自由に開けられるのが普通です。 しかし、原点の『DQ1』は違います。
ダンジョン(洞窟)は、「たいまつ」を使わなければ真っ暗闇です。 (呪文「レミーラ」を覚えれば明るくできますが、序盤はMPが貴重です) 「たいまつ」はラダトームの町などで買える消耗品で、1つ使うと一定時間(歩数)、主人公の周囲だけが明るくなります。 ダンジョンに挑む際は、道具袋(HD-2D版でも実装されるはず)に「たいまつ」を最低でも5〜6本は常備していないと、道に迷って遭難する危険があります。
さらに厄介なのが**「かぎ」**です。 町やダンジョンにある「とびら」は、「かぎ」が無ければ絶対に開けられません。 この「かぎ」も消耗品(FC版仕様の場合)であり、1つの扉を開けるたびに1本消費します。
冒険を進めると、マイラの村で「かぎ」をまとめて売ってくれる店がありますが、そこへたどり着くまでが大変です。 「かぎ」が無いと重要な情報やアイテムが手に入らない場面も多く、常に「かぎ」の残量を気にする必要があります。
SFC版リメイクでの変更点
SFC版リメイクでは、「かぎ」は消耗品ではなくなり、「まほうのかぎ」を入手すれば何度でも使えるようになりました。 HD-2D版がこの便利なSFC版仕様を採用する可能性は高いですが、もしFC版のシビアなリソース管理を再現するなら、消耗品のままかもしれません。 どちらの仕様でも対応できるよう、「かぎ」の存在は常に意識しておきましょう。
5. こまめなセーブと「おうじょのあい」
『DQ1』で冒険者が最も恐れること、それは「し」です。 主人公が力尽きると、所持しているゴールド(お金)が半分になった上で、前回セーブしたラダトーム城の王様の前に強制送還されます。
ゴールドが半分になるペナルティは非常に痛烈です。 苦労して「はがねのつるぎ」を買うために貯めたゴールドが、一瞬の油断で半減してしまうのです。 この悲劇を避けるため、以下の2点を徹底する必要があります。
- こまめに王様に報告(セーブ)する。
- ゴールドを預かり所に預ける。
特に重要なのが1つ目です。 『DQ1』のセーブは、ラダトーム城の王様に話しかけ、「そなたの ちからを きろくする」ことで行われます。 レベルが上がった時、強い装備を買った時、ダンジョンから生還した時。 区切りがついたら必ず王様の元へ戻り、セーブする癖をつけましょう。
冒険の必須アイテム「おうじょのあい」
とはいえ、毎回城に戻るのは面倒です。 そこで重要になるのが、ストーリー中盤で手に入る**「おうじょのあい(王女の愛)」**というアイテムです。 これは、ラダトームのローラ姫を救出すると(そして城まで連れ帰ると)もらえるアイテムで、使うと「次のレベルアップまでに必要な経験値」と「現在地から王様(セーブポイント)までの距離」を教えてくれます。
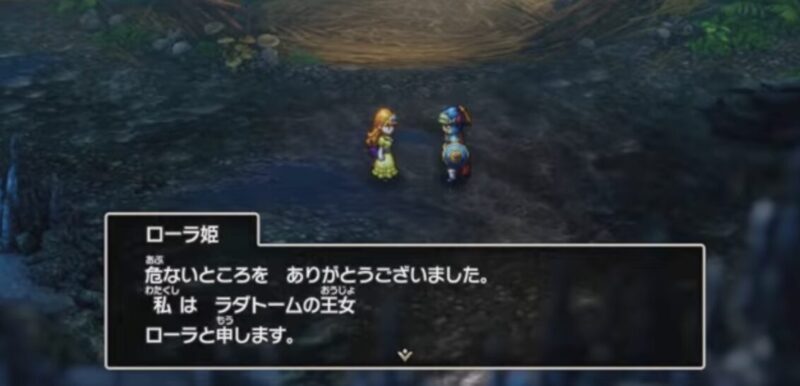
特に重要なのが後者の機能です。 これにより、「今、城に戻るとどれくらいかかるか」が視覚的にわかり、冒険を続けるか、引き返すかの判断基準になります。 HD-2D版ではマップ機能が強化されるかもしれませんが、この「おうじょのあい」は原作の雰囲気を味わうためにも、ぜひ手に入れて活用してほしいアイテムです。
6. 呪文の習得レベルとMP管理の重要性
主人公は勇者として、回復呪文と攻撃呪文をバランスよく習得していきます。 特に以下の呪文は、冒険の節目となる非常に重要なものです。
- ホイミ(Lv 3): 最初の回復呪文。MP効率は悪いですが、これがないと始まらない。
- ギラ(Lv 7): 最初の攻撃呪文。スライムベスやゴーストなど、序盤の強敵に有効。
- ルーラ(Lv 13): **最重要呪文。**一度行った町や城(ラダトーム)に瞬間移動できる。これが有るのと無いのでは、冒険の快適さが天と地ほど違います。
- レミーラ(Lv 9): ダンジョン内を明るく照らす。たいまつの節約になる。
- リレミト(Lv 12): ダンジョンから瞬時に脱出できる。ピンチの時、探索が終わった時に必須。
- ベホイミ(Lv 17): ホイミの上位呪文。回復量が大幅に増え、冒険が安定する。
『DQ1』はMP(マジックパワー)が非常に貴重です。 特に序盤は、ホイミを数回使っただけでMPが尽きてしまいます。 ダンジョン探索では、「帰りのリレミト用MP」を常に温存しながら進む必要があります。 MPが尽きたら、潔く町に戻り、宿屋で回復する勇気を持ちましょう。
7. すべての情報は「人々の会話」にある
現代のRPGのように、親切な「次に行くべき場所」を示すマーカーや、詳細なクエストログはありません。冒険のヒントは、すべて城や町にいる人々(NPC)との会話の中に隠されています。
「東に歩いていくとマイラの村がある」 「沼地の洞窟で姫のうわさを聞いた」 「ゴーレムは笛の音に弱いらしい」
これらの何気ない会話が、次の目的地やボスの攻略法を示唆しています。 新しい町に着いたら、そこにいる全ての人に話しかけるのが鉄則です。 重要な情報は、現実のあなたがメモ帳に書き留めておくことを強く推奨します。
HD-2D版では、SFC版リメイクのように「おもいだす」コマンドで重要な会話を振り返る機能が実装されるかもしれませんが、自ら情報を集め、謎を解く楽しさこそが『DQ1』の醍醐味です。 人々の言葉を注意深く聞く姿勢が、竜王への道を切り開きます。
8. ゴールド稼ぎと経験値稼ぎのバランス感覚
本作は、レベルアップによるステータス上昇と、装備の強化によるステータス上昇、その両方が必要です。 そのため、プレイヤーは常に「経験値稼ぎ」と「ゴールド稼ぎ」を意識する必要があります。
序盤は、ラダトーム周辺でスライムを倒し続け、最低限の「かわのふく」と「どうのつるぎ」を買うためにゴールドを稼ぎます。 装備が整ったら、少し足を伸ばしてゴーストやまほうつかいを倒し、レベル(経験値)を稼ぎます。 レベルが上がり、ルーラを覚えたら、さらに遠くの敵(ガライの町周辺など)を倒して、次の装備「はがねのつるぎ」のためのゴールドを稼ぐ…という流れです。
この「稼ぎ」の時間は、現代のRPGに比べると長く感じるかもしれません。 しかし、HD-2D版では戦闘速度の調整機能(倍速など)が搭載される可能性が高く、原作よりもテンポ良く稼ぎができると予想されます。
稼ぎの小ネタ:ゴーレム
ストーリー中盤、マイラの村の南にある「聖なるほこら」を守るボス「ゴーレム」は、倒さなければ先に進めませんが、実はこのゴーレム、倒しても経験値やゴールドは持っていません。 しかし、あるアイテムを使うと一撃で倒すことができます。 そのヒントも、もちろん町の人の会話の中にあります。 このように、力押しだけでなく、知恵を使って強敵を倒す手段が用意されているのも『DQ1』の魅力です。
HD-2D版『ドラゴンクエストI』を遊び尽くすための追加知識
上記の8選は、主に原作のシステムに基づいた初心者向けの注意点です。 しかし、HD-2D版はただのリメイクに留まらない可能性があります。 先に発表された『DQ3』HD-2D版は、原作になかった要素(職業の追加グラフィックや新機能)が多数盛り込まれています。
『DQ1&2』も同様に、原作の良さを残しつつ、現代の技術で遊びやすく、そしてより深く楽しめる作品になるはずです。 ここでは、ゲーム評論家としての視点から、HD-2D版で追加されそうな要素や、より深く楽しむための知識を解説します。
『DQ3』HD-2D版との「繋がり」は?
ご存知の通り、『DQ1』『DQ2』『DQ3』は「ロト三部作」と呼ばれ、時系列順では『DQ3』→『DQ1』→『DQ2』となります。 今回、HD-2D版は『DQ3』(2024年11月発売)が先で、『DQ1&2』(2025年発売)が後という、物語の時系列通りの発売順となりました。
これは、スクウェア・エニックスの粋な計らいだと感じています。 『DQ3』でロトの伝説を築いた勇者の冒険を体験した直後に、その子孫たちの物語である『DQ1&2』をプレイできるのです。
HD-2D版『DQ3』のセーブデータがあると、『DQ1』のオープニングが少し変わる、あるいは特別なアイテムが手に入る…といった「連携要素」が仕込まれている可能性は十分に考えられます。 『DQ3』の主人公(あなたの分身)が、『DQ1』の主人公(子孫)に何らかの影響を与える。 そんなロマンあふれる演出に期待したいところです。
原作(FC版)とリメイク(SFC版)どちらがベースか?
『DQ1』には、大きく分けて1986年のFC版と、1993年のSFC版(『ドラゴンクエストI・II』として発売)の2つのベースがあります。 両者には以下のような大きな違いがあります。
| 項目 | FC版(原作) | SFC版(リメイク) |
|---|---|---|
| 戦闘 | 敵は必ず1体 | 敵が複数出現する(最大5体) |
| グラフィック | 8bitドット絵 | 16bitドット絵(DQ5,6風) |
| 移動 | 主人公が向いている方向にしか攻撃できない | 主人公がどの向きでも攻撃可能 |
| かぎ | 消耗品(1回使うと無くなる) | 「まほうのかぎ」入手で無限に使える |
| 呪文 | 「ギラ」は敵1体 | 「ギラ」は敵グループ |
| 便利機能 | なし(持ち物8個まで) | 「ふくろ」があり、多数のアイテムを持てる |
| その他 | BGMがシンプル | オーケストラ風BGM、SEが豊富 |
公開されたHD-2D版の映像を見る限り、グラフィックはSFC版をベースにHD-2D化しつつ、戦闘バランスやUIは現代風に再構築されているように見えます。
おそらく、SFC版の「遊びやすさ」(敵が複数、ふくろ有り、かぎが無限)をベースに、HD-2D版『DQ3』で培われた快適なシステム(オートセーブ、倍速戦闘など)が組み合わさる形になると予想するのが妥当でしょう。
FC版の「1対1の緊張感」や「消耗品のかぎ」といったシビアなバランスも魅力的でしたが、現代のプレイヤーにはSFC版ベースの方が受け入れられやすいと判断するはずです。
『ドラゴンクエストI』のストーリーを深掘りする
『DQ1』の物語は非常にシンプルです。 「竜王にさらわれたローラ姫を助け出し、闇の世界を支配する竜王を倒す」 これだけです。
しかし、その背景には深い設定があります。 主人公は、かつてアレフガルドを闇から救った「勇者ロト」の血を引く者。 竜王もまた、ロトと共に戦った「竜の一族」の子孫(あるいは竜そのもの)と言われています。
そして、冒険の途中で見つけることになる「ロトのつるぎ」「ロトのよろい」。 これらは、『DQ3』で勇者が最後に装備していた最強の武具です。 なぜそれらがアレフガルドの各地に隠されているのか。 『DQ3』をプレイした後だと、その「なぜ」を考えながら冒険することになり、物語の深みが一層増します。
「竜王の誘い」という究極の選択
『DQ1』の物語のクライマックス、竜王の城で待ち受ける竜王との対峙。 ここで、竜王は主人公に衝撃的な問いかけをします。
「もし わしの みかたになれば せかいの はんぶんを おまえに やろう」
この「世界の半分」という誘惑は、当時のプレイヤーに強烈なインパクトを与えました。 もし、ここで「はい」と答えてしまったら…?
FC版では、この誘いに乗るとゲームオーバー(正確にはパスワードが聞けなくなる)という恐ろしい罠が待っていました。 SFC版では、少しコミカルな結末(夢オチのようなもの)に変更されました。
HD-2D版でこの有名なシーンがどのように描かれるのか。 そして、もし誘いに乗ってしまったらどうなるのか。 原作を知るプレイヤーにとっても、非常に楽しみなポイントです。 (セーブしてから試してみることをお勧めします)
最強装備「ロト」シリーズの在処
『DQ1』の冒険の目的の一つが、勇者ロトの遺した3つの装備「ロトのつるぎ」「ロトのよろい」「ロトのたて」を探し出すことです。 (※原作FC版では「たて」は存在せず、「ロトのしるし」が重要アイテムでした。SFC版で「ロトのたて」が追加されました)
これらは店では売っておらず、アレフガルドのどこかに隠されています。 そのヒントも、やはり人々の会話の中にあります。
- ロトのよろい: とある町の近くにある、毒の沼地に隠された洞窟の奥深く…。
- ロトのつるぎ: 竜王の城へ向かうために必要な「あるアイテム」が隠されている場所の、さらに奥…。
これらの装備は、竜王を倒すために必須ではありませんが、最強の性能を誇ります。 特に「ロトのよろい」は、歩くたびにHPが回復するという破格の性能を持っています。 HD-2Dで美しく描かれるアレフガルドを隅々まで探索し、伝説の装備を見つけ出す喜びは、本作の大きな魅力となるでしょう。
そして『ドラゴンクエストII』へ… 難易度激変の罠
今回発売されるのは『ドラゴンクエストI&II』です。 『DQ1』で竜王を倒し、アレフガルドに平和を取り戻した後には、その100年後を描いた『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』の冒険が待っています。
ここで、最大の注意点をひとつ。 『DQ1』と『DQ2』は、全く別のゲームと言っていいほど難易度が異なります。
『DQ1』が「1対1」のシンプルな冒険だったのに対し、『DQ2』は以下の点で劇的に難易度が上がります。
- 初の3人パーティバトル: ローレシアの王子(戦士)、サマルトリアの王子(戦士+魔法)、ムーンブルクの王女(魔法使い)という3人パーティ。戦略性が一気に増します。
- 敵の集団化: 敵が平気で5〜6匹の集団で現れます。
- 理不尽な難易度: 「サマルトリアの王子がどこにいるか分からない」「ロンダルキアへの道が鬼畜すぎる」「ハーゴンの神殿での絶望」など、RPG史に残る高難易度ポイントが満載です。
『DQ1』をクリアした感覚で『DQ2』に挑むと、その難易度の高さに心を折られるかもしれません。 HD-2D版でどこまで遊びやすく調整されるかは不明ですが、『DQ2』に挑む際は、『DQ1』とは別次元の覚悟を持って臨む必要があります。
しかし、その困難を乗り越えた時の達成感もまた、格別なものです。
HD-2D版『DQ1&2』への期待(評論家として)
ゲーム評論家として、私はこのHD-2D版『DQ1&2』に大きな期待を寄せています。 『DQ1』は、そのシンプルさゆえに、リメイクで「何を足し、何を引くか」のさじ加減が非常に難しいタイトルです。
あまりに便利にしすぎると、原作の「たった一人で広大な世界を切り開いていく緊張感」が失われます。 かといって、原作のままでは、現代のプレイヤーには不親切すぎます。
SFC版は、そのバランスを非常によく取った名リメイクでした。 今回のHD-2D版は、そのSFC版をベースに、「ロト三部作」の時系列順での発売という、これ以上ない「物語体験」を提供しようとしています。
『DQ3』で築いた伝説が、『DQ1』でどのように受け継がれ、『DQ2』でどのように完結するのか。 グラフィックの進化だけでなく、その「物語の繋がり」を補完するような、HD-2D版ならではの新しい解釈や追加シナリオが少しでも含まれていることを、心から期待しています。
まとめ
今回は、HD-2D版『ドラゴンクエストI』リメイクをプレイする上で、初心者が気を付けるべき8つのポイントと、関連する深掘り知識を徹底的に解説しました。
『ドラゴンクエストI』は、RPGというジャンルの面白さの「核」が詰まった作品です。 「レベルを上げて強くなる喜び」「新しい装備を手に入れる高揚感」「未知の場所を探索する緊張感」「人々の言葉から謎を解く達成感」。 これら全てを、たった一人の冒険で体験できます。
HD-2D版で初めてアレフガルドに降り立つ方も、かつて「ふっかつのじゅもん」を書き写したベテラン勇者の方も、このレビューで解説したポイントを押さえておけば、新たなロトの伝説を存分に楽しめるはずです。
2025年の発売が、今から待ち遠しくてたまりません。