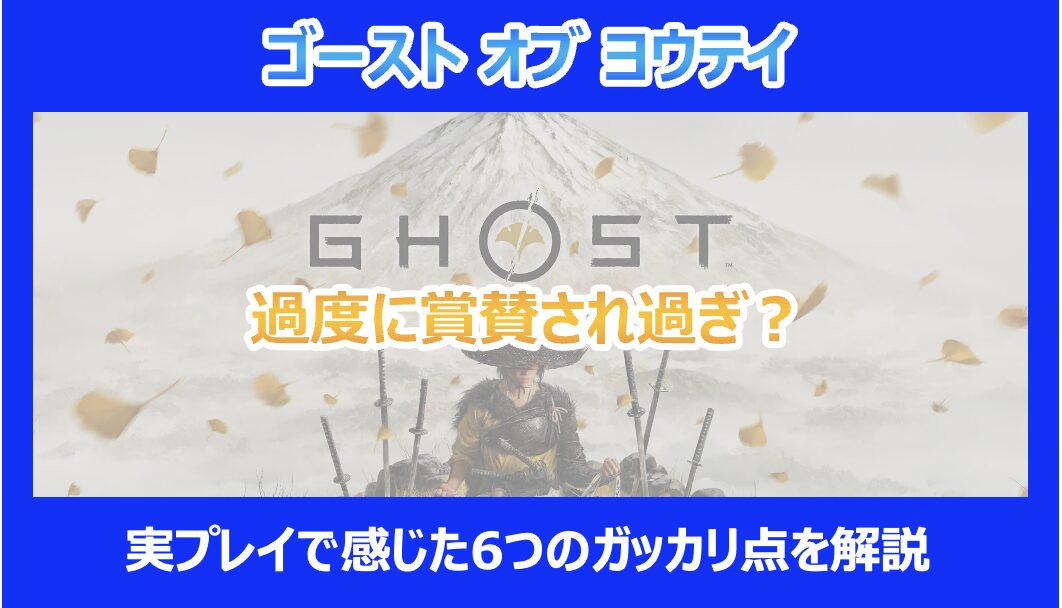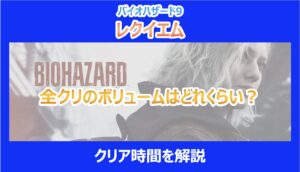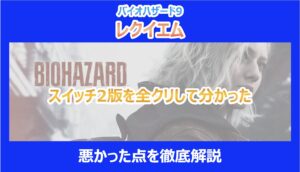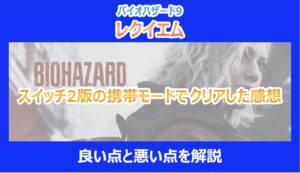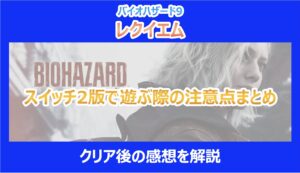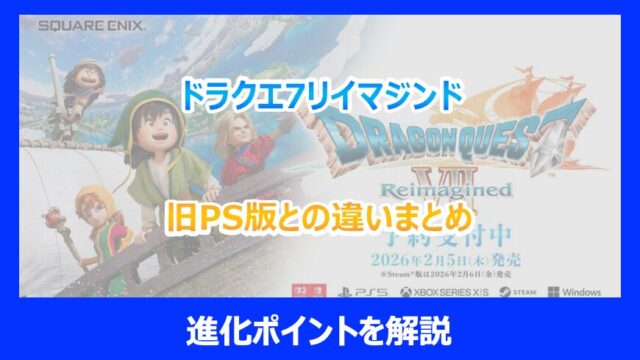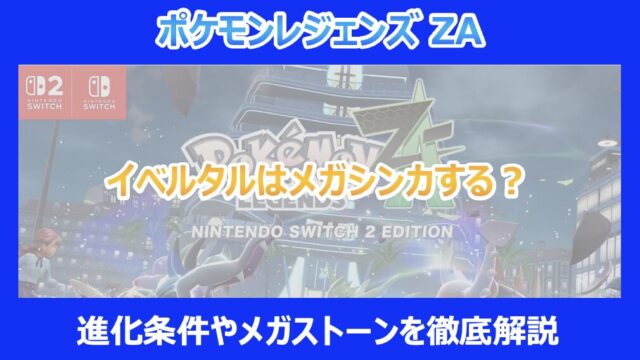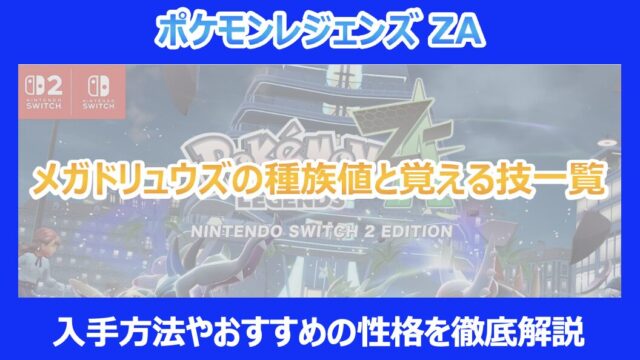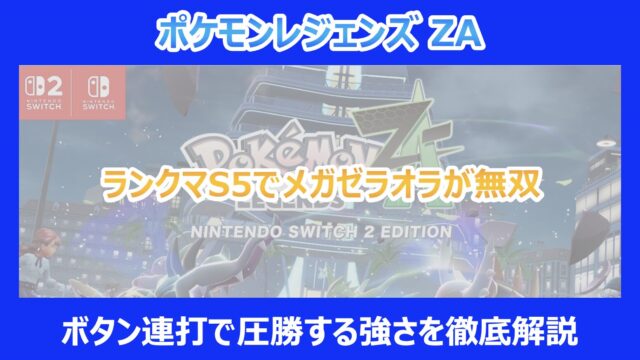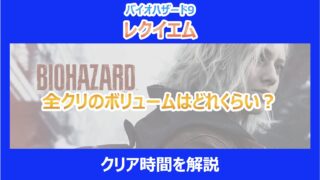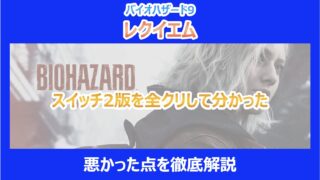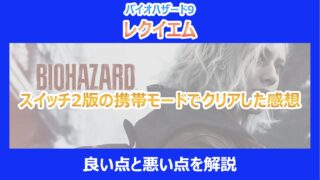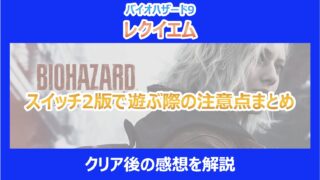ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年10月2日に発売され、絶賛の嵐を巻き起こしている『Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)』に興味がある一方で、本当に欠点はないのか、過度に賞賛されているのではないかという疑問を抱いているのではないでしょうか。 私自身も発売日からプレイを重ね、この広大な世界と復讐の物語を深く味わってきました。

巷で聞かれる「神ゲー」の声ばかりで、購入に踏み切れない方や、既にプレイしているけれど「あれ?なんか思ってたのと違うな…」と感じている方もいるかもしれません。
このレビューを読み終える頃には、『Ghost of Yōtei』の実プレイで感じた詳細なガッカリ点や、購入を検討する上での具体的なヒントに関する疑問が解決しているはずです。
- 息をのむグラフィックと退屈な移動体験のギャップ
- 復讐譚とオープンワールドが引き起こすストーリーの熱量低下
- 前作からの進化に疑問符が付く戦闘システムの爽快感
- 探索依存の成長システムがもたらす「作業感」
それでは解説していきます。

グラフィック:美しい“が”退屈という矛盾
まず、多くのレビューで口を揃えて賞賛されるのが『Ghost of Yōtei』のグラフィックです。 私も異論はありません。 晴天の草原を吹き抜ける風、木々の間から差し込む木漏れ日、遠景に広がる雄大な山並みなど、その美しさは文句なしの一級品で、思わずフォトモードを起動してしまう瞬間が確かに存在します。 しかし、この「美しい」という点に関して、私個人としては複雑な感情を抱きました。 なぜなら、その美しさの裏側には、時にゲーム体験を退屈にさせてしまう側面があったからです。

美しいが退屈な景観のワケ
『Ghost of Yōtei』の世界は、細部に至るまで作り込まれた圧倒的なビジュアルでプレイヤーを魅了します。 特に自然の描写は秀逸で、風に揺れる草花、水面のきらめき、壮大な建造物など、見渡す限り息をのむような絶景が広がっています。 しかし、この美しさが長時間にわたって続くと、徐々に「慣れ」が生じてしまうのが人間の感覚というものです。
初めて見たときの感動は薄れ、いつの間にかそれが「当たり前の景色」となってしまうのです。 さらに、ゲームの進行とともに訪れる様々な天候変化も、期待とは裏腹に、必ずしも常に感動を伴うものではありませんでした。 夜間の雨や霧の中では、確かに雰囲気は増すものの、視認性の悪さからプレイに支障をきたす場面も少なくありません。
「天候の変化も楽しめる」という意見も理解できますが、個人的には「あ、天候が変わったな」程度の認識で、特に大きな感情の揺さぶりを感じることは少なかったです。 むしろ、暗闇の中での探索や戦闘はストレスに繋がり、美しい景色をゆっくりと堪能する余裕すら奪われることもありました。 この「視覚的な美しさ」と「ゲームプレイの快適性」のバランスが、もう少し考慮されていれば、より一層没入感を高められたのではないかと感じます。
前作からのグラフィック進化の限界
多くのプレイヤーが本作を前作と比較するのは当然の流れでしょう。 前作のグラフィックも当時としては最高峰のものであり、その美しい世界観に多くの人が魅了されました。 本作のグラフィックが素晴らしいことは疑いようがありませんが、前作をやりこんだ私としては、「大きく飛躍したか」と問われると、正直なところ「そこまでではない」という印象を受けざるを得ませんでした。 前作で既にあのクオリティを経験しているプレイヤーにとって、本作のグラフィックは「当然の進化」として目に映り、驚きの振り幅が小さくなっているように感じられます。
もちろん、技術的な向上や細部の描写の深化は随所に見られますが、それがゲーム体験全体を劇的に変化させるほどの影響力を持っているかというと、やや疑問符が付きます。 例えば、水の表現や光の描写、キャラクターモデルの精細さなどは向上していますが、それらが「次世代の体験」と呼べるほどの革新をもたらしているかというと、前作の感動を上回るものではなかったのです。
私たちがゲームに求めるのは、単なるビジュアルの美しさだけでなく、その美しさがゲームプレイや物語にどのように作用し、新たな感動を生み出すかという点です。 その意味で、『Ghost of Yōtei』は、前作の「圧倒的な体験」を「順当にアップデート」した、という評価に留まるでしょう。
広大なマップにおける移動の虚無感
オープンワールドゲームの醍醐味の一つは、広大なマップを自由に探索し、予期せぬ発見や出会いを体験することにあります。 しかし、『Ghost of Yōtei』では、この「移動」そのものが、時に退屈なものに感じられました。 目的地をマークし、馬で数分間走り続けても、途中で何かしらのイベントが発生することは稀で、ただ景色が流れていくだけの時間が少なくありません。
もちろん、この美しい風景を眺めながらの移動を「癒し」と感じるプレイヤーもいるでしょう。 しかし、ゲームとしての体験を重視する私としては、前作と比較して野良の敵との遭遇が少ないこともあり、オープンワールドにおける移動が「単なる移動」に終始しているように感じられました。
オープンワールドの移動における課題
オープンワールドの移動における課題は、プレイヤーの興味をいかに持続させるかという点に集約されます。 ただ広大なだけでなく、その広大なフィールドにいかに意味を持たせるかが、傑作と凡作を分ける大きな要因となります。 『Ghost of Yōtei』の場合、移動中に発生するランダムイベントや、探索を促すような魅力的なランドマークが不足しているように感じました。 結果として、広大なマップは、美しいものの、時にプレイヤーを目的地までただ運ぶだけの「通過点」となり、オープンワールドならではの「探索の喜び」や「偶発的な出会いの興奮」を十分に提供できていなかったと言えるでしょう。
他のオープンワールドゲームとの比較
例えば、ある有名オープンワールドRPGでは、移動中に様々なサイドクエストが発生したり、ユニークなモンスターとの遭遇、隠された財宝の発見など、常にプレイヤーの好奇心を刺激する要素が散りばめられています。 これにより、プレイヤーは「寄り道」をすることで、予定していなかった新たな物語や成長の機会に出会うことができます。 『Ghost of Yōtei』の場合、このような「うっかり寄り道してしまう楽しさ」がやや希薄で、結果として「綺麗だけど退屈」という感想を抱かざるを得ませんでした。

オープンワールドという形式を採用する以上、移動そのものがゲーム体験の一部となるような工夫が、さらに求められていたのではないでしょうか。 単なるビジュアルの美しさだけでなく、その美しさがゲームプレイと密接に結びつき、プレイヤーを飽きさせない工夫が不可欠だと痛感しました。
ストーリーとゲームシステム:復讐譚とオープンワールドの不協和音
『Ghost of Yōtei』の物語は、復讐をテーマにした重厚な展開が魅力とされています。 私も本作のストーリーが持つポテンシャルは高く評価していますが、広大なオープンワールドというゲームシステムとの間で、時に不協和音が生じていると感じました。 復讐という一方向性の強い感情を原動力とする物語には、ある種の「切迫感」や「直線的な推進力」が不可欠です。 しかし、オープンワールドの自由度が、その熱量を保つことを難しくしている側面がありました。

復讐譚とオープンワールドの不協和音
復讐の物語は、プレイヤーを一直線に目的へと駆り立てる強い感情が必要です。 例えば、往年の名作アクションゲームのように、緊迫した状況が続き、プレイヤーが「今すぐにでも敵を斬りに行きたい」という衝動に駆られるような設計が理想的だと私は考えます。 しかし、『Ghost of Yōtei』は広大なフィールドに複数のボスを配置し、プレイヤーに倒す順番を委ねるという設計を採用しています。 この自由度は、一見するとオープンワールドの利点のように見えますが、復讐というストーリーが持つべき感情の連続性を維持することを難しくしていました。
ストーリーのテンポと感情移入の阻害
広大なマップでの移動が長く、さらに頻繁に回想シーンが挟まるため、プレイヤーが「ひたすら斬りたい」という感情に傾いている時に、回想によってその勢いが削がれてしまうことが多々ありました。 演出としての回想の意図は理解できますが、オープンワールドの移動時間も考慮すると、全体的なテンポが悪く感じられます。 もしストーリーを最優先でプレイヤーに見せたいのであれば、思い切ってオープンワールドではなく、一本道の動線にすることで、復讐劇としての緊張感をより高められたのではないか、というのが正直な感想です。 本作は「ストーリーにも感情移入してほしい」と「オープンワールドも楽しんでほしい」という二兎を追った結果、どちらの魅力も中途半端になってしまったように思えます。 この二つの要素の融合は、オープンワールドゲームにおける永遠の課題であり、本作においても完全に解決されたとは言い難い状況でした。
親切すぎる設計が奪うワクワク感
オープンワールドゲームの大きな魅力は、プレイヤー自身の発見と探求にあります。 未知の場所を探し、隠された秘密を見つけ出す「偶発的な出会い」が、プレイヤーのワクワク感を最大限に高めます。 しかし、『Ghost of Yōtei』の一部の設計は、このオープンワールドならではの醍醐味を損なっていると感じました。 特に決定的に萎えてしまったのが、序盤に新武器の配置や取得経路が事前に分かってしまうという設計です。
事前情報がもたらす「作業感」
「このボスを倒す前には、この武器が手に入る」といった形で、いわば「ネタバレ」のような情報がプレイヤーに事前に与えられていました。 これにより、オープンワールドが「ワクワクする冒険」ではなく、「どこに何があるか分かっている場所へ取りに行く」「倒す」という、まるでチェックリストを消化するような「作業」に感じられてしまったのです。 不親切な設計ももちろん良いことではありませんが、親切すぎる設計もまた、プレイヤーから発見の喜びや驚きの感情を奪ってしまうことがあります。 オープンワールドの本来の魅力は、意識していない時に不意に手に入る偶然の出会いや、苦労して探し出した時の達成感にあるはずです。 どこに何があるかがあらかじめ明かされてしまうと、探索のモチベーションは大きく低下し、ゲームが途端に味気ないものになってしまいます。 この「親切すぎる設計」は、私にとって個人的に非常に萎えてしまったポイントであり、オープンワールドの楽しみ方を根本から揺るがすものでした。
深みに欠けるキャラクター描写と物語
復讐に感情移入できるという評価も多く見かけます。 しかし、主人公であるアツ(仮称)の描写に関して言えば、理屈としては復讐に至る経緯は理解できるものの、感情的に深く共感できるかというと、正直なところ「心が動かない」というのが私の感想です。 復讐の起点が描かれたとしても、広大なマップを目的地へ向かう長い移動の間に、その熱量が冷めてしまうことが多々ありました。 広い世界は、まったりとした感動や穏やかさを生むかもしれませんが、復讐という怒りの感情を核とするストーリーとは相性が悪いと感じざるを得ません。
アツの感情の起伏の不足
アツという人物の造形自体は悪くありませんが、彼がもっと復讐に飲み込まれていき、危うさや怖さを感じるような瞬間は少なかったです。 例えば、スター・ウォーズのダース・ベイダーがダークサイドに闇落ちしていくような、強烈な感情の揺れ動きや葛藤が描かれていれば、物語にさらに深みが増したのではないでしょうか。 復讐という王道で分かりやすいストーリー自体は否定しません。 しかし、オープンワールドという広大な背景が、皮肉にも復讐という怒りの感情を希薄にしてしまっていたように感じます。 プレイヤーがアツの復讐に感情移入するためには、彼の内面がより深く描かれ、その葛藤や苦悩がゲームプレイを通じて肌で感じられるような工夫が求められます。 そうすることで、単なる「ストーリーを見る」体験ではなく、「アツの復讐を追体験する」という真の没入感を生み出せたはずです。 現状では、アツの行動原理は理解できても、彼の苦しみや怒りに寄り添うことが難しく、物語がどこか他人事のように感じられてしまう点が、大きな不満点として残りました。
戦闘システムと成長要素:前作以下の爽快感と作業感
『Ghost of Yōtei』の戦闘システムについても、多くのレビューで「爽快感がある」と評価されています。 しかし、個人的な体感としては、前作の方が遥かに「斬っている」という手応えと爽快感を感じられました。 本作の戦闘には、いくつかの点で物足りなさやストレスを感じる部分がありました。

前作に劣る戦闘の爽快感とその要因
本作では、モーション全体がわずかに重く感じられる瞬間が多く、これが戦闘のテンポを悪くし、結果として爽快感を損ねている大きな要因だと感じました。 特にゲーム序盤は、使用できる武器やスキルが少なく、□ボタンと△ボタンの連打で敵の攻撃をしのぐ時間が長く、駆け引きを楽しむ前に単調な連打突破の作業的なアクションになりがちです。
戦闘テンポの悪さ
戦闘テンポの悪さは、敵の攻撃モーションやプレイヤーの回避・反撃モーションが、全体的に「もっさり」していることに起因します。 これにより、敵の攻撃を流麗に捌き、素早く反撃するという一連の動きが阻害され、戦闘が「重苦しい」ものに感じられます。 特に複数の敵に囲まれた状況では、このテンポの悪さが顕著になり、プレイヤーは爽快感よりも、いかに敵の攻撃をさばき、生き残るかという「防御的な思考」に陥りがちでした。 前作で感じられた、刀を振り抜き、敵を両断するような「切れ味」と「スピード感」が、本作ではやや薄れているように思えてなりません。 これは、戦闘の根本的な楽しさを損ねる、非常に残念な点です。
序盤の単調な戦闘と成長の遅さ
さらに、序盤における武器やスキルの少なさも、戦闘の単調さに拍車をかけています。 プレイヤーは限られたアクションの中で、ひたすら敵の攻撃を防ぎ、隙を見て攻撃するという、ルーティン化された行動を強いられます。 これにより、戦闘が「攻略」ではなく「作業」に感じられ、新たな戦術を試す面白さや、キャラクターの成長を実感する喜びが薄れてしまいました。 本来、ゲーム序盤はプレイヤーがシステムの基礎を学び、少しずつできることが増えていく段階であり、その中でキャラクターが強くなっていく「実感」が重要です。 しかし、『Ghost of Yōtei』の序盤は、その「実感」を得るまでが長く、多くのプレイヤーが途中で飽きを感じてしまう可能性があると危惧しています。 この初期段階での戦闘体験の改善は、プレイヤーのゲームへの引き込みという点で、非常に重要だと考えます。
ストレスフルな敵の配置とカメラワークの問題
戦闘の爽快感を損ねる要因として、敵の配置とカメラワークにも大きな問題がありました。 特に、鎖を持った敵の存在は、私にとって非常に大きなストレス源でした。
鎖持ちの敵による理不尽さ
正面の敵との駆け引きに集中していると、画面外から不意に鎖で拘束され、連続攻撃を受けることが少なくありませんでした。 これは緊張感を生み出すというよりも、純粋な「理不尽さ」が先に立ち、プレイヤーの集中力を削ぐ結果となっていました。 このような敵の配置は、プレイヤーに多角的な注意を促す意図があるのかもしれませんが、それがゲームプレイの楽しさを上回るストレスとなってしまっては本末転倒です。 特に、戦闘が苦手なプレイヤーにとっては、この鎖持ちの敵がゲーム全体の難易度を不必要に引き上げ、フラストレーションの元となるでしょう。 もっとプレイヤーに公平な形でリスクとリターンが提示されるべきであり、画面外からの不意打ちのような要素は、慎重に設計されるべきだと感じます。
室内戦におけるカメラワークの問題
また、室内での戦闘では、カメラが壁にめり込んだり、視界が遮られたりすることが頻繁にあり、戦いづらさを感じました。 これは、プレイヤーが敵の動きや攻撃を正確に把握することを困難にし、誤った判断や操作ミスを誘発する原因となります。 オープンワールドゲームにおいて、狭い空間での戦闘は避けられない要素ですが、それに対応できるようなカメラの自動調整機能や、視界を確保する工夫が不足しているように感じました。 特に、複数の敵に囲まれた状況でカメラが暴れると、プレイヤーは自分が何をしているのかすら見失い、ただボタンを連打するだけの無駄な行動に走りがちです。 戦闘の没入感を高めるためには、プレイヤーが常に状況を正確に把握できるような、ストレスフリーなカメラワークが不可欠であると、改めて認識させられました。 これらの問題は、一つ一つは小さなことかもしれませんが、積み重なることで戦闘体験全体を大きく損ねていました。
探索偏重の成長システムがもたらす弊害
『Ghost of Yōtei』の成長システムは、スキルを寺院巡りで解放するなど、探索依存の仕組みが目立っています。 確かに、五歩の取得で受け流しを強化したり、隠密特化といったビルドを組むことは可能ですが、私が期待していた「戦闘して強くなる」という感覚とは異なっていました。 広大なマップで参拝や収集をすることで強くなるというシステムは、「もっと戦闘を楽しみたい」というプレイヤーの気持ちを阻害してしまう要因となっていました。
「戦う喜び」よりも「集める作業」へ
RPGやアクションRPGにおいて、プレイヤーがキャラクターを強くする主なモチベーションは、より強い敵を倒し、より困難な状況を乗り越える「戦う喜び」に直結しています。 戦闘を通じて経験値を稼ぎ、新たなスキルを習得し、強力な装備を手に入れるというサイクルが、プレイヤーをゲームに深く没入させる原動力となるのです。 しかし、『Ghost of Yōtei』の場合、この成長の大部分が戦闘ではなく「探索」に依存しているため、プレイヤーは「戦う喜び」よりも「集める作業」に重点を置かざるを得なくなります。 これにより、戦闘そのものへのモチベーションが低下し、キャラクターが強くなるプロセスが、どこか事務的なものに感じられてしまうのです。
サブクエストの単調さと「寄り道の目的」
サブクエストも、会話、目的地への移動、敵を倒す、報酬を得るという流れが多く、バリエーション不足だと感じました。 オープンワールドゲームは本来、「うっかり寄り道する楽しさ」で時間が溶けていくような設計が理想です。 プレイヤーはメインストーリーの進行を忘れ、偶然見つけたクエストや場所の探索に夢中になることで、広大な世界を心ゆくまで満喫できます。 しかし、本作では、スキルポイントや収集アイテムを集めるという「寄り道の目的」が最初から分かってしまっているため、それが「寄り道」ではなく、単なる「収集作業」になってしまっていました。 まるで「このエリアの収集物を全て回収する」というチェックリストを消化しているかのような感覚に陥り、オープンワールドならではの自由な探求の喜びが薄れてしまったのは非常に残念な点です。
単調になりがちなサブクエストの課題
前述の通り、サブクエストの多くが「会話 → 目的地へ移動 → 敵を倒す → 報酬」という定型的な流れに終始している点は、オープンワールドゲームとしての物足りなさを強く感じさせます。 確かに、ゲーム開発におけるリソースの問題は理解できますが、プレイヤーの体験を重視するならば、もう少し工夫が欲しかったところです。
物語性や多様性に欠けるサブクエスト
多くのオープンワールドゲームでは、サブクエストがメインストーリーを補完するような深い物語を持っていたり、ユニークなキャラクターとの出会い、あるいは特別なアイテムや能力を獲得するきっかけになったりします。 これにより、プレイヤーはサブクエストを通じて世界の背景を深く知り、キャラクターとの繋がりを感じ、ゲーム全体への没入感を高めることができます。
しかし、『Ghost of Yōtei』のサブクエストは、その多くが単発的で、あまり深い物語性やキャラクターの掘り下げが見られないため、メインストーリーへの影響も限定的です。 結果として、サブクエストをこなすことが「作業」に感じられ、プレイヤーの時間を有効に使えているという実感が薄れてしまいました。 多様性に欠ける点も、飽きを早める要因となります。 例えば、ただ敵を倒すだけでなく、謎解き要素があったり、特定のアイテムを探索したり、あるいはステルスを駆使して目標を達成したりと、もう少しゲームプレイの幅が広がっていれば、飽きずに楽しめたかもしれません。 同じようなことを繰り返すだけでは、どんなに美しい世界でも、プレイヤーの心は離れていってしまいます。
その他の不満点:体験を阻害する細かな要因
ここまでは主にゲームプレイの根幹に関わる部分のガッカリ点を述べてきましたが、他にもプレイヤー体験を阻害するような細かな不満点がいくつか存在しました。 これらは単体では些細なことかもしれませんが、積み重なることでゲーム全体への印象を悪くする要因となります。
説得力に欠ける修行イベント
ゲーム冒頭の二刀流の修行イベントは、あっさりしすぎていて、正直なところ「必要だったのか?」と感じてしまいました。 ただ竹や炭を切るだけで免許皆伝をもらうという流れは、あまりにも軽すぎて説得力がありません。 これほどまでに軽いのであれば、いっそのこと最初から二刀流を扱えるという設定でも良かったのではないかとすら感じます。 プレイヤーが新しい能力や武器を手に入れる際、それがいかにして習得されたのか、どのような困難を乗り越えて身につけたのかというプロセスが描かれることで、その能力への愛着や価値が生まれます。 しかし、本作の二刀流修行イベントは、そのプロセスが極めて希薄で、プレイヤーにとって「ただ通過するだけのイベント」になってしまっていました。 これにより、二刀流という魅力的な要素への期待感が、十分には高まらなかったのが残念です。
過去作との比較と期待値
過去の剣戟ゲームや武士道をテーマにした作品では、修行イベントがプレイヤーの腕前を試す重要な機会であったり、師弟関係の絆を深める感動的な場面として描かれたりすることが少なくありません。 そうした作品を経験しているプレイヤーにとっては、本作の修行イベントはあまりにも淡白に感じられ、期待値とのギャップが生じてしまうでしょう。 二刀流という、主人公アツの戦闘スタイルにおいて非常に重要な要素であるからこそ、その習得過程はもっと丁寧に、そして説得力のある形で描かれるべきだったと強く感じます。 例えば、特別な技を会得するために特定の敵を倒す、あるいは過去の達人の残した巻物を読み解くといった、具体的な課題や物語が伴っていれば、二刀流への思い入れも深まったはずです。 この修行イベントの軽さは、本作が持つ「武士道」というテーマと、その世界観への没入感を損ねる一因となっていました。
スキップできないムービーと会話のテンポの悪さ
現代のゲームにおいて、ムービーや会話シーンのスキップ機能は、プレイヤーの快適性を考慮する上で必須の要素となっています。 しかし、『Ghost of Yōtei』では、一部のムービーや会話がスキップできないことがあり、非常に直辛く感じました。 特に、ありきたりな内容の会話や、既に理解している状況説明が、スキップできない時間で延々と聞かされるのは、現代のテンポの感覚とはかけ離れていると言わざるを得ません。
プレイヤーの主導権の欠如
ムービーや会話で世界観を伝えること自体は歓迎すべきことですが、もっとプレイヤーに主導権を与えるような演出にして欲しかったです。 例えば、初めて見るムービーは強制でも構いませんが、一度見たものはスキップ可能にする、あるいは会話中に複数の選択肢を用意し、プレイヤーが会話の流れをある程度コントロールできるようにするなどの工夫があれば、不満は軽減されたはずです。 ゲームは一方的に情報を受け取るだけのメディアではなく、プレイヤーが自ら行動し、物語を紡いでいく体験です。 その体験が、スキップできないムービーによって中断されてしまうのは、没入感を損ねる大きな要因となります。 特に、周回プレイを考える場合、同じムービーや会話を何度も強制的に見せられることは、プレイヤーにとって大きな負担となり、再プレイの意欲を削いでしまう可能性すらあります。 現代のゲームデザインにおいては、プレイヤーの時間価値を尊重し、快適なゲーム体験を提供することが重要です。 その点で、『Ghost of Yōtei』のこの仕様は、時代錯誤であるとさえ感じてしまいました。
『Ghost of Yōtei』はこんな人におすすめ/おすすめできない
ここまでに、『Ghost of Yōtei』の実プレイで感じたガッカリ点を忖度なくお話ししてきました。 しかし、どんなゲームにも向き不向きがあります。 このゲームが誰にとって最高の体験となり、誰にとって残念な体験となるのか、私の正直な意見をまとめたいと思います。 あなたのプレイスタイルやゲームに求めるものと照らし合わせて、参考にしてみてください。
『Ghost of Yōtei』はこんな人におすすめ
- グラフィックの美しさを心ゆくまで堪能したい人: 本作のグラフィックは間違いなく一級品です。特に、日本の自然が織りなす四季折々の風景、精巧に描かれた建造物、そして光と影の表現は、まるで息をのむような芸術作品のようです。フォトモードを駆使して美しい写真を撮ったり、ただ馬に乗って広大な世界を散策するだけでも十分な価値を感じられるでしょう。現実世界ではなかなか体験できないような絶景を、ゲームの世界でじっくりと味わいたい方には、強くおすすめできます。
- フォトモードで写真を撮りながらまったり遊びたい人: 上記のグラフィックの美しさにも通じますが、このゲームは「急いでクリアする必要がない」と感じる人には、非常に合うでしょう。美麗な景色を背景に、主人公アツの雄姿を最高の構図で撮影する。あるいは、ひっそりと佇む神社や、風情ある集落を写真に収める。そういった、ゲームの進行とは直接関係のない「写真撮影」というアクティビティに時間を費やすのが好きな方にとって、本作のフォトモードは無限の可能性を秘めています。ストレスなく、自分のペースでゆったりとゲームの世界を楽しみたい方には、最高の体験となるでしょう。
- 復讐劇を映画のように眺めたい人: 『Ghost of Yōtei』のストーリーは、復讐をテーマにした王道的なものです。主人公アツが、家族や仲間を奪った敵に立ち向かい、その裏に隠された陰謀を暴いていく過程は、まるで一本の時代劇映画を見ているかのような感覚を味わえます。 特に、主要キャラクターたちの表情豊かな演技や、要所で挿入される壮大なムービーシーンは、映画的な没入感を高めてくれます。ゲームプレイよりも、物語の展開や登場人物たちのドラマを重視し、感情移入しながらストーリーを追いたい方にとっては、見ごたえのある作品となるでしょう。あくまで「見る」ことを楽しむ、というスタンスであれば、オープンワールドとの相性の悪さも気にならないかもしれません。
- 日本の歴史や文化、武士道の世界観に深く浸りたい人: 本作は、架空の「ようてい」という島を舞台にしていますが、その根底には日本の武士道精神や、当時の文化、風習が色濃く反映されています。主人公の武士としての葛藤、仁義と復讐の間で揺れ動く心、そして日本の美しい自然が織りなす世界観は、日本の歴史や文化に興味がある方にとって、非常に魅力的に映るはずです。作中に登場する様々な伝承や習わしに触れることで、日本の美意識や精神性をゲームを通じて体験できるでしょう。
- 探索を通じて新たな発見を楽しみたい人: 確かに、一部の要素が事前に分かりすぎてしまうという不満点は述べましたが、それでも広大なマップには、隠されたアイテムや小さな祠、景色が美しい場所などが点在しています。 メインストーリーやサブクエストを追うだけでなく、自分の足でマップの隅々まで探索し、隠された要素を見つけ出すことに喜びを感じるプレイヤーにとっては、この広大な世界は宝の山となるでしょう。 特に、収集癖のあるプレイヤーや、マップのコンプリートを目指すタイプのプレイヤーであれば、長く楽しめる要素が詰まっていると言えるでしょう。
『Ghost of Yōtei』はこんな人にはおすすめできない
- 戦闘やアクションをたっぷり味わいたい人: 前作と比較して、本作の戦闘は爽快感に欠け、特に序盤は単調に感じられる部分が多いです。また、モーションの重さや、敵の理不尽な攻撃、カメラワークの問題など、アクションゲームとしての完成度には疑問符が付きます。 複雑なコンボや、流麗な剣捌き、戦略的な立ち回りを期待している方にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。純粋に「アクションゲームとしての面白さ」を追求したい方には、他の作品を探すことをお勧めします。
- 意外性のある寄り道や濃厚なサブ物語を求める人: オープンワールドの醍醐味である「偶発的な出会い」や「予想外の展開」が、本作ではやや希薄です。サブクエストも定型的なものが多く、深く練り込まれた物語や、プレイヤーの選択によって大きく変化するような要素は少ないです。 「メインストーリーそっちのけで寄り道に夢中になる」ような体験を期待している方にとっては、本作のサブコンテンツは「作業」に感じられてしまう可能性が高いでしょう。探索の目的が明確すぎてしまう点が、逆に自由な探求の喜びを奪っていると言えます。
- 前作をプレイ済みで、大きな進化を期待している人: 前作の『Ghost of Tsushima』をやりこんだプレイヤーであれば、本作の『Ghost of Yōtei』に対して、グラフィックやゲームシステムにおいて「劇的な進化」を期待してしまうのは当然です。 しかし、残念ながらグラフィックは順当な進化に留まり、ゲームシステムにおいても、オープンワールドと復讐譚の融合、戦闘の爽快感といった点で、前作以上の感動を得ることは難しいかもしれません。 むしろ、「既視感」や「前作からの停滞」を感じてしまう可能性すらあります。 前作で得た感動をそのまま、あるいはそれ以上に強く味わいたいと期待する方にとっては、やや肩透かしを食らう結果となるかもしれません。 新たな驚きや革新を求めているのであれば、一度冷静に本作の評価を見極める必要があるでしょう。
- 効率的にサクサクとゲームを進めたい人: スキップできないムービーや会話、広大なマップでの長い移動時間など、本作にはプレイヤーのテンポを阻害する要素がいくつか存在します。 ストーリーを早く進めたい、サクサクとクエストをこなしたいというタイプのプレイヤーにとっては、これらの要素がフラストレーションの原因となる可能性があります。 特に、現代のゲームでは時間の効率性が重視される傾向にあるため、本作の設計は一部のプレイヤーにとってはストレスに感じられるかもしれません。
まとめ
さて、ゲーム評論家の桐谷シンジとして、『Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)』の実プレイで感じた、巷の絶賛評価とは異なるガッカリ点を深掘りしてきました。 本作は、確かに息をのむような美しいグラフィックと、重厚な復讐譚という魅力的な要素を兼ね備えています。 しかし、その一方で、私個人としては以下の点で物足りなさを感じずにはいられませんでした。
- グラフィックの美しさは認めつつも、前作からの劇的な進化には乏しく、広大なマップでの移動が単調に感じられ、視覚的な感動が薄れてしまう瞬間があったこと。
- 復讐という感情を軸にしたストーリーと、広大なオープンワールドというゲームシステムとの間で、感情移入の連続性が途切れがちになり、物語の熱量が保ちにくいと感じたこと。特に、親切すぎる設計が、オープンワールド本来の発見の喜びを奪い、「作業感」を生み出してしまっていた点は残念でした。
- 戦闘システムの爽快感が前作よりも低下しており、序盤の単調さや、理不尽に感じる敵の配置、室内戦でのカメラワークの問題などが、アクションゲームとしての体験を損ねていたこと。
- 成長システムが探索に過度に依存しており、「戦闘を通じて強くなる」という喜びよりも、「収集作業」としての側面が強く感じられたこと。サブクエストもバリエーションに乏しく、飽きやすい印象を受けました。
- 二刀流の修行イベントが軽すぎて説得力に欠け、一部のムービーや会話がスキップできないことで、現代のゲームとしてはテンポの悪さが目立ったこと。
正直なところ、数時間遊んだ段階で、物語の展開がおおよそ読めてしまい、ストーリーへの興味が徐々にしぼんでいきました。 戦闘も単調になりがちだったため、常に「楽しい」という気持ちを維持してプレイし続けるのが難しかったです。 グラフィックは文句なしの一級品ですが、それを上回るような、心に深く突き刺さるストーリーテリングや、没入感のあるアクション性を感じられなかったのが、私にとっては非常に残念なポイントでした。
もちろん、これはあくまでゲーム評論家としての私の個人的な見解であり、本作の持つ魅力や楽しさを否定するものではありません。 どのようなゲームも、プレイヤーによって感じ方は様々です。 しかし、もしあなたが「絶賛されているけれど、本当に欠点はないのか?」と疑問に感じていたのであれば、今回のレビューが、あなたのゲーム選びの一助となれば幸いです。
もし私と同じように『Ghost of Yōtei』をプレイして、「ここがガッカリした」「ここが物足りなかった」という点があれば、ぜひコメント欄で教えてください。 皆さんの率直な感想を聞かせていただけると嬉しいです。 それでは、また次のレビューでお会いしましょう!