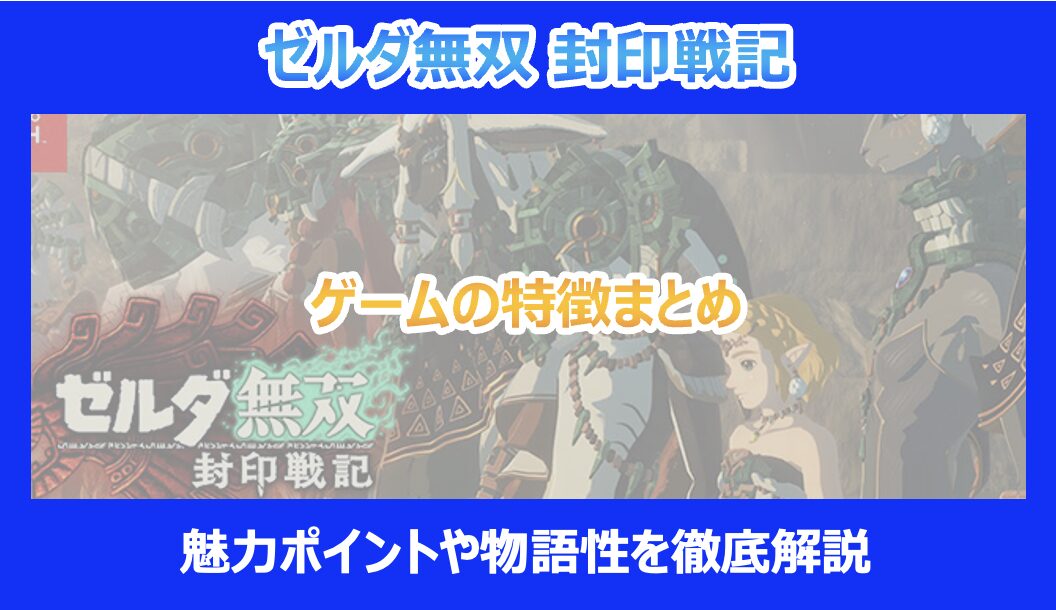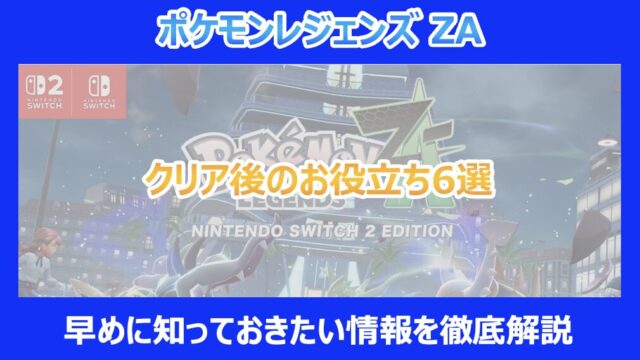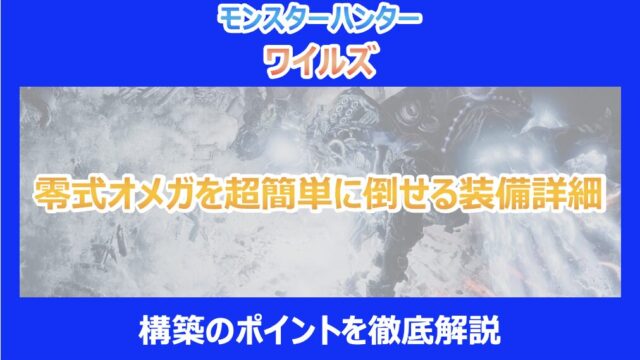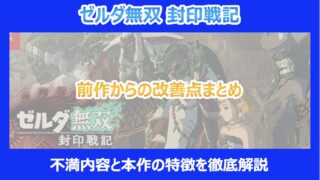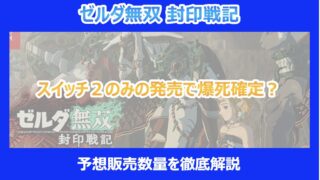ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年11月6日に発売が迫った待望の新作「ゼルダ無双 封印戦記」について、そのゲームシステムやストーリーがどのようなものなのか、非常に気になっていることでしょう。

「ゼルダと無双の組み合わせは面白いの?」「前作とはどう違うの?」「ティアキンで描かれた、あの壮大な物語の裏側が本当に体験できるの?」といった疑問が尽きないはずです。 私自身、東京ゲームショウで幸運にも先行プレイを体験する機会を得て、その完成度の高さと新たな発見に心を躍らせました。
この記事を読み終える頃には、「ゼルダ無双 封印戦記」がどのようなゲームで、どこに注目すべきなのか、その全ての疑問が解決しているはずです。
- ティアキンの世界観で繰り広げられる爽快な無双アクション
- ゼルダやラウルを操作し「封印戦争」の物語を追体験
- 仲間との連携が鍵を握る新システム「シンクストライク」
- ゾナウギアを活用した戦略的で奥深いバトルシステム
それでは解説していきます。

ゼルダ無双 封印戦記とは?ゲームの基本情報を整理
まずは待望の新作「ゼルダ無双 封印戦記」がどのような作品なのか、基本的な情報からおさらいしていきましょう。 すでに多くの情報が公開されていますが、改めて整理することで、本作への理解がより深まるはずです。

発売日と対応機種
「ゼルダ無双 封印戦記」の発売日は2025年11月6日を予定しています。 対応機種はNintendo Switch2です。

前作「ゼルダ無双 厄災の黙示録」と同様に、携帯モードでもTVモードでも、場所を選ばずにハイラルの壮大な戦いを体験できます。 特に、先行プレイでは処理落ちが大幅に改善されている印象を受けましたので、携帯モードでも快適なプレイが期待できるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | ゼルダ無双 封印戦記 |
| 発売日 | 2025年11月6日 |
| 対応機種 | Nintendo Switch2 |
| ジャンル | アクション |
| プレイ人数 | 1〜2人 |
| CERO | 審査予定 |
開発はコーエーテクモゲームスが担当
本作の開発は、前作「ゼルダ無双 厄災の黙示録」に引き続き、コーエーテクモゲームスのω-Force(オメガフォース)が担当しています。 「無双」シリーズといえば、コーエーテクモゲームスのお家芸とも言える看板タイトルです。 「真・三國無双」や「戦国無双」シリーズで培われた、「一騎当千の爽快感」をコンセプトにしたアクションゲーム開発のノウハウは、他の追随を許しません。
任天堂のゼルダチームが監修する密度の濃い世界観と、コーエーテクモゲームスが誇る爽快なアクションが融合することで、唯一無二のプレイ体験が生まれるのです。 この強力なタッグは、前作でも見事な化学反応を見せてくれました。 「ゼルダの伝説」という謎解きや探索が魅力のIPを、いかにして無双アクションに落とし込むか。
その答えとして、単に敵をなぎ倒すだけでなく、シーカーアイテムを使ったギミック解除や、巨大な神獣を操作するパートなど、ゼルダらしい遊びが随所に盛り込まれていました。 本作では、その経験を活かし、さらに洗練されたゲームデザインが期待されます。
物語の時系列と舞台設定
本作の物語は、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」で描かれた、遥か昔の時代に起こった**「封印戦争」**が舞台となります。 これは、「ティアーズ オブ ザ キングダム」において、龍の泪を通じて断片的に語られた、初代ハイラル国王ラウルとその妻ソニア、そしてゼルダが魔王ガノンドロフと戦った、あの伝説の戦いを指します。
「ティアーズ オ- ザ キングダム」では、過去の出来事としてムービーシーンで描かれるのみでしたが、「封印戦記」ではプレイヤー自身がその当事者となり、ハイラル王国の存亡をかけた壮絶な戦いに身を投じることになります。 ハイラル城がまだ空に浮かんでおらず、始まりの大地にあった頃の、緑豊かなハイラル王国を駆け巡ることができるのです。 これはシリーズのファンにとって、まさに夢のような体験と言えるでしょう。
前作「ゼルダ無双 厄災の黙示録」との繋がり
前作「ゼルダ無双 厄災の黙示録」は、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の100年前に起こった「大厄災」を描くif(もしも)の物語でした。 対して、本作「封印戦記」は「ティアーズ オブ ザ キングダム」の過去、つまり正史の物語を描く作品となります。
直接的なストーリーの繋がりはありませんが、「厄災の黙示録」で確立された「ゼルダ無双」としてのゲームシステムの多くは、本作にも引き継がれ、正統進化を遂げています。 「厄災の黙示録」をプレイしていれば、よりスムーズにゲームに入り込めることは間違いありませんが、物語は独立しているため、本作から初めて「ゼルダ無双」シリーズに触れる方でも全く問題なく楽しむことができます。
物語性を徹底解剖!ティアキンで語られなかった「封印戦争」の真実
本作最大の魅力は、なんといってもその物語性にあります。 「ティアーズ オブ ザ キングダム」で多くの謎を残した「封印戦争」の全貌が、ついに明らかになるのです。 先行プレイで体験できた序盤のストーリーや、そこから読み取れる考察を交えながら、本作の物語の核心に迫ります。

先行プレイで判明した序盤のストーリー展開
今回の先行プレイは、フィローネの森の地底に、ゼルダ、ラウル、ミネル、そして二人のハイリア人が調査に赴く場面から始まりました。 どうやらミネルは、地底に眠るゾナウ文明の遺産を研究しており、その調査の護衛として一行が同行しているようです。
ミネルのセリフから、彼女自身も地底の奥深くへは足を踏み入れたことがないと語られており、未知の領域への探索であることが伺えます。 この時点で、ゼルダはラウルとソニアから戦闘訓練を受け、光の力を宿したゾナニウムの剣を手に、戦う力を身につけていることが判明しました。 これは、ただ守られるだけだった姫が、自らの意志で戦う覚悟を決めた重要な描写です。
地底を進む一行は、打ち捨てられたゴーレムや危険な生物と遭遇しながら、ミネルの研究施設を目指します。 その道中では、ゾナウギアを駆使した戦闘や、多数のゴーレムとの大規模な戦闘が繰り広げられました。 そして、デグガーマやイワロックといった巨大なボスとの連戦を経て、物語の核心に迫る古代の遺跡へと足を踏み入れていきます。 残念ながら、先行プレイは巨大な扉のギミックを解いたところで時間切れとなりましたが、この先に「封印戦争」の引き金となる重大な発見があることを予感させる、非常に密度の濃い内容でした。
ハイラル王国建国以前に存在した「邪(ジャ)」とは?
先行プレイの後半で、非常に興味深い敵が登場しました。 それは、正気(しょうき)で作られたかのような異形のゴーレムです。 ゼルダはこれを「邪(ジャ)」と呼んでいました。 「ティアーズ オブ ザ キングダム」におけるガノンドロフの力の源は「瘴気(しょうき)」でしたが、この「邪」はそれとは異なる概念のようです。 というのも、この物語の時点では、まだガノンドロフは魔王と化していません。 つまり、この「邪」はガノンドロフが生み出したものではなく、それ以前からハイラルの地に存在していた根源的な悪意である可能性が示唆されています。
公式の設定資料集「マスターワークス」によると、ラウルとソニアはハイラル王国を建国する前、各地に点在する「邪」を鎮める旅をしていたと記されています。 「ブレス オブ ザ ワイルド」で登場した「怨念」に近い、実体を持たない悪意のようなものが、「封印戦記」ではゴーレムなどの形を借りて具現化しているのかもしれません。 この「邪」の正体こそが、「封印戦争」の根本的な原因であり、本作の物語を貫く重要なテーマとなるのではないでしょうか。
「ティアーズ オブ ザ キングダム」へと繋がる伏線
本作は、「ティアーズ オブ ザ キングダム」の過去を描く物語である以上、未来(ティアキンの時代)へと繋がる数多くの伏線が散りばめられているはずです。 例えば、先行プレイの舞台となった地底には、「聖なる力が満ちる場所」が点在していました。 これは、地上の魔物を浄化し、光を灯す「破魔の根」が育つ場所である可能性が高いです。

破魔の根と地上の破魔の祠の関係性など、「ティアキン」でも謎に包まれていた部分が、本作で明らかになるかもしれません。 また、ロード画面に表示されるマップは、中央に旧ハイラル城が描かれているものの、周囲に不自然な空白が広がっています。 これは物語の進行に合わせて、「ティアキン」で龍の泪が落ちていた場所など、重要なロケーションが追加されていくことを示唆しているように思えます。 本作をプレイすることで、「ティアーズ オブ ザ キングダム」の物語を、より一層深く理解できるようになることは間違いないでしょう。
ゼルダが戦う理由とその成長
「ティアーズ オブ ザ キングダム」の過去視において、ゼルダは主にソニアと共にあり、直接的な戦闘シーンは多く描かれませんでした。 しかし本作では、彼女は紛れもなく主人公の一人として、最前線で剣を振るいます。 ラウルとソニアによる特訓の末、光の力を自在に操り、無数の敵をなぎ倒していく姿は、これまでのシリーズで描かれてきたゼルダ姫のイメージを覆すものです。
故郷ではない時代に飛ばされ、戸惑いながらも、ハイラルを救うために自ら戦うことを選んだ彼女の覚悟と成長の物語は、本作の大きな見どころの一つとなるでしょう。 彼女がどのようにして戦士としての力を開花させていくのか、その過程をプレイヤー自身が体験できるのです。
ゲームシステムと新要素を徹底解説!爽快感と戦略性の融合
「ゼルダ無双 封印戦記」は、ただのキャラクターゲームではありません。 「無双」シリーズならではの爽快感をベースに、ゼルダの世界観を巧みに落とし込んだ、戦略性の高いアクションゲームとして完成されています。 ここでは、先行プレイで判明したゲームシステムと、胸が熱くなる新要素について詳しく解説します。

「無双アクション」と「ティアキン」の操作感が奇跡の融合
まず驚いたのが、その操作感です。 キャラクターを動かした瞬間、「これはティアキンだ」と直感するほど、移動やカメラ操作のフィールが忠実に再現されていました。 無双シリーズ特有のアクションを行いながらも、フィールドを探索している感覚はまさしく「ゼルダの伝説」そのもの。
このシームレスな融合が、没入感を極限まで高めています。 前作「厄災の黙示録」も素晴らしい出来でしたが、本作ではゲーム機本体の性能向上も相まって、より広大で美しいフィールドを、ストレスなく駆け巡ることができます。 敵の大群をなぎ倒す無双の爽快感と、ハイラルの大地を冒険するゼルダの探索感。 この二つの魅力が、かつてないレベルで両立されているのです。
戦略の鍵を握る「ゾナウギア」システム
「ティアーズ オブ ザ キングダム」の象徴的な要素であった「ゾナウギア」は、本作のバトルシステムにおいても中心的な役割を担います。 先行プレイでは、「火龍の頭」と「タイマー爆弾」を使用できました。
- 火龍の頭: 前方に広範囲の炎を放射します。その場に設置することも可能で、他の攻撃と組み合わせることで継続的なダメージを与えられます。前作の「ファイアロッド」の上位互換と言える性能です。
- タイマー爆弾: バッテリーを消費することで、何度でも投げることができます。威力が高く、特にイワロックの腕を破壊するなど、特定の部位を持つボスに対して絶大な効果を発揮しました。
これらのゾナウギアは、キャラクターの固有アクションとは別に、Rボタンからいつでも使用可能です。 前作の「シーカーストーンアイテム」に近い役割ですが、本作ではバッテリーの管理が重要になります。 「ティアキン」とは異なり、バッテリーは一度使い切らないと自動回復が始まりません。 そのため、無闇に使うのではなく、戦況を見極めて効果的に使用する戦略性が求められます。 道中でスペアバッテリーを拾うことで回復も可能なため、リソース管理も攻略の鍵となるでしょう。
爽快感抜群の新アクション「追撃」
本作で追加された新アクションの中でも、特に爽快だったのが「追撃」システムです。 これは、タイマー爆弾などで遠くにいるボスのダウンを奪った際に、瞬時に敵との距離を詰めて攻撃を仕掛けられるというもの。 前作では、遠くの敵のダウンを取っても、駆け寄る間に起き上がってしまうというジレンマがありましたが、本作ではその心配は無用です。 ボタン一つで、まるで「ブレス オブ ザ ワイルド」のラッシュのような高速移動で敵に肉薄し、弱点への攻撃を叩き込めます。 このスピーディーなアクションは、ゲーム全体のテンポを向上させており、一度味わうと病みつきになること間違いなしです。
仲間との連携が熱い「シンクストライク」
本作を象徴する新システムが、この「シンクストライク」です。 これは、二人のプレイアブルキャラクターの「シンクゲージ」が最大まで溜まり、かつ二人が近くにいる時に発動できる、超強力な合体必殺技です。 その威力は通常の必殺技の約2倍にも及び、ボスの体力を一気に奪い去ります。 ゲージが溜まりにくく、発動条件もやや厳しいですが、その分、繰り出せた時の達成感と威力は絶大です。
先行プレイでは、2種類のシンクストライクを確認できました。
- ゼルダ&ラウル: 二人が光のビームを放ち、それを左右のスティックで別々に操作して敵を攻撃します。複数のボスを同時に相手にする場面などで非常に有効でしょう。
- ラウル&ミネル: ミネルが出現させた無数の剣をラウルが操り、広範囲の敵を殲滅します。大量の雑魚敵を一掃するのに適しています。
キャラクターの組み合わせによって技の内容が変化するため、どのキャラクターを同時に出撃させるかという戦略性が生まれます。 お気に入りのキャラクター同士のシンクストライクを探すのも、本作の楽しみ方の一つになりそうです。
ボス戦を有利に進める「弱点属性」
ボス戦の戦略性を深める要素として、「弱点属性」が導入されました。 先行プレイで戦ったイワロックの弱点(背中の鉱床)には、鋼のようなUIが表示されていました。 これは、爆弾系の攻撃が特に有効であることを示唆しています。 今後、炎、氷、雷といった属性を持つ敵が登場し、それぞれに有効な攻撃手段が設定されることは間違いないでしょう。 例えば、炎の敵には氷属性の攻撃が、水の敵には雷属性の攻撃が弱点となる、といった具合です。 キャラクターやゾナウギアの特性を理解し、ボスの弱点に合わせて的確な攻撃を選択することが、攻略の重要なポイントとなります。
キャラクターを強化する「聖なる力が満ちる場所」
フィールドの特定の場所には、光の力が満ちているエリアが存在します。 このエリア内では、ゼルダやラウルといった光の力を使うキャラクターの固有技ゲージが高速で溜まるようになり、戦闘を有利に進めることができます。 単に敵を倒すだけでなく、こうした地形効果を活かして立ち回ることも、本作の戦術の一つです。 どのキャラクターをどの場所に配置し、どのタイミングで攻勢に出るか。 無双アクションに、シミュレーションゲームのような戦略性が加わったと言えるでしょう。
個性豊かなプレイアブルキャラクター!アクションと特徴を解説
「ゼルダ無双」シリーズの魅力は、なんといってもリンク以外のキャラクターを操作できる点にあります。 本作では、伝説の「封印戦争」を戦い抜いた英雄たちを、自らの手で操作できます。 先行プレイで確認できた3人のキャラクターについて、そのアクション性能や特徴を詳しく見ていきましょう。
光の矢を放つ聖なる姫「ゼルダ」
本作のゼルダは、光の力を宿した剣と弓を操り、広範囲の敵をなぎ払うことを得意とします。 特筆すべきはその雑魚処理能力の高さです。 フープのように回転する光の刃を放ちながら移動する「強5攻撃」は、攻撃範囲、移動性能、敵の巻き込み性能すべてが優秀で、序盤はこの技を連発するだけで戦場を支配できました。 一方で、単体のボスに対する火力はやや控えめな印象です。 光の矢をピンポイントで弱点に当てることで、ボスの弱点ゲージを強制的に露出させることができるため、テクニカルな立ち回りが求められるキャラクターと言えるでしょう。 足が速く、手数も多いため、ヒットアンドアウェイで戦場をかき乱す遊撃手のような役割が適しています。
光の力で万物を操る初代ハイラル王「ラウル」
初代ハイラル王ラウルは、ウルトラハンドのように光の力で巨大な剣を自在に操り、敵を粉砕するパワーファイターです。 その一撃は非常に重く、攻撃範囲も広いため、対ボス性能、雑魚処理能力ともに高水準。 特に、左右から光のビームを放って敵を挟み込む「強4攻撃」は、広範囲の敵を一網打尽にできます。 弱点は、移動速度がやや遅いこと。 しかし、その欠点を補って余りあるほどの圧倒的な攻撃性能を誇ります。 どっしりと構え、敵軍の正面に立ちはだかり、その豪腕で戦況を覆す、まさに王の名にふさわしいキャラクターです。
ゴーレムを率いる魂の賢者「ミネル」
魂の賢者ミネルは、ゴーレムやゾナウギアを召喚して戦う、トリッキーなテクニカルキャラクターです。 序盤の技構成はやや地味で、火力も控えめな印象を受けましたが、これは彼女が「伸びしろ系」のキャラクターであることを示唆しています。 物語を進め、様々なゾナウギアを収集していくことで、召喚できる兵器が増え、性能が飛躍的に向上していくのではないでしょうか。 トゲ付きの車輪で敵を轢きながら移動する「強4攻撃」は、移動と攻撃を兼ね備えており、道中の雑魚を蹴散らしながら進むのに便利です。 プレイヤーの知識と工夫次第で、無限の可能性を秘めた大器晩成型のキャラクターと言えるでしょう。
他に操作可能なキャラクターは登場するのか?
先行プレイでは上記の3人のみが使用可能でしたが、製品版ではさらに多くのキャラクターが登場することは確実です。 まず筆頭に挙げられるのは、ラウルの妻であり、時の力を操るソニアでしょう。 そして、「ティアーズ オブ ザ キングダム」でも活躍した、風、水、雷、炎の賢者たちの子孫が登場したように、その祖先である古代の賢者たちもプレイアブルキャラクターとして参戦する可能性が非常に高いです。 個性豊かな賢者たちを操作し、それぞれの特殊能力を駆使して戦うことを想像するだけで、期待に胸が膨らみます。
前作からの進化と気になるポイント
最後に、前作「ゼルダ無双 厄災の黙示録」と比較して、本作がどのように進化したのか、そして製品版に向けて気になるポイントをまとめます。
グラフィックとパフォーマンスの劇的な向上
最も顕著な進化点は、グラフィックとパフォーマンスです。 「ティアーズ オブ ザ キングダム」のエンジンをベースにしているためか、キャラクターモデルやフィールドのテクスチャ、光の表現などが格段に美しくなっています。 特に地底の暗闇を照らす光の表現は、思わず息をのむほどの綺麗さでした。 そして何より、前作で一部のプレイヤーを悩ませた処理落ちが、先行プレイの範囲では一切感じられませんでした。 大量の敵やエフェクトが画面内に表示されても、フレームレートは安定しており、非常に快適なプレイ体験でした。 これは、無双アクションの爽快感に直結する重要な改善点です。
UI/UXの改善点
ユーザーインターフェース(UI)やユーザーエクスペリエンス(UX)も、より洗練されている印象を受けました。 ゾナウギアや固有技を選択するメニューは直感的で分かりやすく、戦闘中に迷うことはありませんでした。 また、「追撃」システムに代表されるように、プレイヤーが「もどかしい」と感じるであろう部分を徹底的に潰し、ストレスなく爽快感に集中できるような調整が随所に施されています。 「ティアキン」の快適な操作性を、無双のフォーマットに見事に落とし込んでいると言えるでしょう。
やり込み要素とボリュームへの期待
無双シリーズの醍醐味といえば、本編クリア後の豊富なやり込み要素です。 前作「厄災の黙示録」でも、ハイラル全土を舞台にした膨大な数のバトルチャレンジや、キャラクター育成、武器収集など、遊び尽くせないほどのボリュームが用意されていました。 本作でも、ストーリーモード以外に、特定の条件下でミッションに挑むチャレンジモードや、高難易度モードなどが実装されることが期待されます。 また、ゾナウギアの種類がどれだけ増えるのか、キャラクターの育成システムはどのようなものになるのかなど、まだまだ謎に包まれた部分も多く、その全貌が明らかになるのが今から待ち遠しいです。
まとめ
「ゼルダ無双 封印戦記」は、単なるスピンオフ作品ではありません。 「ティアーズ オブ ザ キングダム」で描かれた壮大な物語のミッシングリンクを埋める、正史にして、もう一つの「ゼルダの伝説」です。 コーエーテクモゲームスが磨き上げた「一騎当千の爽快感」と、ゼルダチームが作り上げた「濃密な世界観と物語」が高次元で融合し、これまでにないアクション体験を生み出しています。
先行プレイを終えた今、私が断言できるのは、本作が「ゼルダの伝説」ファンはもちろん、全てのアクションゲームファンにとって、必プレイの一本になるということです。 ハイラルの未来を賭けた伝説の戦い「封印戦争」。 その結末を、ぜひあなた自身の目で見届けてください。 発売日である2025年11月6日が、今から待ちきれません。