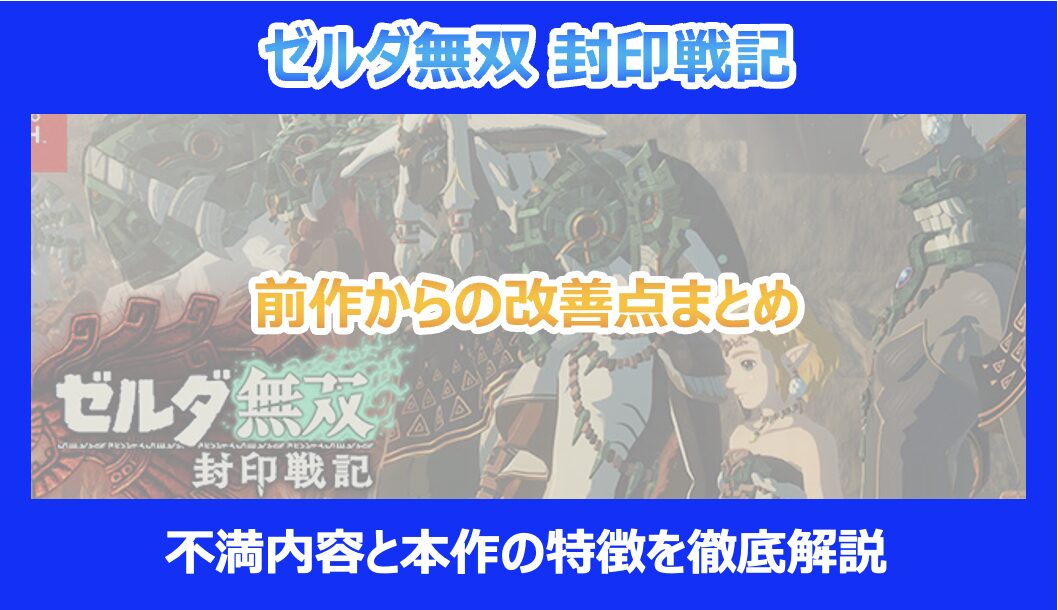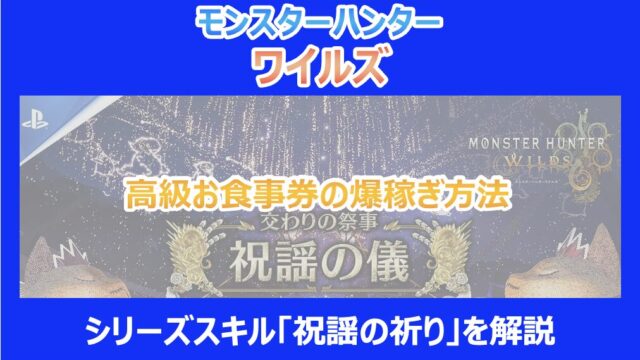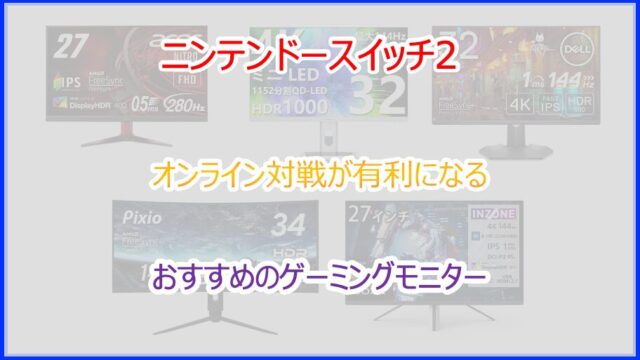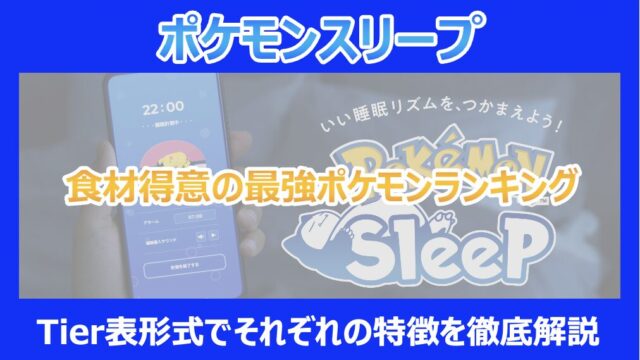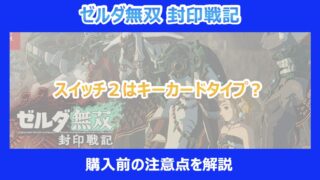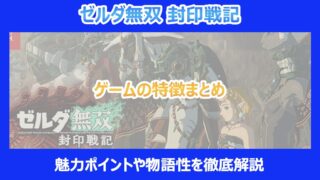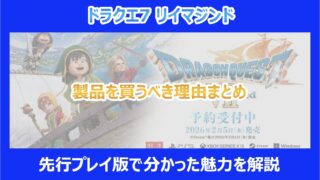ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年11月6日に発売される待望の新作『ゼルダ無双 封印戦記』について、特に前作『ゼルダ無双 厄災の黙示録』から何がどう変わったのか、気になっていることでしょう。 「前作で不満だった処理落ちは改善された?」「戦闘システムはもっと爽快に進化した?」といった疑問を抱えているのではないでしょうか。

ご安心ください。 私自身、先日開催された東京ゲームショウで本作を先行プレイし、その進化を肌で感じてきました。
この記事を読み終える頃には、『ゼルダ無双 封印戦記』が前作からどれほどの進化を遂げたのか、その魅力と改善点に関するあなたの疑問がすべて解決しているはずです。
- 前作の不満点だった処理落ちの完全解消
- 爽快感を加速させる新アクションシステムの追加
- 戦略の幅を広げる進化したゾナウギアと協力技
- 先行プレイで判明した各キャラクターの性能詳細
それでは解説していきます。

ゼルダ無双 封印戦記|前作『厄災の黙示録』からの主な改善点
『ゼルダ無双 封印戦記』は、単なる続編ではありません。 前作『ゼルダ無双 厄災の黙示録』をプレイした多くのファンが感じていたであろう、いくつかの課題点を見事に克服し、正統進化を遂げた作品と言えるでしょう。

ここでは、先行プレイで特に顕著だと感じた「改善点」に焦点を当てて、具体的に解説していきます。
①グラフィックとパフォーマンスの大幅向上|処理落ちは解消されたか
前作『厄災の黙示録』で最も多くのプレイヤーから指摘されたのが、敵が密集した際の「処理落ち」でした。 一騎当千の爽快感が魅力の無双シリーズにおいて、このフレームレートの低下は没入感を大きく損なう要因となっていました。
結論から言うと、本作『封印戦記』では、先行プレイの範囲で処理落ちは一切確認できませんでした。

敵の数がどれだけ増えようと、派手なエフェクトが飛び交う必殺技やシンクストライクを繰り出そうと、その動作は驚くほど滑らか。 これは、ゲーム機本体の性能向上もさることながら、開発陣の最適化への強いこだわりを感じさせます。
さらに、グラフィック全体の質も格段に向上しています。 特に印象的だったのは、地底ステージにおける光の表現です。 キャラクターが持つ光源が壁や水面に反射し、周囲をリアルに照らし出す様子は、まるで『ティアーズ オブ ザ キングダム』(以下、ティアキン)をプレイしているかと錯覚するほどの美しさでした。
イワロックの岩肌の質感や、キャラクターの髪の毛一本一本の揺れ動きまで、細部にわたって作り込まれており、「無双ゲーム」のグラフィックレベルを新たな次元へと引き上げています。 前作の処理落ちに悩まされた方ほど、この快適かつ美麗なゲーム体験には感動を覚えるはずです。
②アクションの爽快感アップ|新システム「追撃」と「カウンター」
無双アクションの核となる戦闘システムも、より爽快で戦略的に進化しています。
ダウンさせた敵を見逃さない「追撃」システム
前作では、爆弾などで遠くのボスをダウンさせても、駆け寄る間に敵が起き上がってしまい、弱点ゲージを攻撃するチャンスを逃すことがありました。 このもどかしい問題を解決するのが、新システム**「追撃」**です。
本作では、敵をダウンさせると、距離が離れていても瞬時に相手の懐へ急接近できるようになりました。 これにより、ダウンさせたら即座に弱点攻撃へと移行でき、戦闘のテンポが格段に向上しています。 この動きは、まるで『ブレス オブ ザ ワイルド』のグリッチ技「TCR(Thunderclap Rush)」を彷彿とさせるほどのスピード感で、一度体験すると病みつきになる爽快感がありました。
戦況を覆す「カウンター攻撃」
今作から、敵が赤いオーラをまとって強力な攻撃を仕掛けてくることがあります。 一見するとピンチの場面ですが、このタイミングでキャラクター固有の技(十字キー上でセット可能)を発動すると、**「カウンター攻撃」**が成立します。
カウンターに成功すると、敵の強力な攻撃をキャンセルさせ、さらに大きなダウンを奪うことができます。 これにより、ただ攻撃を繰り返すだけでなく、敵の動きを見極めて的確にカウンターを狙うという、アクションゲームならではの駆け引きが生まれました。 ボスの強力な一撃を華麗にいなし、反撃に転じる瞬間は、本作屈指の快感ポイントと言えるでしょう。
③ゾナウギアシステムの進化|バッテリー消費と永続使用
前作の「シーカーストーン」に代わる新たなシステムとして、「ゾナウギア」が登場します。 これもまた、ティアキンの要素を取り入れつつ、無双アクションとして最適化された素晴らしいシステムです。
前作のシーカーストーンアイテムは、一度使用するとクールタイムが発生し、連発できないという制約がありました。 しかし、本作のゾナウギアは、ティアキン同様**「バッテリー」を消費する限り、何度でも連続して使用可能**です。
先行プレイで使えたゾナウギアは以下の通りです。
| ゾナウギア | 特徴 |
|---|---|
| 火龍の頭 | 前方に広範囲の炎を放射。設置して自動攻撃させることも可能で、前作のファイアロッドの上位互換のような使い方ができる。 |
| タイマー爆弾 | バッテリーがある限り、何個でも投げられる。前作のリモコン爆弾のように扱え、イワロックの腕を破壊するなど、部位破壊にも極めて有効。 |
バッテリーは、使い切ると自動で回復が始まります。 また、道中に落ちている「スペアバッテリー」を拾うことで、即座に回復させることも可能です。 クールタイムの待ち時間がなくなったことで、ゾナウギアを戦術の軸として積極的に活用できるようになり、戦闘の自由度が大幅に向上しています。
④キャラクター操作の多様性と戦略性|新要素「シンクストライク」
キャラクターを切り替えながら戦う無双の楽しさも、新要素によってさらに深まっています。 その目玉となるのが、協力必殺技**「シンクストライク」**です。

これは、操作キャラクターと仲間キャラクターの「シンクゲージ」が最大まで溜まった状態で、2人が近くにいると発動できる合体技です。 その威力は通常の必殺技の約2倍と絶大で、ボスの体力を一気に削り取ることができます。
ゲージが溜まりにくく、2人が近くにいる必要があるなど、発動条件はやや厳しいですが、それに見合うだけの圧倒的な破壊力と、キャラクターの組み合わせによって変化するド派手な演出は必見です。 どのキャラクターとどのキャラクターを組ませて戦うか、誰のゲージを優先的に溜めるかといった戦略性が生まれ、単独で戦うだけでは味わえない共闘の楽しさを提供してくれます。
⑤UIとロード画面の洗練|ティアキン要素の踏襲
ユーザーインターフェース(UI)やロード画面も、ティアキンに近いデザインに刷新され、非常に洗練された印象を受けました。
特に興味深いのがロード画面です。 先行プレイでは、中央に旧ハイラル城が描かれているだけでしたが、その周りには不自然な空白が広がっていました。 これは、ティアキンの地上絵のように、物語の進行度に合わせて新たな絵柄やモチーフが追加されていくことを示唆しているのかもしれません。 ゲームの進行がビジュアルで表現されるという、遊び心あふれる演出に期待が高まります。
⑥ボスの弱点システムの深化|属性相性の追加
ボスの弱点システムにも変化が見られました。 前作では、特定の攻撃で弱点ゲージを出すというシンプルなものでしたが、今作では**「属性」**の概念が加わった可能性があります。
例えば、先行プレイで戦ったイワロックの弱点ゲージは、鉱石のような硬質なUIで表示されていました。 そして、この弱点は「タイマー爆弾」による爆破攻撃で容易に露出させることができました。 これは、弱点に「鋼」や「岩」のような属性が付与され、特定の攻撃タイプ(爆弾系など)が特効を持つことを示唆しています。
今後、炎、氷、雷といった属性を持つ敵が登場した場合、それぞれに対応したキャラクターやゾナウギアを使い分ける必要が出てくるでしょう。 これにより、ボス戦の攻略に更なる深みが生まれることは間違いありません。
ゼルダ無双 封印戦記|先行プレイで判明した新要素と考察
前作からの改善点だけでなく、『封印戦記』には多くの魅力的な新要素や、考察の余地がある謎が散りばめられています。 ここでは、ゲーム評論家としての視点から、特に気になったポイントを深掘りしていきます。
①物語の舞台と導入|フィローネの森の地底から始まる物語
本作の物語は、ゼルダ、初代ハイラル王ラウル、そして賢者ミネル、さらに2人のハイリア人を加えた5人が、フィローネ地方の地底を調査するところから始まります。

ラウルとミネルは、かつて地上を平定した後、彼らの祖先が残したゾナウ文明の遺跡を調査するために地底を訪れたようです。 しかし、ミネルの研究施設より奥は、彼女たちにとっても未踏の領域。 そこに待ち受けるものとは一体何なのか。 ティアキンでは断片的にしか語られなかった「封印戦争」以前の時代が、彼らの視点で詳細に描かれていくことになります。
操作感は驚くほどティアキンに近く、フィールドを探索する感覚は無双ゲームというよりアクションRPGに近いです。 広大な地底空間に眠る謎を解き明かしていく、壮大な物語の幕開けを予感させます。
②新たな敵「ジャ」の存在|正気とは異なる謎の概念
先行プレイの後半で、**「ジャ」**と呼ばれる謎の敵が出現します。 これは正気で赤黒く染まったような見た目のゴーレムで、ゼルダはこの敵を明確に「ジャ」と呼称していました。
重要なのは、この時点ではまだガノンドロフは魔王化していないはずだという点です。 つまり、この「ジャ」はガノンドロフが生み出したものではない、別の存在である可能性が高いのです。 公式設定資料集によれば、ハイラル建国以前から世界各地には「邪」が点在し、ラウルとソニアはそれを鎮める旅をしていたとされています。
この「ジャ」は、ティアキンにおける「正気」が生物を強化・汚染するものであるのに対し、ゴーレムのような無機物さえもコピーして単独で実体化する能力を持つようです。 もしかすると、『ブレス オブ ザ ワイルド』で語られた「怨念」に近い、より根源的な負のエネルギーなのかもしれません。 この「ジャ」の正体が、封印戦争の引き金となる重要な鍵を握っているのではないでしょうか。
③プレイアブルキャラクターの性能と技|ゼルダ・ラウル・ミネルを徹底解説
ここでは、先行プレイで操作可能だった3人のキャラクターの性能や技について、詳細なレビューをお届けします。
光の力で戦う王女「ゼルダ」
ソニアとラウルの特訓により、光の力を操って戦えるようになったゼルダ。 その戦闘スタイルは、広範囲を薙ぎ払う技が多く、雑魚敵の集団を一掃する能力に長けています。 動きもスピーディーで、初心者でも扱いやすいキャラクターと言えるでしょう。
- 特徴: 雑魚処理能力は高いが、単体のボスに対する火力はやや低め。手数で押していくタイプ。
- 強攻撃1: 光の弓矢を放つ。前作のリンクのユニークアクションに似ているが、上下にも照準を動かせるよう改善されている。
- 強攻撃5: 本作のゼルダを象徴する超強力な技。巨大な光の輪をフラフープのように回しながら移動し、敵を巻き込みながら進む。最後に巨大な光の熊(?)を放ってフィニッシュ。攻撃範囲、移動性能、巻き込み性能の全てが優秀で、序盤はこの技を連打するだけで突き進めるほどの性能でした。
- 固有技: 前方に光の矢を集中させる「光の五月雨」や、リーチの長いビームを放つ「貫く光」など、遠距離から安全に攻撃できる技が揃っています。
光の合剣を操る初代ハイラル王「ラウル」
威厳あふれる初代ハイラル王ラウルは、その見た目に違わぬパワーファイター。 光の力で生み出した巨大な剣を、ウルトラハンドで豪快に振り回して戦います。
- 特徴: 攻撃力、攻撃範囲ともに最高クラス。対ボス戦におけるエースアタッカー。ただし、移動速度はやや遅め。
- 強攻撃1: 前方広範囲をゾナウの体験で薙ぎ払う。ボタン追加入力で攻撃時間を延長でき、雑魚処理に最適。
- 強攻撃4: 両手から放った光のビームを中央で交差させる。左右の広範囲をカバーできる非常に強力な技。
- 固有技: 前方に光の柱を突き出す「光創術・上壁」や「光創術・衝天」など、近接戦闘で真価を発揮する技が多い。カウンターを狙うには、敵をギリギリまで引きつける勇気が必要です。
- スマッシュ攻撃: 手で三角形を作り、額の第3の目からビームを発射する。もはや気功波の領域です。
ゴーレムを操る賢者「ミネル」
魂の賢者ミネルは、ゴーレムやゾナウギアを召喚して戦う、テクニカルなキャラクターです。
- 特徴: 先行プレイの段階では、技がやや地味で火力も低く、最も扱いにくい印象でした。しかし、これは彼女が**「大器晩成型」**のキャラクターであることを示唆しているのかもしれません。物語を進めて強力なゾナウギアを集めることで、性能が飛躍的に向上する可能性を秘めています。
- 強攻撃1: 2体のゴーレムを召喚し、矢を放たせる。
- 強攻撃4: トゲ付きのタイヤが付いた車を召喚し、それに乗って敵を轢きながら移動攻撃する。移動と攻撃を同時に行える便利な技。
- スマッシュ攻撃: 大量のゴーレムを召喚し、一斉に攻撃させる。数の暴力で敵を圧倒します。
④協力技「シンクストライク」の詳細|組み合わせによる効果の違い
絶大な威力を誇るシンクストライクは、キャラクターの組み合わせによって演出と効果が変化します。
- ゼルダ&ラウル: 2人がそれぞれ光のビームを放ち、プレイヤーはLスティックとRスティックで2本のビームを個別に操作できます。 複数のボスや広範囲の敵を同時に攻撃できるため、非常に汎用性が高いです。
- ラウル&ミネル: ミネルが召喚した4本の剣をラウルが操り、高速で敵に投げつけます。 最後に無数の剣を前方に射出する、圧倒的な手数で敵を殲滅する攻撃です。雑魚敵の集団に対して特に有効でしょう。
残念ながら「ゼルダ&ミネル」の組み合わせは試すことができませんでしたが、製品版でどのような協力技を見せてくれるのか、今から楽しみです。
⑤聖なる力と地底の謎|浜の根との関連性を考察
ストーリー序盤、ミネルは「地底には聖なる力の満ちる場所が点在している」と語ります。 実際にゲーム後半では、その聖なる力に触れてギミックを解除する場面がありました。

この「聖なる力」が満ちる場所は、ティアキンで地底を照らす**「浜の根」**と深く関係しているのではないでしょうか。 公式設定資料集では、「浜の祠から根が地底に伸びた」という説と、「地底の浜の根から地上に祠が生まれた」という、2つの説が併記されています。 本作では、その起源が明らかになるのかもしれません。 ラウルやゼルダのような光の力を持つ者は、この場所で力が強まるという設定も、浜の根との関連性を強く示唆しています。
⑥タイトル画面とロード画面に隠された伏線
最後に、少しマニアックな考察を。 タイトル画面に映っているのは、おそらくティアキンで「始まりの空島」として浮上する前、地上にあった頃の**「旧ハイラル城」**だと思われます。 そして前述の通り、ロード画面の空白は物語の進行と共に埋まっていく可能性があります。
これは、プレイヤーが体験する封印戦争の物語が、歴史の空白を一つ一つ埋めていくメタファーなのかもしれません。 ゲームをクリアした時、ロード画面にどのような絵が完成しているのか、非常に興味深いポイントです。
まとめ
今回の先行プレイを通じて、『ゼルダ無双 封印戦記』が前作『厄災の黙示録』の正統進化と呼ぶにふさわしい作品であることを確信しました。
- 処理落ちの解消とグラフィックの向上による、ストレスフリーで没入感の高いゲーム体験。
- 「追撃」や「カウンター」といった新アクションによる、より爽快で戦略的な戦闘。
- バッテリー式に進化した「ゾナウギア」と、仲間との絆を感じさせる「シンクストライク」。
- ティアキンでは語られなかった「封印戦争」の真実を描く、重厚なストーリーへの期待。
前作のファンが抱えていた不満点は丁寧に取り除かれ、シリーズのファンなら誰もがニヤリとするであろう新要素がふんだんに盛り込まれています。 これは単なる無双ゲームではなく、紛れもなく「ゼルダの伝説」サーガの新たな1ページを刻む、重要な一作となるでしょう。
発売まであとわずか。 ハイラルの運命を分けた壮大な戦いを、ぜひその手で体験してみてください。