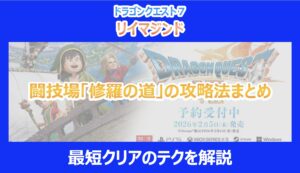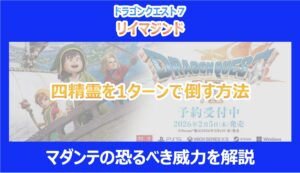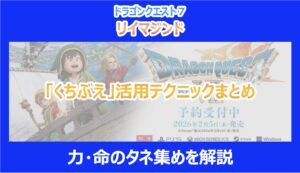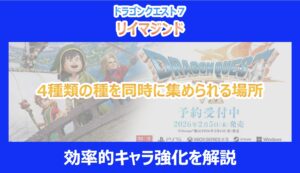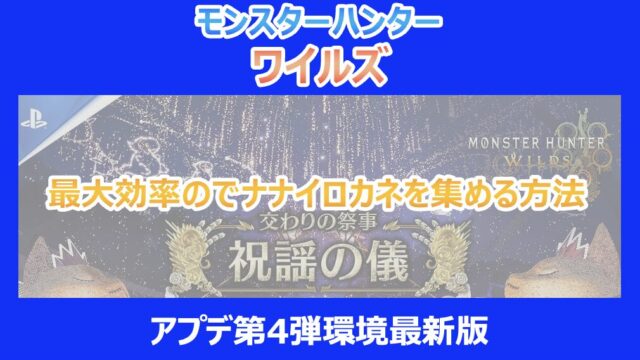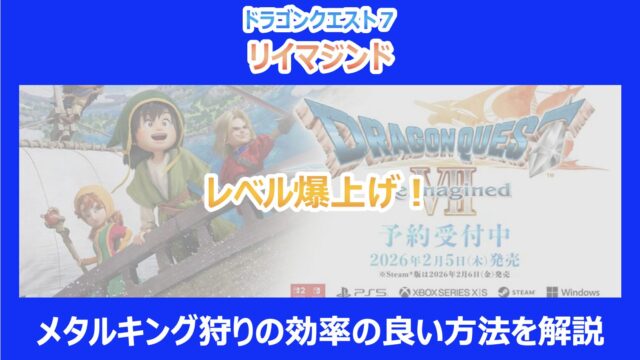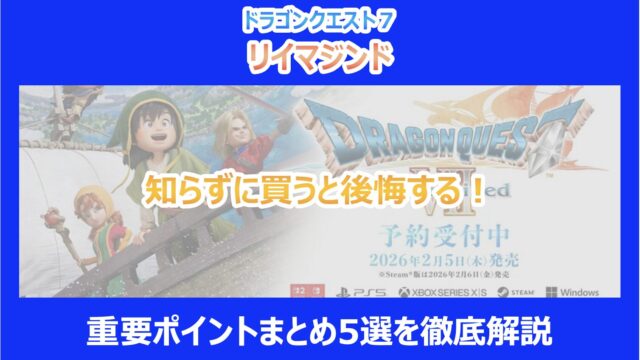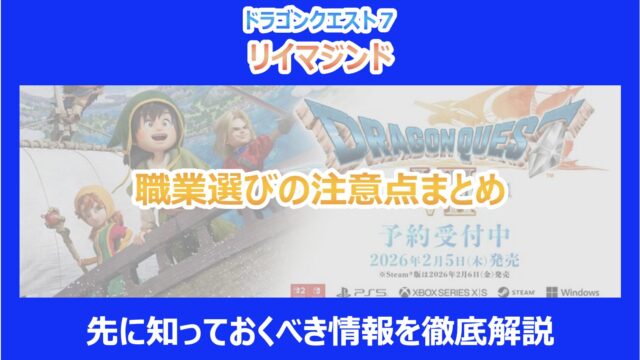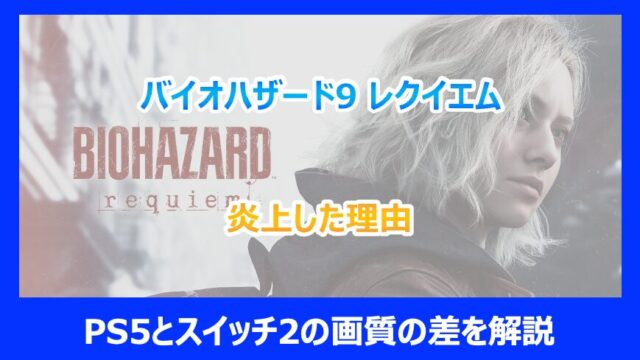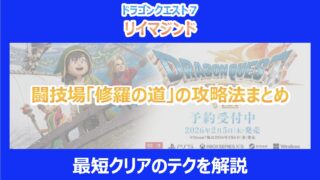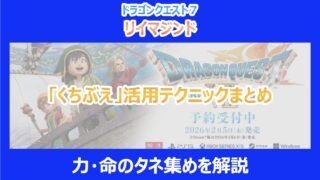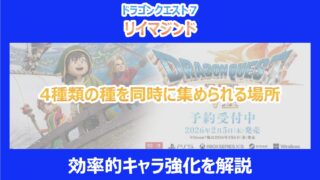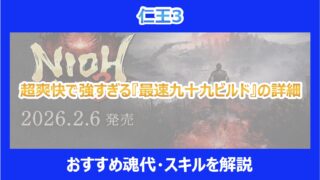ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年10月2日に発売された待望の新作「Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)」について、前作「ゴースト・オブ・ツシマ」から何が変わり、どのような新要素が追加されたのか、特に詳しく知りたいと思っているのではないでしょうか。

この記事を読み終える頃には、「Ghost of Yōtei」の進化したゲームシステムや新たな物語に関するあなたの疑問が、きっと解決しているはずです。
- UIを排した没入感の高い探索システム
- 「構え」を廃し多彩な武器を切り替える新戦闘システム
- 復讐に生きる新主人公「梓」が紡ぐ新たな物語
- 狼の相棒やキャンプなどオープンワールドを彩る新要素
それでは解説していきます。

Ghost of Yōteiの物語と世界観
まずは、多くのプレイヤーが最も心惹かれるであろう、本作の物語と世界観について深く掘り下げていきましょう。 前作が描いた元寇という歴史的事件とは全く異なる時代と場所で、新たな主人公による、より個人的で濃密なドラマが繰り広げられます。
物語の舞台は1603年の蝦夷地
本作の舞台は、1603年の日本。 徳川幕府が成立したばかりの、泰平の世が訪れようとしていた時代です。 しかし、物語が繰り広げられるのは、その統治がまだ及ばぬ北のフロンティア、蝦夷の地(現在の北海道)。 当時の蝦夷地は、和人(日本人)の開拓民が足を踏み入れたばかりの、美しくも過酷な大自然が広がる未開の土地でした。

プレイヤーは、季節風が吹き抜ける広大な草原、雪に閉ざされたツンドラ地帯、そして人の手が及ばない原生林など、息をのむほど雄大でありながら、同時に命の危険に満ちた世界を冒険することになります。 前作の対馬も美しい島でしたが、本作の蝦夷地は、より荒々しく、神秘的な魅力に満ちたフィールドとして描かれています。 この手つかずの自然が、物語にどのような深みと挑戦を与えてくれるのか、非常に楽しみなポイントです。
時代設定がもたらす変化
前作の鎌倉時代から約330年後の江戸時代初期へと舞台が移ったことで、世界にもたらされる変化は少なくありません。 特に注目すべきは、武具や文化の変遷です。 トレーラーでも確認できるように、本作には「火縄銃」が登場します。 戦国時代を経て、鉄砲という兵器が戦の様相を大きく変えた後の時代設定は、戦闘スタイルにも新たな選択肢をもたらすでしょう。 また、人々の暮らしや町の景観、登場人物たちの価値観も、鎌倉武士が中心だった前作とは大きく異なり、新たな視点で日本の歴史を体験できるはずです。
新主人公「梓」は復讐を誓う無名の女性
本作の主人公は、境井仁のような御家人という高い社会的地位を持つ侍ではありません。 主人公の名は「梓(あずさ)」。 幼い頃に「六人衆」と呼ばれる謎の一団に家族を奪われ、自らも死の淵を彷徨った過去を持つ、名もなき浪人の女性です。

長い年月を経て、彼女はただ一つの目的のために刀を手に取ります。 それは、家族の仇である六人衆を追い詰め、その全員をこの手で葬り去ること。 彼女の旅は、国を守るためでも、民を救うためでもなく、あくまで個人的な復讐心に端を発しています。 この設定が、物語全体に前作とは異なるダークでシリアスなトーンを与えています。
境井仁との対比
前作の主人公・境井仁は、「誉れ」という侍の教えと、民を守るために手段を選ばない「冥人(くろうど)」としての戦い方の間で激しく葛藤しました。 彼の物語は、武士としてのアイデンティティを巡る苦悩の物語でもありました。
一方、今作の梓は、最初から何者にも縛られていません。 彼女には守るべき「誉れ」も、社会的地位もありません。 あるのは、燃え盛る復讐の炎だけです。 目的のためならば、いかなる卑劣な手段も厭わない。 その姿は、民から見ればまさに「鬼」や「怨霊(ゴースト)」のように映るでしょう。 前作の「ゴースト」が、侍からの逸脱を意味していたのに対し、今作の「ゴースト」は、復讐に身を捧げた存在そのものを指していると言えます。 この主人公の根本的な違いが、プレイヤーの感情移入の仕方を大きく変え、全く新しいゲーム体験を生み出すことに期待が高まります。
タイトル「Yōtei」に込められた意味とは
本作のタイトルにもなっている「Yōtei(ようてい)」とは、蝦夷地にそびえる実在の山「羊蹄山」を指します。 この羊蹄山は、アイヌ語で「マチネシリ(女性の山)」と呼ばれており、作中では主人公・梓にとって、失われた故郷と家族の象” 徴として、極めて重要な意味を持つ場所として描かれています。
タイトルにこの山の名が冠されていること自体が、彼女の復讐劇と、その先にある運命が、この山と深く結びついていることを示唆しています。 プレイヤーは、ゲームを通じて羊蹄山の雄大な姿を何度も目にし、その度に梓の過去と決意を再認識することになるでしょう。 物語のクライマックスが、この山の麓、あるいは山頂で繰り広げられることは想像に難くありません。
前作『ゴーストオブツシマ』との物語・主人公の比較
ここで、前作との違いをより明確にするために、表で比較してみましょう。
| 項目 | Ghost of Tsushima (前作) | Ghost of Yōtei (今作) |
|---|---|---|
| 時代設定 | 1274年(鎌倉時代・元寇) | 1603年(江戸時代初期) |
| 舞台 | 対馬 | 蝦夷地 |
| 主人公 | 境井 仁(さかい じん) | 梓(あずさ) |
| 身分 | 対馬の地頭・侍 | 浪人・復讐者 |
| 物語の動機 | モンゴル軍から故郷を守る | 家族を殺した「六人衆」への復讐 |
| 葛藤の核 | 侍の「誉れ」と冥人の道 | 復讐を遂げるための手段の是非 |
| 物語の規模 | 国家間の戦争 | 個人的な復讐劇 |
このように、基本的な設定からして大きく異なっていることがわかります。 前作が「公」のための戦いを描いた壮大な英雄譚であったのに対し、今作は「私」怨を晴らすための、よりパーソナルで内省的な物語になることが予想されます。 しかし、己の信念を貫くために戦うというシリーズの根幹的なテーマは共通しており、前作ファンも、そして新規プレイヤーも、深く引き込まれる重厚なストーリーが待っているはずです。
Ghost of Yōteiのゲームシステム徹底解説|前作からの進化点
物語や世界観だけでなく、ゲームプレイにおいても本作は劇的な進化を遂げています。 前作で高い評価を得たアクションや探索の楽しさを基礎としながら、さらにプレイヤーの没入感を高めるための大胆な変更が加えられました。 ここでは、特に注目すべき新要素を項目別に徹底的に解説していきます。
【探索】UI表示を廃止し、没入感を極限まで高めたオープンワールド
最も大きな変化と言えるのが、探索システムです。 前作でも、風が目的地を示してくれる「導き風」など、極力ゲーム的なUI(ユーザーインターフェース)を排したデザインが特徴的でした。 しかし、本作はその思想をさらに推し進め、画面上に表示される目的地アイコンやクエストマーカーといった、いわゆる「お約束」のガイドを原則として完全に廃止しました。

広大な蝦夷の地に降り立ったプレイヤーは、ミニマップに表示される「?」マークを追いかけるのではなく、自らの目と耳、そして好奇心だけを頼りに世界を旅することになります。 どこへ向かうも、何を発見するも、すべてはプレイヤー自身の選択に委ねられるのです。 これは、昨今のオープンワールドゲームが採用しがちな「チェックリストを埋めていく」ようなゲームプレイとは一線を画す、挑戦的かつ革新的な試みと言えるでしょう。
【探索】自らの五感で世界を読み解くヒントの数々
では、完全にノーヒントで広大な世界に放り出されるのかと言えば、そうではありません。 本作では、ゲーム的なマーカーの代わりに、世界そのものに無数のヒントが散りばめられています。
<h4>自然や動物が導き手となる</h4>
前作でも黄金の鳥や狐が隠し場所へ案内してくれましたが、その役割はさらに強化・多様化されています。 例えば、特定の動物がプレイヤーを珍しい植物や隠された洞窟へと導いてくれるかもしれません。 あるいは、不自然な煙が上がっている場所には、野営地や助けを求める人がいる可能性があります。 遠くで光る何か、特徴的な地形、風の音の変化など、周囲の環境を注意深く観察することが、新たな発見への第一歩となります。
<h4>人々の会話がクエストの始まり</h4>
前作では、クエストを受注するNPCの頭上には分かりやすいアイコンが表示されることもありました。 しかし今作では、村人たちの何気ない立ち話や噂話に耳を傾けることが、新たな物語の始まりとなります。 「最近、あの森の奥で不気味な叫び声が聞こえる」「峠のあたりに凶悪な盗賊が住み着いて困っている」といった会話こそが、プレイヤーを新たな冒険へと誘う重要な手がかりになるのです。 情報を得るために積極的に人々と関わり、世界に生きる一人の人間として物語を紡いでいく感覚は、これまでのゲームでは味わえなかった深い没入感を与えてくれるでしょう。
【探索】新たな出会いを生む「キャンプシステム」
探索に深みを与える新要素として、「キャンプシステム」が導入されました。 プレイヤーはフィールド上の好きな場所にキャンプを設営し、休息を取ることができます。 しかし、このシステムの真骨” 頂は、単なる回復ポイントではない点にあります。
夜、焚き火を囲んで梓が一人でいると、旅人や地元住民といったNPCがふらりと訪れ、火を囲んで語りかけてくることがあります。 彼らはただの背景ではなく、有益な情報をもたらしてくれたり、新たなサイドクエストのきっかけとなる出会いを提供してくれたりするのです。 時には、先の目的地に関する警告をしてくれることもあれば、梓の身の上話に共感し、ささやかな助けを申し出てくれることもあるかもしれません。 プレイヤーがNPCの元へ出向くだけでなく、NPC側からアプローチしてくるこの動的なシステムは、オープンワールドの世界に偶発性と生命感を与え、旅をより一層ドラマチックなものにしてくれる画期的な機能です。
【戦闘】「構え」を廃止!多彩な武器を使い分ける新バトルスタイル
戦闘システムも、前作から大きく変化しました。 前作の戦闘の核であった、敵の種類に応じて「石の型」「水の型」などを切り替える**「構え」システムは廃止**されました。 これは、主人公である梓が、境井仁のような体系だった剣術を学んだ侍ではない、という設定を色濃く反映した結果です。
彼女の戦い方は、いわば傭兵や実戦主義者のそれ。 一つの刀の型に固執するのではなく、状況に応じて様々な武器を瞬時に持ち替え、敵の弱点を突いていく、よりダイナミックで自由度の高い戦闘スタイルへとシフトしています。 刀で斬り結んでいたかと思えば、リーチの長い槍で距離を取り、鎖鎌で敵を引き寄せ、大太刀でまとめて薙ぎ払う。 流れるような武器の切り替えが、今作の戦闘の醍醐味となるでしょう。
【戦闘】刀から火縄銃まで!梓が扱う武器種一覧
梓が戦場で扱うことになる武器は、非常に多彩です。 公開されている情報だけでも、以下のような武器の登場が確認されています。

- 刀(かたな): 全ての基本となる、近接戦闘の要。前作同様、素早い斬撃や強力な一閃を繰り出します。
- 槍(やり): 長いリーチを誇り、敵との距離を保ちながら戦うのに有効。突きだけでなく、薙ぎ払いによる範囲攻撃も可能でしょう。
- 鎖鎌(くさりがま): 鎌による近接攻撃と、分銅による中距離攻撃を組み合わせたトリッキーな武器。敵を転ばせたり、引き寄せたりと、戦術の幅を広げます。
- 大太刀(おおだち): 重量級の刀。一撃の威力は絶大で、複数の敵を同時に攻撃するのに適していますが、動きはやや鈍重になることが予想されます。
- 小太刀(こだち): 二刀流で用いる小型の刀。手数が多く、素早い連続攻撃で敵を圧倒するスタイリッシュな戦闘が楽しめそうです。
- 弓矢(ゆみや): 前作同様、隠密行動に欠かせない遠距離武器。近距離用の「半弓」と、長距離・高威力の「長弓」を使い分けることになります。
- 火縄銃(ひなわじゅう): 本作で新たに追加された強力な遠距離武器。一撃で敵を仕留めるほどの威力を持つ反面、大きな発砲音で敵に気づかれやすく、リロードにも時間がかかるというデメリットを持つ、ハイリスク・ハイリターンな武器となるでしょう。
これらの主武器に加え、前作にも登場した「くない」や「煙玉」、「目つぶし粉」といった冥人の暗具も健在。 どんな手を使ってでも復讐を遂げるという梓の覚悟が、この豊富な兵装に表れています。
【戦闘】窮地を好機に変える「武器落とし・武器奪取」
戦闘にさらなる緊張感とダイナミズムをもたらす新アクションとして、「武器落とし」と「武器奪取」が追加されました。 激しい戦闘の最中、敵の強力な一撃によって、梓が手にしている武器を弾き飛ばされてしまうことがあるのです。 愛用の刀を失えば、普通なら絶体絶命のピンチ。
しかし、本作ではそれが新たな戦術への扉を開きます。 武器を失った梓は、素手で敵をいなし、その隙に倒した敵が落とした武器を拾い上げて即座に戦闘に復帰できるのです。 例えば、槍を持つ足軽との戦いで刀を落とされてしまったら、素早く懐に潜り込んで足軽を打ち倒し、その槍を奪い取って、次々と迫りくる敵兵を薙ぎ払う…といった、まるでアクション映画のような流麗でアドリブ感満載の戦いが可能になります。 このシステムは、プレイヤーに常に緊張感を与えつつも、窮地を乗り越えた際の達成感をより大きなものにしてくれるでしょう。
【アシスト】頼れる相棒!動物との共闘システム
前作では、石川先生や政子殿といった人間の仲間と共に戦う場面がありましたが、今作の梓には、より緊密な絆で結ばれた相棒がいます。 それは、一匹の狼です。
公開された映像では、梓が狼を連れて行動し、戦闘中に狼が敵兵に噛みついて動きを封じる様子が確認できました。 この狼は、単なる演出ではなく、戦闘を補助してくれるアシストキャラクターとして重要な役割を担うようです。 敵の注意を引きつけたり、特定の敵を無力化したりと、プレイヤーの指示、あるいは自律的な判断で梓を助けてくれることでしょう。 この狼との間には、育成要素や絆を深めるイベントなどが存在する可能性も高く、孤独な復讐の旅路における、かけがえのない癒やしと頼れる戦力になってくれるはずです。
【グラフィック】PS5の性能を最大限に活かした映像美
本作は、開発チームがPlayStation 5(PS5)向けにゼロから開発した初のタイトルであり、そのグラフィックは前作を遥かに凌駕するレベルに達しています。 PS5のハード性能を存分に活かし、広大な蝦夷の自然が圧倒的なディテールで描かれます。
ダイナミックな天候システムはさらに強化され、嵐が吹き荒れ、深い霧が立ち込め、雪が静かに積もる様子が、現実と見紛うほどのリアリティで表現されます。 草花が生い茂る道を馬で駆け抜ければ、花びらが美しく舞い上がり、一時的に馬の速度が上昇するといった、環境と相互に作用する演出も報告されており、世界の密度と没入感を格段に向上させています。 4K解像度と安定した高フレームレート、そして高速SSDによるシームレスなロードは、プレイヤーを完全に「Ghost of Yōtei」の世界へと誘ってくれることでしょう。
まとめ
今回は、待望の続編「Ghost of Yōtei」について、前作からの進化点や新要素を徹底的にレビューしてきました。
- 物語と世界観: 1603年の蝦夷地を舞台に、復讐を誓う新たな女性主人公「梓」の、よりダークでパーソナルな物語が展開される。
- 探索: UIガイドを極力廃し、プレイヤー自身の五感と好奇心を頼りに冒険する、没入感の極致を目指したオープンワールド。NPCとの偶発的な出会いを生む「キャンプシステム」も新しい。
- 戦闘: 「構え」を廃し、刀、槍、鎖鎌、さらには火縄銃といった多彩な武器をリアルタイムで切り替えて戦う、自由でダイナミックな新バトルシステムへ進化。「武器奪取」などの新アクションも追加。
- 仲間: 孤独な旅の相棒として、戦闘をアシストしてくれる「狼」が登場。
前作「ゴースト・オブ・ツシマ」が築き上げた高い評価を土台としながらも、決してその成功に安住することなく、あらゆる面で大胆な革新に挑んでいることがお分かりいただけたかと思います。 より深く、より自由に、そしてより美しくなった「ゴースト」の世界。 梓が紡ぐ復讐の物語の果てに何が待っているのか、自らの手で確かめられる日が待ち遠しくてたまりません。