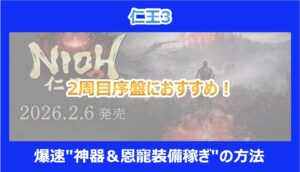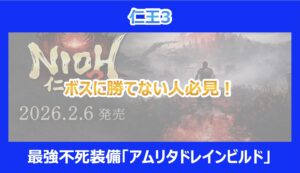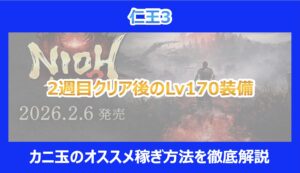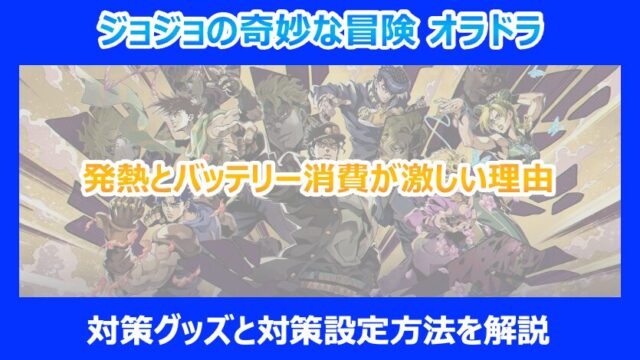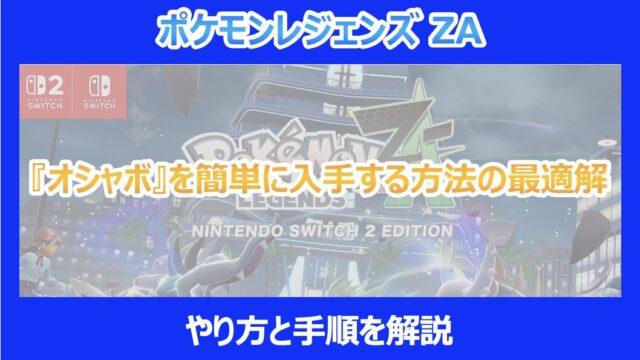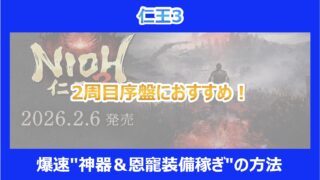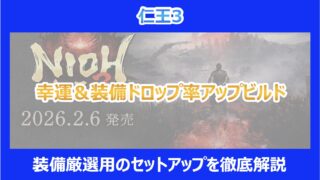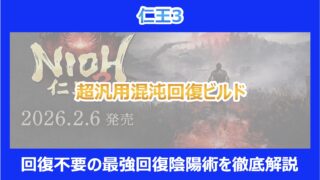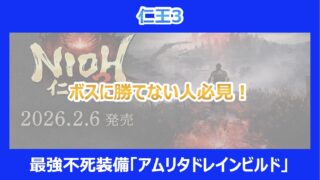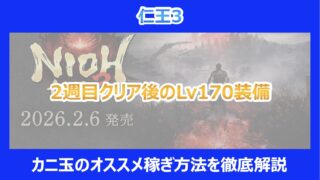ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、2025年10月2日に発売された待望の新作「Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)」について、購入すべきか、それとも見送るべきか、深く悩んでいることと思います。 特に、前作「ゴースト・オブ・ツシマ」が高く評価される一方で、その歯ごたえのある難易度から「人を選ぶ」と言われていたこともあり、今作のプレイフィールがどうなっているのか気になっているのではないでしょうか。

昨今のゲームは決して安い買い物ではありません。 だからこそ、購入後に「自分には合わなかった」と後悔することだけは避けたいはずです。
この記事を読み終える頃には、あなたが「Ghost of Yōtei」を買うべきかどうかの疑問が解決しているはずです。
- 前作とは異なる物語の方向性
- 正当進化を遂げた戦闘と探索システム
- 購入後に後悔する可能性のある人の特徴
- 気になる難易度とグロテスク表現の詳細
それでは解説していきます。

Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)とは?作品の基本情報を紹介
まずは本作がどのようなゲームなのか、基本的な情報からおさらいしていきましょう。 前作をプレイした方も、今作から興味を持った方も、購入を検討する上での基礎知識としてぜひご確認ください。

発売日・価格・レーティングについて
「Ghost of Yōtei」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントから発売されたPlayStation®5専用のアクションアドベンチャーゲームです。 基本的な製品情報は以下の通りです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年10月2日 |
| 対応機種 | PlayStation®5 |
| 価格(通常版) | 8,980円(税込) |
| CEROレーティング | Z(18才以上のみ対象) |
特筆すべきは、CEROレーティングが「Z」である点です。 これは前作「ゴースト・オブ・ツシマ」と同様で、戦闘におけるリアルな描写や欠損表現などが含まれていることを意味します。 血しぶきが舞うような激しい戦闘が苦手な方は、この点を十分に考慮する必要があります。 ただし、前作同様に血液表現のオン・オフといった設定変更も可能ですので、過度に心配する必要はありません。 設定を調整することで、ある程度マイルドな表現で楽しむこともできます。
物語の舞台とあらすじ
本作の舞台は1603年の「蝦夷地」、現在の北海道です。 前作の対馬から約300年後の時代が描かれており、徳川が幕府を開き、日本が新たな時代へと移り変わろうとする激動の時代が背景となっています。

主人公は、女武芸者である「あや」。 彼女は16年前に家族を惨殺した謎の集団「羊蹄六人衆」に復讐を誓い、極めて個人的な動機から刀を手に取ります。
前作の主人公「境井仁(さかいじん)」が、モンゴル軍の侵攻から故郷である対馬を守るという、領主としての「大義」を背負っていたのとは対照的です。 本作の物語は、あくまで「あや」個人の復讐劇から幕を開けます。
しかし、物語は単なる復讐譚では終わりません。 蝦夷地の雄大な自然を旅する中で、彼女は様々な人々との出会いと別れを経験します。 先住民族との交流、異なる文化を持つ人々との衝突、そして仲間との絆。 これらの経験を通じて、「あや」は復讐の先に何を見出すのか。 本作は、一人の女性の心の成長を丁寧に描いた、重厚な人間ドラマが大きな見どころとなっています。
前作「ゴースト・オブ・ツシマ」との関係性
最も多く寄せられる質問の一つが、「前作をプレイしていなくても楽しめるか?」という点です。 結論から言うと、全く問題ありません。
前述の通り、本作は前作から約300年後の世界を描いており、物語に直接的なつながりはありません。 主人公も舞台も一新されているため、今作から初めてこのシリーズに触れる方でも、100%楽しむことができます。 いわば、本作は「ゴースト・オブ・ツシマ2」ではなく、同じ世界観を共有する完全新作と捉えるのが正しいでしょう。
もちろん、前作をプレイしていると、思わずニヤリとしてしまうようなファンサービス的な要素も随所に散りばめられています。 作中に登場する剣術の流派や、語り継がれる伝説の中に、かつての「冥人(くろうど)」の面影を感じ取れるかもしれません。 前作ファンであれば、そうした要素を探しながらプレイするのも一興でしょう。
Ghost of Yōteiを買う前に知っておくべき3つの特徴
では、本作の具体的なゲームシステムはどのような進化を遂げたのでしょうか。 私がクリアまでプレイして感じた、本作を象徴する3つの大きな特徴を解説します。 これらのポイントが、あなたの好みに合うかどうかを判断する重要な材料になるはずです。

特徴①:前作とは別物の、より個人的で感情的な物語
前作「ゴースト・オブ・ツシマ」は、侍としての誉れと、民を守るための非情な手段「冥人」との間で葛藤する境井仁の姿を描いた、壮大な英雄譚でした。 国を守るというスケールの大きな物語は、多くのプレイヤーの胸を打ちました。
対して今作は、極めて個人的な「復讐」から始まります。 主人公「あや」は、国や民のためではなく、ただひたすらに己の過去と向き合うために戦います。 このシナリオの方向性の違いは、本作最大の特徴と言えるでしょう。
英雄譚から人間ドラマへ
物語の序盤は、家族を奪われた「あや」の憎しみや悲しみが色濃く描かれます。 そのため、前作のような爽快なヒーロー活劇を期待していると、少し戸惑うかもしれません。 しかし、旅の仲間との出会いが、彼女の心を少しずつ変えていきます。 なぜ戦うのか、誰のために生きるのか。 復讐という目的が揺らぎ始めた時、物語はより深みを増していきます。
前作が「公」の物語だったとすれば、今作は「私」の物語です。 人の心の機微や、キャラクター同士の感情的なつながりを丁寧に描く作風が好きな方には、間違いなく心に響く作品となるでしょう。 家族や仲間との絆、そして再生といったテーマが、今作の根幹を成しています。
特徴②:戦闘と探索システムの正当進化
ゲームプレイの核となる戦闘と探索も、前作の良さを引き継ぎつつ、確かな進化を遂げています。 特に、アクションの幅とフィールド探索の自由度は格段に向上しています。
武器種の増加と「構え」の廃止
前作の戦闘システムを象徴していた「構え」の切り替えは、本作では廃止されました。 その代わりに、5種類の武器種をリアルタイムで切り替えながら戦うスタイルへと変化しています。
- 刀: バランスの取れた標準的な武器。
- 二刀: 素早い連続攻撃で敵を圧倒する。
- 槍: リーチが長く、間合いを取って戦うのに有利。
- 鎖鎌: トリッキーな動きで敵を翻弄する中距離武器。
- 大太刀: 一撃の威力が重く、敵の体勢を崩しやすい。
敵の種類や装備によって有効な武器が異なるため、状況に応じて最適な武器を選択する戦略性が求められます。 感覚としては、前作の「構え」がそのまま「武器種」に置き換わったようなイメージです。 操作感は前作を踏襲しているため、シリーズファンはすぐに馴染めるでしょう。
さらに、弓(短弓、長弓)や銃(短筒、種子島)、そして目潰しに使う砂やくない、てつはう(爆弾)など、暗具の種類も大幅に増加。 近接戦闘だけでなく、遠距離からの狙撃やステルスキルなど、プレイヤーの好みに合わせた多彩な戦術が可能です。 戦闘のバリエーションが増えたことで、より深く、より長く楽しめるアクションパートに仕上がっています。
新たな探索要素「野営システム」
広大な蝦夷地の探索をより快適で自由なものにしているのが、新システムの「野営」です。 プレイヤーはフィールド上の好きな場所にキャンプを設営できます。
野営地では、火おこしや料理、装備のクラフト、さらには三味線の演奏といったアクティビティが楽しめます。 重要なのは、一度設営した野営地はマップ上に残り続け、ファストトラベルのポイントとして機能する点です。 これにより、広大なオープンワールドの移動が格段に快適になりました。 「あの景色の良い場所に自分の拠点を作ろう」といった、ロールプレイングの楽しみ方も広がっています。
サバイバル要素の強化
蝦夷地ならではの過酷な自然環境も、ゲームプレイに緊張感を与えています。 例えば、吹雪が吹き荒れる極寒のエリアでは、対策をしないと体力が徐々に奪われていきます。 また、フィールドの至る所に野生のヒグマが生息しており、遭遇すれば熾烈な戦いを強いられることも。
前作以上にサバイバル要素が強化されており、ただ目的地へ向かうだけでなく、周囲の環境に注意を払いながら旅をする必要があります。 この要素が、蝦夷地を冒険しているという没入感を一層高めてくれています。
特徴③:圧倒的な没入感を生む映像美と最新技術
PS5専用タイトルとして開発された本作は、その映像美も特筆すべき点です。 北海道の雄大な自然を表現したビジュアルは、思わず息をのむほどの美しさ。 プレイの手を止めて、スクリーンショットを撮りたくなる瞬間が何度も訪れるでしょう。
北海道の雄大な自然を表現したビジュアル
雪化粧を施した荘厳な羊蹄山、色とりどりの花が咲き乱れる草原、厳しい寒さが伝わってくる氷の世界。 時間や天候によって刻一刻と表情を変える風景は、それ自体が冒険のモチベーションになります。 特に、風の表現は前作からさらに進化しており、草木が揺れる音や、雪が舞う様子は圧巻の一言です。
映像モードの追加
前作で好評を博した、黒澤明監督の時代劇映画をオマージュした「黒澤モード」は今作でも健在です。 それに加え、新たに2つの映像モードが追加されました。
- 三船モード: 俳優・三船敏郎の力強い芝居をイメージし、血や土埃がより激しく舞い上がる、荒々しい映像表現が特徴。
- 渡辺モード: アニメ監督・渡辺信一郎からインスパイアされた、ローファイな音楽が楽しめるスタイリッシュなモード。
これらのモードを切り替えることで、同じシーンでも全く異なる雰囲気で物語を体験できます。 フォトモードも充実しており、自分だけの一枚を追い求めるのも楽しみ方の一つです。
PS5の機能をフル活用した体験
PS5ならではの機能も、ゲームへの没入感を高めるのに一役買っています。 Tempest 3Dオーディオ技術により、風の音、動物の鳴き声、敵の足音などが360度から聞こえ、臨場感あふれるサウンド体験が可能です。
また、DualSense™ ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーに完全対応。 刀がぶつかり合う衝撃、弓を引き絞る抵抗感、三味線の弦を弾く繊細な振動などが、コントローラーを通してダイレクトに手に伝わってきます。 これらの技術により、プレイヤーはまさにあや自身になったかのような感覚で、この世界に没入できるのです。
実際にプレイして感じた気になる点|好みが分かれるポイント
ここまで本作の魅力的な点を中心に紹介してきましたが、もちろん完璧なゲームというわけではありません。 実際にクリアまでプレイしたからこそ見えてきた、人によっては好みが分かれるであろう「気になる点」も正直にお伝えします。

エンタメ性を重視した一部の演出
本作は、開発チームが日本の時代劇を深くリスペクトし、現地取材を重ねて制作されていることがひしひしと伝わってきます。 しかし、あくまで海外のデベロッパーが作る「時代劇風エンターテインメント作品」であるという側面も忘れてはいけません。
例えば、敵である「羊蹄六人衆」が全員、特徴的な仮面をつけている設定。 あるいは、倒した敵の名前を、その場で血を使って書き記すといった演出。 これらはキャラクターの個性を際立たせ、ゲームとしての分かりやすさを生む一方で、リアルな日本の時代劇を求める方にとっては、少し大げさで違和感のある描写に映るかもしれません。 どこまでを「ゲーム的な演出」として許容できるかが、評価の分かれ目になりそうです。
シナリオの方向性の変化(英雄譚から人間ドラマへ)
これは特徴の項でも触れましたが、やはり前作とのシナリオの方向性の違いは、好みが分かれる最大のポイントでしょう。 国を救うという大きな使命感に燃えるダークヒーローの物語に熱狂した人ほど、個人的な復讐に終始する今作の序盤の展開に、物足りなさを感じる可能性があります。
もちろん、物語が進むにつれてテーマは深化していくのですが、最後まで軸足は「あや」という一人の人間の内面描写に置かれています。 スケールの大きな物語を期待している方は、その点を理解した上でプレイする必要があります。
革新性よりも「正当進化」である点
本作のゲームシステムは、あらゆる面で前作から進化しています。 しかし、それはあくまで「正当進化」の範囲内であり、ゲーム業界全体を揺るがすような、全く新しい革新的な要素が含まれているわけではありません。
戦闘システムも探索も、前作の面白さを拡張・改善したものであり、基本的なプレイフィールは大きく変わっていません。 そのため、「ゴースト・オブ・ツシマ」をやり尽くしたプレイヤーの中には、「目新しさに欠ける」と感じる人もいるかもしれません。 安定した面白さは保証されていますが、驚きや斬新さを最も重視するゲーマーにとっては、少し刺激が足りないと感じる可能性があります。
【本題】Ghost of Yōteiを買わない方が良い人の特徴
さて、ここまでの情報を踏まえ、本題である「Ghost of Yōteiを買わない方が良い人」の特徴を、私なりに5つのポイントにまとめました。 もし、ご自身がこれらの項目に複数当てはまるようであれば、購入は少し慎重に考えた方が良いかもしれません。

①前作のような英雄譚・救国の物語を期待している人
再三述べている通り、本作の物語は英雄譚ではありません。 主人公は対馬を救った境井仁のようなヒーローではなく、個人的な過去に囚われた一人の復讐者です。 人々を救い、国を守るという使命感に満ちた体験を求めている方には、本作のシナリオは地味で、スケールが小さく感じられるでしょう。 キャラクターの心情描写をじっくり味わう人間ドラマよりも、分かりやすい勧善懲悪のヒーロー活劇が好きな方は、購入を見送るのが賢明かもしれません。
②日本の時代劇の完璧な再現性を求める人
開発チームの並々ならぬリスペクトは感じられるものの、本作はあくまで「外国から見た日本の時代劇」です。 時代考証はしっかりと行われていますが、ゲームとしての面白さやエンターテインメント性を優先している部分も多々あります。 仮面をつけた敵や、物理法則を無視したような派手な剣技など、純粋な時代劇ファンから見れば「ありえない」と感じる描写も含まれています。 歴史的な正確性や、日本の「わびさび」といった文化的表現の完璧さを重視する方にとっては、違和感がストレスになる可能性があります。
③全く新しい革新的なゲームプレイを求めている人
「Ghost of Yōtei」は、前作の成功体験をベースに、丁寧に作られた続編です。 操作性、システムの根幹は前作を色濃く受け継いでいます。 オープンワールドのアクションアドベンチャーとして非常に高い完成度を誇りますが、どこかで見たことのある要素の集合体であることも事実です。 「今まで遊んだことのない、全く新しいゲーム体験がしたい」という、革新性を何よりも重視するゲーマーにとっては、本作は予定調和で退屈に感じてしまうかもしれません。
④高難易度アクションが極端に苦手な人
前作で指摘されていた難易度の高さ。 今作もその歯ごたえのある戦闘は健在です。 敵は賢く、数で襲い掛かってくるため、油断しているとあっという間に倒されてしまいます。
難易度設定は可能だが…
もちろん、本作には複数の難易度設定(例:易しい、普通、難しいなど)が用意されており、ゲームの途中でも自由に変更が可能です。 アクションが苦手な方でも、「易しい」を選べばストーリーを中心に楽しむことは十分にできます。
しかし、本作の戦闘の醍醐味は、敵の攻撃を見切り、多彩な武器や暗具を駆使して切り抜ける緊張感にあります。 最低難易度でプレイすると、そのスリルが薄れてしまい、戦闘が単調な作業に感じられてしまう可能性も否定できません。 ボタンを連打しているだけで勝てるようなゲームを求めている方や、そもそも戦闘自体が好きではないという方には、本作のゲーム性は合わないでしょう。
⑤サバイバルや探索要素が好きではない人
本作は広大な蝦夷地を自由に探索するのも大きな魅力の一つです。 しかし、裏を返せば、目的地にたどり着くまでに時間がかかるということでもあります。 温泉や神社を探したり、アイテムを収集したりといった、寄り道要素が豊富に用意されていますが、これらに興味が持てない場合、移動が苦痛に感じられるかもしれません。
また、寒さや野生動物といったサバイバル要素も、人によっては「面倒くさい」と感じる可能性があります。 一本道のストーリーをサクサク進めたい方や、探索や収集といった要素を好まない方にとっては、本作のオープンワールドは広すぎるかもしれません。
逆にGhost of Yōteiの購入を強くおすすめする人の特徴
もちろん、本作が多くの人にとって素晴らしいゲーム体験となるであろうことも事実です。 ここでは、どのような方に「Ghost of Yōtei」がおすすめできるのか、その特徴をまとめました。

①前作の世界観や探索が好きだった人
前作「ゴースト・オブ・ツシマ」の、あの美しい世界を風に乗って駆け巡る感覚が好きだった方なら、本作は間違いなく「買い」です。 基本的な面白さはそのままに、野営システムなどの追加で探索の自由度はさらに増しています。 安定した高いクオリティは健在ですので、前作ファンは安心して楽しめるでしょう。
②北海道や江戸時代の歴史・文化に興味がある人
江戸時代初期の蝦夷地という、他のゲームではほとんど扱われないユニークな時代設定は、本作ならではの大きな魅力です。 和人だけでなく、先住民族であるアイヌの人々も登場し、彼らの独自の文化や生活が丁寧に描かれています。 歴史、特に日本の特殊な時代の文化に興味がある方にとっては、知的好奇心を大いに刺激される作品となるはずです。
③オープンワールドでじっくり探索するのが好きな人
本作のフィールドは、正確にはいくつかのエリアに分かれた「セミオープンワールド」ですが、その広大さは本物です。 各地に点在する温泉や神社、お地蔵様を巡ることで、主人公の能力を強化できます。 美しい景色を眺めながら、自分のペースで世界を探索するのが好きな方にとっては、最高の時間となるでしょう。 メインストーリーそっちのけで、寄り道ばかりしてしまうタイプのプレイヤーには、たまらない作品です。
④重厚な人間ドラマ・ストーリーを重視する人
派手なアクションだけでなく、物語にも深く没入したいという方には、本作を強くおすすめします。 主人公「あや」が、復讐という呪縛からいかにして解放されていくのか。 仲間との絆を通じて、彼女の心情が変化していく様が丁寧に描かれており、クリア後には深い余韻に浸れるはずです。 何を成したかではなく、登場人物たちが何を感じ、どう変化したのかに焦点を当てる物語が好きな方には、心に響く体験が待っています。
⑤PS5の性能を最大限に活かしたゲームを体験したい人
せっかくPS5を持っているのだから、その性能をフルに活かしたゲームが遊びたい、という方にも本作は最適です。 息をのむほど美しいグラフィック、3Dオーディオによる臨場感、DualSenseコントローラーによる触覚フィードバック。 最新技術がもたらす圧倒的な没入感は、まさに次世代のゲーム体験と呼ぶにふさわしいものです。 フォトモードも非常に高機能なので、美しいゲーム世界を撮影するのが好きな方にもおすすめです。
Ghost of Yōteiに関するよくある質問(Q&A)
最後に、これまでお話しした内容以外で、多く寄せられるであろう質問についてQ&A形式で回答します。
Q. 前作をプレイしていなくても楽しめますか?
A. はい、全く問題ありません。 物語に直接のつながりはないため、本作から始めても100%楽しめます。
Q. 難易度は高いですか?変更はできますか?
A. 戦闘は歯ごたえがありますが、複数の難易度設定が用意されており、いつでも変更可能です。 アクションが苦手な方でも、難易度を「易しい」にすれば、ストーリーを中心に楽しめます。
Q. グロテスクな表現はありますか?
A. CERO Z(18歳以上対象)の作品であり、戦闘における欠損表現や血液描写が含まれます。 ただし、設定で血液表現をオフにすることも可能です。
Q. クリアまでのプレイ時間はどれくらいですか?
A. プレイスタイルによりますが、メインストーリーだけを追うなら30~40時間程度です。 寄り道要素や収集物をコンプリートしようとすると、80時間以上は楽しめるボリュームがあります。
Q. オンライン要素はありますか?
A. 本作はシングルプレイ専用のゲームであり、オンラインマルチプレイ要素はありません。 自分のペースでじっくりと物語と世界に没入できます。
まとめ
今回は、2025年10月2日に発売された「Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ-ヨウテイ)」について、購入をおすすめしない人の特徴を中心に、徹底的にレビューしてきました。
本作は、前作「ゴースト・オブ・ツシマ」の良さを見事に継承し、戦闘や探索を正当進化させた、非常にクオリティの高い作品であることは間違いありません。 特に、PS5の性能を活かした圧倒的な映像美と没入感は、多くのプレイヤーを魅了するでしょう。
しかし、その一方で、物語の方向性が英雄譚から個人的な人間ドラマへと変化した点や、あくまで「正当進化」であり革新的な新しさには欠ける点など、プレイヤーを選ぶ要素も確かに存在します。
決して安い買い物ではないからこそ、本レビューで挙げた「買わない方が良い人」の特徴をご自身のプレイスタイルと照らし合わせ、後悔のない選択をしていただければ幸いです。
個人的には、クリアまで夢中でのめり込めた、紛れもない傑作でした。 このレビューが、あなたの購入の参考になれば嬉しく思います。