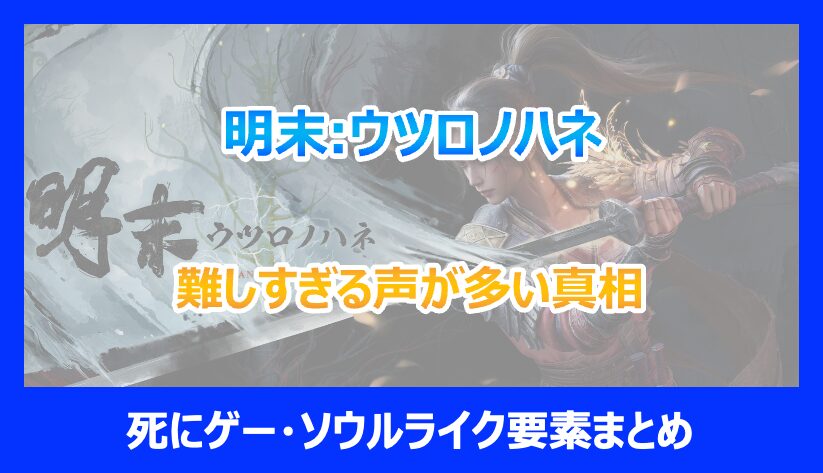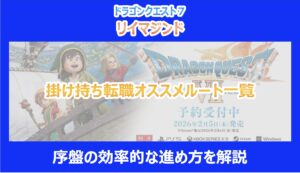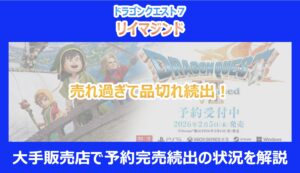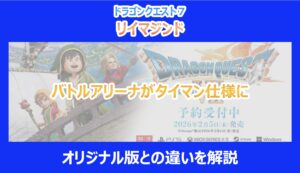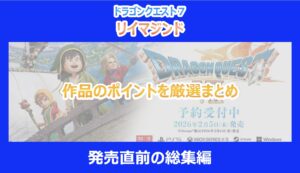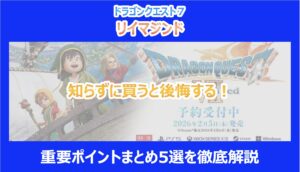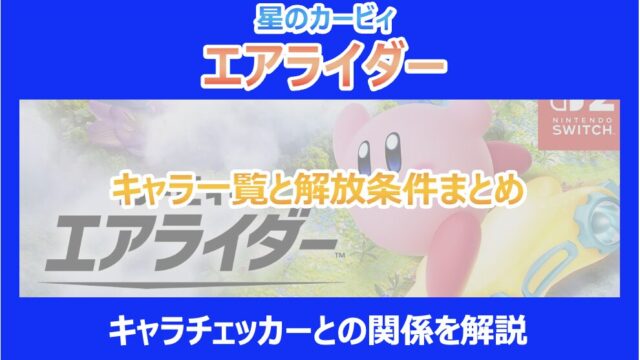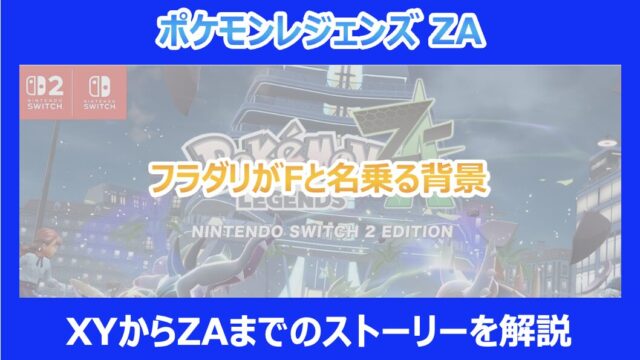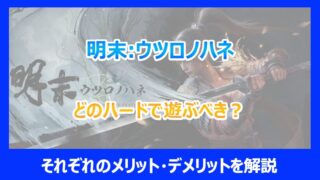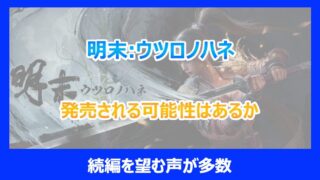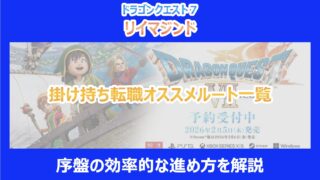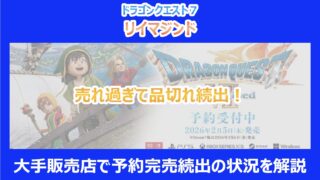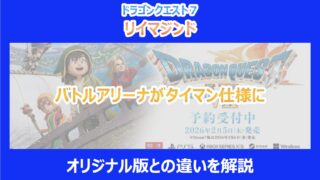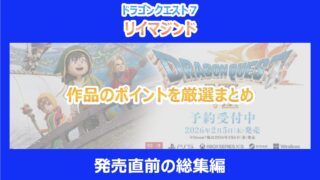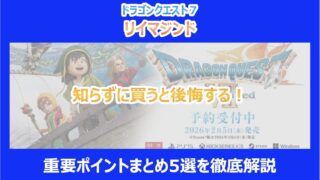ゲーム評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、話題のソウルライクゲーム『明末:ウツロノハネ』について、「難しすぎる」「人を選ぶ」といった声が多いけれど、実際のところどうなのか、本当に楽しめる作品なのかどうかが気になっていると思います。 セクシーなキャラクターデザインに惹かれつつも、高難易度という評判に購入をためらっている方も少なくないでしょう。

引用 : SIE HP
この記事を読み終える頃には、あなたが『明末:ウツロノハネ』を買うべきか、あるいは見送るべきかの疑問が、明確に解決しているはずです。
- 賛否両論を呼ぶゲーム性の真相
- 高難易度と言われる具体的な理由
- 本作ならではの独自の魅力とシステム
- どんなプレイヤーにおすすめできるか
この記事を読めば、きっと問題が解決できるはず。

『明末:ウツロノハネ』とは?基本情報と世界観
まずは『明末:ウツロノハネ』がどのようなゲームなのか、基本的な情報から見ていきましょう。 多くのプレイヤーが「難しい」と感じる背景には、このゲームならではの独特な世界観とシステムが深く関わっています。

ゲームの概要とジャンル
『明末:ウツロノハネ』は、中国のデベロッパー・零犀(Lingxi)Gamesが開発したアクションRPGです。 ジャンルとしては、フロム・ソフトウェアの『DARK SOULS』シリーズに代表される、いわゆる「ソウルライク」や「死にゲー」に分類されます。
プレイヤーは何度も死を繰り返しながら敵の行動パターンを学び、自身のプレイヤースキルを向上させて強大なボスに挑んでいくことになります。 広大で入り組んだマップを探索し、キャラクターを強化しながら物語の真相に迫っていくという、ソウルライクの王道をいくゲームデザインが特徴です。
しかし、単なる模倣作品ではなく、後述する「粋(すい)」や「心魔(しんま)」といった独自のシステムを導入することで、他のソウルライクゲームとは一線を画すプレイフィールを実現しています。
舞台となる時代背景とストーリー
物語の舞台は、三国志の時代が終わりを告げた後の、中国の「明」の時代末期。 第17代皇帝・崇禎帝が自害し、国内は権力争いや紛争によって混乱の渦中にありました。
そんな中、人々の体に羽が生えるという奇妙な病「羽病(うびょう)」が蔓延し始めます。 羽病に罹患した者は、徐々に記憶を失い、やがては理性を失った化け物へと変貌してしまうのです。
この混沌とした世界で、プレイヤーは記憶を失った一人の女性として、自らの過去と世界の謎を解き明かすための過酷な旅に出ることになります。 ダークで重厚な世界観と、謎が謎を呼ぶミステリアスな物語は、多くのプレイヤーを引き込む魅力の一つと言えるでしょう。
主人公「無常」と謎の病「羽病」
プレイヤーが操作するのは、記憶喪失の主人公「無常(むじょう)」。 彼女自身もまた「羽病」に侵されており、なぜ自分が戦うのか、何者なのかも分からないまま、妹と思われる存在を救うために奔走します。
声優には小清水亜美さん(日本語吹き替え)が起用されており、過酷な運命に翻弄される主人公の心情を巧みに表現しています。 物語はマルチエンディング方式を採用しており、プレイヤーの選択や行動によって、無常を待ち受ける結末は大きく変化していきます。
スペックや価格などの基本情報
購入を検討する上で気になる基本情報を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 明末:ウツロノハネ (WUCHANG: Fallen Feathers) |
| 開発元 | 零犀(Lingxi)Games |
| 発売日 | 2024年7月24日 |
| 対応機種 | PlayStation 5, PC (Steam) |
| ジャンル | アクションRPG (ソウルライク) |
| 価格 (PS5版) | 通常版: 7,260円 (税込) / デラックス版: 8,250円 (税込) |
| CERO | Z (18才以上のみ対象) |
| プレイ人数 | 1人 |
インディーゲームとしては比較的手に取りやすい価格設定ですが、その内容はフルプライスの大作にも引けを取らないボリュームを誇っています。
なぜ「難しすぎる」「クソゲー」と言われるのか?徹底分析
さて、ここからが本題です。 『明末:ウツロノハネ』は、なぜ一部のプレイヤーから「難しすぎる」「理不尽だ」「クソゲーだ」とまで言われてしまうのでしょうか。 実際にクリアまでプレイした私が、その原因を項目別に徹底的に分析していきます。

これらの要素は、本作の評価を大きく左右する重要なポイントです。
根本的な操作性の問題点
多くの批判が集まっているのが、キャラクターを動かす上での根本的な操作性です。 死にゲーにおいて、プレイヤーの意のままにキャラクターを動かせないことは、致命的なストレスに繋がります。
ダッシュ・移動速度が遅すぎるストレス
本作をプレイして誰もが最初に感じるであろう不満点が、移動速度の遅さです。 特にダッシュの速度が他のソウルライクゲームと比較しても顕著に遅く、これが様々な場面でストレスを生み出しています。
- ボスへの再挑戦(マラソン)が苦痛:チェックポイントからボス部屋まで距離がある場合、この遅いダッシュで何度も同じ道のりを往復させられます。
- 探索のテンポが悪い:広大なマップを探索する際にも、移動の遅さが常につきまといます。敵を殲滅した後のアイテム回収ですら、億劫に感じることがあります。
- 時間稼ぎと受け取られかねない仕様:ゲーム全体のプレイ時間を水増しするために、意図的に移動速度を遅くしているのではないか、と勘繰られても仕方のないレベルです。
この「移動」というゲームプレイの大半を占める行為にストレスがかかる点は、間違いなく本作の評価を下げている大きな要因です。
回避アクションのテンポの悪さ
回避は死にゲーにおける生命線ですが、本作の回避アクションにも癖があります。 連続して素早く入力することができず、一度回避すると次の行動までに若干の硬直時間が存在します。
これにより、『Bloodborne』や『SEKIRO』のようなスピーディーな戦闘を期待していると、肩透かしを食らうことになります。 むしろ、盾を構えてじっくりと立ち回る『DARK SOULS 1』のような、ターン制に近いバトルを強いられる感覚です。
しかし、問題は敵の攻撃スピード。 プレイヤーの動きが緩慢なのに対し、敵、特にボスは非常に素早く、苛烈な連続攻撃を仕掛けてきます。 このアンバランスさが、「敵だけが楽しそうだ」という印象を与え、プレイヤーに不公平感とストレスを感じさせる原因となっています。
爽快感のない攻撃モーションとSE
アクションゲームの根源的な楽しさである「攻撃の気持ちよさ」。 残念ながら、本作はこの点においても評価が高いとは言えません。
攻撃モーションはどこか軽く、武器を振っても敵に当たっている感触、いわゆるヒットストップがほとんど感じられません。 効果音(SE)も迫力に欠けるため、強力な一撃を叩き込んでも、「やった!」という達成感や爽快感が得られにくいのです。
死にゲーは、困難を乗り越えた先の達成感が最大の報酬です。 その道中である戦闘行為そのものに楽しさを見出しにくい点は、モチベーションを維持する上で大きな障害となります。
ダウンからの復帰が遅く、理不尽な「起き攻め」
本作の理不尽さを象徴するのが、ダウンからの復帰モーションの遅さです。 敵の攻撃を受けてダウンすると、完全に起き上がって行動可能になるまで体感で2〜3秒かかります。
問題は、このダウン中や起き上がり途中にも敵の攻撃がヒットすることです。 そのため、一度ダウンさせられると、
- 敵の攻撃でダウンさせられる。
- ゆっくりと起き上がっている最中に、次の攻撃を重ねられる(起き攻め)。
- 再びダウンし、何もできずに殴られ続けて死亡する。
という、いわゆる「ハメ技」のような状況が頻繁に発生します。 これはプレイヤースキルではどうにもならないシステム上の問題であり、多くのプレイヤーが「理不尽だ」と感じる最大の要因でしょう。 「自分のミスで死んだ」という納得感がないため、ただただストレスだけが溜まっていきます。
探索を阻むマップデザインの問題点
ソウルライクのもう一つの醍醐味である「探索」においても、本作はいくつかの問題を抱えています。 緻密に計算されたレベルデザインとは言い難い部分が散見されます。
チェックポイント(祠)の配置の悪さ
セーブや回復の拠点となるチェックポイント(作中では「祠」)の配置バランスが非常に悪いと感じました。
- 長すぎる区間:次の祠までの道のりが異常に長く、敵も強いため、途中で力尽きると長時間を無駄にすることになります。
- 意味不明な位置:ボスを倒した直後に祠がなかったり、分かりにくい場所に隠されていたりするため、見つけられずに探索を続ける羽目になることもあります。
- ボスまでの距離:前述の通り、ボス部屋までの距離が遠いケースが多く、移動速度の遅さと相まって再挑戦の意欲を著しく削いできます。
これらの配置の不親切さが、探索の楽しさよりも苦痛を上回らせてしまっています。
分かりにくいマップ構造と機能しないショートカット
本作にはゲーム内マップが存在しません。 これはソウルライクでは珍しくありませんが、本作の場合はマップの構造自体が問題です。
全体的に似たような風景が続くため、現在地を把握しにくく、非常に道に迷いやすいです。 私も数時間にわたって同じ場所を彷徨った経験があります。
また、探索の動線を繋ぐショートカットも、開通させてもあまり意味をなさない場所に設置されていることが多く、発見した時の感動や利便性が薄いのが残念です。 どこに繋がっているのかが直感的に分かりにくく、その機能を十分に活かせているとは言えません。
理不尽さを感じる敵の配置とギミック
難易度の高さを「理不尽さ」に変えてしまっているのが、悪意に満ちた敵の配置やギミックの数々です。 「難しい」と「理不尽」は似て非なるもので、後者はプレイヤーのやる気を奪います。
暗闇、死角からの初見殺し
とにかくマップが暗いエリアが多く、敵の姿を視認しづらい場面が多々あります。 さらに、通路の角や天井といった死角から、いきなり掴み攻撃を仕掛けてくるなど、初見ではまず回避不可能な「初見殺し」が大量に配置されています。
これはプレイヤーに学習を促す健全な難しさではなく、単なる嫌がらせに近いギミックです。
執拗な遠距離攻撃と即死の状態異常
プレイヤーの位置を正確に狙ってくる遠距離攻撃を持つ敵が非常に厄介です。 しかも、その弾は追尾性能が高く、障害物に隠れても回り込んでくることがあります。
さらに、食らうと即死につながる状態異常を持つ敵も存在し、複数の敵に囲まれた状態でこれを食らうと、なすすべなくゲームオーバーとなります。 特に、ボスへ向かう道中にこれらの敵が配置されているのは、意地が悪いとしか言いようがありません。
スーパーアーマー持ちの雑魚敵との集団戦
ほとんどの雑魚敵が、こちらの攻撃を受けても怯まない「スーパーアーマー」状態を持っています。 そのため、一体一体を相手にするのも骨が折れるのですが、本作ではそういった敵が常に複数で襲いかかってきます。
序盤は特にプレイヤーの火力が低いため、囲まれて一方的に攻撃され続けるという状況に陥りがちです。
分かりにくいUIと不親切なシステム
ゲームプレイの快適性を損なう、ユーザーインターフェース(UI)の問題も指摘されています。 例えば、非戦闘時にHPバーが自動で消えてしまうため、現在の体力を確認するために毎回ボタンを押す必要があります。 こういった細かい不便さが、プレイ中に小さなストレスとして蓄積していきます。
また、チュートリアルも十分とは言えず、本作の重要なシステムを理解しないまま進めてしまい、結果として「理不尽な難しさ」に直面するプレイヤーが多いのも事実です。
『明末:ウツロノハネ』の魅力と評価できるポイント
ここまで厳しい点を挙げてきましたが、もちろん『明末:ウツロノハネ』には、多くのプレイヤーを魅了する素晴らしい点も存在します。 むしろ、先述した欠点を許容できるのであれば、唯一無二の体験ができるポテンシャルを秘めた作品です。

キャラクターの魅力とセクシー要素
本作が発売前から注目を集めていた大きな理由が、魅力的なキャラクターデザイン、特にそのセクシーな要素です。
豊富な衣装と見た目のカスタマイズ
主人公・無常には、多種多様な衣装(防具)が用意されています。 世界観に沿ったシリアスな鎧から、肌の露出が多いセクシーなもの、可愛らしいデザインのものまで、そのバリエーションは非常に豊富です。
装備重量の概念がないため、性能を気にすることなく、完全に見た目の好みで装備を選べるのは大きな魅力です。 お気に入りの衣装で強敵と渡り合うのは、モチベーションの維持に繋がります。
魅力的なボスキャラクターのデザイン
敵として登場するボスキャラクターたちも、非常に魅力的です。 恐ろしくも美しいデザインのボスが多く、中には主人公同様にセクシーさを感じさせる人型のボスも存在します。 苦戦を強いられる相手だからこそ、そのキャラクター性やデザインの秀逸さが際立ちます。
戦略の幅を広げる独自の戦闘システム「粋」と「心魔」
単なる高難易度ゲームで終わらないのが、本作の戦闘システムです。 「粋」と「心魔」という二つの独自要素が、戦闘に深い戦略性をもたらしています。
FP(マナ)の役割を果たす「粋」システム
「粋」は、他のゲームで言うところのMPやFPに相当するリソースです。 これを消費することで、強力な武器スキルや法術(魔法)を使用できます。
面白いのは、この「粋」の回復方法です。 敵の攻撃をガードしたり、タイミングよく回避したりすることで、「粋」が大幅に回復します。 つまり、守りに徹するのではなく、敵の攻撃を積極的に捌いていくことで、強力な攻撃を連発できるチャンスが生まれるのです。
このシステムにより、「危険を冒して攻める」というハイリスク・ハイリターンな戦い方が可能になり、単調になりがちな戦闘にスリルと戦略性を加えています。
リスクとリターンが面白い「心魔」システム
「心魔」は、本作の難易度をプレイヤー自身がある程度コントロールできるユニークなシステムです。
- 心魔が溜まる条件:プレイヤーが死亡するたびに「心魔」のゲージが上昇します。
- 心魔が高いことのデメリット:受けるダメージが増加し、死亡時に失うソウル(経験値)の量も増えます。
- 心魔が高いことのメリット:ソウルの獲得量が増え、「粋」の回復速度も上昇します。
つまり、死ねば死ぬほどゲームは難しくなりますが、その分リターンも大きくなるという諸刃の剣のシステムです。 あえて心魔が高い状態で強敵に挑み、一攫千金を狙うといったプレイも可能です。 このリスク管理が、本作の面白さの核の一つとなっています。
自由度の高いキャラクタービルド
本作は、プレイヤーの戦闘スタイルを自由に構築できる、非常に懐の深いビルドシステムを持っています。
膨大なスキルツリーと振り直しの手軽さ
本作には、武器種ごとに膨大なスキルツリーが用意されています。 『Path of Exile』を彷彿とさせる広大なツリーの中から、どの能力を伸ばしていくかを考えるだけでも楽しめます。
さらに特筆すべきは、スキルポイントの振り直しがいつでも無料で、何のペナルティもなく行える点です。 これにより、「このボスにはこのスキルが有効そうだ」と考えた時に、気軽にビルドを変更して試すことができます。 試行錯誤のハードルが非常に低いため、様々な戦術を積極的に試せるのが素晴らしい点です。
武器強化システムの独自性
武器の強化システムもユニークです。 特定の武器一本を強化するのではなく、スキルツリーを解放していくことで、「片手剣」や「槍」といった武器カテゴリー全体が強化されます。
これにより、同じカテゴリー内であれば、新しい武器を手に入れてもすぐに一線級の強さで使うことができます。 また、武器強化に使用した素材もリセットして回収できるため、途中でメイン武器を気軽に変更できるのも嬉しいポイントです。
やりこみ要素と収集の楽しさ
一度クリアして終わりではない、長く遊べるだけのやりこみ要素が用意されています。
NPCイベントとマルチエンディング
道中で出会うNPC(ノンプレイヤーキャラクター)たちには、それぞれ固有のイベントラインが用意されています。 会話の選択肢や特定の条件を満たすことで、彼らの運命は変化し、貴重なアイテムを入手できることもあります。
そして、これらのNPCイベントへの関わり方などが、物語の結末を左右するマルチエンディングに繋がっています。 全ての結末を見るためには、周回プレイが必須となるでしょう。
周回プレイ(ニューゲームプラス)の存在
ソウルライクお馴染みの、クリア後のデータを引き継いでプレイする「ニューゲームプラス」も搭載されています。 周回を重ねるごとに敵は強化され、配置も一部変化するため、新鮮な気持ちで再びプレイすることが可能です。 全ての武器や防具、スキルをコンプリートするには、相当な時間遊べるボリュームがあります。
結局『明末:ウツロノハネ』はどんな人におすすめ?
ここまで賛否両論のポイントを解説してきましたが、最終的にこのゲームはどのような人におすすめできるのでしょうか。 購入を迷っているあなたの疑問に、一つずつお答えしていきます。

セクシー要素目当ての購入はアリかナシか
結論から言うと、「アリ」ですが、注意が必要です。
確かに、魅力的な衣装やキャラクターは本作の大きなセールスポイントです。 しかし、そのセクシーな衣装を手に入れるためには、本作の非常に高い難易度を乗り越えなければなりません。 あくまでメインは骨太なアクションゲームであり、セクシー要素はクリアまでの長い道のりを彩る「ご褒美」のような位置づけです。
『Stellar Blade』のように、アクションが苦手でも楽しめるようなアシスト機能は存在しません。 「セクシーなキャラを愛でるためなら、どんな苦行も厭わない」という強い覚悟がある方ならば、購入しても満足できるでしょう。 しかし、手軽にセクシー要素だけを楽しみたいという方には、残念ながらおすすめできません。
フロムソフトウェア作品(ダクソ・SEKIRO)ファンは楽しめるか
これも一概には言えず、「人による」というのが正直な答えです。
- 『DARK SOULS』シリーズ、特に1や2が好きな方:楽しめる可能性は高いです。盾に頼らないものの、じっくりとした立ち回り、敵のモーションを見切って一撃を叩き込む重量感のある戦闘は、初期のソウルシリーズに近いものがあります。緻密さには欠けますが、理不尽さも含めて楽しめる方ならハマるかもしれません。
- 『Bloodborne』や『SEKIRO』が好きな方:おそらく、楽しめない可能性が高いです。本作の緩慢な操作性やテンポの悪い回避は、これらの作品が持つスピード感や爽快感とは正反対です。SEKIROのような華麗な弾き合いを期待すると、大きく裏切られることになるでしょう。
フロム作品が好きだからという理由だけで手を出すのは危険です。 自分がどの作品のどの部分が好きなのかを自己分析した上で、判断することをおすすめします。
死にゲー初心者にはおすすめできるか
絶対におすすめできません。
操作性の悪さ、理不尽な敵の配置、不親切なシステムなど、本作は死にゲーに慣れたプレイヤーですら音を上げる要素に満ちています。 初心者が最初にこのゲームに触れてしまうと、「死にゲーとは、ただ理不尽でストレスが溜まるだけのジャンルだ」と誤解してしまう可能性が非常に高いです。
もし死にゲーに挑戦したいのであれば、まずは完成度の高い『ELDEN RING』や、比較的難易度が低めの『CODE VEIN』などから始めることを強く推奨します。
ビルド構築やハクスラ要素が好きな人への適性
非常に高い確率で楽しめます。本作が最も輝くのはこの部分です。
アクションの腕前に自信がなくても、膨大なスキルツリーを眺め、シナジーを考え、最強のビルドを構築することに喜びを感じるタイプのプレイヤーにとって、本作はまさに楽園のようなゲームです。
「この強敵をどうやって倒すか」という課題に対し、アクションで真正面からぶつかるのではなく、「スキルや装備の組み合わせという”アイデア”で勝つ」ことに面白さを見出せる方なら、本作の欠点は些細なものに感じられるでしょう。 事実、高評価をしているプレイヤーの多くは、このビルド構築の自由さを絶賛しています。
このゲームを買うべきでない人の特徴
まとめとして、以下に当てはまる方は、購入を見送った方が賢明です。
- アクションゲームの爽快感や快適な操作性を最も重視する人
- 短気で、理不尽な死にストレスを感じやすい人
- 死にゲーをプレイしたことがない初心者
- キャラクタービルドやステータス画面を眺めるのが苦手な人
- セクシー要素だけを手軽に楽しみたい人
まとめ
『明末:ウツロノハネ』は、**「荒削りだが強烈な魅力を持つ、極めて人を選ぶ作品」**であると結論付けます。
移動のもっさり感や理不尽な起き攻めといった、ゲームの根幹に関わる部分に看過できない欠点を抱えているのは事実です。 これらの要素が、多くのプレイヤーにとって大きなストレスとなり、「クソゲー」という評価に繋がっています。
しかしその一方で、自由度の高いキャラクタービルド、リスクとリターンが絡み合う独自の戦闘システム、そして魅力的な世界観とキャラクターは、他のどのゲームにもない強烈な中毒性を秘めています。
プレイヤースキルだけでなく、知恵と工夫で困難を乗り越えることにカタルシスを感じるプレイヤーにとっては、本作は数十時間、あるいは百時間以上も没頭できる傑作になり得るでしょう。
購入を検討している方は、本レビューで挙げた良い点と悪い点を天秤にかけ、自分がこの「理不尽さ」を許容し、その先にある「面白さ」にたどり着けるタイプのゲーマーかどうか、じっくりと見極めてみてください。 このレビューが、あなたの判断の一助となれば幸いです。