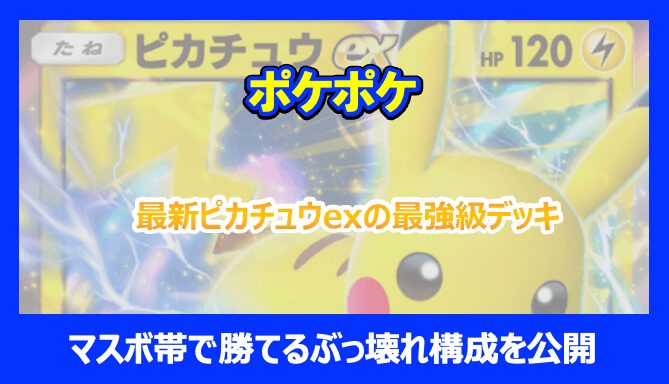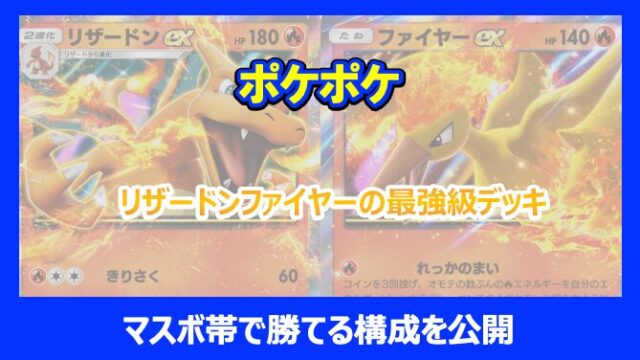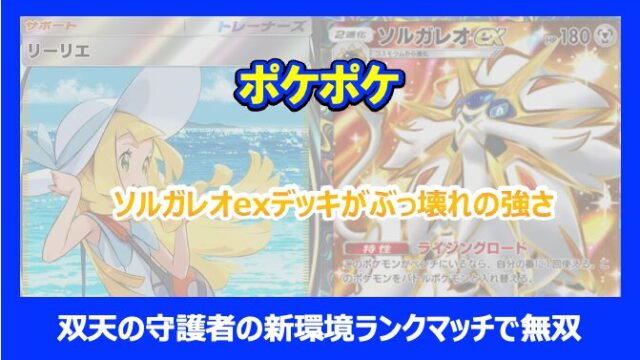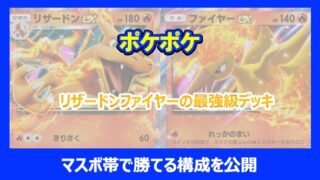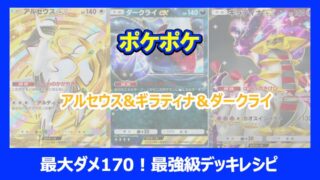ピカチュウexデッキでマスターボールランクを目指しているけどなかなか勝てない、という悩みを抱えている方は少なくないでしょう。
引用 : ポケポケ公式HP (https://www.pokemontcgpocket.com/ja/)
しかし、このレビューを読めば、環境上位デッキにも勝てるピカチュウexデッキの最強構成がわかります。今回ご紹介するのは、実際にマスターランク帯でも勝利を収めている最新構成のピカチュウexデッキです。
この記事でマスボランク攻略の鍵を掴むことが可能です。
- マスボ帯でも戦える最新ピカチュウexデッキの詳細構成
- デッキ運用の具体的な戦術と立ち回り方法
- ピカチュウexデッキが苦手とする環境デッキへの対策
- 実際にマスボ帯で勝率を上げるための実践的アドバイス
それでは解説していきます。
以下関連記事をまとめています。参考にご覧ください。
デッキレシピ詳細|ピカチュウex最強構成
キーカード|ピカチュウex

引用 : ポケポケ公式HP (https://www.pokemontcgpocket.com/ja/)
ピカチュウexは、コストパフォーマンスに優れた主力アタッカーであり、1エネルギーで高打点を叩き出せる点が最大の魅力です。特に、進化が不要なexポケモンであるため、序盤からすぐに場に出しやすく、先手を取る展開がしやすいのも特徴です。相手の場に出たポケモンを的確にワンパン(1撃KO)で処理できる性能は、現環境のアグロ寄り構築に非常に適しており、マスターボールランクでも上位帯で通用する実力を発揮しています。
高打点+スピード展開で制圧
ピカチュウexは150ダメージを与えることができる技を持ち、これを2ターン目から安定して繰り出すことが可能です。これはパチリスやジバコイルといったエネ加速ポケモンとの連携によって実現され、序盤から高火力で相手を押し切る展開が狙えます。
環境メタとの相性にも優れる
環境に多いギラティナVSTARやミュウツーV-UNIONのような高HPポケモンに対しても、エネルギー調整やレッドの奇襲などで対応が可能で、柔軟な立ち回りができます。特に一撃でダメージが通る場面では、大型ポケモンの展開を抑え込む力を発揮します。
エネルギー加速|ジバコイルラインの重要性

引用 : ポケポケ公式HP (https://www.pokemontcgpocket.com/ja/)
このデッキの鍵を握るのはジバコイルラインです。レアコイルを経てジバコイルに進化することで、高速のエネルギー加速が可能になり、盤面展開の安定感が格段に向上します。ピカチュウexの高打点攻撃を早期に実現するためにも、このラインの構築は必須です。
ジバコイルの特性「ボルトチャージ」の強み
ジバコイルは特性「ボルトチャージ」により、手札から雷エネルギーを複数枚ベンチポケモンに一気に付けることができます。これにより、ピカチュウexや他のアタッカーが即座に攻撃態勢に入れるのが強力です。
レアコイルへの進化タイミングがカギ
ジバコイルを早く立てるためには、レアコイルを適切なタイミングで進化させる必要があります。初手からコイルを場に出し、2ターン目までにレアコイルへ進化しておくことで、その次のターンにはジバコイルでエネ加速が狙える状況を作るのが理想的です。
安定構築のための採用目安
安定してジバコイルラインを成立させるためには、コイル・レアコイル・ジバコイルをそれぞれ2~3枚ずつ採用するのがおすすめです。また、モンスターボールや博士の研究といったカードで進化ラインをサーチできるようにしておくことで、事故率を下げて展開をスムーズにします。
サポートポケモン|パチリスの役割

引用 : ポケポケ公式HP (https://www.pokemontcgpocket.com/ja/)
パチリスはエネルギー加速をさらに促進し、ピカチュウexやジバコイルが早期に動き出すための重要なサポートポケモンです。その特性と技を活かすことで、序盤の安定感が格段に増し、後続の展開に繋げやすくなります。以下では、パチリスの強みと立ち回りのコツを詳しく解説します。
特性や技を活かしたエネ加速
パチリスは場に出た際に手札からエネルギーを加速できる特性を持っており、これを活用することでピカチュウexがすぐに高火力を発揮できる状況を作り出せます。特にジバコイルに繋げるための中継役としても非常に重要で、2ターン目にエネ3枚が揃う動きを支援します。
パチリスの理想的な使用タイミング
初手でコイルとともに出せると、レアコイルやピカチュウexへの素早い進化とエネルギー供給を同時に進められます。1ターン目に手札に引けなかった場合でも、モンスターボールや博士の研究でサーチする動きを意識しましょう。
採用枚数の目安と注意点
安定性を高めるには、パチリスは2枚以上の採用が推奨されます。ただし、HPがやや低く狙われやすいポケモンでもあるため、ベンチ保護カードや状況に応じた立ち回りが求められます。また、早めにエネルギーをトラッシュできるカード(博士の研究など)との組み合わせで真価を発揮します。
サポートカードの選択|ナツメ・レッド・ヒカリの使い方
デッキに少数ながら重要な役割を果たす「ナツメ」「レッド」「ヒカリ」の効果的な使い方は、ピンチをチャンスに変えるための鍵となります。以下では、各カードの役割と最適な使用タイミングを詳しく解説します。
ナツメ|手札コントロールで主導権を握る

引用 : ポケポケ公式HP (https://www.pokemontcgpocket.com/ja/)
ナツメは、お互いの手札枚数に関与することでゲームの流れを変えるカードです。相手が大量の手札を抱えている場面で使えば、相手の選択肢を大幅に削ぎつつ、自身は必要なカードを補充できるため、状況を一気に有利に持ち込むことが可能です。
レッド|奇襲と確定ダメージの決め手
レッドは、特定の状況で高ダメージを叩き出すピンポイントなサポートです。HPの高いポケモンを確実に落とすための決定打として、またギリギリの勝負を制す場面で非常に有効です。ジバコイルとの連携で雷エネルギーを一気に供給し、フィニッシュムーブに繋げる使い方がベストです。
ヒカリ|エネルギー移動による柔軟な戦術展開

引用 : ポケポケ公式HP (https://www.pokemontcgpocket.com/ja/)
ヒカリはエネルギーを別ポケモンへ移動させることで、盤面の立て直しや予期せぬ展開に対応する戦術カードです。ピカチュウexがやられた後の再構築、あるいはジバコイルを前線に出す準備として有効に働きます。1枚採用で十分な存在感を発揮します。
この3枚は、それぞれが単体で強力というよりも、デッキ全体の連携を支える潤滑油のような存在です。適切なタイミングでの運用により、逆転劇や一方的な展開を生み出す力を秘めています。
対策必須の環境デッキ|ギラティナ・ギャラドス
マスターランク帯で多く使われるギラティナやギャラドスデッキに対しては、明確な対策と柔軟な立ち回りが求められます。以下に、それぞれのデッキに対する戦術と対策を具体的に解説します。
ギラティナデッキへの対策|エネルギー加速勝負で上回る
ギラティナデッキは高い打点と強力なエネ破壊能力が魅力ですが、ピカチュウexデッキはジバコイル+パチリスのエネルギー加速により、それを上回る展開力を発揮します。特に2ターン目にジバコイルを立てられれば、エネルギー差で先手を取り、一気に主導権を握ることが可能です。また、ギラティナの特性によるロスト送りに対しては、ベンチポケモンを多めに展開し、狙われるリスクを分散させることが有効です。
ギャラドスデッキへの対策|速攻+ナツメで崩す
ギャラドスデッキは高耐久・高火力で知られていますが、その弱点は準備に時間がかかることです。ピカチュウexの早期展開+ナツメによる手札干渉で、相手のコンボを崩すことができます。特にギャラドスが並ぶ前にパチリスやピカチュウexで攻め込むことができれば、一方的に盤面を制圧できます。
共通の工夫ポイント|光やレッドで差をつける
ギラティナ・ギャラドスいずれに対しても、「ヒカリ」でのエネ移動や「レッド」での高打点フィニッシュは非常に有効です。勝負どころでこれらのカードを使いこなすことで、一気に勝利へ持ち込むことが可能になります。
このように、相手の特徴を理解し、それに応じた柔軟な対応と戦術を採ることで、環境上位デッキ相手でも十分に勝ちを狙うことができます。
不利な相性の克服|闘タイプ対策
ピカチュウexデッキが苦手とする闘タイプデッキに対しては、無理に正面からぶつかるのではなく、リスクを最小限に抑えた割り切り戦術が重要です。以下では、闘タイプに対応するための実践的な考え方と工夫を解説します。
闘タイプの代表格とその強み
闘タイプデッキの多くは、ルカリオやマーシャドウのような特性と火力に優れたアタッカーを採用しています。これらのポケモンはピカチュウexの弱点を突くことができるため、一撃で倒される危険が常につきまといます。
無理に対抗しない「割り切り」の判断
闘タイプとのマッチアップでは、あえて勝ちを狙いに行かず、ほかのデッキとの勝率で取り返す“捨て試合”の考え方も必要です。リスクが高すぎる状況では、被害を最小限に抑え、残りのバトルで確実にポイントを取る戦略に切り替えましょう。
闘タイプ対策カードの選択肢
どうしても勝ち筋を狙いたい場合は、無色タイプや超タイプのアタッカーを1枚差しで採用するのも手です。例えば、ドラパルトやエーフィなど、闘タイプに強い非雷ポケモンをピン差しで組み込むことで、サブプランとして機能します。
立ち回りの工夫で粘る
パチリスやヒカリを使ったエネルギーの再配置で、狙われやすいピカチュウexを一時的にベンチへ逃がす、あるいはリソース切れを狙った遅延戦術も有効です。また、道具カードでHPを底上げし、ワンパンされない構築を意識することで勝機が見えてくる場合もあります。
安定して勝利するためのプレイング|ポイント解説
マスボランクで安定して勝つために必要な細かなプレイングテクニックを解説します。単に強いカードを揃えるだけでは安定した勝利にはつながらず、状況判断やリスク管理を含めた細やかなプレイが求められます。以下のポイントを意識することで、勝率は劇的に向上します。
先攻・後攻で動きを変える判断力
先攻時にはジバコイルの進化を優先し、できるだけ早くエネルギー加速体制を整えます。一方で後攻時は、相手の盤面展開を見てからのナツメやマーズによる干渉を検討し、カウンター気味の動きが有効です。
進化ラインの展開は段階的に
コイル→レアコイル→ジバコイルと一気に進化させることに意識が向きがちですが、相手の手札干渉やサーチ手段に備えて、1ターンごとに段階的に展開するほうが安定性が増します。
ベンチマネジメントの徹底
闘タイプなどのメタに弱いピカチュウexを無防備にベンチに出し続けないよう注意。バトル場との入れ替えをスムーズに行えるよう「ヒカリ」を絡めてベンチ構成を維持し、相手のロスト対策も兼ねた配置を意識しましょう。
リソース管理と終盤の読み
博士の研究を序盤で多用しすぎると終盤でキーカードが枯渇します。ナツメやレッド、ヒカリといったピン差しカードは1ゲームに1度使うつもりで計画的に温存・使用し、終盤で一気に形勢を逆転できる動きを狙いましょう。
ピカチュウexデッキの実戦立ち回り攻略|勝率を上げるコツ
初動の立ち回り|理想の展開方法
デッキ初動の理想的な展開と、初ターンで絶対に押さえておきたいポイントを詳しく解説します。序盤の立ち回りは勝敗を左右する最重要ポイントであり、ここでの準備と判断力がその後の展開に大きく影響します。
初手の理想パターンとは?
最も理想的な初動は、先攻で「コイル」+「パチリス」が場に揃い、次ターンで「レアコイル」へ進化しつつ「ピカチュウex」へエネルギー加速ができる展開です。この状態を目指すためには、初手でのドロー・サーチカードの使い方が重要になります。
モンスターボールや博士の研究の活用
安定した初動を取るためには、サーチカードである「モンスターボール」や、「博士の研究」などのドローカードをフル活用して必要なポケモンや進化パーツを揃えます。特に「コイル」「パチリス」「ピカチュウex」の3種が早期に揃えば、その後の動きが非常にスムーズになります。
先攻と後攻で変わる初動の考え方
先攻では、ジバコイルまでの進化を意識しつつ展開準備に注力します。後攻の場合は、相手の盤面次第で「パチリス」や「ピカチュウex」で先に攻撃する選択肢も出てきます。この判断を誤らず、リスクとリターンを見極めることが重要です。
「スピーダー」や「ヒカリ」の補助的役割
1ターン目に「スピーダー」でデッキを回し、「ヒカリ」でエネルギーの再配置ができる状況を想定しておくと、柔軟な立ち回りが可能になります。特に不安定な初手になった場合は、これらのカードでリカバリーを図る動きが有効です。
中盤の制圧方法|盤面コントロールの重要性
中盤以降、盤面をコントロールしながら優位性を保つためには、攻防のバランスを保ちつつ、ジバコイルとピカチュウexの連携を軸に戦略的な立ち回りが必要です。ここではその具体的な方法を詳しく解説します。
ジバコイルで継続的なエネ供給を維持
中盤に入ると、毎ターンのエネルギー加速が非常に重要になります。ジバコイルの「ボルトチャージ」によって、毎ターン安定してピカチュウexにエネルギーを供給することができれば、絶え間なく圧力をかけることが可能です。これにより、相手は盤面の処理に手を焼き、受け身に回らざるを得なくなります。
ピカチュウexで盤面をコントロール
エネルギーが充実してきた中盤では、ピカチュウexの高火力を活かし、相手のキーカードや育成中のポケモンを優先的に狙うことで盤面を制圧します。特にサイドレースをリードする上では、アタッカーの数を削る意識が重要です。
ベンチ構成とターゲットの見極め
ジバコイルを含む盤面はエネルギーの供給元として常にリスクを抱えているため、相手が狙ってきそうなターゲットを常に先読みする必要があります。HPの低いベンチポケモンは「ヒカリ」でエネを移動させて守るなど、リスクを分散する立ち回りも中盤戦では求められます。
回復や干渉カードでテンポを取る
「マーズ」や「ナツメ」のような干渉系サポートカードを使うことで、相手の手札やエネルギー供給を乱し、自分のテンポを維持することができます。また、「キズぐすり」などの回復手段を挟むことで、相手のサイドプランを崩す戦術も有効です。
終盤のフィニッシュ|勝負を決める戦術
終盤で勝利を確定させるためには、サイド差の調整やリソース管理、そして一撃で相手のキーカードを倒す戦術が重要となります。ピンチに陥っても状況を逆転できるようなテクニックを習得しましょう。
サイド計算を意識したプレイング
終盤では残りサイドの数が勝負を左右する重要な要素です。相手のサイド獲得手段を先読みし、自分が最後の1枚を確実に取れるように盤面を設計しておくことが求められます。特に「レッド」や「ヒカリ」などのカードを残しておくことで、計画的なフィニッシュが可能になります。
ピカチュウexの一撃フィニッシュ
ピカチュウexは終盤のフィニッシャーとして非常に優秀です。ジバコイルによって十分なエネルギーを供給できていれば、高HPポケモンでも一撃で倒すことができます。これにより、相手の逆転プランを断ち切ることができるため、ピカチュウexを終盤まで温存する判断も有効です。
相手のキーカードの封じ方
相手の勝ち筋となるカード(エースポケモンや回復手段)を早期に見極め、「ナツメ」や「マーズ」で手札を削り、動きを止めることで勝率を引き上げられます。特に終盤では相手もリソースが限られているため、1ターンの妨害が致命打になるケースも多くあります。
リスクを抑えた攻撃の選択
無理にアタックを続けてリソース切れやサイド逆転を許すよりも、1手2手先を読んで安全に勝ちに繋げるプレイングが大切です。ときには逃げエネを残しておき、入れ替え手段を確保しつつ相手の行動を誘導するなど、慎重な判断力が問われます。
トップ環境デッキとのマッチアップ分析|勝率アップ戦術
トップ環境のデッキとの具体的なマッチアップ分析と、それぞれに対する実践的な対策を紹介します。環境には日々さまざまな強力デッキが登場していますが、ピカチュウexデッキはその中でも柔軟に対応可能な構築を目指すことができます。
ミライドンex系への対応策
ミライドンexを軸とした速攻型の雷デッキは、エネルギー加速と高火力の両立が魅力です。ピカチュウex側は、進化を必要としないぶん展開速度で対抗可能です。序盤からパチリスとジバコイルで差をつけつつ、相手のエネ供給源(ライコウVなど)を優先的に落とすことがカギです。
リザードンex構築への考え方
高火力かつ持久力のあるリザードンexデッキは、ピカチュウexが主力のままだとやや不利な相性です。そこで、レッドの奇襲やヒカリによるエネ再配置でタイミングよくリザードンを撃破することが必要です。また、早い段階でジバコイルを立ててアグレッシブに攻めることで、相手に時間を与えないのも有効です。
ミュウVMAX系への戦術的対応
高速で展開し、ベンチから連続打点を繰り出すミュウVMAXデッキに対しては、こちらも高速展開で対抗する必要があります。重要なのは、相手の「ゲノセクトV」などのドローソースを潰すこと。マーズやナツメを使ってテンポを崩すと、意外と崩れやすいデッキです。
環境対応の柔軟性を持たせる
ピカチュウexデッキは、基本は雷特化で構成されていますが、メタを読んで一部に超タイプや無色のサブアタッカーを組み込むなど、状況に応じた調整が必要です。トップ環境デッキごとに想定カードを1〜2枚差しで変えるだけでも勝率は大きく変動します。
マスボランクでの勝率アップ|実践で役立つメンタル管理
ランクマッチで安定して結果を出すためのメンタル管理方法を詳しく解説します。ピカチュウexデッキで安定した勝率を出すためには、技術的な立ち回りだけでなく、精神的な安定も大きな要素になります。以下では、ランクマッチを戦い抜く上で重要なメンタル面の工夫を紹介します。
負けを受け入れるメンタリティの重要性
連勝が続いているときは調子に乗りがちですが、連敗が続いたときこそ冷静さを保つことが必要です。負けを「次への学び」と捉え、自分のプレイングを分析・改善する姿勢を持つことで、結果として勝率も上がります。
プレイ時間と集中力の管理
集中力が落ちた状態で連戦すると、プレミや判断ミスが増えがちです。1〜2試合ごとに短い休憩を取る、気分転換に画面から目を離すなど、試合ごとの切り替えを意識しましょう。
相手の煽りや運要素に振り回されない
相手のプレイスタイルや急な運負けに対して感情的になると、冷静な判断が難しくなります。カードゲームにおける不確定要素も「ゲームの一部」と割り切り、最善の行動を取る意識を持つことが大切です。
勝ち続けるためのポジティブマインド
勝てる構築・戦術を持っていても、メンタルが崩れると本来の力が発揮できません。試合ごとに「成長のチャンス」と捉えること、自信を持ってデッキを信じる姿勢が、結果として安定した勝率に繋がります。
デッキ改良のポイント|最新環境に対応
環境の変化に応じて柔軟にデッキを調整するための具体的なアドバイスを紹介します。ピカチュウexデッキは環境適応力が高く、相手の流行や構成に合わせてカードを1〜2枚入れ替えるだけで大きく勝率を変えることができます。定期的な微調整こそが、マスターボール帯で長期的に勝ち続けるための秘訣です。
メタ読みの重要性とカード調整
毎週のように環境が変わるランクマッチでは、直近で流行しているデッキタイプ(例:ギラティナ系・リザードン系・マスカーニャ系など)に合わせて構成を調整する必要があります。たとえば、ギラティナが増えてきた場合はベンチ展開を厚くしてロスト送りへの耐性を高めたり、超タイプのアタッカーを1枚採用するなどの調整が有効です。
サブアタッカーの差し替え例
闘タイプに弱いピカチュウexの弱点を補うために、超タイプのエーフィや、無色アタッカーのドラパルトなどをピン差しで組み込む構成もあります。これにより相性不利の相手に対してもワンチャンスを作ることができます。
サポートカードの入れ替え判断
環境の速度に応じて「博士の研究」を増減させたり、「ナツメ」や「レッド」のようなピン差しサポートの種類や枚数を調整することで、より勝負どころに対応しやすくなります。また、「ヒカリ」や「マーズ」などのテクニカルカードも、読みが当たれば大きく機能するため定期的な見直しが必要です。
練習と記録で調整精度を上げる
対戦ログを取っておくと、自分がどの構築にどれだけ勝っているか・負けているかを客観的に判断できます。それをもとに苦手な対面に刺さるカードを差し替えることで、より実戦的な調整が可能になります。
まとめ
最新のピカチュウexデッキは、ジバコイルとパチリスを活かした高速エネルギー加速と、的確なカード運用によってマスターボール帯でも通用する高いポテンシャルを秘めています。特に序盤の展開速度と終盤のフィニッシュ力の両立ができる構築であり、さまざまな環境デッキに対しても柔軟に対応可能です。
また、プレイヤーの技量次第でプレイングの幅が広がるため、初心者から上級者まで習得価値のある構成と言えます。環境デッキへの的確な対策、細かな立ち回りテクニック、そして心構えや調整力を磨くことで、確実にマスボランクを攻略できるはずです。