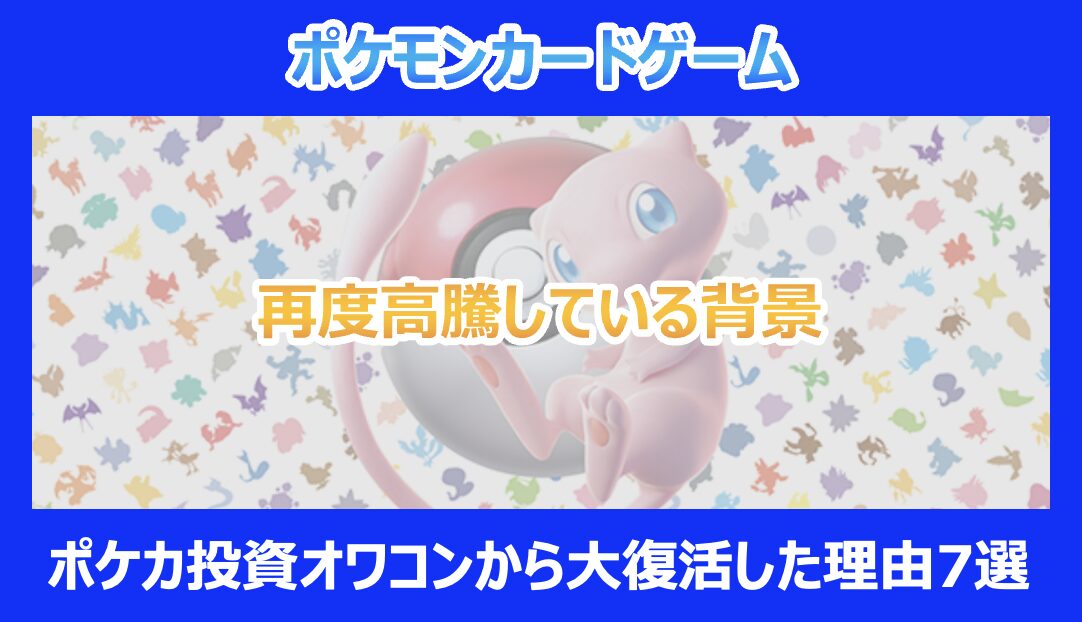トレカ評論家の桐谷シンジです。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、「一時期オワコンと言われたポケモンカードが、なぜ今になって再び高騰しているのか」その理由が気になっていると思います。 2023年中盤から後半にかけての市場の冷え込みは、多くのコレクターや投資家を不安にさせたことでしょう。 しかし、2024年に入り、市場は息を吹き返し、かつての熱気を取り戻しつつあります。

この記事を読み終える頃には、ポケカ市場がなぜ復活し、今後どのような可能性を秘めているのか、その疑問が解決しているはずです。
- ポケカ投資が「オワコン」と言われた具体的な背景
- 市場が復活を遂げた7つの決定的な要因
- PSA鑑定や海外需要が市場に与える影響
- 今後のポケカ投資で注目すべき視点

ポケカ投資が「オワコン」と言われた時代の背景
ポケモンカードが現在のように再評価される以前、特に2023年の後半には「ポケカ投資は終わった」「バブルは崩壊した」という声が市場に満ちていました。 あの熱狂的なブームから一転、なぜ市場はそこまで冷え込んでしまったのでしょうか。 まずは、ポケカ投資が「オワコン」とまで揶揄された時代の背景を、複数の視点から深く掘り下げていきましょう。 この時期の市場を理解することが、現在の復活劇を正確に把握するための鍵となります。
転売ヤーの過度な買い占めと市場の混乱
「オワコン」化の最大の要因として挙げられるのが、転売ヤーによる過度な買い占めです。 特に「イーブイヒーローズ」や「VSTARユニバース」といった人気パックが発売されると、彼らは組織的に動き、家電量販店やコンビニから商品を根こそぎ買い占めていきました。 その結果、本当に遊びたいプレイヤーや純粋なコレクターの手にカードが渡らないという異常事態が発生したのです。
本来、誰もが定価で購入できるはずの商品が、フリマアプリなどでは数倍の価格で取引されるのが当たり前となりました。 この状況は、新規プレイヤーの参入障壁を著しく高め、既存のファンでさえも「もうポケカは買えない」と疲弊させてしまう結果を招いたのです。 市場は健全な需要と供給のバランスを完全に失い、投機目的のマネーゲームの様相を呈していました。
ジェットコースターのような相場の急騰と急落
転売ヤーの買い占めに伴い、シングルカードの価格は異常なまでに高騰しました。 特に「がんばリーリエ」や「帽子リーリエ」といった希少な女性キャラクターのカードは、数百万円、時には1,000万円を超える価格で取引され、ポケカは一部で「カードの形をした金融商品」とまで言われるようになります。
しかし、このような投機的なバブルは長続きしません。 加熱しすぎた相場は、些細なきっかけで一気に暴落するリスクを常に抱えています。 実際、特定のカードが再録されるという噂や、有力なインフルエンサーの否定的な発言ひとつで、価格が数十万円単位で下落することも珍しくありませんでした。 このような不安定な値動きは、短期的な利益を狙う投機家には魅力的だったかもしれませんが、長期的な視点でコレクションを楽しむ層や、資産としてポケカを保有していた投資家にとっては、大きな不安材料となったのです。 「いつ価値がなくなるか分からない」という恐怖感が、市場からの資金流出を加速させました。
公式による生産体制の強化と再販ラッシュ
市場の異常な過熱と品薄状態を問題視した株式会社ポケモンは、生産体制の強化に乗り出します。 これまで品薄で入手困難だった人気パックの再販を繰り返し行い、さらには受注生産という形で、希望者全員が定価で購入できる機会を提供するようになりました。 代表的な例が「ポケモンカード151」です。 当初は品薄で高値がついていましたが、複数回にわたる再販と受注生産により、市場価格は大きく下落しました。
この公式の対応は、純粋なプレイヤーやコレクターからは歓迎されました。 しかし、転売目的で商品を大量に抱えていた業者や、高値でカードを購入してしまった投資家にとっては大打撃となります。 「再販されれば価値が下がる」という認識が広まり、これまでのような強気な価格での取引が成立しにくくなりました。 供給量が増えたことで希少性が薄れ、市場全体が下落トレンドに転じる大きなきっかけとなったのです。
YouTuberやインフルエンサーの影響力の変化
ポケカブームの火付け役の一つが、YouTuberやインフルエンサーによる開封動画や高額カード紹介でした。 彼らが紹介するカードは軒並み高騰し、その影響力は絶大でした。 しかし、市場が下落局面に入ると、その状況も一変します。
一部のインフルエンサーは、これまで相場を煽るような発信をしていたにもかかわらず、手のひらを返したように「ポケカはもう終わり」といったネガティブな情報を発信し始めました。 これは、視聴者の関心を引くための戦略だったのかもしれませんが、結果として市場の不安をさらに煽ることになります。
また、視聴者側も情報リテラシーを高め、「インフルエンサーが紹介するから高騰する」という単純な図式が通用しなくなってきました。 情報の受け手が冷静になるにつれて、インフルエンサーの影響力は相対的に低下し、ブームの勢いを削ぐ一因となったと考えられます。
ワンピースカードゲームなど新規TCGタイトルの台頭
ポケカ市場が停滞する一方で、他のトレーディングカードゲーム(TCG)が勢いを増していました。 その筆頭が「ワンピースカードゲーム」です。 原作の絶大な人気を背景に、発売直後から大きなムーブメントを巻き起こし、多くのTCGプレイヤーやコレクター、投資家の資金がそちらへ流れました。
ポケカの品薄や価格高騰に疲弊していた層にとって、定価で買えて、なおかつ新しい環境で楽しめるワンピースカードゲームは非常に魅力的に映ったのです。 市場の資金や注目は有限です。 強力なライバルの登場は、ポケカ市場の熱を冷まし、「オワコン」という言説に拍車をかける要因となりました。
コレクターとプレイヤー双方の疲弊
最終的に、この混乱した市場は、ポケカを愛する全てのファンを疲弊させました。
- プレイヤー:遊びたいのにパックが定価で買えない。対戦で必要なカードが高騰しすぎてデッキが組めない。
- コレクター:欲しいカードが入手困難、もしくは異常な高値で手が出せない。コレクションの価値が乱高下して安心して集められない。
- 投資家:再販リスクや突然の暴落に怯え、安定した資産形成が望めない。
それぞれの立場の人々が、それぞれの理由でポケカから距離を置き始めたのです。 コミュニティ全体に漂うこの「疲れ」こそが、「ポケカオワコン」という言葉の正体だったのかもしれません。 市場は、一部の投機家を除いて、誰もが楽しめない状況に陥っていたのです。
ポケカが高騰!オワコンから大復活した理由7選
「オワコン」というレッテルを貼られ、一時は冷え込みを見せたポケカ市場。 しかし、2024年に入るとその様相は一変しました。 沈黙を破り、再び力強い上昇トレンドを描き始めたのです。 では、一体何が市場を復活させたのでしょうか。 ここでは、ポケカ投資がオワコンから大復活を遂げた7つの理由を、多角的な視点から徹底的に解説していきます。

理由1:新規参入者の増加と市場の健全化
逆説的ですが、「オワコン」と言われた時期の市場の落ち着きが、結果的に新規参入者を呼び込む土壌を育みました。 転売ヤーの撤退や投機的な価格の収束によって、市場は本来あるべき姿、つまり「遊ぶ」「集める」を楽しむユーザーが主役の市場へと回帰し始めたのです。
カードの入手難易度の低下
以前は棚に並ぶことすらなかったポケモンカードのパックが、コンビニや家電量販店で普通に定価で買えるようになりました。 この変化は非常に大きく、これまで興味はあっても手が出せなかった層、特に親子連れや学生といったライト層が気軽にポケカを始められる環境を整えました。 長期的な熱狂が落ち着いたことで、純粋にゲームを楽しみたい、好きなポケモンのカードを集めたいという人々が市場に戻ってきたのです。
デッキ構築コストの低下
市場の健全化は、シングルカードの価格にも良い影響を与えました。 二次流通の場であるカードショップでは、実際の対戦環境で活躍するような強力なカードでさえ、数百円から1,000円以下で手に入るようになりました。 これにより、初心者が少ない投資で本格的なデッキを構築し、すぐにゲームの面白さを体験できる状況が生まれたのです。 転売目的ではない、純粋なプレイヤー層の増加は、市場の底辺を支える強固な土台を形成しました。 このプレイヤー層の厚みこそが、市場の安定感と持続的な成長に不可欠なのです。
理由2:PSA鑑定需要の拡大と定着
ポケカの価値を語る上で、今や欠かせないのが「PSA鑑定」の存在です。 PSA(Professional Sports Authenticator)は、カードの状態を10段階で評価する世界最大の第三者トレーディングカード真贋鑑定・グレーディングサービス会社です。 このPSA鑑定の需要が、一過性のブームではなく、文化として定着したことが市場復活の大きな要因となっています。
「状態の良いカード=資産」という価値観の浸透
一時期は「PSA10(最高評価)のカードが増えすぎて価格が暴落する」という懸念もありました。 しかし、結果的に「状態の良いカードは資産価値が高い」という考え方はコレクターや投資家の間で確固たるものとして根付きました。 特に、旧裏面のカードや限定プロモーションカード、そして海外のコレクターに人気の高い日本語版カードなど、希少性の高いカードにおける鑑定需要は衰えることを知りません。 PSA鑑定によってカードの状態が客観的に保証されることで、高額カードであっても安心して取引できる環境が整ったのです。
鑑定ビジネスの一般化
近年、日本国内でもPSA鑑定の提出代行サービスが当たり前になり、一般のユーザーでも手軽に鑑定に出せるようになりました。 これにより、「自分でパックから引いた完美品のカードを鑑定に出して付加価値をつける」という、新たな楽しみ方やビジネスが生まれました。 PSA10のカードを収集することが一種のステータスとなり、「このカードは将来高騰するかもしれないから、今のうちに鑑定に出しておこう」といった中長期的な視点を持つコレクターも増加しています。 このように、コレクター層に厚みが増したことで、市場はより安定し、多少の価格変動では揺るがない強さを手に入れました。
| カードの状態 | 推定価値 | 特徴 |
|---|---|---|
| PSA10 (Gem Mint) | 非常に高い | 完美品。カードの四隅、エッジ、表面、センタリング全てが最高状態。 |
| PSA9 (Mint) | 高い | ニアミント。極めて軽微な欠陥が1つあるのみ。 |
| PSA8 (Near Mint-Mint) | 中〜高い | 軽微な欠陥が複数見られるが、全体的に美しい状態。 |
| PSA7以下 | 状態に応じて変動 | 傷や汚れが目立つようになり、コレクション価値は下がる傾向。 |
PSA鑑定済みカードの安定した需要がある限り、ポケカ市場が再び「オワコン」になることは考えにくいでしょう。
理由3:魅力的な新パックの継続的な登場
市場の熱気を維持するために最も重要なのは、ユーザーを飽きさせない魅力的な新商品の供給です。 その点において、近年のポケモンカードは驚異的なクオリティを維持し続けています。
話題性に富んだパック構成
2023年末に発売された「シャイニートレジャーex」以降、「ワイルドフォース」「サイバージャッジ」「クリムゾンヘイズ」、そして記憶に新しい「変幻の仮面」に至るまで、プレイヤーとコレクター双方の心を掴む魅力的なパックが次々とリリースされています。 特に、過去に絶大な人気を博したキャラクターの再登場は、市場に大きなインパクトを与えました。 「リーリエ」や「アセロラ」、「N(エヌ)」といった伝説的な人気トレーナーが、新たなイラストで収録されることにより、かつてポケカから離れていた「復帰勢」の購買意欲を強く刺激しているのです。
予測不能なワクワク感の提供
ポケモンカードの魅力の一つは、「次のパックでは何が収録されるのだろう?」という予測不能なワクワク感にあります。 公式はその期待を裏切ることなく、むしろファンの想像を遥かに超えるレベルのカードを戦略的に投入してきています。 人気キャラクターやポケモンを惜しみなく収録し、常に市場に新しい話題を提供することで、ファンの関心を引きつけ、熱量を維持することに成功しているのです。 この巧みな商品展開がある限り、ポケカ市場の灯が消えることはないでしょう。
理由4:YouTube市場の拡大と情報発信の多様化
現代のTCG市場において、YouTubeをはじめとする動画プラットフォームの役割は無視できません。 ポケカ関連のコンテンツは成熟期を迎え、市場の新たな入り口として、そして市場を活性化させるエンジンとして機能しています。
コンテンツの多様化
かつては開封動画が中心でしたが、現在ではポケカ関連のYouTubeチャンネルは多岐にわたっています。
- 対戦解説チャンネル:最新の環境デッキやプレイング技術を解説し、プレイヤー層のレベルアップに貢献。
- 開封動画チャンネル:高額パックの開封や、特定のカードを狙うエンターテイメント性の高い動画。
- 高額カード紹介・相場分析チャンネル:カードの価値や市場の動向を分析し、投資家やコレクターに有益な情報を提供。
- 初心者向けチャンネル:ルール解説や、少ない予算でのデッキ構築方法などを紹介し、新規参入をサポート。
これらの多様なコンテンツにより、カードをプレイしない人でも「見るだけ」で十分に楽しめる環境が整っています。 特に最近では、単にカードを開封するだけでなく、その価値を検証したり、初心者がポケカを始めるリアルな体験を追ったりするコンテンツに注目が集まっています。 視聴者は購入前の参考にすることができ、これが新たな購買動線となっているのです。 動画をきっかけに興味を持ち、少しずつカードを買い始めてみる。 この流れが確立されている限り、市場は一定の底堅さを保ち続けると考えられます。
理由5:海外需要の増加とグローバルな市場形成
ポケモンというコンテンツが持つグローバルな人気は、ポケカ市場の強さを支える非常に重要な要素です。 国内市場だけに依存しない、世界的な需要の存在が市場の安定性を高めています。
日本語版カードの国際的な価値
驚くべきことに、海外の熱心なファンにとって、コレクションの対象は英語版カードだけではありません。 クオリティの高いイラストや、希少性から、日本語版のオリジナルカードは国際的に高い人気を誇ります。 特にPSA鑑定によって状態が保証されたカードは、世界最大のオークションサイトである「eBay」などを通じて、日常的に国境を越えて取引されています。 これにより、日本の市場が多少落ち込んだとしても、海外からの需要が価格を下支えする構造が生まれています。 近年の円安傾向は、海外のバイヤーにとって日本のカードが割安に購入できる状況を生み出しており、この流れをさらに加速させています。
アジア市場の拡大
特に中国やその他アジア地域でのポケカ人気は目覚ましいものがあります。 正規の中国語版カードが登場したことで、これまで以上に多くの国や地域でポケカ文化が浸透し始めています。 世界中でプレイヤーとコレクターが増え続けているという事実は、ポケカが単なる国内のブームではなく、世界共通の文化コンテンツであることを示しています。 このグローバルな強みは、他の多くのTCGにはない、ポケカならではのアドバンテージと言えるでしょう。
理由6:長期的ファン層の定着と世代交代
ポケカ市場の根幹を支えているのは、一過性のブームに乗った層だけではありません。 子供時代からポケモンと共に成長してきた、熱心なファン層の存在です。
経済力を持つポケモン世代
1996年のゲームボーイソフト「ポケットモンスター 赤・緑」発売当時に子供だった世代は、現在20代後半から30代、40代に差し掛かっています。 彼らは、自身の趣味に自由にお金を使える経済力を持った年代に突入しており、子供の頃の憧れだったカードのコレクションを本格化させています。 彼らにとってポケカは、単なる趣味を超え、生活や人生の一部に組み込まれたカルチャーです。 このような深く根付いた趣味は、市場の流行り廃りに左右されることなく、簡単には終わりません。 ファンの「高齢化」ではなく、より成熟したファンへと「熟成」が進んでいるのが、現在のポケカ市場の強さなのです。
次世代への継承
さらに素晴らしいのは、その文化が次の世代へと継承され始めている点です。 かつてプレイヤーだった親が、今度は自分の子供と一緒にパックを開封したり、家族でポケモンカードのイベントに参加したりする光景は、もはや珍しいものではありません。 親子二代、あるいは三代にわたって楽しまれるコンテンツとなることで、ファン層は絶えることなく拡大し続けていきます。 この世代を超えたファンの連鎖が、ポケカ市場の長期的な安定性を担保しているのです。
理由7:再販・暴落を乗り越えた実績と市場の信頼性
最後に挙げる理由は、市場そのものが過去の失敗から学び、強くなったという点です。 一度は「オワコン」とまで言われた再販による暴落を乗り越えた経験が、市場に新たな信頼と耐久力をもたらしました。
「育てる資産」としての認識
例えば、現在再び高騰している「ポケモンカード151」や、一時期は店頭に溢れていた「シャイニートレジャーex」のように、再販や暴落で一時的に価格が下がっても、長期的に見れば再び価値が上昇しているカードは数多く存在します。 これらの事例は、コレクターや投資家の間に「ポケカは短期的な投機の対象ではなく、長期的に価値を育てる資産である」という認識を広めました。
下落局面での買い支え
「一時的な下落はあっても、長期で見れば価格は戻る」という信頼感が市場に生まれたことで、価格が下がった局面で積極的に購入する「買い支え層」が形成されました。 彼らは目先の価格変動に一喜一憂せず、将来的な価値を見据えてカードを収集します。 この存在が市場のセーフティネットとなり、暴落時でも価格がある一定のラインで踏みとどまる要因となっています。 一度暴落を経験し、そこから自力で這い上がってきたという「実績」こそが、現在のポケカ市場が持つ何よりの強みであり、投資対象としての信頼性の証左なのです。
まとめ
今回は、「ポケカ投資はオワコン」と言われた状態から、市場が見事に復活を遂げた7つの理由について深く掘り下げてきました。 レビューのポイントを振り返ってみましょう。
- 新規参入者の増加と市場の健全化:転売ヤーの撤退でカードが入手しやすくなり、純粋なプレイヤーやコレクターが戻ってきた。
- PSA鑑定需要の拡大と定着:「状態の良いカード=資産」という価値観が文化として根付き、高額カード市場が安定した。
- 魅力的な新パックの継続的な登場:人気キャラクターの再登場など、ファンを飽きさせない戦略的な商品展開が続いている。
- YouTube市場の拡大と情報発信の多様化:動画が新たな入り口となり、多様なコンテンツが市場全体の活性化に貢献している。
- 海外需要の増加とグローバルな市場形成:ポケモンという世界的IPの強みを活かし、国内だけでなく世界中に需要が拡大している。
- 長期的ファン層の定着と世代交代:経済力を持つポケモン世代が市場を支え、さらにその子供世代へと文化が継承されている。
- 再販・暴落を乗り越えた実績と市場の信頼性:過去の価格下落を乗り越えた経験から、「長期的に価値が上がる資産」としての信頼を獲得した。
これらの要因が複雑に絡み合うことで、現在のポケモンカード市場は、短期的な価格の波に揺らぐことはあっても、決して「終わる」ことのない、強く、広く、そして深い市場へと進化を遂げました。
一時期のネガティブな情報に触れ、「ポケカは本当にオワコンなのか?」と感じていた方も、今回のレビューをきっかけに、もう一度ポケモンカードとの向き合い方を考えてみてはいかがでしょうか。 そこには、かつての熱狂とは質の異なる、より成熟した市場と、新たなチャンスが広がっているはずです。